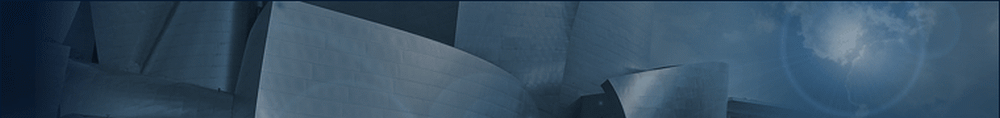○と・し・ろ・ん (都市論)
○野宮安寿さんのところで、<世田谷の農道> のことに触れた
ことから、断片的な知識の披露におよび、ヨーロッパなどの
<シンプルな>都市計画が日本にはないこと。となった。反転
し、現在この日本的な<複雑な>風景を注視する研究者の存在
へと。日仏文化学院の院長。オギュスタン・ベルクの「仕事」
へと。こんな記し方をしても、なんことかわからない。これ
らのことを既知のこととしているヒト以外には、なかなかワ
カラナイ。ということだ。だから、端的な説明の方途を捜し
ウダウダと頭をめぐらしながら、記しているのだ。○説明の
ための説明。では無意味だ。○日本に都市計画はない。とい
のは、比較的よく言われることだ。これは都市計画などの専
門家だけの発言ではない。東京都知事の石原慎太郎の常套句
であり、あのJUSCOの会長の岡田などもそのことに触れ
る。出店計画、商業施設の調整協議などで頻発する<地元・
既成商店主>などの地域エゴなどに窮した経験を持つ、リテイ
ルのパイオニアの指摘は、単に「都市計画」という「図」の
ことだけでなく、そこに<市民意識>の不在を糾弾している。
のだ。○「都市計画」がない。とは、このように都市のベー
スを形成する、<市民>そのものの不在までも示すところのも
のとなる。○ここらあたりのことは、その分野の専門書の数
々ということにしておく。○とりあえずの焦点は、<都市計画
がない>という時に、われわれが描く、その<イメージ>のこと
だ。地域ブロック別の性格付けされ整然とした「合目的な空
間」。商業・業務・学区・居住などの<性格>づけ。それらの
地域間を結び付ける「交通(網)」体系。都市住民の多種な要
求に体系性を与え、全体としての整合性をもつ、全体として
の合目的性、あるいは合理性の反映した存在。○それらを、
進める<優先的な意思>は、<市民>の自由意思による選択を、
最大の根拠としている。○大概の「都市」を語る書物は、こ
うしたレベルから、つまり大所高所、為政者などの視点から、
・・・延々と蓄積されてきた、そして世界を獲得してきた、権力
を背景として成立している。つまり、近代・現代は、西欧が
世界の中で圧倒的優位をもってきた。それの反映として、「都
市」があり、「都市論」があった。そして、あり続けている。
ということなのだ。○それに<翳り>(かげり)が、見えてきた。
そう指摘されてきたのは、1960年代後葉のことだ。世界が
<新しい価値観>の模索に入ったころのことだ。戦後のベビーブ
ーマー世代が青年期に突入したころのことだ。この時期の、産
物、あるいは獲得物の評価には、虚実を交え、賛否両論が山積
している。が、それほど、というのは思ったほどのの意味だが、
それほど大きな実りの獲得に至っていない。のだ。○延々と
続いてきている「都市論」の変化には、この間のプロセス的変
化を無視できない。ということだ。
○(略)
○(いくつかの、中)をはさんで。
○東京は、<「の」の字、プラン>をもつ。中心のない中心をしめ
る「皇居」を基点として、南から、「右回り」で、「の」の字を、
描く。というものだ。言い出しっぺが、だれなのかは定かではな
い。が、ともかくそう言われてきた。東京の「都市化」は、江戸
から始まるとされる。家康のブレーンだった、天海僧正などの正
体不明の知恵者たちの思考の結露だというのだ。さまざまな憶測、
推測、夢想が羽ばたく場でもある。○「南」から回り始めるのは、
<向日性>だからだ。太陽にむかう、からだ。ぐるぐる回って、4
00年も経った現代では、4~5回ほどは、回っているとされる。
あははっ。<Hanako の銀座特集> の比ではないのだ。この程度の
ことは、地区別の発展、地価上昇、人口の集中、増減などで、<実
証可能>なものだ。たぶん、それはなされているはずだ。○その<南
回り>の発展。に対して、他の地域との交通として、<放射状の道路
>が、重なる。発展に関しての重いファクターの2番目がこれだ。
○問題は、1,2,とファクターを重ねていく。という遣り方。考
え方。にある。つまり、「それ以前」を、払拭しない。払底しない
ということだ。対するのが、「堆積」であり、「重層」(かさなり)
という概念が、「都市計画」に<温存>されるという風景が成立する。
のだ。はじめの<世田谷の農道>も、そうした「風景」のひとつなの
だ。ここらあたりが、オモシロイ。ヨーロッパと対比されるのは、
こうしたことからきている。なぜそうなるのか。という答えも、用
意されている。<強・権力>の不在、だ。その答えは、答えの中の一
つでしかない。結局の論は、日本人は、望まない。に、落ち着くの
だ。いずれにせよ、<強・権力>も時に台頭するが、一時に過ぎない。
サンドウィッチのなかのレタスのように、青々とした<権力>が、歴
史を彩っている。○こうして、<農道>がのこる。残った。江戸時代
の大場代官時代のものだ。世田谷の「大場一族」が、残るように、
<農道>も、ということだ。こんな不思議な光景、風景は、日本では
いくらでもある。「堆積」「重層」された、風景だ。それらのなか
には、うち捨てられた風景もあれば、都市の中で脈々と、連綿と、
生々と、粛々と「存在」している<モノ>もある。○はじめに戻る。
こうした空間の生成というべきか、形成か。この味に興味を、妙味を
覚える「変な外国人」が登場してきている。ということだ。○この
あたりの「吟味」は、また。
○ファクター、1,2と記している。この、1,2自体に優先的な
意味はない。はずだ。便宜的な、あるいは分かりやすさ、説明の仕
方が先行しているだけだ。○概念的なものの説明には、デッサンを
するように全体像を捉えやすくするために、できるだけ大きな部分
から入るのがコツだ。ただそれだけのことだ。○ファクター2,の
「放射状の道路」は、他の地域との接続路なのだ。東海道・中山道
・奥州(東北)道・水戸道・などの主要幹線の基点は、「日本橋」。
とした。交通手段。その開発には、自然的な条件がおおきく影響す
る。河川・池沼・丘陵・山地・などの(ここでも、これらも)ファ
クターだ。(笑い)○再び、東京。を、例として見るなら、ここで
もやっぱり「世田谷の農道」に、拘っている。東京図に、左の掌
(てのひら)の指を開いてかざす。その指、ひとつひとつが、東京
の<丘陵>、きょうりゅうではない。を示すという。上(北)から、
赤羽台・・・中に、駿河台、・・・・南に、多摩丘陵。その間に、ふたつ
あるが、急遽健忘のため略す。が、それらの丘陵・台地が、東京
の起伏のある景観(風景)を演出し、大舞台の雰囲気を醸し出して
いる。ここらあたりが、野宮さんへのサービス。
(2005.05.10 20:20:50)
○この起伏のある東京の風景。これを前提にするにしても、自然
の恩恵だけで、これだけの巨大な人口を賄えるだけの地勢の確保
には至らない。自然との抗争がある。西欧の、大陸の、歴史的な
都市と同じように、自然との確執の「開発」の歴史がある。のだ
。江戸初期の<八重洲>。それは、幕府のお抱え学者、ヤン・ヨー
スティンから命名されたという。が、その土地は、そもそも。そ
もそもばやりだが、江戸湾の入り江のなかの入り江。なのだ。古
地図を参照して欲しい。それが、分かる。はずだ。とりあえず、
日本橋の古地図専門店アタリか。はたまた、国会図書館か。広尾
の都の中央図書館か。まあ、どこでもいいが、どこにでもあると
いうものでもない。○<八重洲>の入り江は、駿河台の丘陵を掘削
し、その土で埋め立てられた。その周辺にも、かなりの湖沼が、
散見され。それらを埋め立て、居住地とした。<下町>と、江戸初
期に呼ばれたエリア、もしくはゾーンは、そうした開拓の地だ。
コトバを変えれば、<悪所>だ。地盤の劣悪な土地。という意味だ
が、現代の不動産業者は、そんなことにお構いなく、結構な価格
を設定し、無知なる大衆に高値で売りつける。そうしたことが、
露見するのが、地震の災害時の時だ。地盤の<悪い>、というのは
耐久性、つまり地質力の劣る「場所」ほど被害が大きい。それら
によつて、露見する。最近の大地震の被害地と、江戸期の埋め立
て地を、重ね合わせると、それがピタリと重なる。のだ。○こん
なことは、既知のことだ。
○おもしろいのは、江戸・東京・日本人が、これらの土地の扱い
方にある。というのが、オギュスタン・ベルク(など)の指摘だ。
人工物であるものを、<自然化>してしまう。のだという。それが
、錯覚でも、健忘症でもなく、自然に還元するかのように。それ
を為す。当然のこととして。そこに着目するのだ。これもまた、
なかなかいい。が。○<神田上水>は、人工の用水であり、都市上
水なのだ。これがいつの間にか、<神田川>になっている。という
のだ。こんな例には、いとまがない。が、かれの指摘するポイン
トの優秀さは、その先にある。この自然に還元された<人工物>の
、コストの高さを指摘するのだ。このあたりになると、おもわず
唸らざるを得ない。「う~む。」である。自然的にみえるものが
、実はなにひとつ、自然のものではない。
○手間暇掛けて、金掛けて。自然に戻している。畏るべき「光景
」のことだ。(ここから先がダイナミック。)
© Rakuten Group, Inc.