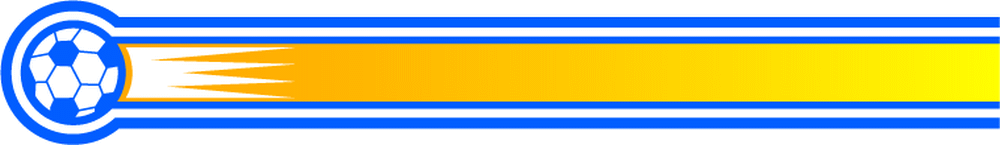沖縄(入門編)
ここでは、本土からきた新入生向けに書いた入門編です。ウチナーンチュは知りすぎているので、ほとんどためにならないと思います。
それでも読んでくれた方、間違いがあったら指摘してください。
丁重に直させていただきます。わたしも本土からやってきたたちなので。
1、沖縄そば
沖縄で「そば」といったら、沖縄そば。むしろ日本そばを食べるのは難しいくらいです。安いものは300円くらいから(実は100円そばなんていうのもあるゾ!)、ちょっと豪華な800円くらいのものまで、さまざまあります。
スーパーに行くと、沖縄そば以外に、宮古そば(宮古すば、という表記もある)や、八重山そば、なんかも良くみられる。麺の形が少し違うような気がしますが、やっぱり普通の沖縄そばが一番かなぁと私は思います。
ウチナーンチュは沖縄そばにはうるさいらしく、図書館で見ただけでも、「ここの沖縄そばはうまい」みたいなことを紹介する本が何冊もあります。「旅の会」でもぜひ一度、食べ比べを企画したいと思います。
2、泡盛
沖縄といったら泡盛でしょ。ふつうは「しま」といって親しまれています。「久米仙」「菊の露」「くら」ぐらいがポピュラーなのかな。5年以上寝かしたものは「古酒」(クースー)と言って、味にも深みがあって絶品。それなりの値段がするのでなかなか普段飲めないのが悔しいのですが。
泡盛は一升瓶で買っても、1000円ちょっとというのがウレシイ。ふつう買うのは、アルコール度数が30度か25度くらいのものですが、それは43度くらいの濃さのものを薄めて飲みやすくしたものらしいです。ちなみに与那国島には「土南」や「舞船」という酒があって、アルコール60度!これはすぐ酔っ払った!
ちなみに泡盛は、ビールや日本酒(とくに安いやつ)と違って、二日酔いになりづらい気がします。これなら翌日に朝から授業があっても、バッチリ飲めますよ!でもほどほどにね。
3、ゴーヤ
もうテレビの「ちゅらさん」などを通して全国に知れわたってます。あのボツボツで濃緑色の物体が、別名「にがうり」のゴーヤー。苦いんです。なのにおいしいんです。不思議ですねぇ。ウチナーンチュはだいたいみんな食べてるのですが、時々「嫌いだ」という人にもぶつかります。しかしチャンプルー(炒め物。具としては何を入れてもかまわないらしい)にゴーヤは欠かせません。ゴーヤを避けて、チャンプルーは考えられません、と私は思います。
ゴーヤを包丁で切ってみると、中には種とその周りのフニャフニャとしたものが詰まってて、この取り除くのにはじめは苦労しました。しかし、金属スプーンを使って、ガリガリやるときれいに取り除くことを発見し、今はおそるるに足らず。夏、6月くらいになると、100g30円くらいまで値が下がるので、その頃にゴーヤ料理を満喫しましょう。
4、サーターアンダギー
これは安いお土産かな?家族に買っていくお土産で、沖縄っぽいものとしてはまずあがるものでしょう。大きい玉が8個くらい入って400円以下で買える。しかも2個も食ったらお腹いっぱい。貧しい時代に甘くてお腹いっぱい食べられる子どものおやつだったのでしょう、きっと。
家によって味がちょっとづつ違うらしい。オバァ直伝のサーターアンダギーが各家庭にはあるようです。是非一度、教わって、自分で作ってみたい食べ物の一つです。
ちなみにお土産と聞いて、「チンスコー」を思い浮かべた人は多いと思いますが、ウチナーンチュは普段はまったく食べてません。あれはきっと観光客用なんじゃないのかな?ホントのところは知りませんよ。
5、ポーク
「ポーク・ランチョンミート」というのが正式名称のようです。ミンチにした豚肉をかためたものです。沖縄で全国消費量の99%を消費しているらしいです。確かに沖縄以外で売ってるのを私は見かけたことありません。スーパーに行けばどこでも山積みになって売っています。種類も10種類以上あって、食べ比べしたことはありませんが、比較的安いのはにおいがきつくマズイ。料理の仕方によるのかもしれませんが。
ポークのすごいのは、焼いて煮てもうまい、とにかく何にでも使えるところがホントにスゴイ。もっともポピュラーなのは、「ポーク玉子」。焼いたポークの傍に卵焼きを添えただけの料理ですが、簡単に料理できるところがグッド。沖縄ではポークを味噌汁にも入れてしまう。ちなみにある本で紹介されていましたが、ある飲み屋でポークを適当に短冊形に切って湯通ししただけのものが出てきたとか。それがその店のお通しだった!・・・まぁこれは普通ありえませんので。
6、豚肉
沖縄では、「豚モモ」とか「豚ロース」とかお上品なものではなく、耳から顔からすべて食べてしまう。耳は「ミミガー」といって、コリコリしてておいしい。顔は「チラガー」という。公設市場なんかに行くと、ドテッと置いてあって、よーく見ると、「安田大サーカス」の左側の人に似てます。ちなみにあの人、高血圧と医者に診断されてペットボトル一気飲みは止められてるそうです。
そのほか、「ソーキ」とか「ラフテー」とか「テビチ」とか沖縄ではなければ聞いたことがないようなものにも出会えると思います。
7、シーサー
これはもう全国的に有名になってますね。屋根の上や家の入り口などに多々見られます。お土産屋にもズラリと並んでます。
これは本来、魔よけの獅子らしく、直接は中国から伝来したもの。2体並んで1対になっているのが通常のようです。右側のものが口を開けていて福を招きいれ、左側のが口を閉じていて災難を家に入れない、というものらしい。
しかし実際、お土産屋に並んでるシーサーなんかはどことなく愛嬌があって、魔よけになるのかな?と思えてしまうのは私だけではないでしょう。シーサーも古いやつから新しいものまで、表情も形もいろいろあって面白い。そんなものを調べてみるのも案外楽しいかもしれません。
8、南部戦跡
沖縄にきたら、やっぱり見ておきたいところ。沖縄は戦争中、地上戦を体験しています。そしてたくさんの住民が殺されました。当時の沖縄の人口の3分の1ともいわれています。とくに沖縄本島の南部は激戦地で一家全滅ということも少なくはなかったそうです。またガマ(自然の洞窟のこと。戦時中は防空壕として使っていた)に逃げて命からがら生き延びた人たちも、戦後、米軍の占領下におかれ苦しい生活を強いられました。
沖縄にはたくさんの米軍基地があります。これらの多くは、戦時下で日本軍が住民を動員して築いた飛行場を米軍が占領した場所だったり、また米軍が住民に収容所生活を強いている間に広大な土地を囲い込んだ場所だったりします。沖縄では「戦争はまだ終わっていない」とも言われますが、本当にその通りだと思います。
糸満市にある「平和記念資料館」「ひめゆり資料館」などは、一度ゆっくり見学しておきたいところです。またガマの見学は必須です。戦争について考えるためにぜひ行ってみましょう。
なお6月23日ですが、この日は沖縄戦において日本軍の組織的戦闘が終了したとされている日(沖縄戦終結の日ではありません、念のため)で、沖縄では「慰霊の日」として休日になっています。この日を前後して、「旅の会」でも戦争について考える企画をしたいと思っています。
9、首里城
まず沖縄観光といったら、首里城でしょうか?戦争で焼失してしまったものが再建されたのは、1992年。朝から夕方まで、観光にきたオジさん、オバさんで賑わってます。「守礼の門」に至る道には、琉葬を着た女性が立っていて、記念写真を取れるようになってます。けっこうな値段らしいです。
首里城正殿、王様がいた場所でしょう、ここは有料です。たしか800円。実は「金払ってまで・・・」という私は、まだ一度も中に入ったことはありません。隙間からチラリとのぞいてみただけです。
10、ウチナーグチ
沖縄言葉のことです。けっこう大学内でも飛び交っています。当たり前か、沖縄なんだから。でも、会話が聞き取れないほどではありません。でも、30代中盤から40代以降のオジサン、オバサンたちの会話は、ほとんど聞き取れないと思っていいです。まぁ全国どこでも、方言で会話されたら聞き取れないのはどこでも同じだと思いますが。それでもウチナーグチは、共通語とはまったく違う響きです。
聞きなれない言葉パート1
サークル員が集まって話している時に、そのうちの一人が「生協行こうね」あるいは「生協行きましょうね」と言ったとします。はじめてこれを聞いた時は、「生協に行こうと誘われてるのかな」と思ったものですが、実は違います。この「・・・しようね」「・・・しましょうね」という語尾は、沖縄では「・・・するから」とか「・・・しますので」という意味で使われるようです。「生協行ってくるから」とみんなに告げて一人トコトコ生協に向かうことになるのです。
50くらいのオバサンでも「これから出かけましょうね」などと言ったりするので、一瞬びっくりします。もう今は完全になれましたが。では、終わりましょうね。
© Rakuten Group, Inc.