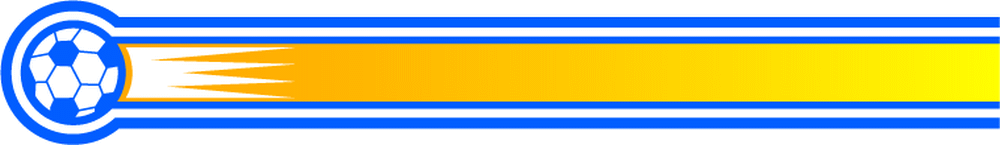〇六年沖大祭報告(1)
THE・データ ~那覇~
1、人口、面積など
人口は、31万688人(05年3月31日現在)です。県庁所在地としてはそれほど大きくはありませんが、人口密度はかなり上位で、1平方キロメートルにつき8005.1人。これは人口百万以上の福岡市や京都市、二百万以上の名古屋市よりも大きい数値です。
面積は39.04平方キロメートルです。そのうち基地面積は、4037千平方キロメートルで、市域面積の約10.3%です。ということは実際の人口密度は、数字以上ということでしょう。基地内はけっこうがら空きですから。
2、市民のお財布事情
市民一人当たりの所得は、198万3千円(02年)です。月に直すと、16万5250円。月ごとの1世帯あたりの消費支出額は22万8545円。市民所得と比較すれば、家族は一人働いただけでは生活を維持できないということになります。結局、共働きが基本になります。
ところで進学率は高校が96.5%、大学が40%。けっこうな割合で、親のスネをかじっています。この教育費がどのくらい家計の負担になっているのか分かりませんが、決して軽いとは思えません。大学まで払ってもらうとするなら、けっこうな負担でしょう。負担は一体いくらになるのでしょうか?「親の財布、子知らず」
3、市民のたばこ事情
那覇市の一般会計114,924,209千円の29.3%が市税でまかなわれています。うち6.8%が市たばこ税。2,280,091,533円。
ところで一箱300円のタバコで税金分は約190円。うち市に入る地方たばこ税は、約66円。市たばこ税総額を66円で割ると、年間約34,546,841箱を市内で売買しているという結果が出てきます。1日に換算すると、約94,649箱。
4、那覇市の一日
結婚6.0件、離婚2.5件。人生いろいろ。
水道供給量1人あたり348リットル。ちなみにシャワーなら1分間で15~25リットル、水洗トイレなら5リットル(小)または15リットル(大)だそうです。
ごみは1日301トン。1人当たり約1キロの計算です。し尿は25,296トン。1人当たり・・・勝手に計算してください。
(※数値データは「那覇統計書」(平成17年度版)より)
THE・その辺 ~沖大~
1、沖縄大学のつつがなき日々
旅の会の某T君の一日について紹介します。
朝起きて、1講時に間に合うように準備して、正門からの急な坂道を汗をかきつつ登校し、昼は「どん亭、ルビー、ときどき山原」、夕方は「ローソンorファミマ」で菓子パンをかじり、家路に着く。充実の一日です。
せっかくなので、沖縄大学を紹介します。
「一九五八年に開学した沖縄短期大学を前身として一九六一年に創設された沖縄大学は、草創期や沖縄の祖国復帰時の困難な時期を経て、一九七八年に『地域に根ざし、地域に学び、地域と共に生きる、開かれた大学』という基本理念を打ち建て、地域になくてはならない高等教育研究機関となることを目指し、様々な改革努力を重ねてきました。」(「沖縄大学ホームページ」より)
ちなみにT君が正門で汗をかいてしまう理由。
「沖大は『祝嶺森』を切りひらいて建てられました。『祝嶺森』は、沖尚校舎らへんにあった『祝嶺毛』という丘のすそに広がる森でしょ、たぶん。高台に建てるから汗をかくんです」そう言って、汗をかきかき正門の坂道を登るわがサークルのT君。はぁと息を吐き、ポケットから取り出したのは青いハンカチ。「“王子”と同じ青いハンカチなのに・・・」とさらに深いため息をつくのでした。
2、国場という地名の由来
沖縄大学の住所は、「那覇市国場555番地」です。ということで(国場)という地名の由来について調べてみました。
沖大周辺の調査の下調べでたびたびお世話になりました「国場誌」からの紹介です。そもそも(国場)という漢字は、たんなる当て字だそうです(こくば)という音に(国場)という文字を当てはめたということです。「国場誌」によると、(こくば)は地形に由来する地名です。そして(こくば)は(くくば)と発音されていました。
(くく)は、クボ(窪)→クブ→ククと変遷しました。つまり(くく)、すなわち(こく)は、「窪地」を意味します。一方の(ば)は、これは漢字の通り「場」を意味するようです。ちなみにウチナーグチでは、「場」のことを、(ば)・(ばら)・(ま)・(ら)などと発音するらしく、こうした音で終わる地名が沖縄各地にあります。国場の近くには、上間や仲井真という地名がありますが、この(間)も(真)も、「場」を意味するそうです。
つまり、上間―仲井真―国場は、(上の場所)―(仲〔中間〕の場所)―(窪地)というように、高いところから次第に低いところへと至る一連の地形に由来する地名らしいです。
ちなみに、国場は、「沖縄ファミリーマート」発祥の地でもあります。「一九八七年十二月に、那覇市国場に1号店を出店しました。」(「沖縄ファミリーマート」ホームページより)
3、完全決着!?「寄宮」の読み方
「寄宮交差点」、「寄宮中学校」と、沖大近くには「寄宮」という地名があります。みなさんはこれをどう読んでいますか?「ヨリミヤ」?それとも「ヨセミヤ」?
どちらも聞いたことがあって、以前タクシーの運転手に尋ねた時は、「どっちでもいい」という返事でした。「どっちでもいい」なんて、なんとなくむずがゆい。
そこで調べてきました。またまた「国場誌」より。
「寄宮は、戦後間もない頃、大字国場の小字寄増原と大字与儀の小字宮城原が合体し、それぞれの小字の頭文字をとって『寄宮』としたのである。」(p83)
「寄増原」は(ヨセマスバル)と読み、「宮城原」は(ミヤギバル)と読みます。ということは、「寄宮」は(ヨセミヤ)と読むのが正しいということになります。まさしく、完全決着!
「すごい発見をしたものだ」と思いつつ、今度は「沖縄地名総集」(大城盛光著、むぎ社)を手に取ってパラパラとめくってみました。「大字一覧」のところをみていると、あった「寄宮」。その読み方は、ヨセ・・・あれ、「よりみや」。「よりみや」って書いてありました。
完全決着、と思ったのですが、どうやらタクシーの運転手が正しいみたいです。
4、真珠道(まだまみち)
正確には分からないのですが、だいたい沖尚のそばを通って、沖大の裏側を通って、真玉橋に至るコースだったようです。
ちなみに、真珠道というのは、首里王府の時代に首里と島尻を結ぶ幹線として整備されたものです。いざというとき、首里城を出た部隊は真玉橋を渡り、島尻の各地からやって来る軍勢と合流、那覇港口の南岸、垣花に位置する屋良座森城(ヤラザムイグシク)に集結し、外敵の侵入に備える必要があった、ということです。今でいうと、58号線くらい重要な幹線だったのでしょう。
ルートは、首里城前石門―首里金城の石畳道―識名坂(しきなヒラ)―真玉橋―石火矢橋(いしひやばし)―那覇港南側の垣花。
5、日本軍射撃場
「国場誌」より。射撃場は明治時代にできたみたいです。「沖大正門前から県道46号を北上し、寄宮中学校正門前から電柱通りへ出て国場消防署前を通り、沖大後ろの里道(田畑に通じる小さな道で公地であった)を経て沖大正門前の区域を言う。」これが勝良股原(カツラマタバル)の説明です。射撃場はここにあったそうです。そして「県道46号線沿い、沖縄大学の北側に位置する丘」(=クチャミ毛)の斜面に、弾打ち込んでいたそうです。
以下、偶然発見した「沖縄タイムス」の記事ですが、射撃場を狙った爆弾だったのでしょうか?
<一九九七年二月十五日> 夕刊 1版 社会(5)
あす不発弾処理/沖縄大学
那覇市国場の沖縄大学駐車場内で見つかった不発弾(米国製五十キロ爆弾)の処理作業が、十六日午前十時三十分から行われる。
半径四百十メートル以内の三千七百世帯(一万二千三百人)と三百六十事業所が避難対象。避難開始は午前九時三十分から、場所は真和志小学校、古波蔵小、上間小の各体育館と国場公民館。
作業に伴い、午前十時十五分から、寄宮交差点から国場交差点一キロ間の県道46号と、寄宮交差点から真玉橋交差点間約一キロの市道が全面通行止めになる。
6、昔、沖縄には鉄道が走ってた ~軽便鉄道~
戦前走っていた「軽便鉄道」は、「ケービン」と呼ばれ親しまれていたそうです。
一九一四年に那覇~与那原間の与那原線が営業開始。つづいて糸満線が計画されていましたが、第一次世界大戦によって資金調達ができず、一時棚上げに。大戦後、糸満線が先か、嘉手納線が先かで議論になりますが、結局一九二二年、嘉手納線の営業が開始されました。当時の沖縄の基幹産業であった糖業が中部でさかんだったことが、嘉手納線に有利に働いたようです。糸満線も翌二三年に営業を開始します。鉄道は新たに登場したバスとも競争しながら活発に運行しました。しかし沖縄戦の戦禍をうけて、一九四五年三月に機能を停止しました。
沖大近くを通っていたのは与那原線です。国場川沿いを機関車が時速十六キロほどでのんびり走っていたようです。現・那覇バスターミナルにあった「那覇駅」を出発した機関車は、国道三二九号線に沿って走っていました。現・ベスト電器国場店の前にトンネルがあり、そこから川沿いを走り真玉橋との交差点付近にあった「真玉橋駅」に到着。さらに川沿いを進み、現「丸彦アパート」(樋川バス停前)の裏手に「国場駅」があったようです。
いくつか当時の名残を紹介します。ひとつは三二九線沿いにある壷川のローソンの裏手にある「壷川東公園」です。当時の鉄道が残っています。鉄道の上に乗っているのは「南大東島でさとうきび等を運搬するのに使われていたディーゼル機関車と蒸気機関車」だそうです。もうひとつは、真玉橋交差点を越えたところの「モス・バーガー」の道路を挟んだ向かい側にある下水道。「溝にレールを架けるために溝の両側にはコンクリートによる工事が施されており、その跡が現在残っている。場所によっては赤いレンガが残されていることもある」(「ケービンの跡を歩く」〔金城功著、ひるぎ社〕)
© Rakuten Group, Inc.