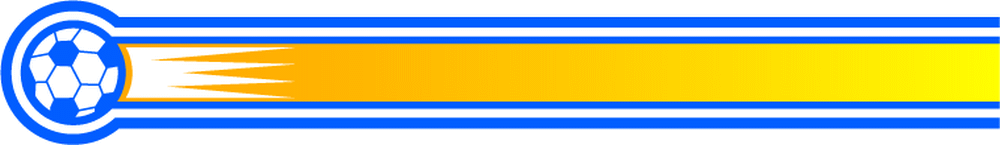07年沖大祭報告(3)
九月、渡嘉敷島へ
九月二十二日、二十三日に渡嘉敷島に行ってきました。以下、報告します。
九月二十二日(土)、朝九時に「とまりん」に到着。「フェリーけらま」に乗船しようとする人たちが窓口前に行列。十時出港。渡嘉敷まで約七十分。波が高いためかやや揺れが大きく、船酔い。
島に上陸。まず、渡嘉敷村渡嘉敷の集落を歩いて回りました。酔いもさめた頃、まず初めにたどり着いたのが「根元家の石垣」。精巧に積み上げられた石垣です。人家のコンクリート壁とは雲泥の差です。中は廃屋になっていて人は住んでいませんが、この石垣は村の貴重な文化遺産です。根元家は、琉球王朝時代に繁栄していました。当時、中国に渡る船の船頭役を勤めていた当家の主が稼ぎ出した財力で造ったものだそうです。第二時世界大戦で一部が破壊されましたが、十年ほど前に修復されました。
石垣から五十メートルほど歩くと、あえなく「渡嘉敷神社」に到着。入口の鳥居だけが目立ちます。鳥居は「昭和十二年一月」に建てられたものです。この鳥居は南方漁業に出稼ぎに行った人たちが寄進して作られたものだそうです。また、沖縄戦の時の砲弾の跡も残っています。鳥居自体は、沖縄に古くからあるはずないですから、その当時の皇民化教育の影響の一つなのでしょうか。
それから歩きました。ひたすら歩きました。途中の田園風景あたりまでは本島でみられるようなさとうきび畑とは違い、ハイキングみたいで気持ち良かったのですが、だんだんと暑さが。とにかく日陰がありません。港に着いた観光客は、港からバスに乗って各ビーチまで一直線。旅の会は、バスから眺められながらひたすら歩きました。地図ではすぐそばに思えたのですが、隣の集落である渡嘉志久までの山道を一時間以上歩きました。これでみんな死にました。
目的は昼ごはんでした。食堂が見当たりません。やっと見下ろせるところまで近づいた渡嘉志久にも食堂がある雰囲気が感じられません。海の青さは素晴らしかったのですが、その時はグレーに見えました。後で調べたところによると、建物群は「国立沖縄青年の家 海洋研修場」と「渡嘉志久団地」でした。泣く泣く、そして企画担当者は突き刺さる視線を痛いくらい感じながら、さらに南の集落である阿波連へ向かって無言で歩きはじめました。
さらに山道を歩くこと十分。一台の車が目の前に停車。「阿波連まで行くのか?乗りな」。この時、おじさんが仏様に見えました。おじさんの優しさに涙し、涼しいクーラーにあたりながら、たった五分で阿波連に着きました。
阿波連は、ビーチ目的の観光客で賑わっていました。旅の会は、ビーチ近くの食堂で腹ごしらえをし、それから「阿波連のクバ林」へ。クバは渡嘉敷島では生活に不可欠なものだったらしく、クバの葉を乾燥させ、クバ扇、クバガサ、クバみの、クバジー(クバの葉のつるべ)などがつくられていました。また特に、阿波連や渡嘉敷では、クバの葉を数百枚、数千枚も組み合わせて小型の舟の帆を作ったともありました。首里王府の時代になると、クバは王府に納める上納品になりました。クバ山だけではクバの生産が間に合わない時は、海を渡って慶留間島や阿嘉島からも取り寄せたそうです。
ビーチで泳がなかったのかって?ビーチには立ちました。見渡しました。靴にも白い砂がいっぱいつきました。感動でいっぱいです。唯一の失敗は、小さい時から泳ぎの練習をせず、今もってカナヅチ、しかもおぼれた経験から水が怖いということだけです。よって、阿波連ビーチに立ったのが渡嘉敷島で唯一のビーチ体験でした。
夕方には、阿波連ビーチから再び渡嘉敷へ。今度はワゴン車で。わずか十分ほどでした。それから呑みはじめて、七時には呑み屋へ。店のご主人や観光客のお兄さんといろんな話ができました。
ご主人は、「灰谷健次郎氏の邸宅」の建設に関わったそうです。場所を聞いてビックリ。旅の会がヘトヘトになって車に乗せてもらった直前に、眼に入っていた白い建物のことでした。そうと知らずに、その時は「何かの観測所かな?」と思っていたのです。渡嘉志久の青いビーチを眺めながら、創作活動をしていたのでしょうか?灰谷氏は昨年なくなりました。ご冥福をお祈りいたします。
十時には呑み屋を出ましたが、大して食べてないことに気づき、「新浜屋」のカップラーメンで腹ごしらえをしてから宿へ。一夜を明かすのは、露天風呂ならぬ露店寝室。別名「港の待合室」。夜は星がきれいでした。写真がないのがもったいないくらいです。もちろん、そんな星空にまったく気づかず、朝まで携帯落としたまま眠りにふけっていたたメンバーがいなかったわけではありません。
翌二十三日。七時半にタクシーに乗って北山(ニシヤマ)へ。目的は「集団自決跡地」。そこは「国立沖縄青年の家」の敷地内にひっそりと立っていました。以下、碑文より。
この台地後方の谷間は去る大戦において住民が集団自決をした場所である 米軍の上陸により追いつめられた住民は友軍を頼ってこの地に集結したが敵の砲爆は熾烈を極め遂に包囲され行く場を失い刻々と迫る危機を感じた住民は「生きて捕虜となり辱めを受けるより死して国に殉ずることが国民としての本分である」として昭和二十年三月二十八日祖国の勝利を念じ笑って死のうと悲壮な決意をした 兼ねてから防衛隊員が所持していた手榴弾二個づつが唯一の頼りで 親戚縁故が車座になり一ケの手榴弾に二、三十名が集まった瞬間不気味な炸裂音は谷間にこだまし清流の流れは寸時にして血の流れと化し 老若男女三一五名の尊い命が失われ悲惨な死を遂げた
昭和二十六年三月この大戦で犠牲になった方々の慰霊のためこの地に白玉の塔を建立したが米軍基地となった為に移設を余儀なくされた 時移り世変わってここに沖縄の祖国復帰二十年の節目を迎えるに当り過去を省み戦争の悲惨を永く後世に伝え恒久平和の誓いを新たにするため ここを聖地として整備し 碑を建立した
「集団自決」に関しては、現在、「教科書検定意見」をめぐって大きな問題となっています。九月二十九日には「教科書検定意見撤回を求める県民大会」が開催されました。偶然にも、大会前に跡地を見学することになりました。
そこは本当に静かな場所でした。ウグイスの鳴き声が響いていました。石碑の後ろからは小道が伸びていました。どんどん下っていくと、突如目の前に二股に分かれる木が立っていて、先へ進むのを押しとどめていたような気がして、そこで立ち止まりました。周りはうっそうと木が生えていました。当時はどうだったのか知りませんが、とにかくひっそりとしていてなんともいえない気がしました。沢のせせらぎが聞こえ、そこまで下りたい気持ちにも駆られましたが、当時の状況を考えてしまうと動けませんでした。じっとすること十分、またもとの道を引きかえしていきました。なんだか下りてくる時にクモの巣を取り払ったこともすまない気持ちになるような、草を踏むことも気になるような不思議な気分になりました。ここは生と死が交錯した場所です。そして今も、島の人たちの心にあるでしょう。なお、タクシーの運転手のおじさんに聞いたところによれば、日本軍の陣地は沢からわずかしかはなれていません。住民と軍が混在していたと思われます。
次に、島で一番の高台と思われる展望台へ向かいました。やや靄がかかっていましたが、儀志布(ギシップ)島や前島、黒島がはっきり見えました。慶良間海峡の青い海も、座間味方面も見えました。
「青年の家」まで下がって休憩。碑文にもあったように、ここは米軍基地跡地です。「渡嘉敷村ホームページ」によると、一九六〇年三月二十二日に「ホークミサイル基地特収命令書」が交付され、すぐに基地建設がはじまりました。それまで鰹漁船乗組員だった島民の大半が基地労働者へ変わっていきました。慰霊の塔「白玉の塔」も軍用地内から移動されます。一九六二年六月一日には米軍ホーク部隊二百五十名西山基地へ進駐しました。そして沖縄返還前の一九六九年八月二日には、陸軍第二兵たん部隊司令官ホーナー少将参列により基地閉鎖式が行なわれました。
疲れていたので動けるメンバーだけで再び山に登って「赤間山立入所跡」へ。首里王府の時代には、渡嘉敷島は中国へ渡る船(渡唐船)の航路に当たっていて、その帰りをいち早く首里王府に知らせるために、ここで火を焚いて知らせたそうです。明治以降は、島から離れる島民を見送る際に火を焚いて、旅路の平安を願ったそうです。多くの島民が本島へ行ったり、さらには南洋諸島へも渡ったのでしょう。今は片道七十分、千六百二十円払えばカンタンに那覇へ行くことができますが、当時の旅は別れを意識するようなものだったのかもしれません。こうしたことから別名「ヒータティヤー跡」(「火を焚く所」の意?)ともいわれています。
十一時半には、朝にお世話になったタクシーに再びお願いして港まで戻りました。出港までお土産を買ったり、ボーっとしたり、コンビニ行って買い物したり、ボーっとしたり。帰りも「フェリーけらま」。実は、前日にヘトヘトのメンバーを車に乗せて下さった方も、呑み屋で一緒になった観光客のお兄さんたちも、同じ船に乗っていました。大変お世話になりました。
以上、渡嘉敷島の一泊二日の旅でした。
※すべての報告は、「旅の会ブログ」を参考にしています。「旅の会」をyahooでブログ検索すると、すぐ見つかります。興味ある方は、ぜひのぞいてみてください。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
- 楽天トラベル
- 美食と絶景に包まれる「HIRAMATSU HO…
- (2025-11-17 20:00:05)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 2025年12月18日~2025年12月22日 静…
- (2025-11-18 00:00:11)
-
-
-

- ★☆沖縄☆★
- 沖縄の産業まつりへ🌺子どもたちと見…
- (2025-11-03 21:57:49)
-
© Rakuten Group, Inc.