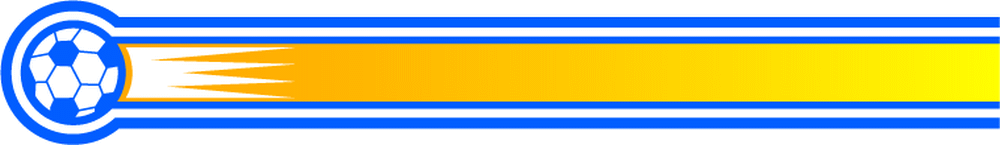首里城行ってきました!
2009・6・1
首里散策してきました!
5月31日、沖大から首里城まで歩いたゾー!
疲れたゾー!
のぼって、下って、のぼったゾー!
メシ喰ったゾー!
マックで待ちぼうけくらったゾー!
・・・詳しい報告は次回以降に回しますが、とにかく
疲れたゾー!!!
2009・6・3
首里城行ってきました!報告(1)
旅の会でいまさら首里城かよ、と言われそうですが、「灯台もと暗し」という言葉もあるように、以外と身近なところを知らないというかなんというか・・・。
それと識名園にも行くはずじゃなかった?という声もあるようなないような・・・それは今は秘密。とにかく報告を急ごう。
5月31日10時。メンバーが沖大正門に集合。今回はやや少なめでしたが、新しいメンバーも参加して、いざ出発。
昨年も首里城行ったんですよ。識名園から首里城コースで。で、同じじゃつまらないということで、旅の会はコース変えてきましたよ。
尚徳王の墓を横目に見ながら、昨年まったりした識名宮を素通りし、ファミマ繁多川店へ。
「ここからかなり歩くから買い物しといたほうがいいよー」というやさしい先輩の提案に、僕たちかわいい後輩は店内へ。
アメリカンドックとシークァーサージュースをかかえるS部長。
・・・喜々とする彼らが地獄を見るのはまだ先のこと。
さらに進んでいくと、識名霊園。するとそこに「歴史散歩の道」の目立たない看板が。左折ヒジガービラ。ここで昨年のコースから外れ、未知なる世界へ。
両脇墓に囲まれた小道をぐんぐん進んでいく。
「疲れた?」
「いや、まだ疲れてない」
まだまだ余裕の旅の会。
しばらく進むと、「県庁壕」の看板が。「とりあえず見ていくか?」
行こう行こう、ということでさらにお墓の深みに入っていく。
お墓の中に入ると、突如ポッカリ穴が。ロープが下ろしてあって、中に入ることができそう。ちょっとだけ降りてみる。中はかなり広そう。何も準備してきているわけじゃないから、ここまで。
一度来たことがある先輩の話によれば、ここは戦争中に最後の市町村会議が開かれたところらしい。
壕の存在は長らく知られていたが、ここが「県庁壕」だと分かったのは戦後何十年もたった後のことらしい。
自分たちがこれから歩くコースは当時の県知事が県庁壕と首里城地下の日本軍司令部を行き来するのに使ったかもしれないコースであること。
そんなことを話してました。
で、はじめのコースに戻りました。
カメラマンは仕事を忘れ、ここまで一枚も撮っていないことに気づき、いたく反省してました。
今回はここまで。
2009・6・3
首里城行ってきました!報告(2)

識名霊園のなかを歩く、一見怪しい集団。墓荒しか?いやいや、旅の会です。このまま坂を下っていくと金城ダム。
コースは元々は石畳だったようです。その昔、琉球の王様が首里城から識名園へ向かう時に使ったコースらしいです。
「金城町の石畳」は有名ですが、ヒジガービラは意外と知られてない。旅の会の目の付けどころです。
「県庁壕」から坂を下っていくと、金城ダムに到着。そこに古びた橋がかかっていました。これが「ヒジ川橋」。

ちょっと分かりづらいかもしれません。今は草に覆われて威厳がありませんが、その当時は王様が識名園に行くのに使ったらしい。
以下、説明板より。
ヒジ川橋及び取付道路
ヒジ川橋は、首里崎山町にあった御茶屋御殿から識名園に至る途中の金城川(現安里川上流)に架けられ、琉球石灰岩を用いた単拱橋(アーチが1つの橋)で、17世紀半ばまでにはつくられていたと考えられています。
橋の全長は13.18メートル、幅は5.2メートル。一見何の変哲もない橋ですが、歴史を感じさせてくれますねー、と感慨にふけっていると、うちのサークルの子ども(ガキ)が、近くの新しい橋の手すりに座って「ここ気持ちいいよ~」
子どもは高いところが大好きです。
ダムにぷかりと浮かんだカメが「カミツキガメだー!」と叫んだり(ホントはどうだったか分かりませんが)、とにかく高い所に登りたがったり。
子どもですから。メンバー一同温かい目で見守ってあげました。
交通量の多い道路を渡ると、目の前に階段が。ここから「ヒジガービラ」本番です。
以下、説明板より。
ヒジ川(ガー)ビラ
ヒジ川ビラは、琉球王朝時代に、首里から南へ伸びる幹線道路の一つとして整備されました。創られた年代は16世紀ごろと推定されています。首里崎山町を抜け、御茶屋御殿(ウチャヤウドゥン)(東苑)と雨乞嶽の間を越えて南へ降り、金城川(カナグスクガワ)(安里川上流)にかかるヒジ川橋を渡って、識名馬場の東端を過ぎる坂道を登り、さらに南の識名之御殿(南苑/識名園)へ通じています。
ヒジ川の名は、ヒラ(坂)の西側にある古くからの湧水「ヒジガー」の名にちなみます。ヒジガーは、見上げる岩のすき間から滴る水が鍾乳石をつくり、あたかもひげ(方言:ヒジ)のようになっています。

今度は登り。金城ダムから舗装道路を渡って登り始めるところが、もっとも歴史を感じさせる石畳・ヒジガービラ。この頃みんな、ゼーゼーゼー。得意の後ろ姿(?)に力がない。
とにかく進むしかない、ということで元気な子どもを先頭に、心なしか口数が減ってきた大人たちものぼっていきました。
「疲れた?」
「ちょっと、ね」
ここらへんの石畳は沖縄戦を免れることができたため、当時の様子をとどめています。急坂だなぁ、こんな道を南苑まで行くために王様は使っていたのかな・・・?
すぐに説明板にもあった「ヒジガー」に入る小道発見。藪の中を突進。「痛っ!トゲあるし」、「滑るし」と、まぁざわざわしながらすぐに到着。小さな滝みたいに、岩肌を水がチョロチョロ。

石畳から少し脇道へそれること数十メートル。これが道路の名前になった「ヒジガー」。チョロチョロ流れる滝(ってほどでもないけど)で疲れをいやす。
誰も前に出ようとしないところをS部長が、水の冷たさ確認。
結果、「そこそこ」。
全員さわってみて「そこそこ」感を確かめました。
ここは説明板によると
むかし、清明祭(シーミー)などで識名方面へ出かけた首里の人たちが、その帰りに岩から滴る冷たい水で喉をうるおし、一服する光景が見られたということです。
ちなみに「ヒジガー」に向かう小道の途中には、戦時中の壕のようなものもありました。
で・・・
メンバーの後ろ姿をお楽しみ(?)ください。

さらに登って、民家の脇を通って、ぱっと開けたところが「儀間真常の墓」。
メンバー内のウチナーンチュに聞いてみましたが、以外と儀間真常のことを知らなかった。けっこう知らないものなんですかね~?
以下説明板より。
儀間真常の墓(麻氏一門の神御墓)
儀間真常は、1557年に垣花に生まれました。1593年に真和志間切儀間村の地頭に任じられ、1624年に親方に叙せられ、1688年88才で没しました。
真常は、1605年に野国総管が中国からもたらした甘藷(サツマイモ)をもらいうけてその栽培普及に力を注ぎました。また1609年の島津侵入後、捕虜となった尚寧王につき随って鹿児島に赴いた際、木綿の種子を沖縄にもち帰って、その栽培法と木綿布の織方を広め、さらに中国から砂糖製造の技術も導入して国中に広めました。これらの功績から「沖縄の産業の恩人」と称されています。
もとの墓は、住吉町にありましたが、千五アメリカ軍の港湾施設として接収され、跡形もなく●きならされたため、1959年この地に移転建立されました。現在の墓は1993年に建て替えられたものです。
ここは景色がいいです。僕たちが歩いてきたコースも結構なもんだと思いました。儀間真常と、そのお墓がたどった歴史には、さらに多くの歴史が込められていることが分かりました。
ちなみに「儀間真常の墓」の隣に「田名本家之墓」が建っていて、その家紋は儀間真常の墓と同じものでした。どういう関係なのでしょうか?同じ「麻氏一門」なのでしょうか?そもそも「麻氏一門」はどういう人たちなのでしょうか?
まったく疑問は解けぬまま次へ向かいました。
今回はここで終了。
2009・6・3
首里城行ってきました!報告(3)
「儀間真常の墓」を後にして、小道を左折すると「国吉比屋の墓」。また墓。
いったい誰だ?国吉比屋って?以下、説明板より。
国吉比屋(クニヨシヌヒャ)の墓
国吉比屋は15世紀ごろの人で、査姓国吉家の始祖になっています。景泰年間(1450~56年)に真壁間切国吉(現在の糸満市国吉)の地頭職に任じられました。また、家譜に拠れば、中城按司護佐丸の子、盛親をかくまって養育したとも伝えられています。
この墓も「儀間真常の墓」とともに住吉町にありましたが、同じ理由で首里に移されたそうです。
ちなみに国吉比屋は、18世紀につくられた組踊「義臣物語」に主人公として登場しているそうです。某メンバーは「組踊見たことある」というから、みんなで「ホントに?」って聞いたら、「授業で、ビデオで」・・・。本物見たことあるのかと思いました。

これが国吉比屋(クニヨシヌヒャ)の墓。
ここから先にも名所が随所にあるので次々紹介しますね。
御茶屋御殿石造獅子
1677年につくられた王府の別邸後茶屋御殿にあった石造の獅子で、火難をもたらすと考えられた東風平町富盛の八重瀬岳に向けられていました。
18世紀、文人として名高い程順則が、御茶屋御殿を詠んだ漢詩「東苑八景」に「石洞獅蹲」と記され、御殿を火災その他の災厄から守る獅子が称えられています。
もとは、現在の首里カトリック教会の敷地にありましたが、がけ崩れの恐れが生じたので、現在地に移しました。
同じ公園内に有名な御嶽もありました。
雨乞嶽

雨乞いのおこなわれた御嶽は沖縄各地にありますが、ここは俗にアマグイヌウタキと呼ばれ、干ばつの打ち続く時に王様が親(みずか)ら家臣たちを率いて、この御嶽で雨乞いの祈願をされました。
・・・
ここから南西方向への眺望の広がりはみごとで、首里八景の一つとして「ウ壇春晴」(春雨の合い間に雨乞いの丘からの眺望が素晴らしい)とうたわれています。
たしかに眺めがいいです!
最近立てられたと思われる展望台にどっかり座ると、いっきに疲れが押し寄せ、空腹であることに気が付きました。ここから「腹減った、腹減った」の合唱がはじまった。
「疲れた?」
「すごく」
子ども以外はみなもう無口に。
遊歩道を歩いていくと、なぜか「足の裏健康道」みたいなのがあって、二人のメンバーが大はしゃぎ。「やってみー、気持ちいいから」の声に某メンバーは一言、
「靴下汚れるし」・・・。疲れてるんです。

すぐそばの崎山公園でまたちょっと休憩。ここも見晴らしが素晴らしい。しかし、ややもやがかかっていたのが残念。
と、そこに迷い犬が一匹。

嬉しそうに子どもが近づいていくと・・・・逃げられました。子どもと幼いが邪念に満ちた大人の違いは犬に簡単に見抜かれてしまいました。
腹減った。
そこから首里城へ一直線。といっても、見事に通り抜けて、芸大前を通って龍潭池通り(でいいのかな?)へ。

さすがは芸大、こんな作品があちこちに置かれていました。
すぐに食堂にin。たしか「いずみ食堂」。
「お姉さん、おススメは?」
「軟骨ソーキおいしいよ、てびちそばもいいよ!」
「どれにしようかな・・・、Sさんはてびちだよね?」
「うーん、軟骨ソーキで」
「わちきは沖縄そば(大)で」
あんまりおススメを聞いた意味がない注文になりました。
このときあとで聞いた話では、S先輩の口の中では口内炎が魔王のようにふるまっていて、軟骨ソーキを丸のみせざるを得なかったそうだ。
沖縄そば(大)が最後にやってきたのに、ブツクサ言ってた(でもないか)某部長は、食べ終わるとさっそく、いつもの、汚れなき(ウソ)、さわやかな(ウソ)、純粋な(ウソ)、世界にのめりこむ。
食堂のお姉さんにあれやこれや聞き出しながら、今度はG大生が姿を見せる平日に来ようと張り切っていました。
思う存分休憩を取った後、やっと首里城へ。実はまだ沖大を出発してから3時間ほど。なのにみんなぐったり。
2009・6・3
首里城行ってきました!報告(3)
昼食後、龍潭池を散策。



この後ろ姿必要?っていうご意見もありましたが、却下! とくとご覧あれ!
龍潭池沿いを歩いて(あそこ入って良かったのか?)、子どもがいうキモドリというやつを見に行く。
この日、道すがらたびたび「キモドリ」の話題が出ていたのですが、正直わたしは「木戻り」という当て字でもありそうな鳥の名前かと思っていました。実はそうじゃなくて、キモい鳥で「キモドリ」。
知らんし。

正体は、池に生息するアヒル(かな?)でした。顔が気持ち悪いって、さっきまで大はしゃぎだった子どもは、やけに怖気づいていました。あぁ池に叩き落とすんだった・・・
途中、子連れのアヒルがいて今度は正真正銘の子どもが親鳥の目の前で小さなアヒルを手づかみしたら、親鳥に襲われ、スッテンコロリン!びちょびちょになってしまいました。

と、まぁそんなほのぼのした雰囲気を楽しみながら、やっと首里城へ。
とにかく前に出たいB君は、あれやこれやと場を和ましてくれるのですが、みんなヘトヘト。
正殿入口で、またしても入らなかった(800円高い!)けど、なんだか偉そうに説明してる風な写真を撮ったり。
「西のアザナ」というその昔は警備が立っていた場所でまた休憩。ここも眺めがいい。地球が丸い!
「あれが沖大かな?」
ちょっと肉眼ではよく確認できませんでした。
しだいに人が増えてきたので退却。さっきから某メンバーが「識名園もこういう感じです」とかいいながら、城内の庭園を説明してるのを聞いて、大きな疑惑が。
こいつ、識名園行く気ないな
昔ここに琉球大学があったという記念碑を見て、観光客向けの休憩所で完全にまったりモードに入りました。

最後の坂道は、琉大の記念碑を発見して・・・疲れた。
はっきりいって、もう動きたくない。
あんまり話もすすまない。
帰るか
ということで、20分ほど休んだあと、タクシー乗って沖大直行。
でもせっかく集まったんだからということで近くのお店でゆんたく。こんどは旅の会で何しようか、そんな話で盛り上がりました。
そんなこんなで最終的な解散は3時くらい。
短い時間だったけど、けっこうハードでした。まぁでもそんなんもありかな、と思います。昨年の識名園―首里城コースとはまた違った面白さがありました。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 鮮やかな盛岡城跡公園の紅葉でした。
- (2025-11-18 18:18:06)
-
-
-

- やっぱりハワイが大好き!
- シャカサインで感じるハワイの風
- (2025-07-28 18:59:01)
-
-
-

- アメリカ ミシガン州の生活
- いよいよ日本へ本帰国
- (2025-01-11 13:13:28)
-
© Rakuten Group, Inc.