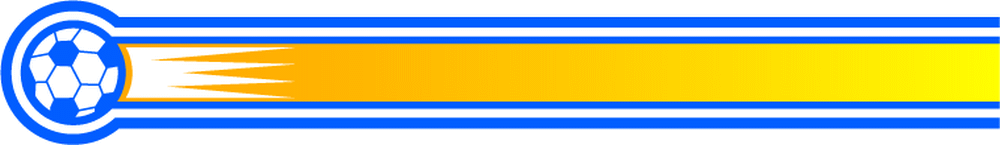2011・5那覇散策
そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)15月23日、旅の会のそば部のメンバーは
「そば食べに行こう」
「そうしよう」
ということで、新都心にあるC君オススメの「てぃーあんだー」に行きました。
11時集合。だと思ったのですが、諸説あって・・・。とにかく楽市の某所に集合して、歩いて「てぃーあんだー」に行きました。
雨がポツリポツリ。
「てぃーあんだー」って有名だから、すでに行ったことがあるメンバーも。

まずは外から撮ってやろうということでパシャ。
で歩いていくと、何だよ、撮ったのは手前の喫茶店かなんかで、「てぃーあんだー」じゃないじゃなんか。知ってたら言ってくれればいいのに(ボソボソ…)。なんか恥ずかしくなった。

こっちが「てぃーあんだー」の入り口。さすが人気店なので待ち。ま、昼時だったもんね~。でもわかれて座ってもいいならということで3分くらいで入店。

これは値段やや高め(軟骨ソーキそば730円)。

これはGさんが注文したセオリー通りの沖縄そば(550円)
ここでH先輩は「金ない」とかいって後輩のそばをそばからススス。
えーっ
・・・。
尊敬ポイントがマイナス2
食べてる時静かだったねぇ。それと味はね、そうだね、カツオの風味を生かしてて、とても食べやすかった。ソーキとかは別皿で丁寧な感じだった。ここならまた来てもいい気がしました。ただ、やや高め。月末はムリ・・・。
まぁ今後のことだけど、夏に○○やりたいなぁとか、旅の会的には何かでかいことやりたいっていう話で盛り上がりました。
食後、まだ待ちのお客さんがいる感じだったのでそそくさと店外へ。次なる場所を目指しました。
そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)2
喰ったなー。歩くかー。
シュガーローフ
新都心のDFSの向い側にある丘。
F先輩が「DFSは○○○・・・の略」っていうのが、けっこうウケただんけど、忘れた。
以下、案内板より。
慶良間チージ(シュガーローフ)
沖縄戦の激戦地。字安里の北に位置する丘陵地帯に築かれた日本軍の陣地の一つ。日本軍は“すりばち丘”、米軍は“シュガーローフ”と呼んだ。一帯の丘陵地は日本軍の首里防衛の西の要衝で、米第6海兵師団と激しい攻防戦が展開された。
とくにここ慶良間チージの攻防は、1945年5月12日から1週間に及び、1日のうち4度も頂上の争奪戦がくりかえされるという激戦の末、18日に至り米軍が制圧した。米軍の死傷者は2662人と1289人の極度の精神疲労者を出し、日本軍も学徒隊・住民を含め多数の死傷者を出した。
それ以降、米軍は首里への攻勢を強め、5月27日、首里の第32軍指令部は南部へ撤退した。沖縄戦は、首里攻防戦で事実上決着していたが、多くの住民をまきこんだ南部戦線の悲劇は6月末まで続いた。
(もう少し詳しい話については→http://plaza.rakuten.co.jp/tabinokai/2026
2008年沖大祭展示、「七、シュガーローフ~多くの兵士が斃れた~」を参考に)
案内文には英文もありました。K君に訳してもらおうと思いましたが・・・。まさか○○…ーション学科ではなかったはず・・・。

この日は慶良間諸島がくっきりとよく見えました。

丘の隣には、大きなビル(ホテル)が建設中。1棟はほとんど完成していて、その隣はまだ空き地でしたが、まもなく「何かしら」(実は旅の会のF君の口ぐせ!)建設される感じでした。その空き地に何が建つか?だけど、ビルだったら慶良間諸島は見えなくなってしまうなぁ。ビルから見えるからいいかぁ・・・。
展望台があって登ってみた。こんな落書きが…
祥○ 杏○ 176日目
名前は一応伏せますが、こういう記録って意味があるんですかね。「落書きするな!」の前にそこのところを聞いてみたい。
首里大名の方面を見ると、丘陵から2本の突起物がニョッキっと(写真無し)。
「見に行こうか・・・」
「今から?」
あまり考えもせず発言して、方々から攻撃を受けつつ、とにかくシュガーローフをあるいてみることにした。丘には「安里配水地」というちょっと奇妙な白い建物。これをぐるっと一周。

トイレの壁。芸術?それとも・・・
R君の弟がかつてこの丘で飲んだくれたとか。
そして次なる場所へ向かう。
そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)3
新都心から歩いて10分、車で2分。泊小学校。小学校を見学って?
実はここには泊小学校の旧校舎という穴場があります。

以下、案内板より。
旧校舎の時計台
昭和5年から昭和54年までの50年間、泊小学校の子どもたちを見守ってきた昔の校舎の正面玄関と時計台です。当時はめずらしい鉄筋コンクリート2階建てでした。戦後は米軍が使用していましたが、昭和34年から再び泊小学校校舎として使われていました。

メンバーがあれこれ見て回りましたが、確かに傷んでる。天井の壁がはがれおちてもおかしくない。
G君が「あっ、卒業記念」

ホントだ。「卒業記念 大時計 第13期生 昭和46年3月25日」と書いてあります。あれ、でも大時計はどこにあったんだろう? よく分かりません。
そしてこの旧校舎は戦場もみてきた。
(1945年)5月中旬、安里のシュガーローフでは激しい戦闘が続いた。西方約1キロメートルにある泊小学校周辺にも米軍の戦車が突入、日本軍を攻撃し民家を破壊した。一面焼け野原となる中で、かろうじて校舎は残り、戦後もしばらくは使用されていた。
(『沖縄の戦争遺跡』より)
旧校舎のそばには「泊村学校所址」という碑も建ってました。その裏面に泊小学校の沿革が出ていました。
享和3年 癸亥 教倫堂
明治14年6月 教倫小学校
明治21年1月 泊尋常小学校
明治21年11月 那覇尋常高等小学校泊分校
明治32年4月 泊尋常小学校
昭和16年4月 泊国民学校
昭和33年4月 泊小学校
ちなみに、
「デジタル大辞泉」によれば「尋常高等小学校」とは 「旧制の小学校で、尋常小学校の課程と高等小学校の課程とを併置した学校。」 のことです。
「yahoo知恵袋」によれば、 「明治19(1886)年の小学校令では、尋常小学校4年、高等小学校4年とされましたので、尋常小学校に6歳で入学して10歳で卒業、高等小学校に10歳で入学して14歳で卒業でした。」 だそうです。
せっかくだから、泊小学校の校歌を紹介しておきます。(1番のみ)
泊港を前にして
黄金の森をせなにおい
たてる我らの学舎は
千代に八千代にさかえなん
校歌は、その土地の紹介をしていることが多いから地域史を調べる際には参考になります。
そうそう、
山里長賢翁頌徳碑
というのもありました。石碑の表面の文字はほとんど読めませんでしたが、案内板によると、長賢さんは泊村出身で貧しかったけど一生懸命勉強して役人になって、そして稼いだ金で泊村で人材育成をはかった人。
自分の地元なら二宮金次郎か、と思いました。金次郎の像は全国にあると思うけど。あれ、沖縄にはないのかな?
小学生の時に、まさか、金次郎の像に悪戯なんかしてませんょ。まさかね。

そういう碑のそばには、枯れた花。現代の小学生は、花に水やるの怠って枯らしてるって…。まぁまぁ。
次へ行きましょう。
そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)4
前島へ。ここはもっと掘り下げたいですが、次に回します。

泊塩田之跡碑
三百有余年の沖縄製塩史日本復帰と共に終る
祖先の偉業を偲びこの碑を建立す
と書かれています。
「とまり会 会長真栄田義見」って、もしかして歴代の沖縄大学学長と同一人物?

焚字炉
以下炉の裏に書かれていた説明より。
1838年(天保9年)尚育王の時代に冊封使林鴻年の勧めにより焚字炉が設けられた。沖縄の旧俗では文字を書いた紙片を大切にする様に適当な場所に焚字炉を設けてて路傍の紙片はこれに入れて積もった時に焼いていた。第二次大戦前迄前島小公園には東西に通ずる大通りに面して一基置かれていた。
この地域は製塩人口が多かったが先人達が儒学にも深い関心をもっていた精神を汲み次代を担う青少年に誇りと励みを与える趣旨で再建するものである。
しばし公園で休んだ後、次に崇元寺へ。まずは写真。この2枚お気に入り


旧崇元寺第一門及び石牆(せきしょう)
崇元寺は臨済宗の寺で山号を霊徳山といった。王府時代の国廟で天孫氏をはじめとする歴代国王の神位が安置され、冊封使が来た時には新王冊封に先立って先王を祀る諭祭が行なわれた。かって崇元寺は国宝に指定されていたが、先の大戦で正廟をはじめとする木造建築物はすべて焼失した。
第一門及び石牆は、正面中央の切石積み三連の棋門(アーチ門)とその左右に延びる両掖門を備えた琉球石灰岩のあいかた積みの石壇であり、沖縄の石造拱門の代表的なものである。
石門の東に立つ石碑が下馬碑で、戦前は西にも同じものがあり、国の重要美術品に指定されていた。表はかな書き、裏は漢文で、この碑のところから下馬することを命じている。また、碑銘に「大明義靖六年丁亥七月二十五日」とあり、この年が1527年(尚清1年)にあたるので崇元寺の創建はこの頃ではないかと考えられている。

これが下馬碑。表面の文字が見えないからメンバーがぶつぶつ・・・
「5」では旅の会が歩いた「泊」について書きます。
そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)5
今回は「泊」に関して。前島の公園で2つ疑問が上がりました。
ひとつは「どうして前島なのに、泊塩田跡なの?」
どうして「前島塩田」じゃないか、という疑問です。
もうひとつは「なぜ海でもないのに、塩田があるの?」
確かに前島小は久茂地川のすぐそばで海からはけっこう離れてます。
これについては『泊誌』や『泊前島誌』などあたってみました。そこから分かってきたことを書いておきます。
まず前島という地域は太古の昔からあったわけではないということ。550年くらい前に島になるまでは海の底だったみたいです。つまり一帯は海だったわけです。
「地域情報誌「み~きゅるきゅる」のブログ」によれば、1451年に「長虹堤が築かれて以後、急速に堆積が進み、泊、兼久の砂洲とともに前島の地が形成された。」とのこと。
長虹堤とは首里王府が、那覇を港湾拠点にするため、当時「浮島」だった那覇と陸地を結んだ海中道路です。
当時の地図とかあれば、海と陸の境界線が分かると思うのですが、そういうのはまだお目にかかっていません。単に調べ不足だと思います。
前島に人が住み始めたのは1733年のことだそうです。まだわずか300年ほどしかたっていません。
そこで製塩業がはじまるようですが、あまり儲かる仕事ではなかったらしく、「泊マース」という蔑視的貧乏の代名詞もあったそうです(『泊前島誌』より)
ところでいったいなぜ泊塩田なのか?ですが、いまは泊といえば泊小学校の近辺の地域名ですが、昔はもっと広い範囲だった。天久、高橋、泊、前島、崇元寺、安里その辺りまで「泊誌」にふくまれています。
町名変更の流れを「み~きゅるきゅる」ブログから。
1921年、那覇区と泊村が合併。那覇市となった際に町名が祟元寺町、高橋町、前島町に変更になった。泊村の拝所が前島町の区域になったので、泊村の拝所を前島町が管理することになった。那覇市となった際に共有地が処分された。
1933年、兼久と前島二丁目をつなぐ新道ができる。今でいう海中道路。これによって現在の前島3丁目と前島1丁目2丁目が濡れずに行き来できるようになった。
1954年、泊の埋立工事が行われ、泊埋立居住区(現・前島)には、那覇軍港拡張整備のため土地が海没した垣花一帯の住民や牧志街道(現・国際通り)、美栄橋土地区画整理事業で立退きになった住民の受け入れ移転先となった。
・・・
泊は那覇が港湾拠点となる前はむしろこっちが拠点だったみたいです。陸続きだったからだと思います。いま訓練を移転するみたいな感じで話題になってる硫黄鳥島は文字通り硫黄がとれるのですが、それは泊の港から荷揚げされていたようです。
長虹堤ができて以降は、那覇に港湾拠点がうつっていきます。どうして那覇に拠点が移っていったのかはよく分かりません。
かの有名な黒船ペリーが上陸したのも泊。Bさんが言ってました、「泊高校の近くに碑が建ってる」
『泊誌』によれば、1853年5月26日、世界最大の蒸気船サンスクエハナ号を旗艦とし他3隻を率いて沖縄へ。泊から上陸。泊前道―崇元寺―坂下―観音堂の坂―首里城という道のりで移動し、6月6日首里城で王府側と会見しました。
いまでいえば崇元寺前の通りを通って、安里サンエーを素通りして、そのまま首里城公園へ向っていく、そういうコースだと思われます。
ペリー一行は何度か寄港してるみたいなのですが、1854年5月頃、ある事件が起きています。那覇の民家に水兵のボートら3人が押し入って、Mitu(ミツ)という女性をナイフで脅しレイプしようとしたのです。女性が声をあげて未遂に終わりましたが、逃亡したボードを人々が追跡し、ついに捕まえて殺し、三重城付近の海に捨てたそうです。
米側は水兵らの起こした件は遺憾だとしつつも犯人捜しを要求してきた。そこで王府は「田場武太」らを差し出したのですが、事の顛末はどうだったかな。…手元にメモになく良く分かりません。ただ田場はしっかりと任務をまっとうし、名前をあげたそうで、後々演劇にも登場するような英雄扱いも受けたとか。
メンバーの言ってた碑「ペリー提督上陸之地」は、1964年に米琉親善という意味を込めて建てられたそうですが、親善の裏側には程遠いおぞましい事件も起きていたわけです。
碑の建ってるあの墓地には水兵だった「ボード」の名が彫られた墓もあるらしいです。
・・・
やや話がそれましたが、はじめのふたつの疑問はほぼ解けたといっていいでしょう。
ちなみに「目からウロコの地名由来」ブログによれば、「泊」という地名は港を意味するアイヌ語に由来する説と、いやいや日本語にも「トマリ」=港という意味があった、と二つ説があるみたいです。
沖縄にも伊平屋島の前泊、久米島の真泊・泊・仲泊、今帰仁村今泊、恩納村仲泊、那覇市泊といろんな「泊」があって、それは海上交通と結びついた地名だそうです。
次が最終回。安里八幡宮までもう一歩。
そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)6
崇元寺に車を置いてすたすた歩く。

「金満宮」という看板があって、これは寄り道コースだと思いふらふらと入る。

金満宮。質素だけど、うーんどんな由来があるのかは不明。

これは古い石碑。前は入口にあったやつだけど崩れてきてしまったので、ここに移動したようです。
なんかおじさんたちが掃除してました。
「何かあるんですか?」
「明日まつりがあるよ」
「そうなんですかー。忙しいところすいません」
「何か調べてるの?」
「サークルです。大学の」
「どこの?」
「沖縄大学です」
「あぁ俺より少し頭悪いな」
・・・だいたいこんなやりとりでした。
おじさんの言うことには、金満宮は宝くじの神様だそうです。「当たった人いるんですか?」と聞いたら、笑ってごまかされました。そんな欲がみなぎった神様なんているのかな~。
実はこの日のことは「安里旗頭青年団のブログ」に載ってました。検索してみてください
→ http://eiseien.ti-da.net/e3364019.html
「若者よ!地域貢献を!」って。たしかに「若者」はいなかった・・・。
次にすたすた歩いていくと、鳥居が見えてきました。「安里八幡宮だっ」と言ったら、途中で左手に「寺がある!」。じゃそっち行こうということですたすた。

何で真言宗なんだろう? 崇元寺は臨済宗だったはずだけど・・・。なんとなく権力者というのは自分に都合のいい宗派にはいい顔して、そうでない宗派は弾圧しそうなものですが。謎です。だれか教えて。

安里八幡宮。F先輩は授業で来たことがあるそうです。隣に保育園がありますが、そこの坊やに「おじちゃん」と言われたそうです。
一同納得。坊やが正しい。
安里八幡宮の由来。『泊誌』によると、尚徳王(1461~69)が鬼界島の反乱を討伐させたが失敗。次は自ら遠征した。出発のとき大道原で休憩中、白鳥がとぶのを見て「南無八幡大菩薩、我は今聖戦に向かう。戦いに利あらば、あの白鳥を射落とさせ給え」。みごと射落とし、戦争にも勝った。その地点(たぶん白鳥が落ちた点)に武神としての鎌倉八幡宮を分神してお宮を建てた。
※「鬼界島」は現在の奄美諸島の「喜界島」のこと。ちなみに中世の流刑地であった「鬼界ヶ島」は現在の喜界島と硫黄島という二つの説があるそうです。この硫黄島は第二次大戦で戦場になった硫黄島(現・東京都)ではなく薩摩硫黄島のほうです。
※「鎌倉八幡宮」とは神奈川県の「鶴岡八幡宮」のこと。詳しくは旅の会のW先輩に聞いてください。

裏手にまわると、おぉー、廃墟。けっこうしっかりした廃墟です。Sさんは霊感スポットなど詳しいのですが、ここについてはあまり聴けませんでした。霊はいないってことで。目の前が神社じゃ霊も出にくいってか。

神社側から撮ってみました。
こうしてすべての道のり終了。「てぃーあんだー」→シュガーローフ→泊小学校旧校舎→泊前島塩田跡→崇元寺→金満宮→安里八幡宮
なかなかな旅でした。「またそば食べに行こう」ということで確認しあい解散しました。報告以上です。
以下、追跡調査です。
続・そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)5 2011/07/08
ここは補足説明です。参考までに。
そば食べて、まわりをぐるっと…の「その5」6月3日付で、次にように書かれていました。
長虹堤ができて以降は、(泊から)那覇に港湾拠点がうつっていきます。どうして那覇に拠点が移っていったのかはよく分かりません。
これについて少し分かったことがありましたので書いておきます。
長虹堤で那覇と首里が陸路で直結したのが1451年とのことですが、その当時の那覇の様子がかかれている本に出会いました。「琉日戦争一六〇九」(上里隆史著、ボーダーインク)です。以下引用です。
珊瑚礁が発達した南西諸島で大型船が停泊可能で、渡航者の長期滞在が可能な居住スペースのある場所は、実はさほど多くない。沖縄島南部の那覇は国場川から流れる淡水により珊瑚礁が発達せず、下流域には外界の波の影響を受けない内海(漫湖)が広がる。さらに「浮島」と呼ばれた平坦な島が存在し、港湾として絶好の条件を有している。このため華人(中国人)をはじめとした外来の民間勢力によって那覇に港湾と居留地が自然発生的に形成されたとみられる。
那覇の浮島には華人や日本人の居留地、さらに彼等によってもたらされた禅宗寺院や神社、天妃など琉球にとって「異国」の宗教施設が林立し、南西諸島の他の地域とまったく異なる都市空間であった。那覇には海商だけでなく、各地の港湾を拠点に布教を行う禅宗ネットワークなどの民間の宗教者、文化人、技術者、女性、倭寇に拉致されてきた被虜人などあらゆる人々が集う場所であった。
こうして一四世紀中頃までに海域ネットワークの拠点としての港湾都市・那覇が形成されたことで、各地の大型グスクに割拠する按司とそれを支える伝統的社会の内部に「異国」的空間が突如出現したのであり、そこに登場した新たな外来のプレーヤーが琉球社会の動向に影響を及ぼしていくことになる。
引用ここまで。
つまり、自然条件があって港湾として開けた。首里王府が那覇に目をつけて港湾拠点として整備したというよりは、それよりも前に泊港と比べてもアジアに開けたネットワークという特異な空間が広がっていて、そこを長虹堤でつないで王国の繁栄に寄与していった、ということになりそうです。
・・・ちなみにこの本は、「アジアの中の沖縄」みたいな視点で描かれていて、いろんな事件や歴史が流れに沿って分かりやすくまとめられていておもしろかったです。
実は、薩摩より琉球のほうが政治的に上らしい時代があったとか、せっかく島津は戦争で力をつけて琉球を属国扱いする勢力を手にしたのに、秀吉にその上から押さえつけられたとか。
一番著者ががんばってるのは、琉球の軍事力。意外と準備万端だったけど、実戦で鍛えられた島津軍にはかなわなかった。その島津軍もそれほど統率のとれた軍隊ではなく、族の集まりみたいな感じだったこと。
などなど。
「琉球八社」の疑問を解く 2011/07/23
5月23日の那覇散策(詳しくは5月25日~の日記「そば食べて、まわりをぐるっと…(那覇)」を参照)で次のような疑問がありました。
それは崇元寺は臨済宗なのに、安里八幡宮の近くにあった神徳寺は真言宗なのはなぜか?ということでした。なんとなく権力者というのは自分に都合のいい宗派にはいい顔して、そうでない宗派は弾圧しそうなものですが。
それについて「琉球八社」のことも含めて書かれてる著書がありました。「琉球宗教史の研究」(鳥越憲三郎著)。これから少し紹介します。
第5編より。
そもそも琉球古来の御嶽は 「我国神社の原初的形態を伝承するもの」 だそうですですが、ここでは中世以降に 「我国の神社から勧請されたところのもの」 を扱っています。
※「勧請」とは「神仏の分身・分霊を他の地に移して祭ること」(ネット辞書より)。
琉球八社は寺=神社で、宗派は真言宗という特徴があります。安里八幡宮のみ祭神を応神天皇・玉依姫・神功皇后とし、他の7つは熊野権現が祀られています。
識名宮、天久宮、金武宮、普天満宮は鍾乳洞を御神体としています。
琉球王国の時代、8つのうち金武宮のみは神職をもたず、他の7社の神職は王府から役奉をうけていたそうです。金武宮のみなかったのは分かりません。しかし7社以外にも神職をもち役奉をうけていた寺社はあるらしいので、7社が特別な存在だったわけではないそうです。
ではなぜ「琉球八社」と呼ばれるようになったかというと、真言宗の者によって宣伝されたんじゃないか、と書かれていました。意外と根拠薄弱な気もしないわけではないですが。
「これらの社寺は何れも民衆の信仰に応えるとか、或は民衆の済度のために創建されたものではなく、ひとえに国王或は国家の安泰のために、換言すれば主権の擁護のために創建されたものである。」 この主張は何度も出てくる著者の主眼です。
では明治期の「琉球処分」をへて「琉球八社」はどのように扱われるようになったか?
まず波上宮が首座を占めます。これは隣接する護国寺が真言宗派の各寺の本寺だったことによります。1891年に波の上宮が官幣小社に列格され、他の7社も無格社の資格で正式に神社とされました。
官幣小社になると日本政府から経済的支援を受けられるようになります。はれて8社は「神社」となったわけですが、琉球のもとでのさまざまな制度の違いがあって簡単ではありませんでした。たとえば、神職制度の違い、琉球では氏子組織がない、祭式方法が異なる、などなど。
だから正式な神社とされたのは 「政治的行為」 だったと。民衆に根づいた御嶽信仰を排除して、上から「神社」を押しつけて、宗教的に同化して沖縄の人びとを支配の下においていった・・・
となるわけですが、ところが著者の結論は違う。実はそもそも神社ではない「琉球八社」を「政治的行為」として「神社」に仕立て上げたのですが、民衆の信仰は集まらなかった。
昭和10年代に各社の状態が書かれています。安里八幡宮は本殿が腐朽倒壊、拝殿は倒壊消滅。天久宮は拝殿無し。本殿も倒壊。識名宮も本殿が腐朽破損。末吉宮は国宝建築物に指定されていたが拝殿無し。本殿は腐朽破損。波上宮は経済支援をうけて何とか保っていたけど、その他はボロボロの状態だったのです。
「各社が民衆の信仰的支持が薄いにもかかわらず。我国の神祇と同系のものであるというただそれだけの理由をもって、これを取り上げたのであるが、結局この政策は失敗に終わった観がある。」
「琉球処分」以降の日本の対沖縄宗教政策は失敗だった。それが著者の結論です。
ところで臨済宗と真言宗の疑問がまだ解けていません。
それについては「沖縄の神社」(加治順人著、ひるぎ社)もあたってみました。こっちのほうが読む分には読みやすいです。薄いし。
真言宗は、14世紀後半に頼重上人が伝来したそうです。臨済宗の伝来は遅れたようです。しかしはじめの間、国王や王府の信頼が厚かったのは臨済宗だったようです。王府が行なう祈願は聞得大君以下の神女らと臨済宗系寺院らの僧侶が担当していたようです。
だから崇元寺は臨済宗だったわけね・・・と納得したのですが、早とちり。
薩摩藩の琉球侵略以降、状況が一変します。
農作物の豊饒祈願は聞得大君‐神女組織、王家の無病息災や国家安泰の祈願は真言宗系寺院、王家の葬儀や位牌の管理など先祖供養は臨済宗系寺院と任務分担されたそうです。
これによってどうやら臨済宗系の崇元寺の任務が確定したということになりそうです。
ちなみに著者の加治氏は「八社は民衆の信仰対象ではなかった」とする鳥越理論に反論し、 「信仰事態はあったのだが、観衆の相違や社会情勢などの要因により、沖縄の神社は荒廃していったものと考察される。」 としています。
この辺りは専門的にはたぶんいろいろ反論なり実証的な研究があるのだろうと思うのですが、はっきりいって分かりません。これ以上考えると泥沼にはまります。なのでやめます。
全体を通してイメージできるのは次のような様子です。
真言宗と比べて遅れて伝来した臨済宗だったが、古琉球の時代は国王や王府と手を結ぶことに成功し、各種宗教行事をまかされていた。一方の真言宗は宣伝で対抗して「琉球八社」を認知させることに成功。
しかし薩摩藩の琉球侵略以降、薩摩藩の宗教政策によって従来の聞得大君‐神女、真言宗、臨済宗は異なる役割りを与えられ共存した。
「琉球処分」で、日本の宗教政策に一本化されたが、制度的な違いや祭式の違いがあり根づかなかった。
この過程全体で御嶽信仰は民衆のあいだに息づいていた。
だいたいこんな感じだと思います。薩摩藩が真言宗を取り立てた理由は?ですが、たぶん当時は宗教は社会的力をもっていたので、それを琉球の支配や藩勢拡大に利用したんじゃないかと、かってに考えています。根拠はないけれど。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 旅の写真
- 中国、北京に行って来た!【6】
- (2025-10-27 23:49:58)
-
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- 【静岡*伊東】伊東温泉 青山やまと
- (2025-11-18 13:49:34)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 令和7年 鳳サマーカーニバル 野田・…
- (2025-11-18 06:58:01)
-
© Rakuten Group, Inc.