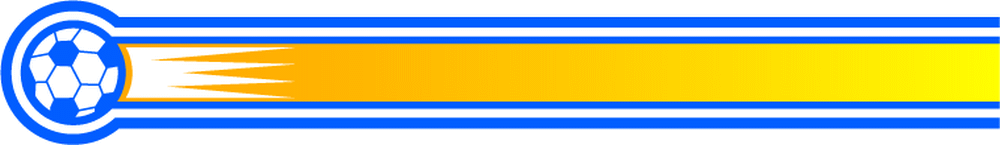「沖縄は基地を拒絶する」、読む
「沖縄は基地を拒絶する」(その1)
最終更新日 2005年12月29日
「これは高文研という出版社から「緊急出版」された本です。考えさせられた本なので、紹介していきたいと思います。
この本は、33人がそれぞれの立場から、10月29日の日米合意(「日米同盟:未来のための変革と再編」)に対する考えを書いたものです。
書く人の立場はさまざまで、政治家もいれば、大学の先生もいるし、市民運動家もいます。冷静に分析する人もいれば、感情をあらわにして怒りを表現する人もいます。体験を切々と書く人もいれば、いくぶん文学的表現を使って書く人もいます。
共通していると思われるのは、日米合意に対する拒否の姿勢です。
わたしは個人的には、今回の日米合意に対して思うところがあったし興味もあるので、「第一刷発行12月25日」よりも前に本屋で買ってしまいました。
金もないのに・・・
「市民投票もやった。選挙もやった。でも何をやっても無駄。今後はどんな選挙も行かないし、署名もしない。もう一度戦争を見る前に死にたい」
これは浦島悦子さんが地域住民(名護)をまわって基地建設に反対するために署名集めをしていた時に、ある年配の女性から言われた言葉です。ちなみに浦島さんは十数年前から沖縄に住んでいる「在沖ヤマトンチュ」です。
買ってすぐに近くの公園で読みすすめていた時に、この部分だけは正直キツカッたところです。この言葉を吐露させたのは一体なんだろうと。その答えがわたしなりに思うところがあっただけに余計にキツカッたのです。
ちなみに「市民投票」とは、1997年12月に名護市で基地建設の是非をめぐって行なわれた住民投票のことです。結果は反対が過半数に達しました。この結果をうけて当時の市長は、わずか3日後に「基地受け入れ」し、辞任を表明しました。「市民投票」は、反対の地元住民からすれば、歓喜と絶望をいっぺんに味わったようなものだったのではないでしょうか。
33人が怒りや悔しさやあきれなどを表現していますが、何度か読み返すうちに特徴的と感じたことがありました。
その一つ目は、今回の日米合意を過去の歴史と重ねて書く方がとても多かったということです。
まず沖縄戦を体験した方々は、自分の体験を決められた分量の中に思いをこめて書かれています。それは今回の日米合意も含めて、沖縄の基地の存在の行き着く先を考えてのことでしょう。
「基地は諸悪の根源です」
(中村文子さん)「沖縄の現状を見ると焦りを感じます。それは沖縄に存在する米軍基地です。」
(安里要江さん)「60年前、軍隊と基地が招いた多くの悲劇が忘れられているのではと、不安と恐怖が増幅する今日この頃です。」
(宮城喜久子さん)などです。
その上で特徴的と強く感じたのは、米軍占領下の時代を書いている方が非常に多かったということです。
「中間報告がもたらした衝撃は、新規接収や土地一括支払い反対など『土地を守る四原則』を否定した1956年の『プライス勧告』が出された時の状況と酷似しているといえよう。」
(比屋根照夫さん)「米軍再編中間報告が発表されたとき、頭をよぎったのは半世紀前の1955年、アイゼンハワー米国大統領の年頭教書演説の『沖縄の無期限保有』という文字だった。」
(石原正家さん)などなど。
その他に
「『またか』という感じで、怒りはあっても驚きはない。そういう事例は数多くあるが、記憶に残るものといえば、1995年9月に起きた〈米兵による少女暴行事件〉と、その後の沖縄県民の〈反基地闘争〉に対する政府の対応である。当時沖縄県知事であった大田知事の、『米軍用地特措法』に基づく『公告・縦覧』の代理署名拒否に対して総理大臣が告訴(代理署名拒否裁判)したこと、1997年のいわゆる『象のオリ』の米軍の不法占拠事件に際して、それを容認するために『米軍用地特別措置法』の改定を、法の原則を無視してまで強行したことなどはその最たるものであろう。」
(岡本恵徳さん)というように、ここ10年ほどの流れを書く方も少なくありませんでした。
沖縄の歴史に関しては、「沖縄現代史」編、「沖縄戦後史」編で書くので省略させてください。
なぜ多くの方々が歴史を持ち出すのか考えましたが、
「今が変わらないから歴史をもちだすのである」
(大城立裕さん)というように「何も変わっていないじゃないか!」という怒りの表現なのだろうと思います。わたしは占領下の歴史が克明に書かれたことの重みを考えないわけにはいきません。
今回はここまでです。
「沖縄は基地を拒絶する」(その2)
最終更新日 2005年12月29日
特徴点の二つ目は、日本人に対して訴える、あるいは突きつけるといった文章が多かったということです。
「ヤマトの土地で、それぞれができることをしてください。沖縄に闘いに来なくていいので、何も変わらないヤマトの土地で、あなたが住んでいる土地で、日本人を変えることを考えてください。」
(石川真生さん)「日本人には私たちの叫びが聞こえないのか。もっと大きな声を出せと言っているのか。気づいている人たちはいる。あなたたちの行動が試されている。」
(国政美恵さん)「・・・今はあからさまに“県外移設”が要求されています。温度差があるのではなく、温度そのものを持たないヤマトへの荒療治とも言えるでしょう。基地を押し付けられ、抱え込まされ、基地被害の生活を強要されることがなければ、ヤマトの平和ぼけはいつまでも目を覚ますことがないでしょう。他者(沖縄)の痛みを感じることも無い非人間的生活、日米軍事体制を自然のことと錯覚する軍事力信者に退廃し切ってしまうことでしょう。」
(平良修さん)などなどです。
微妙にニュアンスの違いは感じますが、やはり「荒療治」と言われなければならないほどに、ヤマトの側が鈍感であるということに尽きるということでしょうか。わたし自身もこれらの言葉に耳を傾けて、答えをみつけていきたいと思いました。
沖縄大学に関係ある方も文章を寄せてます!せっかくだから紹介しま~す。
まず前学長の新崎盛暉先生。題名は「アメリカには笑いが止まらぬ『シュワブ沿岸案』」です。
先生は、「日米同盟:未来のための変革と再編」という今回の日米合意をまとめるまでの、
「約3年間に及ぶ日米協議は、基地所在地域の過重負担と抑止力のバランスを考慮した在日米軍の再編成や在日米軍基地の再配置が主要なテーマだったわけではない。」
と言います。じゃ、何が「主要なテーマ」だったの?
「中心的なテーマは、日米同盟の再編強化、具体的には、在日米軍と自衛隊の役割や任務分担、情報共有や相互運用能力の統合強化にほかならない。東京・府中の航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊の横田移転と在日米軍司令部による共同統合運用調整所の設置、機動運用部隊や専門部隊を一元的に運用する陸上自衛隊中央即応集団司令部のキャンプ座間設置と在日米陸軍司令部の改編強化などがそれである。」
うーん、漢字の羅列がイヤになる。これは先生の責任ではありませんが。他の方も「米軍と自衛隊の一体化」といった内容を書いていましたので、そのことでしょう。
「沖縄の負担軽減」
ということがたびたび報道されてきましたが、これは「重要な政治的争点」となることを避けるために利用された、というのが先生の指摘です。けっきょく、沖縄の負担は軽くなんてならない、ということかもしれません。
この間の日本政府やアメリカ政府がどう考えて行動してきたかについては、先生の文章がもっとも詳しいです。
ちなみに新崎先生は「沖縄現代史〔新版〕」(岩波新書)も出しています。(めちゃめちゃ仕事してるじゃないですか!)近いうちに読んでみたいと思います。
今日はここまでです。次がラストです。
「沖縄は基地を拒絶する」(その3)
最終更新日 2005年12月30日
次に、屋嘉比収先生。現在、法経学部で教えています。題名は「大の虫を生かすために小の虫を殺す・・・」です。
まず、
「日本政府は沖縄側の反対を予想して、県民の声を封じ込めるために、県知事が保有している辺野古沿岸の公有水面の使用権限を、国に移管する特別措置法案の提出を検討している」ことについて、「憲法で保障された地方自治の本旨を否定するものであり、日本の民主主義の根幹を揺るがすものである。」
と批判します。
そして
「だが、考えてみれば、むしろ戦後憲法の成り立ちそのものの中に、沖縄の切り捨てが構造的に組み込まれていたと理解したほうがわかりやすい。そのことは、沖縄の中で広く共有されている、沖縄に米軍基地を押し付けることによって日本本土の平和憲法が成立しているとの認識につながっている。」
この指摘は「沖縄の中で広く共有されている」としても、ヤマトではほとんどといってもいいくらい、問題にされてないと思います。「平和憲法」があること、あるいは守ることが、ストレートに「平和」がある、あるいは「平和」を守ることだと考えていると思います。わたしも以前はばく然とそう考えていました。
そして先生は、
「最近、沖縄から日本をみて思うことは、日本政府だけでなく、自らの安寧を謳歌して犠牲を強いている沖縄の状況を見ようとしない多くの日本国民の怖さである。」
と言います。わたし自身ヤマトンチュでありながら、沖縄に住んでいるとあまりの感覚の違いに冷や汗をかくことがあったり、口ごもらざるを得ないときがあります。
さらに主語が「私たち」として書かれている部分にも注目しました。
「私たちに問われているのは、基地建設に反対だが、当事者である辺野古の人たちの中により経済的恩恵を受ける人々がいるから、簡単に結論を下せないと立ちすくみ自分の考えを保留することではない。あなたは誰の声を聞いて行動するのかという、私たち一人ひとりの選択が厳しく問われているのだ。私は、その米軍基地建設により、平和的生存権を侵され根源的なダメージを受ける人々が発する声を何よりも優先して聞き止めたいと思う。」
わたしも「保留」の声を多々聞いてきたし、「それは違う」と思いつつそれに対しうまく反論できないことも多々ありました。で結局、「保留」に押し止められてしまう。「誰の声を聞き止めるのか」というのは考えさせられました。
最後の「挫折の歴史に学ぼう」という訴えは大切だと思います。個人だって失敗から学ばないと、同じ誤ちをくり返しますから。やはり歴史は大切なんだとあらためて感じました。
最後に、真喜志好一(よしかず)さん。実は、沖大(1・2・3号館)を建築した方だそうです。
まず他にも何人かの方が指摘していましたが、今回の日米合意は「中間報告」と報道されたにもかかわらず、外務省ホームページにある「日米同盟:未来のための変革と再編」のなかのどこにも「中間報告」とは書かれていないそうです。
「日本政府の作為を感じる」
と真喜志さんは書いていますが、確かに。「中間」ということは「最終」があるはず。それは2006年3月に発表するということなのですが、いかにも「中間」と「最終」の間に、地元の意見を聞いたうえで内容が変更可能であるかのような印象を与えます。
今現在、沖縄をはじめ米軍が移転するどこの地域でも反対の声が上がっています。「中間」というのなら内容は変更されるのでしょうか・・・?
真喜志さんは、「2005年10月29日に「2プラス2」で合意した計画図」と「1997年9月29日付の米国防総省『運用構想』より」と「1966年12月の海軍マスタープラン」という3つの図面を出しています。
1966年→1997年→2005年という一本のつながりを理解することで、今回の「沿岸案」の狙いがハッキリ見えてくるということなのだと思います。詳しくは省きます。
真喜志さんは、
「米軍が欲しているのは滑走路だけでなく、装弾場、軍港の三点セットである。」
とズバリ書いています。そして
「今回の合意文書で『燃料補給用の桟橋及び関連施設』とあるのはまさしく軍港であり、水深20メートルを超える大浦湾には原子力空母も接岸できる深さがある。」
だそうです。もう一つ。「沿岸案」が遺跡にかかる、という報道を読みましたが、実は1997年の段階で、アメリカ政府は「開発の妨げ」の理由の一つとして、「文化遺跡」をあげているというのです。
10年足らずの間に「文化遺跡」の存在を忘れてしまったのでしょうか、それとも「無きものにしましょう」と日米政府の間で意見が一致したということなのか、果たして・・・
真喜志さんは、今回の「沿岸案」は報道されたような妥協案とか折衷案ではなく、「苦心の『合作』」だとハッキリと書いています。「合作」とはその通りだと思います。
真喜志さんの文章は、謎解きのようで面白く、もっと「沿岸案」について知りたい、と思わせる文章でした。
最後に。
率直にいい本だと思いました。10月29日の日米合意は、どのくらいの知名度があるのか分かりませんが、必ず2006年の政治の焦点の一つになるだろうとわたしは思います。ぜひ読んでほしいと感じた一冊でした。
© Rakuten Group, Inc.