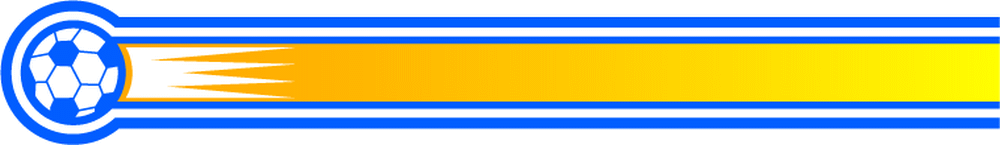沖縄戦後史~返還まで
2006.03.02
「沖縄戦後史」(その1)
本書は、岩波新書で新崎盛暉先生の著作です。1945年の沖縄戦から1972年沖縄返還までを扱っています。
本書を引用しつつ、沖縄の戦後史を見てみたいと思います。
返還前の沖縄社会は、
一、アメリカの世界政策との関連
二、日本の対沖縄政策との関連
三、一・二に対する沖縄人民の対応
の3点で整理していくとつかみやすいのではないかと思います。
なお、本書の「はじめに」で、「沖縄戦後史を規定してきた直接的要因」として4つあげられています。第四の要因として「本土国民の沖縄問題をめぐる動向」というのがありますが、これは自分が「本土」出身だと客観的に書くわけにもいかないので、各所との関連で触れる程度にします。
なお、「はじめに」の時期区分が示されていますが、戦後史を整理するうえでとても参考になります。
一、アメリカの世界政策との関連
沖縄戦が開始され、米軍の沖縄島上陸直後、「ニミッツ布告」が出されて、沖縄は事実上、軍政下に入ります。
しかし沖縄戦が終結して以降も、当初は沖縄の扱いについて、米中枢でも意見が一致していなかったようです(国務省と軍部の対立)。そのため現地での対応(さまざまな住民対策など)も場当たり的でした。この頃には米兵による暴行事件なども相次いでいました。
しかし中国革命が進展していくと、しだいに沖縄政策も定まってきます。なお革命の勝利によって現在の中華人民共和国が成立したのは、1949年のことです。
戦後の世界体制がどうだったかというと、資本主義体制が共産主義諸国を「反共」という立場からいかに封じ込めるのか、そのためにどういった戦略を確立するか、というのが最重要でしかも急務な課題でした。
ようするにソ連や中国などにアメリカを中心とした資本主義体制が、どう対処するのかということです。
そうしたなかで沖縄は、極東の重要な拠点として位置付けられていきます。
沖縄現地でも場当たり的対応から戦後沖縄復興計画と「民主化」政策の実施へと変わっていきます。
復興計画としては、基地建設とガリオア援助というのが指摘されています。
当時、シーツ長官は「基地建設工事は沖縄経済の自立復興計画にきわめて大きな意義がある」と言っているようですが、もうひとつ重要な指摘がされています。それは鹿島建設、清水建設、間(はざま)組、大成建設、竹中工務店など本土大手土建業の沖縄進出による日本経済の復興です。
戦後の日本経済の復興は、よく朝鮮戦争の際の朝鮮特需といわれていますが、「そのなかには、沖縄米軍の需要が少なからぬ割合を占めていた。」そうです。
もう一つ、ガリオア援助ですが、これを資金に、運輸・食糧・石油販売などの民間企業が創設されたそうです。
「沖縄経済自立政策の本質は・・基地収入をあたえて住民を基地にしばりつけることであった。」
このへんに「基地は経済発展に役立ってきたし、いまも役立っている」という主張の根拠があるのかもしれません。
一方この時期の「民主化」政策について、本書で「暗黒の時代」と書かれています。そのことからもある程度察しがつくと思います。沖縄人民のさまざまな闘いについて、「反共」の立場から弾圧が強化されました。詳しくはここでは省略します。
1952年4月28日、対日平和条約(サンフランシスコ条約のこと)が日米安保条約とともに発効します。
アメリカは、対日講和会議前から、「太平洋反共同盟に日本を結びつけることによって、太平洋諸国の日本の再侵略に対する懸念を解消するダレス構想にもとづ」く諸政策を決定し、米比条約・アンザス条約(米・オーストラリア・ニュージーランド)、米韓条約を次々と締結していきます。日本とは日米安保条約を結んで独立させ、再軍備をすすめます。
この根っこには、「軍事的に強固な中ソ包囲網をつくりあげよう」という戦略があるわけです。
この対日平和条約で、沖縄と奄美ははっきりと日本から分離されました。
けっきょく平和条約は、「平和」とはあっても、沖縄を占領下におくことを、国際的に認めるというものです。沖縄にとっては、とても「平和」とはいえない気がします。
しばらくして奄美は「日本政府が沖縄の『防衛を保全し、強化し、容易にするためにアメリカ合衆国が必要と認める要求を考慮』に入れる(奄美返還協定付属の交換公文)という条件つき返還」されました(1953年12月25日)。
戦略的価値の低い奄美返還と引き換えに沖縄の米軍支配を確立したということでしょう。
実際、「共産主義の脅威があるかぎり、アメリカは沖縄を保有する」(53年11月、ニクソン副大統領)、「沖縄のわれわれの基地を無期限に保有するつもりでいる」(54年、アイゼンハワー大統領一般教書演説)と露骨に沖縄占領が宣言されていきます。
沖縄では軍事優先政策が強化されていきます。「すでに米軍は、沖縄占領と同時に、住民を収容所に入れている段階で、白地図に線を引くようにして広大な軍用地を接収し、これを無償で使用してい」ました。
それでは条約後、アメリカがどのように軍用地を確保したのでしょうか。
一つに、「契約権」(1952年11月)という布令を公布して契約をすすめました。
これは「行政主席が土地所有者と賃貸契約を結び、つぎに米軍と契約するという形式」でしたが、契約期間は20年と長く、使用料が低かったので、契約率はわずか2%でした。最終的には、「契約が成立してもしなくても米軍側は『土地使用』の事実によって賃借権をえたものとみなして借地料を支払うと、一方的に宣言した」のです。
二つに、「土地収用令」(1953年4月)という布令を布告して暴力的に新規接収をすすめました。
それは「武装米兵を動員し、農民の頑強な抵抗を排除して」行われました。伊江島真謝地区の土地接収については、旅の会で昨年行った「反戦資料館ヌチドゥタカラの家」でもその酷さの一端を見ることができました。
こうして現在まで続く、基地の島=沖縄がつくられました。
以上のような過酷な占領支配に対して、「島ぐるみ」の闘いがまき起こります。それがどう発展し、どう変質し、収束していったかは「三」で書きます。
日米政府の日米安保条約の改定交渉は、「島ぐるみ」の闘いが収束がハッキリした頃はじまりました。
安保改定はアメリカ政府からすれば「日本、韓国、台湾などの地上兵力を強化して、これを極東防衛の前面に立て、その背後にアメリカ海空軍を配置するという当時のアメリカ極東戦略」にそったものでした。日本に置かれた極東軍司令部は廃止され、極東全域の米軍はハワイに司令部を置く太平洋統合軍のもとに置かれました。
このころ沖縄に関連することで言えば、大きくは二点あります。
一つは、日本本土からの「いっさいの米陸上戦闘部隊の撤退」です。一部は沖縄へ移動しました。たとえば、第三海兵師団という部隊は沖縄に集中されました。
もう一つは、共同防衛地域に沖縄を含めるか否か、つまり沖縄が攻撃されたときに米軍と自衛隊(すでに1954年に設置されてました)が沖縄を「防衛」するか否か、という問題。安保改定の大きな焦点となった問題ですがこれについて詳しくは「三」で書きます。
結局、安保改定は、「沖縄におけるアメリカの排他的軍事支配を承認したうえでの日米協力体制が一歩前進した」といえそうです。
佐藤内閣が成立するのは、1965年です。この頃は、日本政府が沖縄返還を要求してもアメリカ政府は「返還しない」とバッサリ切っていました。沖縄返還が日米政府の間で、具体化し始めたのは、1966年後半から1967年頃にかけてのようです。
どうして両政府の政策が転換したのでしょうか?
「日米両政府の政策転換を生みだした直接的契機は、教行二法阻止闘争にいたる闘いの結果生じた沖縄支配の破綻にあったが、これとわかちがたく結びついていたのは、アメリカのベトナム政策の破綻であった。」(教行二法阻止闘争についてはここでは省略します)
アメリカは1965年からベトナム戦争に全面介入しますが、戦場は泥沼化し、国内のベトナム反戦運動が激化してベトナム政策が揺らぎ、しかも反戦運動は世界的に広がりました。しかも軍事的政治的破綻が経済面にも波及。ようするにこの頃、戦後の世界体制が危機に陥って、にっちもさっちもいかない状況だったのです。
アメリカは破綻した極東政策を再編成のために、アジア最大の同盟国=日本の協力を必要とします。
しかし同盟国の領土と住民を軍隊が支配している。この状態はまずいのではないか・・・民衆は沖縄返還を要求している。ならばこの返還運動と極東政策の再編成をなんとか両立できないだろうか・・・。
こうして「沖縄返還は、アメリカ極東政策再編成のための日米協力関係(日米安保体制)強化の中心環として位置づけられることになった。」
1969年11月の佐藤・ニクソン共同声明が発表されます。ここで初めて「72年返還」が正式に発表されますが、そのなかには、
・アジアの平和と繁栄のための緊密な日米協力
・その平和と繁栄は極東の米軍の存在から
・韓国の安全、台湾の安全は、日本の安全
・日本のベトナム戦争への積極的加担
が明確に記されています。「72年返還」は、これらを前提にしていたということです。
民衆の要求をのむ形で沖縄返還を実現し、一方で返還を安保体制強化と結びつける。もちろん、日本政府は沖縄返還=安保体制の強化などとは説明しませんよ。これが政治のカラクリです。
こうして1972年5月15日、沖縄は日本に返還されました。基地はほとんど減ることなく、米軍が基地を自由に使用できる状態は、占領下とまったく変わらぬままでした。
佐藤栄作首相は、あれこれの業績を称えられ、ノーベル平和賞を受賞しました。ベトナム戦争を支持したり、沖縄の基地を維持したり、いったいどのような「平和」に貢献したといえるのでしょうか?
以上です。
2006.03.04
「沖縄戦後史」(その2)
二、日本の対沖縄政策との関連
沖縄戦が何のために行なわれたのか? それは、天皇制を守るために、あるいは本土攻撃までの時間かせぎのために、「捨て石」として行われた、といわれています。
また、沖縄戦で起きたさまざまな悲劇について、以前旅の会の活動でチビチリガマ(読谷村)などを知花昌一さんに案内してもらったときに、「軍国主義と皇民化教育こそが元凶だ」と説明していただきましたが、本当にその通りだと思います。
敗戦で日本は非武装化され、1947年に日本国憲法が制定されます。この点について本書では「はじめに」において「平和憲法を成立せしめた諸条件のなかで、軍事支配下の沖縄は、いかなる意味をもつ存在だったのか。」と書かれています。
戦後、「日本の平和憲法」と「軍事支配下の沖縄」は共存していました。新崎先生は、たんに共存してただけでなく、「軍事支配下の沖縄」がなければ「平和憲法」も存在し得なかったということを指摘しているのだと思います。
つまり、沖縄を除いた日本の「平和」は、「捨て石」とされた沖縄の「軍事支配」(=暴力支配)によって初めて成立しえた・・・。
1952年の対日平和条約で、日本は独立しました。
一方、沖縄(正確には「北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島」ということです)は、日本から分離され、「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に」おかれることになりました。
詳しくは条約第3条に書かれていますが、その成立当初から「併合という悪名をまぬがれながら、併合にともなうすべての利権を手に入れた『法的怪物』とよばれていた」そうです。日本政府は「潜在主権」を認めてくれたということで連合国に感謝しています。
ここのカラクリについては、「沖縄の歴史~日本からの分離」で宮里政玄氏の著作紹介で詳しく書いておきました。
日本政府の対沖縄政策が積極化するのは、1950年代後半です。岸・アイゼンハワー会談(1957年6月)では沖縄返還が取り上げられますが、アメリカは拒否します。
安保改定について。
政府は、安保改定について「基地貸与方式から相互防衛条約方式に改めることによって、日本の自主的立場を強化することにある」と説明しました。そのため、沖縄・小笠原を共同防衛地域に含めるか否かが焦点となりました。
岸首相は、「沖縄・小笠原を共同防衛地域に含めれることは施政権返還の第一歩」などと主張しました。しかし革新勢力や自民党の一部からは、「米軍が米台、米韓条約にもとづいて沖縄を作戦基地として台湾海峡や朝鮮半島の紛争に介入すれば、日本も自動的にその戦争に巻きこまれることになる」という批判を受けます。
この革新勢力などの主張に対し、沖縄からは「『戦争のおこった場合、火の中の栗になる沖縄のためにけがをしたくないということに外ならぬ。』」(琉球新報よりの引用)などと反発が起こりました。
結局、このときは沖縄は共同防衛地域には含まれませんでした。
1965年1月、第一次佐藤・ジョンソン会談が行われ、「日本が沖縄にアメリカと共通の軍事的利益を有していることを確認」しました。翌月、アメリカは北爆を開始し、以降ベトナム戦争に全面介入します。
ところで「共通の利益」とは何でしょうか?たしかに安保は、国と国が結んだ条約(同盟)なのだから、どちらかが一方の属国でもないかぎり、そこには何らかの「共通の利益」があるのは当然といえば当然なのですが、それが何だか分からないというなんだか不思議な感じです。しかし、安保をとおして沖縄を見ると、いつもこの日米両国の「共通の利益」にぶつかります。したがって、「共通の利益」が???のままでは、問題解決の糸口がつかめません。
「共通の利益」って何ですかね?
同年8月、佐藤首相は沖縄を訪問します。復帰運動が高まる沖縄では、「歓迎」「請願」「抗議」「阻止」などのさまざまな反応が上がりました。首相は、「沖縄の祖国復帰が実現しないかぎり、わが国にとって戦後の終わっていないことをよく承知しております。」という有名な演説をしました。
これについて「彼の帝国主義的野望のひそかな表明でもあった」と書かれています。どういうことでしょうか?
首相は、「沖縄が攻撃をうければ『日本人らしい行動』をとる」と発言して問題となり、のちに「現状のままでは沖縄への自衛隊出動はできない」と形式的に撤回するということがありました。
「帝国主義的野望」とは一言でいえば「沖縄返還を利用した軍事増強(自衛隊の増強)」のことをさしているのではないでしょうか。
この頃、沖縄人民は、返還を熱望していた。首相も返還を熱望していた。しかし、その両者の意図は余りにも違うものでした。
1966年度予算では、沖縄援助が拡大され、アメリカの援助額を初めて上回りました。
1966年後半から1967年はじめにかけて、日米両政府が「沖縄返還」に政策転換したとき、「沖縄基地の自由な使用を保証することが施政権返還の前提条件」という「核つき返還論」が登場しました。少し、本書を引用してみます。
「東南アジア諸国への経済援助の肩がわり」「ベトナム政策への政治的支持」「沖縄基地の自由使用だけでなく、在日米軍基地全体のいままで以上の自由な使用」このようなアメリカ政府の要求は、「日本政府・支配層にとって、けっして受け入れがたいものではなかった。たとえば、東南アジア諸国への肩がわりは、日韓条約の成立(1965年)以降、急速に拡大しつつあった東南アジアへの経済進出を促進することにほかならなかった。それは肥大化する日本経済の原材料供給源や輸出市場を確保するための手段であった。」
「ベトナム政策の支持は、国内の反戦運動を刺激することではあったが、日本支配層の経済的利害は、これを否定することができないほどにベトナム戦争と深くかかわりあっていた。」、在日米軍基地の自由使用について「アジアにおける日米の軍事的目的は、基本的に一致していた。」しかし、独自の軍事力増強への要求もまた強まっていました。
やや分かりづらいです。しかし分かりやすく書く力量がわたしにはありません。
とにかくこうした状況のもとで、沖縄返還へむかっていきました。こうした中、沖縄人民がどのような思想と行動をつくりあげていったのでしょうか?次回以降、紹介したいと思います。
以上です。
2006.03.15
「沖縄戦後史」(その3)
三、一・二への沖縄人民の対応(1)
沖縄戦が終結し米軍政下にあったとき、民衆は「絶望的貧困」で「アナーキーで混沌たる状態」のなかにありました。
それでも1947年頃から政党が結成されはじめます。この年の6月には沖縄民主同盟、7月には沖縄人民党などが結成されました。各群島別にも政党が結成されたようです。
共通のスローガンは、「民主化」です。また米軍を「解放軍」と規定し、とくに奄美や沖縄島の政党は独立を志向する傾向が強かったようです。
「絶対的貧困」のなかでも、「民主化」を要求して政治活動がはじまったというのは、ある意味すごいことだと思います。食うことに困ってるからこそ政治が身近なものとなり、生き生きとした政治活動が行なわれていたのかもしれません。
独立論的傾向に対して、日本復帰思想の萌芽もみられます。ここで登場する仲吉良光の復帰思想は、日琉同祖論(日本と沖縄の人類学的・言語学的・歴史的な同一性)と天皇制への愛着を根っこにしたものでした。
後者について仲吉は「なんだか身内にほのぼのと勇気がわき出るのを覚えた」と書いていますが、このような体験は「多くの日本人に共通するものであった」。実際に仲吉は、占領米軍や外務省、GHQなどへの働きかけも行いました。
ところで戦前・戦中の最高権力者であった天皇および天皇制が、戦後も引き続き維持されたというのは、沖縄に限らず日本とっても戦後思想の最大の焦点でした。はたしてもう終わった議論なんでしょうか?
シーツ長官の「民主化」政策をすすめましたが、その具体策として、1950年9月から10月にかけて群島知事選挙と群島議会議員選挙が行われました。群島知事選には以下の三人が立候補します。沖縄民政府工務交通部長・松岡政保/平良辰雄/人民党書記長・瀬長亀次郎。
松岡は、復興資金を一手に握り「典型的な植民地官僚の頂点に立っていた」人物で町村の政治指導者たちの支持を受けていました。平良は知識層とくに教職員などの支持を受け、農民層の支持も厚かったようです。結果、平良が当選。
一方、講和会議が近づき、日本の独立と沖縄の日本からの分離がしだいに明らかになるなかで、沖縄では民衆の政治意識は日本復帰へ向かいました。だから選挙結果は、「民衆の復帰への志向により密着していたか」が強く問われるものでした。
なお、1950年10月、平良支持者たちは社会大衆党を結成します。1951年には、奄美を筆頭に各群島で日本復帰の署名運動が取り組まれ、住民の7~9割近い署名を集めました。
この頃の復帰運動の特徴をみておくと、一つは「文化的民族的一体感の強調」、二つに、全面講和や基地反対などの政治的主張の積極的排除です。
一方で、独立論が強調したヤマトの沖縄に対する歴史的「差別支配」の問題は、「戦後の日本は生まれ変わった」「戦前までの日本とはちがう」として清算されていきました。このもとで、当初あった憲法制定要求や日本政府への戦争被害の賠償請求(人民党)などの問題はあいまいなままになってしまったそうです。
ここで大きな疑問がわきあがります。なぜ沖縄戦であれだけひどい犠牲を被ったのに、日本復帰を主張したのでしょうか?
「絶望的貧困」からの克服という生活欲求と、敗戦から立ち直りつつあり独立を目前としている日本への憧れが結びついたこと。戦前からの日本志向が戦後に引き継がれ、日本肯定が補強されたこと。この2点が、「政治的主張を極力排除(つまり米軍占領に反対しないということ)しての日本復帰」という主張につながったのではないでしょうか?
ここには、戦後沖縄の歴史の重要な問題(良くも悪くも)が含まれているような気がしてなりません。先へ進みます。
「対日平和条約発効から1956年なかばまでは、沖縄の民衆にとっての暗黒時代であった。」
「反共」政策が前面化する中で、米民政府は人民党つぶしを目的とした露骨な選挙干渉を行います。この頃、初代任命行政主席・比嘉秀平の与党として親米・反共を掲げた琉球民主党ができました。それでも民主党が選挙によって多数派となるには数年かかりました。それだけ反米意識が強かったということでしょう。
対日平和条約発効後も復帰運動は続きますが、「奄美返還は、すなわち沖縄支配永続宣言であり、復帰運動弾圧宣言でもあった。復帰運動は、祖国日本の同意もえてつくられた合法的国際秩序を破壊するものであるから、国際共産主義運動に利益をあたえるのみである、というのが米民政府の見解であった。」
こうして運動の先頭にたっていた沖縄諸島祖国復帰期成会は自然消滅しました。
日本独立と沖縄の分離を日本政府が認めた以上、国際秩序維持を防衛する米軍占領との衝突を回避したいかなる日本復帰運動も消えるしかなかった、ということでしょう。逆にいえば、こうした過程を通して、日本復帰運動は強くなっていったのかもしれません。
2006.03.17
「沖縄戦後史」(その4)
三、一・二に対する沖縄人民の対応(2)
復帰運動への圧力が強まったこの時期、労働運動が台頭しつつありました。「争議のほとんどは、本土土建業者を相手に闘われてい」たそうです。米・比・日・琉球という人種差別賃金が横行していたそうです。
メーデーも開催されます。とくに第三回メーデー(1954年)はひどいものでした。米軍は「共産主義者以外は参加するな」と呼びかけ、中止に追い込もうと必死でした。これに応えて主要な会社が「参加者は解雇する」と社長通達を出し、結果として、教職員会会長が不参加を表明したり、社大党が参加を取り止めたりしました。
教職員会は、校長や教頭も含めた先生や学校職員のグループです。力のある団体だったみたいです。
こうした弾圧網の中でも396人が参加(米民政府発表)したそうです。「参加したら酷い目にあわせるぞ」という圧力が頂点に達してたときに、あえて参加した決意を想像しないわけにはいきません。
以降、「人民党事件」で指導者を次々逮捕し、組織壊滅を狙う弾圧はさらに強まりました。
軍用地政策も新たな展開を見せます。「土地収用令」のもと暴力的に土地強奪しつつあるなかで、米民政府は、「軍用地一括払い方針」を発表します。これは「米軍の定めた借地料(地価の6%)の16.6ヵ年分、つまり地価相当額を一度に支払うことによって永代借地権を設定しようという」ものです。
この傲慢さ加減は、ブッシュ大統領並です。「銃剣とブルドーザー」で力づくで土地強奪を進めながら、一方で「金払うんだ、文句あるか」ってなもんでしょ。しかも「半永久的に返す気ないよ」という借地料の設定です。
1954年4月、立法院は、のちに「土地を守る四原則」とよばれる「一括払い反対・適正補償・損害賠償・新規接収反対」を全会一致で可決します。同時に、行政府・立法院・市町村長会・土地連合(軍用地主約4万の組織)が四者協議会を結成し、米民政府と交渉し、本国政府に陳情を行ないました。
それに対する答えが「プライス勧告」です。
沖縄の基地は
・制約なき核兵器基地として
・アジア各地の地域的紛争に対処する米極東戦略の拠点として
・日本やフィリピンの親米政権が倒れた場合のよりどころとしてきわめて重要である
これらを強調し、軍用地政策を含む米軍の占領統治は基本的に正しい(!)というものでした。「四原則」は全否定されました。
しかも1955年9月には由美子ちゃん事件(6歳の幼女暴行惨殺事件)、1956年4月には悦子さん事件(スクラップ拾いの婦人が射殺される)が相次いで発生し、民衆の怒りは頂点に達しました。
1956年6月20日の「四原則貫徹・領土死守・国土防衛」を掲げた市町村住民大会に16万~40万人が立ち上がりました!
スローガンからも分かりますが、「島ぐるみ闘争は、復帰思想に支えられた日本復帰運動としての側面をもっていた。」早くも五者協(四者協+市町村議長会)が後退しつつも、住民運動はさらに前進しました。
講和条約の締結を前後するころに高まっていた日本復帰運動がいったんは停滞しましたが、土地闘争が高まる中であらためて息を吹き返したということでしょうか。
「島ぐるみ闘争は、漠然とではあったが米軍があたえた形式的な三権分立の政治機構をこえた人民政府的な住民自治組織を構想しはじめていたのである。」と指摘されています。
もし「防共の拠点」とされた沖縄で「人民政府」が実現してしまったら、アメリカには絶対に認められないことです。ちょっと前にアイゼンハワー大統領が「沖縄のわれわれの基地を無期限に保有するつもりでいる」とまで言っているわけですから。
だから住民組織が五者協の制動を突破して、「沖縄土地を守る協議会」へ発展改組した段階で、弾圧は一挙に強まりました。その手段を見てみましょう。
一つは、中部地域に対するオフリミッツ。
米兵相手の風俗業者が密集するコザを中心とした地域一体に米兵要員の立ち入り禁止したのです。米兵相手に生計立ててた業者は真っ青になりました。
二つに、琉大に対する反米学生の処分要求。
学生の「過激な反米的行動」がオフリミッツの理由であると示唆して地域住民の反発を煽り、オフリミッツ解除を主張する側の怒りの矛先を「反米学生」に向けつつ、大学当局へは財政援助の打ち切りを通告。結局、大学側は除籍を含む厳重処分で応えました。
最近(07年9月)、この処分が数十年ぶりに撤回されたという新聞記事がありました。
民主党も行政府も米民政府側につき、土地協や五者協の解散を提起。結局、沖縄土地を守る協議会は解散します。そして大衆運動とは無縁な沖縄土地を守る総連合が結成されました。
ようは、金でつる、仲違いさせてつぶす、権力を効果的に駆使して叩きつぶす。そんな簡単に済ませられる話ではないと思いますが、先へ進めます。
一方、1956年12月から那覇市長問題がはじまります。この動きのなかで、「一括払いに反対でない」「一括払いを認めてその資金を経済復興に当てるべきだ」というところで、財界と政界の結びつきはじめました。
これは「新しい支配層の成立」と指摘されています。これはのちに沖縄自由民主党の結成(1959年10月)として、姿をあらわします。
この頃、那覇市長問題もおこります。これはこれとして重要ですが、長くなるので詳しくは省略します。
1956年12月、米民政府は、辺野古地区の土地所有者と直接賃貸借契約を結びます。「島ぐるみ闘争後はじめての新規接収であった。」
??辺野古??今、燃えあがってるあの辺野古?そうだったんだ、まったく知りませんでした。
沖縄土地を守る総連合は、
・契約期限を5ヵ年とし契約更新のたびごとに双方の合意に基づく地料を定めること
・地料は原則として毎年払いだが契約期限以内の分の前払いについては考慮すること
・新規接収は不毛地などの条件つきで必要最小限はこれを認めること
という「軍使用問題解決具体案」を提起し、ついに「四原則」反対から脱落しました。立法院でも、この方針通りに決議されました。
アメリカ政府は、大幅な土地使用料の値上げを中心にこの方向で土地問題を収束させました。立法院内で少数革新派であった人民党も社大党も、決議に対し大衆を組織して反撃しようとはしなかったということの問題が指摘されています。
「プライス勧告」とへの闘いの高揚~土地問題の収束までが、戦後沖縄の最大の大衆運動の高揚期で「島ぐるみ闘争」と呼ばれるものです。これは記憶にとどめ、いま考えてることが必要で有意義だと思います。そしてなぜ「島ぐるみ闘争」がつぶされたのか
も。
土地問題が収束し、安保改定がやってきます。
これに対して、沖縄の民主団体や革新政党は「安保改定よりまず復帰」を掲げて復帰運動をすすめました。1960年4月には教職員会、沖縄県青年団協議会、官公労が世話役団体となって、沖縄県祖国復帰協議会が結成されました。沖縄自民党へも参加を呼びかけましたが、不参加。
ここで重要な問題が指摘されています。復帰協は「安保改定よりまず復帰」というように、安保論議を棚上げにするところから出発したということ。一方、60年安保闘争も全体としてみればけっして沖縄を視野に入れていなかったということ。
この頃、復帰運動を批判する政治的潮流も形成されたそうです。詳しくは略します。
1961年には全沖縄軍労働組合連合会(全沖労連)が結成されます。島ぐるみ闘争の成果として、労働運動も前進し労働組合の組織化もすすんでいました。
「一方、58年ごろから米民政府の労働政策は『労働組合主義と共産主義を同列にみる傾向』から、労組の『健全育成』をめざす方向に転換しつつあった。」という条件もありました。全沖労連は1963年7月には全軍労となり、沖縄最大の労組に成長していきました。
何はともあれ、基地労働者が労働組合を結成し、自分たちの権利を堂々と訴える条件ができつつあったということです。
1962年2月1日、「日本領土内で住民の意思に反して不当な支配がなされていることに対し、国連加盟諸国が注意を喚起することを要望する」という「植民地解放宣言」(国連総会で可決)を一部引用した決議(二・一決議)が、自民党が多数である立法院で可決されました。
日本政府は「沖縄は植民地じゃない」とあわてて発表したり、革新側はこれを契機に復帰運動の発展を切りひらこうとしたりしました。
ちょうど、アジア・アフリカで植民地から独立する国々が増えた頃のことです。
二・一決議直後のケネディ大統領の沖縄新政策は、「『米国の施政をつづけることが軍事上絶対必要である』との前提のもとに、『琉球諸島は日本の一部である』ことを認め、沖縄に対する『援助供与について日本政府と協力する』ことを明らかにするとともに、アメリカ政府の大幅な経済援助額を約束したにすぎなかった。」これははなはだ不評。立法院の勢力地図も、自民後退・革新共闘回復となりました。
そして二・一決議以降の政治状況への反動として「キャラウェイ旋風」。
「自治は神話でしかない!」沖縄の人たちは、この言葉を怒りと悔しさでいっぱいで聞いたんじゃないでしょうか。
この頃、自民党が一時分裂し、反主流(のちに沖縄自由党を結成)は、動揺しつつも主席公選闘争に身を投じたりもしました。すぐに日本政府の圧力に屈して再合同(1964年9月)し、主席公選闘争からの戦列からも去ってしまいます。
「保守派の動きは、中央権力に追随しながら利権を争う地方政治家のみじめな派閥争いにすぎなかった。」と。
この頃、革新側も組織分裂が相次ぎます。詳しくは略。
保守再合同による裏切りは、主席(=民政府トップ)公選闘争に火をつけてしまい、主席指名実力阻止となって爆発します。デモ隊と警察隊が激突、いったん議会が流会し、ピケを排除した上でなんとか松岡政保が主席に指名されました。
安保改定、日本復帰、保守分裂、革新分裂、労働組合運動の前進・・・いろんな要因が複雑に絡まってきました。そして世界情勢も、沖縄をノンビリとさせておくことはなかったのです。
以上です。
2006.03.20
「沖縄戦後史」(その5)
三、一・二に対する沖縄人民の対応(3)
1965年、アメリカがベトナム戦争に全面介入します。沖縄ではすさんだ米兵による犯罪が激増しました。沖縄からB52戦略爆撃機が出撃しました。
ベトナム戦争というと、映画「プラトーン」とか「地獄の黙示録 」で知っている程度です。
しだいに戦争は泥沼化するのですが、全世界でベトナム反戦運動が起こります。沖縄でも、ベトナム戦争に対する加害者意識(沖縄から出撃した爆撃機がベトナム人を殺してる、これはわたしたちが戦争に加担してるということではないか・・・)にたった反戦意識も生まれてきました。
そのころちょうど、佐藤首相が沖縄を訪問します。
これに対して、「佐藤総理を迎える会」(委員長・松岡主席、副委員長・屋良教職員会会長)が結成されたり、沖縄県祖国復帰協議会(復帰協)は「首相にたいする祖国復帰要求県民大会」が開催されたりしました。
首相の来沖に対してはいろいろな意見があったみたいです。歓迎行事と「県民大会」に同時参加した教職員も少なくなかったそうです。ちょっと不思議な感じです。どっちが本音で、どっちがたてまえ(お付き合い)だったのでしょう。
「県民大会」ではデモ隊が首相との直接会見を要求し、1号線(現在の国道58号線)を400メートルに渡って占拠しました。首相に会えないことが分かった段階で多数決で解散が決定しましたが、最後まで残った二千人は警官隊に襲撃されて多数の負傷者が出たそうです。
結局、佐藤首相は米軍基地から出ることができず、基地内で一夜を明かさざるをえませんでした。
つづいて教公二法阻止闘争が起こります。
この頃、「本土なみに教職員の政治活動や争議行為の禁止、勤務評定などを盛り込んだ教公二法、すなわち地方教育区公務員法(本土の地方公務員法に当たる)と教育公務員特例法の制定が急がれた」そうです。
なぜでしょう?それは、復帰運動を後退させ、沖縄民主党の退勢挽回を図るために、復帰運動の中心勢力である教職員会の行動に制約をはかるためにしかけられたということらしいです。
民主党が議会で強行成立させようとしましたが、阻止闘争の力で結局廃案に。あまりに短期間のうちに激しく情勢が動くので、書ききれません。「詳しくは本を読んでください」というしかありません。
「もはや小手先の政策修正で沖縄の政情を安定させることは不可能であった。祖国復帰運動に集約されてきた沖縄人民の諸要求をばらばらに解体させ、そのエネルギーを低下させるためには、なんとかして『沖縄返還』を実現しなければならなかった。」
変ですよね。講和条約前から教公二法阻止闘争の時期に至るまでずっと復帰運動に圧力かけ続けてきたのに。これは一体どういうことでしょうか?
「沖縄戦後史」はこの時期の沖縄返還論議について次のように指摘しています。
「特徴的だったことは、なぜ日本政府が、67年前半から急に『国民的願望』の達成に熱心になりだしたかという認識を欠いたままで、どのような返還方式が現実的にあるいは道義的に望ましいかを論じていたということである。もっとも、日本政府の政策転換の意図を見抜けなかったという点では、沖縄問題に対する国民的関心とともに『70年闘争の突破口としての沖縄闘争』などという言葉を口にしはじめた革新勢力の場合も同じであった。」
「国民的願望の達成」という熱烈な歓迎ムードの中で、軍事拠点が維持された。はたしてどのような「願望」が達成されたというのでしょうか。
1968年始め頃から、しだいに基地撤去闘争が高揚してきます。加害者意識にたったベトナム反戦運動がついに直接基地に向かったということです。
それに対しては、「沖縄返還の障害になっているのは、沖縄の基地撤去を主張している連中で、施政権返還の最大の障害は何だといえば、それは赤旗だ」(福田自民党幹事長)と嫌悪感に満ちた発言もありました。
そして1968年4月24日、全軍労がついに大幅賃上げ要求を掲げたストライキ(2万3千人参加)に立ち上がります。この2万3千人という数字は、組合員の実数を凌ぐものでした。
モンパチでもORANGE RANGEでも、これだけ集めるのは大変でしょう。
同年11月には主席公選選挙が行なわれます。初の選挙です。これまでは(その4)でも書いたように主席は米軍にとって都合のいい人間が「指名」されてました。
教職員会会長・屋良と自民党が支援する那覇市長・西銘の一騎打ちとなります。
西銘・自民党は、「屋良を選べば、イモを食いハダシの生活をすることになる」と宣伝しまくりました。
このイモ・ハダシ論の出所は、「基地が縮小ないし撤去された場合、沖縄はたちどころに昔のイモとキビだけのハダシの経済に帰るだろう」というアンガー高等弁務官の発言だそうです。
屋良・革新共闘は、当初は基地問題を争点にするのを避けましたが、けっきょく争点にせざるをえず、「基地容認は戦争容認だ」と切り返します。
結果、屋良当選。
西銘陣営が占領軍の言葉=イモ・ハダシ論で選挙戦をたたかったということの意味を考えないわけにはいきません。この言葉が、今だったら日本政府が沖縄に対して言ってそうな気がしませんか?「基地を拒否すれば振興策はないぞ」・・・。歴史がこうもダブるとクラクラしてきます。
ところで今わたしたちは、イモ・ハダシ論に対し「基地容認は戦争容認だ」と切り返せるでしょうか?
数日後の11月19日、嘉手納基地でB52が大爆発をひき起こします。「いのちを守る県民共闘」が結成(復帰協と同じ枠組み)され、B52撤去闘争から二・四ゼネストへと闘いが一気に高まります。
ゼネストとは、「全国の全産業、または同一地域・同一産業の労働者が統一要求を掲げて一斉に行うストライキ」。ついヤフー辞書引いてしまいました。
日本政府は「どうにかしないと」との思いを強くしました。その結果、二・四ゼネストは、政府のゼネスト回避工作に対する屋良主席の屈服と、総評・同盟の屈服が、県労協の後退に通じ、ゼネスト失敗へ結実しました。
屋良は、「6~7月にB52撤去する」という感触と「復帰が遅れる」という政府の脅しに屈服した、と。政府はトップの切り崩しに成功したのです。
総評とか同盟というのは、日本の労働運動の革新勢力みたいなものです。その総評や同盟は、反戦派労働運動が指導層の制御を踏み越える可能性を恐れたそうです。そして屈服した。そもそも「本土側労働団体が、二・四ゼネスト支援のために努力した痕跡はほとんどみることができない。」
ラジカルに闘う労働運動グループが壁を突き破る可能性があった、そうなると総評も同盟も困るということなのでしょう。
「二・四ゼネストの挫折は、強烈な自己主張なしに本土革新勢力と系列することや、なによりも日本復帰を優先させるという思想心情では、沖縄が直面する困難な状況を打開することはできないことをおしえた。」のだそうです。
ところで米軍は、「ゼネストやったら首切るぞ」と脅していました。で、けっきょくゼネストは回避されたのですが、そうしたら想定の3倍もの労働者が解雇されました。闘っても闘わなくても解雇されたのです。だったら・・・だったなら・・・
1969年。
6月5日、解雇撤回を要求した全軍労スト。
6月23日、「慰霊の日」を「反戦の日」として、「安保破棄・B52撤去・即時無条件返還」を掲げた県民総決起大会(復帰協主催)。
ところで、政府が屋良主席に口添えした「『6~7月にB52撤去する』という感触」はどうなったのでしょうか?
はたして。B52は常駐化しました・・・。
つづいて11月佐藤首相の訪米。復帰協は「訪米阻止」から「首相の意図する返還方式に反対」へトーンダウンしました。
11月21日、佐藤・ニクソン共同声明が出されます。詳しくは「共同声明」を読んでるしかないのですが、じっと耐えながら読んでみると、「1972年沖縄返還」についての日米政府の考え方、狙いがよくわかる気がします。味気ない文章ではありますが。
以後、基地労働者の大量解雇、賃下げ、労働強化などの合理化政策がはじまります。
1970年。
全軍労は合理化政策に対し解雇撤回闘争で対決する方針を打ち出し、ストを展開します。米軍は力で対抗しました。オフ・リミッツの再現(島ぐるみ闘争のときの米軍の対応)、基地関係風俗業者と結びついた暴力団によるピケ隊襲撃も発生しました。
こうしたむき出しの暴力とも向き合ったにもかかわらず、全軍労の解雇撤回闘争は革新勢力全体の問題とはなりませんでした。
11月、国政参加選挙。返還を前にして、沖縄でも国政選挙が行なわれたのです。革新政党は「日米同盟に対して沖縄の民意を示すチャンス」として積極的に取り組みました。拒否派は「沖縄返還協定とその国会承認の準備作業としての国政参加選挙を拒否する」。
毒ガス撤去問題にかかわるアメリカの身勝手さ、5月女子高生刺傷事件、9月米兵酔払い運転による主婦轢殺事件、そして米兵が無罪になったとき、怒りは爆発します。
12月コザ暴動。「コザ暴動は、多くの民衆の圧倒的ともいえるような支持と共感をよびおこした。」その後、国頭村での実射演習実力阻止、美里村での毒ガス移送実力阻止もたてつづけに闘われました。
1971年。
4月15日、全軍労ストと結合した沖縄返還協定粉砕をスローガンした県労協統一スト。5月19日、返還協定粉砕ゼネスト。
「四・一五統一ストから五・一九ゼネストにいたる闘いは、二・四ゼネストの挫折、佐藤訪米阻止闘争の敗北を各組織のなかでのりこえようと人びとの努力と、コザ暴動で噴出した民衆のエネルギーとの接点に構築されたものであった。」
11月、衆院沖縄返還協定特別委員会で返還協定の強行採決。
そのとき国会では爆竹が鳴り響きました。沖縄青年同盟の3人の沖縄出身者の手によるものだったそうです。
1972年。
3月、全軍労無期限スト。
5月15日、沖縄返還。そのとき復帰協による「沖縄処分抗議、佐藤内閣打倒、5・15県民総決起大会」が開催されました。
沖縄は返還されました。しかし復帰運動の中で要求された基地撤去も合理化反対も、捨て去られてしまったのです。
以上です。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…
- 金沢旅行 4日目
- (2025-11-12 17:42:15)
-
-
-

- ヨーロッパ旅行
- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…
- (2025-10-28 17:31:03)
-
-
-

- 皆さんの街のイベントやお祭り
- 令和7年 鳳サマーカーニバル 野田・…
- (2025-11-17 06:07:21)
-
© Rakuten Group, Inc.