○コンテスト
それは、どの地区も金管アンサンブルの成績が悪いのは何故?ということです。
サックス4重奏はしばしば見かけますが、巷でフルートやクラリネットのアンサンブルには殆どお目にかかりません。
打楽器のアンサンブルも同様です。
強弱、音域・音色どれをとっても圧倒的なものを持つ金管アンサンブルが木管のアンサンブルに対してコンテストでは絶対優位なんじゃないかと思うのは、私がラッパ吹きだからという理由だけのものではないと思います。
同じカテゴリーに属するどうしが点数を争うわけですから、経験年数などの違いが大きいとは思えません。
それなのに金管パートは学内予選さえ突破できないでいる印象が強く、高校生より中学生というように若年層になるほど顕著になるようです。
金管楽器は初歩の段階で木管楽器より難しいということでしょうか?
聴いているだけなら、金管アンサンブルが圧倒的に面白いと思うのは私だけですか?
<<たまくながおさんからトラックバック>>
※そたぱぱさんのHPよりコピーさせていただきました
一度,トラックバックなるものをやってみたかったので,
たかくながおさんからのブログからトラックバック!!(^O^)
アンサンブルコンテストについて書いていらしてました。
アンサンブルコンテストは金管と木管,どっちが有利か!?
・・・どっちだと思います?
審査員的立場で考えてみた。
(実際に審査員になったことはないけれども)
審査員は技術と表現のランク付けを点数化して審査する。
それでは,どんな演奏が高得点を得られるか。
1
あくまで私の持論だが,
コンクールでもアンサンブルでも
審査の結果に大きく左右するのは,
「選曲」ではないかと思っている。
少なくても審査の5割は占めていよう。
2
選曲だということは,
木管と金管,レパートリーの幅が広いのはどちらか。
おそらくレパートリーの幅が広いのは,
金管楽器での組み合わせが木管楽器よりも
自由度が高いことを考えると,金管楽器か。
3
ただし,初心者が多い中1,中2。
初心者に木管楽器と金管楽器,どちらが音域が広がりやすいか
考えてみる。唇で倍音を調節する金管楽器のほうが,
押さえてハイトーンが鳴る木管楽器よりも圧倒的に不利。
中1の段階で,らっぱの場合,
チューニングより上が出るようになったら
通常は「上手い」部類に入る。
いくらレパートリーが多くても,
音域が狭いと,やれる曲は至極制限される。
4
それに比べると,木管楽器のほうが音域が広く,
指の運動量の差も加味すると,中学生でも吹けるレパートリーが多く,
フルートも溶け込みやすい上に,
サックスは同属楽器で作品も多彩。
クラリネットもオプションクラを加えると,
まるでオルガンのような響きになる。
演奏会映えする曲やテクニックが中学生でも扱いやすい。
以上 1~4より,
どちらかが有利かと訊かれると,木管楽器と答えてしまう。
しかし,これはあくまで確率論。
指導者が金管楽器を知り尽くし,
鍛え上げられれば,
同じ実力で演奏会映えするのは金管楽器です。
それだけ,金管楽器のほうが遅咲きの気がするのですが。
異論あるかた,いらっしゃいますかね~
次回は,打楽器のことについてほざいてみるか。
<<dongguan777さんの日記より転載させていただきました>>
※ http://plaza.rakuten.co.jp/malay/ をご参照ください。
金管楽器は木管楽器より難しいのか?(長文です。)
※この日記はたまくながおさんの仰っている「難しい」と言うポイントとは
だいぶ違う話かと思いますし、いつもの事ですが話がかなり違う方向に
行ってしまっています。
また、金管楽器奏者からの一方的な見方ですので、あまりフェアとは言えない書き方に
なっています。
決して木管楽器が簡単だと言っているわけではありませんので、その点は我慢して
お読み下さい。
http://tb.plaza.rakuten.co.jp/tamakunagao/diary/200503250000/
今日もこちらのたまくながおさんの日記の中に興味深いお話が
ありましたので、そちらについての日記を書きます。
まず1行だけたまくながおさんの日記から引用させていただきます。
>金管楽器は初歩の段階で木管楽器より難しいということでしょうか?
私が金管系の者なので言うわけではありませんが、確かに難しいのではと思います。
それでは、難しいと思う点について、
「音楽」としての総合力や個々の楽器に求められることは全く無視して書いて行きます。
・早い時期にとりあえず標準的な運指表の下から上までの音が出るようになる。
・早い時期に標準的な運指表の下から上までの音が曲中で使えるようになる。
木管の方に怒られそうですが、これに関しては木管の方が優位かと
思います。
金管の特にらっぱでは吹き始めてから1年程度では本番でFis以降の音を
外す方は結構いらっしゃるかと思います。
(たまくながおさんのお弟子さんではいらっしゃらないかもしれませんし、
いまどきは無いのかもしれませんが、私は結構見ましたが。)
あるいは全く当たらない場合もあるでしょう。
例えばらっぱと同じ様な音域と思われている(これは絶対に違いますが)
Bクラリネットでさきほどの吹き始めて1年経ってこのFis(チューニングのBの上のFisです)
が出ない事はまずないのではないでしょうか?(もしあったらごめんないさい)
当然Bクラリネットには当たり前の様に要求される五線譜の遥か上の音で
苦しみがあるのは承知しています。
でも、素人でもわかるようなミス(特に音を外す事)をプロがしてしまうのは
金管くらいじゃないでしょうか。
素人でもわかるミスとは、
フィギュアスケートでのジャンプの着地失敗
体操での鉄棒の落下
こう言う事と同じ様なレベルの話だと思います。
「ロケットの打ち上げ失敗」も入れようかと思いましたが、流石にこれは無理があるので
やめましたが、
世界最高峰の方でも経験が浅い方でも、失敗に至る次元が違えども、
素人目にわかり易い失敗をすると言う事は共通しているのでは無いかと思います。
・早い時期にそれなりの演奏が出来る様になる。
・早い時期に楽器経験の無い一般の方から見てそれなりの演奏が出きる様になる。
良い表現が思いつきませんが、金管からみて木管のフルートとかクラリネットの
譜面って難しく思ったことは無いでしょうか?
私はむかし楽器を初めて数ヶ月後くらいに同年入部のクラ吹きの譜面を見て
「こんなの吹けるの?」
とビックリした様な記憶があります。
例えばの話ですが、楽器を吹き始めて6ヶ月くらいの新入生の中で
「クラリネットパートで一番上達が遅い生徒」と
「らっぱパートで一番上達が遅い生徒」
両方に同じ曲を吹いてもらうこととします。
条件は、
「そのクラリネットパートの生徒が吹ける最も難しいパッセージが含まれる曲を一緒に吹く事」
とです。
この場合、らっぱパートの生徒はたぶんこの曲を吹けないんじゃないでしょうか?
私は早い段階ではこの位の差があると思っています。
さて、木管の方に怒られそうな事を書きつづけましたが、
なんと言うか、音が出る、指が廻る等の「テクニカル」な面でしょうか?
この点ではあるレベルに達するのは木管の方が早いような気がします。
また、木管の方は早い段階から曲を演奏する上で「テクニカル」な
要求が厳しいと思います。
例えば、コンクールで演奏しそうなオケ曲の編曲物では、
「らっぱはほとんど刻みだけ」、「クラリネットは16部音符の大群」
と言う様な曲もありますよね。
また通常吹奏楽オリジナル曲でも、クラリネットはオケの「ヴァイオリン」的な扱いで
あるため、常に「テクニカル」な要求が厳しいと思いますが、
金管系は「テクニカル」な要求が厳しく無い曲も結構ありますよね。
(これが英国式ブラスバンドだとコルネットが「ヴァイオリン」になりますので、
非常に「テクニカル」な要求が厳しいのですが・・・)
以上、音楽としてではなく「テクニカル」な面だけに限って
思うことを書きましたが、初歩の段階では木管優位の様な気がします。
(必要に迫られるためか、楽器の特性上そうなるのかは書かないでおきます。)
とは言っても木管対金管じゃなくてクラリネット対らっぱの話になってしまいました。
家人がクラ吹きなのでどうしても比較対象がそれになってしまいます(笑)
またちょっと訂正しますが、ピッコロとEsクラリネット、オーボエ(ファゴットもかな?)は木管の中でも
難しい楽器の部類に入るのでは無いかと思います。
これらの楽器は初心者の場合は異常なほど、下手に聞こえてしまう様な気がします。
初心者にピッコロ、Esクラリネットを普通は吹かせませんからこの2つは
あまり問題無いのでしょうが。
※これまでの木管の話は私の経験も少し含んでいます。
遊び程度ですが、一般的な管楽器は一通り吹いた事がありますので、
その時の感覚も少し交えています。
最後にもう1行引用します。
>聴いているだけなら、金管アンサンブルが圧倒的に面白いと思うのは私だけですか?
これは私は同意します。 でも木管アンサンブルでもホルンが入っている木管五重奏は大好きですが。
原文につきましては http://plaza.rakuten.co.jp/malay/ をご参照ください。
<<みっか^^さん>>
私はずっと金管楽器のほうが難しいと思ってきました。
だって木管なんて一つの音に対して運指が決まっていますから、正しい指つかいで息を出せば、誰にでも音が出るんですから。
それに対して金管は指は同じでも唇を変化させて音を変えるということが、とてつもなく難しいことに感じています。
私も金管アンアサンブルはとても魅力的だと思います。
ただ、聴いていて、気持ちよく聴けるところと聴けないところの差が大きいのも事実。
アンサンブルは個性も必要ですが、音を融けあわせることもとても大切で、個性ばかりが目立っていても、また逆にこじんまりとしていてもダメなんですよね。
金管の場合、どちらかというと融合させるのが難しいのでしょうか???
それを武器にするような演奏が必要だということなのかなぁと思いました。(2005/04/01 04:45:30 PM)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 月のボイドタイム(2025年12月)
- (2025-11-28 09:00:05)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 全ショップ2倍もきた!🤩楽天BF6日目…
- (2025-11-28 16:47:43)
-
-
-
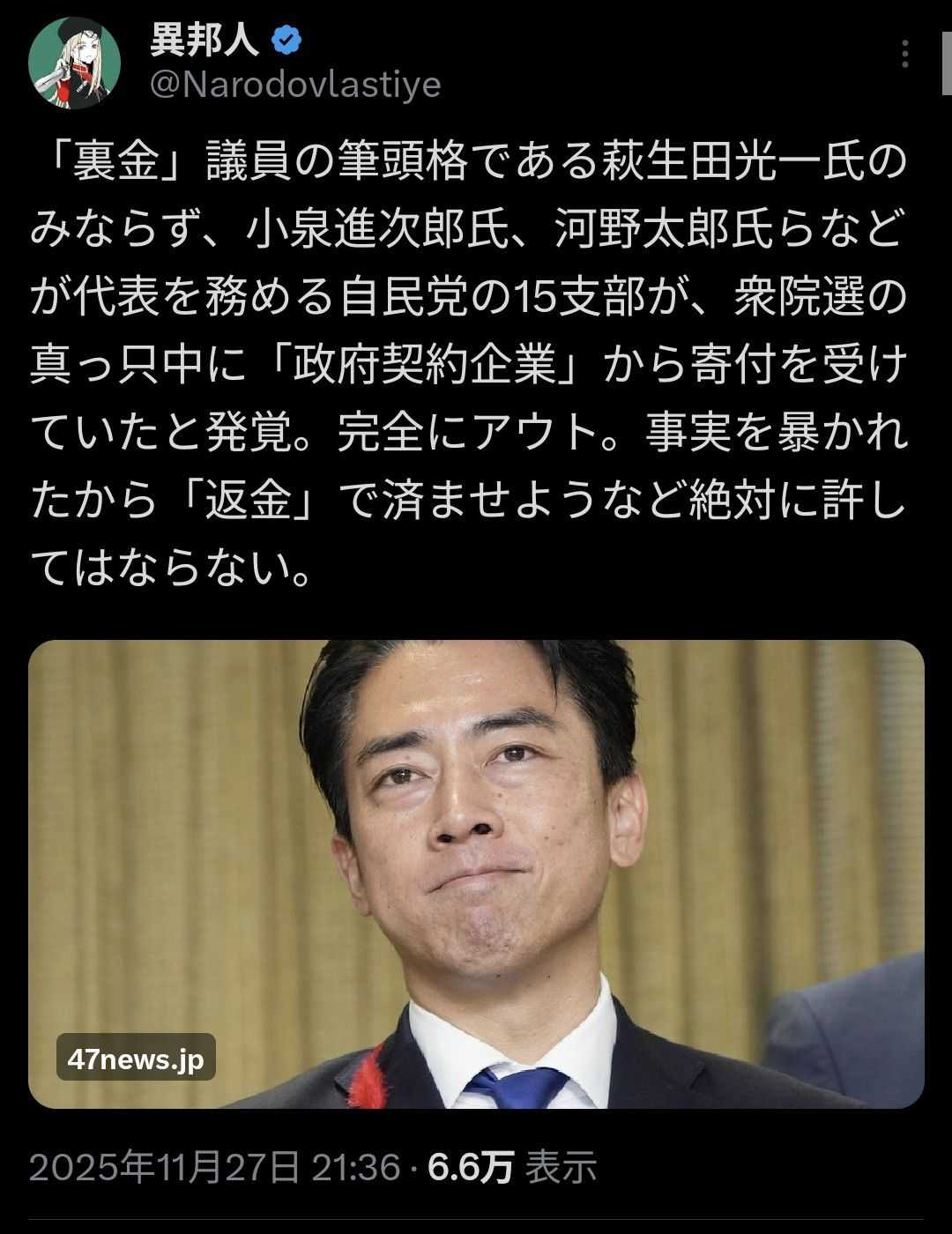
- 政治について
- 腐りきっている自民党。
- (2025-11-28 19:40:38)
-
© Rakuten Group, Inc.



