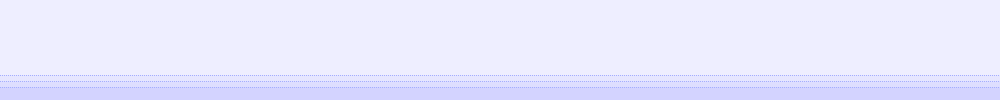新説【竹取物語】・・・2
k_tombowの『新説・竹取物語』
k_tombowの『新説・竹取物語』
k_tombowの『新説・竹取物語』
新説【竹取物語】・・・・・・《6》
黄金に輝く小鉢を見つめる『かぐや姫』の横で、『石作皇子』は緊張の面持ちで、
かしこまっていた。
身分の違いを忘れて、姫の言葉を、固唾を飲んで待っていたのである。
だが、なかなか彼女の口は、開かれなかった。
眼前に置かれた鉢を、ただ見つめるだけで、手に取ろうともしない。
皇子は、その緊張に押しつぶされまいと、左右の肩を上下させて、
小さく咳払いをした。
その動きに誘われるように、ようやく、姫から問いかけの言葉が、投げかけられた。
「よくぞ、このようなものを、お手に入れあそばされましたなぁ。
ご苦労は、いかばかりかと、畏れ入りまする。」
ふと、皇子の頬がゆるんだ。
そのときから、緊張から解き放たれたように、苦労話が、堰を切って流れ始めた。
野山に分け入り、わずかな望みにも縋るように、
賊が跋扈する山中の荒れ寺をも訪ねたこと。
海を渡り、見知らぬ島の、言葉も通じぬ土地を訪ねたことなどなどと・・・。
ひと月あまりの出来事が、止めどなく語られて、時間の過ぎるのも忘れそうな、
長い話になりそうだった。
屋敷の外では、静まりかえった中の様子を、身動きも忘れて、4つの男たちの影が、
窺っていた。
早くも、『石作皇子』が『かぐや姫』の難題を、クリアしてしまったのではないかと、
気が気ではなかった。
陽は竹林の陰に隠れて、代わって姿を現した丸い月が、徐々に輝きを増しつつあった。
止めどなく続く『石作皇子』の言葉に、『かぐや姫』の澄んだ声が、重なった。
「お疲れ様でございました。今宵は、お帰りになりまして、
どうぞごゆるりとお休みなさいませ。」
皇子はその言葉に、不満を伝えるように、
「なぜに? 私が持ち帰った“鉢”に、何かご不審でもありや?」
と、わずかに気色ばんだ声を返した。
「“御仏の御石の鉢”というは、釈迦牟尼仏が、お持ちあそばされたという、
尊いお宝でしょう。釈尊のお宝が、なぜにこのような輝きなのでしょう?」
「それは、山寺の僧が持つうちに、輝きが失せたかと・・・。」
「“鉢”の謂われは、ご承知あそばしますな?」
「もちろん」
「私が手に取ってみても、よろしいものでしょうか?」
「それには及びませぬ。一刻も早くお目に掛けたいと、手入れもそこそこに運びましたので、
お手を汚してはいけません。私が持ってご覧に入れましょうぞ。」
『かぐや姫』に直接持たれたのでは、その鉢の真贋がたちまちにして見抜かれそうで、
皇子は、狼狽した。
姫の眼前に押し出してあった“鉢”を、慌てて持ち上げて、
姫のそばに寄れる絶好のチャンスとばかりに、にじり寄ろうとした。
そのわずかな気の弛みが、皇子の大失態になった。
宝物の“鉢”を、取り落としてしまったのである。
床に転がり落ちた“鉢”には、何事もなかったように見えた。
しかし、弾みというものは、恐ろしい。
『かぐや姫』の前に、改めて差し出された“鉢”には、
かすかな“金箔の欠け跡”ができていたのである。
「これが、まさに“御仏の御石の鉢”と申されるのでしょうか?
先ほど、殿は、謂われはご存じとおっしゃいましたが・・・。」
絶対に欠けることがないはずの“鉢”が、簡単に欠けてしまったのだ。
「あの山寺が、私を謀って・・・。」
そうつぶやくと、皇子は目も上げられずに、そそくさと鉢を抱えて、部屋を飛び出した。
(おいおい、偽物だったんかい?)
(そうみたいだね)
(よくまあ、いわば“結納の品”のようなものだろうに、偽物なんかを持ち込んで)
(皇子本人は、承知していたようだね)
(ばれないと思ったのかねぇ)
(ばれたあとは、潔く身を引いたんだから、そこは認めてあげたらどう?)
(ばれなければ、嫁にできたっちゅうことか?)
(『かぐや姫』にとっては、最初の男がこの調子では、幻滅だったろうね)
(でも、悪いことはできないよなぁ。うっかりミスで、企みがバレちゃって)
(不運だったんだろうな)
(そんなものなの?)
(ここで幸運なやつなら、偽物を掴ませたままで、一生騙し続けることがある)
(世の中なんて、そんなものさ)
(不運=ふうん=そうなの?)
(軽~くダジャレが出たところで・・・)
宝物の(はずだった)“鉢”を抱えて飛び出した皇子を見た4人は、
そのただならぬ気配で、ほぼ状況を察知した。
皇子は“宝物の鉢”を、無造作に竹林に投げやると、4人から顔を背けて、
その場を立ち去った。
後を振り返ることもなく、悄然とした後ろ姿には、誰も声を掛けることができなかった。
皇子の背を、月明かりが、冷たく照らしている。
竹林に投げられた“宝物”を、確かめようとする男も、誰ひとりとしていなかった。
確認することさえ、“むごい仕打ち”に思えたのである。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
一方では、ほかの4人にも、『かぐや姫』にプロポーズできるチャンスが、
残されていることをも、意味した。
これから与えられる『課題』の厳しさを思うと、身が引き締まる思いがするが、
反面で、嬉しさを隠しきれない4人でもあった。
「次は、『車持皇子』(藤原不比等)殿が、ご苦労をなさるのじゃな。」
「気後れするではないか。景気よく送り込んでくれぬか。」
「我らも後に控えておる。ほどほどに・・・な。」
「ほどほどに、では、“姫”を娶れぬではないか。」
「ささ、お行きなされ。」
妙な“景気づけの言葉”を頂戴して、『車持皇子』が『憶良』の屋敷に姿を消した。
「車持殿は、首尾よう成し遂げようか。」
「我らにも、機会がこようかと思うと、成功を手放しで祈ることもできぬ。」
「複雑な心地よなぁ。」
『車持皇子』の首尾が判明するのは、さらにひと月は要するだろう。
3人の候補者たちは、『車持皇子』が現れる頃に、またこの竹林で合うことを約して、
思い思いに散っていった。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
憶良の屋敷内では、息つく間もなく現れた男を迎え入れて、
憶良とかぐや姫が、挨拶を交わしていた。
姫には疲れの色があったが、“次の満月の日”までの安息の時を得るために、
新たな望みを、車持皇子に、告げようとしていた。
「“蓬莱の玉の枝”なるものが、この世のどこぞにあるそうな。
その珍しいものをば、ひとめ見たいものです。」
「承知。お任せを。」
「流石は車持殿であらせられる。“蓬莱の玉の枝”をご存じとは・・・。」
「早速に、見つけ出してご覧に入れましょう。」
車持皇子は、少しでも長く『かぐや姫』のそばにいたかったが、
それよりも“課題”の探索時間を失うことのほうが気がかりで、そそくさと暇を告げて、
自分の屋敷にとって返した。
車持皇子は、“蓬莱の玉の枝”なるものがどのようなものなのか、実体を知らなかった。
まずそれを知ることから始めなければ、探索もできない。
屋敷に帰れば、物知りの誰かが、教えてくれるだろう。
跳ぶように帰宅した車持皇子は、屋敷に入るのももどかしく、
声を張って、家人に問いかけた。
「誰か! “蓬莱の玉の枝”が如何なるものか、存知おるか!?」
「それなる“宝物”は・・・。」
たちまちに、その答えが得られた。
(へえ。そんなに早く、わかるものなの?)
(かぐや姫が知っているんだから、
博識者が多い貴族屋敷なら、誰かは知っているだろうよ)
(誰も知らなければ、知人に電話で・・・)
(電話なんて、この時代にあるものか)
(一刻も早く探したいんだから、手段を選ばないだろうと思ってさ)
(無いものは、使えないだろうよ)
(早く探したいだろうから“電話急げ”って)
(ダジャレなら、何でも良いっていう感じだね。“善は急げ”と“電話急げ”って?)
(ごめん。ところで、18禁の文章は、いつ出るの?)
(忘れてた。堅いこと言わないで、24禁{24金}で許して。)
(万年筆の、ペン先みたい)
(万年筆自体を、今はほとんど使わないって)
(話が逸れっ放し)
(どうでもいいけど、この『竹取物語』って、間延びしていない?)
(中身を、もっと省略した方がいい?)
新説【竹取物語】・・・・・・《7》
“蓬莱の玉の枝”なるものは、何ぞや?
この答えは、屋敷の識者によって、
『東の海のかなたに、蓬莱という山があり、そこにあることが、確認された』という情報が、
車持皇子の元に寄せられた。
「その“蓬莱”とは、東のどこにあるというのか?」
「ひと月ほど、大船を走らせると、行くことができることがある、と古来から伝わる、
“神仙峡”だそうでございます。」
「ひと月掛けても、その仙郷にたどり着けるという、確たる見通しはあるのか?」
「そこはそれ、いかんせん“仙郷”ございますれば・・・。」
「では、万が一にも見つけることができても、行きにひと月、帰りにひと月では、
とうてい期限には、間に合わぬではないか。」
「左様にございます。」
「吾に与えられた、姫の課題は、ひと月のうちに、“蓬莱の玉の枝”を、
手に入れてご覧に入れることである。これでは当初より、諦めよと言うことではないか?」
「左様にございまする。」
「おまえは、己が娶る姫ではないから、そのように気楽なことを言っておられる。
もそっと、吾の身に置き換えて熟慮せよ。」
「はぁ・・・。」
(どだい無理な注文だよね)
(家来も、答えに窮するだろうねぇ)
(思っていることを、はっきり言うこともできないだろうし)
(どうしてさ?)
(“絶対に無理”な課題を与えたと言うことは、探す前から“断られた”ということだもの)
(そうか。直接言うのは、可哀想だね)
(だろう?)
「その“蓬莱の玉の枝”が、中国の仙郷にではなく、大和国の“仙郷”にあれば、いかが?」
「おう! そのほう、佳きことに気づくものよ。」
「では、早速に・・・。」
「くれぐれも、佳きに計らえよ。」
「承知仕りました。」
(意味が、解らないんだけど)
(そこは、主従ならではの、ツーカーの会話だからねぇ)
(で、どんな意味なの?)
(あるとも、無いとも言える“宝物”を、いつまで探しても埒があかないでしょう)
(そうだけど・・・)
(誰も見たことがない宝物で、しかもそれがどんなものか、よく知られている)
(ふんふん・・・)
(それなら、作っちまえば、てっとり早いじゃないか?)
(そういうことか)
(あからさまには言えないから、“腕の良い工人を捜せ”と、暗に匂わせたわけだ)
(きったねぇ!)
(宝物も、伝説も、こうして作られる・・・)
(“草薙の剣”も?)
(専門家じゃないから、そんなことは知らん)
車持皇子は、表向きは、“仙郷”を探して、都を旅立った。
『かぐや姫』には、その後の皇子の行方を、それとなく伝えて、
苦労の様子を知らしめた。
家来のものは、皇子が向かった方とは反対に位置する、
かねてから名を伝え聞いていた“鍛冶匠”を訪ねて、
「金に糸目はつけぬ。いかようにしても、“絶対に欠けることのない玉の樹”を打ってくれ。」
と依頼した。
鍛冶匠は、ほかの注文を総て断り、この特注品に、全精力を傾けた。
とてつもない金額を、払ってくれるというのだから、これを受けない法はない。
朝廷に伝わると言われる、伝説の剣“草薙”にも勝るほどの、
素晴らしい出来映えの品が、ほぼひと月後に、皇子の元に届けられた。
人里離れた仙郷の隠れ湯で、ゆったりとくつろいで知らせを待っていた皇子は、
その“蓬莱の玉の枝”を受け取ると、山を下った。
人里で馬を調達すると、一路、都への道を、ひた走らせた。
(ねぇ。。。)
(今度は、何よ)
(本物の話では、“蓬莱の玉の枝”って、
匠が作るのに3年も掛けたっていうことに、なっていなかった?)
(どうして、そんなに細かいことに、こだわるの?)
(3年と、ひと月とじゃぁ、差がありすぎるから・・・)
(3年なんて、待てると思うの?)
(原作が・・・)
(原作通りに進めたら、『かぐや姫』が、お婆さんになっちゃうでしょ)
(『かぐや姫』って、歳をとるの?)
(歳をとらなかったら、“お化け”でしょ)
(じゃぁ、『ひと月』で妥協しとく)
(ありがと)
調達した馬は、尻を叩けど、走らない。
時々は、機嫌を損ねて、進まなくなってしまうこともある。
皇子は、そんな馬を背負ったり、鼻先に人参をぶら下げたりしながら、
都への道を、さらに急がせた。
「馬を背負うなんて、これじゃ、借り受けずに自分で走ったほうが、速いじゃないか」
『だって、オラァ“農耕馬”だもの。走り方なんて、忘れてらぁい。』
そんな状態が続いて、へとへとに疲れた皇子だったが、
かぐや姫が指定した期日よりも、1日だけ早く、都に帰り着いた。
その『馬を背負う』苦労が、都の人々には、
いかにも“宝探しで疲れ果てた”皇子の姿と、捉えられた。
何が幸いするか、わからない。
そのままの姿で、車持皇子は憶良の屋敷を訪ねて、
『かぐや姫』への面会を求めた。
「おうおう、そのお姿は。さぞやご苦労をなさったことと、察しあげまする。」
「ありがたきお言葉。」
「姫を、これへ呼びましょう。」
「お頼み申し上げます。」
『かぐや姫』の前に、見事な“蓬莱の玉の枝”が捧げられて、
眼前に置かれた。
それを手にした『かぐや姫』は、前回の『石作皇子』の一件があり、
一見みごとに見える、その“蓬莱の玉の枝”を、しげしげと、
時のたつのも忘れて、眺め続けた。
車持皇子は、石作皇子と違い、“蓬莱の玉の枝”の出来映えに自信があり、
姫が眺めるに任せていた。
苦労話も、述べることはなかった。
家人がそれとなく、皇子の苦労を、かぐや姫に伝えていることを知っているので、
屋上屋を重ねる愚を、避けたのである。
それに加えて、皇子の現在の姿を見れば、その苦労は、言わずもがなのこととして、
存分に、姫には伝わっているはずである。
『これというも、あの“役立たずの農耕馬”の、怪我の功名よなぁ。』
皇子は、ひとり、ほくそ笑んだ。
宝物の“蓬莱の玉の枝”にしても、尋常な叩き具合では、
間違っても、傷つくような、ヤワな代物ではない。
『これで『かぐや姫』は、私のものに決まりだな。』
車持皇子は、そう確信した。
憶良の屋敷を、外で窺っていた残りの3人は、気が気ではなかった。
皇子の苦労話は、都に知れ渡り、
『今度こそは、皇子のお手柄よ。』
と、評判になっていたからである。
“蓬莱の玉の枝”さえも、さも誰かがそれを見たかのように、
『今度という今度は、本物に間違いなかろう。みごとな代物であった。』
と、3人の耳にも、入っていたのである。
「車持殿は、家人の働きも、なかなかのものよなぁ。」
「うーむ、籤運の悪さが、我らの敗因になったかも知れぬ。」
「いかな吾等が探索でも、斯様に早い発見には、至らぬと思うが、いかが?」
「能力と、運のなせる賜物であろうか。」
「しかし、姫を諦めきれぬよのぅ。」
「いかにも。しかし、吾等が姫を得たとしても、それは時の運だったのではあるまいか。」
「そうじゃなぁ。車持殿の妻女になられれば、遊びに行った折りにでも、
お顔を拝すことができようし・・・。」
この先は、18歳以下のかたは、父兄同伴で・・・ね。
3人の脳裏には、月の光のように輝く、『かぐや姫』の白い肌と、
車持皇子の姿が、重なって見えていた。
もういいよ。
その3人を押し分けて、血相を変えた匠の一団が、憶良の屋敷に入り込んだ。
「何事ぞ?」
「車持殿が大事なときに、何事か?」
3人は、ただ顔を見合わせるばかりで、匠たちの勢いに押されて、
ことの成り行きを見守った。
「車持の殿は、おわせられるか!?」
「何者か? 儂はここに居る。」
「表にまいれ。出てこなければ、吾等が失礼して、押し入ろうぞ。」
「落ち着け。こちらには姫がおわす。儂が外に出よう。」
「このたびの、許せぬ所行。説明を賜ろう。」
「儂は“不始末”は、身に覚えがない。しかしながら、家人が所行も、責めは儂にある。」
屋内でただならぬ様子に驚いて、様子を窺っていたかぐや姫にも、
皇子らのやりとりは、響くように伝わってきた。
『家人の責めをも、ご自分で負われる潔さ。このお方ならば・・・。』
かぐや姫は、そんなことも、思い始めていた。
だがそこで、続いて発せられた匠たちの言葉は、
『かぐや姫』の傾きかけた『車持皇子への想い』を、完全に冷えさせるものだった。
(この“匠たち”って、どうしてここに登場したわけ?)
(皇子が、“悪運が強い男”じゃなかったってことでしょ)
(裏返せば、『かぐや姫』の運が、勝っていたってぇこと?)
(何にしても、間が悪いと言おうか、まるでドラマのようなタイミングの良さと言おうか・・・)
(ドラマーは、タイミングが大切だから。)
(楽器の演奏じゃないんだから。)
(おじんギャグじゃなくて、楽器《ガキ》ギャグになっちゃったかな?)
(それで、車持皇子の苦労は、どうなるの?)
(どうしようか? ほかの3人も、妄想がふくらんだことだし、“濡れ場”でも設けようか?)
(そんな場合じゃないでしょうよ)
(ふがふが・・・濡れ場が・・・)
(それは、“入れ歯”が外れたの)
ということで、ことの顛末は、次回に・・・。

新説【竹取物語】・・・・・・《8》
どこを取ってみても、完璧な“蓬莱の玉の枝”に違いがない。
『かぐや姫』は、まさか、ひと月あまりの短期間で、在処どころか、
存在の真偽さえも解らない宝物を、探し当てる人がいるとは、予想もしなかった。
二人目の『車持皇子』が、苦労のあとは見せたものの、
こうも簡単に、持ち帰るとは思わずに、次の求婚者に与える課題を、
早くも考えていたのだ。
しかし眼前に、紛う方ない宝物を差し出されては、
『この殿に、嫁がねばなるまい』と、覚悟を決めていた。
そこへ、数人の匠が、踏み込んできたのである。
何事か? と様子を窺っていると、彼らはなにやら、車持皇子に詰め寄っている。
他の者に危害を加える虞はなさそうなので、憶良夫妻と姫は、室内で静かに、
耳をそばだてていた。
「静かに、話し合えぬものか?」
「これが、穏やかに済むまいものかは。」
「お主らの謂わんとすることは、理解しよう。この場は、山之上殿のお屋敷内である。
ご迷惑をおかけしては、申し訳が立たぬ。そこで、穏便に、と申して居る。」
「そちらが、約束を違えるから、吾等がわざわざ、遠路はるばるこうして、
京都までやってきたのではないか。心あらば、吾等が心情も察せられよ。」
「家人が、なにやら、大変な不調法をしでかしたようじゃな。」
「そなたは、“家人”のせいにしやるか?
家人の不始末は、主人の日頃の行いが、手本になるのではあるまいか?」
「いかにも。して、いかな不調法を為したかな?」
「吾等が何者であるかは、解っておいでであろう。ならば、言わずもがな。」
「う~む、正当な責めは受けようほどに、その意味がよくわからぬ。」
「まだそのような!」
車持皇子は、屋敷内で様子を見ているだろう『かぐや姫』たちの手前、
できればうまく、匠たちを、遠ざけようとしたのである。
だがそれが、火に油を注ぐ結果を招いた。
「いや、待たれよ。そのほう等が言わんとするは・・・。」
「どこまでも、のらりくらりと・・・。ええい! 言ってくれようぞ!」
「ま、待て!」
車持皇子が制止する間もなく、匠たちは大音声に皇子の“非”を、あげつらい始めた。
「口止めをしながら、吾等に打たせた“蓬莱の玉の枝”の紛い物は、どこぞにある!?
確かな出来映えに喜ばれたと、噂には伝わって来よったが、その吾等が苦労は、
全く報われぬではないか!」
「他の仕事を投げてまで、京都の高貴なかたのお頼みと言うから、半月以上もかけて、
一振りばかりを、打ち上げたのではないか!」
「その報酬は、決して法外なものではなかったはず! そなたの家人殿も、
納得して吾等が手を、頼ったのではないか!」
「褒美を、まだ取らしてないと申すか? そのようなことが・・・。」
「あるまいことか。」
(なんだか、もっともらしい言葉遣いだけど、昔はこんな言葉で話したの?)
(知るわけ、ないよ)
(無責任)
(だから、最初に断ったじゃないか。“時代考証は無視します”って)
(だけど、京都のお公家さんなんだろう?)
(そうだけど、だからといって、あの時代の京都言葉に、
公家言葉をプラスしたら、どうなると思う?)
(う~ん、まったりと・・・)
(今でさえも、話の展開が“まったり”しているのに、言葉まで“まったり”させたら、
ダレ過ぎちゃって、どうしようもなくなるよ)
(ほんじゃ、このままでいいか・・・)
(良いも悪いも、公家言葉なんて、知らん)
(調べたら、どうなの?)
(やだ)
ということなので、いい加減な言葉遣いは、この後も続きます。
「“蓬莱の玉の枝”にも劣らぬ代物を、と頼んだが、その支払は済ませたはずではないか!」
「猛々しい! 手付けだけで済ませて、『皇子が心待ちであるから』と、残金も払わずに、
持ち去ったまま。」
「そうよ! その後は、なしのつぶてじゃ。」
事態が総て解ったところで、憶良がのそりと、間に割って入った。
「埒があかぬのでは、ありますまいか?」
匠たちとの押し問答で、我を忘れていた車持皇子は、憶良の一言で、我に還った。
つい夢中になって、匠たちと争ってしまったが、総てのいきさつは、憶良に知られてしまった。
勿論、ともに聞いていた『かぐや姫』の知るところになったのも、疑う余地はない。
最早、“蓬莱の玉の枝”の贋作が、どれほどみごとな出来映えでも、
その“捧げ物”には、何の価値もない。
「こうなったは、お主(匠)たちが為したことぞ。残金を払うなどとは、もってのほか。」
「では、いかようになさるか?」
「この“蓬莱の玉の枝”を、持ち帰るがよかろう。お主等が“神”と、奉るがよろしい。」
「な、アホなことが・・・。」
呆然と、あきれ顔を見せる匠たちを残して、皇子は振り返るそぶりも見せずに、
月が白く浮かび上がらせた竹林の道を、足早に立ち去った。
憶良に対してだけ、わずかに恥を忍ぶような、挨拶を交わして・・・。
ことの成り行きを見守っていたのは、かぐや姫だけではなかった。
残りの、3人の求婚者たちも、離れたところから総てを読み取って、
うっそりと、喜びの笑みを見せ合っていた。
「お次は、阿倍の殿でござるな?」
「こうも続いて、不始末を見せつけられると、私がいよいよ心して掛からねばならぬよなぁ。」
「あ、“心して掛かる”は、残る私らに任せて、おまえ様は“ほどほどに”なぁ。」
「先のお二人も、“ほどほどに”と、吾等に送られて、あのようなことになりましたわえ。
ほどほどは、いかんのと違いますかな?」
「何はともかく、さ、さ、早うにお行きなされ。」
残る二人に背中を押されて、阿倍右大臣が、憶良のそばに進み出た。
憶良は、残金を匠たちに支払ってやり、贋作も引き取ってもらう話し合いを、
済ませたところだった。
『やれやれ・・・。』
ふうぅっと、大きく一息ついて、まぁるく輝く月を見上げたところに、
阿倍右大臣が、名乗り出たのである。
「続いておいでで、ございましたか。ご覧の通りで、かくなる仕儀を見て、
姫も心痛めて居るはず。あなたは、姫の落胆を、軽くさせ賜うか?」
「お任せください。」
「姫も、早く済ませたいかと思えばや。お入りなされ。」
(相変わらず、怪しげな言葉やわいなぁ)
(おまえさんこそ、怪しげでおわすのぅ)
(げに怪しきは・・・いよぉお!!)
(見栄まで、きるな! そないなことは、気にせんで行こかぁ・・・ってのに)
(気にせんでも、ええのんか?)
(そこを許してこそ、“新説”(親切)なんじゃないのかい?)
(いよぉ! 待ってました! とびっきりの下手なダジャレ!)
「ありがたき。」
「姫、お次のおかたじゃ。阿倍右大臣でおわす。」
「ああ・・・。」
「初めてお目もじ叶いまする。私は、アホなほどに正直者でありますれば、
先のおふたかたのようなことは、到底できませぬ。
しからば、姫のご落胆も、これまでと思し召せ。」
「嘘の無いのは、救われそう。しかしながら、宝物の探索は、これまた別物。
よろしゅうございましょうや?」
「何なりと。」
「先のおふたかたは、“御仏の御石の鉢”も“蓬莱の玉の枝”も、
私の望みは叶えられませんでした。右大臣殿には、また別の物を。」
少しの間、客間は緊張に包まれたように、静まりかえった。
窓から射し込む月明かりが、炎の明かりを包むように、
明るさを増したように、感じられた。
やがて、『かぐや姫』の口が開かれた。
「私を娶りたいとご希望なさる殿方は、あと如何ほどおわしましや?」
「は?」
すぐにも“課題”を告げられると思っていた右大臣は、意気込みを逸らされた面持ちで、
かぐや姫を見つめた。
「いつまでも、このような状態が続いても、限りないこと。
この先を知りたいと、思いまする。」
「なるほど、ごもっとも。しからば、お答え仕る。残るはおふたかた。」
「ありがたき・・・。」
「何の。姫のお望みは、私が叶えますれば、あとのおふたりのことは、
お気に掛けまするな。」
「ごめん遊ばせ。では、右大臣殿への、私の願いをば・・・。」
「・・・・・。」
「唐のお国には、“火鼠の皮衣”なるものが、あるそうな。それを是非、目にしたいと・・・。」
「唐の国でおじゃりまするかぇ?」
(だからぁ、言葉遣いで、無理すんなって)
(ちょっと、遊んでみた)
(解りやすいほうがいい)
(ラジャ)
「そのように伝え聞いておりますが、殿が運のよいお方ならば、
そのようなものが大和国に、来ているのかも知れません。」
「そうであれば、ラッキーなのですが。」
(くだけすぎ!)
(かも。反省!)
(猿でもできる、“反省”か?)
(“どうせい”っちゅうんじゃい?)
(また、ダジャレか? そのために、割り込んだのか?)
(んだ。おとなしく去るか・・・)
「期限は、次の満月の夜までです。よろしいでしょうね。」
「努めてみましょう。」
一日早いスタートになった右大臣は、ちょっとだけ得をした気分で、
屋敷に駆け戻り、家人を集めて、てきぱきと要領を手配した。
勿論、偽物を作らせるつもりはなく、山奥の古寺から、いかがわしい代物を、
取り寄せるつもりもなかった。
ただ、“火鼠の皮衣”を求めて、大和国の隅々まで、探索方の依頼は、
行き渡らせた。
“火鼠”は寝て待て、とばかりに、報奨金につられて、好ましい情報が寄せられるのを、
ひたすら、待ち続けた。
唐の国まで探しに行っても、往復の行程だけで、期限の日が来てしまう。
己が探し回ったのでは、非効率である。報奨金をたっぷりと付けて、
“火鼠の皮衣”を持つ物が、名乗り出てくれるのを待つほうが、
確率が高い。体力を温存したほうが、かぐや姫との生活が、
当初から順調に行く。右大臣は、そう考えたのである。
「俺って、頭いいかも・・・。」
果報を、屋敷で寝て待っているところへ、
諸国を渡り歩いているという、とある商人が、訪ねてきた。
「私が有り金をはたいて手に入れた、曰く因縁のある奇妙な物が、
殿がご所望の、逸品では無かろうかと、名乗り出ました。」
家人から、急ぎ、知らせを受けた右大臣は、
「曰く因縁とな? その者を、早うこれへ呼び寄せよ。」
昼寝から飛び起きて、縁先へ出て、旅の商人が現れるのを待った。
「私がどのようないきさつで、この品を手に入れたのか、まずそこからお話を・・・。」
「待て待て、まずそれを見てからの話に、してたもれ。」
商人は、苦労話を先に済ませたい様子を見せたが、高額報奨金を考えて、
不承不承、右大臣の申し出を受け入れた。
独りでに零れる笑みを、必死に噛み殺しながら、旅の商人は、
汚れた革袋から、さらに薄汚れた“火鼠の皮衣”を、引き出した。
(今度は、本物みたいだね)
(でもなぁ、高く売れる“宝物”を、そんなにいい加減に扱うものかなぁ)
(さ、どうなんだろうねぇ)
(知っているなら、さっさと教えてよ)
(お楽しみは、また今度)
(また、話の引き延ばし作戦?)
(次は、二人いっぺんに済ませるから、落ち着け)
(どこが?)
(“オチ”つかない? ついてないよね)

新説【竹取物語】・・・・・・《9》
旅の商人が、右大臣が探している『宝物』とやらが、
自分の持つ袋の中にありそうなことに気づいて、嬉しさを抑えることができなかった。
それが“本物か偽物か?”なんていうことは、この際、どうでも良いことだった。
右大臣が高額で買い上げてくれさえすれば、放浪生活に、終止符を打てるのである。
真偽のほどは、右大臣の判断に任せればいい。
そう思って届け出たのだが、意外にも簡単に、
右大臣が自ら会ってくれることになった。
「“火鼠の皮衣”とは、どのような物か? ささ、直ぐに見せてくりゃれ。」
「そのように急かされては・・・。取り出すときに、破れてもいけませぬでな。」
「それほどに“柔”なもので、おじゃるかや。うむむ・・・。」
「そげなことは、まずは無かろうと、ご安心召されるがよろしかろうと存じまするが、
万一にも破れては、価値が疑われまする。」
「これか・・・。これが彼の“火鼠の皮衣”・・・と。」
阿倍右大臣は、初めて見る伝説の宝物を前にして、そっと“眉に唾”を付けながらも、
本物であることを願いながら、“それなり”の報賞を約して、
商人を手厚くもてなした。
商人は、旅先はおろか、生まれてこの方、食したことがないほどのご馳走と、
滑り落ちそうに滑らかな絹の布団に包まれて、一夜を明かした。
“火鼠の皮衣”とは、何あろう、買い取る折りに、
「これは“土龍”(もぐら)の皮で作られた衣服で、寒さにはめっぽう強い。
しかも、雨水にも丈夫ときている。買い得ぞよ。」
「うまく捌ければ、それなりに売れよう。貴重な物には、違いないしのぅ。」
ということで、そこそこの金額で買い取った、曰くがあったのである。
それが、ひょんなことで、幻の“火鼠の皮衣”に、大化けしようとしている。
あとは、約束の金を受け取ったら、さっさと屋敷をお暇するだけである。
そのタイミングを逸すると、褒美を手に入れるどころか、
詐欺商人として、処罰される畏れもある。
成り行き次第では、一夜のもてなしを得ただけで良しとして、
姿をくらます覚悟もしていた。
「今宵だけでも、儲け物じゃて。とりあえずは、何も考えずに、寝るべし。」
● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★
勿体を付けて、期限一杯になってから『憶良』の屋敷へ『かぐや姫』を訪ねるほうが、
“それらしく”思われそうだったが、右大臣には、それだけの心の余裕がなかった。
日が昇るのを待ちかねるように、薄汚れた“火鼠の皮衣”を絹の風呂敷に押し包み、
供も連れずに、屋敷を飛び出した。
左右の田畑にはレンゲソウが咲き乱れ、西の空には、沈みきれない月が、
白く浮かんでいた。右大臣の目には、その景色も、うつろにしか映っていなかった。
ただ一刻も早く、姫に会いたい。唐の国にあるといわれる宝物が、
思いも掛けない幸運で、手元に転げ込んできた。
あとはこれが、本物であることを、願うばかりである。
気持ちは、その一点に集中されていたのである。
供を連れずに飛び出したのは、いつもの右大臣の行動としては、珍しいことだった。
『偽物だったときの、落胆した顔を、供の者に見られたくない。』
その思いが、頭の隅に、不透明な影を落としていたに違いない。
『かぐや姫』に求婚する予定の、残りの2名も、つかず離れずに、
右大臣の後を追っていた。
期限よりも数日も早くに、十三夜の、
沈みきらない月を見ながら、『憶良屋敷』を訪ねるとは、二人の予想しないことだった。
だが昨夜、右大臣の屋敷に『旅の商人』が入ったままで、丁重なる接待を受けて、
宿したことを、伝え聞いていた。
「さては、姫の課題の品を、入手なさったか?」
気が気でない二人は、互いに連絡を取り合い、右大臣屋敷に見張りを付けて置いた。
その見張りから、『早朝に右大臣が屋敷を出られた』と、知らせが入った。
そこで、慌てて駆けつけて、右大臣の後を追っていたのである。
右大臣は、後を振り返る余裕もなく、まっすぐに『憶良屋敷』を、目指していた。
憶良屋敷の表では、召使いが、玄関先を清めていた。
貧しさを嘆いていた憶良だったが、かぐや姫への贈り物が後を絶たず、
結構裕福な暮らしができるようになっていた。
貢ぎ物が屋敷に収まりきれなくなると、専用の倉を建てて、その見張りを兼ねた
召使いも、数人を雇えるようになっていたのである。
「憶良殿は、ご在宅でしょうや?」
「お早うに、何事かおわしますや。床を払っておいでと思いまするが、
朝餉は未だ、と想いまするが・・・。」
「左様か。さすれば、お待ち致そうか。私の訪問だけでも、お伝え願いまえか。」
「しばし、お待ちあられませ。」
召使いが屋敷内に姿を消すと、右大臣は自分も朝食前だったことを、
思い出した。
「主人が、『もしもよろしければ、右大臣様にも、朝餉を』と仰せられておいでですが。」
「いや、私はご覧に入れたい品を持参したまでで、ご相伴に与るわけにはいきませぬ。」
「お口には合いませぬかと存じますが、主人の『是非に』との言付けもありますれば。」
「私の至らなさを、お心にお留めくださるご配慮、頂戴いたしましょう。」
「お入りくださいませ。」
「甘えさせて戴こうか。」
「お早うに、ご免くださいますよう・・・。」
「ご訪問、嬉しく存じます。粗末な朝餉なれば、
お迎えするにはお恥ずかしい限りではありますが、僅かばかりの心を、と。」
「時をわきまえずに訪ねたご無礼を、お赦しください。」
そう言いながらも、右大臣の視線は、落ち着き無く邸内を漂っていた。
その気持ちを察したように、憶良は、
「まだ約束の日まで、幾日もございますれば、
右大臣殿が斯様に早く、おいでくださるとは、思いの外にございます。
さすれば姫は、まだゆるりと書物などを、耽って居ることでしょう。」
と、『かぐや姫』が姿を見せない理由を、伝えた。
「それは残念。一時も早く、姫にも“火鼠の皮衣”をお目に掛けたい。」
「殿がこと。間違いはございませんでしょうが、食事を済ませてからになさっては、
いかがでしょう。」
「姫は・・・。」
憶良の言葉が理解できない様子で、右大臣は、『かぐや姫』の姿を求めた。
とても朝餉のご相伴などと、悠長なことに時間を費やす場合ではない、
と判断した憶良は、右大臣に“ある提案”を申し出た。
「前のおふたかたは、“紛い物”をお持ちなさり、姫によって見破られ申した。
さあらば、最早、姫にお顔を会わすことは、叶いませぬ。阿倍の殿は、
ご自身の手によって、かくなる品を作らせ賜うたのではありません。
そこで、私が“真偽”を見定めれば、万にひとつ、偽物であっても、それは、
持ち込んだ商人の罪であって、阿倍の殿には、非がございません。」
「重ね重ねのご配慮、ありがたくお受けいたしましょう。」
「では、その“火鼠の皮衣”を拝見いたしましょう。」
「これに。」
「これはまた・・・。」
憶良も、衣類の汚さに眉をしかめながら、包みから取り出された“宝物”を、
摘み上げた。
「言い伝えによれば、“火鼠の皮衣”なるは、
どのような苛烈な火にも、燃ゆる事なきとぞ云わるる。さて、これは・・・?」
はっと息を飲む右大臣の止めよう間もなく、無造作に“宝物”は、囲炉裏に放り込まれた。
憶良にとっては、朝餉の席に持ち込まれた、薄汚い皮衣など、触りたくもなかった。
だが、右大臣の手前、何もせずに“偽物”と断定することはできない。
そこで、一時も早く手放したいという気持ちが顕れて、皮衣は、囲炉裏に放り込まれたのだ。
皮衣は、炎に耐えるだけの根性もなく、たちまちにして燃え上がり、たちまちにして灰と化した。皮衣が白くなるのに合わせるように、右大臣も姿が小さくなるように、うなだれてしまった。
「や、これは、申し訳ないことをしてしもうた。やはり、朝餉の後にしたほうがよかったか・・・。」
「ご懸念にや及ぶ。斯様な旅商人の胡乱な言葉を、鵜呑みにした私の恥じること。
こたびの“火鼠の皮衣”は、見つけられなかったことに、しては戴けないでしょうか。」
「言うまでもなく。して、朝餉はいかがに?」
「その気分ではありません。早く帰り、彼の商人を、引っ捕らえてくれましょう。」
(ねぇ。皮の服って、そんなに簡単に燃える?)
(古いんだろう)
(俺の革ジャンも、そんな簡単に燃えちゃうのかなぁ)
(普通なら、燃えないと思うけど、何しろ古かったようだから・・・)
(ひどいボロだったんだ)
(あげくに、乾燥していたんだろうね)
(乾【皮】いていたって言うの?)
(そんなつもりじゃなかったんだけど)
(ダジャレを出さないと、落ち着かないんでしょ?)
(そんなつもりじゃ・・・)
右大臣が、商人の始末を考えながら家路を急いでいる時分に、その商人は、
報奨金を受け取るまでの欲を出さずに、僅かばかりの『銀食器』を懐にして、
遙か遠くの山を、越えようとしていた。
(それって、泥棒じゃないの?)
(日本人って、昔からセキュリティ意識が、弱かったんだね)
(油断できないねぇ)
(夜盗も、旅の商人も、いつだって泥棒に早変わりした時代だと思うよ)
右大臣が、商人に騙されたという噂は、都に広まった。しかし、小細工を弄して騙そうと
企んだわけではないと言われて、かろうじて体面は保たれた。
● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★
「吾等にとっては、幸いなことだが、事はうまく運ばぬものよなぁ。」
「・・・でおじゃるよ・・・なぁ。」
順番が巡ってきた、残りの求婚者は、不安を募らせながらも、どうにか自分にもチャンスが残されたことを、そっと喜び合った。
他人の不幸は、密の味?

新説【竹取物語】・・・・・・《10》
次の満月の日に、『かぐや姫』の前に姿を見せたのは、『大伴大納言』である。
『憶良』にとっては、まんざら縁のない名前ではない。
複雑な面持ちで、大納言を迎え入れた。
「父上が、大納言様に懇意にして戴いておわしますることは、承知しております。
然れども、石作の皇子、車持の皇子、そして阿倍の殿と、
何れのおかたにも、宝物を探し求めて戴きました。
やはり大伴様にも、同じように課題を差し上げたいと思います。」
「免除して戴いても、私は一向に構いませぬが。」
「そうは参りませぬ。左様なことでは、後々、非難されましょう。」
「では、どうかお手柔らかに、お願い申す。」
「簡単なところで・・・『龍の首の玉』なるものを、所望いたしましょう。」
『げっ! ちっとも簡単やおまへんやないかぇ。
そないなもの、聞くからに、“げに恐ろしげ”でおじゃりますがな。』
内心で、『厄介な物を』と思いながら、大納言は、虚勢を張った。
「ひと月もの間は、不要に御座そろ。たちまちのうちに、差し出してご覧じように。」
「おお、頼もしや。」
大納言も、帰邸するやいなや、家人たちに『龍の首の玉』探索を、命じた。
「へぇ、へえ。承知仕り申した。旅支度が整い次第に、ゆるりと・・・な。」
「ゆるりとなどと、そないな余裕は有らしめへん。早うに出立せんかな。」
「旅支度が、まだ済んでまへんので・・・。」
「後から追って、届けさせようほどに、早う、早う!」
急き立てられて、家人たちは八方に散っていった。
「おぬしは、『龍の首・・・』何たら言うもんを、本気で探しますんかいな?」
「聞くからに、恐ろしげよのう。ま、湯にでも浸かって、ゆるりと行こかぁ。」
「そら、そうよのう。そら恐ろしい物なんぞ、近寄りたくもない。」
(だ・か・ら・・・怪しげな京言葉もどきは、やめれ!)
(んだな。慣れね事すっと、笑われっかんな)
(普通の言葉だって、充分に笑われてるっちゅうの)
(そうだべねぇ)
家来たちが、探索に散りながら、全く“宝物探し”に本気にならない、と知った大納言は、
業を煮やして、ついには自分で探し出すことにした。
「もう、残りの日にちも多くはない。家人に頼った儂がアホやった。南海の果てに、
“龍の首の玉”はあるというではないか。」
「伝え聞きまするは、そのように。」
「では、船を出せ!」
船を漕ぎ出して、3日もたたずに、大納言は、嵐に見舞われた。
台風ではなかったが、春の嵐は凄まじく、一行の船は次々に破損して、
大納言も這々の体で、大物浦に打ち上げられた。
この浜は、後に源義経一行が都落ちをも、嵐によって阻んでいる。
何という因縁か、人の希望を打ち砕く、浜なのであろうか。
余談はとにかく・・・
大納言一行は、この被害によって探索資金も乏しくなり、むなしく期日が迫るのを、
屋敷で待つだけになってしまった。
期日近くなると、湯治場で元気いっぱいになった家人たちが、三々五々に、帰り始めた。
「あきまへん。幸いなことに・・・なんの、残念なことに『龍』の姿も拝めませんでしたわ。」
「私も、おないです。『龍』が天に昇る姿かと思いきや・・・。」
「温泉から立ち上る“湯気”でっしゃろ?」
「おお、ご同輩!」
『こんな奴らに、頼んだのが間違いだった。
温泉三昧をさせるために、旅費を出してやったようなもんやないかい。』
大納言は、腹立たしさを忘れて、脱力感に襲われていた。
残りの日々を、万に一つの“果報”を待ちながら、過ごすしか方途がなかった。
果報はもたらされないままに、期限の日は、無情に迫っていた。
大納言はついに、期限を待たずにギブアップをした。
『かぐや姫』への求婚者は、最後のひとりを残すだけになった。
石上中納言、その人である。
皇子たちの申し出も断り、大納言の申し出も断って、残ったのが『中納言』なのである。
“おみくじ”のようなもので、この先、出世の楽しみがあるということでは、
『大吉』よりも『中吉』のほうが喜ばれる、ということに、似ているかも知れない。
「“家宝”にできるお宝を探すなんて、“果報”は寝て待て、ということでおじゃるかな?」
(あらら、中納言にまで、ダジャレを言わせちゃって)
(彼も、1ヶ月じゃ、“宝物”は見つけられないだろうね)
(ダメなの?)
(お名前が『石上』なんだもの。3年はかかるんじゃないの?)
(『石上』にも3年・・・)
(お後がよろしいようで)
よろしくない。。。
『憶良』の屋敷を訪ねた中納言に、『かぐや姫』が、言い渡した。
「“燕の子安貝”は、お家の繁栄を願う物。それを是非にも。」
「嬉しいお言葉。この中納言の、命に替えても。」
暗示的な言葉を言い置いて、中納言は、憶良邸をあとにした。
中納言の耳には、澄んだ鈴の音のような『かぐや姫』の声が、いつまでも転がっていた。
「姫が、満月の日を期限に選ぶ理由が、ようやく解ったような気がする。
あの眼差しには、“満月の輝き”が、確かに住み着いておわす。」
中納言は、ぼそっと、つぶやいた。
ところで、『燕の子安貝』って、そんなに貴重品なの?
うちにも、『子安貝』くらいならあるんだけど、“燕の”の意味が、よくわからない?
その辺のことは、次回にでも・・・。
私も、よく解っていないんだけど。

黄金に輝く小鉢を見つめる『かぐや姫』の横で、『石作皇子』は緊張の面持ちで、
かしこまっていた。
身分の違いを忘れて、姫の言葉を、固唾を飲んで待っていたのである。
だが、なかなか彼女の口は、開かれなかった。
眼前に置かれた鉢を、ただ見つめるだけで、手に取ろうともしない。
皇子は、その緊張に押しつぶされまいと、左右の肩を上下させて、
小さく咳払いをした。
その動きに誘われるように、ようやく、姫から問いかけの言葉が、投げかけられた。
「よくぞ、このようなものを、お手に入れあそばされましたなぁ。
ご苦労は、いかばかりかと、畏れ入りまする。」
ふと、皇子の頬がゆるんだ。
そのときから、緊張から解き放たれたように、苦労話が、堰を切って流れ始めた。
野山に分け入り、わずかな望みにも縋るように、
賊が跋扈する山中の荒れ寺をも訪ねたこと。
海を渡り、見知らぬ島の、言葉も通じぬ土地を訪ねたことなどなどと・・・。
ひと月あまりの出来事が、止めどなく語られて、時間の過ぎるのも忘れそうな、
長い話になりそうだった。
屋敷の外では、静まりかえった中の様子を、身動きも忘れて、4つの男たちの影が、
窺っていた。
早くも、『石作皇子』が『かぐや姫』の難題を、クリアしてしまったのではないかと、
気が気ではなかった。
陽は竹林の陰に隠れて、代わって姿を現した丸い月が、徐々に輝きを増しつつあった。
止めどなく続く『石作皇子』の言葉に、『かぐや姫』の澄んだ声が、重なった。
「お疲れ様でございました。今宵は、お帰りになりまして、
どうぞごゆるりとお休みなさいませ。」
皇子はその言葉に、不満を伝えるように、
「なぜに? 私が持ち帰った“鉢”に、何かご不審でもありや?」
と、わずかに気色ばんだ声を返した。
「“御仏の御石の鉢”というは、釈迦牟尼仏が、お持ちあそばされたという、
尊いお宝でしょう。釈尊のお宝が、なぜにこのような輝きなのでしょう?」
「それは、山寺の僧が持つうちに、輝きが失せたかと・・・。」
「“鉢”の謂われは、ご承知あそばしますな?」
「もちろん」
「私が手に取ってみても、よろしいものでしょうか?」
「それには及びませぬ。一刻も早くお目に掛けたいと、手入れもそこそこに運びましたので、
お手を汚してはいけません。私が持ってご覧に入れましょうぞ。」
『かぐや姫』に直接持たれたのでは、その鉢の真贋がたちまちにして見抜かれそうで、
皇子は、狼狽した。
姫の眼前に押し出してあった“鉢”を、慌てて持ち上げて、
姫のそばに寄れる絶好のチャンスとばかりに、にじり寄ろうとした。
そのわずかな気の弛みが、皇子の大失態になった。
宝物の“鉢”を、取り落としてしまったのである。
床に転がり落ちた“鉢”には、何事もなかったように見えた。
しかし、弾みというものは、恐ろしい。
『かぐや姫』の前に、改めて差し出された“鉢”には、
かすかな“金箔の欠け跡”ができていたのである。
「これが、まさに“御仏の御石の鉢”と申されるのでしょうか?
先ほど、殿は、謂われはご存じとおっしゃいましたが・・・。」
絶対に欠けることがないはずの“鉢”が、簡単に欠けてしまったのだ。
「あの山寺が、私を謀って・・・。」
そうつぶやくと、皇子は目も上げられずに、そそくさと鉢を抱えて、部屋を飛び出した。
(おいおい、偽物だったんかい?)
(そうみたいだね)
(よくまあ、いわば“結納の品”のようなものだろうに、偽物なんかを持ち込んで)
(皇子本人は、承知していたようだね)
(ばれないと思ったのかねぇ)
(ばれたあとは、潔く身を引いたんだから、そこは認めてあげたらどう?)
(ばれなければ、嫁にできたっちゅうことか?)
(『かぐや姫』にとっては、最初の男がこの調子では、幻滅だったろうね)
(でも、悪いことはできないよなぁ。うっかりミスで、企みがバレちゃって)
(不運だったんだろうな)
(そんなものなの?)
(ここで幸運なやつなら、偽物を掴ませたままで、一生騙し続けることがある)
(世の中なんて、そんなものさ)
(不運=ふうん=そうなの?)
(軽~くダジャレが出たところで・・・)
宝物の(はずだった)“鉢”を抱えて飛び出した皇子を見た4人は、
そのただならぬ気配で、ほぼ状況を察知した。
皇子は“宝物の鉢”を、無造作に竹林に投げやると、4人から顔を背けて、
その場を立ち去った。
後を振り返ることもなく、悄然とした後ろ姿には、誰も声を掛けることができなかった。
皇子の背を、月明かりが、冷たく照らしている。
竹林に投げられた“宝物”を、確かめようとする男も、誰ひとりとしていなかった。
確認することさえ、“むごい仕打ち”に思えたのである。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
一方では、ほかの4人にも、『かぐや姫』にプロポーズできるチャンスが、
残されていることをも、意味した。
これから与えられる『課題』の厳しさを思うと、身が引き締まる思いがするが、
反面で、嬉しさを隠しきれない4人でもあった。
「次は、『車持皇子』(藤原不比等)殿が、ご苦労をなさるのじゃな。」
「気後れするではないか。景気よく送り込んでくれぬか。」
「我らも後に控えておる。ほどほどに・・・な。」
「ほどほどに、では、“姫”を娶れぬではないか。」
「ささ、お行きなされ。」
妙な“景気づけの言葉”を頂戴して、『車持皇子』が『憶良』の屋敷に姿を消した。
「車持殿は、首尾よう成し遂げようか。」
「我らにも、機会がこようかと思うと、成功を手放しで祈ることもできぬ。」
「複雑な心地よなぁ。」
『車持皇子』の首尾が判明するのは、さらにひと月は要するだろう。
3人の候補者たちは、『車持皇子』が現れる頃に、またこの竹林で合うことを約して、
思い思いに散っていった。
★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ● ★ ●
憶良の屋敷内では、息つく間もなく現れた男を迎え入れて、
憶良とかぐや姫が、挨拶を交わしていた。
姫には疲れの色があったが、“次の満月の日”までの安息の時を得るために、
新たな望みを、車持皇子に、告げようとしていた。
「“蓬莱の玉の枝”なるものが、この世のどこぞにあるそうな。
その珍しいものをば、ひとめ見たいものです。」
「承知。お任せを。」
「流石は車持殿であらせられる。“蓬莱の玉の枝”をご存じとは・・・。」
「早速に、見つけ出してご覧に入れましょう。」
車持皇子は、少しでも長く『かぐや姫』のそばにいたかったが、
それよりも“課題”の探索時間を失うことのほうが気がかりで、そそくさと暇を告げて、
自分の屋敷にとって返した。
車持皇子は、“蓬莱の玉の枝”なるものがどのようなものなのか、実体を知らなかった。
まずそれを知ることから始めなければ、探索もできない。
屋敷に帰れば、物知りの誰かが、教えてくれるだろう。
跳ぶように帰宅した車持皇子は、屋敷に入るのももどかしく、
声を張って、家人に問いかけた。
「誰か! “蓬莱の玉の枝”が如何なるものか、存知おるか!?」
「それなる“宝物”は・・・。」
たちまちに、その答えが得られた。
(へえ。そんなに早く、わかるものなの?)
(かぐや姫が知っているんだから、
博識者が多い貴族屋敷なら、誰かは知っているだろうよ)
(誰も知らなければ、知人に電話で・・・)
(電話なんて、この時代にあるものか)
(一刻も早く探したいんだから、手段を選ばないだろうと思ってさ)
(無いものは、使えないだろうよ)
(早く探したいだろうから“電話急げ”って)
(ダジャレなら、何でも良いっていう感じだね。“善は急げ”と“電話急げ”って?)
(ごめん。ところで、18禁の文章は、いつ出るの?)
(忘れてた。堅いこと言わないで、24禁{24金}で許して。)
(万年筆の、ペン先みたい)
(万年筆自体を、今はほとんど使わないって)
(話が逸れっ放し)
(どうでもいいけど、この『竹取物語』って、間延びしていない?)
(中身を、もっと省略した方がいい?)

“蓬莱の玉の枝”なるものは、何ぞや?
この答えは、屋敷の識者によって、
『東の海のかなたに、蓬莱という山があり、そこにあることが、確認された』という情報が、
車持皇子の元に寄せられた。
「その“蓬莱”とは、東のどこにあるというのか?」
「ひと月ほど、大船を走らせると、行くことができることがある、と古来から伝わる、
“神仙峡”だそうでございます。」
「ひと月掛けても、その仙郷にたどり着けるという、確たる見通しはあるのか?」
「そこはそれ、いかんせん“仙郷”ございますれば・・・。」
「では、万が一にも見つけることができても、行きにひと月、帰りにひと月では、
とうてい期限には、間に合わぬではないか。」
「左様にございます。」
「吾に与えられた、姫の課題は、ひと月のうちに、“蓬莱の玉の枝”を、
手に入れてご覧に入れることである。これでは当初より、諦めよと言うことではないか?」
「左様にございまする。」
「おまえは、己が娶る姫ではないから、そのように気楽なことを言っておられる。
もそっと、吾の身に置き換えて熟慮せよ。」
「はぁ・・・。」
(どだい無理な注文だよね)
(家来も、答えに窮するだろうねぇ)
(思っていることを、はっきり言うこともできないだろうし)
(どうしてさ?)
(“絶対に無理”な課題を与えたと言うことは、探す前から“断られた”ということだもの)
(そうか。直接言うのは、可哀想だね)
(だろう?)
「その“蓬莱の玉の枝”が、中国の仙郷にではなく、大和国の“仙郷”にあれば、いかが?」
「おう! そのほう、佳きことに気づくものよ。」
「では、早速に・・・。」
「くれぐれも、佳きに計らえよ。」
「承知仕りました。」
(意味が、解らないんだけど)
(そこは、主従ならではの、ツーカーの会話だからねぇ)
(で、どんな意味なの?)
(あるとも、無いとも言える“宝物”を、いつまで探しても埒があかないでしょう)
(そうだけど・・・)
(誰も見たことがない宝物で、しかもそれがどんなものか、よく知られている)
(ふんふん・・・)
(それなら、作っちまえば、てっとり早いじゃないか?)
(そういうことか)
(あからさまには言えないから、“腕の良い工人を捜せ”と、暗に匂わせたわけだ)
(きったねぇ!)
(宝物も、伝説も、こうして作られる・・・)
(“草薙の剣”も?)
(専門家じゃないから、そんなことは知らん)
車持皇子は、表向きは、“仙郷”を探して、都を旅立った。
『かぐや姫』には、その後の皇子の行方を、それとなく伝えて、
苦労の様子を知らしめた。
家来のものは、皇子が向かった方とは反対に位置する、
かねてから名を伝え聞いていた“鍛冶匠”を訪ねて、
「金に糸目はつけぬ。いかようにしても、“絶対に欠けることのない玉の樹”を打ってくれ。」
と依頼した。
鍛冶匠は、ほかの注文を総て断り、この特注品に、全精力を傾けた。
とてつもない金額を、払ってくれるというのだから、これを受けない法はない。
朝廷に伝わると言われる、伝説の剣“草薙”にも勝るほどの、
素晴らしい出来映えの品が、ほぼひと月後に、皇子の元に届けられた。
人里離れた仙郷の隠れ湯で、ゆったりとくつろいで知らせを待っていた皇子は、
その“蓬莱の玉の枝”を受け取ると、山を下った。
人里で馬を調達すると、一路、都への道を、ひた走らせた。
(ねぇ。。。)
(今度は、何よ)
(本物の話では、“蓬莱の玉の枝”って、
匠が作るのに3年も掛けたっていうことに、なっていなかった?)
(どうして、そんなに細かいことに、こだわるの?)
(3年と、ひと月とじゃぁ、差がありすぎるから・・・)
(3年なんて、待てると思うの?)
(原作が・・・)
(原作通りに進めたら、『かぐや姫』が、お婆さんになっちゃうでしょ)
(『かぐや姫』って、歳をとるの?)
(歳をとらなかったら、“お化け”でしょ)
(じゃぁ、『ひと月』で妥協しとく)
(ありがと)
調達した馬は、尻を叩けど、走らない。
時々は、機嫌を損ねて、進まなくなってしまうこともある。
皇子は、そんな馬を背負ったり、鼻先に人参をぶら下げたりしながら、
都への道を、さらに急がせた。
「馬を背負うなんて、これじゃ、借り受けずに自分で走ったほうが、速いじゃないか」
『だって、オラァ“農耕馬”だもの。走り方なんて、忘れてらぁい。』
そんな状態が続いて、へとへとに疲れた皇子だったが、
かぐや姫が指定した期日よりも、1日だけ早く、都に帰り着いた。
その『馬を背負う』苦労が、都の人々には、
いかにも“宝探しで疲れ果てた”皇子の姿と、捉えられた。
何が幸いするか、わからない。
そのままの姿で、車持皇子は憶良の屋敷を訪ねて、
『かぐや姫』への面会を求めた。
「おうおう、そのお姿は。さぞやご苦労をなさったことと、察しあげまする。」
「ありがたきお言葉。」
「姫を、これへ呼びましょう。」
「お頼み申し上げます。」
『かぐや姫』の前に、見事な“蓬莱の玉の枝”が捧げられて、
眼前に置かれた。
それを手にした『かぐや姫』は、前回の『石作皇子』の一件があり、
一見みごとに見える、その“蓬莱の玉の枝”を、しげしげと、
時のたつのも忘れて、眺め続けた。
車持皇子は、石作皇子と違い、“蓬莱の玉の枝”の出来映えに自信があり、
姫が眺めるに任せていた。
苦労話も、述べることはなかった。
家人がそれとなく、皇子の苦労を、かぐや姫に伝えていることを知っているので、
屋上屋を重ねる愚を、避けたのである。
それに加えて、皇子の現在の姿を見れば、その苦労は、言わずもがなのこととして、
存分に、姫には伝わっているはずである。
『これというも、あの“役立たずの農耕馬”の、怪我の功名よなぁ。』
皇子は、ひとり、ほくそ笑んだ。
宝物の“蓬莱の玉の枝”にしても、尋常な叩き具合では、
間違っても、傷つくような、ヤワな代物ではない。
『これで『かぐや姫』は、私のものに決まりだな。』
車持皇子は、そう確信した。
憶良の屋敷を、外で窺っていた残りの3人は、気が気ではなかった。
皇子の苦労話は、都に知れ渡り、
『今度こそは、皇子のお手柄よ。』
と、評判になっていたからである。
“蓬莱の玉の枝”さえも、さも誰かがそれを見たかのように、
『今度という今度は、本物に間違いなかろう。みごとな代物であった。』
と、3人の耳にも、入っていたのである。
「車持殿は、家人の働きも、なかなかのものよなぁ。」
「うーむ、籤運の悪さが、我らの敗因になったかも知れぬ。」
「いかな吾等が探索でも、斯様に早い発見には、至らぬと思うが、いかが?」
「能力と、運のなせる賜物であろうか。」
「しかし、姫を諦めきれぬよのぅ。」
「いかにも。しかし、吾等が姫を得たとしても、それは時の運だったのではあるまいか。」
「そうじゃなぁ。車持殿の妻女になられれば、遊びに行った折りにでも、
お顔を拝すことができようし・・・。」
この先は、18歳以下のかたは、父兄同伴で・・・ね。
3人の脳裏には、月の光のように輝く、『かぐや姫』の白い肌と、
車持皇子の姿が、重なって見えていた。
もういいよ。
その3人を押し分けて、血相を変えた匠の一団が、憶良の屋敷に入り込んだ。
「何事ぞ?」
「車持殿が大事なときに、何事か?」
3人は、ただ顔を見合わせるばかりで、匠たちの勢いに押されて、
ことの成り行きを見守った。
「車持の殿は、おわせられるか!?」
「何者か? 儂はここに居る。」
「表にまいれ。出てこなければ、吾等が失礼して、押し入ろうぞ。」
「落ち着け。こちらには姫がおわす。儂が外に出よう。」
「このたびの、許せぬ所行。説明を賜ろう。」
「儂は“不始末”は、身に覚えがない。しかしながら、家人が所行も、責めは儂にある。」
屋内でただならぬ様子に驚いて、様子を窺っていたかぐや姫にも、
皇子らのやりとりは、響くように伝わってきた。
『家人の責めをも、ご自分で負われる潔さ。このお方ならば・・・。』
かぐや姫は、そんなことも、思い始めていた。
だがそこで、続いて発せられた匠たちの言葉は、
『かぐや姫』の傾きかけた『車持皇子への想い』を、完全に冷えさせるものだった。
(この“匠たち”って、どうしてここに登場したわけ?)
(皇子が、“悪運が強い男”じゃなかったってことでしょ)
(裏返せば、『かぐや姫』の運が、勝っていたってぇこと?)
(何にしても、間が悪いと言おうか、まるでドラマのようなタイミングの良さと言おうか・・・)
(ドラマーは、タイミングが大切だから。)
(楽器の演奏じゃないんだから。)
(おじんギャグじゃなくて、楽器《ガキ》ギャグになっちゃったかな?)
(それで、車持皇子の苦労は、どうなるの?)
(どうしようか? ほかの3人も、妄想がふくらんだことだし、“濡れ場”でも設けようか?)
(そんな場合じゃないでしょうよ)
(ふがふが・・・濡れ場が・・・)
(それは、“入れ歯”が外れたの)
ということで、ことの顛末は、次回に・・・。

どこを取ってみても、完璧な“蓬莱の玉の枝”に違いがない。
『かぐや姫』は、まさか、ひと月あまりの短期間で、在処どころか、
存在の真偽さえも解らない宝物を、探し当てる人がいるとは、予想もしなかった。
二人目の『車持皇子』が、苦労のあとは見せたものの、
こうも簡単に、持ち帰るとは思わずに、次の求婚者に与える課題を、
早くも考えていたのだ。
しかし眼前に、紛う方ない宝物を差し出されては、
『この殿に、嫁がねばなるまい』と、覚悟を決めていた。
そこへ、数人の匠が、踏み込んできたのである。
何事か? と様子を窺っていると、彼らはなにやら、車持皇子に詰め寄っている。
他の者に危害を加える虞はなさそうなので、憶良夫妻と姫は、室内で静かに、
耳をそばだてていた。
「静かに、話し合えぬものか?」
「これが、穏やかに済むまいものかは。」
「お主らの謂わんとすることは、理解しよう。この場は、山之上殿のお屋敷内である。
ご迷惑をおかけしては、申し訳が立たぬ。そこで、穏便に、と申して居る。」
「そちらが、約束を違えるから、吾等がわざわざ、遠路はるばるこうして、
京都までやってきたのではないか。心あらば、吾等が心情も察せられよ。」
「家人が、なにやら、大変な不調法をしでかしたようじゃな。」
「そなたは、“家人”のせいにしやるか?
家人の不始末は、主人の日頃の行いが、手本になるのではあるまいか?」
「いかにも。して、いかな不調法を為したかな?」
「吾等が何者であるかは、解っておいでであろう。ならば、言わずもがな。」
「う~む、正当な責めは受けようほどに、その意味がよくわからぬ。」
「まだそのような!」
車持皇子は、屋敷内で様子を見ているだろう『かぐや姫』たちの手前、
できればうまく、匠たちを、遠ざけようとしたのである。
だがそれが、火に油を注ぐ結果を招いた。
「いや、待たれよ。そのほう等が言わんとするは・・・。」
「どこまでも、のらりくらりと・・・。ええい! 言ってくれようぞ!」
「ま、待て!」
車持皇子が制止する間もなく、匠たちは大音声に皇子の“非”を、あげつらい始めた。
「口止めをしながら、吾等に打たせた“蓬莱の玉の枝”の紛い物は、どこぞにある!?
確かな出来映えに喜ばれたと、噂には伝わって来よったが、その吾等が苦労は、
全く報われぬではないか!」
「他の仕事を投げてまで、京都の高貴なかたのお頼みと言うから、半月以上もかけて、
一振りばかりを、打ち上げたのではないか!」
「その報酬は、決して法外なものではなかったはず! そなたの家人殿も、
納得して吾等が手を、頼ったのではないか!」
「褒美を、まだ取らしてないと申すか? そのようなことが・・・。」
「あるまいことか。」
(なんだか、もっともらしい言葉遣いだけど、昔はこんな言葉で話したの?)
(知るわけ、ないよ)
(無責任)
(だから、最初に断ったじゃないか。“時代考証は無視します”って)
(だけど、京都のお公家さんなんだろう?)
(そうだけど、だからといって、あの時代の京都言葉に、
公家言葉をプラスしたら、どうなると思う?)
(う~ん、まったりと・・・)
(今でさえも、話の展開が“まったり”しているのに、言葉まで“まったり”させたら、
ダレ過ぎちゃって、どうしようもなくなるよ)
(ほんじゃ、このままでいいか・・・)
(良いも悪いも、公家言葉なんて、知らん)
(調べたら、どうなの?)
(やだ)
ということなので、いい加減な言葉遣いは、この後も続きます。
「“蓬莱の玉の枝”にも劣らぬ代物を、と頼んだが、その支払は済ませたはずではないか!」
「猛々しい! 手付けだけで済ませて、『皇子が心待ちであるから』と、残金も払わずに、
持ち去ったまま。」
「そうよ! その後は、なしのつぶてじゃ。」
事態が総て解ったところで、憶良がのそりと、間に割って入った。
「埒があかぬのでは、ありますまいか?」
匠たちとの押し問答で、我を忘れていた車持皇子は、憶良の一言で、我に還った。
つい夢中になって、匠たちと争ってしまったが、総てのいきさつは、憶良に知られてしまった。
勿論、ともに聞いていた『かぐや姫』の知るところになったのも、疑う余地はない。
最早、“蓬莱の玉の枝”の贋作が、どれほどみごとな出来映えでも、
その“捧げ物”には、何の価値もない。
「こうなったは、お主(匠)たちが為したことぞ。残金を払うなどとは、もってのほか。」
「では、いかようになさるか?」
「この“蓬莱の玉の枝”を、持ち帰るがよかろう。お主等が“神”と、奉るがよろしい。」
「な、アホなことが・・・。」
呆然と、あきれ顔を見せる匠たちを残して、皇子は振り返るそぶりも見せずに、
月が白く浮かび上がらせた竹林の道を、足早に立ち去った。
憶良に対してだけ、わずかに恥を忍ぶような、挨拶を交わして・・・。
ことの成り行きを見守っていたのは、かぐや姫だけではなかった。
残りの、3人の求婚者たちも、離れたところから総てを読み取って、
うっそりと、喜びの笑みを見せ合っていた。
「お次は、阿倍の殿でござるな?」
「こうも続いて、不始末を見せつけられると、私がいよいよ心して掛からねばならぬよなぁ。」
「あ、“心して掛かる”は、残る私らに任せて、おまえ様は“ほどほどに”なぁ。」
「先のお二人も、“ほどほどに”と、吾等に送られて、あのようなことになりましたわえ。
ほどほどは、いかんのと違いますかな?」
「何はともかく、さ、さ、早うにお行きなされ。」
残る二人に背中を押されて、阿倍右大臣が、憶良のそばに進み出た。
憶良は、残金を匠たちに支払ってやり、贋作も引き取ってもらう話し合いを、
済ませたところだった。
『やれやれ・・・。』
ふうぅっと、大きく一息ついて、まぁるく輝く月を見上げたところに、
阿倍右大臣が、名乗り出たのである。
「続いておいでで、ございましたか。ご覧の通りで、かくなる仕儀を見て、
姫も心痛めて居るはず。あなたは、姫の落胆を、軽くさせ賜うか?」
「お任せください。」
「姫も、早く済ませたいかと思えばや。お入りなされ。」
(相変わらず、怪しげな言葉やわいなぁ)
(おまえさんこそ、怪しげでおわすのぅ)
(げに怪しきは・・・いよぉお!!)
(見栄まで、きるな! そないなことは、気にせんで行こかぁ・・・ってのに)
(気にせんでも、ええのんか?)
(そこを許してこそ、“新説”(親切)なんじゃないのかい?)
(いよぉ! 待ってました! とびっきりの下手なダジャレ!)
「ありがたき。」
「姫、お次のおかたじゃ。阿倍右大臣でおわす。」
「ああ・・・。」
「初めてお目もじ叶いまする。私は、アホなほどに正直者でありますれば、
先のおふたかたのようなことは、到底できませぬ。
しからば、姫のご落胆も、これまでと思し召せ。」
「嘘の無いのは、救われそう。しかしながら、宝物の探索は、これまた別物。
よろしゅうございましょうや?」
「何なりと。」
「先のおふたかたは、“御仏の御石の鉢”も“蓬莱の玉の枝”も、
私の望みは叶えられませんでした。右大臣殿には、また別の物を。」
少しの間、客間は緊張に包まれたように、静まりかえった。
窓から射し込む月明かりが、炎の明かりを包むように、
明るさを増したように、感じられた。
やがて、『かぐや姫』の口が開かれた。
「私を娶りたいとご希望なさる殿方は、あと如何ほどおわしましや?」
「は?」
すぐにも“課題”を告げられると思っていた右大臣は、意気込みを逸らされた面持ちで、
かぐや姫を見つめた。
「いつまでも、このような状態が続いても、限りないこと。
この先を知りたいと、思いまする。」
「なるほど、ごもっとも。しからば、お答え仕る。残るはおふたかた。」
「ありがたき・・・。」
「何の。姫のお望みは、私が叶えますれば、あとのおふたりのことは、
お気に掛けまするな。」
「ごめん遊ばせ。では、右大臣殿への、私の願いをば・・・。」
「・・・・・。」
「唐のお国には、“火鼠の皮衣”なるものが、あるそうな。それを是非、目にしたいと・・・。」
「唐の国でおじゃりまするかぇ?」
(だからぁ、言葉遣いで、無理すんなって)
(ちょっと、遊んでみた)
(解りやすいほうがいい)
(ラジャ)
「そのように伝え聞いておりますが、殿が運のよいお方ならば、
そのようなものが大和国に、来ているのかも知れません。」
「そうであれば、ラッキーなのですが。」
(くだけすぎ!)
(かも。反省!)
(猿でもできる、“反省”か?)
(“どうせい”っちゅうんじゃい?)
(また、ダジャレか? そのために、割り込んだのか?)
(んだ。おとなしく去るか・・・)
「期限は、次の満月の夜までです。よろしいでしょうね。」
「努めてみましょう。」
一日早いスタートになった右大臣は、ちょっとだけ得をした気分で、
屋敷に駆け戻り、家人を集めて、てきぱきと要領を手配した。
勿論、偽物を作らせるつもりはなく、山奥の古寺から、いかがわしい代物を、
取り寄せるつもりもなかった。
ただ、“火鼠の皮衣”を求めて、大和国の隅々まで、探索方の依頼は、
行き渡らせた。
“火鼠”は寝て待て、とばかりに、報奨金につられて、好ましい情報が寄せられるのを、
ひたすら、待ち続けた。
唐の国まで探しに行っても、往復の行程だけで、期限の日が来てしまう。
己が探し回ったのでは、非効率である。報奨金をたっぷりと付けて、
“火鼠の皮衣”を持つ物が、名乗り出てくれるのを待つほうが、
確率が高い。体力を温存したほうが、かぐや姫との生活が、
当初から順調に行く。右大臣は、そう考えたのである。
「俺って、頭いいかも・・・。」
果報を、屋敷で寝て待っているところへ、
諸国を渡り歩いているという、とある商人が、訪ねてきた。
「私が有り金をはたいて手に入れた、曰く因縁のある奇妙な物が、
殿がご所望の、逸品では無かろうかと、名乗り出ました。」
家人から、急ぎ、知らせを受けた右大臣は、
「曰く因縁とな? その者を、早うこれへ呼び寄せよ。」
昼寝から飛び起きて、縁先へ出て、旅の商人が現れるのを待った。
「私がどのようないきさつで、この品を手に入れたのか、まずそこからお話を・・・。」
「待て待て、まずそれを見てからの話に、してたもれ。」
商人は、苦労話を先に済ませたい様子を見せたが、高額報奨金を考えて、
不承不承、右大臣の申し出を受け入れた。
独りでに零れる笑みを、必死に噛み殺しながら、旅の商人は、
汚れた革袋から、さらに薄汚れた“火鼠の皮衣”を、引き出した。
(今度は、本物みたいだね)
(でもなぁ、高く売れる“宝物”を、そんなにいい加減に扱うものかなぁ)
(さ、どうなんだろうねぇ)
(知っているなら、さっさと教えてよ)
(お楽しみは、また今度)
(また、話の引き延ばし作戦?)
(次は、二人いっぺんに済ませるから、落ち着け)
(どこが?)
(“オチ”つかない? ついてないよね)

旅の商人が、右大臣が探している『宝物』とやらが、
自分の持つ袋の中にありそうなことに気づいて、嬉しさを抑えることができなかった。
それが“本物か偽物か?”なんていうことは、この際、どうでも良いことだった。
右大臣が高額で買い上げてくれさえすれば、放浪生活に、終止符を打てるのである。
真偽のほどは、右大臣の判断に任せればいい。
そう思って届け出たのだが、意外にも簡単に、
右大臣が自ら会ってくれることになった。
「“火鼠の皮衣”とは、どのような物か? ささ、直ぐに見せてくりゃれ。」
「そのように急かされては・・・。取り出すときに、破れてもいけませぬでな。」
「それほどに“柔”なもので、おじゃるかや。うむむ・・・。」
「そげなことは、まずは無かろうと、ご安心召されるがよろしかろうと存じまするが、
万一にも破れては、価値が疑われまする。」
「これか・・・。これが彼の“火鼠の皮衣”・・・と。」
阿倍右大臣は、初めて見る伝説の宝物を前にして、そっと“眉に唾”を付けながらも、
本物であることを願いながら、“それなり”の報賞を約して、
商人を手厚くもてなした。
商人は、旅先はおろか、生まれてこの方、食したことがないほどのご馳走と、
滑り落ちそうに滑らかな絹の布団に包まれて、一夜を明かした。
“火鼠の皮衣”とは、何あろう、買い取る折りに、
「これは“土龍”(もぐら)の皮で作られた衣服で、寒さにはめっぽう強い。
しかも、雨水にも丈夫ときている。買い得ぞよ。」
「うまく捌ければ、それなりに売れよう。貴重な物には、違いないしのぅ。」
ということで、そこそこの金額で買い取った、曰くがあったのである。
それが、ひょんなことで、幻の“火鼠の皮衣”に、大化けしようとしている。
あとは、約束の金を受け取ったら、さっさと屋敷をお暇するだけである。
そのタイミングを逸すると、褒美を手に入れるどころか、
詐欺商人として、処罰される畏れもある。
成り行き次第では、一夜のもてなしを得ただけで良しとして、
姿をくらます覚悟もしていた。
「今宵だけでも、儲け物じゃて。とりあえずは、何も考えずに、寝るべし。」
勿体を付けて、期限一杯になってから『憶良』の屋敷へ『かぐや姫』を訪ねるほうが、
“それらしく”思われそうだったが、右大臣には、それだけの心の余裕がなかった。
日が昇るのを待ちかねるように、薄汚れた“火鼠の皮衣”を絹の風呂敷に押し包み、
供も連れずに、屋敷を飛び出した。
左右の田畑にはレンゲソウが咲き乱れ、西の空には、沈みきれない月が、
白く浮かんでいた。右大臣の目には、その景色も、うつろにしか映っていなかった。
ただ一刻も早く、姫に会いたい。唐の国にあるといわれる宝物が、
思いも掛けない幸運で、手元に転げ込んできた。
あとはこれが、本物であることを、願うばかりである。
気持ちは、その一点に集中されていたのである。
供を連れずに飛び出したのは、いつもの右大臣の行動としては、珍しいことだった。
『偽物だったときの、落胆した顔を、供の者に見られたくない。』
その思いが、頭の隅に、不透明な影を落としていたに違いない。
『かぐや姫』に求婚する予定の、残りの2名も、つかず離れずに、
右大臣の後を追っていた。
期限よりも数日も早くに、十三夜の、
沈みきらない月を見ながら、『憶良屋敷』を訪ねるとは、二人の予想しないことだった。
だが昨夜、右大臣の屋敷に『旅の商人』が入ったままで、丁重なる接待を受けて、
宿したことを、伝え聞いていた。
「さては、姫の課題の品を、入手なさったか?」
気が気でない二人は、互いに連絡を取り合い、右大臣屋敷に見張りを付けて置いた。
その見張りから、『早朝に右大臣が屋敷を出られた』と、知らせが入った。
そこで、慌てて駆けつけて、右大臣の後を追っていたのである。
右大臣は、後を振り返る余裕もなく、まっすぐに『憶良屋敷』を、目指していた。
憶良屋敷の表では、召使いが、玄関先を清めていた。
貧しさを嘆いていた憶良だったが、かぐや姫への贈り物が後を絶たず、
結構裕福な暮らしができるようになっていた。
貢ぎ物が屋敷に収まりきれなくなると、専用の倉を建てて、その見張りを兼ねた
召使いも、数人を雇えるようになっていたのである。
「憶良殿は、ご在宅でしょうや?」
「お早うに、何事かおわしますや。床を払っておいでと思いまするが、
朝餉は未だ、と想いまするが・・・。」
「左様か。さすれば、お待ち致そうか。私の訪問だけでも、お伝え願いまえか。」
「しばし、お待ちあられませ。」
召使いが屋敷内に姿を消すと、右大臣は自分も朝食前だったことを、
思い出した。
「主人が、『もしもよろしければ、右大臣様にも、朝餉を』と仰せられておいでですが。」
「いや、私はご覧に入れたい品を持参したまでで、ご相伴に与るわけにはいきませぬ。」
「お口には合いませぬかと存じますが、主人の『是非に』との言付けもありますれば。」
「私の至らなさを、お心にお留めくださるご配慮、頂戴いたしましょう。」
「お入りくださいませ。」
「甘えさせて戴こうか。」
「お早うに、ご免くださいますよう・・・。」
「ご訪問、嬉しく存じます。粗末な朝餉なれば、
お迎えするにはお恥ずかしい限りではありますが、僅かばかりの心を、と。」
「時をわきまえずに訪ねたご無礼を、お赦しください。」
そう言いながらも、右大臣の視線は、落ち着き無く邸内を漂っていた。
その気持ちを察したように、憶良は、
「まだ約束の日まで、幾日もございますれば、
右大臣殿が斯様に早く、おいでくださるとは、思いの外にございます。
さすれば姫は、まだゆるりと書物などを、耽って居ることでしょう。」
と、『かぐや姫』が姿を見せない理由を、伝えた。
「それは残念。一時も早く、姫にも“火鼠の皮衣”をお目に掛けたい。」
「殿がこと。間違いはございませんでしょうが、食事を済ませてからになさっては、
いかがでしょう。」
「姫は・・・。」
憶良の言葉が理解できない様子で、右大臣は、『かぐや姫』の姿を求めた。
とても朝餉のご相伴などと、悠長なことに時間を費やす場合ではない、
と判断した憶良は、右大臣に“ある提案”を申し出た。
「前のおふたかたは、“紛い物”をお持ちなさり、姫によって見破られ申した。
さあらば、最早、姫にお顔を会わすことは、叶いませぬ。阿倍の殿は、
ご自身の手によって、かくなる品を作らせ賜うたのではありません。
そこで、私が“真偽”を見定めれば、万にひとつ、偽物であっても、それは、
持ち込んだ商人の罪であって、阿倍の殿には、非がございません。」
「重ね重ねのご配慮、ありがたくお受けいたしましょう。」
「では、その“火鼠の皮衣”を拝見いたしましょう。」
「これに。」
「これはまた・・・。」
憶良も、衣類の汚さに眉をしかめながら、包みから取り出された“宝物”を、
摘み上げた。
「言い伝えによれば、“火鼠の皮衣”なるは、
どのような苛烈な火にも、燃ゆる事なきとぞ云わるる。さて、これは・・・?」
はっと息を飲む右大臣の止めよう間もなく、無造作に“宝物”は、囲炉裏に放り込まれた。
憶良にとっては、朝餉の席に持ち込まれた、薄汚い皮衣など、触りたくもなかった。
だが、右大臣の手前、何もせずに“偽物”と断定することはできない。
そこで、一時も早く手放したいという気持ちが顕れて、皮衣は、囲炉裏に放り込まれたのだ。
皮衣は、炎に耐えるだけの根性もなく、たちまちにして燃え上がり、たちまちにして灰と化した。皮衣が白くなるのに合わせるように、右大臣も姿が小さくなるように、うなだれてしまった。
「や、これは、申し訳ないことをしてしもうた。やはり、朝餉の後にしたほうがよかったか・・・。」
「ご懸念にや及ぶ。斯様な旅商人の胡乱な言葉を、鵜呑みにした私の恥じること。
こたびの“火鼠の皮衣”は、見つけられなかったことに、しては戴けないでしょうか。」
「言うまでもなく。して、朝餉はいかがに?」
「その気分ではありません。早く帰り、彼の商人を、引っ捕らえてくれましょう。」
(ねぇ。皮の服って、そんなに簡単に燃える?)
(古いんだろう)
(俺の革ジャンも、そんな簡単に燃えちゃうのかなぁ)
(普通なら、燃えないと思うけど、何しろ古かったようだから・・・)
(ひどいボロだったんだ)
(あげくに、乾燥していたんだろうね)
(乾【皮】いていたって言うの?)
(そんなつもりじゃなかったんだけど)
(ダジャレを出さないと、落ち着かないんでしょ?)
(そんなつもりじゃ・・・)
右大臣が、商人の始末を考えながら家路を急いでいる時分に、その商人は、
報奨金を受け取るまでの欲を出さずに、僅かばかりの『銀食器』を懐にして、
遙か遠くの山を、越えようとしていた。
(それって、泥棒じゃないの?)
(日本人って、昔からセキュリティ意識が、弱かったんだね)
(油断できないねぇ)
(夜盗も、旅の商人も、いつだって泥棒に早変わりした時代だと思うよ)
右大臣が、商人に騙されたという噂は、都に広まった。しかし、小細工を弄して騙そうと
企んだわけではないと言われて、かろうじて体面は保たれた。
「吾等にとっては、幸いなことだが、事はうまく運ばぬものよなぁ。」
「・・・でおじゃるよ・・・なぁ。」
順番が巡ってきた、残りの求婚者は、不安を募らせながらも、どうにか自分にもチャンスが残されたことを、そっと喜び合った。
他人の不幸は、密の味?

次の満月の日に、『かぐや姫』の前に姿を見せたのは、『大伴大納言』である。
『憶良』にとっては、まんざら縁のない名前ではない。
複雑な面持ちで、大納言を迎え入れた。
「父上が、大納言様に懇意にして戴いておわしますることは、承知しております。
然れども、石作の皇子、車持の皇子、そして阿倍の殿と、
何れのおかたにも、宝物を探し求めて戴きました。
やはり大伴様にも、同じように課題を差し上げたいと思います。」
「免除して戴いても、私は一向に構いませぬが。」
「そうは参りませぬ。左様なことでは、後々、非難されましょう。」
「では、どうかお手柔らかに、お願い申す。」
「簡単なところで・・・『龍の首の玉』なるものを、所望いたしましょう。」
『げっ! ちっとも簡単やおまへんやないかぇ。
そないなもの、聞くからに、“げに恐ろしげ”でおじゃりますがな。』
内心で、『厄介な物を』と思いながら、大納言は、虚勢を張った。
「ひと月もの間は、不要に御座そろ。たちまちのうちに、差し出してご覧じように。」
「おお、頼もしや。」
大納言も、帰邸するやいなや、家人たちに『龍の首の玉』探索を、命じた。
「へぇ、へえ。承知仕り申した。旅支度が整い次第に、ゆるりと・・・な。」
「ゆるりとなどと、そないな余裕は有らしめへん。早うに出立せんかな。」
「旅支度が、まだ済んでまへんので・・・。」
「後から追って、届けさせようほどに、早う、早う!」
急き立てられて、家人たちは八方に散っていった。
「おぬしは、『龍の首・・・』何たら言うもんを、本気で探しますんかいな?」
「聞くからに、恐ろしげよのう。ま、湯にでも浸かって、ゆるりと行こかぁ。」
「そら、そうよのう。そら恐ろしい物なんぞ、近寄りたくもない。」
(だ・か・ら・・・怪しげな京言葉もどきは、やめれ!)
(んだな。慣れね事すっと、笑われっかんな)
(普通の言葉だって、充分に笑われてるっちゅうの)
(そうだべねぇ)
家来たちが、探索に散りながら、全く“宝物探し”に本気にならない、と知った大納言は、
業を煮やして、ついには自分で探し出すことにした。
「もう、残りの日にちも多くはない。家人に頼った儂がアホやった。南海の果てに、
“龍の首の玉”はあるというではないか。」
「伝え聞きまするは、そのように。」
「では、船を出せ!」
船を漕ぎ出して、3日もたたずに、大納言は、嵐に見舞われた。
台風ではなかったが、春の嵐は凄まじく、一行の船は次々に破損して、
大納言も這々の体で、大物浦に打ち上げられた。
この浜は、後に源義経一行が都落ちをも、嵐によって阻んでいる。
何という因縁か、人の希望を打ち砕く、浜なのであろうか。
余談はとにかく・・・
大納言一行は、この被害によって探索資金も乏しくなり、むなしく期日が迫るのを、
屋敷で待つだけになってしまった。
期日近くなると、湯治場で元気いっぱいになった家人たちが、三々五々に、帰り始めた。
「あきまへん。幸いなことに・・・なんの、残念なことに『龍』の姿も拝めませんでしたわ。」
「私も、おないです。『龍』が天に昇る姿かと思いきや・・・。」
「温泉から立ち上る“湯気”でっしゃろ?」
「おお、ご同輩!」
『こんな奴らに、頼んだのが間違いだった。
温泉三昧をさせるために、旅費を出してやったようなもんやないかい。』
大納言は、腹立たしさを忘れて、脱力感に襲われていた。
残りの日々を、万に一つの“果報”を待ちながら、過ごすしか方途がなかった。
果報はもたらされないままに、期限の日は、無情に迫っていた。
大納言はついに、期限を待たずにギブアップをした。
『かぐや姫』への求婚者は、最後のひとりを残すだけになった。
石上中納言、その人である。
皇子たちの申し出も断り、大納言の申し出も断って、残ったのが『中納言』なのである。
“おみくじ”のようなもので、この先、出世の楽しみがあるということでは、
『大吉』よりも『中吉』のほうが喜ばれる、ということに、似ているかも知れない。
「“家宝”にできるお宝を探すなんて、“果報”は寝て待て、ということでおじゃるかな?」
(あらら、中納言にまで、ダジャレを言わせちゃって)
(彼も、1ヶ月じゃ、“宝物”は見つけられないだろうね)
(ダメなの?)
(お名前が『石上』なんだもの。3年はかかるんじゃないの?)
(『石上』にも3年・・・)
(お後がよろしいようで)
よろしくない。。。
『憶良』の屋敷を訪ねた中納言に、『かぐや姫』が、言い渡した。
「“燕の子安貝”は、お家の繁栄を願う物。それを是非にも。」
「嬉しいお言葉。この中納言の、命に替えても。」
暗示的な言葉を言い置いて、中納言は、憶良邸をあとにした。
中納言の耳には、澄んだ鈴の音のような『かぐや姫』の声が、いつまでも転がっていた。
「姫が、満月の日を期限に選ぶ理由が、ようやく解ったような気がする。
あの眼差しには、“満月の輝き”が、確かに住み着いておわす。」
中納言は、ぼそっと、つぶやいた。
ところで、『燕の子安貝』って、そんなに貴重品なの?
うちにも、『子安貝』くらいならあるんだけど、“燕の”の意味が、よくわからない?
その辺のことは、次回にでも・・・。
私も、よく解っていないんだけど。

ホームへ戻る 続く(次ページへ)
© Rakuten Group, Inc.