2020年07月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

銀輪花散歩・花も実も
今日は半月。弓張月です。 雨続きの梅雨空、夜空に月を見るのも久しぶりな気がする。(今日の月) 大阪もいよいよ明後日には梅雨明け宣言がなされるようですが、コロナ明けはいつになるのでしょうか。今日の新規感染者は155人とこれまでの最多を記録です。 ますます出辛くなっていて、梅雨ということもあって、銀輪散歩も近隣のみでお茶を濁して居ります。 さて、そんなことで、今日の記事は「花」であります。 この時期の花と言えば、百日紅ですかね。(花園中央公園のサルスベリの花) この花は、夏の暑い盛りに長い期間にわたって次々と咲くということからだろうか、漢字では百日紅と書く。 千日紅という花もあるから、名前の上ではそれに負けているが、百日紅とは立派な名前である。しかし、訓はサルスベリ(猿滑り)であるから、いささか情けない名前になってしまう。 サルスベリの方は、この木の幹の木肌に着目しての名前で、百日紅の方は、花に着目しての名前。(同上) サルスベリからすれば、花の方に着目してくれよ、というところなんだろうが、百日紅とは書いても、誰も「ひゃくにちべに」とか「ひゃくにちこう」とかは読んでくれず、「さるすべり」と読まれてしまう。 囲碁で「さるすべり」というのは、裾深く相手陣地に滑り込んで相手の陣地を小さくする手で、終盤の寄せでは有効な手である場合が多いが、何となく狡猾な手という感じがしないこともない。 樹皮が老化すると、日焼けした皮膚がペロリと剥けるように、或いは傷の瘡蓋がポロリと剥がれるように、樹皮が浮き上がって来て剥がれ落ち、スベスベ、ツルツルの木肌が現れる。猿も滑るようなツルツルの幹となることから、サルスベリという名を誰かが付けたのだろうが、それが運の尽き、「百日の説法屁一つ」ではないが、百日の紅も猿滑り、となってしまった次第。 この樹皮をめくってみたことがあるが、面白い形にめくれるので、ついつい次々とめくってしまったりするのであります。 百日と言えば、百日草という花もありますね。 百日咳と言えば、咳が長く続く気管支感染症の病気。 百日裁判というのも、公職選挙法違反の広島の国会議員夫妻の事件で近頃よく耳にした言葉。 百日祝いは、生後100日目のお祝い。 百日祭は、死後100日目の神道で行う祭事。 百日鬘は、歌舞伎で、盗賊や囚人などの役に使う、月代が長くのびた様子を表現した鬘のこと。 百日曽我は、浄瑠璃の出し物で、曽我兄弟の仇討から彼らが神として祀られるまでを描いた作品。 百日天下は、ナポレオンがエルバ島を脱出してパリに戻り、帝政を復活させてからワーテルローの戦いで敗れて退位するに至るまでの100日間の支配のこと。 百日法華は、他宗の者が、病気平癒などを祈願するため一時的に法華信者になること。 百日詣で、百日参りとは、同じ神社や寺に100日間お参りして祈願すること。 「百日」も色々あるようです。(サフランモドキ) これは、水走公園の片隅に咲いていた花。(同上) 季節は、そろそろ実の準備に入る頃。 コブシがあの特長のある奇妙な形の実をつけている。(コブシの実) コブシの実を初めて見たときは、虫こぶではないかと思ったものだが。(同上) 上2枚は少し前のもの。 今日撮影のものは、一層色づきが進んでいました。(同上) ギンナンもはや実をつけて、秋に備えています。(ギンナン)(同上) 近寄って見ると、少し色づき始めているようにも見える。(同上) 以上、花も実もある、銀輪花散歩でありました。
2020.07.28
コメント(0)
-

花より団子虫
昨日(24日)の大阪の新型コロナ感染新規陽性者は149人と過去最多。 東京は260人と23日の366人よりは少なくなったものの高水準。 <追記>本日の新規陽性者は東京295人、大阪132人 Go to トラベルの前倒し実施がなされたのに合わせるかのように新規感染者急増という皮肉な現象。政府の施策もチグハグ、専門家会議も何だか頼りない。新規感染者は今後もこの勢いで増えて行くことになるのだろう。 さりとて、ダンゴムシのように丸まって身を潜めている訳にもまいらぬのが人間様であるから、ワクチンや有効な治療薬が実用化されるまでは、こういう状況は変わらずに続くということなんでしょう。 今年はコロナ禍の所為で遠出の銀輪散歩も自粛していることから、当ブログもその中心的記事となる「銀輪万葉」カテゴリの記事が激減している。それに替わって増えているのが「花」カテゴリの記事である。「虫」カテゴリなどの記事も増えている。ネコ歩きなどという訳の分からない記事も登場する始末(笑)。 今日も雨模様の空。明日も雨らしい。銀輪での外出は無理。 されば、花の記事でもと思ったが、花の写真が左程にはない。 では、「花より団子」で、お団子の記事を、というのはもっと無理。 ということで、花より団子虫の記事とします。 長い前振りとなりましたが、要するに、先日たまたま何を思ったかダンゴムシの写真を撮ってしまい、手元に8枚のダンゴムシの写真があり、これの処置に困ったから、ということに過ぎないのであります。 まあ、こんなことでもなければ、ダンゴムシが当ブログに登場するということもあるまいから、一度くらいはいいでしょう。(オカダンゴムシ)<参考>ダンゴムシ・Wikipedia 上記<参考>のウイキペディアの記載によると、ダンゴムシとは「ワラジムシ目の動物のうち、陸生で刺激を受けると体を丸める(団子のような体勢になる)習性を持つものを指す。一般に『ダンゴムシ』と呼ばれるものはオカダンゴムシである。」とのこと。(同上)(同上) オカダンゴムシはヨーロッパ原産だろうとされる帰化動物とのこと。 これに対して、海浜(特に砂浜)で見られる大型のハマダンゴムシや森林の土壌で見られる小型のコシビロダンゴムシは、日本土着の虫だとのこと。 ダンゴも色々なのだ。(同上)(同上) 落ち葉などを食べて、微生物が分解しやすい状態にするので、土壌を豊かにしてくれるという点ではミミズと同じく益虫と言うべきであるが、落ち葉に限らず農作物の葉や茎、新芽も食べたりするので害虫でもある。 虫の嫌いな人ならその姿を見るだけで不快、これを不快害虫と言うそうである。こんなことで害虫にされてはたまったものではないが、何しろ、有益・有害は「人間様」の決めることであるのだから、虫の方からの異議申し立ては認められてはいないのである。(同上)(同上) アリとにらめっこ。 何事も起こらず、すれ違い。 背中に斑点模様のあるダンゴムシはメスで、オスにはそれがないらしいから、これらはすべてオスということか。 ダンゴムシとは親しいお付き合いがなかったヤカモチ。斑点模様のダンゴムシを見たという記憶がない。(同上) 不快害虫であることを承知の上で、8枚も写真を並べました。 こういう虫も見慣れると、そう不快でもなくなるのでは・・ということで並べてみたのですが、益々不快になられたお方には謹んでお詫び申し上げます。<参考>虫関連の過去記事はコチラ。<追記>気分直しに今日の空の写真でも。(今日の空です。)
2020.07.25
コメント(2)
-

クマゼミ
大阪の梅雨明けは未だのようだが、連休明けにはそろそろでしょうか。 ヤカモチは、気象台の梅雨明け宣言を待たず、セミが鳴き出したら「梅雨明け」勝手宣言というのが例年のことでありますが、今年はちょっと勝手が違って、セミが鳴きだしても雨が続きという具合で、未だに勝手宣言を出せぬままに今日に至っています。しかし、気象台に後れをとるのも癪なので、今日、梅雨明け宣言してしまいます。 相変わらずコロナ感染新規陽性者数の増大が続いていますが、東京は遂に366人と300人台を突破、大阪は103人(だったかな?)とこれまた二日連続の100人超え。 先日の東大阪市のスポーツバーでのクラスター発生、18人の陽性者云々のスポーツバーとはどうやら瓢箪山駅近くのバーらしい。 ヤカモチの日常生活圏の範囲に存在しているバーでした。下戸のヤカモチですから、そんな店がそんなところにあるということも今回のことで初めて知ったにすぎず、出入りする可能性はどの道ゼロですが、これまでに何度となく店のある建物の前の道は自転車で通っていました。 まあ、そんなことで、Go to トラベル・キャンペーンも吾事に非ず、と近隣を銀輪散歩するなどは別として、連休は自宅で「自粛」と決めましたが、こんな次第では、梅雨が明けようが明けまいが余り関係ないか・・でありましょうか。 かくてブログの方もこれといったネタも無いことゆえ、このところ毎朝のように庭先でやかましく鳴いているクマゼミの写真でも並べて置くことにします。 庭の木のクマゼミの写真ではなく、銀輪散歩で立ち寄った公園の木にいたクマゼミたちであります。 先ずは、花園中央公園のケヤキのクマゼミです。(クマゼミA)(クマゼミB) 次は、水走公園のクマゼミです。 アオメアブの居た公園です。白猫のアオメの居た公園でもあります。(クマゼミC)(クマゼミD)(クマゼミE)(同上) 再び、花園中央公園に戻って、本日撮影のクマゼミです。 発生数が増えたのか、一つの木に何匹ものクマゼミがとまっています。(クマゼミの群れA) この木はモミジバフウの木でありますが、ざっと見ただけで20匹以上はいました。 このように群れている、密になっていると、個々のクマゼミは警戒感が薄くなるのか、人が近づいたからといってすぐに逃げるということがありません。手の届く距離に近づいても逃げない。どうかすると素手で摑まえることもできてしまう。 集団心理、群集心理というもので人も群れると、常軌を逸する行動に走ることがありますが、セミも集団をつくると警戒を群れの仲間に依存するという「心理」に陥るのでしょうか。かなり無防備になります。(同上B) 隣の木のコナラには地面から10cm程度の高さに1匹、40cm程度の高さに1匹と、ずいぶん低い位置にもクマゼミがとまっていました。1m位の高い位置からカメムシがそれを見下ろしているという愉快な構図も見られました。クマを見下すカメ、というキャッチコピーが思い浮かびましたが、写真に収めるには距離が離れすぎていました。(同上C) 今日は、クマだらけ・・でした。
2020.07.23
コメント(4)
-

ヤカモチ的ネコ歩き5・おこげとアオメ
今日は、本来なら健人会の納涼昼食会で、瀬田川畔の料亭「新月」に集まっている筈でしたが、新型コロナ感染拡大第2波かという動きもあって中止。家でゴロゴロしていることと相成りました。 当初予定では、この健人会の後、JR湖西線・大津京駅近くのビジネスホテルに宿をとり、翌日、宇佐山城跡、大伴黒主神社、坂本城跡、西教寺などを銀輪散歩することとしていましたが、健人会が中止とあれば、この日である必要もなく、宿泊予約もキャンセル、日を改めることとしたのでありました。 今日の大阪の新規感染者数は過去最多の121人だそうですから、この選択は「正解」というものでしょう。 という次第で、今日は「ヤカモチ的ネコ歩き」の記事とします。 最近の銀輪散歩で出会った猫三態であります。 先ず、最初はキジトラ猫のネコロンであります。(ネコロン) ネコロンは花園中央公園を根拠地とする♀ネコで、同じくキジトラ猫の清兵衛(♂)やジャックナイフ(♂)と行動を共にしていることが多いのであるが、この日は一人、いや一匹でいました。(同上) ネコロンという名は、最初に出会った時、清兵衛やジャックナイフと一緒で、彼らがお座り乃至は立っている状態なのに彼女だけは終始寝そべっていたので、つまり寝転んでいたので「ネコロン」と名付けたのでありました。 ネコ論を論じさせるとひとかどのネコ論を展開するからという説はフェイクであります。(同上) はい、ヤカモチと完全に目が合いました。 いかにも「女の子」という感じのネコで、ネコ論を論じるようなネコでないことは明らかであります。 「ニャン?」と言って居ります。 ここは花園中央公園の桜広場の一画。 この後、一時、彼女は姿を消しますが、噴水広場を挟んだ反対側の地区でまたまた彼女と再会します。 しばらくして自転車で通りかかった男の人が、エサらしきものを置いて行ったと見えて、それを食べている気配。 ヤカモチはそれを離れた場所から見ていましたが、同じように彼女を見ている奴がいました。(サビ猫おこげ) それは、このネコ。 焦げた色合いなので「おこげ」という安直な命名です。 彼はオス猫です。 やんちゃ坊主のような顔つき。じっとネコロンの方を見ていました。 ヤカモチの視線に気づいたか、こちらに顔を向けた。(同上) 右の耳が桜耳になっているから、オス猫です。 ヤカモチとは多分初対面。 黄金色の目でじろり。 「じろり」という名にするか、「おこげ」という名にするかで、迷いましたが、「おこげ」という名に落ち着きました。 次は、水走公園で出会った白猫です。 アオメアブを撮影していて、視線を上げると、広場の反対側、遠くを白いネコが歩いて行くのが見えました。 ぐるりと回って、少し近くまでやって来たので、ヤカモチも彼の方へ少し接近。無難な距離から彼を観察。(アオメ) 目が青い色なので「アオメ」と名付けることにしました。 ネコの目というと金色というのが相場であるが、白猫の場合は目の中の色素も少ないと見えて、眼球は「水色」と言うか、青っぽい色になるのが居るようです。白人の目が青いのと同じ原理でしょうか。 アオメも、右耳が桜耳になっているから、♂である。 上のネコロンやおこげが何となく幼い雰囲気を残しているのに対して、アオメは成熟した大人という感じのネコである。(同上) ネコロンではないのに、伏せの恰好、寝そべってしまった。 視線は何処に。 撮影しているヤカモチには全く無関心である。 ならばと、更に接近してみる。(同上) お前のことなんか・・プイと顔をそむけて馬鹿にしたような仕草。 ヤカモチ「おいおい!」 無視。 やがて目をつむってしまった。(同上) しかし、よく見ると、何やら懊悩の表情である。 腰痛ですかな? それとも・・何かお悩みですかな?(同上) アオメ「そんな訳ねえだろうが・・・!!」 初対面のネコには、ヤカモチと雖も、余り立ち入ったことを聞いてはいけないようであります。 友人からの受け売りの話であるが、右目が金色で左目が水色というように左右で色の異なる目を持つネコも居るそうで、そういうネコは結構人気があるのだという。 何でも、神秘的な雰囲気を漂わせるのでいいのだそうだが、ヤカモチ的には何だかチグハグで滑稽な表情になってしまうように思えるのだが、実のところはどうなんだろう。まあ、そんなネコが居るのなら、一度お目にかかりたいものである、ニャンてね。<追記・参考>左右で目の色が違うオッドアイの猫<参考>犬、猫など関連の過去記事はコチラ。
2020.07.22
コメント(4)
-

祝・智麻呂画伯ご退院
昨日(20日)、智麻呂画伯が退院されました。 3月7日に入院されて以来ですから、実に4ヶ月半になります。 今日、智麻呂邸を訪問、久々に智麻呂氏のお元気なお顔を拝してまいりました。コロナ禍の所為で、面会・見舞い禁止措置でありましたので、4ヶ月半ぶりの再会。嬉しい限りでありました。 お孫さんのナナちゃんのお見立てだという青い涼しげなシャツ姿の智麻呂画伯のお元気な笑顔。今日今日と 待ちし君はも 涼やかに 青き服着て 笑みてしあれる (偐家持)(祝・退院の花束) 上は、若草読書会一同からの祝退院の花束であります。 ヤカモチが代表してお持ちしました。 既に、偐山頭火さんからだという花束が届いていて、智麻呂画伯は早速にそのスケッチを始めて居られました。 奥様の恒郎女さんは「少し休んでからにすればいいのに、早速に色鉛筆を出せ、などと言ってスケッチを始めました。」と嬉しそうに仰っていましたが、ようやくにいつもの日常、かつての当たり前の日常が帰って来た安堵感が感じられました。 奥様同様、我々若草読書会の面々もこの日をどれだけ待っていたことか。本当に嬉しい限りであります。 まあ、絵の方は、余り張り切り過ぎずぼちぼちと描いて下さればいいかと思いますが、再び、近いうちに皆様に「智麻呂絵画展」という形で、その作品をご紹介できることになるかと思いますので、どうぞお楽しみにお待ちいただければと存じます。 今日は、その嬉しいご報告を申し上げました次第にございます。<参考>若草読書会関連過去記事はコチラ。智麻呂絵画展関連過去記事はコチラ。
2020.07.21
コメント(6)
-

ムシヒキアブ・トンボとアブの中間みたいなアブ
昨日、今日といい天気です。 梅雨が明けた、と言ってもいい位な感じなのだが、前線の配置状態や太平洋高気圧の張り出し方など天気図的には、まだ梅雨明け宣言するのは早いというのが、今日の大阪ということでしょうか。(2020年7月18日午後3時半頃の水走公園の空) 上は、昨日の水走公園の空の写真である。 今日の空は、昨日よりも少し雲が多い印象を受けるが、青い空に白い雲という好天気にて、もう梅雨明けの空という風情である。 話が少し逸れるが、一昨日(17日)あたりから背中が重苦しく痛い感じがあって、肩でも凝っているのかと、昨日(18日)銀輪散歩で立ち寄ったこの水走公園で体を反らしたり、腕や肩をグルグル回したりの体操を、かなり入念にやってみたら、却って痛みが酷くなったようで、帰宅した夕刻からはズキズキと疼くような具合となり、咳をしたり、体をひねったりすると少し強い痛みが走るようになった。 で、ネットで「背中が痛くなる病気」で調べたら、狭心症、心筋梗塞、肺塞栓症、椎間板ヘルニア、十二指腸潰瘍、急性大動脈解離、膵炎、膵臓癌、腎炎、腎結石、尿管結石、胆嚢炎、脊髄腫瘍、骨粗鬆症による圧迫骨折、などが見つかった。 背中の痛む部位で病気は異なるが、背中の中ほどだと大動脈解離、心筋梗塞、肺塞栓症などが該当することとなる。 十数年前(2004年)に自転車の事故で背中の肋骨を5本折ったことがあった。その時の激痛は息もできない位のものであったが、そのような激しい痛みになる前の状態か幾分治癒軽快した段階の背中の痛みに感じが似ている。もし、骨折ならその部分に圧力を加えると強い痛みが走る筈だが、そういう風でもない。 こうしてPCに向かっていても、姿勢を伸ばしたり、変えたりすると背中に痛みが走る。これ以上、痛みが強くなると困るし、何か悪い病気であっても困るということで、救急医療病院でもある馴染みの病院へ電話を入れて、症状を説明の上、日曜日だが診察して貰えるかを照会すると、OKの返事。 一応、診察していただいた。問診と簡単な触診のみであったが、内臓関係の病気、動脈解離や心筋梗塞など重大な病気の可能性は低いと認められるので、筋肉の炎症の可能性が高いという診断。 明日、月曜日に整形外科を受診してみて下さい。痛みが激しくなったり、痛む場所に変化が見られるなどがあれば、すみやかに連絡して下さい、というのが医者の指示。湿布薬をもらった。が、これは貼っていない。この暑い時期に貼ると皮膚が荒れて激しい痒みに襲われるということを何度か経験しているので、使わないで様子を見ることとする。 結論は、明日以降に持ち越しであります。 さて、脱線話が長すぎました。本論に戻します。 昨日、水走公園で珍しい虫を見ました。(アオメアブ) トンボのような細長い胴体で、翅はアブやハチのような折りたたみ型という面白い姿。 調べると、ムシヒキアブ科に属するアブで、複眼が緑色なのがアオメアブといい、黒色なのがシオヤアブというらしい。 これは美しい緑色の眼球であるから、アオメアブである。(同上)<参考>アオメアブ シオヤアブ 頑強そうな逞しい脚、最強のハンターと呼ばれるそうだが、いかにもそんな風貌の虫である。(同上)(同上) この公園では、青い目の白猫にも出会いましたが、それはまた別の機会にご紹介申し上げましょう。猫は虫ではないので。 で、アオの付く蝶の写真を掲載して置きます。この蝶も水走公園の同じ広場で舞い遊んでいました。(アオスジアゲハ) 寝転がっていた木製ベンチから立ち上がって帰ろうとしていたら、こいつがのこのこやってきました。 アオクサカメムシです。アオカメムシの一種ですが、こいつも「アオ」が付くので、ここに参加する資格アリであります(笑)。(アオクサカメムシ) よく見ると、外翅の一部が欠損しています。 天敵に襲われたところを辛うじて逃げることができたということか。 カメムシの世界もなかなか過酷なようです。(同上) 右外翅は下部が欠けているだけですが、左外翅は付け根部分から全部無くなってしまっています。(同上) 外翅は、言わば翅の格納庫の扉みたいなもので、それが欠けても、生命にはすぐさまの影響はないようです。元気に動き回っています。 今日は銀輪虫散歩・青編といったところでした。<参考>虫関連の過去記事はコチラ。
2020.07.19
コメント(12)
-

セスジスズメとミノムシ
クマゼミが盛んに鳴いている。 クマゼミは午前中に鳴き、午後から夕刻にかけてはアブラゼミが鳴く、というのがセミ時計というものであるが、今年は長引く梅雨の所為で、セミの体内時計にも狂いが生じたか、午後、夕刻近くになっても鳴いているクマゼミが目立つ。目で見ている訳ではなく、耳で聞いている訳だから「目立つ」のではなく「耳立つ」と言うべきでしょうか。しかし、「耳立つ」というと「耳ざわりになる」という否定的なニュアンスになるので、ちょっと違うか。 まあ、クマゼミの、あの騒がしい鳴き声に限って言えば、「耳立つ」のではあるが(笑)。 その耳立つクマゼミの声を聞くにつけて、午後遅くになっても、アブラゼミの声が一向に聞こえて来ないことに気が付き、アブラゼミがクマゼミの隆盛に押されて、どんどん減少しているのではないかと危惧している次第。 温暖化によって、南方系のセミであるクマゼミは勢いを増し、どんどん北上しているようだが、現時点ではどの辺りが北限となっているのだろう。 それはさて置き、今日はセミの話ではなく、蛾の話である。 先日(15日)、接着剤を買い求めるため石切のコーナン(ホームセンター)まで出かけたついでに、喫茶・ペリカンの家に立ち寄りましたが、その折にまたしてもスズメガの仲間、セスジスズメと出会いました。 この蛾とは余程にご縁があるのか、それとも発生数が増えているのか、このところよく出くわす。 最初は、6月5日の墓参の帰り道で、この時は蛾になる前の幼虫の姿。 次が、6月20日の銀輪散歩の途中で、この時は成虫の蛾の姿。 そして、今回が7月15日で、成虫の姿での再会。40日の間に3回も出会っている計算であるから、かなりの高頻度である。 セスジスズメは特徴のある模様の蛾であるから、ひと目でそれとわかる。(セスジスズメ) 6月20日に出会ったセスジスズメは腹部の真ん中辺りの鱗粉が一部剥がれていて、背筋と名付けられた白い1本の「スジ」が途中で切れていたが、今回のセスジスズメは完全な姿。頭部から尾部まで白い一本の「スジ」が通っていました。(同上) 一枚目の写真では左翅の下部が枯葉の陰に隠れていたので、その枯葉を少し動かして翅全体が写るようにして撮ったのが上の写真。 そして、さらに接近して撮ったのが下の写真。(同上) ついつい見惚れてしまう美しい模様、見事なデザイン。 頭部付近の豊かな鱗粉は犬猫などの毛並みを思わせ、撫でてみたい衝動に駆られる姿である。(同上) 撮影の角度を変えて行き、横から複眼が写る角度で撮ろうとカメラを近づけた瞬間、やっと目が覚めたか、カメラの接近に気づいたか、飛び立ってしまった。 次の写真は蓑虫。 これは、喫茶・ペリカンの家と道路を挟んで向かい側にある病院の庭の入り口にあるカエデの木の枝先にぶら下がっていたもの。 この木にはいつも蓑虫がいることを承知しているので、上のセスジスズメと違って、偶然ではなく、それと意図し、探し当てての撮影である。(ミノムシ) ミノムシという名前であるが、正しくはミノガという蛾である。 ミノガ科の蛾は、例外もあるが、雌は成虫になっても羽化せず、翅も脚も持たず、生涯を蓑の中で過ごす。蓑の中で産卵した雌は、やがて蓑から出て地上に落下して死ぬ。 オオミノガ、チャミノガなど日本には20以上の種が存在するとのことであるが、最近は余り見かけなくなっている。<参考>ミノムシ・Wikipedia(同上) オオミノガはヤマトミノガとも言い、日本産の最も大きいミノムシであるが、1990年代後半から激減しているという。 外来のオオミノガヤドリバエというハエは、オオミノガの終齢幼虫を見つけると、彼が摂食中の葉に産卵するらしい。幼虫が葉とともにそのハエの卵を食べる。噛み砕かれることなく無傷で幼虫の体内に入った卵はそこで孵化して、幼虫を餌にして育つのであろう。 オオミノガは、このオオミノガヤドリバエの寄生の所為で激減し、各地で絶滅危惧種に指定されているとのことである。 寄生も共生も仕組みは同じ、紙一重。我々の体の中にも無数の菌が寄生している。悪さをするのが悪玉菌、有益なことをしてくれるのが善玉菌と名付けられているのだろうが、益虫・害虫と同じことで、それは一つの価値観、一つの切り口で評価しての区分に過ぎない。生物全体、生態系から眺めれば、善も悪もなく、益も害もない。それぞれが「種」として生き残るための営みの中で相互に影響し合い、作用し合っているに過ぎないことになる。 そういう中で「種」として生き残るための適応・進化を遂げたものだけが、新しい環境の中での生存が許されるというのが、生物というものの基本原則、掟である。してみれば、世界中で猛威をふるっている只今の新型コロナウイルスも、そういった現象の一つに過ぎないですな。
2020.07.18
コメント(2)
-

COCOA
このところ、新型コロナウイルス新規感染者の数が急増していますが、昨日(16日)は、東京都で286人、大阪府で66人の多数になった。 大阪府の66人のうち、18人はわが町の東大阪市在住者だという。 その18人のうちの11人は、東大阪市内のスポーツバーでの集団感染者だとのこと。スポーツバーって何?と調べたら、店内にスポーツ観戦用のTVを備置して、客が飲み食いしながらスポーツ観戦して贔屓のチームや選手を一緒に応援するということができるバーであるとのこと。酒を飲まない下戸のヤカモチには無縁の店であるが、ネットで検索してみると東大阪市内で8店舗が見つかった。近鉄布施駅付近に4店舗、近鉄長瀬駅付近、同八戸ノ里駅付近、同花園駅付近、地下鉄長田駅付近に各1店舗である。 問題の店がこれらの中の一つなのか、ネット検索では見つからなかった別の店なのかは分からないが、布施、八戸ノ里、花園、長田などは銀輪散歩のコースにある身近な駅。感染がいよいよ身近になってきている気配である。<参考>7/16東大阪市で過去最多の新規陽性者18人 東大阪市の最新感染動向 ウィズコロナですから、自分の身は自分で守るしかない。 マスク着用、人混みは避ける、手洗い・・など基本的なことを心掛けた上で、最後は自身の免疫力に期待するということでしょうか。 このウイルスの厄介なのは、感染していても無症状乃至軽症である場合が多いので、自身が感染していても気が付かず、知らないうちに他者を感染させてしまうという危険性があること。 感染者やそれとの濃厚接触者をいかに迅速に捕捉するかが感染拡大防止の要となるが、この点で効力があると期待されるのがCOCOA(新型コロナ感染者接触確認アプリ)ではないだろうか。 ヤカモチは、夜の街とは無縁、銀輪散歩だけなので、このアプリをインストールしても余り意味がないようにも思うが、一応、スマホに取り込んでいます。 或る人・Aさんが陽性者となった場合に、Aさんが自身のスマホでこのアプリによって匿名でその旨を入力すると、Aさんと濃厚接触があったと認められる一定距離以内に一定時間以上一緒に居た人(Bさん、Cさん、Dさんたち)のスマホにその旨の通知が届くというもの。 このシステムが効力を発揮するためには、人口の8割程度までがこのアプリを利用する必要があるらしいが、現状は5%程度が利用しているに過ぎないらしい。 (COCOA画面) (同上) 陽性と診断されたAさんがその情報をこのアプリに登録しなければ、始まらないのであるが、それさえ行っていただければ、B、C、Dさんたちにはすぐに、何処で誰とかなどは分からないが、陽性と診断された人と濃厚接触があったことの知らせが行くというものである。 B、C、Dさんたちは、この通知に従って、すぐにPCR検査を受けるように行動を起こせるほか、自身も感染の疑いありということで行動に気を付けることができて、更なる感染の拡大に対して一定の歯止め的効果が期待できるという次第。 これの利用者がもっと増えるといいと思うが、それほどに話題にならないのは残念な気がする。<追記>本日(17日)の東京、大阪の新規感染者は以下の通り。 東京:293人(過去最多) 大阪: 53人
2020.07.17
コメント(2)
-

銀輪散歩・マンホール(その16)
マンホールの写真のストックが34枚にもなっていました。 昨年4月の銀輪散歩・マンホール(その12)で、岬麻呂氏から頂戴した北海道陸別町のマンホールカードより撮影のもの1枚を掲載したのが皮切りで、以後、岬麻呂氏から次々とマンホールカード、マンホールの写真が届くということもあって、従来、銀輪散歩の片手間に撮影したものを集めて掲載していたこのシリーズの記事であったものが、岬麻呂氏提供というものが付け加わることとなり、記事アップ回数・掲載写真点数が急増することとなりました。<参考>岬麻呂旅便り234・道東 2019.3.5.2017年 記事件数2件 掲載マンホール点数47点2018年 記事件数2件 掲載マンホール点数61点2019年 記事件数3件 掲載マンホール点数99点(49点)2020年 記事件数2件 掲載マンホール点数75点(58点)※2020年は7月14日現在までの数字。※( )は岬麻呂提供関係のもの、内数である。<参考>過去の「銀輪散歩・マンホール」の写真はコチラ 過去のマンホール関連記事はコチラ という次第で、今回掲載のマンホール写真34点のうち、岬麻呂氏提供ではないのは僅か3点に過ぎませんから、「銀輪散歩・マンホール」というよりも「銀輪三点・マンホール」というのが正しいのでしょうか。 既に、34点中31点は岬麻呂旅便りで紹介済みである。 これでは、もう、銀輪散歩・マンホールの記事は、記事としての意味があるのかという疑問も生まれてまいりますが、余り深くは考えず、前例に従って、(その16)を記事アップすることといたします。(注)★は、岬麻呂氏提供のマンホールカードを撮影したもの。 ●は、岬麻呂氏撮影のもの。(以下同じ)1.北海道上川郡東神楽町のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)2.北海道旭川土木現業所のマンホール(●)※同じ図柄の小樽土木現業所のマンホールは(その5)に掲載。3.富良野市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)※このデザインのマンホール写真(furano-craft氏撮影)は(その12)に掲載済みである。4.稚内市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)5.北海道上川郡和寒町のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)6.北海道上川郡剣淵町のマンホール (左★右● デザインの由来はコチラ) (左カラー版●、右モノクロ版●)(●富山県射水市のマンホール)※剣淵町・射水市の姉妹都市提携を記念して設置されたものとのこと。7.名寄市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)※旧風連町のマンホール8.北海道天塩郡天塩町のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)9.北海道天塩郡豊富町のマンホール(● デザインの由来はコチラ)10.大東市のマンホール ※大東市のマンホールは(その1)にも掲載。11.富田林市のマンホール※富田林市のマンホールは(その3)にも掲載。12.福井市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)13.石川県羽咋郡志賀町のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)(● 旧富来町のマンホール)14.かほく市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)15.福島市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)16.会津若松市のマンホール (左●、右★ デザインの由来はコチラ)17.喜多方市のマンホール (★ デザインの由来はコチラ) (● 松・モノクロ版)18.会津坂下町のマンホール (★ デザインの由来はコチラ) (● モノクロ版)19.仙台市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)※仙台市のマンホールは(その10)も掲載。20.宮城県大河原町のマンホール(★ デザインの由来はコチラ)21.鶴岡市のマンホール(★ デザインの由来はコチラ) (● カラー版) (● モノクロ版)※同じデザインのものを含み鶴岡市のマンホールは(その1)にも掲載。(★デザインの由来はコチラ※加茂地区のマンホール)<追記・参考> 加茂水族館のことが書かれている記事は下記です。 鶴岡銀輪散歩(2)・加茂水族館 2013.5.25.(● 温海地区のマンホール)
2020.07.14
コメント(2)
-

赤い訪問者と黒い訪問者
一昨夜(9日)は赤い訪問者の、昨夜(10日)は黒い訪問者の、訪問を受けました。 赤い訪問者は体長が4mm程度、黒い訪問者は10mm程度と、どちらも小さな虫である。(キウイヒメヨコバイの♂) 赤い訪問者はキウイヒメヨコバイという虫。 書斎の窓の網戸の網目を容易にすり抜けることのできる体のサイズ。 パソコンの横のメモ用紙の上にとまっているのに気づきました。 勿論、名前などは分からなかったのでネットで調べたのであるが、この手の虫は、ウンカ、ヨコバイ、キジラミなどであるから、調べる手がかりがあるというもの。ということで、撮影して写真をPCに取り込んでから、名前を調べて、キウイヒメヨコバイに到達したという次第。(同上) 爪楊枝(使用済みのものを偶々メモ用紙の上に放置していた)の先にとまらせてみると、上のような写真に。その体がいかに小さいのかお分かりいただけると思うが、それだけに撮影はなかなかうまく行かず大変でした。(同上) 何とか撮れたのが、これらの写真であるが、鮮やかな紅色の翅、パンダみたいな目の部分の黒い丸、なかなか可愛らしい虫だ。 胸部背面に3対の黒い紋があるようだが、紅色の翅に隠れてよくは見えない。しかし、上の写真では、うっすらとその黒い斑紋が透けて見える。 もし、これがセミくらいのサイズだったら、子どもたちの人気を集める虫になっていたかもしれない。 この虫は、キウイの葉を吸汁する害虫らしいが、日本人が発見した新種のヨコバイだそうな。 ネットでこんな説明文を見つけたので、それを転載して置きます。東京都病害虫防除所 発生予察情報特殊報 平成7年度第2号より抜粋(1)学名:Alebrasca actinidiae HAYASHI et OKADA (2)和名:キウイヒメヨコバイ(仮称) (3)形態:成虫は体長3~4mm、雌は黄白色、雄は前翅の基方3分の2が緋紅色で日時を経て濃色になる。後翅は翅脈のみが赤い。チャノミドリヒメヨコバイに似る。幼虫は、体長1~3mm、ふ化当初は白色で後に黄白色になる。胸部背面に3対の黒色紋があり、大きくなると目立つ。 (4)生態:神奈川県病害虫防除所の調査によれば、成虫は5月から11月に見られ、年4回程度の発生経過をたどる。卵は葉裏の葉脈内に産み付けられ、ふ化した幼虫は葉裏で直ちに吸汁・食害をはじめる。幼虫は、非常に活発に運動するが、他の葉への移動は少なく、そのため幼虫が多発すると被害が激しくなる。成虫も動きは活発で、主に葉裏に寄生し吸汁加害する。落葉とともに園から見られなくなる。越冬は卵で行われ、枝の芽基部に産み付けられる。翌年4月頃から幼虫は発芽して展葉まもない葉上に現れる。 (5)寄主植物:キウイフルーツに寄生し、それ以外の植物では寄生は確認されていない。 最近は、庭でキウイフルーツの木を植えて居られるお宅もよく見かけるようになったので、この虫も増えて来ているのかもしれないが、こんな赤いヨコバイを見るのは初めてである。 普通よく見るウンカやヨコバイは黄緑色である。 キウイヒメヨコバイもメスや成熟する前のオスは薄い黄褐色だそうだが、オスは成熟するに伴って、翅がこのように濃い紅色に変色するのだという。(同上) 撮影が終わった後、何処かへ飛んで行ってしまったので、行方不明となりました。何しろ小さいので、目を離すともう行方知れずなのである。 次の黒い訪問者は、翅を持った黒いアリである。 これは、体長が10mm程度のやや大きい目のアリであるから、網戸の網目をすり抜けて部屋に侵入することは出来ないはず。どこの隙間から侵入したものか。 激しく動き回るのと、翅で飛んで行ってしまうことも懸念されたので、捕獲してティシュに包み込んで、しばらくその中の狭い空間でおとなしくしていてもらうことにする。PCでの作業を30分ほどしてから、そっとティッシュを開くと、アリさんはおとなしくなっていました。 撮影開始。(翅蟻 クロオオアリ) 白い世界に包まれて混乱したのも束の間、今はもうすっかり落ち着いたようで、ティッシュの凸凹を探りつつ、ゆっくりと動き回る。 アリも色々な種類が居るが、これはクロオオアリだろうと思う。(同上) ティッシュがいいアングルを作ってくれるので、面白い写真が撮れる。(同上) 翅があるアリは女王アリと女王アリと交尾するためのオスのアリだと思うが、オスのアリは交尾すると間もなく死ぬそうだから、これは女王アリで、何処かで新しい巣を地中に作り、卵を産むつもりで、飛び回っていたのかもしれない。(同上) うろうろ動き回るものの、翅で飛び立つ気配がないから、そろそろ卵を産める場所を探す段階に来ているのかもしれない。 しかし、ティッシュは彼女の辞書にはないだろうから、「ここは一体なんなの。」と少し慌てているのかも。(同上) 余りアリをからかうのも、いい趣味とは言えないから、撮影終了。ベランダから外に向かって、ティッシュに「フーッ」と強く息を吹きかける。 アリさんは吹き飛ばされて、暗い庭の地面へと消えて行きました。 着地した我が庭先で新居の巣を構えられても困るというものであるが、考えてみれば、左程に困るということでもないから、彼女の意のままに任せましょう(笑)。(同上) 赤い虫がオスで、黒い虫がメス。 何だか逆のような色具合でしたが、赤と黒の彼らは今頃は何処でどうしているのやら。 わが庭にはキウイの木はないのであるが、赤いキウイヒメヨコバイはオスだから、卵を産むべき木がなくても関係ないか。 クロオオアリの女王は雨で濡れた庭の土を掘り返して、地中深くに卵を産んでもいるか。 されば、アリにとってもヒトにとっても、この後、余り雨が降り過ぎないのが一番、そのことを祈りましょう。
2020.07.11
コメント(2)
-
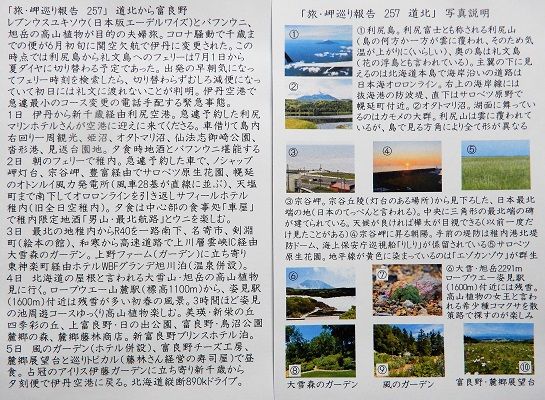
岬麻呂旅便り257・道北から富良野
ヤカモチがアシナガキンバエと遊んでいるうちにも、岬麻呂氏は北海道への旅に出て居られたようで、本日、その旅便りが届きました。 今回は、「レブンウスユキソウとバフンウニ、旭岳の高山植物が目的」のご夫婦旅とのことでしたが、出発当日になって、礼文島へのフェリーが欠航になっていることに気がつかれて、出発の伊丹空港で急遽コース変更の電話手配をされるなどの「緊急事態」もあったりの、7月1日~5日(4泊5日)の旅であったようです。(旅・岬巡り報告257・道北から富良野&同写真説明) 上記の「報告257」の記載に従い、別途メールで送信いただいた写真をご紹介することとします。 北海道縦断890kmのドライブ旅であります。7月1日伊丹空港→新千歳経由利尻空港→姫沼→オタトマリ沼→仙法志御崎公園→沓形港→見返台園地→利尻マリンホテル(泊) 先ずは、機上からの利尻島、利尻富士遠望であります。(↑利尻島 ※写真説明1の写真)(↑利尻富士とオタトマリ沼 ※写真説明2の写真)(↑エゾカンゾウ)7月2日フェリーで稚内へ→ノシャップ岬灯台→宗谷岬→豊富経由→サロベツ原生花園→幌延・オトンルイ風力発電所→天塩町→(オロロンライン)→稚内・サフィールホテル稚内(泊)(↑ノシャップ岬灯台)(↑宗谷岬 ※写真説明3の写真)(↑サロベツ原野・黄色の花はエゾカンゾウ ※写真説明5の写真)(↑北防波堤ドーム)<追記>岬麻呂氏より下の写真が送信されて参りましたので、追加で掲載します。(↑オトンルイ風力発電所)※岬麻呂氏からのメールによると「オロロンライン沿いに設置されていまして・・(中略)天塩町役場にマンホールカードをもらいに行く往復で撮影しました。」とのことです。 今回も、見かけられたマンホールを撮影下さってその写真を送信いただきました。また、マンホールカードも入手下さり、これはブロ友のひろみちゃんへのものですが、旅便りに同封下さいました。 これらも併せご紹介します。 ヤカモチの勝手推量ですが、行程に照らして、取得・撮影されたのではないかと思われる日に合わせてご紹介します。 この日に取得されたのは、多分、稚内市、豊富町、天塩町のマンホールカードではないかと思います。(↑稚内市のマンホールカード)(↑豊富町のマンホールカード)(↑天塩町のマンホールカード)7月3日稚内→(R40南下)→名寄市→剣淵町(絵本の館)→和寒町→上川層雲峡IC経由→大雪森のガーデン→上野ファーム→東神楽町経由→ホテルWBFグランデ旭川(泊)(↑宗谷岬の日の出 ※写真説明4の写真)(↑名寄市<旧風連町地区>のマンホールカード)(↑風のまちマンホールマップ)(↑絵本の里けんぶち町マンホールマップ)(剣淵町のマンホールA)(↑同上マンホールカード)(剣淵町のマンホールB)(↑同上C)(追記・注)※上掲のマンホール蓋は、剣淵町と姉妹都市提携関係にある富山県射水市のもので、姉妹都市関係を記念して特別に設置されているらしい。(↑同上D<モノクロ版>) マンホールカードではありませんが、松浦武四郎関連の、こんなカードも同封されていました。 (↑テッシ武四郎カード 剣淵と和寒)<参考>松浦武四郎・Wikipedia(↑和寒町のマンホールカード)(↑大雪森のガーデン ※写真説明8の写真)(↑東神楽町のマンホールカード)(↑旭川土木現業所のマンホール)7月4日大雪山・旭岳の高山植物を見に、ロープウェイ山麓駅→同姿見駅→姿見の池周遊コース散策→美瑛・新栄の丘、四季彩の丘→上富良野・日の出公園→富良野・鳥沼公園→麓郷の森(木力工房)→麓郷藤林商店→新富良野プリンスホテル(泊)(↑大雪・旭岳 ロープウェイ姿見駅付近から ※写真説明6の写真)(↑コマクサ ※写真説明7の写真) ブロ友のfurano-craftさんの木力工房、富良野麓郷庵(富麓庵)もお訪ねになられたようで、furano-craftさんはお元気にされていたとのこと。(↑麓郷の森 木力工房)(↑富良野市のマンホールカード)7月5日風のガーデン→富良野チーズ工房→麓郷展望台→トピカル(昼食)→占冠・アイリス伊藤ガーデン→新千歳空港→伊丹空港(↑風のガーデン ※写真説明9の写真)(↑富良野・麓郷展望台 ※写真説明10の写真)<参考>過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。同上・岬麻呂マンホールカード写真集はコチラ。 以上、岬麻呂旅便り記事でした。
2020.07.09
コメント(10)
-

アシナガバエ
アシナガバチというのは知っていたが、ハエにもアシナガバエというのがいるようです。 その仲間で金緑色の小さな奴がアシナガキンバエ。 普通、キンバエというと普通サイズのハエで金緑色の体をしている奴で糞などによくたかっているという印象があるので、ちょっとノーサンキューなハエであるが、このアシナガキンバエというのは体長が5mm程度の小型のハエで、アブラムシやダニなどの虫を捕食する益虫らしい。 その名の通り、足の長いハエである。(アシナガバエの仲間、アシナガキンバエか。)<参考>アシナガバエ・Wikipedia(同上) アシナガバエと言っても多くの種類がいるそうです。 世界では約240属7000種に及び、日本では12属60種が記録されているという。 アシナガキンバエ、というのも何やら曖昧な名前のようで、これがアシナガキンバエであるというようなことには必ずしも明確になっていないのか、ネットで調べてもイマイチよく分からないというのが実情です。<参考>アシナガキンバエ・身近な昆虫図鑑(同上) 小さい虫なので、ズームで撮る必要があるところ、活発に動きまわることもあって、なかなかうまく行かない。しかし、遠くへ飛び去るということはなく、隣の葉に飛び移る程度なので、またカメラを構えて、その姿を追ってしまうのでありました。 そんなことを何度か繰り返して撮ったのがこれらの写真ですが、何やらハエにからかわれていたような気もしないではない(笑)。(同上) ハエだけでは、手抜き記事だろう、という声がかかりそうですから、アベリアの花に遊ぶキアゲハの写真でも・・まあ、こんなことを言っていては、自ら「手抜き」を自白しているようなものですな(笑)。(アベリアの花とキアゲハ) 以上、虫散歩記事でありました。<参考>過去の虫関連記事はコチラ。
2020.07.08
コメント(2)
-

墓参・花散歩的実散歩
昨日(4日)は月例の墓参。 いつもの坂道にさしかかると、ギンバイカの木が庭先にある民家の前。 先月の墓参の折には純白の花を咲かせていた木であるが、既に花はすべて散ってしまったようで、実らしきものが膨らみ始めていました。(ギンバイカ) 先月(6月5日)の墓参では、花が咲き始めで(下掲写真参照)、ブログ記事を見ると、ももの郎女さんへの返事コメントでは「間もなく満開の時期を迎えるでしょうから、近々に再訪問してみます。」などと書いているが、すっかりそのことは忘れていたようで、花の盛りは見ないままになってしまいました。(ギンバイカの花・6月5日記事掲載写真の再掲載)<参考>墓参・花散歩ほぼ白い花 2020.6.5.(同上) 花の盛りは見落としたが、今度はこの実がどのように熟れて行くのかを見届けることにしよう。 熟して黒紫色になると食べられるらしい。 他人様の庭先の木であるから、見るだけ、味見をする気はありませぬ。 さらに少し上ったところの民家の庭先に咲いていたのはこんな花。(名前不詳の黄色の花) 面白い形の花である。(同上) 多分、初めて目にする花である。<追記>上の花、名前が判明しました。 学名:アスクレピアス・ツベロサ(Asclepias tuberosa) 和名:ヤナギトウワタ(柳唐綿) <参考>アスクレピアスとは・植物の育て方図鑑ヤサシイエンゲイ アスクレピアス(トウワタ)の育て方・ガーデニングの図鑑 さらに少し上ると、門前の言葉の寺、教覚寺である。(教覚寺) 昨年の9月頃から始まった改修工事も、漸くに終盤です。 塀も綺麗に仕上げ塗装が施され、新しい門も完成したようです。(同上・門) 山号や寺名を記した額がまだ掲示されていないし、従来、門の右側の塀には掲示板が設置されていて、そこに「門前の言葉」が掲出されていたのであるが、それも未設置であるから、まだ完成とは言えないのだろう。 どんな風になるのかは、来月の墓参の折の楽しみということになる。 そして、墓地に到着。(墓地)(墓地から、あべのハルカスを望む) 天気予報では「曇り・雨」で一応傘持参の墓参であったが、往復、雨に降られることはなし。しかし、空はどんよりした梅雨空にて、六甲山や淡路島の影は見えずでありました。 墓参の記事は、銀輪散歩などで見かけた花、植物などの写真を併せ掲載するということが多いのであるが、今回もそのパターンの記事とします。 先ずは、クチナシの花。(クチナシ) クチナシの花期も過ぎたようで、この一輪だけが咲き残っていました。 ひとり遅れて咲くのは冬の庭の白菊というのが相場であるが、クチナシもひとり遅れて咲きたるは、何やら寂しくものの哀れを感じさせて、ついカメラを向けてしまった次第。ここぞと沢山に咲いていた時には見向きもしなかったのに・・人の心とは妙なものである。 そのクチナシのつづきに植わっていたニシキギの木が沢山の実をつけていました。 ニシキギの花も目立たない小さな地味な花であるが、実を見るのは初めてではないかと思って、過去記事を調べたら、2009年10月10日の記事に、その実の写真が掲載されていました。<参考>銀輪・秋の実散歩 2009.10.10.(ニシキギの実) 上の写真のように、カエデの実に似た形です。 カエデの実は翼果である。 ニシキギの実もカエデの実と同じ翼果であるとは新発見、などと思ったことから、初めて見たのではないかと思ったのでしたが、これは成熟前の形で平べったい形になっているにすぎず、成熟するとともに丸く膨らみ、やがて丸い普通の形をした実になる。2009年10月10日記事に掲載の写真はそのような丸い形の実であるから、余り印象には残らなかったものと思われる。 その写真のように丸く膨らみ、完熟すると果皮が割れて、中から仮種皮に包まれた赤橙色の種子が現れる。マユミやツリバナの実などとよく似ている。翼果は風で飛ばされて遠くへ運ばれるように翼を持っているのであるが、これはそういう戦略ではなく、小鳥に食べてもらってその糞にまじって遠くへ運んでもらおうという戦略の実なのである。(同上) 翼果かと思ったものだから、カエデの翼果に似た形のものについカメラが向けられたようです。(同上) ニシキギは、スズランノキ、ニッサボク(和名:ヌマミズキ)と並んで世界三大紅葉樹とされる、紅葉の美しい木であるが、早くも色づき始めている葉もチラホラとある。(同上)(同上) ギンバイカの実ではないが、このニシキギの実も成熟して行く姿を観察してみることにするか。 ニシキギの花同様に目立たない小さな花はオリーブの花も同じ。(オリーブの花) 本来は白い花であるが、花の色は移りにけりな、で薄茶色に変化して、花の下にオリーブの実となるべき膨らみができかかっている。 一向に「花散歩」らしき景色にならないので、夏萩でも。(ハギ)(同上) もう一つ、ユリの花の中を覗き込んだ写真があるので、これも。(ユリのめしべ) ふむふむ、ユリの雌蕊とはこんな風になっているのか。 概ね三角形というか、オムスビ型で、角の部分に花粉が付いたようで黄色くなっているから、受粉完了ということか。 ユリのムカゴも見つけました。<参考>むかご・Wikipedia(ユリのムカゴ)(同上) ムカゴは漢字では零余子、珠芽などと書くようだが、こう書いてむかごと読める人はそう多くないだろう。 ムカゴのできるユリはオニユリ、タカサゴユリなどのようで、ムカゴのできないユリの方が品種としては多数派のようだ。(同上) 食用になると言うか、食べることができるらしいが、虫こぶみたいで、余り食べたいとは思わない。(同上)(同上) 以上、墓参兼花散歩的実散歩でした。
2020.07.05
コメント(7)
-

帰り来の知らせうれしみ
昨日はとてもうれしい知らせがありました。 3月7日入院された智麻呂氏ですが、その退院の日が決まったという、奥様の恒郎女さんからのお電話による知らせでありました。 智麻呂氏のご入院のことは、去る5月17日の記事(「ミニ智麻呂絵画展」)で概略ご報告させていただきましたが、4月14日にリハビリ病院に転院されてからのご様子は、ほとんどよくは分からないままに、今日に至って居り、心配して居りました。しかし、漸く退院の目処がついたようで、7月20日が退院日と決まったとのことです。 3月7日の入院日から数えれば、実に4ヶ月と13日の長きにわたる入院生活ということになります。 新型コロナ感染症対策としての面会・見舞い禁止という病院側の措置によって、奥様の恒郎女さんらご家族は勿論、我々若草読書会の仲間も、情報が遮断された状況に、不安とストレスを感じていましたが、退院の日が決まったということで、それらが一気に晴れて、快哉でありました。 退院の日まで、まだ2週間以上もありますが、ともかくも退院の日が決まったということは、智麻呂氏の体調もリハビリの進捗状況も順調であるということが保証されたようなものですから、安堵・安心で、思わず快哉の声が口をついて出るという風でありました。 コロナ禍の中、若草読書会も休止となり、再開をどうするか模索中でありますが、最近はまた、「第2波」襲来かとも懸念される、東京での感染者数の急増という事態に立ち至っていますので、なかなか一筋縄では行かないようです。 そういったことはともかく、とにもかくにも智麻呂氏の退院が実現しなければ、物事は始まらないのでありますから、退院近しの報は、先への希望をつなぐ明るいニュース、うれしい限りでありました。若草の わが待つ君の 帰り来の 知らせ嬉しみ 朝顔の咲く (偐家持)(今年最初に咲いた朝顔)君があたり 見つつや待たむ 生駒山 雲な隠しそ 雨もな降りそ (偐恒郎女)(本歌)君があたり 見つつも居らむ 生駒山 雲なたなびき 雨は降るとも (万葉集巻12-3032)
2020.07.04
コメント(6)
-
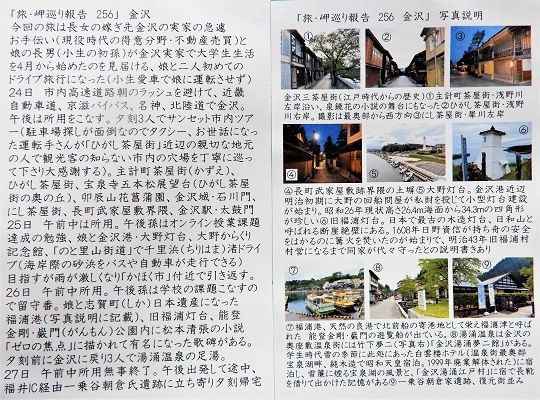
岬麻呂旅便り256・金沢
友人・岬麻呂氏からの旅便りが届きました。 6月24日~27日の金沢、福井の旅ですが、今回は、所用を兼ねての旅にて、いつもの岬麻呂氏の旅とは趣を異にする旅でありました。(旅・岬巡り報告256 金沢&同写真説明) 旅の詳細は、上掲の「旅・岬巡り報告256」をご覧ください。 画面をクリックするとフォト蔵の画面に切り替わり、大きいサイズの写真でご覧いただけます。 以下、同写真説明に掲載の写真9点は、別途メールで送信いただいていますので、これを掲載順に貼り付けて置きます。上の説明文をご参照しつつ、写真をご覧ください。 これらの写真も画面をクリックすると、大きいサイズの写真が別窓で開きます。1.金沢三茶屋街(1)主計町茶屋街(2)ひがし茶屋街 下は、「写真説明」掲載の写真ではありませんが、岬麻呂氏が「お気に入りの風景」とのことで、送ってくださった「ひがし茶屋街の路地裏」の風景写真であります。(3)にし茶屋街(4)長町武家屋敷跡界隈の土塀 以上、(1)~(4)は夕暮れ時を狙った移動で、空の色の暮色が徐々に深くなって行く様が見て取れるという仕掛けのようです。2.灯台など(5)大野灯台 四角形の珍しい灯台。(6)旧福浦灯台 日本で最古の木造灯台とのこと。(7)福浦港3.湯涌温泉(8)湯涌温泉街4.一乗谷朝倉氏遺跡(9)朝倉氏遺跡北入場口 なお、今回も、ブロ友の「ひろみちゃん」氏にお渡し下さいと、マンホールカードが3枚同封されていました。 また、旧富来町(合併されて現在は志賀町の一部になっている)のマンホールも撮影くださったようで、その写真をメール送信くださいました。(旧とぎ町のマンホール) そして、お預かりしたマンホールカード3枚です。(かほく市のマンホールカード)(志賀町のマンホールカード)(福井市のマンホールカード) 明日(4日)はバタバタするので、日曜日(5日)か月曜日(6日)か、ひろみちゃんのご都合の良い日にお渡しすることとしましょう。<参考> 過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。 フォト蔵アルバム・岬麻呂写真集はコチラ。フォト蔵アルバム・岬麻呂氏提供マンホールカードはコチラ。
2020.07.03
コメント(2)
-

ヤカモチ的イヌ歩き・吾輩は犬である
今日から7月。 ということは、今年も半分が過ぎたことになる。 今年半分が過ぎたところで、今年の記事件数は103件。 この記事が104件目になる。 去年(2019年)の年間記事件数が184件、2018年・2017年のそれがともに183件、2016年が178件と、この4年間は200件に届かない記事件数が続いていたことを思えば、今年は、今のところ、久々に200件に届きそうなペースですから、まあ、頑張っていることになるか。 とは言え、そろそろ記事ネタも尽きて、記事を書く意欲もいささか減退気味になっていますので、後半戦もこのペースで記事アップできるのかどうか、それが問題であります。 で、今日も、コレというネタがありませんので、銀輪散歩で見かけた犬たちでも紹介することにします。 ペットフード協会の調査によると、2019年10月現在、ペットとして飼われている犬は、日本全国で約879万匹で、猫は約977万匹だという。 2016年までは犬の方が上回っていたが、2017年に猫に逆転され、以来、犬は猫の後塵を拝しているのだそうな。 このところ、ヤカモチ的ネコ歩きなどと猫が登場することが多くなっていますが、今日はヤカモチ的イヌ歩きとし、犬にご登場いただくこととしました。まあ、ここでもネコの後塵を拝していることに違いはありませんが。 先ずは、花園中央公園で見かけた犬です。(花園中央公園のドッグランで見かけた犬)(同上) リードにつながれていない犬の写真が撮れる場所と言うと、公園のドッグランであるが、ヤカモチが知るドッグランのある公園と言えば、花園中央公園と深北緑地である。 それはさて置き、ドッグランと言うだけあって、ここではどの犬も結構、走り回る。従って、遠方からのズーム撮影はかなり苦労である。 次は、同じ花園中央公園の桜広場で見かけた犬。 散歩を済ませて、飼い主に引かれてお帰りのようであります。(花園中央公園桜広場で見かけた犬) 次は深北緑地で見かけた柴犬。 首輪とリードの色からして雌犬のようですね。(深北緑地で見た柴犬) こちらは、オスの柴犬。 加納緑地で見かけました。(加納緑地で見た柴犬) 次は、長田中公園で見かけた犬。 ちょっと太りすぎかも。(長田中公園で見かけた犬)(同上) 以上、ヤカモチ的イヌ歩き・吾輩は犬である、でありました。
2020.07.01
コメント(2)
全16件 (16件中 1-16件目)
1










