吉備路自転車散歩の記事が長引いてアップが遅れましたが、本日は僧正遍昭のお墓参りの記事であります。
僧正遍昭の墓は山科にある。地図を見て居てたまたま目についたので訪ねてみることにしたもの。
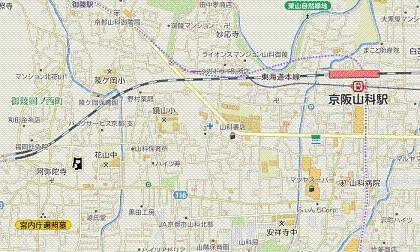
(阿弥陀寺の右上の黒く塗りつぶされた処が元慶寺)
遍昭墓は、山科駅から2.5km位の距離にある。
山科駅から南に延びている道(外環状道路)を南下、三条通りの交差点の一つ南の外環渋谷交差点で右折、府道116号(渋谷街道)を西へ行く。北花山交差点(角に阿弥陀寺がある。)を左に入る。120m位で道の左側、奥まった処に墓がある。住宅の立ち並ぶ一角なので、注意していないと通り過ぎてしまう。小生も実は通り過ぎてしまい、引き返して見つけた次第。
墓は宮内庁の管理のようだが、草茫々。天皇陵と違って手入れは行き届かないということでしょうか。
遍昭さんと言えば、先ず小倉百人一首のこの歌でしょうな。
天つ風 雲のかよひ路 ふきとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ
(古今集巻17-872 小倉百人一首12)
<空吹く風よ、天女が通る天上への通路をお前の力で雲を吹き寄せて閉ざしてくれ。この美しいおとめの舞姿をもうしばらく地上にとどめて置きたいから。>
この歌は仁明天皇の時代、遍昭がまだ良岑宗貞 (よしみねのむねさだ)
という名で仁明天皇に仕えていた時に作った歌。古今集の詞書に「五節舞姫を見てよめる」とある通り、宮中での新嘗祭に際して舞われる少女達の舞を見て詠んだ歌である。
古今集仮名序で「僧正遍昭は歌のさまは得たれどもまこと少なし。たとへば、絵にかける女を見て、いたづらに心動かすがごとし」とこきおろされている遍昭であるが、名を上げてこきおろされたことで六歌仙になっているのだから、これもよしとしなくてはなるまい。
名を上げて言及されるということのなかった六歌仙以外の人々については「この外の人は・・・歌とのみ思ひて、その様知らぬなるべし。」とバッサリ切り捨てられているのだから(笑)。
さて、話は変るが一昨年の冬に銀輪散歩で奈良県天理市を訪れた際に、遍昭と小野小町が交わした歌を刻んだ歌碑を目にしたが、それはこのようなもの。
いそのかみ 旅寝をすれば いと寒し
苔の衣を われにかさなむ (小町)
世をそむく 苔の衣は ただ一重
かさねばうとし いざふたり寝む (遍昭)
墓の前での話題としては適切を欠く気もするが、小町さんのもとへの百日通いの深草の少将は遍昭がモデルだとの伝説もあるようなのは、このような歌がのこされているからでしょうか。
<参考> 「天理から奈良へ銀輪散歩(その1)」
2011.1.15.
なんで坊主の墓を宮内庁が管理しているのだとお思いかも知れませぬが、彼は桓武天皇の孫に当るということでもあるからでしょう。
<参考> 遍昭
・Wikipedia
遍昭の墓から北花山交差点に戻り、角の阿弥陀寺から東へ120m程、府道116号を戻った処で左に入ると元慶寺という寺がある。
境内に遍昭の歌碑があるので立ち寄ってみる。
この寺は遍昭開基の寺。花山天皇が此の寺で出家したと伝えられる。「大鏡」では花山院の出家した寺は花山寺と記されているが、この辺りの地名が花山であるから、当時は「花山寺」と一般には呼ばれていたのだろう。
<参考> 元慶寺
・Wikipedia
 (同上碑)<参考> 花山天皇
・Wikipedia
(同上碑)<参考> 花山天皇
・Wikipedia
遍昭の歌碑の歌は上の「天つ風・・」の歌なので、隣にある遍昭の息子の素性法師の歌碑の歌を紹介して置きましょう。
こちらも百人一首でお馴染の歌ですな。
いまこむと いひしばかりに 長月の
ありあけの月を まちいでつるかな
(古今集巻14-691 小倉百人一首21)
<もうすぐ行くと仰ったので、秋の夜長を待ち続けて、九月の長い夜のありあけの月が出るまでお待ちしてしまいました。>
この歌は女性の立場に立って作られた恋歌ですな。
この歌は父親の遍昭の次の歌を本歌としている。
今こむと いひてわかれし
朝
より 思ひくらしの
音
をのみぞなく
(遍昭 古今集巻15-771)
素性法師の俗名は良岑玄利 (よしみねのはるとし)
。遍昭が在俗の時にもうけた子供である。三十六歌仙の一人。
素性
・Wikipedia
遍昭を たづねしぐれぬ 秋の道 (筆蕪蕉)
本日は遍昭遍路の記事でありました。
PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
 New!
龍の森さん
New!
龍の森さん思い出の佐賀へ(その…
 New!
MoMo太郎009さん
New!
MoMo太郎009さんいよいよ 忘年の候 New! lavien10さん
竹遊びその後 New! ふろう閑人さん
美味しくて嬉しい頂… New! ひろみちゃん8021さん
恥をかく寸前
 New!
ビッグジョン7777さん
New!
ビッグジョン7777さん東京タワー
 New!
七詩さん
New!
七詩さんキャラメルアイス
 New!
☆もも☆どんぶらこ☆さん
New!
☆もも☆どんぶらこ☆さん吉松隆 大河ドラマ … くまんパパさん
晴のち曇ブログ fusan2002さん




















