春の弘前城さくらまつり
私やまんばが撮影した、弘前城さくらまつりの写真です。
写真をクリックして頂けると、写真販売サイトへ移動します。もしよろしかったらお買い求め下さいませ!
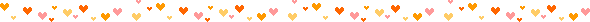
写真をクリックして頂けると、写真販売サイトへ移動します。もしよろしかったらお買い求め下さいませ!
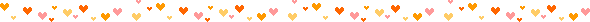

弘前城弘前公園への入り口のひとつ、追手門です。外堀にかかる桜と、水面に浮かぶ花びらとの組み合わせが絶妙な、人気スポットです。 |

弘前城弘前公園「追手門」です。色の濃いしだれ桜。追手門に切り取られた向こうの桜もまた綺麗。お互いに映えますね。 |

弘前城弘前公園を追手門から入ってすぐの「杉の大橋」です。真っ赤な欄干が素敵です。 |

弘前城弘前公園の内堀を渡る手前に、立派な枝垂桜が出迎えてくれます。ソメイヨシノより濃いピンク色が目に鮮やかな、美しい大木です。 |

満開の桜と、弘前城の本丸、真っ赤な下乗橋を、一気に眺められる人気スポットです。 |

お堀に垂れる満開の桜、弘前城の本丸、真っ赤な下乗橋を望む絶好のスポットで撮影しました。 |

下乗橋のそばから、眺めた弘前城天守閣と内堀です。撮影は2014年。石垣修理のため内堀が埋められるので、この景色はしばらく見られません。 |

下乗橋を過ぎたところの小さな庭園越しに見える、桜の弘前城天守閣です。ピンク色と緑色のコントラストが綺麗です。 |

下乗橋を過ぎたところの小さな庭園越しに見える、桜の弘前城天守閣です。ピンク色と緑色のコントラストが綺麗です。 |
弘前城(ひろさきじょう)
は、青森県弘前市にあるお城です。
弘前藩 (津軽藩は通称らしいです)の祖、 津軽為信(つがる ためのぶ) 公が鷹岡に築城を開始するものの京都で亡くなり、一時中断されてしまいます。その後、2代目信枚(信牧)が築城を再開、1611年(慶長16年)にようやく完成します。
別名、鷹岡城(高岡城)とも呼ばれ、城跡は国の史跡に指定されています。
現在、全国屈指の桜の名所として慕われる弘前公園。
桜の植樹が行われたのは「1903年(明治36年)以降のこと」と書かれたものもありますが、「一般財団法人 弘前市みどりの協会」の情報ではそれより前、明治15年に ソメイヨシノ が植えられました。(「 弘前公園と植栽の歴史 」より)
弘前城内への桜の植樹の歴史はさらに遡り 1715年(正徳5年) ! 300年以上も昔に京都からカスミザクラ、関山(かんざん)、正徳桜など桜の苗木25本を持参し、植えたのが始まりでした。(「 桜 (サクラ) | 弘前公園総合情報 」より)
( 弘前さくらまつり | 弘前公園総合情報 」参照)
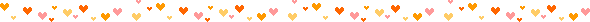
○「 日本最古のソメイヨシノ 」と言われる推定樹齢140年の桜は、「二の丸与力番所~東内門の間」に立ち、これが 菊池楯衛 が植えた最初の桜の生き残りの一本であると言われています。
○「日本最大幹周のソメイヨシノ」と言われる推定樹齢100~120年、主幹幹周5.37m、樹高10mの桜は、「緑の相談所裏」に立ち、これも上の桜と同時期に植えられたと思われるのですが、詳細は不明だそうです。
(「 弘前公園の古木名木 」より)
しかし、他にも 福島県郡山市開成の開成山公園 に「日本最古のソメイヨシノ」を謳う桜があり、 明治11年 に植えられたと樹齢調査で分かったそうです。(「 日本最古級のソメイヨシノを見に行こう!|郡山市観光協会 」より)
現在、弘前公園には ソメイヨシノ 、 シダレザクラ など 約50種2,600本 の桜が咲き誇ります。(56種類?)(「 弘前公園で見られる桜の種・品種 」より)
毎年春に行われる 弘前さくらまつり は「 日本さくら名所100選 」、「 人と自然が織りなす日本の風景百選 」に選ばれています。
「 たか丸くん 」は、「弘前城築城400年祭」のイメージキャラクターとして誕生したゆるキャラです。鷹岡城の鷹がモデルで、弘前城をのせた兜に、津軽為信の前立てをあしらっています。
弘前藩 (津軽藩は通称らしいです)の祖、 津軽為信(つがる ためのぶ) 公が鷹岡に築城を開始するものの京都で亡くなり、一時中断されてしまいます。その後、2代目信枚(信牧)が築城を再開、1611年(慶長16年)にようやく完成します。
別名、鷹岡城(高岡城)とも呼ばれ、城跡は国の史跡に指定されています。
現在、全国屈指の桜の名所として慕われる弘前公園。
桜の植樹が行われたのは「1903年(明治36年)以降のこと」と書かれたものもありますが、「一般財団法人 弘前市みどりの協会」の情報ではそれより前、明治15年に ソメイヨシノ が植えられました。(「 弘前公園と植栽の歴史 」より)
弘前城内への桜の植樹の歴史はさらに遡り 1715年(正徳5年) ! 300年以上も昔に京都からカスミザクラ、関山(かんざん)、正徳桜など桜の苗木25本を持参し、植えたのが始まりでした。(「 桜 (サクラ) | 弘前公園総合情報 」より)
1715年(正徳5年) 藩士が京都から 桜の苗木を25本
持参( カスミザクラ
、 関山(かんざん)
、 正徳桜
が今も残っています)
1869年(明治2年) 版籍奉還
1873年(明治6年) 廃城令発布により廃城処分とされ、この後、本丸御殿や武芸所等が取り壊される7
1880年(明治13年) 旧藩士の 内山覚弥 が城内が荒れ果てたのを見かね、自費で 桜20本 を植栽(三の郭)
1882年(明治15年) 旧藩士(山林取締役兼樹芸方) 菊池楯衛 が内山の話を聞き、ソメイヨシノ(吉野桜)1000本を寄贈・植栽(西の郭、二の丸を中心に)(新編弘前市史通史編4(近・現代1)によると、当時は「城の中に桜を植えて、花見酒などとはもってのほか」との批判もあり、切られたり、引き抜かれたり、ほとんどは成木にならなかった。)
1894年(明治27年)旧藩主津軽氏が城跡を市民公園として一般開放するため、城地の貸与を願い出て許可される。
1895年(明治28年) 弘前公園開園
日清戦勝記念として、 内山覚弥 が ソメイヨシノ100本 を寄贈。(さらに市会議員の在任中、桜の植栽による公園美化を訴え続けた)
1901~3年(明治34~36年) 内山覚弥 (旧藩士、市議)の提案により ソメイヨシノを1000本 植栽(大正天皇の結婚記念として、本丸、二の丸、西の郭一帯に)(700本は市が負担し、300本は内山が寄付したとも)
1914年(大正3年) 弘前市在住の宮城県人会が シダレザクラ を寄付
1916年(大正5年) アーク灯やイルミネーションをつけての夜桜見物が話題に
1918年(大正7年) 観桜会 が行われる( 福士忠吉 は第1回観桜会開催発起人の1人。市会議員を務めた際には公園の桜による観光振興を訴えたという)
(太平洋戦争により一時期中断)
1947年(昭和22年) 観桜会を再開
1952年(昭和27年) 国史跡指定「津軽氏城跡弘前城跡」
明治時代に植栽された桜が目に見えて衰えてきた昭和20年代ごろ、サクラの管理が本格的に行われるようになり、リンゴ栽培をお手本とした管理方法で次第にサクラは蘇りました。その管理方法は「弘前方式」と呼ばれます。
1956年(昭和31年) 元市議 福士忠吉 が7年木 ソメイヨシノ1300本 寄付(市は限られた予算内で補植に取り組んできたが、その窮状に手を差し伸べたのが福士忠吉)
1961年(昭和36年) 「弘前さくらまつり」と改称
1968年(昭和43年) 市内ライオンズクラブが本丸に ヤエベニシダレ を寄付
1973年(昭和48年) 県緑化推進委員会が ソメイヨシノ95本 、八重桜50本寄贈(外濠、二の丸)
1975年(昭和50年) 開園80周年記念で 昭和桜24本 植栽(三の丸)
1985年(昭和60年) 開園90周年で 八重桜11種25本 植栽(三の丸)
1869年(明治2年) 版籍奉還
1873年(明治6年) 廃城令発布により廃城処分とされ、この後、本丸御殿や武芸所等が取り壊される7
1880年(明治13年) 旧藩士の 内山覚弥 が城内が荒れ果てたのを見かね、自費で 桜20本 を植栽(三の郭)
1882年(明治15年) 旧藩士(山林取締役兼樹芸方) 菊池楯衛 が内山の話を聞き、ソメイヨシノ(吉野桜)1000本を寄贈・植栽(西の郭、二の丸を中心に)(新編弘前市史通史編4(近・現代1)によると、当時は「城の中に桜を植えて、花見酒などとはもってのほか」との批判もあり、切られたり、引き抜かれたり、ほとんどは成木にならなかった。)
1894年(明治27年)旧藩主津軽氏が城跡を市民公園として一般開放するため、城地の貸与を願い出て許可される。
1895年(明治28年) 弘前公園開園
日清戦勝記念として、 内山覚弥 が ソメイヨシノ100本 を寄贈。(さらに市会議員の在任中、桜の植栽による公園美化を訴え続けた)
1901~3年(明治34~36年) 内山覚弥 (旧藩士、市議)の提案により ソメイヨシノを1000本 植栽(大正天皇の結婚記念として、本丸、二の丸、西の郭一帯に)(700本は市が負担し、300本は内山が寄付したとも)
1914年(大正3年) 弘前市在住の宮城県人会が シダレザクラ を寄付
1916年(大正5年) アーク灯やイルミネーションをつけての夜桜見物が話題に
1918年(大正7年) 観桜会 が行われる( 福士忠吉 は第1回観桜会開催発起人の1人。市会議員を務めた際には公園の桜による観光振興を訴えたという)
(太平洋戦争により一時期中断)
1947年(昭和22年) 観桜会を再開
1952年(昭和27年) 国史跡指定「津軽氏城跡弘前城跡」
明治時代に植栽された桜が目に見えて衰えてきた昭和20年代ごろ、サクラの管理が本格的に行われるようになり、リンゴ栽培をお手本とした管理方法で次第にサクラは蘇りました。その管理方法は「弘前方式」と呼ばれます。
1956年(昭和31年) 元市議 福士忠吉 が7年木 ソメイヨシノ1300本 寄付(市は限られた予算内で補植に取り組んできたが、その窮状に手を差し伸べたのが福士忠吉)
1961年(昭和36年) 「弘前さくらまつり」と改称
1968年(昭和43年) 市内ライオンズクラブが本丸に ヤエベニシダレ を寄付
1973年(昭和48年) 県緑化推進委員会が ソメイヨシノ95本 、八重桜50本寄贈(外濠、二の丸)
1975年(昭和50年) 開園80周年記念で 昭和桜24本 植栽(三の丸)
1985年(昭和60年) 開園90周年で 八重桜11種25本 植栽(三の丸)
( 弘前さくらまつり | 弘前公園総合情報 」参照)
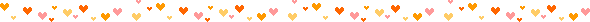

弘前公園 杉の大橋 |

下乗橋から眺める弘前城 |

桜の弘前城天守閣 |

弘前城 亀の甲門と亀甲橋 |
|---|---|---|---|

弘前城 天守閣 |

弘前城 天守閣 |

弘前城 亀の甲門 |
|

弘前城 内濠 2015年春 |

弘前城 南内門 |

弘前城 東門 |
|

弘前城 東門 |

弘前城 東門 |

弘前城 天守閣のしゃちほこ |
|

弘前城 追手門 |

桜の弘前城天守閣 |
○「 日本最古のソメイヨシノ 」と言われる推定樹齢140年の桜は、「二の丸与力番所~東内門の間」に立ち、これが 菊池楯衛 が植えた最初の桜の生き残りの一本であると言われています。
○「日本最大幹周のソメイヨシノ」と言われる推定樹齢100~120年、主幹幹周5.37m、樹高10mの桜は、「緑の相談所裏」に立ち、これも上の桜と同時期に植えられたと思われるのですが、詳細は不明だそうです。
(「 弘前公園の古木名木 」より)
しかし、他にも 福島県郡山市開成の開成山公園 に「日本最古のソメイヨシノ」を謳う桜があり、 明治11年 に植えられたと樹齢調査で分かったそうです。(「 日本最古級のソメイヨシノを見に行こう!|郡山市観光協会 」より)
「52品種約2600本もの多彩な桜が存在する弘前公園は、 桜全体の65%をソメイヨシノが占める
。 樹齢100歳を超えたものに至っては400本を超え
、歴史を重ねたソメイヨシノが若木に負けないほどの花を毎年咲かせている。
ソメイヨシノの〝寿命60年説〟がにわかにささやかれ出したのは明治時代に植栽された桜が目に見えて衰えてきた昭和20年代ごろ。そして、それは弘前公園も例外ではなかった。
「桜切る馬鹿(ばか)、梅切らぬ馬鹿」の定説が当たり前に信じられていた。桜は切り口から病気が入りやすく、強い剪定は御法度とされていた。ところが公園管理事務所(現・市公園緑地課)のある作業員が、実家がリンゴ農家で、弱るシダレザクラを見かねて 枝をばっさり強剪定し、根元に肥料を入れてしまった 。だが、翌年には切り落とした枝先から若芽がひょっこりと顔をのぞかせ、徐々に樹勢が回復。初代所長だった工藤長政氏は、リンゴ農家に教えを請い、自らも研究を開始。桜とリンゴは同じバラ科であり、日本一のリンゴ生産地弘前ならではの「 弘前方式 」が育まれていった。 桜守 の系譜は工藤所長から次の石戸谷恵二郎所長、 小林範士さん へと受け継がれ、 範士(のりお)さんの弟の小林勝さん 、そして現在は チーム桜守 が継承している。」(「 桜と生きて 弘前観桜会100周年by陸奥新報 桜を未来へ 」より)
「1973年に桜の管理を引き継いだ 小林範士さん は92年、 桜の根元を掘り起こし病の根を切り取る「外科手術」 に初めて踏み切った。剪定、施肥、薬剤散布といった枝ぶりを重視した管理から土中にも目を向け、弘前方式を新たな段階へ引き上げた。
勝さん は83年から市公園緑地協会の職員として範士さんを支えた。2000年4月に脳内出血で倒れた兄の後を継いで04年、市職員として公園緑地課に配属。11年12月に高さ16メートルの園内最大のシダレザクラ「二の丸大枝垂れ」が雪の重みと根の病気によって倒れると、 根を再生し増やそうと、別の桜の根や幹を活着させる新手法「根接ぎ」に挑み、成功させた 。」(「 小林 範士さん、勝さん(弘前)-「弘前方式」の管理法確立 : Web東奥・第66回東奥賞 - 東奥日報 」より)
「弘前公園では剪定の後の 枝の切り口を消毒 する時に、 消毒剤に墨汁を混ぜたオリジナルの液 を作り塗っています。切り口に菌がつくことを防ぎ、切り口の見た目の痛々しさもなくしてくれる 弘前独特の手法 です。
枝や幹は雨や雪、風などに曝されるうえに、最近では、酸性雨や排気ガス、桜の木の回りを囲むコンクリートの影響など、木を衰弱させる環境が増えているそうです。枝や幹はもちろん、根の状態、 花の咲き方、花の数、そして、落ち葉の状況まで気を配り、痛んだ木は手当をしてゆきます。 」(「 Botanist13今が盛り、弘前公園の桜を守る「桜守」たち - NOEVIR 」より)
NHK プロフェッショナル 仕事の流儀「桜よ、永遠に美しく咲け 樹木医・小林勝 」(第199回 2013年5月6日放送) )
ソメイヨシノの〝寿命60年説〟がにわかにささやかれ出したのは明治時代に植栽された桜が目に見えて衰えてきた昭和20年代ごろ。そして、それは弘前公園も例外ではなかった。
「桜切る馬鹿(ばか)、梅切らぬ馬鹿」の定説が当たり前に信じられていた。桜は切り口から病気が入りやすく、強い剪定は御法度とされていた。ところが公園管理事務所(現・市公園緑地課)のある作業員が、実家がリンゴ農家で、弱るシダレザクラを見かねて 枝をばっさり強剪定し、根元に肥料を入れてしまった 。だが、翌年には切り落とした枝先から若芽がひょっこりと顔をのぞかせ、徐々に樹勢が回復。初代所長だった工藤長政氏は、リンゴ農家に教えを請い、自らも研究を開始。桜とリンゴは同じバラ科であり、日本一のリンゴ生産地弘前ならではの「 弘前方式 」が育まれていった。 桜守 の系譜は工藤所長から次の石戸谷恵二郎所長、 小林範士さん へと受け継がれ、 範士(のりお)さんの弟の小林勝さん 、そして現在は チーム桜守 が継承している。」(「 桜と生きて 弘前観桜会100周年by陸奥新報 桜を未来へ 」より)
「1973年に桜の管理を引き継いだ 小林範士さん は92年、 桜の根元を掘り起こし病の根を切り取る「外科手術」 に初めて踏み切った。剪定、施肥、薬剤散布といった枝ぶりを重視した管理から土中にも目を向け、弘前方式を新たな段階へ引き上げた。
勝さん は83年から市公園緑地協会の職員として範士さんを支えた。2000年4月に脳内出血で倒れた兄の後を継いで04年、市職員として公園緑地課に配属。11年12月に高さ16メートルの園内最大のシダレザクラ「二の丸大枝垂れ」が雪の重みと根の病気によって倒れると、 根を再生し増やそうと、別の桜の根や幹を活着させる新手法「根接ぎ」に挑み、成功させた 。」(「 小林 範士さん、勝さん(弘前)-「弘前方式」の管理法確立 : Web東奥・第66回東奥賞 - 東奥日報 」より)
「弘前公園では剪定の後の 枝の切り口を消毒 する時に、 消毒剤に墨汁を混ぜたオリジナルの液 を作り塗っています。切り口に菌がつくことを防ぎ、切り口の見た目の痛々しさもなくしてくれる 弘前独特の手法 です。
枝や幹は雨や雪、風などに曝されるうえに、最近では、酸性雨や排気ガス、桜の木の回りを囲むコンクリートの影響など、木を衰弱させる環境が増えているそうです。枝や幹はもちろん、根の状態、 花の咲き方、花の数、そして、落ち葉の状況まで気を配り、痛んだ木は手当をしてゆきます。 」(「 Botanist13今が盛り、弘前公園の桜を守る「桜守」たち - NOEVIR 」より)
NHK プロフェッショナル 仕事の流儀「桜よ、永遠に美しく咲け 樹木医・小林勝 」(第199回 2013年5月6日放送) )
現在、弘前公園には ソメイヨシノ 、 シダレザクラ など 約50種2,600本 の桜が咲き誇ります。(56種類?)(「 弘前公園で見られる桜の種・品種 」より)
 ヤエベニシダレ
ヤエベニシダレ |
* |  ソメイヨシノ
ソメイヨシノ |
* |  十月桜
十月桜 |
 十月桜
十月桜 |
* |  松月
松月 |
* |  松月
松月 |
|---|---|---|---|---|
 ヤエベニシダレ
ヤエベニシダレ |
* |  ヤエベニシダレ
ヤエベニシダレ |
* |  ウコン
ウコン |
「日本の桜の代表としてイメージされることの多い ソメイヨシノ
だが、品種としては実は若手だ。 江戸時代末期
、江戸の郊外にあった 染井村
(現・東京都豊島区)の植木屋が「 吉野桜
」として売り出したのが始まりとされ、明治政府の推奨により、全国に広まったとされている。(「 桜と生きて 弘前観桜会100周年by陸奥新報 桜を未来へ
」より)
花つきがよく、葉が目立たず、成長も早いため全国に広まった。明治時代に入ると分類学の発展に伴い、奈良・ 吉野のヤマザクラとの違い が明らかになり、1900年に「 染井吉野 」の和名が付いた。60年代には雑種だという学説が定着。95年に京都大の研究者らが 全国 で採取した個体の遺伝子を調べ、 全て遺伝的に同じクローン だと分かった。
ソメイヨシノの起源は、 母方がエドヒガン であることは知られていたが、父方は長く決着がついていなかった。日本の野生の桜は10種あり、うち4種は近縁のため遺伝子による親子鑑定が難しい。そこで森林総合研究所多摩森林科学園の勝木俊雄チーム長は、遺伝子の目印を複数組み合わせる手法を使い、2014年に 父方がオオシマザクラ だと突き止めた。
日本の花見は古来、和歌に詠われたヤマザクラが対象だった が、今ではソメイヨシノが主役だ。接ぎ木による栽培で増えてきたが、クローンがこれほど広がるのは異例だ。どの木も遺伝子が同じで均一の性質を持つため、一斉に咲いて散る演出をもたらす。
学術的な価値もある。 開花の様子から 、春の訪れが例年より早いかなどを正確に把握できる。開花時期を示す桜前線は、地球温暖化の影響など 気象変動の理解にも役立っている 。(「 【クローズアップ科学】桜の王者「ソメイヨシノ」 見えてきた起源、クローンの弱点も 」より)」
花つきがよく、葉が目立たず、成長も早いため全国に広まった。明治時代に入ると分類学の発展に伴い、奈良・ 吉野のヤマザクラとの違い が明らかになり、1900年に「 染井吉野 」の和名が付いた。60年代には雑種だという学説が定着。95年に京都大の研究者らが 全国 で採取した個体の遺伝子を調べ、 全て遺伝的に同じクローン だと分かった。
ソメイヨシノの起源は、 母方がエドヒガン であることは知られていたが、父方は長く決着がついていなかった。日本の野生の桜は10種あり、うち4種は近縁のため遺伝子による親子鑑定が難しい。そこで森林総合研究所多摩森林科学園の勝木俊雄チーム長は、遺伝子の目印を複数組み合わせる手法を使い、2014年に 父方がオオシマザクラ だと突き止めた。
日本の花見は古来、和歌に詠われたヤマザクラが対象だった が、今ではソメイヨシノが主役だ。接ぎ木による栽培で増えてきたが、クローンがこれほど広がるのは異例だ。どの木も遺伝子が同じで均一の性質を持つため、一斉に咲いて散る演出をもたらす。
学術的な価値もある。 開花の様子から 、春の訪れが例年より早いかなどを正確に把握できる。開花時期を示す桜前線は、地球温暖化の影響など 気象変動の理解にも役立っている 。(「 【クローズアップ科学】桜の王者「ソメイヨシノ」 見えてきた起源、クローンの弱点も 」より)」
「実は、 奈良時代の花鑑賞といえば梅の花が一般的
でした。その証拠に、奈良時代に作成された万葉集を見ると、桜よりも梅を詠んだ歌のほうが多いんです。梅は約120首あるのに対し、桜は約40首。梅が随分人気だったことがわかります。
花見に桜が愛でられるようになったのは、平安時代 。平安時代に作られた古今和歌集では、梅を詠んだ歌が約30首に対し、桜を詠んだ歌が約60首。奈良時代とは違い、桜と梅の人気が逆転しています。この背景には、遣唐使の廃止が関わっています。 遣唐使が派遣されていた時は、中国文化の影響を強く受けていました。梅の花もその一つ です。しかし、遣唐使が廃止されたことにより、日本独自の文化が発展し始めます。そのため、日本に古くから自生していた桜に注目が集まったわけです。
貴族が梅を愛でることから始まった花見ですが、実は花見のルーツにはもう一つあります。農民の間では、春になると、 冬をもたらす山の神様を送り返し、春を呼ぶ田の神様を迎える「春行き」「春山入り」 というものが行われていました。具体的には、桜の下で持参した酒や食べ物を飲み食いして1日を過ごすというもの。その時、 桜の色や開き具合いを見て、その年の豊作を占っていた とも言われています。農民の間ではこれが「花見」でした。(「 思わず誰かに話したくなる!お花見の歴史とルーツ - ウェザーニュース 」より)」
花見に桜が愛でられるようになったのは、平安時代 。平安時代に作られた古今和歌集では、梅を詠んだ歌が約30首に対し、桜を詠んだ歌が約60首。奈良時代とは違い、桜と梅の人気が逆転しています。この背景には、遣唐使の廃止が関わっています。 遣唐使が派遣されていた時は、中国文化の影響を強く受けていました。梅の花もその一つ です。しかし、遣唐使が廃止されたことにより、日本独自の文化が発展し始めます。そのため、日本に古くから自生していた桜に注目が集まったわけです。
貴族が梅を愛でることから始まった花見ですが、実は花見のルーツにはもう一つあります。農民の間では、春になると、 冬をもたらす山の神様を送り返し、春を呼ぶ田の神様を迎える「春行き」「春山入り」 というものが行われていました。具体的には、桜の下で持参した酒や食べ物を飲み食いして1日を過ごすというもの。その時、 桜の色や開き具合いを見て、その年の豊作を占っていた とも言われています。農民の間ではこれが「花見」でした。(「 思わず誰かに話したくなる!お花見の歴史とルーツ - ウェザーニュース 」より)」
毎年春に行われる 弘前さくらまつり は「 日本さくら名所100選 」、「 人と自然が織りなす日本の風景百選 」に選ばれています。
「 たか丸くん 」は、「弘前城築城400年祭」のイメージキャラクターとして誕生したゆるキャラです。鷹岡城の鷹がモデルで、弘前城をのせた兜に、津軽為信の前立てをあしらっています。
<他にも花の写真なども販売しています>

|

|

|

|

|

|

|

|

|
 写真素材 - フォトライブラリー
写真素材 - フォトライブラリー
© Rakuten Group, Inc.









