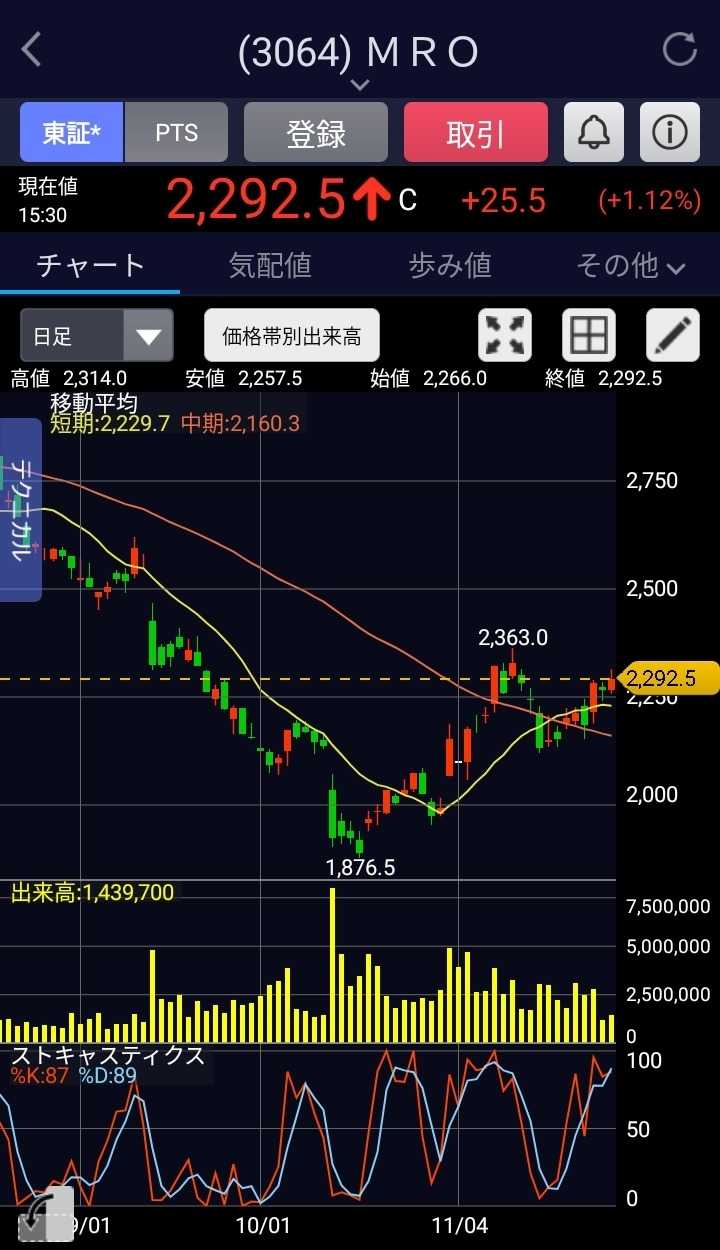全63件 (63件中 1-50件目)
-
イーバンクと楽天とEdy
楽天がイーバンクに200億円出資へ楽天、Edy利用でポイントが貯まる携帯アプリを提供どちらもだいぶ前の話になってしまったがとりあえず楽天がらみの話二題。東京都民銀行楽天支店はどうなったかというとまだ変わらずいたりするのだが、楽天はSBIのような金融コングロマリットを目指す上ではまるまる一行ほしかったりしたのだろうか。Edyについて言えば楽天キャッシュとの絡みで見るとEdy側からのアプローチがあったのではないかと。個人的にはポイントの話などどうでも良いので決済手段としてのEdyが使えるようになってくれたら嬉しいのだが、、、まあ、一部の店舗ではEdy決済が出来るようなのでこのあたりは店舗次第なのかもしれない。AmazonもマーケットプレースではEdyが使えないし、結局小さな店舗が使うには手数料面等でEdyは効率が悪いと言うことなのだろうか。
September 15, 2008
コメント(89)
-
「Saving the sun」及び新生銀行の近況について
セービング・ザ・サン 楽天ブックスの在庫では英国版と米国版のペーパーバックしかなかったので、とりあえずリンクだけ張っておく。日本では日経新聞社から2004年にハードカバーで刊行。ここ最近のドッグイヤー的な時代の流れからするともはや旧刊の類に分類されてしまうのかもしれないが、まだその傷が生々しいだけに日本人が書くと兎角ハゲタカが日本の大事なところをついばんでという議論になりがちな、長銀から新生銀行への流れを2年間の休業を経てフィナンシャルタイムズの東京支局長であったジリアン・テット氏が物した大著。氏のバックグランドからしてどうしようもないキリスト教正統史観や、グローバリズムや米国的先進的金融工学賛美、そして日本人のメンタリティを氏自身はある程度理解している節はありながら結局サムライの一言で片付けてしまうやっつけ的な部分は散見されるが、まだ歴史と言うには生々しい事件を氏の出来る範囲内で史書的に可能な限り客観的にかつアウトランダーとしての立場を最大限活かしてジャーナリズムの原則に基づいた取材により還元的に取材した成果を良心に基づいて再構成した力作だと思った。ある意味一番ショックだったのは自分にとって就職して社会人になったあとの出来事を書いたノンフィクションだったのに歴史書を読むような読後感を持って読んでしまったこと。当時、結構仕事が忙しい時期だったこともあって後に労働厚生大臣としてホワイトカラー・エグゼンプションを提案したり「産む機械」発言をしたりで安倍内閣の寿命を縮めた柳沢伯夫氏が金融再生委員長や金融庁誕生前に金融担当大臣として日本を代表する開明派政治家としてアメリカでもてはやされていたことなどをwiki等で再認識した次第。 長銀問題にしてもジリアン・ティット氏の本書を著する最大の要因となった幻のあおぞら銀行初代頭取、本間氏怪死事件にしても歴史と言うには早すぎる話題であったにもかかわらず、既に少なくとも僕の記憶からは遠い出来事であり、かつ現在もまだ触れれば鮮血が吹き出るような生々しい傷跡であったことを再認識した。ジリアン・テット氏自身が2年の休業というリスクを負ってまで物した著作であること、氏自身が時系列的に見て事件が起こる前から取材を開始できた立場にいたこと、そして恐らく当事者たる長銀最後の頭取、大野木氏を含め、当時の関係者の中でも開明的な日本人にとって外国人であり、フィナンシャルタイムズの東京支局長という立場にあった氏はある意味ジャーナリズムのなんたるかを基礎的な部分で了知していた氏の方が日本人ジャーナリストよりも余程信頼が置けたように想像出来ることもあってソースの部分では結構信頼が置けるのではないかと思った。まあ、本著が出版されてから明らかになったイ・アイ・イーに関する訴訟の和解等で一部歴史の判断に委ねなければならない部分はあるにせよ、その辺りは歴史書ではなくジャーナリズムの一環として書かれた本著の守備範囲外であろう。むしろ、我々日本人にとっては本著に描かれている問題はまだ歴史ではなく、政府保有の優先株処理は東洋経済の最新号で批判の対象となったばかりで、当書の主要な登場人物であるジョン・フラワー氏は最近このような事件の当事者として日本のメディアを騒がせていると言うことを深く認識する必要があると言うことだ。僕個人としては恥ずかしながら本著を読むまで同時代を生きてきた日本人としてこれまで知らないことが多すぎたことをひたすら恥じる。もちろん本著に著されていることをそのまま鵜呑みにするつもりはないが、日本人が深く追い込まれ、後に自分の正義を証したいと願ったとき、その証言者として信頼するのは残念ながら日本社会にどっぷりつかった日本人ジャーナリストよりは客観的な証言者としてより信頼に足る欧米のジャーナリストではないだろうかと個人的に想像してしまう。その意味で、本著は非常に近い過去に起こり、現在もなお進行している長銀=新生銀行問題を理解する上で最良で無いまでも必読な図書であると思った。 ここ最近、新生銀行の業績を引きずり下ろしたのは本書で語られているバブルに由来する不良債権問題ではなく、その後傘下におさめた消費者金融やカード会社がいわゆるグレーゾーン金利問題で表舞台に出てきたところと、日本政府が未だ同行の株主としての地位を放棄していない(そこにどんな意味があったかは定かではないが)ことに由来することを考えると、ここ数年間の日本の金融部門に於ける劇的な発展はしかしながらまだ十分な成果を発揮していないと結論づけられてもしょうがないと結論づけられても文句の付けようながないと思ってしまう。僕個人の立場とすれば、銀行については生活者の立場としてツールとしての銀行を評価するに留まることが最善と思っていたが、2004年発行でありながら現時点で楽天ブックスでも入手困難なことは当著が正当な評価を得ていない証佐と思い、ここに駄文を記すことをご容赦いただければと思う。つきあってくださった方が見えれば、本当にまとまりもな長いだけの駄文につきあってくださってありがとう。言い尽くせぬ思いはあれど、一人でも当著を読んでくださいとは言わない、あの事件とその周辺の出来事に思いを馳せてくれれば今ここに起こっていることについて考えるだけの知性を日本人は持ち合わせているのだからと祈るばかり。
November 23, 2007
コメント(0)
-
「イーバンク銀行がATM手数料を値上げ!乗り換えるならどの銀行が有利?」
「イーバンク銀行がATM手数料を値上げ!乗り換えるならどの銀行が有利?」:日経トレンディネット非常に扇情的なタイトル。我々ブロガーがブー垂れるのとはレベルが違うと思うんだけど、よくもまあ、こう思いきって特定企業を一方的に攻撃するような記事を書けるモノだと感心するが、一方でイーバンクはまあ、経営状況的にそうするしかなかったんだろうけどそう言われてもしょうがないことをしたとも思う。上述の記事はイーバンクからの取材について広報へのインタビューを断片的につぎはぎするというジャーナリストの信義に悖る書き方をしているのでイーバンクが本当にそういう文脈で取材に応えたのかは不明だけど、入出金の回数を制限した表向きの理由として「想定外のATM利用法により手数料が膨れあがっている」ことと並んで「デビットカード機能のあるイーバンクマネーカードがある程度利用者に行き渡ったので買い物のための出金が減る」ことを上げているのは金融機関としての見識を疑う。イーバンクに預けた資金を買い物に使うとすればオークション等でイーバンク口座同士で振り込む用途は想定されているが、買い物用資金をプールする先としては殆ど使われていないのではないか。というか、そもそもデビットカードの信用枠と現金とは全然性格の違うモノでしょう。特にイーバンクがヘッジファンドまで揃えて資産運用方面を収益源に使用としているならなおさら。現金は単なる決済手段ではなくて運用の原資になるモノ。デビットカードからの出金でその面がフォローできるのか。まあ、実際のところ経営上これ以上無駄なATM手数料を負担できなかったというところ以上の理由はないのだろうけど、そこで下手な言い訳をすることがプラスになるかマイナスになるかの判断すら出来ないのかと思ってしまう。
November 18, 2007
コメント(0)
-
金庫番からの手紙
ソニー銀行のコアコンピタンスの一つは目的別貯金箱である、と個人的には思っているのだが、この貯金箱を作ると今や懐かしのポストペットキャラが番人としてもれなく付いてくる。そして時折メールをくれるのだ。たいがい他愛もないことを書いてほんのちょっと和みの瞬間をくれるといった感じなのだが、たまに深い内容が含まれていたりして油断がならない。先日、僕の老後を支える貯金箱の番人、ビッグマウスハムスターのみらい君から届いたメールを紹介したい。>誰かが金利だけで生活できるようになった時、>誰かは生活に苦しくなってたりするかも知れない。>だってみんながみんな、金利生活できるなんてことは>ありえないよね。おおよそ銀行関係者、しかも個人資産の形成を主業務と自らもって任じているソニー銀行から来た人の言う台詞ではないような気もするが、短いフレーズで一つの真実を伝えている。例えば商品先物取引。本来は天候等の変動要因に左右されがちな商品価格を安定させるために作られた仕組み。それが結局のところ投機的な資金の流入で実態とかけ離れておおよそ世界中の人たちの生活を脅かす。その意味では自分の行動だってスケールこそ小さいけど利己的過ぎやしなかったかと反省する。まあ、資金の大小にかかわらず、自分のお金の行く末に少し想像力を働かせることが大事なんだということ、ですかね。
November 15, 2007
コメント(0)
-
SBIの攻勢続く
E*TRADEを返上してSBIで勝負を掛けるそうな。No.1になったブランドを返上するとは思い切ったことをと思ったが、恐らくけっこうな額のライセンス料を支払っていると思われる本家イートレは屋台骨が揺らいでいるとのこと。せっかくセンセーショナルに売り出した銀行とのグループ内シナジーを高めるためにもSBIの名前を前面に出すのは当然の戦略とも言える。ただ、僕としてはこのリリースの方により興味を引かれた。SBIと言えば、色々と問題行動を指摘されながら結局日本のブロードバンドを世界最安水準に引き下げたSBBBと兄弟会社。手数料の高さが問題視されている日本投信界に一石を投じるのではないかと期待する。まあ、出来れば投信が盛り上がっていた半年前、せめて2ヶ月前であればまともに話題になっていたんだろうな(^^;
November 14, 2007
コメント(0)
-
「首都高のETC利用率、8割突破――完全キャッシュレス化の鍵を握る「首都高X」とは?」
神尾寿の時事日想:首都高のETC利用率、8割突破――完全キャッシュレス化の鍵を握る「首都高X」とは?:BusinessMedia誠「首都高速道路のみで利用できるシステムで、プリペイド・匿名の電子マネー方式になり、簡易型の端末をクルマのシガーソケットに接続して使う形」が検討されているとのこと。僕自身はETCは使っていない。均すと月1~2回は高速道路に乗っているので色々考えると使った方がよいのだろうが、導入してしまうと結果的に高速道路を無意味に使ってしまいそうで怖い(^^;後段で神尾氏が述べている「ETC利用率増加とキャッシュレス化の進展は、料金制度やサービスで様々なアイディアを具現化する上で強い追い風になる。」と言う意見についてはむしろ逆でインフラの利用効率を考えるとむしろ100%ETCによる決済になる方向に誘導する必要があるのではないだろうか。そうなると料金所のおじさん達が失業しちゃうから無理か(^^;それにしてもどうしてETC普及と高速道路無料化の議論って何故同じ俎上に上らないんだろうか?
November 10, 2007
コメント(0)
-
「約1年で1000万円――モバイルSuicaの不正利用はなぜ起きた?」
約1年で1000万円――モバイルSuicaの不正利用はなぜ起きた?:BusinessMedia誠非常にアナクロな原因。多少の個人情報とその人物の所持するクレカのカード番号、有効期限さえ知っていて、足のつかない携帯端末さえ手に入れば誰にでも出来る手口。あまりにも敷居が低すぎる。まあ、これは個別の会社の問題とも言えるが電子マネーの普及に少なからぬ影響を与えるかもしれないと思うと腹が立つ。いずれ技術的にハックされる可能性もあるだろうが、こういう裏技でちょこちょこ毟られるようだと社会インフラとしてはあまりにも心許ない。運用側に手口がばれていないからこそ使える手ではあるが、少し考えればこういう事態が起こることは想定できるだろうに。おそらく正規に定められた手順と「現場の判断」の隙間で起こった「事故」という扱いになるんだろうな。失敗学のケーススタディとしては典型的なんだろうが、金融インフラの運用でこうも古典的なミスが、しかも組織運営の手順の中で起こったと言うことはある意味「歴史的な事故」と言うことになるのではないだろうか。ネット上でお金を動かしている者の一人として電子マネーに限らず金融各社には今回の件を教訓にしていただきたい。切実に。
November 9, 2007
コメント(0)
-
「ユーザーインタフェースで経営が変わる!?」
「ビジネスを考える目」鈴木貴博:ユーザーインタフェースで経営が変わる!?新生銀行の導入した古典的な暗号表的セキュリティを例にとって消費者の選択基準としてユーザーインターフェイスがサービス内容や信頼性と同じくらいの比重で存在しているという論。僕は仕事でネト銀を使っているわけではないが、確かにこのセキュリティに関しては導入当初に「非常に面倒臭い」と思ったことを覚えている。導入時点である程度抜き差しならぬ関係になっていた(投信を購入済みだった)こともあってだからといって取引を打ち切ろうとまでは思わなかったが、たしかにログインの回数はかなり減ったと思う。ただ、新生銀行を多少擁護するとパワーコール(電話による取引、ユーザーサポート)が飛び抜けて充実していて仮にセキュリティの関係でロックがかかってしまっても他のネト銀のように完全にロックアウトを喰らう可能性は実は低いと思われる。ま、でもユーザーの一人としてはより良い方向に変わって欲しいとは思っているが。自分の使っているネト銀を比較してみるとソニーバンクの取引できる端末を限定する方法、JNBの取引時点で自動生成された番号を入力する方法と各社それぞれ発想の違う障壁を立てているわけだが、単純にユーザビリティを考えるとJNBは優れていると思う。具体的には番号を入力するのは実際にお金を動かすときに限られるという線引きが秀逸だ。実際にネト銀にログインする場面のほとんどは口座残高の確認で、そうそう振り込みやら定期への移行やらをするわけではない。まあ、インターフェイス、セキュリティ、サービス内容と指摘されてみれば同じようにどれも大事な要素だとは思うが、個人的にはこれまでのところサービス内容に偏った選択をしてきたと思う。住信SBIが打ち出してきた携帯認証はまだ僕の口座を本格稼働させていないので使用感的な部分では発言できる立場にいないのだが、概要だけ見るとJNBの手法を後出しじゃんけんでブラッシュアップさせた方法のような気がする。新規参入による刺激が単純な利率競争にならずに既存各社のユーザビリティの向上にもつながることを期待する。
November 9, 2007
コメント(0)
-
Tポイントはファミマに
ローソンに振られたTポイントはファミリーマートと再婚することになったらしい。実は引っ越す前はメインのコンビニがローソンで3年ほどチマチマと結構な額のTポイントを溜め込んでいたりする。ファミマもEdy対応だし、近所と言え無くない距離に一軒あったりもするのだが、ATMとの兼ね合い等諸事情を考慮するとTポイントのために乗り換えるのも動機としては薄いような気もする。ま、今のところはときどきで気が向いた方を使うことになりそう。選択の幅が広がったという意味では良いことなんだろう。しかし、Tポイントは最終的な吐き出し先をどうするかが悩ましい。ANAマイルにするか、最悪は楽天ポイントか、、、(^^;
November 7, 2007
コメント(0)
-
ハイカ返金完了
返還請求から約二週間で処理完了。よく考えてみると八年前にロシア旅行したとき、新潟まで車で移動したときに買ったっきりだった。往路の途中のPAで自販機見てこれならプレミア分儲かると思って買ったんだけど結局使い切らなかったんだよね。典型的な計画倒れだよね。当時社会人二年目で結構それまでマメに溜め込んでいた財形をほぼ全額払い戻してしまったのがその後の貧乏生活の始まりだったような気もする(ToT)まあ、たかだか6000円程度戻ってきただけなんだけど、こういう小金集めがいずれ成果を生む、と良いなあと思っているんですけどね(^^;
November 6, 2007
コメント(0)
-
めでたくも無し?
「米シティグループが東証に上場 初値は4580円」などと言うことがありつつも、「26ドル未満なら三角合併ご破算 米シティ株価低迷」と言う事情もあったりで、総合的に見ると関係者はめでたいなんて言っている場合ではなさそう。元々東証では新株発行はしていないとのことだし。それにしても50株が単元と言うことは、取引単価はSFHの半額、新生銀行の2/3。冬のボーナスまで東証に居てくれればちょっと手が出るお値段ではありますな。腐っても鯛。しかも良い具合にこれ以上ないぐらい腐っていてくれると来れば。まあ、それまでの波乱に満ちた一ヶ月の中でどのように熟成するかは神のみぞ知る、ですが。日興合併失敗なら早々に東証撤退と言うこともあるんだろうか。
November 5, 2007
コメント(0)
-
イーバンクの決断
今まで無制限だったイーバンクのATM利用手数料が改定されるとのこと。出金はともかく入金まで合わせて2回(イーバンクマネーカードクラシック利用の場合)と言うことは自社ATMを持たないイーバンクの利用者にとってかなりこれまでの使途を制限する結果しか生まないような気がする。どちらかと言えばここのところ上場、開業ラッシュで大盤振る舞いばかりが目に付いた銀行業界の中にあって利用者数の割に収益構造の脆弱なイーバンクが息切れしていると言ったところか。イーバンクに関してはメルマネやゴールドラッシュプログラム、ポイントサイトからの換金といった裾野を広げるための販拡策ばかりが目に付いてしまって、本来事業の柱になってしかるべき資産形成のためのリスク性商品の販売に目が行かない状況を作ってしまったことがマイナスポイントになっている、と言うことだろう。正直、ゼロ金利時代(同時に僕が最も貧しかった時代)に小銭稼ぎのためにさんざん利用させていただいていたことを考えるとそう言った「若者向け」のサービスへの注力が削がれてしまうことは寂しいが、ソニーバンクの不可解なまでの成功ぶりと比較すると見事なまでの対照ぶりが浮き彫りになってこないだろうか。
November 4, 2007
コメント(0)
-
「パキスタンに戒厳令 憲法停止、テレビ局などに軍展開か」
アメリカあたりが支えきれなくなった段階でムシャラフ亡命、ブット政権誕生というシナリオを描いていると思っていたが、正規の手順を踏まずに外部の演出による革命では軍部や宗教界を納得させられないという判断か、ムシャラフ氏の独断専行か。いずれにせよ、核保有の事後承諾という最後のカードを切ってまで実現させた束の間の「南アジアの繁栄」による果実は今まで通りには落ちてこないと言うことだろう。パキスタンの経済的成功は周辺国家の安定に大きな影響を与える可能性があっただけにもう少し出来ることがあったのではないかとも思うけど、世界は結局僕たち衆生の与り知らぬところで動いていると言うことなんだろうか。いずれにせよ、冗談でも滅多なことは言ってはならないと深く反省。
November 4, 2007
コメント(0)
-
「シティグループCEO辞任へ サブプライム問題で損失拡大」
ここまで追い詰められていたとすると、本当になりふり構わず小銭稼ぎに来ていたのかなと思ってしまうな。まあ、金融商品は企画してすぐに発表できるような類のモノでもないのでタイミングは偶然なんだろうけど。あとは、せっかくSFCが金融機関のIPOについて良い流れを作ってくれたのにシラケムードが漂わないことを祈るばかり。まあ、どのみち額的に全然関係ない世界になるだろうけど、TOPIXを巻き添えにするのは止めて貰いたい。
November 4, 2007
コメント(0)
-

「ぼくたちは、銀行を作った。」
ソニーバンク立ち上げの主要メンバーであり、現役役員でもある十時裕樹氏が立ち上げまでの軌跡をほぼリアルタイムに描いたメルマガを素にした書籍、「ぼくたちは、銀行を作った。」を読んだ。時代のスピード感を考えると今更取り上げるのもどうかと思ったが、メルマガからの再編モノということで結果的に当時の空気感がよく読み取れる貴重な資料となっていると思う。ソニーバンクの開業が2001年とのことで、開業準備に追われる2000年頃から開業に至る時期に書かれ、内容としてはプロジェクトが動き出した1998年頃からの動きが綴られている。表題からは金融監督庁(現金融庁)や同業他社との駆け引きや軋轢といったことを想像してしまったが、ソニーらしく創業に関わった各氏のキャラクターの強烈な個性が新しい「ソニープロダクツ」を作る様をおもしろおかしく描いている。現社長の石井茂氏も創業時の社長として開業プロジェクトの一員として描かれているが、山一証券の死に水をとり、リタイア状態だったところをソニーに請われてプロジェクトに巻き込まれていった氏の経歴を見て「ソニーバンクからのメッセージ」の独特の色調やソニー銀行イズムのようなものの原点を見たような気がする。2001年と言えばついこの間のような気もするが、もう6年。僕の個人史を遡ってみると丁度ブロードバンドが一年間のヤフーBBの放置プレーの後ようやくやってきたところで、ネットは今の生活インフラ然としたモノではなく、自分の金をネット上で右から左に動かすことなんて想像も出来なかった(まあ動かす金もなかったが(~~;)。そう考えるとその時期に「リテール客に資産形成のための最適なツールを提供する」という現在も変わらない足場を固めてかつそこからぶれていないことは賞賛に値すると言える。ただ、サービスとしては創業当時に想定されていた範囲から実に一歩も外に出ていないことはこのネト銀戦国の時代にどうなんだろうとも思う。その意味では上場(直接したわけではないが)した今がいろんな意味で見直しの良い機会ではないかと。
November 3, 2007
コメント(0)
-
CITIの???
シティバンクから口座維持手数料無し、金利0.50%のオンライン専用日本円普通口座、「eセービング」と言うサービスが出ていたのを発見。まあ、口座維持手数料がかからない、海外の提携ATMから現地通貨で引き出せると言う点は確かに利点ではあるだろうが、「米ドルを米ドルとして扱える」というシティバンクの一番のメリットが享受できないことを考えるとこれまでのシティバンクとは全く別の銀行に預けると考えた方が良いかもしれない。開設はオンライン手続きと身分証明書のファックス、あとから印鑑の登録という手順らしいが、基本的に口座開設自体はファックした証明書を審査したら出来てしまうようだ。この辺りの異常なまでの簡便さを含めて、これまでの富裕層向けのサービスとは全く別の「誰でも良いからとにかく数を稼ぎたい」サービスっていうことだろうか。正直ファックス前提の身分証明書はどっかからクレームが入らなかったのかなと思わなくもないが、まあ現時点で受け付けていると言うことは話が通っていると言うことなんだろう。もともとシティグループ内にはクリアカードという引き落とし口座のいらないカードがあったりして両極端の層を取り込むのは戦略として存在しているのかもしれない。留学先の学生への仕送りとか、取りあえず海外旅行で使ってみようかといった辺りがターゲットなのかもしれないけど、自社ATMは365日24時間無料と言ったってシティバンクのATMなんて東海エリアでは栄、名駅、セントレアしかないし、提携ATMからの引き出し無料の条件が前月平均預金高100万円以上では入金は新生銀行等を使うとしても引き出しには電車賃か引き出し手数料がかかってしまうと言うことになる。と言うわけでシティバンクのATMが日常生活圏内にある人ならともかく、僕の現状条件下では流石に食指が動かないな。
November 3, 2007
コメント(0)
-
いらっしゃいませ
帰ってきてアクセスログを見ると少なくともお昼からの半数ぐらいがソニーバンクからのご一行だった模様。まあ、ソニーバンクに関してはかなり辛口に書いていたし、前々回には社長様のお言葉にも不遜なコメントを付けてしまったのでさぞかしお怒りかと思いますが、これも一ユーザーの正直な心持ちということで勘弁いただければと思います(^^;まあ、これからも遠慮はしないですけどね。
November 1, 2007
コメント(0)
-
住信SBIネット銀行開通
それにしても住信SBIネット銀行ってなんか正式な略称を出せばいいのに。それとももう発表しているのかな?閑話休題。29日に手続きした口座開設が完了したようなので入ってみた。キャンペーン金利の1%というのは期間限定とはいえインパクトがある。イーバンクの5年もの定期100万円以上一口でようやく1.08%だからな。振込手数料月3回まで無料というのも使える。メインの証券口座をマネックスからイートレに移すまでのことはしないかもしれないけど、これなら配球役兼流動資産のストックヤードとして現状のイーバンクと新生銀行に振り分けている役を両方こなせそう。まあ、ここまでの大盤振る舞いはそう続かないとは思うが、これを契機に何となくそれぞれ生態的地位を獲得して大人しくなりかけていたネト銀業界の台風の目になったことは確かだ。
October 31, 2007
コメント(0)
-
「ソニーバンクからのメッセージ」について
ソニー銀行社長、石井茂氏の顧客向けレター、「ソニーバンクからのメッセージ」について、実はSFHが上場するまではその存在にすら気付かなかったのだが、上場以降配信されるようになったメールでその存在を知り、実に記載内容がソニーバンク的なのが面白いなあと思ったので紹介してしまおう。内容的には現役の経営者とかバンカーの書いた文章と言うよりは新聞の論説委員が書くメッセージ性の強い社説かコラムのような感じ。いろいろと読者を教化してくれるようなモラルの高い文体、内容の最後に蛇足的にキャンペーンの紹介なんかが載っているのがなんだか社長なんだからこのぐらいは書かないといけないかな的な雰囲気でまあ微笑ましいのだが、僕の印象としてはまさにその高いモラルというかむしろ道徳的な雰囲気がソニー銀行を象徴しているように感じる。悪く言えば、一つ一つの商品に競争力がないというか、良く言えばがっついていないというか、イオン銀行や住信SBIネット銀行が特別金利を打ち出したりしているのに、SFH上場記念キャンペーンは「ソニー製品が抽選で当たります」が象徴しているように「ソニーの金看板」がうちのコア・コンピタンスなんで値下げ競争には応じません的な姿勢が貫かれていて、それが良い意味でも悪い意味でもソニー銀行を特異な存在にしているのだと思う。先行者利得とブランドの遺産でこの先やっていけるのかと言う疑問は感じるのだが、このおおらかさが無くなると企業は「赤福的な失敗」をしてしまうのかもと感じさせる何かがあったりもする。恐らく今のままではいられないとは思うけど、大切な何かを忘れずに進化してくれればネト銀に欠けがちな風格みたいなものを漂わせる存在として独自の地位を築いていくのかもしれない。なんか今回のエントリーは抽象的な話ばかりで自分でも何だかなと思うけど、ま、結局個人の感想意見以上のことはこれまでも書いていないつもりなのでその意味では一緒かなと開き直ってみたりして(^^;
October 30, 2007
コメント(0)
-
E*TRADE来た!
マネックス以来の金融口座開設になるイートレの開設通知が来た。住信SBIネット銀行の開業やらで忙しかったのか、意外と遅かったと言うのが正直なところ。今日は「イートレ遅いな」で一本上げる予定だったので帰ってきて封筒を見つけたときはちょっとびっくりした。それにしても口座開設は何度やっても結構ウキウキする。自分の世界が開けていくような気がする。ま、タダだしね。早速住信SBIネット銀行の口座開設手続きをする。まあ、取りあえず現時点ではそんなに自由になるお金も無いので銀行口座が開くのを待ってから冬のボーナス辺りからスタートと言うことになりそう。
October 29, 2007
コメント(0)
-
CITIいよいよ
いよいよCITIが東証に上場するとのこと。日興グループを傘下におさめるための方策なのでここまで来てしまえば選択肢はないのだろうが、CITIと言えばもう忘れている人もいるかもしれないけど、日興グループ同様日本では脛に傷持つ身。おまけにサブプライム問題の影響も大きく受けていると言うことになればSFHの上場のようには上手くはいかないだろうということが予想される。そもそもの企業規模の違い、日興という全方位的なチャンネルを日本に確保したこと、知名度も抜群と来れば買う側からすれば上場時点ではかなりお買い得な値段になっている可能性もあるが、今はCITI本体も失地回復のためにここで下手は打てないはず。どうするんでしょうな。
October 29, 2007
コメント(0)
-
ポイントサイトの黄昏?
一応いい年した大人なので少々恥ずかしいのだが、実はポイントサイトに嵌っている。今年度の前半は引越後のネット環境整備が遅れて手つかずの状態だったが、8月頃からネットに復帰すると同時にポイント厨生活も復活。現状、一日二時間ほどを費やしている。それで、どのくらいのアガリが出ているかと言えば、実質2年間ほどで換金分が14万円強。まあ、換金していない分、換金できずに不良債権化している分等もあって一概には言えないのだが、感覚としては「クレジットカード発行」とか「100%還元」とか「楽天で大きな買い物」といったイベントがなければ月1万円強がいいところだろう。大体メールやサイトのクリックポイントは多くて1円、悪ければ0.001円なんて言うのもあって、これにはまり始めると時間泥棒に吸い取られるように時間給は下がっていく。いくら何でもこれはやばいと思い、「非効率的な作業の切り捨て」とともに「どう考えても換金できないサイト」の切り捨てを敢行して現在は1日2時間程度に収まっているのだが(^^;、一時期は働いている以外の時間はほとんどこれに費やしていたような気がする。まあ、持ち金が目減りするわけではないので、パチンコよりはマシかもしれないが、大当たりする可能性も無いわけでその点からするとより絶望的な作業とも言える。更に過当競争のせいか、最近になってポイントサイトの閉鎖がちょくちょく見られるようになった。閉鎖するサイトは概ね一月以上前から予告は入れてくれるのだが、予告されたところで現金かを焦って労力と個人情報をつぎ込むような賭けには出られないので指をくわえて見ているしかないし、酷いところでは他サイトに個人情報を売り払っておきながらポイントは移行しないなんて言う例もあった。現状では個人のアフィリエイトに毛が生えた程度の手間でポイントサイトを構築することが出来たりするらしいので運営体制はサイトによってピンキリで、しかも見た目ではなかなか区別が付かなかったりする。僕の場合、始めた当初はゼロ金利時代で投資も始めていなかったので、とにかく給与以外の現金収入が欲しいということで、手当たり次第に出現するサイトに登録していった結果今でも切り捨てられない不良債権を幾つか作ることになってしまったが、理性的に考えると、1 一ヶ月試してみて一年未満で現金化できそうにないサイトは切り捨てる。2 楽天等のネット通販サイトとの提携還元率の高さは大きな目安。3 総数は3~4に留めないと実生活に悪影響を及ぼす。といったあたりを考慮に入れてみれば、例えば最新のウェブサービスの動向を知る手段としても利用できるし、ただ楽天で買い物をするだけでポイントを得たりすることも出来る利点のみを享受することが出来るだろう。
October 28, 2007
コメント(0)
-
金商法とは?
日経トレンディネットで「浅井秀一の先読みマネー塾」という連載がスタートした。浅井秀一氏とはALL ABOUTの執筆陣の一人で「いわゆるFP」の立場で色々書いている人らしい。で、その初回のテーマが「わが家に銀行員が来なくなる日 金融商品取引法で投信ネット販売に拍車?」。僕は元々投資歴のほとんどがオンラインで、もちろん銀行員が家に来たりするわけもない貧乏人なわけで、金融商品取引法略して金商法に関しては一方的に既に購入している商品についてリスクに関する確認を取らされたり、最近投資の手順が煩雑になったりしたな程度の印象しかなく、いったい何の役に立つ法律なのかと疑問に思っていたのだが、この記事を読んでその疑問が氷解した。1 団塊世代の退職金受け取りを狙ってリスク商品を売りつけようとする輩に対して発せられた事前警告ということらしい。2 電話勧誘、訪問営業などで投資をする意志の無い人に対してろくに商品のリスクを説明せずに販売する行為を取り締まるためのものらしい。3 オンラインで申し込んだり、自分で店頭に来たりする自分で何をやっているのか理解している「つもり」の人は庇護の対象にならないらしい。結局はいつかお金持ちになって自分から何もしなくても銀行屋サンに追いかけられる身分にならない限りは関係ないらしいということは判った。それにしても「金商法」という略称は一見すると新手の詐欺商法の一種にしか見えないところが何とも。
October 25, 2007
コメント(0)
-
Edy、大丈夫か!?
家計簿を振り返ってみると公共料金等を除いた支出先の第一位がサークルKだった(^^;まあ、親元からの通いだし、帰る時間帯にはコンビニぐらいしか開いていないことが多いし、近所には選べるほどコンビニがあるわけじゃないしね。そのサークルKおよび連合を形成しているサンクスについて、こんな記事を発見「サークルKサンクス、FeliCa決済4方式を全店舗導入へ」ま、今月頭の記事だし、導入も10月3日からということで、サークルKサンクスユーザー各位は既に気づいていることと思うけど、僕はこの記事を読むまで気付かなかった。確かに読み取り端末の一部が今月半ばぐらいから入れ替わっていたことには気付いていたけど、特に店頭等で積極的なPRはしていないような気がする。さすがにEdyの本丸の一つだけあって大っぴらに裏切り行為は出来ないのかな。まあ、僕に関しては選択肢が増えてもしばらくはEdyでいくと思う。実はQUICPayもスマートプラスもIDも携帯に入っていたりする。確かに使い勝手から言えばEdyのようなプリペイド形式の場合、先にチャージする必要があって一手間余分にかかるとか、チャージする金額を調整しないと金利のつかない死に金を抱え込むことになるとか端末を落とすとチャージ分は諦めなきゃならなくなると言った具合にマイナス点が多いのだが、ここまで投資してしまった額を考えると簡単には乗り換えられない。単純にEdyをサークルKで使うと、ANAのマイレージ、カルポイント、そして最近ではソニーポイントが付いてくる。紐付けたメインカードのスマイルポイント(UFJカード)も含めると四種類のポイントが付いてくるわけだ。ポイントの業というものは根深いもので、仮にここでEdyを諦めたところで換金額としてはたいした額を切り捨てるわけではないのだけど、ここまで掛けてきた時間が降り積もってしまい、「負けた」感が合理的な経済的価値を超えて降りかかって来そうなのだ。正直唯一の「先行者の強み」と言える使える窓口の多さでも多くのコンビニで「Felicaだったら何でも来い端末」が設置されている状況。プリペイド形式の中でも後発組の交通系と流通系に追いつめられ、本丸の一つといえるサークルKサンクスにも一歩引かれてしまった今、長期的に生き残れるのか疑問になってくるが、だからこそ生き残り策はポイント複合技とクーポン乱発ということになるのかな。PC用のFelicaリーダーもソフト的な対応で後発組も対応できてしまいそうだけど、そこを死守すればもう一つ光明が見える可能性も?
October 23, 2007
コメント(0)
-
チャレンジャーな皆さん
新生銀行の9月の投信購入件数ランキングの一位は新生・フラトンVPICファンドだったそうで、結構すごい話だなと思った。まあ、現状もっとも成果を上げている新興国市場である中国と少々景気過熱に冷や水は掛けられたものの内実的には中国以上に評価の高いインド、そしてポストBRICsの最右翼ヴェトナムを投資対象として、シンガポールの政府系運用会社という如何にもな肩書きの運用会社と組み合わせて商品化する組み合わせの妙はさすが新生インベストメントマネジメントとは思うものの、もう一つの投資対象はパキスタンで概ね20%は彼の地で運用するとのこと。まあ、何のかんのと言っても西側よりだし、アフガニスタンのようにレッドゾーンの紛争地帯というわけではないものの、相当な不安定要因を抱えた国への投資をむしろ売りにした商品が設定当初の一ヶ月間とはいえトップに立つとは皆さん肝っ玉が据わっていらっしゃる。まあ、結局BRICs投資にしたところで、これまで調子が良かったという結果論があるだけで決して先進国の仲間入りをしたわけではなくむしろそのリスクプレミアゆえにもうけが出ていたと言うことを考えると、今この不安定な時期に敢えてパキスタンという選択肢も判らなくはないけど、サブプライムとかで冷え込んだ投資マインドとかっていう報道はいったい何だったんだろうと思わなくはない。でも資金的に余裕があれば僕も10本ぐらいは買っておいたかも。宝くじを買うことを思えば分の良い賭けだし、まあ4本中一本が欠けても紙くずにはならないしね。むしろこれから買うのなら政変等でパキスタン市場が暴落したときかななんて一瞬思ったけど、これって「汚い大人」どころか「武器商人のマインド」だよね(^^;洒落にならん。CSR優先投資とまでは言わないまでも倫理観は大事だよね。お金は使う人によってきれいにもきたなくもなってしまうものだからね。
October 22, 2007
コメント(0)
-
FPの日らしい
11月の第一土曜日はFPの日らしい。なんか商標登録までしてあるんだけど、ネットを探しまくっても何故この日がFPの日なのか判らない。とにかく今年は11月5日がその日にあたり、全国で無料相談会なんかが開催されるらしい。今からでは申し込んでも間に合わないこともあるかもしれないけど、興味のある方はどうぞ。それはそれとして、日本に於けるFPと言う存在はなんだか鵺のような得体の知れない存在ですな。資格的に見ても国家資格と民間資格が共存し、公認会計士や税理士、中小企業診断士あたりはともかく、司法書士やら行政書士にもFPを名乗る資格があるらしい。そもそも僕たちが実例としてFPに接触する機会があるとすれば銀行か保険屋さんが客寄せのためにやる「資産運用相談会」なる商品説明会がほとんどじゃなかろうか。フィナンシャルプランナーとして独立して看板を掲げている事例としては公認会計士さん、税理士さんが本業ついでというパターンが多いのではなかろうか。東海地方は産業規模の割に士業が育たない風土があるらしいので僕の視点は偏っているのかもしれないが、これからの自己責任で資産運用をする時代にFPの現状がこれだけ混沌としていて合法的にFPを名乗っている人の実体が一見して判らないようでは問題があるのではないだろうかと思う。この問題は突っ込めば突っ込むほど何か出てきそうなのでもうちょっと時間を掛けて調べてみようと思う。
October 22, 2007
コメント(0)
-
小銭拾いな休日
今日は休み。と言っても代休なのでありがたみは半減だが。どうせ有給は余っているので残業手当の方が良かった。まあ、うちの会社もまともに出張旅費も払えないほど疲弊しているらしいので給料ちゃんともらえるだけありがたいけど。と言うわけで多少なりとも休みを有意義にするために細々とした用事を済ますことに。まずは前に書いた高速料金の誤請求を片付けるためにカード会社に連絡。電話の向こうで「私、高速道路のことはよく判らないんですけど」とか言われて若干切れそうになりながら事情を説明し取りあえず「一週間ぐらいはかかるかもしれませんけど」とのことだったがまあ、やれるだけのことはやったのでこれは良しとして連絡待ち。高速ついでにプレミア込みで6400円分残っていたハイウェイカードを換金することに。近所に料金所があるので行ってみると「ここでは換金できないのでこれで郵送して」と予想外の珍客にオドオドしている料金所のおじさんに封筒を渡される。中に入っていた申請書を書いて早速送る。ま、両方とも上手くいったとしても6500円ぐらいにしかならないんだけど、気持ち的には多少すっきりした。
October 22, 2007
コメント(0)
-
JNBの乾坤一擲?
これまで言っちゃ悪いけど、(イーバンク)+(ネットキャッシング)-(ゴールドラッシュプログラム)ぐらいのイメージしかなかったJNBだが、ヤフーポイントの換金ができるようになったらしい。ヤフオクのプロモの一環みたいだけど、これまで楽天ポイントとともにポイント交換のターミネーターと化していたヤフーポイントの価値が一気に上がるかも。
October 20, 2007
コメント(0)
-
真っ赤だった
昨日は持ち株はおろか手持ちの投信19銘柄のうち16銘柄が下がっていた。かなり分散には気を遣っているのでここまで全面的に下がったのはサブプライムショックの全盛期にあったかなかったかぐらい。ただ、不思議だったのは恐らく下落要因のうち、大きなウェートを占めていると思われるインド市場の下落を一番受けても不思議じゃないUTIインドファンドが一番上げていたこと。価格への反映が遅いだけかとおもったけど、今日もとりあえず上げている。不思議だ。すみません、よくよく確認したらやっぱり18日は大幅に下げていました。しかし、中国政府もこのくらいインパクトのあるバブル抑制策をとらないと中長期的には痛い目を見るのでは。彼の国の現状を考えるに経済政策の失敗は政権転覆を招きかねないと思うのだが、、、
October 18, 2007
コメント(0)
-
「戦略的・家計運営術」について
日経BPに「戦略的・家計運営術」という連載がある。著者はFPの内藤 眞弓さん。続けられる家計簿の書き方から有効な予算の立て方など、家計の運営に関するヒントが判りやすく書かれていて僕も色々と参考にさせていただいている。日経BPは会員サイトなので登録されていない方は直接リンク先に跳べないかもしれないけど、この連載を読むためだけでも無料登録の労をとる価値はあると思う。直近の「キャッシュフロー表を使って運用を考える」は最近の僕の悩みであるいざというときのための流動資産の確保についてのヒントになるものだった。日経ということで想定読者層が男性メインなせいか、「家計も企業会計も手法は同じ」なんて副題が付いていたりして余計な誤解を招きそうな体裁になってしまっているのは不幸だが、主婦の方から独身男性までいろんなケースに対応できる内容だし、文体も簡潔明瞭。是非一読することをお奨めする。
October 16, 2007
コメント(0)
-
反省点5
サブプライムショックが起こったときに結構な額を投下することが出来たのはたまたまボーナスの使い道をウダウダと考えて先延ばしにしていたせいで、普段の僕は割とドルコスト平均法の忠実な信者だったりする。おまけに「手のかからない長期投資」を最適化された手段と思い、卵は出来れば一つずつ別の籠に入れて保管したいとさえ思っている。だが、このときの経験でロバートさんの言っていた「キャッシュフローの重要性」とやらを身をもって実感したことも確かだ。今のところ僕の生み出すキャッシュフローは給与所得に限られ、親元住まいの利点を最大限に生かしてはいるものの自律的なお金の動きによって余剰資産は収まるべきところにおおかた収まってしまい、自由になる金はそれほどあるわけではない。今後もサブプライムショックのような都合の良い状況にある程度そなえるべきなんだろうとも思うが、僕の小さなサイフでは単に費用機会の喪失を生むのが関の山なんだろう。さて、長々と続いた回想は次回でお仕舞いにするつもりだったが、実はここからはそれまでの投信一辺倒から現物株式への挑戦となるわけで、銘柄ごとにまとめた方が都合が良かったり、現在進行形の部分もあるので(もちろん投信投資も現在進行形ではあるが)これまでとは違った構成にしたい。よって「投資のこと」シリーズは取りあえず前回でお仕舞いと言うことにしようと思う。
October 15, 2007
コメント(0)
-
ちっさい悩み
久々に家計簿の整理をしていたらクレカ払いの高速料金で普通車料金を請求されていたことがあったことに気づいてしまった。行きも帰りも高速使っているうちの片道だし、普通に考えればまともに抗議すれば通る話だとは思うけど、たかだか1000円にもならない話でクレカ会社とNEXCO中日本という割と判らんちんの組織と話をするかと思うとアホらしいような気もする。ちなみにクレカ会社は話のわかるところは合点承知で話を進めてくれることは承知しているのだが、僕のメインカードは地銀の関連会社が発行していおり、社員は地銀からの派遣組がほとんど(と思われる)。以前ちょっと難解な処理を依頼したところ電話をする度に一から説明はしなきゃならないは、最初に言っていたことは適当な出任せだったりで良い印象がない。でもこういう事例を放っておくと結局社会が良くならないし、自分が舐められるのである程度コスト無視でもいかなきゃならないんだろうな。ふぅ。
October 14, 2007
コメント(0)
-
投資のこと9
さて、だらだらと書いてきた回想も残りあと2回ぐらいかな。間が開いたのでまとめると、前回(今年の5月頃まで)時点の投資対象は全て投資信託。預け先は地元の地銀を皮切りに、新生銀行、マネックス証券の3カ所。銘柄の構成としては地銀ではグロソブ、ピクテのグロインとプレミアム・ブランド、後にAIGのイレブンプラスを追加。グロインとイレブンプラスは月々の定積みを実施中。新生銀行はボーナスの預け先として。新興国モノ4本とJ-REITものを等額購入。マネックス証券はMRF以外はTOPIXインデックスと海外インデックスのファンドオブファンズを一本ずつ月々定積み。と言ったところ。その後、夏のボーナスはまたしても新生銀行に。銘柄選定とそもそも新生銀行でよいのかという悩みもあって実際の購入は8月頃にずれ込んだのだが、ちょうどそのころはサブプライム騒動真っ盛り。投資意欲も萎えかけていたのだが、ここまでの観測で安定的に数字を伸ばしていた幾つかの銘柄が基準価格を大幅に落としているのを見てこれはチャンスと思い直し、ポートフォリオのバランス上の問題もあって債券モノを中心に選んだ。めぼしい債券モノ4本を選びそれ以外に一本分の予算があったので、サブプライム騒動でもっとも値を下げたそれまでの稼ぎ頭、J-REITものを買い足すかどうか迷ったが、投資対象の日本版REITそのものの値動きにバブル的要素もあったと言う情報も入っていたので断念し、新生インベストメント・マネジメントの新規設定商品であるアメリカン・ドリーム・ファンドを購入することに。新生IMは若い商品ばかりなので信頼性という点では計りかねるところがあるのだが、小さくても専門性の高い特徴的な運用会社と組んだ独自性の高い商品を設定しているところが好き。アメリカン・ドリーム・ファンドに関してはプライベート・エクイティティを含めた米小型株専門のRSインベストメンツ社と組んでいる。アメリカのカントリーリスクはあるし、設定後一年間は解約できないなど躊躇う要素はあったが、ギャンブルするにしてもドラマチックに商品を見せる工夫が見えたところを買ってしまった。まっ、投資家の判断基準としては間違っているけど、結局投資行動もエモーショナルな部分があるんだから納得して買った銘柄は可愛いよね。
October 14, 2007
コメント(0)
-
SFH上場記念キャンペーン
SFH上場記念キャンペーンだそうです。なんか応募の口数がリスク製商品で30万円一口、預金等で100万円と気軽にキャンペーンで応募できる単位じゃないんですけど。まあ、ソニー銀行がメインバンクの人には軽いハードルなのかもしれないけど、結局抽選でソニー商品が当たるという対価を考えるとバランス的にどうなんだろう。なんだか必死さが感じられないというか、理性的な条件比較でもおまけでも負けているようでこれからやっていけるのか?ソニーブランドっていまだにそれほどのものなのかな?
October 13, 2007
コメント(0)
-
イー・トレード証券から入ってみました
住信SBIネット銀行について、早いうちに手をつけておかないとネタにしにくいけど、待っていればポイントサイトで好条件のリベートが提示されそうな気がするという葛藤(我ながらちっさい、ふぅ(^^;)があったのだが、よくよく考えるとイー・トレード証券とセットなわけで、そちらはそこそこポイントサイトに出ていたりするのでそちらから入ってみることにして申し込んでみた。メインの証券口座の座を入れ替えるところまでいくかどうかは判らないが、ソニー証券よりは可能性高いかな。
October 13, 2007
コメント(0)
-
最近どうよ、っていうかどうします?
ここ数日忙しくしているうちに金融界にも結構いろいろありましたな。SFHは結構良い値を付けたみたいだし、イオン銀行は29日に営業開始とギリギリで公約死守できたみたいだし。そうこうしているうちに保有している各銘柄も値を上げてきて一時は±0に限りなく近くなっていたのが収益12%台に回復。とはいえ米経済はまだ景気後退の種を孕んだままだし、それほど根拠はないけど、前回以上に根深い景気後退が待っているような気もする。ここいらで一旦店仕舞いするのが吉なのかとも思ったのだが、長期投資をポリシーにしている手前それはちょっと短絡的かとも思う。どうしようかね(^^;
October 13, 2007
コメント(0)
-
SFHいよいよリリース!
明日はいよいよソニー・フィナンシャル・ホールディングスの上場日。まあ、市場は結構暖まってきたみたいだし、初値はそこそこつくかもしれないね。ユーザーとしてはともかく株価的には手が出そうにないので見てるだけだけどね。
October 10, 2007
コメント(0)
-
ソニー証券のうり?
Stock Gearなる株売買用ツールが使えるみたい。この手のツールは有料だったり条件がいろいろあったりするんで無条件で使えるのは一つの売りになるかも。紹介ページ見る限りでは結構多機能そうだし。まあ、使い勝手は使ってみないと判らないので何とも言えないけど。まあ、短期売買はしないのでテクニカルとかあんまり関係ないんだけど。
October 9, 2007
コメント(0)
-
投資のこと8
さて、年度を越すと環境ががらりと変わった。転勤し、この歳になって就職してから初めて親と暮らすことになった。それまでと比べて結構自由になるお金が増えたと言うこと。とはいえあまりの環境の激変に投資にいそしむ余裕はしばらく無かった。それまでの各種口座の住所変更だけでも結構時間がかかってしまった。中でも大変だったのはメインバンクの地銀。支店を変えるのに膨大な数の書類を作成するハメになった。実はそれまで細々と外貨貯金をしていたりもしたのだが、何故か先方の都合で解約するハメになったし。それに比べるとネト銀関連はそもそも支店の概念もないしネットで手続きして証拠書類を郵送する程度で済んだ。あのときの経験で本当に支店の概念って銀行側の勝手だなって思った。その後、地銀に関してはサブプライム問題直前に投信の定時定額購入を一本増やした。最初に買った3本のうち、実はこの時点で一番成績の良かったピクテのプレミアムブランド。その後サブプライムショックで劇的に下がってしまったのだが、結果的に安いうちに買えたので今は結構成績がよい。このあたりドルコスト平均の効果が実感できたところ。あとは無駄遣いに走らないように余った分は出来るだけマネックスに喰わせていたのだった。3月から買っていた投信を除けばMRFを買っていただけだけどね。
October 9, 2007
コメント(0)
-
イオン銀行もあったね
今朝の日経によると色々と遅れの出ているとの噂もあったイオン銀行の10月開業は間に合うらしい。今のところホムペはティザー広告並みなんでサービス内容の詳細は判らないけど、セブン銀行みたいにATM賃貸業をするものと思っていたらフルサービスを破格の長時間営業(土日込み)で行うらしい。これはゆうちょ銀行よりよっぽどインパクトがある。ネト銀と比較してコスト高になることを指摘する声もあるけど、一人頭の人件費は既存の銀行よりずっとリーズナブルになる可能性が高いし、ハードにかかる経費もテナントが一つ増えたと思えばたいしたものではないような気もする。それにしても既存の銀行もだいぶ出資するらしいけど下手をすると軒を貸して母屋を取られるのでは?まあ影響力はイオンの商圏に限られるので今の僕には関係ないけどね。
October 8, 2007
コメント(0)
-
見落としていたメリット2
う~ん、やっぱり金融機関のサービスについては隅々まで読み下しておかないといかんね。住信SBIネット銀行についてまた見落としを発見。イー・トレード証券との連携についていまいちメリットが判らない旨を書いてしまったが、連携用の専用口座、イートレ専用口座というのが準備されていてこれが年利0.55%とのこと。もっともATMからの直接入出金は出来なくていったん普通預金に払い出す必要があるとのことなので、普通預金と言うよりは新生銀行のパワー預金に近いと言える。ま、金利面ではイートレ専用口座の圧勝だけど。流動性資金の仮置き場としては各種MRFを除けばeBankの普通預金年利0.35%が現状最高かと思っていたが、これならJNBの一ヶ月定期0.5%にも勝てる。使い勝手の点を考えるとメインの証券口座がイートレで無い場合は面倒な点を感じるが、まあ、そう感じさせるのが作戦なんだから大成功といえるだろう。他にも目的別口座とかどこかでみたことのあるサービスを後発の利点でブラッシュアップしたサービスが目についてあざとさを感じるが、この薄利多売的なコスト体系が維持できるだけ口座数が集まるのならまさに台風の目になりそう。というか、SFHはもっと危機感持つべし。ただ、金融機関については日本人はかなり保守的な面があるので、経営的に分離しているとはいえソフトバンクの名を冠した銀行に資産を預けることにためらいを覚える人はいるだろうな。イートレード証券だってSBI系列と判らずに使っている人の比率はかなり高いだろうし。その点で住信の名前は絶対欲しかったところなんだろう。
October 8, 2007
コメント(0)
-
見落としていたメリット
ホムペを眺めていて気づいたのだが、住信SBIネット銀行の個人客向けサービスとして他行宛て振り込み月3回無料というのがあった。キャンペーンなので恒久的なサービスじゃないんだろうけど。これは結構な引きの強い要素だな。う~ん。いっちゃおうかな、、、
October 8, 2007
コメント(0)
-
さもしい?
ネト銀に関しては一通り試してみる主義なので住信SBIネット銀行も口座を作ってみたいのだが、出来れば口座開設で1000円もらえるキャンペーンをやっている11月30日までには。もしかしてポイントサイトで追加のキャンペーンやっていないかと探してみたが、やっぱ無いね。難しいのは口座数が伸びなかったらさりげなくより良い条件でポイントサイトに出ていたりすることもあるからな。まあ、おまけはおまけ、必要があればどんな条件でも開設すべきだろうけどそこまでの必要性は感じていないってこともある。でも結局イー・トレード証券からの流れ込み組でノルマは埋まっちゃうのかな。
October 7, 2007
コメント(0)
-
Money!
実は一週間ほど前にMicrosoftMoney2007を買ってしまったのだった。で、その後二日ほどしてPlus Editionの発売に気づいたのだった。元々エクセルでチマチマと家計簿をつけていたが、重さに耐えきれずマスターマネーを導入したのが昨年の夏頃。これはこれで柔軟性があって値段はMoneyの半分程度と非常にコストパフォーマンスの高い良いソフトだったのだが、ここのところ扱う口座や銘柄数が増えてネットから各種データの取得できるMoneyの方がいいかもと乗り換えてみたのだが、、、Plus Editionになったからと言って慌てて乗り換えなきゃならない必然性もないのだが、2007と銘打っているからには2007年の間ぐらいは最新版でいて欲しかった(ToT)
October 7, 2007
コメント(0)
-
ゆうちょ銀行雑感
週刊「東洋経済」9/15号の特集「郵便局の未来」を読んだ。正直、現時点で既に敗戦処理に入っているとしか読めなかった。過去の大型民営化案件もしがらみの切り捨て、収益体質向上のための無理なダイエットなどの産みの苦しみを味わってきたが、オンリーワンな経営資源を持っていたがために一時的な苦しみを乗り越えればハッピーな未来が見えていた(ステークホルダー全てにとってでは無いにせよ、事業体としてはと言う意味で)。しかし今回はゆうちょ銀行はじめ、グループ企業全てにライバルが存在し、唯一のオンリーワン要素であるユニバーサルサービスは単なる足かせでしかない。組織体としても公社としての歴史すら浅く、中央官庁としての色が濃く残っており、その贅肉、というより毒素の切り捨て作業が十分でないうちに民営化の荒波に晒されることになったようだ。物流は資源高によるコスト構造の変化に苦しむだろうし、金融部門はことを起こすには最悪の時期、保険にしても民間ですらこなし切れていないコンプライアンス体制を実現するには二段飛びの努力が必要になるだろう。唯一の明るい材料は不動産運用部門らしいが、これは実体経済の浮沈に大きく影響を受けるものだけに今スタートすることは近い将来の実体経済沈下に向け、却って甘いコスト体質を生むことにもなりかねない。ゆうちょ銀行のホムペをみて銀行としてのスペックを数字だけから拾ってみても利率面では各ネト銀に大きく後れをとり、リスク商品(といっても投信のみだが)の品揃えは中途半端、手数料面でも特にみるべき点はない。昔は学生への仕送りの定番は郵便貯金の親子カードだったが、ネト銀ならそもそも支店という概念すらないしね。手数料と言えば僕にとってここ数年、郵便局の金融機関としての存在意義は各ネト銀の窓口としてのATM機能だったわけだが、近所にようやくセブン銀行の端末が出来た今となってはご無沙汰になってしまっている。旅先でネト銀の口座から引き出すような使い方は個人的には余程の緊急事態だが現状僕にとっての郵便局の存在意義はそれぐらいかな。アンプラグドな人たちの銀行としての社会的存在意義はある程度認めるが、それだけの存在であれば将来的に利用者数は先細りするしかない。CITIグループとの提携で最近増えている外国人観光客にとってはオンリーワンな存在ではあるようだけど、その地位も美味しくなればライバルに参入されることは目に見えているしね。僕として考えられる生き残り策はいわゆるコンビニ化でワンストップサービスを徹底することぐらいだが、現状でも民業の圧迫で批判を浴びる中これ以上敵を作るようなまねはしにくいだろう。上場なんて計画もあるみたいだけど、今を見る限り長年かかって国民から預かった資産と共倒れにならないようにソフトランディング(どこに?)して貰いたいというのが僕の望みかな。あとは変な外資に屍肉荒らしをされないように願いたいものだ。新生銀行のような成功例も結局ある程度人的資源があったればこそだろうしね。現状ではハードしか残らないような、、、あくまで個人的な感想なので、昔住んでいたアパートが郵便配達員の休憩所になっていて吸い殻の入った缶コーヒーが散乱していたことを恨んでこんなこと書いているわけじゃないんですよ(^^
October 6, 2007
コメント(0)
-
反省点4
マネックス証券での投資信託の定時定額購入に「カードde自動つみたて」というサービスを使っている。ついこの間気づいたのだが、このサービスはあまりに意味無しである。セゾンカードとの提携サービスで毎月5日にカードの引き落とし口座から購入金額分が引き落とされ、その月の20日に実際に購入が行われる。僕はてっきりカードのポイントがつくものと勘違いしていたのだが、実はつかない。つまり5日から20日の間の15日間、利子も付けずにカード会社に金を貸しているのと同じなのだ。と言うわけでこのサービスを使う意義は全くと言っていいほど無い。同じように「銀行de自動つみたて」というサービスも2日に登録した銀行口座から引き落とされて9日後に購入がなされる。これも意味無しだ。と言うわけでマネックス証券で投信の積立サービスを使いたい場合は証券口座への入金については手動で行い、MRFからの自動つみたてを行う「自動つみたて」をつかうべきだろう。というか僕は今度からそうする。ま、こんな手に引っかかるのは僕ぐらいかな。
October 6, 2007
コメント(0)
-
反省点3
問題は幾つかあるが、そもそもネット証券を選ぶことは結構難しい。たいがいの日本人同様、僕にとっても初めて証券会社を選ぶ経験だったし。手数料は一つの大きな目安だろう。が、自分で全てをオペレートするネット証券では使い勝手も重要だろう。で、使い勝手については実際使ってみるしかない。最後はエイヤで飛び込むしかない面もあるわけで。そう言う意味ではキャンペーンなんかは最後に背中を押す要素として現状では全く有効なのかもしれない。しかし、何となくプライドに障るというか、そんなほとんど自分の判断が入っていない状態での選択は今からしてみると、、、それから先他の選択肢を試してみることも出来たけど、しなかったし。実際のところは、年度が替わった時点で僕の生活環境も大きく変わり、いろいろ試してみる余裕がなかったこともある。いずれは色々と整理統合していく必要があるとは思うけど、今後はいったん出来るだけ手を広げてみる必要があるのかな。新規参入組の影響でしばらくは凪の状態だったネット証券界(FX業務除く)にも地殻変動が起こりそうな予感がするし。
October 4, 2007
コメント(0)
-
投資のこと7
とは言え、マネックス証券は手数料高いことは高い。携帯からの取引なら10万円以下は105円になるという裏技的に低価格なゾーンが実質的な僕の売買範囲(今のところ予算上どうしてもそうなるだけなんだけど)とは言え、逆にその範囲なら手数料ゼロのところもちらほらあったりする。マネックスポイントで補填できるとはいえ、ガバガバ売り買いするわけでもないのでそちらもそうそう貯まるものではないし、使うときも細かい単位で使えないので貧乏性には使いづらい。そう考えると株の現物買い目的にまともに検討したらマネックスは選ばなかったはず。結局のところ前述の通りきっかけはポイントサイトのキャンペーン、そして実際使ってみる気になったのはノーロード投信があったから。まあ、他のネット証券も投信が充実しているところはあるけど、たまたまのタイミングですな。今から思うと。それまで買っていた投信が比較的高コストなものが多かったこと、ちょうどVanguard社の創設者ジョン・C・ボーグルのお言葉なんかにふれて今までの自分は間違っていたのでは?インデックス投資こそ王道?なんて思い始めていたこともあって年末も押し迫った3月から東証モノと米市場モノのインデックス(こちらはインデックスを対象としたファンズ オブ ファンズだけど)の計2本を月々定額買いで始めたのだった。
October 3, 2007
コメント(0)
-
CITI+日興=??
CITIといえば50万円以上の月間平均預高がないと2100円も口座維持手数料を取るというブルジョアしか相手にしません商法というイメージだが、海外旅行に行ったりすると便利そうとか外貨を生で扱えて分散投資に便利そうとかで密かにあこがれがあったりする。この合併で50万の枠にマネックスの預かり資産が含まれるようになればいけそうだな。ま、ターゲット顧客層がまるで違いそうなんでそう言う安易な仕組みは期待できそうにないかな。
October 2, 2007
コメント(0)
-
ソニー証券スタート
ソニー銀行からのメールで「ソニーバンク証券との証券仲介サービス開始」とのこと。「ソニーバンク証券開業記念!株式取り引き手数料半額キャンペーン」とのことだが、半額になっても特に手数料上のメリットは無いかな。いまのところもうちょっと頑張りましょうかな。
October 1, 2007
コメント(0)
全63件 (63件中 1-50件目)