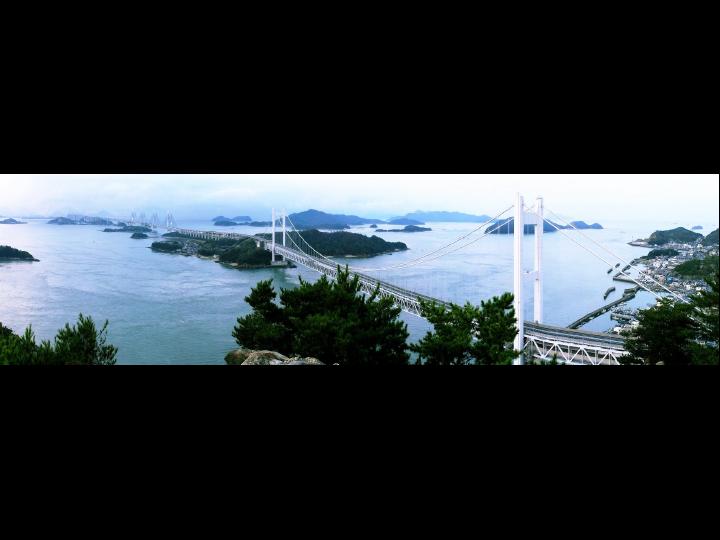創作秘話 「上を向いて歩こう」
永六輔と坂本九の作と歌唱だが、この歌にたいしての感慨は殆どない。世界的にヒットしたと言うくらいだ。
なぜ、この題にしたのかは、私が好きな言葉だからだ。
また、なぜにこの作品を書いた歌は、現代の俯き加減の人達を多く見るから、と、どうか前向きに生きてほしいという思いがあった。
それとデモの鎮静化に盾となった機動隊の人たちがマスコミによって何も報道されなかったという事も、その不思議さもあった。バブルの時期やくざの地上げ屋に脅かされ騙されて退いた人達もここに登場させている。最後はこの人たちの復讐劇になった。
現代の風情をかきながら社会の柵のなかで生きる、その事を少しで見、真実として書ければと言うものだった。
狂言回しに一人の女を登場させている。時代の証言者として、時代の背景として、国民の総意として語らせている。
私もその時代をそれらの闘争の渦中で生きてきた一人だ。社会は両極端に分かれ意見は対立し、離別を繰り返していた時期、なにが本当の真実か分からない、分かろうとせずに何かに酔っていた時代だった。ただ現在の不安に対しての叫びだけが空しく木霊していたのだ。戦後の悲惨な状況からようやく一人で立った幼子の様な存在が国民の姿であった。
デモの先頭に立っていたのは、全学連でもなく、演劇人たちであった。其の頃の演劇界は思想的には共産主義の人達が占めていた。俗に言う新保的な人達である。要するにアメリカとの安保は絶対受け入れられないという、ただそれだけで、それならどうするのか、日本を何処へ導くのかの議論はなく、代替えの案も持ち合わせていなかった。ただ反対、と叫んでいたという事だ。
文化人、労働者、大学生、それらは、新宿駅構内で線路の石をポケットに詰めて参加していた。ヘルメットをかぶり、鉄パイプを携帯するものもいた。それらの人達は機動隊と小競り合い殴られヘルメットをわられて額から流血していた。が、機動隊のなかにも鉄パイプで殴られ再起不能の重傷を多く出していた。、が、その機動隊の事は一文字も報道されなかった。これは書く時に思いあの時代は一体何だったのかと言う疑問がわいて心が震えた。
あの頃から今の日本、報道のでたらめが始まったとしか思えないからだった。
デモ隊であろうが応戦する機動隊員であろうが命は等しく平等であるはずだと言うのが私の思いだったからだ。主義主張を超えて其の命を見つめた。
安保、原潜寄港、成田闘争、公害問題、ウーマンリブ、赤軍派、原発、授業料値上げの学生闘争、等は、日本国の、国民の脱皮であったのだろうか。其の根底にはアメリカの日本全滅作戦、日本人の精神の破壊、国民一億地方政策、公職追放、旧憲法の切り捨て、押し付けの新憲法、教育勅語の破棄、財閥解体、農地改革、等など。
思想の自由と言いながら低級な娯楽に埋没させる、プロ野球、プロレス、映画、テレビ、ジャズ、ロカビリー、新聞社などにGHQは金をばらまき国民を其の享楽へ導いていく、
日本教職員組合を支援し日本は悪い事をしたと教え押さえつける。朝鮮人と共産党員に対しても裏から手を回して応援しそれを実行させる、また、新興宗教に対しても莫大な金を投じて宗教界を分裂させる、ようするに日本人精神の支えを断絶させる作戦をしていたのだ。
アメリカは、日本との戦争で国民を全員殺すと言う戦いをしていたと言えよう。事実ルーズベルトは皆殺し作戦と言った。
其の証拠に敗戦して戦勝国は敗戦国を裁いてはならないと言う事を無視して、当時の軍部と政治家を東京リンチとして裁判に架け絞首刑にしている。
そんな混乱のなかでアメリカの作戦にまんまと乗せられたのが反対と叫んだ人たちであったのだ。何も分からなく扇動にまんまと乗せられたのだ。
そんな時代を過ごしてそれを自由と勘違いした人たちの群れがあった。
私はその渦中にあってつぶさに見てきた。また、それらの人達が書いたものを読みあさっていた。
この時代を克明に解き明かしたのが「されどわれらが日々」芥川賞になった柴田翔である。が、デモたちの中を書いたもので其の鎮火に働いた機動隊の人の事は書いていない。
それでは平等ではない、その思いが30年後になってようやく気付きこの作品を書く動機になったと言える。
現代の時間のなかに生活して蠢く人達の事を書きながら背景としてはここに書いた人のなかに思いを密かにしみ込ませたものだった…のだが…。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 読書
- 「やりたいこと」が見つかる時間編集…
- (2025-11-15 10:34:54)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 59 タムタムさんカッコいい
- (2025-11-11 14:59:50)
-
© Rakuten Group, Inc.