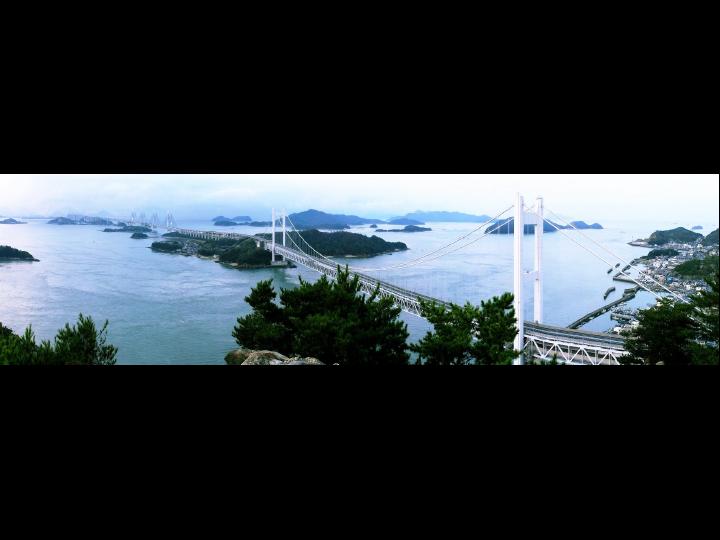小説 堀河の局

堀河の局
今田 東
序
そこを行(ゆ)かれるお坊さま・・・誰ぞお尋ねでございましょううかな。この京は西山辺りには人は誰も住んではおられませんゆえ・・・道でも間違われたのでしょかな。・・・。
なにぞこの尼の顔についておりましょうかな。歳を取り醜(みにく)い尼が荒れ放題の庵・・・珍しゅう御座いますかな。
・・・もしや、あなた様は・・・西行どの、西行法師殿・・・。左様でござりましょう。いいえ違いませぬ・・・お顔は・・・お変わりになられておられますが・・・あの頃の面影が・・・。
笠をお取りになってように見せてくだされませい・・・。
この堀河は歳を取るというまだ歩んだことのない道を彷徨(さまよ)い、西行殿に一目ではお分り頂く事も叶(かな)わぬ程の変わりよう・・・。
笠をお取りになられたそのお顔、まさしく・・・。
それにしましてもなんというお変わりようで御座いましょうか。歳月を無駄になさらず、ご立派に・・・男を、いいえ・・・。人を研かれたのですね。
女院様がみまかられてその後消えるように京をお離れになられ、能因法師(のういんほうし)様が歩まれた道程(みちのり)を訪ねられ陸奥(みちのく)は平泉(ひらいずみ)へ、その道すがらお目にしたことの様々をお心に貯えられ、流れに宿命(いのち)を託す生き方をものにされ、また、お帰りの後は高野山にお入りになられ数多(あまた)の経を読み砕き無言の行に励まれたことは・・・。大峰山の頂へ登られるという荒行・・・。そして、高野、吉野、伊勢の二見、奥嵯峨、小倉山、西山と庵をお結びになられ、仏の道を極めるご修行を、歌の言葉の習得をと・・・。
崇徳院とのご親交によってさらにさらに森羅万象(いきとしいけもの)を包み込まれて、御仏の意を、お歌を深められ・・・。和歌(うた)で人の心も現実(うつせも)も変えようと精進なさいまして・・・。
風の便りで・・・そのことは・・・。
人は為す思いがあれば如何様(いかよう)にも変われるのものなのですね。お出立ちも御風貌も・・・。錫杖(しゃくじょう)をつかれたお姿が、墨ごろもがよう馴染んでおられますな。
今の、堀河の前にお立ちになる西行殿には・・・。
正に・・・この堀河が近寄れぬなにか空気の壁があるような、また、引き込まれそうな力を感じまするが・・・。澄んだ眸のなかに宿る厳しさと、深い慈悲の光・・・。削り落としたような頬には理知と耐えぬかれた修行の後を刻まれ・・・。
それではわざわざこの堀河を尋ねてくださりましたのか。そうで御座いますか、よくぞ尋ねてくださいましたな。
この雨や風に晒(さら)され傷んだ庵では御座いますが、濡れ縁に座って都を眺め東山を望み、昔の懐かしい事どもを思い起すには・・・。今の我が身を静にここに置き、待賢門院璋子(たいけんもんいんたまこ)様こと女院様をご供養いたし偲ぶには最も確かの所で御座いまする。女院様の陵(みささぎ)もここから近こう御座いますゆえ、今の私には相応の場所でございます。
汚れた池になお見せる蓮の花・・・。枯れてもなお季節(とき)を感じ咲く野辺の花・・・。その花の命をいとおしく眺めることも出来ます。また、雨の風の景色を彩るさまざまな営みにも・・・。
御仏に縋(すが)り、森羅万象(いきとしいけるもの)に心を託し、手を合わせる日々・・・。
兵衛(ひょうえ)に西行殿におうたら一度尋ねてほしいとの言伝(ことずて)、届きましたのか。待賢門院様の皇女上西門院統子(じょうさいもんいんむねこ)様の女房をいたしております妹の兵衛とは仲ようしており、西行殿が良く菩提院(ぼだいいん)へ足を向けられお会いすることがあると聞き及んで一度こちらへお尋ね頂ければと頼んでおきましたのですけれど・・・。
上西門院統子様にはすっかり女院様の面影を備えておられますと か・・・。
女院様のご落飾(らくしょく)のおり私と中納言の局が御供を致し出家をいたしました。兵衛も御供をすると言い張りましたが、未だ若かったので思い留まらせ内親王統子様へ・・・。女院様亡き後、私は仁和寺(にわじ)に入り、中納言の尼は高野山西麓の天野へ・・・。そしてこの堀河は西山へ・・・中納言の尼はその後、小倉山に庵を結んでおります事は・・・。この西山も小倉山も西行殿には縁(えにし)の深い地で御座いましょう・・・。まだ奥嵯峨に庵をお持ちとか・・・。
それにいたしまてもうれしゅう御座いまする。願いが叶ったので御座いますもの。今日はなんという良い日でございましょうか。朝起きたときなにかいい事がと・・・何度も庵への坂を上がり降りをいたした甲斐があったというものでございます。
朝夕の御仏へのお願いが届いたのでございましょうか・・・。
御仏のご慈悲か、お悪戯(いたずら)か、さてどちらでございましょう。
底冷えのする都の地にも、山の木立は芽を吹き始め、またこの庭の山櫻はあのようにして漸(ようやく)く蕾をつけましたょ。西行殿と都と櫻・・・。
それよりも何よりも西行殿がご立派にお過ごしのこと、昔を知る者にはほんに胸を撫で下ろし、近しく昵懇(じっこん)にしていただいた者には誇りにすら思えまする。
鳥羽院の北面(ほくめん)の武士佐藤義清(さとおのりきよ)殿が、今、歌人(うたびと)西行と、御仏の使いの円位上人(えんいしょうにん)、その名声は都はおろか国の隅々まで届いておりましょうほどに。
おしゃべりが過ぎますか・・・。
にこにこ笑ってないでなにか申されませ。女子に喋らせて・・・歌詠みは喋らぬもの、語ると歌の魂が消えてゆくとでも言いたいので御座いまするか。ほんにお手のかかるお人じゃな。全くあの頃と変わっておりませんな。
佐藤義清どの、西行法師殿・・・
終日一人庵に篭もり考えることは、華やかであった頃の待賢門院璋子様のこと、そして、西行殿のこと・・・。
はたして、この堀河がいたしたことは良かったのかと・・・。そのことは私を思い煩わせ・・・。この数年心の澱(おり)となり何やら重い石を胸に抱いているように晴れやかな日がありませなんだ。御仏に心を託しても、しかし、今日、西行殿にお会いして、お顔を拝見いたしまして少しは心やすうなりましたが・・・。
ああ、こんな筈では御座いませなんだ。
懐かしき想い人を前にして、まるで恨みつらみの言葉を投げ付けているようで・・・。
歳を取りますると何もかも吐き出してしまわないとと焦りまするが・・・。何事にも顔を赤らめておりました私がこのようにお喋りになって・・・。一人で居りますと胸に言葉がつかえまして、西行殿にお会いして一気に口元がゆるみ零(こぼ)れまする。
このような私をお許しくださいませ。
ただただ嬉しいゆえなのでございますから。
さあさ、むさくるしいたたずまいでは御座いますが、お上がりくださいませ。
さあさ、脚絆(きゃはん)に草鞋(わらじ)をお取りになられて・・・さあ・・・。
このような、着るものは墨衣(すみごろも)、住まいは何もなくさんじらかし・・・。欲も得もなく生きておりますと、遠い昔のことが泡沫(うたかた)の夢のように感じられることも御座いますが・・・。
あれは・・・。
西行殿が父源顕仲(みなもとあきなか)の所へ歌を持って通ってこられておられましたのは・・・。
私が父の病気見舞いで里帰りをいたしておりました折り、まだ十代の西行殿、いいえ佐藤義清殿に初めて御目かかりました。
その頃、待賢門院様に姉の大夫典侍(だいぐてんじ)、妹の兵衛(ひょうえ)、それに私、姉妹三人がお側でお仕えいたしていたのでございま す。
そのことはご存じで・・・。遠い日その事はお話を・・・。
蹴鞠(けまり)の上手な若者、まだまだ歌は未熟では御座いましたが、父顕仲が申しますには直接訴えてくる不思議な歌じゃと、綺麗に歌うのではのうて森羅万象の心を歌っておると申し、将来が楽しみじゃと・・・。父の目は曇ってはおりませなんだな。
年上の女でも、義清殿を遠くから眺め弾んだ気持ちがおこりましたぞ。この私は艶やかに着飾り装い、顔に化粧(けわい)を施(ほどこ)し・・・。それ程見 事な美丈夫なお人で御座いましたゆえ、都の女子を如何程(いかほど)やきもきさせた事でしょうかな・・・。この歳になっては恥ずかしさも慎みも捨てて何事も言葉として口の端に乗せることが出来まする。今にして思うにあの時から、想い人として密かに心に・・・。その事が、のちに義清殿の行為をお助けし叶えるという事へと繋(つな)がっていたのでしょうか。
義清殿には萩の前様とご一緒になられ・・・。
それから、鳥羽院の北面の武士として御所詰所での警護、御幸の御供と。
義清殿は鳥羽院のご寵愛はめでたく、将来を嘱望されておいでで、紀伊の國は田仲の庄のご安堵は約束され、同輩から羨望の的として見詰められておいででしたょ。義清殿は、蹴鞠に乗馬、そして弓と励んでおられましたな。特に歌の習いごとは御気性の通り熱く懸命に・・・のめり込まれて・・・。上達も早うございましたな。
その頃、女院様には欲しいものは総てが叶う、そのお力は比べるべき女人はおらず、の生活は暗喩(くらい)の日々が・・・。
女院様の幸せは時の流れとでも申すのでございましょうか、白河法皇が御崩御なさいました後、様変わりを見せたのでございます。 女院様は七人のお子に恵まれましたが、鳥羽院のお足がだんだんと遠退きお淋しい季節を過ごされるようになるので御座います。鳥羽院には十七才の得子(なりこ)様をお側から離す事無く過ごされておいでで御座いましたから、夜枯れが続いておられ、あの権勢並ぶべき者がないと言われておいでだった女院様の時代が終わろうとしておったのでございます。
幸福(しあわせ)など川を流れる泡のようなもの、永遠(とこしえ)などこの世にあろう筈は御座いませなんだ。
そうでございましょう、西行殿・・・。
それでも、待賢門院様の御所は才長けた美しい女子の園で、賑やかに笑いがたえませなんだ。が、だんだんと女院様の一喜一憂に心を砕くという日々を過ごすようになるのでございました。
お淋しい事のお嫌いな女院様は白河法皇の護願寺と致しまして法金剛院を御建立に心血をそぞいでお気を紛らわせておられました。女の喜びを知った熱いお体を鎮めるために何人の男を引き込みになられたか、その時女の哀しみと強かさを感じ取ったのでございます。女の性、それはどのような罪をも恐れぬものでございました。
男を手引き致したのはこの堀河で御座いました。
男の性とは異なりますゆえお分り頂くことは叶いますまいが・・・。
女院様と西行殿がお会いなされたのは・・・。
女院様こと璋子様は藤原氏北家の流れの徳大寺家の御出身、義清殿もその流れ、義清殿が稚き頃より徳大寺家へ出入りをされて、璋子様にお会いになられておられるのでしょうか・・・。私の知るかぎりでは、鳥羽院と女院様が熊野詣でのおり・・・お初めてと・・・。
鳥羽院は女院様の仲を男と女のご関係を超越(通り超し)され、ご敬愛(うやまいあいす)というお間柄で接しおられました。鳥羽院は女院様をお誘いになられ熊野詣でを好んでなさいました。
女院様をお慰めするという意味がございました。つまり、ご機嫌をおとりになるという・・・。
崇徳新院と後白河帝との確執、保元の内乱・・・。崇徳新院が敗れ讃岐は直島へ配流(はいる)・・・。女院様が御存命なら嘆きはいかばかりであったことか・・・。お二人のお子が争う事に身も細る思いで、ただ御仏に縋るそんな日々であられたことで御座いましょう。
西行殿は崇徳新院と後白川帝の仲を取り持つためにいかほどの努力をなさいましたことか・・・。お心を痛められたことか・・・。 その事でまた大きくなられ・・・。
藤原璋子様、中宮璋子様、それから待賢門院様へ、女子と致しましてどうであられたのかと・・・堀河はこの歳になって初めて羨ましく想うのでございます。
西行殿、女とは此の様な者・・・愚(おろ)かで・・・いいえ、強かで・・・。お分り頂けますまいが・・・。
破
白河法皇に一身の寵愛(ちょうあい)をうけておられた祇園女御(ぎおんにょうご)様のもとへ御養女としてお入りなられ、そこで法皇に孫のように可愛がられた藤原璋子様・・・。そこから運命の糸は複雑に縺(もつ)れあい絡(から)み合いを見せるのでございますが・・・。
西行殿、あの頃の堀河の女と致しましての感情の起伏(たかまり)より、今はあの頃のことを静かに眺め、振り返ることが出来るのでございます。
知っておりながら言葉にならなかった事が今、言葉として語ることが出来るので御座います。
総てを捨てこの西山に庵を構えなにの柵(しがらみ)もなく過ごし御仏の使いとして、経を読み、書き写す心静な日々、今まで見えませなんだ物が見え、物事の理(ことわり)が分かるにつれて・・・。振り顧(かえり)みますと、私の人生は女院様の生き方の中にありまして、私を語るときには女院様の総てを語らなくてはなりませぬゆえ。 それゆえに・・・。
女院様との関わりのあります西行殿にお会いしてみとうなりましたのです。
源顕仲の娘として生まれ、父の影響(いきかた)から歌を学び、堀河として中古六歌仙の中の一人、また「千載(せんざい)和歌集」にも取り上げられ歌詠みと認められるようになるその道程(みちのり)で、令子(よしこ)内親王の女房、六条の局としましてお仕え致し、それから堀河としまして藤原璋子様に・・・。
祇園女御様を源忠盛殿へ下げ渡したその夜、お二人はなにの差し障りもなく結ばれました。璋子様は幼き頃より白河法皇にまるで成熟した女のよう甘えになられ、胸に抱かれておいででございました。
それは艶っぽく、男の心を蕩(とろか)すいたずらの瞳とあどけない仕草を持っておいででございました。それにもましてお声は皆の心を擽(くすぐ)り魅了する響きを持っておいででございました。お生まれついてた御気性だったので御座います。
それから・・・毎夜のようにお二人の痴戯は続きました。
お二人のことをなぜか不潔に感じなかったのはどうしてか、むしろ清々しく思えたのはなぜだったのか、不思議でございました。まるで母か姉の心で眺めていたのでございましょうか。
女子の私は振り返ってみますれば羨ましゅうさえ思えるのでございます。あれほど愛される女子の幸せを知らぬゆえなのでしょうか。
月の物を知ったすぐ後、男を向かい入れる、歳の端(は)のいかぬ少女の痛々しい性。女として生きる意味を知らされるということ、夜毎の営みがより深い悦びに誘うということ。そのお相手がまして、この國一番の権力者に愛されていることになればこれ以上の女の冥利(みょうり)で御座いませんでしょう。女子は強い男の愛を欲しがるものでございます。
常に雌は強い雄を欲するもの、それはあらゆる動物(いきもの)の世界の成り立ちでございましょう。森羅万象悉(いきとしいけるものことごと)くその営みが・・・。人の世も変わりませなんだ。
あれほど睦みあいを重ねられてもご懐妊(おめでた)がなかったのは幸せであったのか・・・そのことを考えますと・・・璋子様の行く道が変わっていたであろうことを考えたりいたしました。
堅い蕾が男の愛撫で柔らかく揉みしだかれ白く粉を吹いた透き通った柔肌に変わり、ふっくらと丸みをおび括れた曲線をたたえたお肢体(からだ)にお変わりになる、森羅万象自然の理とはいえ、見事な女の脱皮(せいちょう)を見たようでございました。
若い男を引き入れ情交するということもみな白河法皇の愛を確かめるためでございました。それは白河法皇がお許しになる事を承知の上でのこと、わざと男を欲しがったのでございます。幼いいたずらでございました。
西行殿、今は櫻も蕾をつけ寒さに耐えてはおりますが、やがて綻びてまいりましょう。寒い冷たい季節を耐えたものが初めて花咲かす事を許される、人の世もまた変わりませぬ。苦しみ辛さを耐えた者が許される誉れ・・・乗り越えられ血肉にされてなお励まれる修養。・・・まるで風の様で・・・それを受け流す柳の様で・・・。 西行殿、お見事でございますな。
白河法皇は璋子様の行く末を按じられて幾つかのご婚儀の話を進められましたが、祖父のように可愛がられた白河法皇との交わりを知っていてなんのかんのと逃げて話がまとまりませんで御座いました。処女(おぼこ)でなくてはと言うような風習はありませなんだが、祖父と孫が愛し合うような間柄、そのことには男と女の出入りに寛容な時の世でも神経を逆立てたのでは御座いますまいか。
祇園女御様のように、白河法皇に愛され後に源忠盛殿ヘ下げ渡す、何人もの男を引き込みながらも輿入(こしいれ)する、そんな世間(よのなか)では御座いましたのに・・・。
最後に白河法皇はお孫にあたる鳥羽の帝(みかど)への話を創りまして御座います。
鳥羽の帝は何とも言えずそれをお受けになり、鳥羽の帝十五才、璋子様十七才、入内(じゅたい)が決まったのでございます。
璋子様のお心がどうであられたのか、最初にお肌を会わせたお人、初めて蕾を開き甘い蜜をおすいになられたお人、そのお人が進めるご婚儀に従わなくてはならぬ我が身の運命。その運命を抵抗(あらがう)ことも許されない事にどれほどの哀しみをお味わいになられたか。お話が決まりましての璋子様は終日泣き明かしておいででございました。そこえ白河法皇がお越しになられ白いお肌に馴染まれる、その慰めの行為により喜びと哀しみが交錯致しておいででございました。断ることの出来ない肢体(からだ)との戦い、求めるいじらしい一途さ、お側で見ている私達は切なさに身を捩(よじ)りました。
入内の儀の日はとどこうりなく過ぎましたが、その夜から高熱に身を妬(や)かれまして御座います。夜には庭に出て衣をむしり取り、髪を掻き揚げ狂ったように泣き伏したのでございます。
夜空に上がった蒼い月が池水の上で微かに揺れておりました。がたちまち雲の中へと隠れたのでした。水鳥が一斉に飛び立ち暗い夜の空へと消えて行きましてございます。
その日はお疲れのご様子と鳥羽の帝に申し上げておりましたので、お立ち寄りもなく事は済みましたが、これからのことを考えますとどのようにと女房たちは茫然と致しました。
鳥羽の帝とご婚儀がなされてもご一緒に過ごされることはなく、ご病気を口実に御所に篭もられる日々で御座いました。
数日が過ぎまして璋子様は御所をお出になられ白河法皇のもとへ・・・。
中宮璋子様のお便りを運んだのはこの堀河で御座いました。色々と言い訳を設けての逢瀬、女房達ははらはらと気を揉みました。
鳥羽の帝に入内なされ中宮(ちゅうぐう)となられましても白河法皇との中は続くので御座います。璋子様を一度はお離しになられた白河法皇は異常とも言える愛欲をみせられ以前にもましてお肌を欲しがられたのでございます。
それは、匂いを放ち蜜を滴らせて待つ花びらに吸い寄せられる蝶の様を見るようでございました。
それからは世間を気にすることを忘れられたかのように白河法皇が御所にお出向きになられ、昼夜を問わずお過ごしになられました。そんな時、女房達はお二人の気配を押しやるように習いごとを始めるのが常でございました。
その時、白河法皇は六十七歳を過ごしになられ眼窩(なみだぶくろ)は垂れて喉元に弛(たる)みをたたえ老いの染(し)み皺を表されておられましたが、まだまだお元気で若こう御座いました。それはまるで璋子様の若さを吸い取り若さを保っているようにお見受けいたしましたが・・・。
璋子様は、十七歳の幼さをお感じさせないほどの女の色香(つやっぽさ)を見せておいででございました。それは白河法皇によって堀り起こされ目覚まされ磨かれたものでございました。
濡れたような黒髪、ふくよかな頬、潤んだ瞳、瑞々しく透き通った肌、それは正に落ちる前の果実のようでございました。それを鳥達が啄(つい)ばむ、まさに白川法皇は一羽の鳥・・・。
女院様のお美しさに堀河も身震いがするほどで御座いました。
白河法皇はご信仰の篤(あつ)いお方でございました・・・理の何たるかの造詣(おもい)は深こう御座いました。そんなお方でさえ理性(あたま)で抑(おさ)えられぬものがあったのでございます。
一年の後、皇子を身篭もるので御座います。鳥羽院から伯父子(おじご)と言われた崇徳の帝ごでございます。お二人目の禧子(よしこ)内親王も白河法皇のお子か鳥羽の帝のお子か定かでは御座いませんが・・・。不義と言うより鳥羽の帝が黙認(みてみぬふりを)した仲でのことでございました。
なんとも総てが思いの外、祖父と孫が一人の女を同時に愛するという倫理(ひとのみち)とか常識では図り知れぬ世界であったのご
ざいました。
西行殿、このような物語(はなし)は聞きとうない・・・。昔の義清殿ならばそう申して太刀を振り下ろされるやも・・・。
今の西行殿は何事も総てを大きく包み込む・・・御仏の心をお持ちでございましょうから・・・。
風が少し出ましたか、夕暮れが近こうなっておるのでございましょう。暫らく致しますと東山に月が懸かりましょう。
白河法皇がお勧めになられて鳥羽の帝は稚い崇徳の帝に譲位(くらいゆずりを)され鳥羽院になられておいででございました。
白河法皇とのご関係は続いておられましたが、鳥羽院との仲も睦ずましくなられ、お二人とのご情交(むつみあい)が続くのでございます。
そんな時、応接に女房達は慌てふためくのでございました。
まるで畜生のそれでは御座いましたが、女院様はお二人を同時に愛される事の出来るお性質であられたのでございましょう。
御身に沁み込まれた蠱惑(こわく)でお二人の心を虜(とりこ)にしたのでございます。
璋子様にはこの頃が一番幸せの絶頂で御座いました。白河法皇とも睦みあいになられ、そして、鳥羽院の寵愛(ちょうあい)を一身にお受けになられ、毎夜のごとくお肌を重ねられ、次から次へと年子(としご)で四人の御出産、一年後にもうお一人と・・・女子といたしまして充実した日々を過ごされておいでで御座いました。
崇徳新院と保元の乱を起こしました後白河の帝は鳥羽院と女院様の皇子で御座います。
西行殿はお二人の中にあってお悩みになられたことでございましょう。女院様の皇子のお二人が権力を・・・。
崇徳院のみまかられての後ゆかりの讃岐は善通寺をお尋ねになられ・・・。世の無常をお感じになられ・・・。その旅もまた歌を深める事に・・・。
女院はお幸せなな日々を過ごされておいでで、女房たちは華やかに装い女院様と観櫻の御供として出掛けたり、熊野詣でを致したり、歌合せ(うたあわせ)へと心を落ち着かせ過ごすことが出来ておったので御座います。
女院様の一行は女房達が目を見張るような衣裳(からころも)を身に纏(まと)っておりましたので評判でございました。女院様のお力の賜(たまもの)でございました。
七人目のお子を宿されておられたときに、白河法皇がご崩御(ほうぎょ)をなされました事は、お子に差し障ることを按(あん)じられ女院様へはお伏せになられました。
白河法皇、七十七歳の大往生で御座いました。
ご出産の後、退いていく潮のように、女院様の運気(うんき)と申せばいいのでしょうか、白河法皇という後ろ盾を失い日陰の時へと移り変わっていくのでございました。
女院様は崇徳の帝へご愛情をましてお深めになるのでございます。その事がお力を保つ唯一のものでございましたから。
人の道は良きことは長続きはせず、苦しきことのみが・・・。それ故に御仏のご慈悲が・・・。
鳥羽院は周囲の者が目を見張るほどの溺れようと言われます得子様へのご寵愛は日毎につのり、女院様の淋しさは頂点に達しておいででございました。奈落の日々とでも・・・。
それでもなお、母親思いの崇徳の帝がおられますことが何よりの慰めでございました。
鳥羽院の女院様へのご愛情は昇華いたしまして尊してやまず、敬愛へとお変わりを見せたのでございます。まるで母上への愛とでも申せばいいので御座いましょうか・・・。
鳥羽院と女院様の熊野詣でに中宮となられた得子様がご一緒なされまして・・・。女院様のお心は安らかであられたかと・・・。
女院様はご一生で十三回の熊野詣でをなさりました。それもなぜか厳しい季節を選ばれてのお行きでございました。その辺りに女院様のお心の苦衷(くるしみ)が見えるのでございます。
御所での女院様はその頃から写経に読経の日々が訪れるのでございます。また、寺院の御建立へと・・・。
ですが、女院様のお肢体は理性では抑えることが叶わず何人かの男を向かい入れなくては業火(ほてったからだ)を鎮めることが出来ず、女の哀れさを思い知るのでございました。そして、お立場の苦悩を・・・。その手引きをこの堀河が・・・。
自然の営みは変わらず巡り、人の心の有様を知ってか知らずか、繰り返すのでございます。
女院様は慎ましやかで温和しい、そして明るい事の好きな御気性のお方でございました。そのようなお方であられたから女院様を取り巻くあの才気煥発な女房達は離れる事無くお仕えしていたのでございます。その生い立ちから男の、女の性を充分にご存じのこと、煩わしい悩みを打ち払うには御仏に御縋りするしか道はなかったのでございます。
白河法皇の護願寺(ごがんじ)しての法金剛院の御建立は、白河法皇の御崩御の一年の後、落慶法要(らっけいほうよう)がつつがなく行なわれたのでございます。
それからの女院様は頻繁(ひんぱん)に神社へ御幸(ぎょうこう)、塔のご供養をなさいまして御座います。それほどお悩みになられておいでだったのでございます。熊野への道程(みちのり)を・・・。
西行殿は、十七歳で北面として・・・。同輩に今はときめく平清盛殿・・・。白河法皇が平忠盛殿に御下げ渡した祇園女御様のお子、世間では白河法皇のお子と・・・。その事は神仏のみご存じのことで御座いましょう。
義清殿は鳥羽院にいたく可愛がられ・・・お側には常に・・・。熊野詣での折り、初めて女院様のお姿を・・・。凛凛しき若武者を・・・。お二人がお目にされたのでは御座いますまいか。
この庵で、堀河が何をと・・・。嵯峨野の里、小倉山、そしてこの西山・・・。西行殿が歩かれた小径になにぞ落ちてはいまいかと・・・。山里の静けさ、ため息が落ちても鳴り響く鈴のような音、風が枯れ枝を揺らし奏でる啜り泣き、季節の健気(けなげ)にも咲くか弱き草花、雨の軒を叩く慈しみの音色、小鳥の大らかな囀(さえず)りの営み、その一つ一つに両の手を合わせ、森羅万象にまた合わせる。そんな堀河の言葉を三十一文字(みそひともじ)に託しても人の心には通じませぬか。老いすればやがて朽ちる命を今は過去の幻に思いを馳(は)せ語る人とてないこの小屋にて、昔知りおうた人達のご成仏と健やかなる営みをみ仏にお祈りいたしておりますと、穏やかな精神と研ぎ澄まされる神経に快いときを過ごす事が出来るのでございます。かつては、男と睦(むつ)みあう女の幸福を、そして、好いたお人ともに歩み苦労をする、そんな道をと・・・。考えたことがありましたが・・・。これもみな御仏のご慈悲と・・・。
零れるように煌(きら)めく満点の星、まるで手が届くようで幾度手を差し伸べたことか・・・。月に託して恋を語り・・・。
西行殿、この堀河まだまだ歌の心を捨ててはおりませぬ。
和歌は歌う人の御仏、歌詠みが歌を創るということは仏を創ること、その想い、いつか西行殿からお聞き申したゆえ・・・。
この辺りは日暮れがはようございます。名残の陽は洛中を照らしますが・・・。東山がまだあのように赤々と染まり・・・。
まるで、女院様と美福門院得子様の有様のようでございます。
女院様の女房たちはお歳で退いていく方の他は離れることは御座いませんでした。
女院様がご落飾を思い立たれたのは何時のことであられたのか。衰えをお見せにならない優雅ないでたちはお変わりなかったので御座いますが、時折お見せになられるお一人の佇まいには憂(うれ)いが漂っておりましたので御座います。
お部屋で読経、写経の日々をお過ごしになられる女院様をお庭へ散歩にお誘いいたし、また、欄干(らんかん)にしなだれかかる櫻をご覧にとお勧めいたしたものでございます。
水面に枝を差し出すしだれ櫻、薄紅色の花びらが、風の悪戯によって、また、時を終えて散る様を、その姿に涙をお見せになる、そんな女院様を優しく愛しく眺めたことか・・・。
女院様は草木の花は総てお好きであられましたが、特にしだれ櫻を愛でておいででございました。
しだれ櫻に御身をお重ねになられたのでしょうか。
鳥羽院、崇徳の帝からの船遊びや、観櫻の宴、紅葉狩りなどの誘いは常にございました。が、なかなかお出かけになることもなかったのですけれど、私達女房を気遣ってお受けになられることも御座いました。
女院様がお幸行(かけ)の折りは私達女房も御供をして晴やかな場所へ着飾って出られ、楽しい一時を過ごすことができるゆえでございます。そんなお優しいお心遣いは、御身のお立場を越えてお見せくだざいました。
法金剛院は五位山の麓の広大な敷地に御建立。西御堂、南御堂、阿弥陀堂である三昧堂を揃え、それに五重塔、当時の宗派を備えておりました。まるで女院様が浄土をお感じらなられる場所の様でございました。そう申す者がおりました。また、広い池をもち、その周りを馬場にし、船遊びや競べ馬(くらべうま)の出来る仕組みで御座いました。それに、精舎(じいん)は花をつける草木は植えぬものと言われておりますが、四季に花を見せる希有(まれ)な精舎で御座いました。女院様のお心は花を御覧になられ華やかであった白河法皇とお過ごしになられた昔を思い出す事より、お深い道へとお入りになられようと致していたのでございます。女院様のお心のまま女房達が植えたでございます。
西行殿、御仏は人の営みの総てをお許しくださるものでございましょう。それがお慈悲で御座いましょう。四季に咲く花の命に心惑わす、その薫りに心定まらずでは、なんと修行のなさでございましょうか。何事があろうと一心に務めることこそ大事であろうと想われまするが。
西行殿のお歌・・・。
仏には 桜の花をたてまつれ
わが後の世を ひととぶらはば
そのように歌っておいでですから・・・。
急
崇徳の帝が法金剛院で観櫻の宴をお開きになられましたその日・・・。その日が、女院様、義清殿にとって運命を変える日になろうとは誰ぞ知る由(ゆし)もなかったことでございました。
催しのなかに競べ馬が御座いました。馬場は大きく曲がるところがありましたが、義清殿は騎馬を巧みに操り、皆が落馬をする中を颯爽(さっそう)と一番乗りを致しましたな。女院様は「のりきよ、義清」とお手を叩いてまるで無邪気なお悦び様で御座いました。 その見事さに女院様が褒美(ほうび)を取らすと仰せになられたのです。私は義清殿にその事を告げに参りました。義清殿は女院様直々の沙汰に怯(ひる)む事無く女院様の御簾(みすだれ)の前に手を着き膝を折りかしこまりました。
御簾の中から義清殿の姿を見られた女院様は、私の方へお顔をお向けになり頷かれたのでございます。私は御簾を揚げました。
その瞬間・・・。
女院様はお身体の力が抜けたように前に少し倒れかかられ、義清殿は咄嗟(とっさ)に両の手を差し出されて・・・。お二人はじっと見詰められておいででございました。そして、義清殿はわなわなと震えだしたのでございます。
辺りは暗やみになりまるでお二人のお姿のみに明かりが・・・また、落雷の稲光がお二人の間に・・・。
お側に居りました私は目が眩(くら)み驚いて平伏しました。
その時、なにかをお感じになられ・・・。
女院様は三十九歳、義清殿は二十三歳の頃で御座いましたな。たしか・・・。
西行殿、憶えておいででございましょう。人は忘却の川を渡るとは申せ、その淵に佇(たたず)みもどかしい日々を過ごしたことを・・・。あの時、過去も未来もなく今を生きておられましたな。否、時を、一瞬を・・・。総てを捨ててなおその出会いを・・・。
西行殿、人として今まで感じたことのないその悦びはやがて苦しみへと・・・。愛するという地獄を・・・。あの一時のご対面が一劫(いちごう)の時に勝るとお感じになられましたことでしょう。運命の悪戯はよりお二人の心の中に、池に小石を投げ込むように、恋情を広げられたのでございましょうな。
その日から女院様は頻りと義清殿のことを尋ねることが多うなったのでございます。運命をお感じになられて総てを森羅万象に託され、一度はお捨てになられた、お忘れになられた女院様のお心に愛の火が灯されたのでございます。義清殿により芽生えたのでございます。
そのお姿は、今まで男を引き入れた女子の血潮ゆえでなく、いじらしい程のお恥じらいをお見せになられ、頬を薄紅に染められ、立ち振る舞いもまるで少女の様でございました。
三条京極第(さんじょうきょうごくてい)の御所にお仕えする女房はそのお可愛らしさにほーとため息をつきました。
都は頻りと風花が舞っておりました。うっすらと大路を白く染め土壁から枝を延ばした寒椿の花びらが時折音を発て下りました。
京独特の身を刺すような寒さでは御座いましたが、女院様のお心は熱う燃えていたのでございましょう。
そんな日々のなか、女院様のお心もお身体も北面の義清殿へ傾斜して行かれまして御座います。
「堀河、あなたは本当に人を愛したことがありますか」
「運命、その運命に沿って生きただけの恋は本当のものではあり
ませなんだ」
「多くの人を愛したように想うが、愛ではなかった」
「もっと早く、若かった頃巡り会えていたら・・・」
「苦しいのです・・・」
「最初で最後の恋、そのように想われて・・・」
「私の人生は総て御仏が仕組まれた・・・ご慈悲なのですね」
几帳(きっちょう)の外に控え待つ私にそのようは弱音を洩らされまして御座います。それはまるで初めての恋をお感じになられた時のように・・・。想いの深さ重さがひしひしと伝わりましたゆえ・・・。
西行殿、あの日、櫻の花びらが、池の水面に垂れ下る櫻の枝から零れるように・・・。
月明かりの下、義清殿を女院様の寝所へ導き入れたのは・・・。「堀河、明かりはいりませぬ」
女院様のくぐもったお声が・・・。
静謐(せいひつ)が暗闇のなかにただ広がっておりました。
更け待ちの月明かりのもとしだれ櫻が紫に染まって・・・。
「一生一度の恋、一夜の想い・・・。私は今日から一人ではない。義清がいつも側にいてくれる・・・。一度ゆえこのように美しくこれからの道を歩んでいくことが出来るのです。終わりが始まりであるのです。もっと大きな広い確かな世界へと誘ってくれるのです」 女院様は、御簾を揚げられ庭のしだれ櫻をご覧になられながら、お言葉を落とされまして御座います。
昨日までのことが嘘のように晴れ晴れと、何事かをふっきられたお姿でございました。
義清殿が、突然の得度(しゅつけ)のことは・・・。
幸福なご家庭を・・・御妻女を、お子を捨ててなお・・・。
女院様は驚かれるお様子もなく莞爾(にっこり)と頬を緩められておいででございました。
ご出家なされても、西行殿はよく御所を尋ねておいでになり、闊達(かったつ)な兵衛の局や明るい中納言の局と歓談しておいででございました。女院様のことはお心の中ではっきりとお決めになっておられるようにお見受けいたしましたが・・・。
女院様は兵衛の局や中納言の局が話す西行殿のことをお聞になられても、ただ、
「そうですか」と頷いておられました。
女院様を狂わせた忌まわしいことは総て義清殿との一夜で綺麗に洗い落とされたように、ご安堵な日々が訪れたのでございます。
が・・・。
崇徳の帝が、鳥羽院と中宮得子様との間にお生れの近衛の帝に譲位、崇徳新院、鳥羽院となられるという世間の動きは、女院様の
お立場をより煩(わずら)わしいところへと向かわせるのでございます。
母親想いの崇徳の帝が譲位され、女院様をお庇(かば)いになられるお方はいなくなりますと、女院様のお力は弱おうなるので御座いました。それに引き替え美福門院様のお力が・・・。
そうしますと、今まで快く想っていなかった人達の嫌がらせが始まったのでございます。女院様のお命をと御所に火をかけることは二度御座いました。
熊野からお帰りになられてすぐお住まいになられていた三条西殿が焼失・・・その前にも四条西洞院第(しじょうにしのとういんてい)が・・・と身にかかるご不幸は後を絶ちませんで御座いましたが・・・女院様は何も恐がることが無きように振る舞われておいででございました。・・・それから以前にお住まいになられておられた三条高倉第(さんじょうたかくらてい)へ・・・。
女院様のご心中はいかばかりかと気を揉み ましたが、それをお忘れになるように・・・。
女院様が三十一歳のお年から三十八歳の間に四度の熊野詣でをなさいまして、白河法皇のご供養と、鳥羽院、崇徳新院のご無事を御記念申し上げ、お子さまのご健康を、また御自身の平安無事を願われたのでございます。どれほどの思い煩わしいことがあられたのでしょうか、御仏におすがりになられ、また、遠い道程をお通いになられてなお、神のお加護をお求めになられたのでございます。
女院様にはそれからも様々な忌(い)まわしい、お心を煩わせる波が押し寄せるのでございます。関白忠通殿と美福門院様の暗い策略(はかりごと)で御座いました。それにじっと耐え時を待つように西行殿と同じ道へと登るのでございます。
花の命が繰り返され、女院様は四十二歳の折り御落飾を致すのでございます。
「これで女子でのうなる。どれほどの安堵(あんど)であろうか」 法金剛院の池を取り巻く馬場の方へ懐かしそうな視線(まなざし)をお投げになられて零(こぼ)された女院様のお言葉・・・。
女院様の運命に堀河も中納言も涙にくれましたぞ。
中納言と堀河が御供を致して髪を下ろしました。
兵衛の局は統子内親王の女房としてお仕えし、ここから女院様にお仕え致しておりました者皆別れ別れになるのでございました。
華やかで賑やかであった女院様のお住まいには、ただ静かな物音さえなく静寂(せいじゃく)が広がっておったのでございます。
その静けさにもまして、女院様のお心は一つの切っ掛けによって悟りを開かれたようにお平でお静でございました。
綺麗な歌は読み人がそのように生きているから生まれるもの。そのように生きてこそ、歌に心が入ったと言える。
歌は人の心を現実を変えるもの・・・。 歌で人を救う・・・。つまり、御仏の広い慈悲のようなもの・・・。それ故に御仏をこの世に生み出すとの・・・。光円が闇を照らすという・・・。
西行殿はその後仏道の修行をするでなく・・・。何をお考えなのか、京を離れる事も無く留まられて・・・。洛北(きょうのきた)に住まわれ・・・。何をお探しになられておいでだったのでございます。深いお考えの中でなにかを見詰められる眼は・・・。おやせになられ・・・。ご自分を責めに責められて・・・。ただ、夢中で御仏の、歌の世界を・・・歩まれておられたのですね。
西行殿、物事をその行為を総て背負われて・・・。それは、おとこの財(たから)・・・。生き歩む目的として・・・。その事で仏の修行にも、歌の道にも・・・。
西行殿、人とはなんと悲しい・・・いいえ、強く生きられるものかと・・・。
女院様は真如法尼(しんにょほうに)とおなりになられ、御仏のお使いとして生きられる日々が平安のうちに続いておられたのでございます。
「何があろうと私は一人ではない。義清がついていてくれる、それも御仏のご慈悲なのですね」
女院様はそうお言いになられ御身を慰(なぐさ)めておいででございました。
女院様の本当のお心はどうであられたのか、推し量ることさえ出来ませなんだ。
法金剛院の庭には藤だなから花が垂れ下り美しい簾(すだれ)のようでございました。
その一年後、はやりの病疱瘡(ほうそう)におかかりになられ、当代一お美しいといわれたお顔は・・・。
それから、寝込む日が多なったのでございます。
女院様は法金剛院から御病気快癒のために三条高倉第へお移りになられましてございます。女院様が三条高倉第を懐かしんだゆえでございました。
崇徳新院が結願(けちがん)の曼陀羅供養(まんだらくよう)を致した折りに鳥羽院もお出ましくださり優しいお言葉をおかけくださりましたが・・・。
女院様は何もお言いにならずただ小さく頬を緩めるという日々が多くなりました。
「運命に沿って生きた、その報いが・・・」とお笑いになられて・・・。苛酷な運命に対してもそれが我が身の運命と従順にお受け取られておいでのようでございました。
西行殿は三条高倉第の外で・・・。じっとしておられずにお気をもまれた事でございましょう。中納言の尼がそのことを女院様へ・・・。
「西行に心配はいりません。今の私は何も恐いものがありません。私には御仏と西行とがついていてくれますから、と伝えて下さい」 なんと言う穏やかな表情をされておられたか・・・。
西行殿はその伝事(ことづて)をお聞きになり涙を流されたとか・・・。より御仏に・・・経を上げられ・・・。
病臥(やまいにふし)なさいましてふた年が巡り・・・。
女院様は、起き上がられることもなくなり、長い夏の陽が西山に沈もうとしていた頃みまかられたのでございます。
名残りを惜しむかのように、蜩(ひぐらし)が一斉に啼きはじめまして御座います。
お手の中から数弁(すうへん)のあの櫻の花びらが・・・。
待賢門院璋子様こと女院様が・・・。
三条高倉第にて四十五歳のご生涯を終えられたのでございます。
かぐや姫は月の世界へ帰られたのでございます。
君こふる なげきのしげき 山里は
ただ蜩ぞ ともに鳴きける
女院様のお旅立ちに堀河はこのように歌いました。
西行殿、なぜこのように女院様のことを語ったか・・・。
総てこの堀河がなしたてむけは・・・。どうであったのか・・・。この堀河が女院様の歩まれる路(みち)をかえたのか・・・と・・・。
この世のことは総て転寝(うたたね)のまぼろし・・・。
その幻は御仏のご慈悲であったのでございましょうか・・・。
西行殿、お応え下されませい。
なに、これは・・・。そのお答えの歌なのですか・・・。
願わくは 花のしたにて 春死なん
その如月の 望月の頃
なんと・・・。
黙ってお立ちになられて・・・。何処(いずこ)へ・・・。
西行殿・・・。西行様!
この稿を書くに及んでの参考文献として
「西行花伝」辻 邦生著
「白道」 瀬戸内寂聴著
「待賢門院璋子の生涯」 角田 文衛著
「逆説の日本史」 井沢 元彦著
「平家物語」 作者不詳
「西行物語」 今田 東著
「山家集」「百人一首」
「西行」 高橋 英夫著
さまざまな諸先輩の労を無駄にせぬ様にと心がけましたがここまでしか書けませんでしたことお許しくださいますように。
作者敬白
これを決定稿とし、
別に稿を新たに「堀河」書いてみたいと思う。
「西行のゆくえ」
「中納言小倉山庵覚え書き」
「菩提院へ西行」
「児島澁川西行の旅」
を別に上梓したいと考えている。
<"EMBED"> SRC=http://www.geocities.jp/yuu323yuugojp/kinjiraretaasobi.mid AUTOSTART=TRUE REPEAT=TRUE
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0928 シンプリスト生活
- (2025-11-14 00:00:18)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-
-
-

- お勧めの本
- ★「心配なことと心配なとき」にチュ…
- (2025-11-14 08:59:24)
-
© Rakuten Group, Inc.