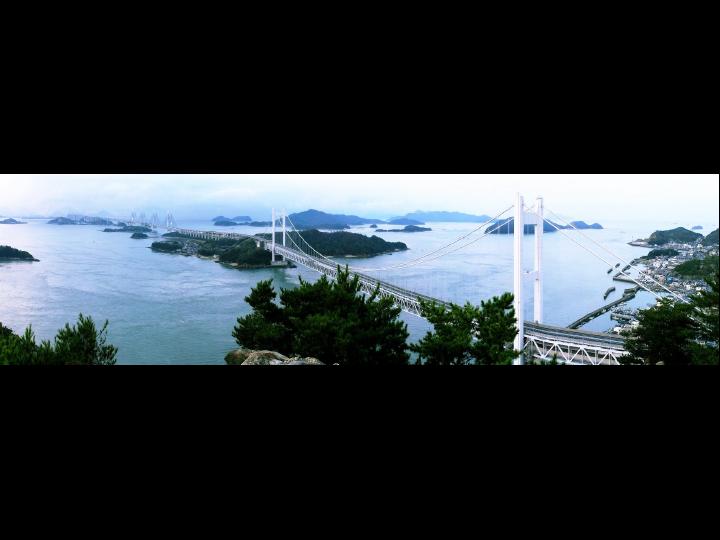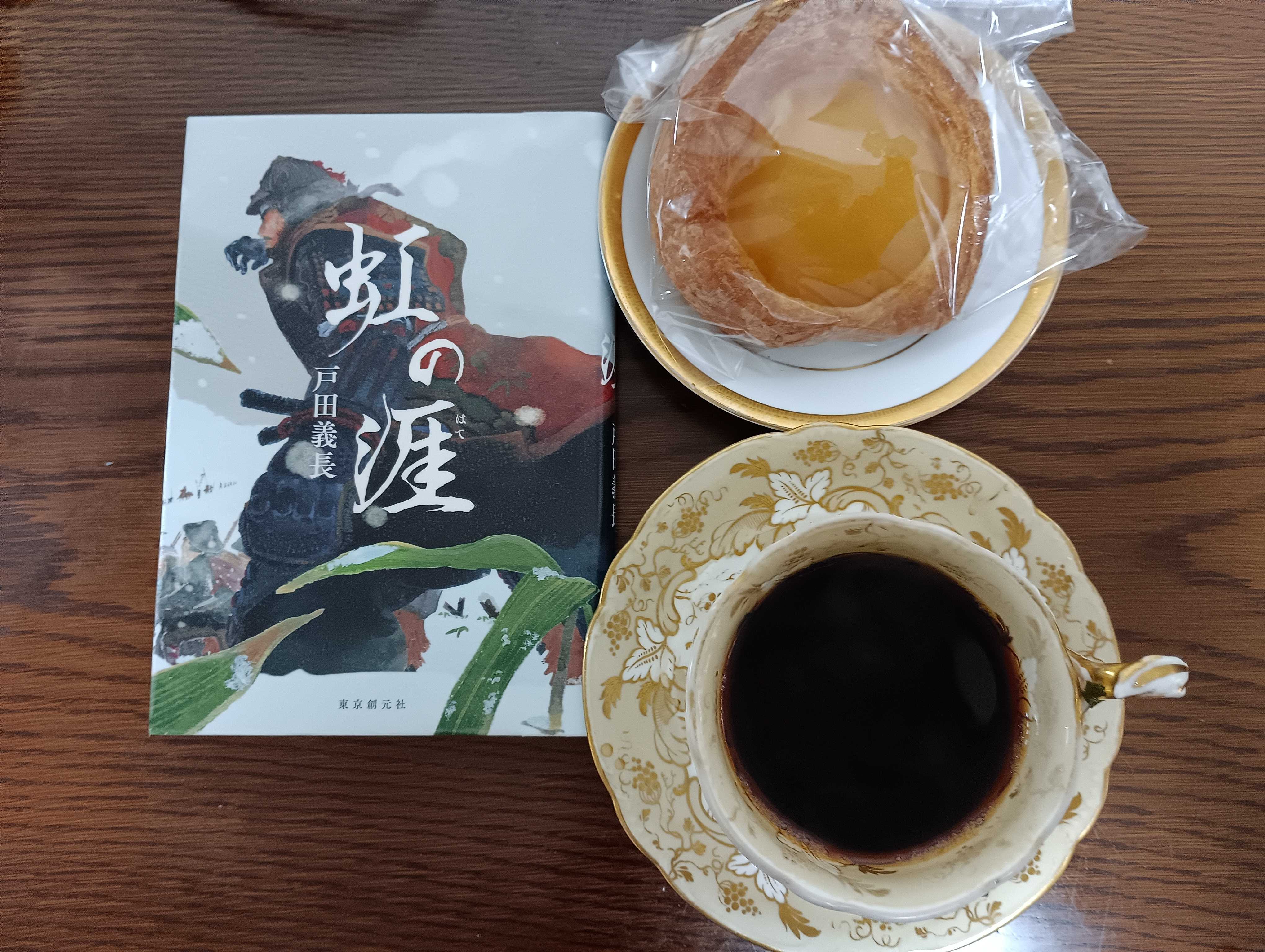月に吠える少年・市民会館大ホール公演
月に吠える少年
よしなれ ゆう (吉馴 悠)
「ベン、ベン、ベン」と三味の音が、雪をがつぽりとかぶった静かな山村に、何処からか響いてきました。村の子供達はその音を聞くと家から飛び出して「ごぜさが来るど」「ごぜさがくるど」と叫びました。子供達は二人、三人と集まり、村のはずれにある丸木橋の方へと走って行きました。橋の上から、村にはいって来る人達が良く見えるのです。丸木橋は雪の中でうっすらと黒く見えました。
「あれ、お地藏さんの前に座りこんだぞ。そして、三味を弾いとるぞ、それも一人で」
と、名主の息子で七歳になる長太が不思議そうにいいました。
「なにをしとるんじやろう」 と、他の子供達がいいました。
「行ってみよう」 と、長太は走りだしました。他の子供達もその後を追いました。
お地藏さんは村に入る手前の道端にありました。その前に年の頃なら二十歳位のごぜがまんじゅう笠を被り、真っ赤な布で頬をかくして、雪の上に座っていました。三味線を右の膝の上に乗せ、胸の前に立てて左手で持ち、刃物のような白い撥を右手に持って、ぽつん、ぽっんと、ゆっくりと弾いていました。
「年の頃なら二歳半、胸に赤い痣のある子がどこにおりましょうか、お教え下さい。その子は私の子の大です。私はごぜのお菊と申します」
と、両眼に涙を一杯に浮かべて語りかけていました。
長太達は、そのお菊より少し離れた後ろでじっとみつめていました。
お菊は三味を弾き終えると、赤い三味袋に納めて立ちあがりました。そして、長太達の気配に気付き振り返りました。「ごぜさ、今日はおら達の村によるんか」
と、長太は問いました。
「いいえ、私は離れごぜですから、、」
と、あ菊は淋みしそうに言いました。そして、
「あなた達は、胸に赤い痣のある子を知りませんか」 と
問いました。
「ううん、知らん」
長太はかぶりをふって言いました。
「そう、まだ三歳になっていない男の子なの」
お菊は、尚も尋ねました。
「それより、村に寄って唄ってくれればええに」
と、長太はお菊の腕を取りました。
「そうよ、うちが手ひいたげる」
「この村には丸木橋があって危ないから」
子供達はそういいながら、お菊の手や肩、背にさばりついて行きました。
お菊は立ち上がって、
「ありがとう。あなた達の名前は、今 なん歳になるの」
と 優しく問いました。
「おら、七歳、長太てんだ」
「私、六歳、お花なの」
「うち、四歳、お雪」
「おら、、」「わしは、、」「うちは、、」
子供達は歳と名前言いました。
「そう、そう」
と、お菊は一人一人の言葉に大きくうなづいて聞いていました。
「村に寄って唄と話を聞かせてくれ」
と、長太はお菊の手を取りひっぱりなから丸木橋を渡って村にはいりました。
「長太ちゃんの手はとても暖かいわ」
村の子供達はお菊をとりかこみました。
子供達はお菊をとり囲み、嬉しそうにはしゃぎまわっていました。
お菊は、農家の前に立ち三味を弾き、
「門付けをさせて貰えないでしょうか」
と、声をかけました。
ごぜとは、三味に合わせて、語り唄う事のうまい、盲目の女旅芸人のこというのです。そして、門付けすると言うことは、三味を弾き、その家の繁栄や健康を願って唄うことで、それによって 、米や、味噌、漬物など貰うことなのでした 。農家の男の人が出てきて、お菊をじろじろと見て、
「あんたは離れごぜか、、。うちは入らん」
と、強い口調で言いました。
離れごぜとは、ごぜの規律を破り、ごぜ屋敷を追われ、一人りで旅をする、盲目の女旅芸人のことです。
「あの、、」
「いらんというとろうが。門付けをしても、おめぇにやる、味噌も米も漬物も金もないわい」
男はお菊の言葉に耳を貸そうせずに言いました。
「すいません。、、少しお尋ねしたいのですが」
「なんじゃ。この村では今までに離れごぜを入れた事がないでな。いっも四人で来るごぜさがもう来る頃でな、、。おめぇもはょう帰るたほうがええぞ」
「はい、そうします。、、年の頃なら二歳半位の男の子で、胸に赤い痣のある子を知りませんか」
お菊は必死の思いで問いました。
「嫌、知らんこの村の者はみんな知らん」
「そうですか。もし、そのような子のことが耳に入りましたら教えてください。その子は私の子の大です。私は離れごぜのお菊ともうします」
お菊は頭を下げてお願いしました。
「うん、聞いたことにしておこうかのう」
「すいません。お願いします。お手間を取らせて申し訳ありませんでした」
お菊は深々と腰を折り、頭を下げて礼を言いました。そして、振り返り帰ろうとしました。
「ごぜさ、帰るんか」
と、お花が声をかけました。
「おらのお父を呼んで来るから、ここで待つててくれ」
長太は大きな声で言いました。
「おぼっちゃま」
男が長太に諫めるような言葉をかけました。
「おらが帰って来るまで、そこにいてくれ、約束じゃ」
そう言い残して長太は走りだしました。その後を、
「長太ちゃん待って」
「長太ちゃん、、」
と、子供達が後を追いました。
「長太ちゃんのお父は、この村の名主で偉い人なの」
「髭を生やして何時も威張ってるけど、本当は優しい人なの」
と、お花とお雪はそう言って長太を追いかけるように走りだしました。
後にはお菊と男が残されました。
「幾らこの村の名主様とは言え村の掟を破る事は出来んのにのう」
男はぽっんと言葉をおとしました。
「私は帰ります」
お菊はそう言って帰りかけました。
「おめえは約束を破るつもりかの。たとえ子供とのものでも約束は破られめえ」
男は静かに言いました。
お菊はその言葉にはっと胸をうたれました。約束は破られない。そう思い、そこに立つて待つことに決めました。
「お菊さんといったな。どこで子供と別れたんじゃ」
男は優しく問いました。
「はい、二年前に吹雪にあい、山の中で、、」
「それじゃ、助かっとらん。諦めることじゃな」
「いいえ、生きております」
お菊は強く言い切りました。お菊は大が死んだとは思いたくなかったのでした。
「そうか、そう思わんではのう」
「はい、そう思ってなくては、私は生きておられません」
お菊の頬に一筋の涙が伝っていました。
「うん、その気持ち、ようにわかる。が、陽のある内に山を降りたほうがええぞ」
男は優しく言いました。
「はい、ですが、私には昼も夜もありません。目が見えないのですから」
「そりゃ、、。そうじゃが、夜の山は何時吹雪に変わるかもしれんからのう」
「はい」
お菊は大きく頷きました。村人の親切がとてもうれしかったのです。村人の言う通り山を降りよう、そうお菊は思いました。
「離れごぜのあんたには、世間の風は冷たかろうが」
「はい、それは。「離れごぜは村にいれない。用はない。と
っとと村から出ていけ。そうでないと川に投げこむぞ 」 と言われた事は二度や三度ではありません。もっと激しく責められたこともたびたびでした。ですが、奥深いごぜの行かないような村では、喜んでくれました」
「なんの楽しみもねぇ山奥では、ごぜさの訪れが何よりの楽しみじゃからな」
「はい」
その時、
「ごぜさ」
と、叫ぶ長太の声がしました。長太は父の名主の手を引っ張っていました。
お菊は声の方え耳を傾けました。雪を踏みしめる小さな足音と、大人の重い足音が近づいていました。
「ああ、これは名主様」
と、村人は頭を下げました。
お菊も、名主の方へ深々とおじきをしました。
「長太、もうよい。そんなに強く引っ張るな」
名主は太い声で言いました。
「お父、どうして、このごぜさを村に入れてはいかんのじゃ」
「それはじゃな、、。それは、、このごぜさは、ごぜの規律破った人じゃからじゃ」
「規律とはなんじゃ」
「規律とは、、」
名主は言いかけて口をつぐんでしまいました。
「長太ちゃん、もういいんですよ。私はこれから次の村まで行きますから」
「次の村迄と言っても二里もある」
と、お花がいいました。
「今からじゃと、夜になってしまう」
と、お雪がいいました。
「次の村も追い帰すかもしれん。お父、このごぜさを一晩泊めてやってくれ」
長太はだだを胡練るよぅに言いました
「それは、出来ん。」
と、名主はきっぱりと言いました。
長太はお菊に近寄り、
「ごぜさ!」
と、泣きそうな声を懸けました。
「いいんですよ。私は慣れていますから」
「裏山には狼もいるし」
「怖くはありませんよ。私にはこの撥がありますから」
その撥はよく切れそうな刃物のように見えました。
「わあ、よう切れそうじゃな」
「私達、目の見えない芸人は、この撥で身を守るように修業しておりますから、大丈夫ですょ。みんなの暖かい心、とも嬉しいわ、有難う」
お菊はそう言って頭をさげ、杖を頼りに丸木橋の方へ歩みかけました。
「ごぜさいくんか、。お父」
長太はお菊と名主を交互に見て言いました。
「私は唄を聞きたい」
「うちはお話を聞きたいわ」
お花とお雪の言葉は、お菊の背にぶつかりました。唄いたい、語りたいとおもっても、村の掟で離れごぜは入れないのですから、二人の声に答えてあげることは出来ませんでした。
「帰るんなら丸木橋を渡してあげよう。この前にきたごぜさが落ちたから」
長太はそう言って、お菊の手とりました。
男は名主に近寄り、
「名主様、あのごぜさは、なんでも、吹雪の中で見失った子供を捜しているそうですがな」
と、囁くように言いました。
「なに、子供をな。それは本当か」
名主はお菊の後ろ姿を見ました。
「年の頃なら二歳半位の男の子で、胸に赤い痣があるそうですが」
「名は何と言った」
「だい、とか」
「そうでなく、ごぜさの名前だ」
「お菊とか、申しておりましたが」
「お菊さん。そうか、お菊さんか」
「なにか、、、」
「いや、、。長太!そのごぜさに少し聞きたい事があるので連れて来なさい」
名主は大きな声を長太に向けてなげました。
「お父!」
長太は嬉しそうにそう答え、お菊の手を引いて連れ戻しました。
「私になにか」
お菊は名主に問いました。
「あんたが離れごぜのお菊さんか」
「はい、私がお菊ですが」
「そうか、あんたがのう、そうでしたか」
「なにか、このごぜさが、、」
と、男が口を挟みました。
「いや、お菊さんのことは私の耳にもはいっている。お菊さんの口説「三椒太夫」 はええ物語じゃとな」
名主は頷きながらいいました。
「いいえ、そんな、めっそうもございません」
「まあ、よかろう。子供達がこれ程慕っているのには、お菊さんになにか暖かい物を感じてのことじゃろうて」
「名主様!」
男が諫めるように言いました。
「お菊さんの三味と唄を聞いてみたいと思うとったところじゃ。今夜は私の家に泊まって、村の者や子供達に聞かせてやって貰えませんかの」
名主は穏やかに言いました。
「名主様、それでは村の掟を破る事になりますがのう」
名主は心配そうな顔を向ける男に、
「かまわん。お菊さんの三味と唄を聞けば村の者も喜んでくれよう。三味も唄も評判での、先日来た薬売りが言うておった。、、村の者がお菊さんの三味と唄を気に入らなんだら、私が村の者にどのようなことでもしょう」
と、名主は、はっきりと言いました。そこまで言われた男は黙りこんでしまいました。
「いや、良いものはいい、悪いものは悪い。真実を知るために掟が邪魔をしていたら、その掟を破り曲げる事も必要なことでな。お菊さんは心配することはない。それより、いい三味と唄を聞かせて下されよ。お願いしましたよ」
「はい、一生懸命に弾き、唄わせて頂きます」
お菊はそう言って、名主の方へ頭を下げました。
「お父!」
三人のやりとりを聞いていた長太が名主に飛び付いていきました。
「名主様、ありがとう」
「なぬしさま」
子供達はそう言って名主をとり囲みますた。名主は笑って、頷きながら、子供達の頭を撫でていました。
「うんうん、今夜はお菊さんに唄と物語を聞かせて貰おうな」
お菊は生まれた時からの盲目ではありませんでした。二歳の時にはしかにかかり、高い熱が続き、お医者に診て貰ったのですが、その時はもう手遅れで盲目になったのでした。山を一つ越した所にある神社が、目の病に良く効くと父が聞いて来まして、お菊は「め」と書いた絵馬を奉納して、毎日毎日父に連れられてお願いに通いましたが、治ずじまいでした。 お菊が生まれた村は山の中で僅かな田と畑しかありませんでしたから、貧しかったのです。だから、どこの家も、長男と長女を産むと、後の子は、産まれてもすぐ首を締めて殺し川に流す風習がありました。それは、村の掟のようになっていました。人間が増えればそれたけ食料が足らなくなり、村全体が滅びてしまうと言うことなのでした。お菊は次女として産まれたのですが、母がどうしても殺すことは出来ないと頑張ってくれて育ったのでした。
産まれてきても殺されて川に流される子の事を日みずっ子と言うのです。
ですから、お菊は村でも隠れるように暮らしていたのですが、病で目が見えなくなり、村の人に知れ、父と母は村八分にされてしまいました。村八分とは、火事があった時、火消しと跡形ずけの手伝いと、死人が出た時、葬式を手伝うと言うもので、後の付き合いは断つと言うものでした。
そんな家でしたが、お菊は父と母、兄と姉に可愛がられて育ちました。
お菊がだんだん大きくなるにつけ、父と母は考えなくてはなりませんでした。おきくをいっまでも家に置いておくこと、お菊の将来に良くないと考えたのでした。
父と母、お菊が座っていました。
「お菊、お前は目が見えんのだから、あんまさんになるか、ごぜさになるか、どっちがええ」
父はお菊に言いました。お菊は何の事かわからずうっむいていました。
「あんた、そう言うても、まだ五歳のお菊にはわからないわな。うちだってどちらがええとも答えられん」
母はそう言ってお菊の顔を見ました。
「習い事は早い方がええと思うて、、」
「まだ幼いんじゃから、家におらせて」
「今度、ごぜさが来たら相談をしてみるか。わしは、お菊がごぜさになってくれたらと思うんじゃが」
「目が見えんよぅになるんじゃったら、育てるんじゃなかった。」
母は目頭を押さえました。
「今更、何を言う」
「せいでも、うちは辛いんじゃ」
「そりゃ、このわしだって。わしらとて何時迄も生きていて、お菊を見守っていてやることは出来ん。だから、お菊が一人で生きて行ける道を捜しだしてやらにゃならん。わしらだけの淋しさだけを考えておったら、それだけ、お菊の生きていく道を邪魔することになるのじゃからな」
「あんた!」
「そうじゃ、思い付いたら早い方がええ。気の変わらん内に、明日にでも、わしはお菊を連れて高田に行って、座元の親方さんに会って頼もうと思う」
「そんなに急に決めんでも」
「いや、早い方がええ。お菊、わしらは、おまえが可愛くねえからごぜさにするんではねえ。目の見えんお菊には一番じゃと思うからじゃ。お菊は唄がうまい、歌を唄ってみんなよろこばせて、、。わしらとて、お菊を手放すのは辛いが、、きっと、後に、わし等の気持ちが分かってくれると思うから」
「うちは行きとうねえ、行きとうねえ」
お菊は母の胸に飛び込んで行きました。
「行かしとうね。行かしとうねえ。けど、けど、、」
母はお菊を抱いて言葉を詰まらせました。
「お菊、わかってくれ。お願いじゃ。わしらも辛いんじゃ、手放しとうはなえ。が一人前のごぜさになって生きてくれ。それしか、お前の生きる道はないんじゃから」
父は優しく言葉を投げかけました。
「うちがごぜさになれば、お父や、お母は嬉しいんか」
お菊は見えない目を父に、母に向けて言いました。
父の頬には幾筋も幾筋も涙が流れていました。
「お菊!」
母はその場に泣き崩れました。
「なら、うちはごぜさになる。お父やお母がそうしたほうがええと云うんなら、うちはごぜさになる」
翌日、お菊は父に手を引かれて家を出ました。小さな風呂敷包みを小さな胸に抱えていました。
「お菊、元気でな」
兄が声をかけました。
「お菊ちゃん、負けたらいかんで」
姉が涙声で言いました。
「お、き、く、」
母は前掛けで涙を拭き拭き叫びました。
お菊はその声に何度も何度も振り替えっては、頷きました。
幼いながらも、自分がごぜになるしかないことを知る、お菊でした。
長い道のりでした。歩いたり、父の背に負ぶさったりしました。お菊は父の背が広く大きいと思いました。時折、その背が小刻みに震えているのが伝わってきました。
高田のごぜ屋敷に入りました。
「お菊と申します。どうかよろしゅうお願いします。よろしゅう頼みます」
父はお菊を紹介し、親方にお願いしました。
「お菊、ここが今日からお前の家じゃからの」
親方は妙に乾いた声で言いました。
「お父、いやじゃ、うちはいやじゃ。お母の所に帰りたい。。お父、お父」
と、お菊は泣きながらさばり付いていきました。
「お菊、わかってくれ、、。親方さんの言われる事をようにきいてな、早ょう立派なごぜさになってくれな。お願いじゃ」
と、父はお菊を抱き締め諭しました。
父は、何度も何度も頭さ下てお菊の事を頼み帰っていきました。
お菊は父の後を追おうとしました。
「泣いて帰ると言うか。これから、どんなに辛うても淋しゆうても泣けんのだから、今日は涙がのうなるまで泣くとええ。が、帰ろうと思うたらいかん。逃げて帰ったら、お前のおととやおかかが困るだけじゃ。一端この屋敷に入った者は、定められた日以外の日に逃げて帰れば、沢山の金をもって、おととが謝りに来んといかん定めがあるでな、、。心配や、迷惑をかけたらいかん。目の見えん者は、誰の力も借りずに生きていくのじゃ。誰も当てにはならし、助けてもくれん。同情や哀れみ受けたらいかん。そのためにも、これから、芸をしっかり身に付けるのじゃ。一人で生きて行ける芸をな」 親方の言葉は、静かな空気の流れる部屋に厳しく響き、お菊の幼い胸にしみ込んでくるものでした。
お菊にとって、ごぜ屋敷の修業は、辛く厳しいものでした。広い部屋の掃除から始まりました。不慣れで、廊下から土間に転げ落ちることなどしばしば、柱に頭をぶつけることも度々でした。目が見えないのですから、普通の人と同じよぅに生活をする為めには、手と足、鼻と耳で目の変わりをして、世の中のことを覚えなくてはなりませんでした。
お菊が三味の練習を許されたのは、一年経ってからでした。それまで、座敷の隅に座り、ごぜの三味や唄、語りをじっと聞く毎日でした。
「やりなおし」
親方は、畳を叩き、最初から弾かせんるのでした。お菊の撥を持つ手が震えました。
「やりなおし。何べん教えれば覚えるんだい。どぢだね、まったく」
親方は音が違うと大きな声で叫びました。お菊はその度に耳をふさぎました。
「耳をふさいではいかん。耳は私等の命ぞ。耳をとうして身体で覚えるのじゃ」
「はい」
「教える方も命がけなら、習う方も命がけでのうては、人より優れた芸人にはなれん。このうちはおまえに命をかけて教えておるのじゃ」
「はい、すいません。うちは一生懸命に頑張りますから教えてください。お願いします」
お菊は、縋るような顔をして言いました。
三味の糸で指先が切れ血が流れでましたが、お菊は痛さをこらえて習いました。
「日本海の荒い波の音に負けたらいかん。波をのりこえて、その向こうまでとどかせるような響きを出せんと、人様に聞いて貰える一人前の芸とは云えん。音にお菊の魂を入れるのじゃ」
親方は物差しで、お菊の肩や手首をびしびしと叩きました。お菊は痛さなど忘れてもう夢中で弾きました。唄の修業も、真冬の日本海に面した岩の上で、冷たい風をまともに受け身を凍らせながら習いました。
「それくらいの声は誰でも出す。声はおなかから出すものじゃ。人より優れたいい喉でのうては芸人とは云えんし、一人では生きられん。岩に砕けるる怒涛を押し返すほどでのうてはいかん」
親方に叱られました。喉から血を吐きました。お菊は泣きながら唄い続けました。顔は波のしぶきに濡れ、刃のようなとがるた冷たい風が、突き差さるように吹き付けていました。お菊は修業の辛さに負けそうになりましたが、早く一人前になって、お父やお母に会うのだと言う気持ちで頑張りました。
「おととやおかかに会いたいじやろう、胸で泣きたいじゃろう。じゃが、会えばよけいに辛くなり、今までの苦労も消えてしまうぞ。あと少しの我慢じゃ。お菊が一日もはょう一人前のごぜになることを願うとんは、うちでもなえ、幼いお菊を手放したおととやおかかじゃからの。早よう一人前になって里に返られるようになることじゃ」
親方の言葉は優しい中にも厳しいものが含まれていました。お菊はこっくりと頷き、一層芸に身を入れました。
お菊の父は時折ごぜや屋敷に来て、玄関戸の隙き間から様子を伺つていました。お菊の事が心配だったのでしょう。ですが、母は、辛い修業の様子を見る事の出来るほど強い人ではありまんでした。家で一日も早く一人前になってくれと祈っていました。
「お菊は三味も唄も上手になるのが早いわの」
「お菊は、色白で、べっびんで大きゆう成ったら男がほっとかんじゃろうて」
「お菊は、明るうて、素直でええ子じゃのう」
と、ごぜの仲間から言われるのでした。
歳月が過ぎました。お菊が初旅にでたのは十一歳の時でした。少し目の見えるごぜを先頭にして、饅頭笠を被り、背荷物を負い、左手に三味抱え、右手を前の人の荷物にかけて、一行四人が連なって旅をするのです。
「ごぜんぼ!ごぜんぼ!」
そう呼ぶ者達はごぜを蔑んだ者達でした。ごぜさと呼ぶ人達は、ごぜを暖かく見守ってくれる人達でした。
ごぜ達一行は、家の前に並んでんで三味を弾き短い歌を唄って、門付けをして回りました。家の人が、お金か、米か、家にある物を、ごぜの首に掛けた袋に志として入れてくれるのでした。そして、次の家へと移って行くのでした。
陽が暮れると、名主とか庄屋の家に泊まりました。そこがごぜ宿となり、村の人達がみんな集まり、楽しい一夜になるのでした。何一つ楽しみのない村の人達は、ごぜの三味と唄、語りを聞きに来るのでした。ごぜ達は三味を弾き、唄い、語り披露するのです。村の人達は三味の音に酔い、唄に笑い、語りに泣きました。そうした旅を続けながら、修業積んでいくのでした。
「ご飯は一杯だけ。おかわりをしてはいかん。魚や汁が付いても決して手をつけては行かん。漬物だけ頂くこと、どんなにすすめられても断るんだよ」
親方にそう言われていました。目が見えないからと言って同情されたり、哀れみをうけてはいけない。ごぜは芸を売って生きるのだと言う規律でした。
「男を好きになったらいかん。愛したら地獄に落ちる。ごぜの規律を破るものは、腕を切り落とし、ごぜ屋敷から追放するからね。離れごぜは地獄への道ぞ」
男を好きになつてはいけないというのも、ごぜの規律でした。親方から男を好きになり、離れごぜになつた人達の悲惨
な運命を聞かされて、お菊は育ちました。
ごぜは旅をしていても、春と夏の祭りと盆と正月にはごぜ屋敷に帰ります。ごぜが親元に帰る事が許されるのは、藪入りと言う日で決まっていました。親元に帰って、旅の疲れ、修業の厳しさを癒すのです。
お菊にとっては初めての里帰りでした。心が浮き立ち、足も軽く里へと向かいました。旅の疲れなどありませんでした。心の中にはお父やお母に、兄ちゃんや、姉ちゃんに会えるという嬉しさで一杯でした。
「辛かったろう。淋しかったろう。うちはお菊のなんの力にもなってやれなんだが、、こんなに立派になって、大きゅうなつて、、、」
母は両手で顔を覆い泣きました。お菊も母の胸に飛び込んで思い切り泣きました。お父やお母に会うたら、あれも言おう、これも言おうと思っていた事が、どこかえ消えてしまい、出るのは涙だけでした。
「お菊、よぅ頑張ってくれた。ほんに大きゅうなつて。親方さんはおまえのこと褒めとったぞ。辛抱強い頭のええ子じゃとな。三味も上手じゃし、唄もうまいと」
父の声は涙に濡れていました。
「お菊、よう頑張ったの」
「お菊ちゃん」
兄も姉も目をうるませていました。
「お父、お母、兄ちゃん、姉ちゃん、うちは定めと諦めとるんよ。その中で力一杯に生きようと、、。この三味も唄も、お父やお母にほんとうは一番に聞かせたかったんよ。そのために一生懸命に習うたんじゃもんね」
お菊はそう言って、三味を出して弾き始めました。お菊の両眼からは新しい涙が溢れ、頬を伝っていました。
名主の家の大部屋には、村人や子供達が沢山に集まっていました。お菊はその前に座って三味を弾き唄っていました。座はしーんと静まりかえり、お菊の弾く三味の音が透きとうるように響き、唄は哀調をかもし出していました。
「おわりに、「三椒太夫」唄いまする」
お菊は三味を弾きながら唄い始めました。
安寿の姫に
都志王丸
船の別れの
哀しさを
あらあら
よみあげ
奉る
たんたんとお菊は物語の筋を追って唄いました。鼻を啜りあげる音。頬をぬぐう人。それぞれの人がそれぞれの思いで聞いていました。時の経つのを忘れて聞いていました。唄も終わりへと近づいていきます。別れた母のもとへ成人した都志王丸が訪れ、再会し京へ、、、。
「お父!」
長太は名主の膝へ泣き崩れました。
「お菊さんの唄には、すぐ目の前で人買いによって母と子が別々の船に乗せられて、別れ別れになる哀しい物語が再現されたように感じられ、心が痛くなるほど締め付けてくるのう」
名主はそう言いました。目は赤く充血をしていました。
「これは、お菊さんの心境かもしれんの」
村の男が言いました。そして、鼻を啜り上げました。
「ごぜさんも、別れた子供と早ょうめぐりあえればええのに」
長太が涙声で言いました。
「早ょう、会えればええのに」
「ほんとじゃ」
「泣けて涙が止まらんわな」
お花とお雪が交互に言いました。
「お菊さんは、夢を心の中に描いて唄ったんじゃないかな」 名主がぽっんと言いました。
「哀しい唄じゃのう。今日はほんにええ三味と唄を聞かせてもろうた。名主さんの言われることは本当じゃった」
「ほんに、ほんに」
「真の芸と言うもの聞かせてもろうたようじゃ」
村人はてんでに、お菊を褒めました。
「いいえ、めっそぅもございません。拙い芸に最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました」
「ごぜさ、ありがとう」
長太がお菊の手を取って言いました。
「ありがとう」
「ありがとう」
子供達はてんでに声をかけました。
「みなさんも、おとなしくよく聞いてくれましたね。有難う」
お菊はそう言って笑顔を向けました。
「お菊さん、どうして、お子さんと別れんさった。良かったら話てみて下さらんか。私等で出来ることなら力になりますから」
名主はお菊に優しく尋ねました。
「そうじゃ、そうじゃ」
村人も名主の言葉に賛成しました。
「はい、有難うございます」
お菊が離れごぜになったのは十八歳の時でした。旅先で村の青年を好きになってしまったのでした。
「男を好きになったら地獄に落ちる。愛したら腕を切り落とし、ごぜ屋敷から追放するからな」
その時、お菊の耳の奥で、親方の言葉が何度も何度も繰り返し鳴っていました。
「お菊!なんしてごぜさの規律を破った。このふしだらな娘、そんな娘にどうしてなった」
父の反省を促す言葉でした。
「お菊、女子の幸せは愛した人と一緒に暮らし、その人の子を産み育てる事じゃが、ごぜになったからには、それは出来ん。考えなおしてくれ」
母の哀願するような言葉でした。
「どうして、どうして、人を愛してはいけないの。私の目が見えないからなの、、。私の心の中に宿った愛は、私の一番大切な宝物なのょ。誰にも邪魔をすることは出来ないし、奪い取り除くことは出来ない筈ょ」
お菊は懸命に心の中にあるものの大切さを訴えました。
「お菊、人を愛すること、信じることはほんに尊いが、ごぜさには規律があってゆるされとらん。考え直してくれ」
父は涙ながらに言いました。
「おきくょ、、」
母はそう叫んで頭を垂れました。
「離れごぜがどんなめにあうか、ように教えたろうが。目が見えん者でも、どんな障害を持った人でも、人を愛することの真実はほんに素晴らしいものじゃ。また、そうでのうてはならん。が、うちらごぜには許されとらん。これは何百年と続いたごぜの掟じゃ。諦めんといかん」
親方は激しく叱りつけるように言いました。
お菊は、父や母 、親方の言葉に迷いました。だけど、考 えに考えた末に、ごぜの規律を破ったのでした。お菊はごぜ屋敷から追放されました。そして、旅芸人をやめ、愛する人と一緒に暮らしました。お菊には、毎日毎日がそれは楽しいものでした。愛する人のただそばにいるだけで、その人のたてる音までがお菊の心を幸福へと導きました。月日が経つのが早い、もっとゆっくりならいいと思ったほどでした。、、ですが、愛する人は雪崩に遭い亡くなりました。
「ごぜの規律を破った罰じゃ」
村人はお菊に冷たく当たり、そう言うのでした。その言葉にお菊は泣きました。見えない目から涙が溢れ止める方法をお菊は知りませんでした。
「この村から出ていけ」
村人の叫びと一緒に小石まで飛んでくるようになりました。そうなると、もう村にいることは出来ません。お菊は村を出ました。そして、元の旅芸人、離れごぜになりました。それしか、お菊は食べていく道を知らなかったのでした。お菊には生まれて数か月の男の子の大がいたのでした。お菊は大を父母に預けようかと考えましたが、親と子が離ればなれに生活する事の淋しさ、辛さを一番良く知っているお菊には、それは出来ませんでした。お菊は三味と大を抱え、ごぜの一行の行かない所へ足を向け、遠く迄旅をしました。
「離れごぜは村に入れることは出来ん」
と、追い返す村もありました。が、お菊は三味も巧く、唄も上手でしたから、山奥の村から村を流して歩くことが出来ました。お菊の三味の音を聞いて、門付けをさせてくれる家もあり、泊めてくれるところもありました。大をそばで遊ばせながら、三味を弾きました。
「お菊、どこを幼い子を抱えてさまょつておる。わし等に気を使わんでもええ、早ょう帰って来い」
「お菊、心配はいらん。どうにかなるから早ょう帰ってこ。みんなで一緒に暮らそうな、そうしてくれ」
風の便りで、父母が心配してそう言ってる事をお菊は聞いて知っていましたが、規律を破った者の罰としてこの苛酷な運命に従うことがお菊の歩む道なのだと思うのでした。
「離れごぜになった者は、ごぜの規律を破った娘ばかりではありませんわの。三味が上手で唄もうまくて人気者になり、村の人達にちやほやされて、有頂天になって、一人で歩いた方がお金が沢山貰えると、欲の皮をつつぱらせて屋敷を出ていった娘もいましたわ。その娘達の行く末は、男に捨てられ、年老いて野たれ死にをすることが多かったわの。欲が絡んでは三味の音も濁るし、声も前に出んわの。また、幾ら教えてもよう覚えん娘もいましたわの。その娘等は、修業の辛さに耐え切れんと辞めて行ったわの。その娘等は温泉宿のあんまさんになることが多かったわの。人間が生きると言うことは、三味が巧いとか、唄が上手とかではねえ。下手でも自分の定められた道を一生懸命にこつこつと足を一歩一歩前に出す事じゃと思うわな。お菊は確かに一歩一歩前に進んどった、、。誰にだって過ちはある。みんなそのすれすれのところで生きているのかも知れん、、。お菊が村の男を好きになってしもうたんも分からんではねえ。誰だって心の中は淋しい。弱い。だから、色々の規律をこしらえて、その規律に縛られとらんと、ついついごぜの道を踏み外すことになる。一人では生きられん。、、男の甘い言葉も欲しい。そして、その言葉に酔いもしたい、。まして、年頃の娘ならなおさらの事じゃ。お菊は三味も唄もうまかったわの。それに、雪の白さに負けん位の色白のべっぴんじゃと村人が騒いどった。それより、なにより、お菊は素直じゃった。明るかった。その素直さと明るさが、男に好かれたのかも知れん。その純粋さが男の甘い言葉をまともに受けとめて、一途に愛へと走っのかも知れん、、。お菊の事は、今でもうちは心配しとる。風の便りで夫[つれあい]を雪崩でのぅしたと聞いた。みどり子を抱えて旅回りをしとると聞いた。、、、お菊には真実の愛を貫いて、本当の幸せになって欲しいと願うとったんじゃがが、、、目が見えん者でも、人並み以上に幸せになれ、生きられると言うことを、お菊を通して知りたかったわの。うちらが出来んかった女としての幸せの道を歩ゆんで欲しかったわの。それなのに、なんして、、。運命は何時の場合でもむごい事をしよる。弱い者を痛めつける。悲しませるわの、、。でも、あのお菊なら、あのお菊なら、きっと立ち直ってくれ、新しい幸せを見付けて生きてくれようと思わんではの、、、。そう思わんでは淋しすぎる、哀しすぎるわの、、。お菊!、お菊!、いっでもごぜ屋敷に帰って来ればええぞ。一からやり直せばええんじゃから、一から、、、、、」
お菊は、そんな親方の心根も知らずに旅を続けていました。
「ごぜさの三味はええし、唄もなんとも言えん悲しみが漂うとってええ。うちに泊まってみんなに聞かせてやって貰えませんかの」
「お菊さんの三味が激しく弾かれる時は、日本海の波が岩にはじける時のように響き、吹雪の悲鳴のように迫ってくるの」
「静かな三味の音は、心の中に染み来んで、胸が締めつけられ、悲しみが沸きたつようじゃ」
どこの村に行っても、村人からそのように言われるよぅになりました。
お菊は、愛した人を失った悲しい心を三味の音に乗せ、唄に込めました。そして、激しく弾く時は、何もかも忘れるために撥をたたきました。大は、三味の音を、子守唄がわりにして寝こむのでした。
「そろそろ、今日あたりから、吹雪になるかも知れん。今夜は泊まっていったほうがええぞ」
と、心配して言ってくれるのを、お菊は、
「はい、有難うございます。ご親切はとてもうれしゅうございますが、甘えてばかりはおられませんし先を急ぐものですから」
と、断ったのでした。
「そうかい、そんなら気を付けてな。危ないと思うたらすぐ引き返すのですぞ。子供さんに万一のことがあったら大変じゃからな」
お菊は礼を言って、村の道を抜け山へと向かいました。杖を頼りに山道を歩きました。山に入って少しして、冷たい風がお菊のそばを通り抜けたかと思うと、すぐ、饅頭笠に粉雪が舞い降りる音が聞こえました。それでも、お菊は山を越えようとしていました。風はだんだんと激しくなり、雪をともなって吹き付けてきました。木立ちが悲鳴を上げ、山が揺れているようで、お菊は歩くことも立つていることも出来なくなりました。吹雪は、お菊と大を包み込みました。お菊は大をしっかりと抱きしめて、岩影に隠れました。
「どうしょう。どうしょう」
お菊はうずくまり叫びました。大は大きな声で泣き始めました。
「よし、よし、かあさんが悪かった。寒かろう、寒かろう。良い子じゃから泣かんでくれ。かあさんが悪かった」
お菊は大をあやしながら声を掛けました。座り込んでおろおろとするばかりでした。が、お菊は何を思ったか岩影の雪をかき穴を掘り始めました。その穴に大を横たえ、背荷物から衣類を出してかけました。引き返して村びとに助けて貰おう。一人ならどうにか山を降りて助けを呼べると、お菊は思ったのでした。
「すぐ返ってくるからな、待ってておくれ」
お菊はそう言って引き返そうとしました。が大の泣き声で何度も何度も振り返りました。
「行かせておくれ、行かせておくれ。そうでないと、ここで二人とも凍え死んでしまうのょ」
お菊は思いを振りはらうょうに懸命に山を降りました。風の音は、大の泣き声のよぅにこだましていました。転んでは起き転んでは起きるお菊は、
「助けて!助けて!、、、、、」
と、泣き叫びながら降りて行きました。
「ごぜさ!ごぜさ!」
「ごぜさ!ごぜさ!」
村人の声が吹雪の音と一緒に聞こえてきました。お菊は一瞬立ち止まりました。そして、転げるように降りながら、
「私はここです」
と、あらんかぎりの声を張り上げて叫びました。
「ごぜさ、無事だったか」
「心配をしたぞ」
「吹雪に巻かれて谷に落ちたかと思うたぞ」
村人達は、お菊の顔を見て安心したのか優しい声をかけました。
お菊を追って村人が助けに山を登ってきてくれたのでした。助かったと、ほっとしたその時、岩影において来た大のことが、お菊の胸の中に広がりました。
「赤ん坊の大を、だいを、、」お菊は山の方を振り返り叫びました。
「赤ん坊がどうしたんじゃ」
「岩影に、雪をどけ、風をさけて、、、、」
お菊は走りだしていました。
「おいてきたんか」
「はい」
「なんということを」
「よっしゃ。わし等は一足さきに行くから」
「そうじゃ」 二人の村人が山へ走りました。
「お菊さん、このわしの手にしっかりと捕まってついてきなせえ」
「はい」
お菊は、村人の手にしっかりと捕まり走りました。雪で足がもつれ幾度も転びそうになりました。
「だい!だい!」
と、叫びながらもう夢中で走りました。
お菊が大を横たえた場所には大はいませんでした。お菊は這い回りながら捜しましたが、大はおらず、かぶせた衣類だけが手に触れました。
「ここに置いた ここで泣いていた」
お菊は両手で雪を掘り始めました。
「おらんぞどこかの誰かが通りすがりに助けてくれたのかも知れんぞ」
「この足あとは、、、」
「狼のものじゃ」
「オオカミ、、。いいえ、そんなことはありません。きっと、そこらにいるはずです。お願いです、捜してください」
お菊は泣きながら叫びました。
村人はそこらじゅう捜して呉ましたが、見つかりませんでした。
お菊は思いました。連れていけば良かった、たとえ二人が死んでも、放すのではなかった。そうすれば、この裂けるよぅな心の痛みもなく、後悔も残らないだろうと。自分が死んでもわが子を助けるのが母の努め。お菊は色々の思いの中でそう思ったのでした。そして、いつまでもいつまでも気が狂わんばかりに雪の中を這い回っていました。
「大!だい!何処え行ってしまったの。何処かの誰かに助けて貰っているの。かあさんは何時までも捜し続けるからね」 お菊にとっては、大が生きていると思わなくては生きておられなかったのでした。
「まだ一歳にもなっておりません。胸に赤い痣のある子に逢うたら教えてください。。その子は私の子の大です。私は門付け唄の前に一言付け加えて旅しました。時が過ぎると苦しみは薄れていきます。悲しみは消えていきますが、子を思う母の心は、時が過ぎることでは忘れられるものではありませんでした。私は、一歳、二歳と、大の成長する姿を思い浮かべながら旅をしました。年の頃なら二歳くらい、、、。私は旅の途中、大を置いた岩影あたりに来ると、三味を弾き、唄いました。
ねんねんしなさい する子がかわい
おきて なく子がつらにくい
ねんねんしなさい まだ夜は夜中
明けりゃ お寺の鐘が鳴る
[高田の子守唄]
大が夜泣きをしたときに聞かせた唄でした。三味の音と、唄を、大が覚えていてくれるのではないかと思って弾きました」
お菊は、名主に語りました。名主は頷いて聞いていましたが、
「そうですか、そのよぅなわけが。私等も力になりましょう。あの峠は、この村の裏山じゃから気をつけておきましょう」
と、言いました。そして、目頭をそっと押さえました。
それから四年の歳月が流れました。
長太の村の秋祭りもすんで、もうすぐ雪の季節になろうとしている夜のことでした。長太は隣村まで用事で出掛け、遅くなり帰りを急いでいました。
その時、遠くで狼達の吠えるのが聞こえてきました。長太は怖くなり足を早めました。西空には二十日月が山山を照らしていました。長太は、狼が岩の上に群れをなして、月に向かって吠えているのを見たのでした。その中に少年がいたのでした。月の光は、はっきりと少年を映しだしていました。 長太は家に帰り父に言いました。
「狼の群れの中に少年がいた」
「そんな馬鹿なことがあるか」
名主は最初は取り合いませんでした。
「あの少年は、ごぜさの子では」
「あの、お菊さんの子だと言うのか」
「そう思うた」
「そう言うこともあるな。よし、無駄でもいい村の者を集めて、その子を助け出そう」
と、名主は言いました。
次の日、使いの者を隣村へと走らせました。どこの村でも、お菊の子供のことは知っていましたから、村から村へと伝わり、どこにお菊がいても耳に届くと名主は考えたのでした。
山は燃えるような紅葉でした。風は山肌を駆け上がり、木立ちを鳴らせていました。紅葉が風に舞って落ちている姿は、まるで赤い雪が降っているようでした。
村人は二人、三人と組になって山に入って捜しましたが、なかなか見付け出すことは出来ませんでした。
「あんたの子供さんらしい少年が、狼の群れ中にいたと、山もんが伝えてきた」
と、お菊が海辺の村に立ち寄った時に聞かされました。お菊は夢ではなかろうかと思いました。
「生きていてくれた、生きて元気に、、、」
お菊は目に涙を一杯に浮かべて、山への道を急ぎました。大の姿が見たい、いや、抱き締めて大きくなった身体を確かめたいと思いました。
その頃、村人は落とし穴を掘り、その上に餌を置いて罠をしかけていました。少年は餌を取ろうとして穴に落ちて捕まりました。
「名主様、納屋に入れて置いて大丈夫で」
「とは言っても頭の髪は肩まで垂れて、身体には毛が一杯におおい、わし等を見る目は鋭く光って、身ぶるいがでるほど怖いぞ」
「でも、あの少年をお菊さんはどうするんじゃろう。六年も、狼の中で生きとったんじゃから、人間じゃと言うても獣と同じじゃ。人間の生活に戻すには、お菊さんの手には負えんのじゃなかろうかのう」
「じょが、母と子じゃ。血がつながっとんじゃからどうにかなるじゃろうわい」
と、名主は言いましたが、その顔は心配そうでした。
少年の入れられている納屋に一匹の狼が近づいていました。少年は縄を歯で咬み切ろうとしていました。その時、少年の耳に三味の音が聞こえてきたのでした。少年は縄を咬み切るのを止めて、耳を傾けました。その音はいっかどこかで聞いたことがあると思ったのでした。その音は、外の狼が戸に身体をぶつける音で聞こえなくなりました。少年は縄を咬み切って戸の外へ出ました。長太も三味の音を聞いて外へ出てきたところでした。少年は山の方へ逃げようとしました。
「逃げたらいかん、逃げるな」
その声に名主も村人とも出てきました。
少年と狼が逃げょうとする前に、お菊が立ちふさがりました。少年はお菊に飛びかかりました。お菊は手に持っていた撥を横に振りました。少年は胸を切られてその場にうずくまりました。
「お菊さん!」
名主は思わず大きな声で叫びました。
お菊には何が起こったか分かりませんでした。見守るために自然に手が動き、何かを切った手ごたえはありました。少し離れたところで、苦しそうなうめき声がきこえて来ました。村人が近寄って来ました。狼は逃げよぅてもせず、少年の胸から流れる血を舐めて止めょうとしていました。名主と長太、村人は狼の姿を呆然と見つめているだけでした。
名主はお菊に何にも言えませんでした。
狼は少年を助けながら、少年も狼の背にもたれかかるようして、山の中へと消えていきました。
「大はどこです。未だ山ですか、助けてくれたのではないのですか」
お菊はうわずった高い声で尋ねました。
名主も長太も答える言葉がありませんでした。お菊はこの場の雰囲気に気づき、
「それでは、今、私にぶっかって来た、、。そうなんですね、大だったんですね。私の子の大であったのですね」
お菊は必死に問いました。
「そうじょゃ、ぶかって行ったんがお菊さんの子じゃ。胸に赤い痣があったからな」
「それではどこえ、今どこえ」
「傷口を狼が舐めて、血を止めて、山に連れて帰った」
「それでは、この私が、私の子を、大をこの撥で傷つけたのですか、この撥で、、、。私はどうすれば、、、、、」
お菊はその場にどっと泣き崩れました。
「お菊さん、子を想う母はの心はようにわかるが、少年の傷口を懸命に舐めとる狼の姿が、私等を無力にしたんじゃ。その姿はまるで親と子のよぅに見えた。愛の姿に見えた」
「それでは、私はどうなるんです。ようやく逢えようところだったのに」
「お菊さん」
名主は小さい言葉を落としますた。
「大!だい!」と、叫びながら走りだしました。
「お菊さん、少年は山での生活の方が幸せじゃ。どこかで生きとる、そう思うて、あんたも強く生きてくれ。もう私等にはなにも出来ん」
名主はお菊の後を追ながら言いました。
お菊は山の中には入り、
「大!だい!、かあさんはこの私よ。狼の中での生活のほうが本当に幸せなの、、」
「お菊さん、あんたの心は痛いほどわかる。子供を抱き締めたい親心もようにわかるが、、。もう後には戻らん。これからは強く生きてくれ」
お菊は、大がいるであろう山の辺りを見えない目できっと見つめ、背筋をしゃんと伸ばして、三味を弾き始めました。両眼から涙がほとばしっていました。
「大ょ幸せになれ。大ょ元気に生きろ。この三味の音が聞こえたら、その音を覚えていたら、どうか答えて」
お菊はあらん限りの力を振り絞り、想いを音に込めて、大に届けと弾きました。
「激しく弾かれる三味の音は、自然が人間に対して挑戦してくる厳しさと、それに耐える心を教えなくてはならん。干き返す波のよぅな音、人間の弱さ、哀しさを感じ取らせなくてはいかん。そして、その音を弾く者は、どんなに辛ろうても哀しゅうても、それを乗り切らんといかん。負けたらいかん」
親方の声が三味の音に重なり、お菊の耳に届きました。
「大ょ、幸せに生きてね。私はどこにいても大のかあさんょ。狼の中の方が幸せならばそれでもいい。どうか、この、私の三味の音に答えて、、、」
青く透きとうるような夜空には月が煌煌と輝き、山に光を降りそそいでいました。
お菊の弾く三味の音が奥深い山の中に吸い込まれていきました。
その時、狼達の遠吠えが三味の音に答えるように、聞こえて来ました。
お菊の耳には「お母さん」と、聞こえていました。
おわり
© Rakuten Group, Inc.