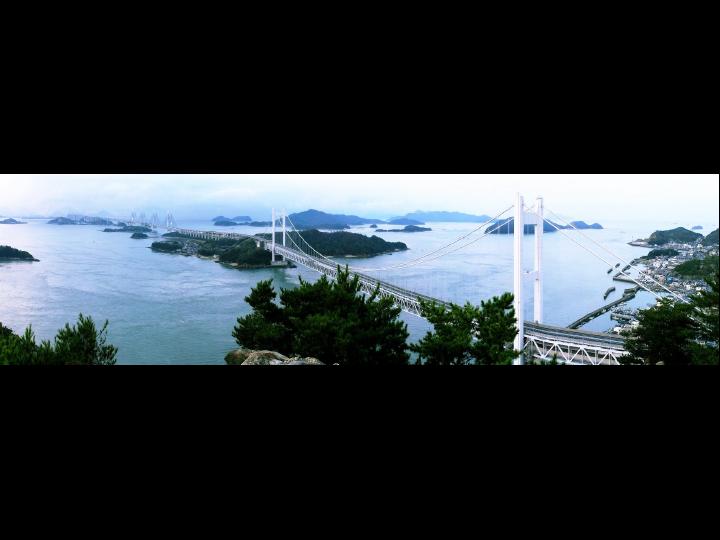時代小説 倉子城物語朗読劇芸文館公演
倉子城物語より


序
「今橋辺りで目と目が合って、中橋渡って二人の仲は、そぞろ歩いて高砂橋へ」
倉敷を流れる倉敷川に架かる三つの石橋を唄った歌である。
今や昔、備中で栄えた倉敷を観光として訪れる人は後を絶たない。
近年、「チボリ公園」の開園でより多くの人が来ている。
様々な人の心に何かを感じてもらっているのだろうか?
ここに記すことは倉子城と言う架空の土地の物語である。
静寂の闇が朝焼けの中に溶け込むと、白い靄のかかった家並みに挟まれた汐入り川が浮かんでくる。常夜灯が小さな灯りを点けている。川面はぼんやりと柳の影を落とし、露の雫がそれを揺らしている。朝露で黒く見える石畳が左右に延びて太鼓橋を繋ぎ、商家の戸口を結んでいる。瓦と瓦とを白い漆喰で貼りつけた滑子壁、江戸職人の精緻な業の格子戸、流れに沿って建てられた蔵屋敷。その下の石垣を洗う波の華。
倉子城の風情はこんな形容で語られる。
この倉子城は江戸になって、幕府直轄備中代官所が置かれた。備中の殆どが、北は伯耆、西は笠岡までが含まれていた。初代代官は小堀遠洲である。遠州については後に触れるが、役職と名を二代目に譲り、その後彼は京に上り、多くの庭園を手懸けた。庭園で有名なのは初代の遠洲である。
時代とともに備中の領内は新見、松山、笠岡となくなって行くのだが、そのぶん倉子城の商家が栄え、松山川の押し流す土砂によって海が中洲になり、干潟になって、そこえ綿を植え年貢税収は変わらなかった。
平安時代は、瀬戸内海に面した小さな漁村であった。「平家物語」の件の「水島合戦」は、藤戸、倉子城、粒江、水島を戦場にしたものである。
その中でも、藤戸の浦人と佐々木盛綱のやり取りは、謡曲の出し物になり「佐々木が憎けりゃ笹まで憎い」と言う老婆の哀しみが綴られたものだ。
松山川が土砂を運んで瀬戸の海に流れこむ、中洲が出来、それが干潟になり、西阿知、中島、四十瀬、笹沖と人が住むようになった。倉子城の海が開墾されてそれらにつながり農地が広がった。
江戸になって、松山川の枝流れは倉子城へ入り、藤戸から児島湾へと注いだが、船の行き来できる川幅はなく、掘って広げながら運河を造り荷出しの海路とした。松山川の流れと、近在の産物が集積されて、京大坂への商人の村になり栄えることになる。
この話の数々は史実には残らなかったが、その村の人達の営みの物語である。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 世界で最もヒトが育つクラブへ「水戸…
- (2025-11-08 08:12:58)
-
-
-

- 読書
- 彬子女王著『飼い犬に腹を噛まれる』…
- (2025-11-14 06:00:05)
-
-
-

- ジャンプの感想
- ジャンプSQ.25年12月号感想♪その3
- (2025-11-14 13:43:41)
-
© Rakuten Group, Inc.