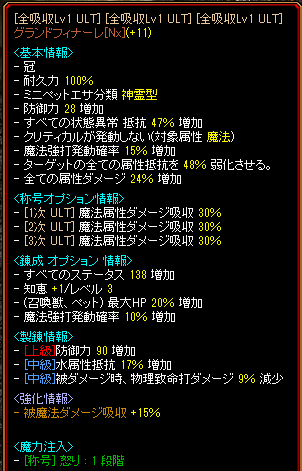♪3
♪ Shall We Dance? ♪
3.
上気した頬を手で押さえなら、ラスティアがティアナの所に戻って来たのはそれから小1時間程経ってからであった。
「お加減はもう宜しいのですか?」
王女の台詞に更に顔を赤らめたラスティアを心配そうな顔で覗き込む。
「ティアナの我侭で、ラスティア様には嫌な思いをさせてしまったのでしょうね。」
「そ、そんな事は無いよ。うん絶対そんな事、無い。」
ラスティアは沈んだ顔の王女に慌てて、明るい顔を作る。
確かに最初は戸惑ってしまったが、始めての体験を楽しんでいた事は事実だから。......あいつが現れたと知るまではの話だが。
ラスティアは気持ちを切り替える為に、大袈裟にごほん、と咳払いをした。
今夜の自分は、王女のパ-トナーとして此処にいるのだ。一緒に踊った時の、彼女の晴れやかで輝くような笑顔を思い出すと、ラスティアの顔も自然にほころぶ。それなのに、ゼネテスの名前を聞いただけで自分は動揺してしまい、王女を独り残して下がってしまった。それを責めもせずラスティアを気づかってくれる王女に、申し訳ない気持ちと共に少し後ろめたさも覚えた。
お詫びの気持ちも込めて、ラスティアは改めてもう一度王女にダンスを申込む。
王女はにっこりと、これ以上は無い程優雅にお辞儀をして、ラスティアの手にその手を重ねた。
それから二人は、周囲の羨望の眼差しの中、お互いに夢のような時間を過ごしたのだった。
***********
ティアナ王女の部屋で着慣れたいつもの服に着替えながら、二人は年頃の少女らしく興奮気味の声で今夜のことを語り合っていた。
ラスティアがパーティーを抜け出していた間、ティアナ王女の方はレムオンと共に過ごしていたのだと言う。
「なんて事は無い世間話や、昔の話ばかりしていたので、レムオン様は退屈為さっておられたかもしれません。社交に疎い私は、華やかな話題は思い付かなくて......。」
そう言いながらも、レムオンはそんな王女にも判る話題を選び、楽し気に相手をして下さったのだ、と付け加えた。頬を赤らめながら話すその様子は、ロストールの王女と言う殻を脱ぎ捨てた何処にでもいる1人の少女の顔だ、とラスティアは思った。
「結局、ゼネテス様は何処にいらっしゃったのでしょうね。ティアナは最後迄お姿を見つけられませんでしたわ。......ラスティア様は?」
「えっ?あ、あたしも......見かけな......かった。」
言い慣れない嘘に顔を赤らめて、とにかく大広間では見かけなかったのだから、あながち嘘だとは言えないだろう、と自分に言い訳をする。
「いつもは社交界を毛嫌いして決しておいでにならないゼネテス様が、どうして今夜に限っていらっしゃる気になられたのでしょう?」
小首をかしげて思案する王女は本当に可愛らしく、ラスティアはゼネテスが目の前の少女では無く何故自分に関心を寄せたのか、改めて不思議に思わずにはいられ無かった。
「お母さまは私とゼネテス様の縁組みを望んでいますけど、私もゼネテス様もこの通り我が道を行く、で、ちっともお母さまの望んだ方向には進みませんでしょう?......お母さまは気を揉んでおられたから、きっと何かきつく仰ったのかも知れませんわね。」
王女はふうッとため息を付くと、諦めたような、もしくは悟ったような微少を浮かべた。だがそれを振払うように小さく首を左右に振って
「人の心は、自由です。どんなに縛ろうとしても、どんなに閉じ込めようとしても、出来る物では無いのです。どんなに押し付けられたとしても、どんなに手が届かなかったとしても、心は止められない。......そうですわよね、ラスティア様。」
ラスティアは、その悲し気な瞳に言葉を見つける事が出来無かった。
彼女の心の奥に秘めた、様々な熱い想いが手に取るように判る気がした。その想いは、ラスティア自身の心の中にも渦巻いている物だったから......。
ーーー ティアナ様......。今夜だけは。今夜だけは、二人で現実を忘れて夢に浸ろう。叶わないかも知れないお互いの夢に、今宵だけは何もかも忘れて、一時の夢に酔おうーーー。
***********
ラスティアが秘密の通路を使って王宮を出たのは、真夜中をとおに過ぎた頃だった。これ以上は無いと言う程丁寧に王女にお礼をいわれ、お陰で本当に久しぶりに心が浮き立つ時を過ごせたと言われた時には、何だか少し申し訳ない気持ちになったりもした。
月光に青白く浮かぶ白い石畳をゆっくりと踏み締めながら、ラスティアは宿に向かって歩く。
歩きながら、いつもの姿からは想像も出来ない、紛れも無い生っ粋の貴族である事を思い知らされた、あの人の姿を思い出す。
初めて会った時から変わらない、いつも飄々としたゼネテスが、今夜は男の人に見えた。
抱きすくめられた時、どうしてもその腕を振りほどけない事に、初めてこの男性を恐い、と思った。
いくら冒険者として名を上げても、幾ら強くなっても、やはりあの人には叶わないのかな。......それとも自分が本心ではそうなる事を望んでいたから、振りほどけなかったのか......。
「俺が今日此処へ来たのは、お前さんを一目見たいと思ったからだ。それが叶えばもうこの服も必要無い。」
あの時。ゼネテスはそう言って笑ってから、その無骨な手で乱れたラスティアの髪を撫で付けた。そうして、ソファの上に放ったままだった上着を取り上げ、ラスティアに手渡した。
「パートナーをあまり独りで放っておく物じゃあない、お相手失格だぜ。」
いつの間にか脱いでいた上着を肩にかけ、胸をはだけ、袖も捲り上げたゼネテスの表情は、既に貴族のそれから、冒険者の顔に戻っているようにラスティアには思えた。
あのあと、ゼネテスが再び広間へ顔を出す事は無かった。
「あの人の事だから、今頃はいつものように酒場で飲んだくれているのかもね。」
そう口に出してから、ラスティアは自分を照らす明るい月明りを見上げた。
貴族の顔をして豪華な衣装に身を包んでいるゼネテスは確かにカッコ良かった。ラスティアがあまり好きでは無い酒の匂いもしなかったし、無精髭も無かった。その洗練された姿に、胸がときめいたのは本当の事。
でも。
いくらその表情は同じでも、いくらその口調は同じでも、ラスティアが好きな彼はいつものむさ苦しい方の彼だ。
そう実感して可笑しくなった。
かっこいい方が嫌だなんて、自分はどうかしてる。王子様より冒険者の方がいいだなんて。
今日ラスティアは知ってしまった。自分のような、平民の冒険者にとっては、一生縁が無いと思っていた世界を。
華やかな世界を生きる美しい女性達。その余りにも自分と懸け離れた世界を、今日自分は知ってしまった。
知ってしまったが故の微かな胸の痛みが無い訳では無い。
だが自分には彼等には無い自由がある。かけがえの無い、自由が。
心は自由だ、とティアナ王女は言った。そういう王女の心は決して自由ではない事も、私は今日、知った。
「......お前さん珍しく酒にでも酔ったのか?さっきから笑ったりしかめっ面したり、見てて飽きないぜ。」
耳に馴染んだ柔らかい声に、ふいにそう声掛けられて、その瞬間に。
じん、と身体が痺れる感覚にくらくらする。
ゆっくりと声の方へ身体を向けると、いつものむさ苦しい格好のゼネテスが、いつにない真面目な表情でその手を自分へと差し出しているのが目にはいった。
「踊ってくれよ。......宮殿で、あの格好のあんたに申込む訳にも行かなくてね。心残りだったんだ。......まあ、あんときゃ踊る余裕なんて無かった、ってのが本当だがな。」
自分と比べて余りにも大きなゼネテスにそっと抱き寄せられる。
耳許をくすぐるゼネテスの息に背中を震わせながら、ラスティアはすっぽりとその腕の中に納まった。
二人は聞こえるはずのない音楽に身を任せ、月明りの中、踊り始める。
「......これでやっと今夜の俺の目的が叶うよ。ダンスの間ぐらいは大人しくしていてくれよ?さっきみたいなのは勘弁な。」
その言葉に思わず顔を上げゼネテスの顔を覗き込めば、少し情けなさそうな目
とぶつかって。
「まだ痛みがひいた訳じゃ無いんだぜ、お嬢さん。」
「だ、だってしょうがないでしょう?あの時は、あんまり吃驚したから......!」
「そうだよな。あんまり吃驚したから思いっきり俺にケリを入れちまったんだよな。」
「......ちがっ、ケリを入れた訳じゃなくて......。」
「俺はもう種無しになっちまったかもな。どうしてくれる?」
「た、種無しって........。あれはゼネさんがいきなり変な所触って来たりするから...。」
「別に変な所じゃ無いだろう?俺は愛しあってる男女なら当然の事をしようとしただけだぜ。」
「変な所だってば!だいたいあんな.......え...?」
ゼネテスの言葉にふいにステップを止めたラスティアの足に躓いて、ゼネテスはがばーっとラスティアに抱き着く形になった。
「い、今、何て言った?」
「ん?変な所じゃ無いぜって。」
「だからァ!そこじゃ無くてその後!」
「当然の事をしようと思ったって。」
「う~!!行き過ぎだって。」
「.....さて、何だったかな。」
とぼけるゼネテスに今度は本気でケリを入れるラスティア。ゼネテスは当然見越してそれをサラッとかわすと。
もう一度ラスティアをリードして踊り始める。
「......今度、そうなった時に、また言ってやるよ。」
「いいよっ。そんな時なんて永遠に来ないんだからっ。」
ラスティアが恥ずかしさに頬を染めて思わずそう言い返すと、耐えかねたように笑出したゼネテスの声が、瞬く間に爆笑に変わる。
「来るさ、そのうちに。賭けても良いぜ。」
「ゼネテス!」
ラスティアを抱く腕が、胸が、笑いで大きく揺れるのを感じながら、月の光だけを浴びて踊り続ける二人。
「叔母貴には悪いが、目論見は見事はずれちまったな。......いや、もしかしたらこうなる事まで計算尽くだったかもな。」
「え?」
「叔母貴は俺の気持ちを知っている。......思い通りにならない腑甲斐無い甥ッ子を笑っているだろうぜ。」
「そ、それって......」
「まあ、今回の事は、叔母貴にとって一番の余興だったんだろうな......。」
にんまりと笑うゼネテスの言葉にぽかんとしたままのラスティア。その表情が何とも可愛らしくて。
「今度はケリは無しだぜ。」
「変な所触ろうとしなければいいのよ。」
「せっかく甘い言葉を囁いてやろうと思ったのによ。」
「結構です......ってさっき言わなかったっけ?」
「......聞こえ無かった。」
二人の唇がそっと触れあう。何度も、啄むように。慈しむように。
Fin
2003.10/27 Up
************************
もう、許して下さい~!!!
どう書いても変だよ、しっくり来ないよ~(涙)
......降参です。
ちなみにこの後二人は
「......へええ。そういう事なの。心配して迎えに来てみれば、なるほどねぇ......。」
と座った目のルルアンタに見つかって、こってり絞られた、とかどうとか......。
ゼネさん、運がありません。戦場で使い尽くしたのかも。
© Rakuten Group, Inc.