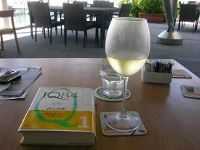PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(7)シンガポールのこと。
(65)星の国ライフ 食とワイン(時々日本のお酒)
(176)シンガポールの美術館・ 博物館・ギャラリー
(24)ドラマ&映画等など。
(125)フランス旅行 ワイン
(11)フランス旅行 美術館 & オペラ座 等など
(30)ロシア旅行 美術館&クラシックバレー 等など
(15)オーストラリア旅行 ワインと動物
(4)アセアン諸国 旅行
(6)日本への帰省
(13)シンガポール 観光スポット
(9)アメリカ旅行 美術館
(4)読書&映画 村上春樹
(25)読書 原田マハ
(30)読書 「古事記・日本書紀」「ギリシャ神話」「昭和史」等々。
(43)読書 「神の雫」&「マリアージュ 最終章 神の雫」
(6)シンガポールから日本のこと。
(102)シンガポールから世界のこと。
(79)本帰国で再発見!
(356)コメント新着
星の国から星の街へ(旧 ヴァン・ノアール)
@ Re[1]:ネゴシアン「Tardieu - Laurent」が造る北ローヌの「HERMITAGE 2004」(10/13)
こちらは朝晩は冬モードの気温になりそう…
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 政治について(21433)
カテゴリ: 本帰国で再発見!

「吉田松陰生誕の地の碑」 門下生 山縣有朋(第3代・9代総理大臣)の名前が刻まれています。
吉田松陰が長州藩の私塾である「松下村塾」で指導した際の「教育方針」の中で①「月謝を取らなかった事(このため身分に関係なく若者が通塾出来た)」②「教科書がなかったため塾生同士の討論を大切にした事」の2点を特に上げていました。
問題は討論の際の相手の呼び方で当時目上の人には「様」、同格かそれより下の場合は「殿」を使っていたため発言者にとって「高杉様か高杉殿か」で討論が途切れたり、農家出身の伊藤博文(後の初代総理大臣)にとって身分が上の人に対する呼び方どころか自分の意見も言えないという状況を打破するため苦肉の策として元々は立場が高い人に対して敬意を込めて使われた「君(きみ→くん)」を使う事にしたそうです。
番組では更に現在も国会で「君」が使われている理由を説明しています。明治23年の「第一回帝国議会」で当時「貴族院(現在の参議院)」の議長を務めたのは吉田松陰の教えを受けた「伊藤博文」で「参議院(貴族院)先例碌」に互いに敬称として「君を用いる事」と規定したそうです。
ところで2015年に萩市を訪れた際、観光ガイドの方から「ここでは絶対に吉田松陰と呼び捨てにせず先生を付ける事が慣習になっている」と聞いて、今更ながらに「吉田松陰先生」の先見の明や指導力には驚かされます。「先生」について検索してみると古代中国から儒教の教えと共に伝わった言葉で「知識や道徳を教える者」という意味です。政治家同士で「先生」と呼び合っているのを未だに耳にし違和感を感じていましたが「君」は理解できても「先生」は全く理解できないというのがよく分かります(道徳を教える者は賄賂を受け取る者とは真逆の位置にあります)

余談ですが、萩市の「円政寺」に奉納された木馬があります。このお寺は高杉晋作や伊藤博文の子供の頃の遊び場で2人はよく馬の鼻をなぜていた事から「神馬」として奉納されたと掲示版に説明があります。これを見た時、子供の頃は武士や農民という身分の差があっても仲良く遊んでいたのかなぁと勝手に想像していましたが松下村塾で伊藤博文が身分の違いを強く意識していたというエピソードに江戸時代の徹底した身分制度を改めて考えさせられました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[本帰国で再発見!] カテゴリの最新記事
-
「バルバレスコ」の生産者「GAJA」が造る… 2025.11.14
-
積雪と紅葉のイルージョンのような景色 @… 2025.11.12
-
ネッピオーロのクローン品種「ランピア」… 2025.11.10
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.