2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年07月の記事
全95件 (95件中 1-50件目)
-

【インターミッション】直方市石炭記念館その3
今日も暑いですね。まだ、気分は黒部に残っているのですが、ブログの確定レポートを進めます。直方市石炭記念館の続きです。今回は屋外展示物をご紹介します。最初は蒸気機関車です。貝島炭鉱で用いられていたものだそうです。ドイツ製のコッペル型蒸気機関車だそうです。クラシックな雰囲気です。このような機関車が昭和30年代後半まで現役で炭鉱で働いていたんですねえ。こんな風な編成展示されておりました。後に繋がっているのは石炭貨車です。後でご紹介するC11機関車の運転台から撮影しました。今度は日本国有鉄道のロコです。C11です。左は移動枠です。筑豊ではあまり使われなかったみたいです。三井三池では盛んに使われたみたいです。こちらも編成展示されています。後に繋げられているのはセム1型石炭貨車です。このC11は密閉運転台を採用しています。割と珍しいかなあ。石炭貨車の前の銅像です。渋い…。展示館から撮り降ろしてみました。石炭貨車の様子が良く分かります。このC11の運転台にも入れていただきました。こういう窓枠は余り見たことがありません。運転台の保存状況はこのようなイメージです。そんなに良くないですね。今まで見た中で、もっとも静態保存で状態が良かったのは人吉市のものでした。これは中の下くらいかなあ。C11の周囲に展示されている採掘設備です。紅いのが移動枠とか自走枠と言われるものです。これが自分で動いて切羽の岩盤を支えます。黄色いのがコールカッターです。石炭層を砕いて行く機械です。このセットで掘り進めるのが今風の炭鉱みたいです。といっても国内にはもう一つしかありませんけど。少し引いて撮影してみました。次は人車です。この人車に鉱員を載せて切羽に運ぶと言うわけです。同じような設備を以前にもご紹介したことがありました。青函トンネルの掘削の展示でもほぼ同じ物が展示されていました。コメントでも頂きましたが、トンネル掘削と石炭採掘には技術的な共通点が多そうです。最後も鉄道関連をご紹介します。鯰田炭鉱の鉱外運搬用に使用された電気機関車です。車体に比べてパンタグラフの大きなこと…。前からみたショットです。痩せていました…。直方市石炭記念館はこのような施設でした。屋外展示品が雨ざらしで錆びが浮き始めているのが気になりました。石炭採掘に関して基本的な理解を得るには大変良い施設です。帰路に乗車した福岡市営地下鉄です。最後の画像は福岡空港のJLラウンジでございます。これで今回のインターミッションを終りにします。このインターミッション自体が次のシリーズの前説になっております。次回のシリーズでは6月の釧路旅行をレポート致します、釧路には日本最後の炭鉱が今日も稼動しております。【本日の成果】朝食(SUICA) 4マイル(JL)ローソン(JCB) 4×1.5倍=6マイル(NH) 良ければ一票お願いします。
2006/07/31
コメント(2)
-

【インターミッション】直方市石炭記念館その2
黒部から帰って参りました。これは凄い。確定レポートを書くのが楽しみです。でも、その前に、インターミッションとして始めた直方市石炭記念館のご紹介を先に進めます。これは切羽のイメージです。囲いのようになっているのが木製の型枠です。これで岩盤を支えるんですね。下の方に見えるのがコールカッターです。この絵柄は後日もう一度引用します。次に釧路のシリーズを流そうと思っています。釧路太平洋炭鉱に比べると、ちょっと古びた方法なのです。筑豊炭田は全国で最初に開発され、高度成長期には枯渇期に入った鉱山も多かったのです。最初に閉山が進んだのも筑豊でした。筑豊には最新の技術が導入されなかったのです。その前に閉山になってしまったのです。この放水機みたいなものも採掘用具なのです。水圧で石炭を掘るという手法も一部の鉱山では採用されていたそうです。この辺は救護隊関係の展示です。前回にもご紹介しましたが、元々、この直方市石炭記念館の建物は、救護隊の訓練所でした。このような気密服と酸素ボンベという装備で救護隊は活躍したそうです。東京消防庁のレスキュー隊員の装備に何となく似ています。各炭鉱の立体模型の数々です。かつて、我が国の産業の支えであった時代の誇りを感じさせる凝った造りの模型が多く、何となくしんみりしてしまいます。筑豊炭田は昭和40年代には殆どの鉱山が閉山となりました。筑豊炭田を知る人もどんどん減っていくことでしょう。寂しいですね。筑豊炭田は少数の家族の私有物でした。この展示は、石炭を支配した筑豊三名家に関する展示です。自民党総裁に立候補した麻生氏も石炭名家のご出身なんですね。石炭化学に関する展示です。現在では「化学工業というと石油化学」というのが常識と化していますが、昔は化学産業と言えば石炭化学でした。筑豊炭田の石炭産出を背景に、九州北部には製鉄業や化学産業が興りました。石炭記念館の建物の裏庭にある訓練施設です。この練習坑道は石炭を掘る訓練を行うためのものではありません。炭鉱事故が発生した際の救護の訓練を行うための施設なのです。練習坑道に掲げられた警告です。「絶対立入禁止」というのが恐ろしげです。実際の訓練の際には、この行動に有毒ガスを注入して、実態に近い坑道救護訓練を行ったのでしょうか。上から見下ろした訓練坑道です。今回はここまでにさせて頂きます。次回は屋外展示物をご紹介いたします。蒸気機関車の時代には、石炭は鉄道の燃料そのものでした。石炭と鉄道は切っても切れない関係にあったのです。そんな訳で次回からちょっと鉄分が入ります。 良ければ一票お願いします。
2006/07/31
コメント(8)
-
【帰投】黒部方面より帰宅
今年の夏の青春18きっぷ第一弾のムーンライト信州+黒部アルペンルート+鉄子駅から帰着しました。とりあえず、感想は「充実してます」です。背景を通常モードの黒に戻しました。【出動】今晩のムーンライト信州で北に向います 【出動】今度こそ出発します。【暫定】ムーンライト信州81号 【暫定】信濃大町駅【暫定】トロリーバス 【暫定】黒部第四ダム 【暫定】アルペンルートの終端 【暫定】北陸本線普通電車 【暫定】快速くびき野1号新潟行【暫定】上越国境 【暫定】上越線湯檜曽駅 【暫定】上越線土合駅 【暫定】外房線長者町駅 【暫定】京葉線普通電車東京行き 【帰投】黒部方面より帰宅
2006/07/31
コメント(2)
-
【暫定】京葉線普通電車東京行き
既に、今回のツアーでやるべきことは概ね終わりました。東京に着くまでやや暇なので、今回の旅行の総括などを…。ムーンライト信州は可も不可もなく、期待通りでした。相変わらずの人気列車でしたけど、客層がながらとは違いました。登山客が多く雰囲気は大分違いました。鉄比率は小さい印象です。信濃大町駅は登山対応に慣れている感じで、売店が朝5時から開いていて好印象でした。朝飯をどうしようか悩んでいたのですが、悩みが一発で解消しました。アルペンルートは凄いです。もう感動でした。観光船ガルベ号が貸切り状態になったのも○でした。天候は本当に心配だったのですが〈直前の天気予報では一時間に50ミリを超える大雨のはずでした〉、黒四では雨が降らなかったし、室堂では晴れ間もありました。こういうところはついていました。もちろん、快晴と言う訳ではなく、室堂到着時は大雨でしたし、美女平も大雨でしたけど、一番重要な場所では何とかなりました。今回の黒部のもう一つの目的であった高山植物の撮影もまあまあ順調でした。この面でも満足感がありました。夜行列車明けのきつさはありましたが…。二日目は「鉄子追体験」でした。上越線の湯檜曽駅と土合駅だけでしたが、これは面白いと感じました。駅そのものだけで面白いというのは珍しいのでした。大抵は車輌と一緒になって、初めて楽しくなるものですが…。湯檜曽の涼しさは特筆ものです。涼しいというより寒いのでした。トンネルの威力ですねえ。土合の階段ではすっかり消耗してしまいました。階段を登るまでは同行者と「高崎駅で信越本線に乗り換えて碓氷峠の遊歩道を歩こうか」などと話していたのですが、階段を登っているうちに「登坂はもうたくさん」と言う雰囲気になりました。二日目の昼ご飯では意外にも苦労しました。水上で駅弁を買えなくて、高崎まで昼飯はお預けになってしまいました。高崎では駅ビルの上層階に「おぎのや」があって「峠の釜飯」を入手可能だったのですが、乗り換え時間が短すぎ、諦めました。結局、D51弁当にしました。高崎から新宿までは、二階建てグリーン車の上階席を確保できました。JR東日本では、土休は快速・普通列車のグリーンが安くなるのでついつい使ってしまいます。どれほど長い行程でも750円です。割安感があります。グリーン車は混雑していました。東日本の営業は今日も快調と言う訳でした。この後に、千葉県内をうろうろして、現在は各駅停車東京行きで西に向かっています。結構消耗していますが、青春18きっぷを十分活用できたので、充実感があります。最後に備忘的にJRの乗車経路を記載して置きます。新宿→信濃大町富山→直江津直江津→長岡→湯檜曽→土合→水上→高崎→新宿→御茶ノ水→錦糸町→千葉→長者町→蘇我→木更津→蘇我→東京何キロくらいになるのでしょうか…。元は取ったと思うのですが。
2006/07/30
コメント(4)
-
【暫定】外房線長者町駅
上越線で鉄子駅〈土合駅と湯檜曽駅〉を訪れた後は、水上駅に南下し、普通電車を乗り継ぎ、高崎まで戻りました。高崎駅で駅弁を買い込み、湘南新宿ラインのグリーン車で新宿まで帰って来て、ここで同行者と別れました。ここからは旅行の性格がガラリと変わります。皆さん、『携帯国盗り物語』というゲームをご存知でしょうか。携帯の位置情報機能を使って、ユーザーが日本の色々な地点〈全部で300ゾーンが設定されています〉をどれだけ多く訪れたかを競うゲームなのですが、今、私はこれにトライしています。青春18きっぷユーザーに向いているゲームなのです。時間が余ったので、新宿からは房総半島方面に向かい、指定エリア〈ゲーム上は「国」と言います〉を可能な限り塗り潰しています。船橋・千葉・茂原・外房を塗り潰したので、ここ長者町でターンし、これから千葉方面へ戻ります。画像は長者町駅の駅舎です。ひなびた雰囲気の可愛い駅舎です。ちなみに有人駅です。
2006/07/30
コメント(0)
-
【暫定】上越線土合駅
鉄子駅その2は上越線土合駅です。上りホームは普通の地上ホームですが、下りホームは地下約70メートルにあるトンネル駅でした。地下ホームから改札までの階段数は484段でございました。はー。画像は土合駅の標札です。「ようこそ日本一のもぐら駅土合へ」と書かれていました。この土合駅の地下ホームは新清水トンネルの中にあります。上越線を複線化する際に運行時間の短縮を図るために、新しいトンネルを深く掘ったところ、このように上下線に70メートル以上の高低差が生じてしまったようです。平面上も上下線がかなり離れていて、下り線から駅本屋に出るには、460段の階段を昇り、長大な跨線橋を渡って行かねばなりません。駅の空間が非常に大きいのでした。なお、改札口には「下りホームまで所要約10分」という旨の警告が表示されておりました。一方の地上ホームは結構な長さで、かつて単線運行していた時代にはここで列車交換を行っていたと言う風情でした。現在は清水トンネル側のホームが切り取られていて、短縮されていました。これ以外は普通の駅でした。駅コンコースの中には、土合駅が関東の駅百選に入った旨の認定証が掲げられておりました。関東なんてレベルではありません。この土合駅のユニークさは少なくとも全国レベルです。アジアレベルかも知れません。凄い駅です、土合駅は。横見さんが絶賛するだけのことはありました。来て良かった。
2006/07/30
コメント(4)
-
【暫定】上越線湯檜曽駅
上越線の鉄子駅を訪れています。湯檜曽駅です。画像は湯檜曽駅の上りホームから宮内方向を見上げたものです。湯檜曽駅には二つのユニークネスがあります。一つはループ駅なんです。画像の右上の方に鉄道の架線が見えますけど、ここを通った列車は山を一周してトンネルを抜けて、湯檜曽駅の地上ホームに入線して来るのです。もう一つの特徴は、上り線は地上駅なのですが、下り線はトンネル駅なのです。トンネル駅自体珍しい存在なのです。暗くて撮影が難しいので、トンネルホームの様子は確定レポートでご紹介致します。トンネル駅だけあって、大変涼しい…。夏向きの駅です。このように湯檜曽駅は大変珍しい特徴のある駅でして、鉄を呼び寄せます。今も鉄っぽい人が2名ほど構内で写真撮影を行っています。湯檜曽駅は楽しい駅でした。
2006/07/30
コメント(2)
-
【暫定】上越国境
今朝は、特急車輌を使う快速くびき野て長岡まで来た後に、上越線の各駅停車で上越国境を目指しております。画像は越後湯沢て発車待ち合わせ中の普通電車です。越後湯沢ではほくほく線との連絡を確保するために少し長めに停車しておりました。上越線の上越国境付近には『鉄子的に面白い駅』がいくつか存在します。昨日は筒石下車を自粛しましたが、今日は下車してみます。maman.mさんに下車駅まで当てられてしまいそうな気がします。
2006/07/30
コメント(0)
-
【暫定】快速くびき野1号新潟行
日記日付は29日ですが、書いているのは30日です。画像は快速『くびき野1号』です。初日は快速『ムーンライト信州81号』の189系で始まりましたが、今日は『くびき野』の485系でスタートです。青春18きっぷは快速にしか乗れません。快速電車は比較的短時間の乗車を想定して製作されるので、長時間乗車すると疲れてしまいます。そこで「特急用の車輌で運行される長時間乗っても快適な快速」をいかに織り交ぜるかが、18きっぷ旅の鍵なのです。このくびき野は、18きっぷユーザーに売ってつけの列車です。今日は、この列車で東に向けて移動中です。車窓の日本海が美しい…。
2006/07/29
コメント(2)
-
【暫定】北陸本線普通電車
皆さん、コメントありがとうございました。今回の旅行も短い日程です。明日には帰宅しますので、帰宅後にお返事させていただきます。さて、黒部アルペンルートを完走後、今度は北陸本線で富山から直江津まで移動し投宿しました。画像は北陸本線の普通電車です。この電車に2時間弱ゆられて移動したのでした。途中、鉄子に登場した筒石駅を通ったのですが、日没後だったので、降車しませんでした。今回の旅は、「夏の18きっぷ」の最初の旅行です。今年は9月まで鉄道旅行は全部18きっぷを使います。当分は特急・急行には乗れません。今日は、立川→信濃大町と富山→直江津を乗ったので、元は取れました。明日は、初期鉄子の追体験を行います。今日の趣向とはがらり変わりますが、楽しみです。同行者も楽しんでくれると良いのですが…。
2006/07/29
コメント(3)
-
【暫定】アルペンルートの終端
アルペンルートを無事に走破しました。画像は、富山地方鉄道の特急『立山』号です。これが黒部アルペンルートの終端になりました。今日は、朝5時に信濃大町駅に着いて以来12時間強で、終点の電鉄富山駅にまで進みました。信濃大町からバス、扇沢でトロリーバスに乗り換え黒四へ進み、地下ケーブルカーとロープウェイとトロリーバスを乗り継いで室堂へ進み、ここで1時間位散策し、バスとケーブルカーと富山地方鉄道を乗り継いで富山までやって来ました。黒部アルペンルート…、大したものでした。天候に余り恵まれなかったのですが、楽しめました。これで全行程快晴だったらどれほどのものか…。もう一つの驚きは、アルペンルートの人気ぶりでした。大手・中小旅行社の団体さんが引っ切りなしに通過して行きました。今回、私達は夜行列車を使って、早朝からアルペンルートに入りましたので、アルペンルート上での宿泊なしで行きましたが、普通に行くと、宿泊なしでは苦しそうです。もし次の機会があったら、富山から入って、室堂で一泊したいです。いやあ、黒部アルペンルートは中々のものでございました。
2006/07/29
コメント(6)
-
【暫定】黒部第四ダム
画像は黒四の放水です。黒部アルペンルートのハイライトでした。同行者からも大変好評でした。付帯施設の整備状況も良好でした。詳しいレポートは後日、確定レポートでご報告致します。
2006/07/29
コメント(6)
-
【暫定】トロリーバス
この画像は今日乗った関電トロリーバスです。黒部アルペンルートには今でもトロリーバスが走っているのです。日本でここだけだそうです。
2006/07/29
コメント(4)
-
【暫定】信濃大町駅
臨時快速『ムーンライト信州81号』は定刻に信濃大町駅に到着しました。これより、黒部アルペンルートへ入ります。眠いので、扇沢までのバスでは寝ます。
2006/07/28
コメント(6)
-
【暫定】ムーンライト信州81号
ムーンライト信州に乗りました。山手線遅延の関係で発車は4分遅れです。ワクワクします。
2006/07/28
コメント(0)
-
【出動】今度こそ出発します。
北陸は大雨の予想です。鬱です。憂鬱です。そろそろ自宅を出発して、ムーンライト信州の始発駅の新宿駅に向います。どうしましょう…。黒部は無理かなあ…。とりあえず、家を出ます。
2006/07/28
コメント(6)
-
【出動】今晩のムーンライト信州で北に向います
夏の青春18キップ第一弾として、今晩のムーンライト信州で北に向います。残念ながら信州北陸の天候は雨の模様ですが…。背景を不在モードに変更いたしました。
2006/07/28
コメント(4)
-

【インターミッション】直方市石炭記念館その1
次のシリーズに行く前にインターミッションを一つ入れます。直方市石炭記念館を訪れた時の様子をレポートします。最初の画像は「白いかもめ」用の885系です。このJR九州の看板特急には乗っておりません。直方に行く電車を待っている時に、向かい側のホームに停まっていたので撮影しただけです。実際に乗ったのはこの817系です。福北ゆたか線という線名が表示されていますが、本名は筑豊本線とか篠栗線なんですけど、こんな愛称が付けられています。今では筑豊本線が電化されていますので、博多へ向う通勤路線になっています。昔は石炭運搬路線でした。車内です。JR九州は各駅停車の車内も何となく贅沢です♪。便所です。非常に広いのでした。運転台から見た直方駅です。今では小さな駅になっておりますが、非常に線数が多いのです。かつては筑豊炭田からの石炭をこの路線で若松港に運び出していました。たくさんの川の支流が本流に合流していくように、筑豊本線には貨物用の支線があったようです。この直方は操車場的に石炭貨物列車の編成を組替え、長大編成にしてさらに北に向わせる駅だったようです。筑豊本線の跨線橋から撮り降ろした直方駅です。40系気動車も見えますね。直方駅から徒歩数分で石炭記念館に付きます。こんな道を通っていくのですこれが本館です。もともとは筑豊石炭鉱業組合だったそうです。その後組合所属の救護隊の練習がここで行われるようになり、九州炭鉱救護隊連盟直方救護練習所として使われたそうです。今では日本国内では炭鉱事故は殆ど起きませんが(炭鉱も釧路の最後の一つを残してなくなってしまいましたので)、その昔はたくさんの事故が起きていたのです。炭鉱事故の時に構内に取り残された鉱夫を救いに行く救護隊の訓練施設であった建物を記念館に再利用しているようです。別アングルです。左側に新館が建設されています。記念館入口の電話番号表示にご注目ください。電話番号133だそうです。昔は炭鉱の景気が良くて、電話が珍しいころから加入していたんでしょうね。こんな看板が出ていました。この後館内に入るのですが、その模様は次回ご紹介します。 良ければ一票お願いします。
2006/07/28
コメント(10)
-

北陸1泊4日(追) リンク付目次
さて、一本シリーズを終えたので、リンク付の目次を作っておきました。長いシリーズにお付き合いいただきありがとうございました。【確定レポート】(1)金沢到着(2)祭の準備(3)茶屋街(4)宇奈月へ(5)渓谷鉄道(6)鐘釣駅へ(7)欅平駅(8)車輌基地(9)工場(10)富山城(11)市役所(12)薪能(13)兼六園(14)徽軫灯籠(15)金沢城(16・終)夜行急行【暫定レポート】【出動】これより家族を連れて北陸方面に出動します。 【暫定】金沢百万石まつり 【暫定】旧富山港線のホーム入口 【暫定】黒部渓谷鉄道 【暫定】宇奈月温泉 【暫定】富山市役所無料展望搭【暫定】金沢城公園百万石薪能【暫定】夜行急行能登上野行き【帰投】北陸より戻りました。 良ければ一票お願いします。
2006/07/27
コメント(2)
-

北陸1泊4日(16・終)夜行急行
ネタ過剰状態(未報告旅行は、ゴールデンウィークの東北縦断、先月の釧路、先々週の三連休パス、先週の沖縄、と三本もあります)で、飛ばしまくった北陸レポートも今回で最終回に致します。最終回は「鉄」です。ここのところの旅行では鉄子というか尊敬する横見先生の影響を強く受けています。今回の旅行では鉄子に登場した夜行急行能登に乗車しました。先ず車号を載せておきます。所属は金サワでした。 クハ489-3 モハ489-2 モハ488-2 モハ489-21 モハ488-206 サロ489-27 モハ489-22 モハ488-207 クハ489-503 堂々の9両編成でした。Tc-4M-T-2M-Tcという編成で、電動車が多いなあ、という編成です。昔はこれで碓氷峠(横川=軽井沢)を越えて、「あさま」とか「はくさん」として運行されていたんでしょうね。 能登の発車アナウンスヘッドマークです。このヘッドマークの形状を見ただけで、鉄の方はピンと来るかも知れませんけど、ボンネットタイプの489系です。方向幕です。急行という文字が眩しい…。手前が急行「能登」、奥が特急「北陸」です。この2列車は全く同じ経路を通って数分違いで上野に向います。正に兄弟列車です。こちらがお尻側です。西側というのかなあ。この2列車は妙な経路を通ります。金沢から北陸本線をひた走り東に向います。直江津から、信越本線に入り途中の長岡まで進みます。ここで方向を転換し(北陸は機関車も付け替えて)上越線に入り、高崎まで進みます。高崎からは高崎線で大宮まで、大宮からは東北本線を走り、終着上野に入ります。つまり、長岡→上野間では、こっちが前になるんですね。兄弟列車の北陸です。実はこの北陸のB個室寝台の寝台指定券を人数分確保していました。しかし、最初から北陸に乗ってはもったいないので、金沢から途中の富山駅まで「急行・能登」に乗って進み、富山から「寝台特急・北陸」に乗り換えることにしたのです。この措置は同行者からは不評でした。北陸に逃げ込むことを防ぐために寝台指定券は私が預かりました(北陸は大半が自由席なので、北陸フリーきっぷだけで乗車できます)。急行能登の側面です。この色も珍しくなってしまいました。銘板は当然のように「日本国有鉄道」でした。保安装置表示です。左側の「S」はATS-B装備車であることを示します。右側の「P」はJR東日本ご自慢のATS-Pも装備していることを表しています。東京の国電区間に乗り入れるので、このような装備になるのでしょう。普通車車内です。少しアコモは改善されていました。トイレです。これは出荷時のままかなあ。一部のトイレは洋式になっていました。肛門疾患を持つ方も安心ですね。洗面台は懐かしい形状をしていました。急行「能登」ならではの装備がこれです。何故かラウンジがついているのです。鉄子でも、ここでおしゃべりしていたみたいですね。私たちもここでお話をしながら富山へ移動したのでした。最後の画像は富山から上野までお世話になったB個室寝台です。 北陸の発車アナウンスとまあ、このようにして北陸を楽しんで参りました。私としては、百万石祭りの情報を掴んでいなかったところは反省していますが、まあまあ、楽しめる旅程に仕上がったのではないかなあ、と思っております。同行者からも概ね好評でした。次回、リンク付見出しを入れて、その後にインターミッションを入れて、釧路レポートを入れたいと思います。この調子だとゴールデンウィークの東北縦断はレポートできないかも知れないですね…。 良ければ一票お願いします。
2006/07/27
コメント(8)
-

北陸1泊4日(15)金沢城
今日は東京の天気は久しぶりにはれました。嬉しい…。週末まで晴れて欲しいです。さて、続きです。北陸の最終局面では夜間シャッターを切りまくりました。前回は兼六園の夜をレポートしました。今回はまだ夜間撮影です。兼六園の夜間撮影で一応の満腹感を得た私は同行者達に合流すべく、再び金沢城公園の薪能会場を目指したのでした。すっかり日が暮れたあとの金沢城五十軒長屋でございます。画面中心部に小さく薪能の舞台が見えると思います。この画像も気に入りました。将来の表紙候補にします。でーん、まだ、薪能をやっていました。終演には間に合いました。画面の真中に薪が見えますよね。思い切り感度を上げています。流石に少しノイズが五月蝿いですね。ここからは公演終了後です。薪です。ホントに燃してました。出し物の終わった舞台は寂しいものです。三度石川門を通って道路に出ます。これで北陸観光を終えました。ここからタクシーでJR金沢駅に向かい、夜行列車に乗りました。次回で最終回にします。最後は金沢から乗車した「急行・能登」をレポートしてお終いに致します。 良ければ一票お願いします。
2006/07/26
コメント(6)
-

北陸1泊4日(14)徽軫灯籠
今日も天気は回復せず…。週末はどうなってしまうのでしょうか…。心配で心配で…。さて、前回の続きです。夜の兼六園の撮影分をご紹介します。日没後の徽軫灯籠でございます。表紙候補です。ふふっ。少し引いてもう一枚撮っておきました。こっちは壁紙候補です。日没後の池です。残念ながら快晴ではなく雲がありました。背景が微妙に光ってしまっています。水面に写る茶屋を狙ってみました。比較的風が弱く、水面にそれなりに写ってくれました。しかし…、スローシャッターでこういう構図は難しいですね。園内の川もこんな感じになります。橋の上から撮ったのですが、通行人が来るとぶれてしまうのです。何回も試さざるを得ませんでした。大体一時間弱、兼六園で粘って撮影を続けました。同行者のうち一名が能に飽きて、私に合流して来ました。こんな感じで兼六園を後にして、同行者に合流すべく、再び金沢上公園に入りました。最後の画像は金沢城の入口の「国宝・石川門」です。今回はここまでにします。次回は日没後の金沢城公園の模様をレポートします。 良ければ一票お願いします。
2006/07/26
コメント(16)
-

北陸1泊4日(13)兼六園
夕闇迫る中、前回ご紹介した金沢城公園の薪能を後にして兼六園に向いました。この時点ではまだ日が暮れきっていません。ライトアップは始まっていますけど、背景がこれでは…。薄暮は野暮だなあ…。でも、日陰はこのとおり、ちょっとそれっぽくなりました。別アングルからです。この日はこの茶屋でハープの演奏が行われていました。池越しにハープを聞くというなかなか乙な演出でした。だんだん日が暮れてきました。良い感じの絵が撮れるようになってまいりました。こんなところで、こんどは日本最古の噴水に行きました。こんな感じです。もう少し夜の兼六園の撮影を続けました。続きは次回にさせていただきます。 良ければ一票お願いします。
2006/07/25
コメント(14)
-

北陸1泊4日(12)薪能
前回は富山市役所をレポートしましたが、あの後は再び北陸本線で金沢に戻りました。金沢百万石祭りのフィナーレを見るためです。金沢市内を走る、循環定期観光バスみたいなものです。その昔は金沢は観光バスで回るものでしたが、今は定期観光バスは流行らないようです。このような循環バスに乗ったり降りたりして自分のペースでこの街を楽しむのが流行のようです。夕暮れの金沢城公園です。百万石祭りのフィナーレの一つとして、この金沢城公園で薪能が開かれておりました。パンフレットです。金沢は能が盛んです。特に宝生流が有力です。加賀前田藩が宝生流を保護し、育成した伝統があるからのようです。金沢駅前の大モニュメントの「もてなしドーム」の木製の柱は鼓門といって、鼓の形状をしています。これも宝生流から採ったらしいです。この日の演目です。最初は子供能から始まります。出し物は土ぐもでした。能をやるこどもがたくさんいるというのも金沢らしいです。郷土芸能はこうして培われるわけですね。沖縄ではサンシンを引ける率が非常に高いのですけど、何となく似ている環境ですね。客席はこんな感じのござ席でした。写真を撮るのにはちょっと辛い環境です。舞台はこんな感じでした。まだ日が暮れていないので、こんな感じです。あとで、真っ暗になるのですが…。いよいよ能が始まりました。同行者はこの能をえらく気に入りまして最後まで見ていたのですが、私は中座しました。夜の金沢の目玉、ライトアップ兼六園を撮りに行くためです。次回はライトアップ兼六園をご紹介します。次回の写真がこの旅行のベストショットです。お楽しみに!。 良ければ一票お願いします。
2006/07/25
コメント(0)
-

北陸1泊4日(11)市役所
「ちょっと脱力写真」の回に差し掛かっています。さくさく、画像だけで流してしまいます。この建物は富山市役所です。左後に妙な塔がありますが、これが展望塔なのです。富山市は素晴らしいことに、この展望塔を無料開放しています。のみならず、日曜日にも開けているのです。これが案内図ですね。早速塔に登りました。以下は展望塔からの眺めです。解説するだけの知識がありません。画像だけお送りします。これは富山城公園ですね。この建物が富山県庁みたいです。眼下の鉄塔のある建物がNHK富山放送局みたいです。ちょっとズームしてます。富山城です。とこんな眺めでした。ただで結構楽しめました。富山市を訪れた時には寄ってみて下さい。 良ければ一票お願いします。
2006/07/25
コメント(4)
-

北陸1泊4日(10)富山城
今度は富山地方鉄道で宇奈月温泉駅から終点の電鉄富山駅まで移動しました。往路と一緒の元京阪電車でした。富山に着くと、金沢に行くまでに少し時間がありました。同行者の意見で富山市内の中心部を歩きました。最初は富山城公園に参りました。堀の掘削工事をやっていました。堀を作っているところを見たのは初めてでした。富山城の天守閣は火災で喪われていたのですが、戦後に再建された居ます。昭和20年代の再建なんで、ちょっと新しすぎる感じがします。この城のような、城じゃないような怪しげな建物は美術館だそうです。こんな歌塚もありました。ちょっと短いのですけど、今回はここまでにします。
2006/07/24
コメント(0)
-

北陸1泊4日(9)工場
この大雨はいつまで続くのでしょうか?。青春18きっぷシーズンが開幕したのに、いつ鉄道が不通になるのか、気が気ではありません。今週末が心配です。さて、続きです。黒部渓谷鉄道の宇奈月車輌基地で撮影を行っていたところまでレポートしました。ここで親切な社員さんが「工場を見ないか」と声を掛けてくれたのでした。なんという幸運!。ここが工場の入口です。前にも書きましたが、黒部渓谷鉄道は通年運行しません。約5ヶ月営業運行が停まります。前後1ヶ月は試運転がありますけど、3ヶ月は完全に停まります。その間従業員は何をしているのか…。勇気を出して聞いて見ました。答えは…。 全車輌を分解整備するなるほど!。これはごもっともな対応です。全従業員が参加して分解整備するので、運転士も車掌も駅員もみんな整備を行う技術があるそうです。なろほどねえ。定期点検(台検)も冬にやってしまうので、夏季営業期間中は工場は閑散としているそうです。これも納得です。工場入口のストックヤードです。車輪車軸のスペアがたくさんありました。暗かったのでストロボも焚かせていただきました♪。整備線ですね。線路の下に人が潜れるように造られています。こうして床下機器の点検や分解作業を行うのですね。もう一つの棟です。4線もあるのに整備中の車輌はありませんでした。工場の片隅で眠るクラシックな機関車です。形状はディーゼル機関車みたいですけど(凸型で)、立派な電気機関車です。ここも工場の中です。架線の位置が低いのでドキドキです。安全祈願の神棚が有るのも工場らしいですね。こんな感じで大満足して、宇奈月を後にして富山に向いました。宇奈月温泉駅の温泉噴水です。富山地方鉄道の駅は宇奈月温泉駅、黒部峡谷鉄道の駅は宇奈月駅でした。ところで、皆さんコメントありがとうございました。ちょっと本文でご紹介したいコメントがいくつかあります。最初は集電装置から。前回の日記で私は説明無しに「トロリーポール」という呼称を用いましたが、これは集電装置の名前です。普通の電車の集電装置はパンタグラフと云いますけど、これ以外に、遅い電車向けに、 ビューゲル(最後の画像) トロリーポール(最後の画像)があります。どんなものかは、各々の日記をご覧下さい。何れにせよ、電車の運転速度が上がると、ビューゲルやトロリーポールでは対応できなくなります。パンタグラフしかだめなんです。それと、もう一つ。今回ご紹介したのは黒部峡谷鉄道です。大変有名且つ楽しめるのですが、これとは別に、更に有名な黒部アルペンルートがあります。もの凄い雪の切り通しの広告写真で有名なところです。日本国内最後のトロリーバス路線のあることろでもあります。この二つは全く別のものです。どっちも素晴らしいデスティネーションです。大技で、黒部峡谷鉄道の終点欅平から十数時間登山をして黒部アルペンルートに出るという手段もありますが、初心者向きではありません。別々に訪れるのが簡単です。 良ければ一票お願いします。
2006/07/24
コメント(2)
-

北陸1泊4日(8)車輌基地
うー、今日も空模様は鉛色ですね。なんだかなあ。さて、前回は黒部峡谷鉄道の欅平駅付近の模様をレポートいたしました。今回は欅平駅から宇奈月駅まで帰ってきた後の模様をご紹介します。この高原のロッジ風の建物は電気館です。宇奈月駅の前にあって入場無料です。ここで黒部川水系の電源開発について知ることが出来ます。これも宇奈月駅前の展示物です。関西電力専用軌道だったころに使われた車輌のようです。集電装置にご注目ください。なんとトロリーポールです。この後に、黒部峡谷鉄道の車輌基地に行きました。適当に撮影しているので整理されていません。昔の客車のようです。形式名がハフです。凄い…。客車なのに客車記号が無いのです。これは極端に軽い客車に適用されるものです。JRでも一形式しかないと聞いたことがあります。無蓋貨車ですね。この二両は現役ではない、保存車輌のようでした。作業車ですね。始発列車の前にこれを走らせて線路状態を確認したりするそうです。主力のEH機関車です。有蓋貨車です。この種別もJRでは殆ど姿を消してしまいました。 良ければ一票お願いします。
2006/07/24
コメント(2)
-

【帰投】那覇より帰宅!
無事に那覇から帰ってきました。あー、面白かったけど、疲れました。背景を普通の黒に戻します。【暫定レポート】【出動】これより沖縄那覇へ向います。 【暫定】首里城公園 【暫定】琉舞と沖縄第32軍司令部壕跡【暫定】那覇市内のホテル 【暫定】ゆいレール【暫定】海軍司令部壕 【暫定】平和祈念公園 【暫定】対馬丸記念館 【暫定】那覇空港で飛行機待ち 良ければ一票お願いします。
2006/07/23
コメント(4)
-
【暫定】那覇空港で飛行機待ち
那覇空港におります。今回も帰路途上が暇なので、旅程総括をしておきます。初日は那覇空港からいきなり首里まで進み、首里城公園へ行きました。首里城正殿に数年ぶりに入りました。とにかく晴れていたのが素晴らしい。無料ガイドツアーに参加し、財団職員のお姉さんに色々教えて貰いながら見て回りました。客は僕一人だけだったので質問し放題でした。これで800円は安いのでした。ついでに無料の琉球舞踊も見せてもらいました。さらに行きたかった第32軍司令部壕〔入口だけですけど〕にも行けました。首里城公園の案内資料には32軍司令部壕は一切表示されていませんでした。案内係のお嬢さんに場所を教えて貰って初めて行けました。非常に満足でした。こんな感じで時間を使っていたら、あっという間に17時になってしまいました。最初は識名園かたまうどんにも行こうと思っていたのですが、どこにも行けませんでした。でも不満なしです。夕刻は、牧志の公設市場と、その奥のディープスポットの農連市場で写真撮影を行いました。写真での写真撮影には気を使うものですが、牧志公設市場は観光化されていて、大体のお店が撮影を快諾してくれました。ありがとう、まちぐわあの皆さん。夕食はラーメン屋にしました。ちむどんどん、という名前の、特濃豚骨スープの店でした。割と臭みのあるスープで〔あれだけ濃いと仕方ないですね〕、客側でスパイスを上手く使わないと楽しめない…。私の場合はしまらっきょうを潰して入れました。大正解でした。臭みは見事に消えて、素晴らしいラーメンになりました。(^ー^)二日目は、豊見城の海軍司令部壕に行って、ひめゆりの塔に行って、平和祈念公園に行きました。前日の32軍司令部壕ですっかり戦跡モードにスイッチしてしまいました。海軍司令部壕は特に変化はなく、こんなものでしょう、という感じでした。しかし、最近は、ソウル郊外の南侵第三トンネルとか、東北の鉱山跡のテーマパークとかに行っているせいか、海軍司令部壕のトンネル断面が大きいと感じてしまいました。ひめゆりでは有名な『新卒の語り部』を見たかったのですが、出勤していませんでした。平和祈念公園では、初めて、85高地に登りました。牛島軍司令官が自決した地点まで進みました。今までは同行者のご意向もあって、資料館とか平和の礎までは行きましたが、自決地点〔黎明の塔〕は初めてでした。結構感動しました。海が大変美しく見える場所でした。あの時期には、海を米艦船が埋め尽くし、猛烈な艦砲射撃を行っていたことでしょう。32軍将兵の御魂に合掌。せっかく南側に来たので、玉泉洞まで足を伸ばしました。ここでスコール状の猛烈な雨に遭遇してしまいました。ぶー。天候に恵まれたのもここまででした。ここから那覇市内に戻り、福州園、波の上神宮、波の上ビーチ、対馬丸記念館と徒歩で回りました。福州園は市内中心部にある割と有名な観光スポットにも関わらず、今回が初めてでした。行って驚いたのですが、実に完成度の高い中国庭園でした。こんな庭園が国内にあったんですねえ。もの凄い勢いでシャッターを切ってしまいました。最後に、知人に頼まれた買物をパレットくもじのリュウボウで済ませました。今回引き受けた注文は、泡盛×2、チンスコウ、ジャガビー〔ジャガリコの親戚みたいなスナック菓子、地域限定販売らしいです〕でした。買いたいものを全部買えました。良かった。ここで揃わないと、重い荷物を背負って小禄で降りなければ行けなくなったのです。おかげで那覇空港に直行できました。今回の沖縄は『初心に帰る』みたいな行程になりました。しかし、充実感も満足感も十分です。総シャッター数は1400回位でした。写真的にも満腹感ありです。天候に恵まれたのが大きかった…。さて、そろそろ搭乗です。後は家に帰るだけです。【備忘記載】Edyが偉く普及していた。ビックリ。搭乗券にキャンペーン印字があった。識別が容易。よい。
2006/07/23
コメント(2)
-
【暫定】対馬丸記念館
jiyma21さんのお勧めで那覇市内波の上の対馬丸記念館に来ています。昭和19年に米海軍の潜水艦に悪石島沖で撃沈された学童疎開船に関連するものを展示している施設です。この対馬丸が沈められたことで沖縄からの疎開は進まず、沖縄戦の被害を大きくしてしまいました。ちなみに、対馬丸を沈めた潜水艦はボーフィン号です。この潜水艦はハワイホノルルで公開されており、私は昨年11月に乗艦しています。対馬丸事件は謎が多く、ゴルゴ13の題材になったこともありました。学童疎開船であることは米軍に伝えられていた、にもかかわらず、攻撃されたそうですね。この記念館での展示は、当時の沖縄の小学校の様子などが中心でした。入場料金は大人一人500円でした。対馬丸の犠牲者に合掌。
2006/07/23
コメント(3)
-
【暫定】平和祈念公園
沖縄第32軍終焉の地です。とにかく、合掌。
2006/07/23
コメント(0)
-
【暫定】海軍司令部壕
昨日の第32軍司令部壕に続いて豊見城市の海軍司令部壕に来ています。沖縄戦の捉らえ方には、本土と沖縄で温度差があります。この地では海軍への評価が極端に高く、陸軍への評価が極端に低いのです。びみょ~な後味でした。
2006/07/23
コメント(0)
-

【暫定】ゆいレール
日記日付は22日ですが、書いているのは23日の早朝です。今は沖縄都市モノレールに乗っています。画像はモノレールの営業車両です。愛称はゆいれーると言います。いまや、那覇にはモノレールが走っているので空港アクセスが随分楽になりました。とにかく時間が読めるのがありがたいのです。横見さんはこのモノレールが開業した時に日帰りで来沖して全駅下車をやったそうですが、この気持ちは分かります。この路線には、日本最南端の駅〔赤嶺駅〕や日本最西端の駅〔那覇空港駅〕などがあるからです。車両的には大したことはありません。開業から日が浅く一形式しかありません。一編成で全てが分かってしまいます。2両編成のかわいいのがシューっと走っています。非常に静かなモノレールです。こう言うところは「流石は日本最新」という感じです。この沖縄都市モノレールの二日乗車券〔千円〕を昨日買いました。この切符で首里まで行ってきた訳ですが、今日は朝から那覇空港駅に来ています。ホテルをチェックアウトしたら直ぐに荷物を空港で預けてしまい、ついでに上級クラスのキャンセル待ちも申し込んでしまいました。こうすると手ぶらで旅行を続けられます。ウンウン。但し、留意事項があります。「当日の空港での前便変更」が不可能になる可能性があります〔時間的な余裕があればOKですけど〕。さて、間もなく県庁前駅です。今日も沖縄本島をさ迷います。【昨日の成果】東京モノレール〔SUICA〕 4マイル〔JL〕飛行機搭乗マイルは判明時に記載。 良ければ一票お願いします。
2006/07/22
コメント(5)
-
【暫定】那覇市内のホテル
最近、楽天さんのブログって少し変ですよね。更新が反映されない問題が一時期は小康状態に入っていたのに、ここ数日は再び悪化しているような気がします。大体ブログを見に行ったときの反応自体がかなり遅くなっているような気がします…。おいおい~、大丈夫ですか?。大規模メンテナンスのアナウンスが流れてますので(あと2時間と少し経つと大規模メンテナンス作業でブログを見られなくなるんですね)、何とかしてくれるのでしょうけど。それと、アクセス記録表示の仕様もいつの間にか変更になっているんですねえ。自分のアクセスが表示されなくなっています。これはいいです。メンテしているときなど、自分のアクセスで、皆さんの記録を流してしまうことも多いので…。今は、那覇市内のホテルで就寝前です。少し疲れているのです。一方同時に悩んでいます。明日どうしよう…。なんとなく戦跡付いてしまったので、南部を目指そうか…、それとも座間味に行こうかなあ…。明日の朝もう一度悩みます。さて、画像は首里城守礼の門です。二千円紙幣の模様にもなっている国民的な観光施設でございます。一説には日本三大見るとがっかりする観光名所にも選ばれているとか…。でもご安心下さい。守礼の門自体は確かに小さくて可愛いですけど、その奥にある首里城正殿は大したもんです。がっかりしませんのでご安心を。日本政府が真剣に作りこんだだけのものではあります。平成4年の再建で、ちょっと古び始めていますけど、あの鮮やかな彩色はがっかりさせません。ただし、晴れていないとダメです。とりとめもないですけど、こんな感じで沖縄初日は終わっていきます。お休みなさいませ。【追伸!】何となく背景(デザインテーマ)を変更してみました。東京に帰ったら、普段の黒に戻してしまいますが。
2006/07/22
コメント(4)
-
【暫定】琉舞と沖縄第32軍司令部壕跡
首里城公園内で琉球伝統舞踊のエギジビジョンをやっていました。宮廷風のゆったりした踊りでございました。じっくり1時間ほど楽しませて頂きました。はい。これを見た後に、同じく首里城公園内にある旧帝国陸軍第32軍司令部壕跡を訪れました。第32軍は陸軍部内では「腰抜け」とか「臆病」とかの悪罵を浴び続けた部隊ですが、米軍側からは最高の評価を受けた部隊でした。高級参謀の八原博通が有能なリアリストで、参謀本部の言うことを聞かずにかってに『戦略持久』という概念を打ち出し、可能な限りの戦力の経済的活用を図り、米軍を苦しめました。大戦後半の帝国陸軍部隊の行動は戦闘というより集団自殺みたいなものが多くなりましたが、沖縄と硫黄島は最期まで戦術原則に忠実でした。沖縄で戦闘指導に当たった八原博通(大佐)も硫黄島で指揮を執った栗林中将も、帝国陸軍では非主流のアメリカ留学組でした。米軍チックなプラグマティックな思考で、島の最終的な防衛を諦め、目的を日本軍兵力の完全な喪失と引き換えに、一人でも多くの米兵の殺害に置きました〔日本軍の思考だとこの辺が限界です。中国やベトナムなら戦傷者や麻薬中毒患者の量産を目指したでしょう〕。この命題を実現するために水際陣地の放棄〔上陸前の艦砲射撃で無力化されるので意味がない〕・飛行場防衛の放棄〔維持したところでもう航空兵力が無い〕・全島防衛の放棄〔防衛拠点を絞った方が自然の要害を防衛に活用しやすい〕などの施策を採りました〔当時の日本軍指揮官でこういう発想の転換を図れる人物は稀有でした〕。このような対応は、帝国陸軍部内では消極的であると批判されました。色々諦めた代わりに、島の要地に濃厚な地下陣地を建設するとともに、大口径砲の統合運用を行い、濃密な火線を形成し、徹底的に抵抗したのでした。米軍は最終的には島を落としますが、物凄い犠牲とタイムスケジュールの遅れを強いられました。沖縄の場合は、嘉手納飛行場を諦め、本部半島以北を諦め、首里前面の重層陣地で抵抗し、米軍に猛烈な出血を強い、敵の本土攻略を遅らせました。素晴らしい戦果を挙げたと言う評価は有り得ます。一方で沖縄第32軍には批判もあります。第一の批判は民間人の被害が余りに大きかったことです。対馬丸事件などの影響で疎開が不十分だったなどの事情はありましたが、私は、膨大な市民の生命が失われた本質的な原因は、首里陣地からの撤退の際の32軍の意思決定にあると思っています。八原博通が、戦後に人に沖縄行きを勧められても「県民に合わす顔が無い」と言って、二度と沖縄の土を踏まなかったそうですが、彼の気持ちはよく解ります。首里前面陣地の維持が絶望となった時に、勇ましい空威張り系のスタッフはバンザイアタック〔自殺攻撃〕に傾きました。八原博通は普段からペシミスティックな思考の戦術家で、事態が深刻化しても、合理的な思考を失わずに「喜屋武半島への後退と戦闘継続」を立案しました。米兵を一人でも多く傷つけ、米軍を一日でも長く沖縄に釘付けにすると言う命題に忠実な策でした。不幸なことに日本軍の後退経路が沖縄県民の避難ルートに重なってしまったのです。合衆国海軍はありったけの砲爆撃を喜屋武半島に叩き付けました。沖縄の非戦闘員の被害の多くは喜屋武半島で生じたのでした。この時の米軍の砲爆撃の凄まじさをして「鉄の暴風」とこの地では呼んでいます。台風の雨粒のように弾が降って来たと言う意味です。筆舌に尽くせぬ被害が発生しました。ひめゆりもこの時に発生しました。西原村の村民は6割が殺害されました。昭和20年4月に沖縄本島に居た人の3~5割が殺害されてしまったのです。非常に評価が難しい。難しすぎる戦いでした。5月中旬まで32軍比較的にクリーンな戦争をしていました。しかし、首里撤退以降はダーティーな戦争になってしまいました。一方で喜屋武半島でも、32軍は、バックナー将軍を戦死させる等の大きな戦果を挙げました。米軍に「日本本土上陸を敢行すれば百万単位の戦死者が出る」と思わせることに成功しています。日本の降伏が、実態的には対米単独降伏であったいことが、戦後の日本の針路を決定付けますが、その大きなファクターに、沖縄と広島と長崎があったと考えています。沖縄や硫黄島の英雄的な抵抗がなければ、日本本土攻略はさらに早まり、米軍は日本本土で地上戦を行った可能性が出てきます。そうすると、物凄い死傷者が出る、とても米国一国で支えきれない、ソビエト連邦を引き込もうという線が出てきてしまいます。沖縄や硫黄島で時間を稼ぎ、広島と長崎で核攻撃を受けて米軍による単独占領で戦後をスタートできたのかも知れません。(核攻撃の成功で、日本政府も降伏やむなしに傾きました。日本政府があの段階で降伏したので米軍の単独占領になりました。もっと頑張れば、やはり赤軍の出番が生じたた可能性が出てきます)現在の日本の繁栄は、沖縄の犠牲者の屍の上にある、と考えることもできます。沖縄が、本土の捨て石となるよう求められ、八原博通が忠実にそれを実現したという見方も出来ると思います。沖縄の地下濠は小禄(現在の行政区分では豊見城市)の海軍司令部壕も有名です。この濠から、かの有名な電文『沖縄県民かく戦えり』が打電された訳です。この中で大田少将は「後世沖縄県民に格別の高配を賜らんことを」と述べますが、実際は高配どころか、戦後も米軍統治下に取り残され、高度成長の恩恵にも預かれず、捨て石であり続けた訳です。現代日本は、沖縄県(と広島市と長崎市)には借りが残っている、ということなんでしょうね。 →著作権も切れているので引用しておきました。首里城公園内の薄暗い第32軍司令部壕の入口に立って、ぼんやりと色々考えてしまいました。この壕で、八原博通は指揮を執っていたのです。沖縄県民にとっては、まだ32軍司令部は戦跡とか史跡になりきって居ないようでした。何の表示もありませんでした。やはり夏になると、戦跡地に来たくなってしまいます。沖縄戦の犠牲者20万余柱に合掌。【追伸】沖縄32軍の司令官は牛島満、参謀長は長勇でした。しかし、作戦を起案したのはほとんど高級参謀の八原博通でした。なお、長勇と八原博通は大変不仲であったと伝えられています。これも八原批判の材料のひとつになっています。【資料】大田電文「沖縄県民かく戦へり」全文沖縄県民の実情に関しては、県知事より報告せらるるべきも、県には既に通信力なく、32軍司令部もまた通信の余力無しと認めらるるにつき、本職県知事の依頼を受けたるにあらざれども、現状を看過するに忍びず、これに代わって緊急ご通知申し上ぐ。沖縄県に敵攻略を開始以来、陸海軍方面とも防衛戦闘に専念し、県民に関しては殆ど省みるに暇無かりき。然れども、本職の知れる範囲においては、県民は青壮年の全部を防衛召集に捧げ、残る老幼婦女子のみが相次ぐ砲爆撃に家屋と財産の全部を焼却せられ、わずかに身をもって、軍の作戦に差し支え無き場所の小防空壕に避難、なお砲爆下をさまよい、風雨にさらされつつ乏しき生活に甘んじありたり。しかも若き婦人は率先軍に身を捧げ、看護婦、炊事婦はもとより、砲弾運び、挺身斬込隊すら申出るものあり。所詮敵来りなば老人子供は殺されるべく、婦女子は後方に運び去られて毒牙に供せらるべしとて親子生き別れ、娘を軍衛門に捨つる親あり。看護婦に至りては、軍移動に際し、衛生兵すでに出発し身より無き重傷者を助けて共にさまよう、真面目にして一時の感情に馳せられたるものとは思われず。さらに軍において作戦の大転換あるや、自給自足夜の中に遥かに遠隔地方の住民地区を指定せられ、輸送力皆無の者、黙々として雨中を移動するあり。これを要するに陸海軍沖縄進駐以来,終始一貫、勤労奉仕、物資節約を強要せられて、ご奉公の一念を胸に抱きつつ遂に・・・・・・(不明)・・・報われることなくして、本戦闘の末期を迎え、実状形容すべくもなし。一木一草焦土と化せん。糧食六月いっぱいを支えるのみなりと謂う。沖縄県民かく戦へり。県民に対し後世特別のご高配を賜らんことを。
2006/07/22
コメント(2)
-
【暫定】首里城公園
沖縄に来ています。今回の前に沖縄に来たのは2月のデジカメのテスト撮影でした。2月以来の沖縄です。前回は、合衆国空軍嘉手納基地とホエールウォッチングと言う組立てでした。今回は伊江島を絡めようと思っていたのですが、泊からの2便がまだ運航していなくて、諦めざるを得ませんでした。〔8月からの運航だそうです。〕こんな事情で定食の首里城に来てみました。首里城は約10年ぶりでしたが、なぜか空いています。今回は無料ガイドツアーに参加してみました。ガイド付きだと理解度が違います。良いものです。見るのも、食べるのも重要ですけど、沖縄にいるときにもっとも大事なのは天気です。現在は快晴です。素晴らしい。非常に快適です。気温は30度で若干の風があります。最高のコンディションです。先週の碓氷峠もその前の釧路も大雨洪水警報でした。たまにはこういう時もないと…。画像は言うまでもなく首里城正殿です。空が青いです。気持ちいい…。
2006/07/22
コメント(2)
-
【出動】これより沖縄那覇へ向います。
今週も週末旅行です。今回の行き先は沖縄那覇です。行き当たりばったりの予定なし旅行です。どうなりますことやら。
2006/07/22
コメント(8)
-

北陸1泊4日(7)欅平駅
明朝より沖縄本島です。なんか嬉しいなあ。今回も動画からスタートします。この黒部峡谷鉄道は今でも関西電力の黒部川水系の発電所群への資材運搬列車が走ります。関西電力専用列車ですね。途中で、一般旅客営業運転をしない「専用列車」とすれ違ったので撮影しておきました。編成の途中に作業車が挟まっているのが分かると思います。さて続きです。前回は鐘釣駅までレポートいたしました。今回は終点の欅平駅からレポートします。欅平駅での機関車の付け替えの風景です。黒部渓谷鉄道の旅客営業運転の終点はこの欅平駅です。ここでターンするので電気機関車の付け替えが必要になります。それにしても…、従業員の方と機関車の大きさを比べてください。非常に小さい車輌であることが分かりますよね。ちなみに営業運転はこの欅平駅で終りですが、関西電力の専用列車用の軌道はこの先も続いているらしいのです。噂では黒部第四ダムまでも行けるそうです。欅平駅の構内に佇む貨車です。この路線は発電所群への資材運搬にも使われています。このような環境ゆえにガンガン貨車が走ります(私鉄で貨物営業が残っているのは珍しいです)。この貨車の積荷はゴミでした。道路アクセスも厳しそうです。ゴミも貨物列車で平地に運ぶのですね。欅平駅もまた発電所駅でした。右側が黒部第三発電所です。その上に欅平駅が見えます。黒部第三発電所の少し上流にある、新黒部第三発電所です。黒部川は水量が多く、水を2系統に分けて発電に使いながら下流に流します。第一の系列が黒部第四→黒部第一に至る系統です。もう一つの系統が新黒部第三→新黒部第一に至るルートだそうです。駅前の表示板です。欅平では川面ギリギリまで下に降りられます。こんな記念撮影スポットが設けられていました。ここまで近づくとはっきり分かるのですが、発電用に水を分離してもなお、凄い水量です。確かにこの川は発電に向いています。川面から奥鐘橋を見上げたところです。この道路も凄いでしょう。この岩の形状が、あたかも獣が人を喰おうとしているところに似ているので「人食い岩」と呼ばれているそうです。こんな感じで、欅平駅を後にして、再び宇奈月を目指しました。帰路の列車には、貨車が連結されていました。客貨混合編成という訳です。非常に珍しい…。同行者が寒そうにしていたので、帰りは露天普通車は止めて、リラックス車というクラスにしました。最後の画像は宇奈月で頂いた昼食です。この飯も、3500円のきっぷに含まれていたのでした。と言うわけで、黒部峡谷鉄道レポートを終りにします。前回黒部に行った時にもう少し詳しい目のレポートを残しておりますので、今回は雑駁な描写にとどめました。もっと黒部を見たいと言う方は下のリンクをご覧下さい。 日帰り黒部峡谷鉄道(2) 始発駅にて 日帰り黒部峡谷鉄道(3) 黒薙へ 日帰り黒部峡谷鉄道(4) 欅平へ 日帰り黒部峡谷鉄道(5/終) 欅平から宇奈月へターン【本日の成果】SUICA(朝食) 4マイル(JL) 良ければ一票お願いします。
2006/07/21
コメント(8)
-

北陸1泊4日(6)鐘釣駅へ
久しぶりに動画です。最近は楽天サーバの調子が悪くて動画がアップできませんでした。この画像は鐘釣駅と欅平駅の間での列車交換です。通常編成の車輌が見られます。話は変わりますが、今週末は沖縄へ出かけます。天候はどうなるのでしょうか。関東地方は雨が続いておりますけど。さて、続きです。今回は、黒部峡谷鉄道での移動などをレポートします。前に(昨年)ご紹介しているところは省きました。宇奈月を出発するといきなり鉄橋です。ダム湖に掛けられた鉄橋を渡って山に入って参ります。柳橋発電所です。凄い外観でした。黒部第二発電所です。表現主義という洋式になるのかなあ、良い建物です。鐘釣駅構内のレールです。長大編成が列車交換を行う関係で、逆走を頻繁に行うので、このようなレールの冷却装置が取り付けられていました。鐘釣駅の線路配置を撮影してみました。非常に複雑な列車交換を行います。先ず手前に向ってくる列車は右側の線路の一番手前まで進みます。この状態で奥に進む列車を通します。その後に手前に進む列車はポイントの向こうまでバック運転し、更に、方向を再度切り替え左側の線路を手前に向って進むのです。鐘釣駅の近くには万年雪があります。標高は大したことはないのですが、風向きとか日差しの関係で、この周辺にはところどころ万年雪があるようです。一応案内図が掲げられておりました。でも見れば分かります。これが辛い…。遊歩道はまだまだ通行禁止なのです。書き忘れていましたが、この黒部渓谷鉄道は冬季は運休します。通年運行しない鉄道なのです。同行者から「鉄道従業員さんは冬は何をしているのか」という質問を受けましたが、答えられませんでした。答えは、帰路の宇奈月駅で得られました。鐘釣駅構内に安置されていたお地蔵さまです…。何人亡くなられたのでしょう…。この週末に青函トンネルに行ってきました。案内人の方が「語弊がありますが、この工事では僅か34人しか死にませんでした」と説明していました。古い時期に難しい工事を行った黒部ではどの位の犠牲者が出たのでしょうか…。合掌。続きは次回にさせていただきます。 良ければ一票お願いします。
2006/07/21
コメント(6)
-

北陸1泊4日(5)渓谷鉄道
楽天さんからメンテナンス作業に伴うサービスの停止がコールされています。詳細は楽天スタッフブログに掲げられていますが、 7/23(日):午前 02:00 - 午前 07:15(予定) 8/06(日):午前 02:00 - 午前 10:45(予定)の各日程で、ブログサービスが停まるようです。この間は日記をみて頂けませんので、お含み置き下さい。はい。北陸の大雨は凄いことになってますね。もうこれ以上犠牲者が出ないと良いんですけど…。私が今ご紹介しているところは大丈夫なのでしょうか。心配になってしまいます。さて続きです。今回は三日目の朝からです。宇奈月温泉の宇奈月ホテルニューオータニをチェックアウトして、黒部渓谷鉄道にトライしました。同行者は皆この鉄道は初めてでした。この切符を使いました。黒部渓谷鉄道全線往復(乗り放題ではありません)できて、途中下車も出来るチケットです。その上、昼食券と温泉入浴券がセットになって3500円です。安い…。但し期間限定発売です。こういう訳なんです。黒部渓谷は山深い「秘境」です。電源開発が行われなければ、このように気楽にアクセスできる場所ではありません。6月中旬でも雪が平気で残っているのです。で、このようにまだ利用できない施設がたくさんあるのです。しかし、全然問題ありません。このような周辺施設もそれなりに楽しいのですけど、黒部渓谷最大の魅力は鉄道そのものにあるのです。またまた見覚えのある列車が…。西武鉄道のレッドアローとして運行されていた「車体」です。今は富山地方鉄道の特急として運行されています。宇奈月温泉駅で撮影しました。宇奈月温泉は今でこそ北陸有数の温泉ですが、もともとは黒部川流域の電源開発の拠点でした。山ちゃん5963さんから「黒四に」というコメントを頂きましたが、黒部渓谷は黒部第一~第四、更には新黒部第一~第三など、多数の水力発電所が建設されています。これらの発電所や水路建設の基地がこの宇奈月であったのです。国家プロジェクト並みの凄まじい土木建築の歴史がここにはあります。黒部の電源開発のストーリーは、有名な映画「黒部の太陽」を始めとして多数の映画や小説がありますが、私のお勧めは吉村昭氏の「高熱隧道」です。一番読み応えがありました。宇奈月の駅名板です。駅はたくさんあるのですが、降りることが出来る駅は僅かです。もともとこの鉄道は鉄道として免許を受けてスタートしたわけではないのです。黒部川流域の発電所建設の資材運搬のために電力会社が(多くの機関は関西電力です。よく知らないのですが、日本発送電も運営していたかも知れません)走らせていたのです。このような訳で、多くの駅は発電所駅で、観光客が降車できないようになっております。ホームの様子です。左側に列車が停車しています。非常に小さなサイズであることが分かりますよね。「軽便鉄道」と言われたサイズだと思います。ナローゲージと言われる狭いレールが使われています。始発列車に乗ったので、まだ基地にたくさんの車輌が寝ていました。一両あたりの長さが短い割にはたくさんの利用客が居るため、長大編成となる路線です。16両編成などという新幹線並みの列車もあるのです。しかも終点までは約60分かかります。このような理由で、この会社の車輌保有数は相当なものなのです。黒部渓谷鉄道の主力機関車です。電力開発のために建設された路線だけあって、全線完全に電化されています。普通の鉄道事業者であれば、電化しないでしょうね。また、信じられないかも知れませんが、この形式はローレル賞を受賞しています。ローレル賞というのは、鉄道友の会が車輌形式に授与する賞で、ブルーリボン賞と共に年に一度選定されます。最近はJR九州とJR西日本が強いですねえ。何故か(当然?)JR東日本はこの賞が苦手です。この黒部渓谷鉄道にはまだ、特筆すべきものがあります。このような軽便鉄道なのに、3クラス制なのです…。天下のJRでも昼行列車は2クラスなのに…。上級クラスだと、このように開閉窓と背もたれ付きの椅子があります。下級クラスは開放式で、背もたれの無い椅子になるのです。機関車の運転台です。運転機器は昭和の電車風に仕上げられています。山岳鉄道の割にはノッチ段数が少なそうな運転台でした。乗車整理券です。黒部渓谷鉄道は全車定員管理を行っているようです。例え、普通車に乗車する場合であっても、このような乗車整理券が必要です。いよいよ出発です。続きは次回にさせていただきます。 良ければ一票お願いします。
2006/07/20
コメント(17)
-

北陸1泊4日(4)宇奈月へ
一昨日まで「鉄」丸出しでしたけど、2回金沢をレポートすると「和」という感じがしてくるので不思議です。さて、続きをご紹介します。ひがし茶屋街を後にして金沢駅に向いました。百万石パレードが出発する直前なんですけど、残念ながら見ている暇はありませんでした。翌日に備え、宇奈月温泉に宿を確保した関係で、金沢を15時過ぎに出発する必要があったのです。金沢駅前で出発を待っている神輿です。午前中に尾山神社で撮影したものが、ここまで移動してきていました。パレード出発直前に敬礼をしている石川県警察本部の皆さんです。こんな準備段階で金沢を後にして宇奈月へ移動いたしました。最初はJRの特急『はくたか』で魚津まで移動し、魚津から富山地方鉄道に乗り換えました。駅名板です。富山地方鉄道の車輌です。どっかで見たことある、と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。この車輌は近畿地方を走る京阪電鉄のお古なのです。往時はテレビカーと呼ばれていました。車内にはこんな操作設備も残されていました。しかし、テレビは撤去されていました。車内の様子です。転換クロスシートのままでした。こちらが富山地鉄の終点の宇奈月温泉駅です。昨年にもブログでご紹介しましたが、駅前の噴水は温泉なんです。触ると火傷をしそうです。宇奈月温泉はここで湧き出している訳ではなく、黒部川上流の黒薙で湧出しています。ダム工事の障害になるくらいの湧出量だったそうで、こんな使われ方もしていました。駅の脇にはこのような黒部峡谷鉄道の車輌基地がありました。こちらが、この旅行でお世話になったホテルです。宇奈月ニューオータニホテルです。このブログを初めて以来、国内でニューオータニに泊まるのは初めてのことでした。夕食は以下のようなものでございました。このようにして、二日目(上野出発日を初日とカウントしています)は終わって参りました。次回は、翌朝の黒部渓谷鉄道をご紹介します。最後に石川県警察本部の方々をもう1ショットご紹介します。 良ければ一票お願いします。
2006/07/19
コメント(15)
-

北陸1泊4日(3)茶屋街
王監督の手術成功のニュースを見ています。先ずは成功して良かったなあ、と思いました。ホークスの選手の皆さんも試合、頑張ってください。旅行から帰ってきて、北陸ツアーの再開です。旅行中はたくさんのコメントをありがとうございました。前回までに近江町市場までご紹介しました。今回はひがし茶屋街をご紹介します。ひがし茶屋街は前回3月に訪れた際に夜景までご紹介してしまっています。外観は見切っているので、今回は内部を探索しました。懐華楼という元のお茶屋さんです。入場料が一人あたり750円もするのですが、入る価値はあったと思っています。この看板は、展示館になった後のもののようです。玄関です。凝った造りと色彩が、当時の御茶屋の文化を偲ばせる、という感じでした。恐らくは江戸時代の建築ですが(ひょっとしたら明治かも知れません)、高い木造建築です。玄関を抜けるとこのような吹き抜けがあり、非常に高い位置に明り取りの窓が設けられていました。こういう建物が残されているのが、金沢らしいです。合衆国陸軍航空隊の第20空軍は300機以上のB29型戦略爆撃機を持て余し、割と小さな街も徹底的に焼き払ったのですが、何故か金沢には手を付けませんでした。京都もですが。おかげでこんな建物が結構な数残っているのです。素晴らしい。玄関直ぐ脇の囲炉裏です。現役の茶屋時代には芸者待機所として使用されたそうです。茶室です。金の畳です。金箔は金沢を代表する伝統工芸ですが、こんなところにも活かされています。近世の金沢は、加賀百万石という大藩の城下町として、あるいは、日本海を行き交う交易都市として、猛烈な富の蓄積が起きました。江戸時代は天下泰平の世の中で、富の使い道は文化しかありません。こうして金沢では茶道とか能などを育む風土が醸成されたようです。二階に上がったところです。この屏風は輪島塗です。恐らく気が遠くなるような制作費がかかっていると思われます。輪島塗なんぞ、いかにも加賀藩が育てそうな工芸ですよね。二階に上がると客室があります。この当時の茶屋ではお客は二階に上げて、一回は従業員の生活スペースに充てていたそうです。女性だけが住み込むことになるので、峻別が必要であったようです。もう一つの客室です。この客室のユーザーは商人だったのですが、造作からは武家文化を感じさせます。中庭です。現役のお茶屋として営業していた時期には何も置いていなかったそうです。こういうところにはこだわらないのですね。大阪とか江戸の商家であれば立派な庭を造りそうですが…。二階の大広間です。入場するとこの広間で説明を15分くらい受けることになります。正面の絵も凄そうだし、友禅も凄く良さそうなんですが、鑑定眼が無いので良く分かりません。もう一箇所友禅が飾ってある部屋がありました。750円の入場料ですが、結構見る価値あるでしょう?。1100円出すとお茶とお菓子も楽しめます。でもでも、一番素晴らしいのは、ストロボ撮影OK、という点です。カメラも喜んでおりました。しかし…、大丈夫かなあ。ストロボを焚くと微妙な色彩の色あせが生じそうで恐いのですけど…。【本日の成果】JR東日本(JCB) 5×1.5倍≒約7マイル(NH) 良ければ一票お願いします。
2006/07/19
コメント(23)
-
【データ】三連休パスの乗車記録
7月の三連休パスの全乗車記録です。全実走行ベースで4108.4キロで終わりました。3日ともに日中観光を入れてしまったので、距離が伸びませんでした…。寝台特急『あけぼの』の遅延が無ければ…、もう数百キロ伸びたのですが…。とりあえず元は取ったようです。205B 新幹線 やまびこ205号 東京07:40 仙台10:04 351.89837 快速 レトロ仙山号 仙台11:15 作並12:01 28.79826M 快速 583系仙山4号 作並15:02 仙台15:44 28.757B 新幹線 やまびこ57号 仙台16:42 盛岡17:53 283.53025M 新幹線 こまち25号 盛岡18:24 秋田19:56 134.92022 寝台特急 あけぼの 秋田21:06 大宮06:31 483.9+61.1+70.4 迂回経路 57分遅延305C 新幹線 とき305号 大宮07:33 高崎08:08 74.7307C 新幹線 Maxとき307号 高崎08:39 越後湯沢09:05 94.21004M 特急 はくたか4号 越後湯沢09:13 直江津10:08 24.73373M 快速 くびき野3号 直江津10:09 長岡11:06 73.0322C 新幹線 Maxとき322号 長岡11:34 高崎12:28 165.6137M 普通 横川行き 高崎13:07 横川13:40 29.7150M 普通 高崎行き 横川15:54 高崎16:26 29.7535E 新幹線 あさま533号 高崎16:33 軽井沢16:50 41.6537E 新幹線 あさま535号 軽井沢17:28 長野18:00 75.8546E 新幹線 あさま546号 長野18:34 上野20:14 218.82021 寝台特急 あけぼの 上野21:45 一ノ関--:-- 迂回 441.5 205分遅延 救済停車3095B 新幹線 はやて95号 一ノ関07:12 八戸08:37 186.84095M 特急 スーパー白鳥95号 八戸08:52 函館12:02 256.49044M 特急 ドラえもん海底列車 函館12:25 吉岡海底13:56 73.5 9045M 特急 ドラえもん海底列車 吉岡海底15:33 木古内15:55 32.34034M 特急 白鳥34号 木古内17:28発 八戸19:49 215.23034B 新幹線 はやて34号 八戸19:58 東京23:08 631.9
2006/07/19
コメント(0)
-
【帰着】青函トンネルから帰ってきました。
盛り沢山の三連休パスツアーを無事に終えて自宅に帰ってきました。今回も題材に恵まれ、トラブルに恵まれ、ネタだらけのツアーでございました。前回の三連休パスの時の「北斗星が強風で駅間長時間停車」も痺れましたけど、今回の「寝台特急あけぼの」大幅遅延にもビビリまくりました。はー。ちなみにあけぼの迂回運転は昨晩で終わりました。今日から運休だそうです。雑感は一つ前の旅程総括に雑感を書きましたので、全体的な印象はそちらの方をご覧下さいませ。今、PCファイルを整理していたのですが、碓氷峠で結構音声を拾っていました。これも確定レポートでご紹介できると思います。また、昨日の朝にスーパー白鳥95号の先頭車両から青函トンネルをいくつか撮影しています。これもブログに載せたいなあ、と思っています。789系は前が見られるのですよ。特急車輌なのに。素晴らしい。画像は三連休パスの最後の状態です。鉄的に使い倒すとこんな券面になってしまいます。判読不能ですね…。暫定レポートへのリンクを載せておきます。ご関心のあるかたはお読みくださいませ。【出動】三連休パスで東北・北海道方面へ出かけます。【暫定】やまびこ205 【暫定】作並温泉 【暫定】快速・583系仙山4号【暫定】上り寝台特急あけぼの 【暫定】はくたか4号 【暫定】再び高崎駅【暫定】碓氷峠鉄道文化むら【暫定】あさま546東京行き【暫定】寝台特急『あけぼの』【暫定】特急スーパー白鳥95号 【暫定】特急ドラえもん海底列車 【暫定】海峡線吉岡海底駅 【暫定】帰路途上での旅程総括【帰着】青函トンネルから帰ってきました。追伸:背景を通常モードに戻しました。
2006/07/18
コメント(7)
-
【暫定】帰路途上での旅程総括
7月三連休パスの全行程を終えて〔というか最終行程として〕東北新幹線『はやて』で東京へ向けて南下中です。今回の三連休パスでは二つの目的を置いていました。一つは「この夏限りの吉岡海底駅へ行くこと」でした。こんなに艱難辛苦の茨の道になるとは予想もしておりませんでしたが、達成出来て非常に満足です。ドラえもん海底列車の悪ノリぶりには笑わせて貰いましたし、海底ワールドのシュール感も素晴らしかった。JR北海道さん、ありがとうございました。流氷ノロッコ・SL冬の湿原・クリスマスイン小樽と北海道の観光列車はとても良い印象です。例外はありますけど。もう一つの目的であった「仙山線交流電化50周年記念の特別列車2本に乗ること」も首尾良く達成できました。うんうん…。レトロ仙山号は文句なしの期待通りの素晴らしい列車でしたし〔非冷房車はちょっと辛かったですけど〕、583系仙山号も往時のはつかりに乗っているみたいでよかった…。贅沢を云えば、寝台車として乗りたかったのですが…〔29日にゴロンとシートで小田原→山形の運行があるのですが、他の用事があるので乗れません〕。事前の期待以上だったのが、出発セレモニーでした。恥ずかしながらテープカット&くす玉は初めてでした。ある種の感動がありました。作並温泉旅館組合の歓迎ぶりにも感動がありました。仙山線交流電化50周年関係だけでも満腹感が生じそうでした。今回、仙山線を選択したのは大正解でした。JR東日本仙台支社さん、ありがとうございました。余った時間で攻略した、ほくほく線や碓氷峠鉄道文化むらや長野新幹線〔というか峠の釜飯〕も大変良かった。碓氷峠鉄道文化むらは雨に降られたので遊歩道〔元信越線上り本線〕に行きませんでした。ここにはもう一度行くことになりそうです。近いので家族を連れて行くのもよさそうです。一方、羽越線土砂崩れによる『あけぼの』のルート変更並びに大幅遅延には徹底的に振り回されましたが、奇跡的にカバー出来ました。車掌さん、指令さん、駅員さんありがとうございました!。横見マジックならぬnotoshunマジックでした。これほど綺麗に行程を修復出来るとは想像もしていませんでした。ちなみに一ノ関で降りる前に、仙台の車掌さんとだべり、色々教えて貰いました。仙台から道案内のために乗り込んで来たそうです。あけぼのは秋田の車掌さんが乗務しているので奥羽線は分かるのですが、東北本線は全然分からないので道案内の車掌を次々に付けているそうです。釜の手配にもご苦労が あるそうで、上野から曳いて来たEF81を仙台で外して、ED75に付け替えて北上まで行くとのことでした。車掌さんの使う略語が面白かったのです。「りくとう」とか「ばんさい」と発音していました。陸羽東線や磐越西線のことでした。また、皆さんの「ご声援コメント」もとても嬉しかったのでした。maman.mさん、こ気味の良いコメントをたくさんありがとうございました。ワブ!さんの温かい励ましコメント、嬉しかったです。元気になりました。修理屋マイスターさん、ソニック猫化計画、笑わせていただきました。iモードだけでブログをこれほどオペレート出来るものなんですね。今回の旅行で一番印象に残っているのは寝台特急『あけぼの』のです。移動で苦労したことはいくらでもありますが、こんなに鮮やかにリカバー出来たのは初めてです。ちょっと自信が付きました。家に着いたらキロ程を計算します。迂回ルートは走行キロ〔東北・北上・奥羽線経由〕を使うか、運賃計算キロ〔上越・信越・羽越・奥羽線経由〕を使うか悩みそうです…。【備忘記載】あけぼのは青森に3時間25分遅れで到着したとの由…。白鳥34号モハ484-3014木古内5分遅れ青森発車1分遅れデッキに立つ乗客多数ドラえもん海底列車は中小国の退避線で折り返しを行うとの由『あけぼの』で一緒になったおじさんによると、大館の比内の親子丼は絶品との由はやて95号には自由席があった。1~5号車が自由席
2006/07/17
コメント(3)
-
【暫定】海峡線吉岡海底駅
吉岡海底海底駅、またの名を「JR北海道ドラえもんイベント・吉岡海底さようなら海底ワールドファイナル・ドラえもん海底ワールド」に行って参りました。近代的な青函トンネルの設備、中でも横取基地は北海道新幹線用の車輛応急補修施設として建設された、青函トンネル付随設備最大の規模を誇ります。この基地がドラえもん海底ワールドとして、実物大のジャイアンの家だの、スネ夫の家の応接間だのの展示場と化していたのです。非常にシュールな…。素晴らしい。素晴らし過ぎました。最高傑作は鉄的な漫画『鉄子の旅』でも紹介されていたジャイ子の部屋でしょう。画像はJR北海道の撒いていたビラです。この企画も北海道新幹線の工事が始まるため、この夏限りだそうです。淋しいですね。最後に見ることが出来て良かったぁ。これで今回の旅行の目的は全て果たしました。後は鉄路でほんの1000キロメートルほど南下し帰宅するばかりです。充実感と満足感…。
2006/07/17
コメント(0)
-
【暫定】特急ドラえもん海底列車
ここに辿り着くまでの幾多の困難を思うと万感の想いです。今、私は、JR北海道の臨時特急『ドラえもん海底列車』に乗っています。当たり前ですが、乗客に占める幼児比率は40パーセントくらいです。恐ろしい喧騒です。走り回る子供に、泣き叫ぶ乳児…。少子高齢化とは無縁の世界がここにあります。車輛も凄いのです。タネ車は781系電車なのですが、車体の至る所にドラえもん、とか、のび太のイラストが描かれています。6両編成のうち4号車は『ドラえもんカー』でした。カーペットカーに遊具を置いてある車輛で、多数の幼児が暴れております。こんな恐ろしい列車です。純真な「鉄」たる私の精神は持つのかなあ…。それにしても…。こんなに苦労しても乗る価値があったのかなあ。【備忘記載】9044M
2006/07/17
コメント(15)
-
【暫定】特急スーパー白鳥95号
寝台特急下り『あけぼの』の2時間を超える遅延をものともせず、第一原案通りの特急『スーパー白鳥95号』に乗って函館駅へ向けて疾走しています。凄いでしょ?。何が起きたかをご報告します。私が上野から乗車した寝台特急『あけぼの』は、仙台を4時52分に発車しました。許せん。岩沼駅と仙台駅に3時間以上も停車していたらしいです。仙台発車時点で遅延幅は2時間を超えておりました。涙。1時間13分以上、『あけぼの』が遅れると、特急『ドラえもん海底列車』に乗り継げなくなってしまいます。ああっ、このままでは吉岡海底駅に行けない。今夏で廃止されてしまうと云うのに…。おのれぇ、謀ったなあ。(x_x;)この遅延を恐れて、高崎駅でJR東日本のテレホンセンターに携帯から自腹で電話をかけて「迂回ダイヤは大丈夫ですか」と照会したのです。オペレーターのお姉さんは「前日の遅れは40分でした。迂回運行初日の慣れない運行でこの程度です。今日は遅れても10分か15分程度だと思います。」と回答しました。それなのにぃ…、許せん。ヽ(*`Д´)ノ早速、車掌さんを探しましたが、見つかりません。2号車から8号車まで探しましたが、いませんでした。残るは『男子禁制』の「ゴロンとシート・レディース」の1号車だけでした。痴漢と誤認されて騒ぎになったらどうしよう…と、ドキドキしながら1号車の最後尾に位置する車掌室に行くと、いました。3人も。もー、車掌さんってば…、女性専用車輛なんかに篭らないで下さいよ~。ちなみに『あけぼの』の女性専用車輛に足を踏み入れたのは初めての経験でした。構造は普通の24系でしたが、化粧の臭いが充満してました。早速、車掌さんに訳を話して、「新幹線に乗り換えるので、ダイヤ上は客扱いしないことになっているのは知ってますけど、一ノ関で下車させて下さい」と申し出ました。車輛さんは直ぐに仙台旅客指令さんと無線連絡を取り、一ノ関駅に列車を停めて私を降ろす算段を付けてくれました。車掌さん、偉いっ。車掌さん、ありがとうございましたっ!。このようにして、寝台特急『あけぼの』から一ノ関駅で降車し、新幹線『はやて95号』に乗り継ぎ、予定の特急『スーパー白鳥95号』に乗れたのです。『あけぼの』が上越線経由になって以降で、『あけぼの』号で一ノ関駅まで移動した経験のある方は少ないことでしょう。画像は一ノ関駅前の撮影です(東北は火祭のシーズンですねえ)。5月にこの街で一泊したことがありました。あの時は宿が見つからなくてドキドキしましたけど、今回の方が痺れました。今回も良い経験を積ませて頂きました。それにしても、三連休パスでは毎回スリリングなことが起きます。ふー。最後に、繰り返しになりますが…、 あけぼのの車掌さん 仙台旅客指令さん 一ノ関の駅員さんありがとうございました!!。m(__)m【備忘記載】クロハ789ー104
2006/07/17
コメント(5)
-
【暫定】寝台特急『あけぼの』迂回運転中
いきなり、表題と関係ない画像ですみません。この画像は、碓氷峠鉄道文化むらで撮影した展示車輛です。EF58とEF30です。現在は、下りの寝台特急『あけぼの』で東北本線を北上しています。羽越本線の崖崩れは当然復旧していませんので、迂回ルートです。東北本線を北上まで進み、北上駅で機関車を交換し、北上線に入り、横手で奥羽本線に入り、秋田へ抜けるルートを辿るとアナウンスされています。途中停車駅は、大宮・横手・大曲・秋田、秋田から先は平常ダイヤ通りとのことです。昨晩の上り『あけぼの』の時は長時間停車の連発でしたが、今晩は今のところ全く停止も徐行もありません。順調です。この列車が大幅に遅れると、吉岡海底に行けなくなってしまいます。どうか遅れ幅が小幅で済みますように…。それではお休みなさいませ。【備忘記載】東京→仙台〈東北新幹線〉自由席仙台→作並〈仙山線イベント列車〉指定席作並→仙台〈仙山線イベント列車〉指定席仙台→盛岡〈東北新幹線〉自由席盛岡→秋田〈秋田新幹線〉立席秋田→大宮〈迂回ルート寝台特急〉指定席大宮→高崎〈上越新幹線〉自由席高崎→越後湯沢〈上越新幹線〉自由席越後湯沢→直江津〈ほくほく線定期在来特急〉自由席直江津→長岡〈信越本線定期快速〉自由席長岡→高崎〈上越新幹線〉自由席高崎→横川〈信越本線普通電車〉自由席横川→高崎〈信越本線普通電車〉自由席高崎→軽井沢〈長野新幹線〉自由席軽井沢→長野〈長野新幹線〉自由席長野→上野〈長野新幹線〉自由席上野→青森〈迂回ルート寝台特急〉指定席
2006/07/16
コメント(6)
全95件 (95件中 1-50件目)
-
-

- 海外旅行
- 【イタリア】ヴァチカン市国サン・ピ…
- (2025-11-14 15:00:07)
-
-
-

- 中国&台湾
- 亡父の故郷•長春に行ってまいりまし…
- (2025-09-19 17:17:04)
-
-
-
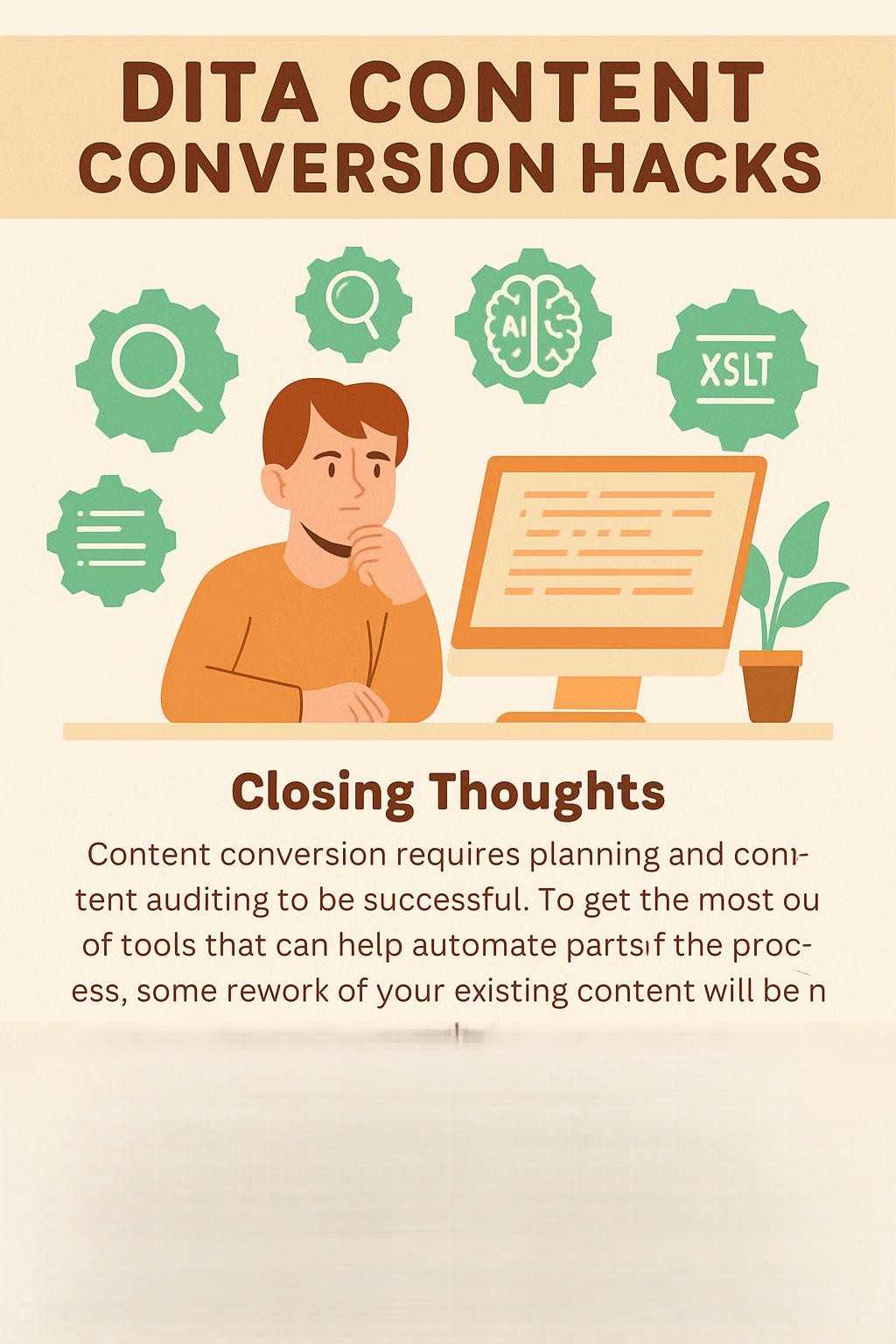
- 英語のお勉強日記
- DITAコンテンツ変換の裏技(DITA Con…
- (2025-11-14 15:01:12)
-








