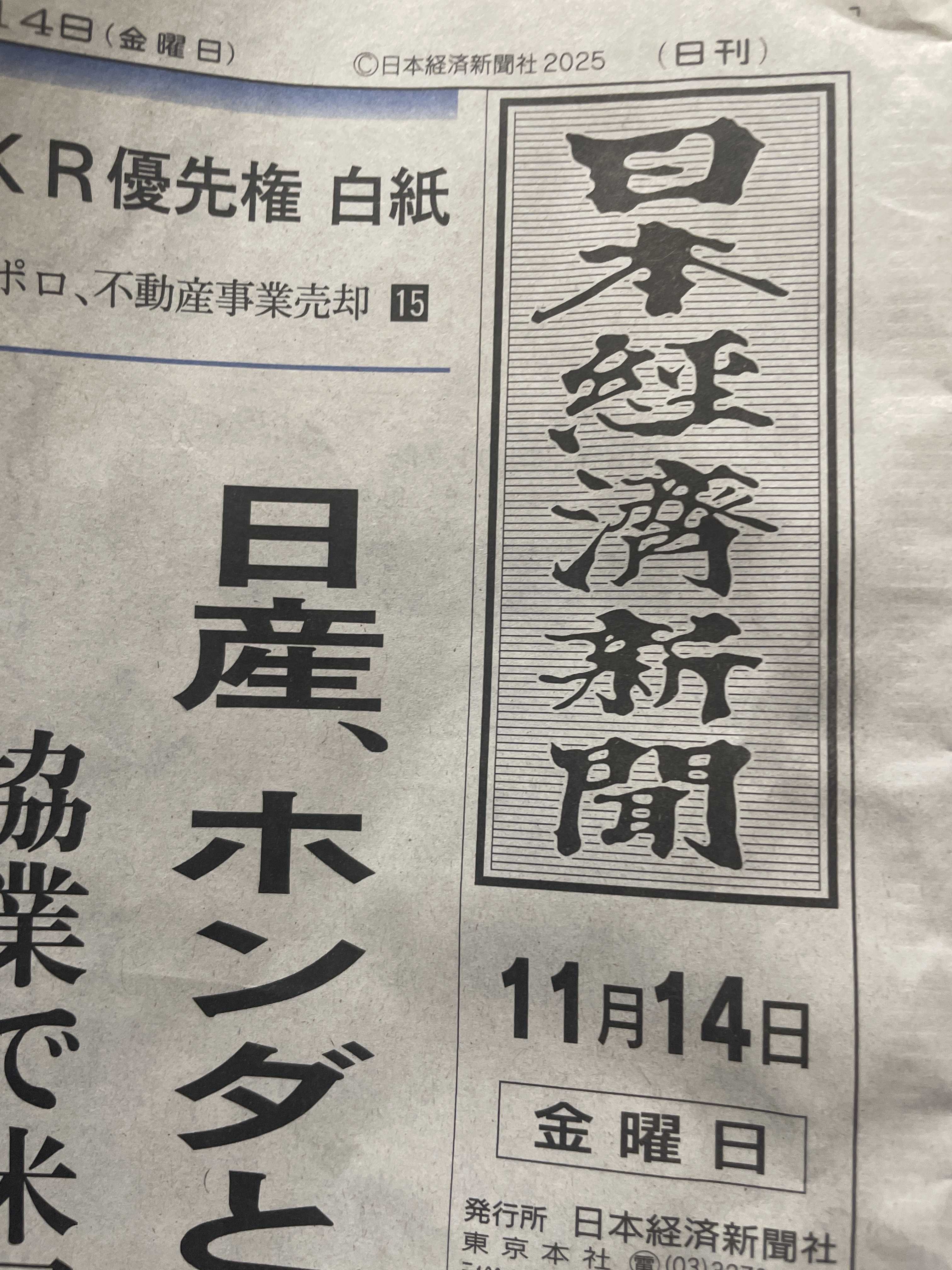2007年05月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
晴れの国の直播
岡山平野にて。稲の直播。 端の列は畔を壊さないように「プロ」がやりましたが、隣は素人(私ですがな)が…、やはり曲がってるわ…。これが稲刈りまで残るのが恥ずかしい限りで…トホホ しかし、乗用車というのが、いかに真っすぐ走りやすくできてるか、よう解ります。 今どきは、水をはった田んぼに田植え機を走らせるのが、一般的な日本の田植え風景ですが、 「晴れの国」岡山ならではの風景が「直播」。 乾いた田に直接籾をまいて、後から水を張る。 昔は「手押し」で2条ずつだったけど、乗用トラクターにくっつけて6条いっぺんにすいすい。 泥んこにならずにすむので、ここは楽。ただし、後で草取りが面倒。 どっちで苦労するか、の選択。(まあ、北陸あたりの米どころでは、選択の余地なく田植えですが。) 全てで楽をしようと思うのは間違い。子育ても同じですか。「楽」でなくても「楽しく」やることをみんなで考えたいものです。 なお、そもそも何で田植えをするか、というと、 水を張った田んぼだと、草が生えてない所に生長した苗を植えるから、雑草に対して稲がフライングスタートで伸びることが出来る、というメリット。 直播だと、雑草と同時スタートだから、どうしても、草取りしなければ草ぼうぼうになってしまう。(或は除草剤頼り) 逆に田植えの難点は、苗の生長と水の深さを合わせないと、浅いと倒れるし、深いと水没する。 他の田んぼの都合もあるし、まめに水管理できないとタイミングが合わせられない。(自分勝手に水を引くのを、「我田引水」という。)
2007年05月29日
コメント(3)
-
高齢議員はクビ?
昨日のTV『太田総理…』のマニフェスト。65歳以上の代議士は隠居させる法案。番組出演者のほうの賛否も、若い世代と高齢者に分かれてしまうのが、まあ、仕方ないんだけど、本来は、議員を選ぶのは有権者。ボケたジイサンに任せておけなきゃ、投票しなけりゃいい。それだけのこと。「国家権力の縛り」で強制的に引退させなきゃ、若い世代が出られない、…と考えてる「若い奴ら」が情けない。若手議員代表の一人で出演した、京都の泉K太議員。君のことだよ。京都の先輩若手議員である前原氏が、一年もたずに民主党の代表を辞めたのは、『長老』の圧力でなく、「若手」の永田議員に、根拠に乏しい追及をさせたあげくの「偽メール」事件で、武部氏を含む「ホリエモン疑惑」そのものをウヤムヤにさせた責任。 (泉くんが、もし、小沢一郎みたいな「オヤジの代表」に従うのが嫌なのなら、「造反」でも何でもできるのに、文句言いながら「公認」に固執するのが、「長老」の平沼議員よりオッサン臭いじゃないか。小沢氏自身も、しがらみを切って新党を立ち上げた実績がある。)お笑い代表、ハリセンボン箕輪さんの「私たちは毎日がオーディションだと思って出ている。偉い人には解らないだろう」発言は正論だが、強制的に「上」を排除しても、若手は育たない。(近藤さんは排除してほしがってたが…) 人間国宝・桂米長さんがいてこそ、門下生も成長する。先代の林家正蔵や三平さん亡きあとの、いまの正蔵さん。米長一門で比べたら、都丸さんより見劣りします。(あくまで主観で)なお、個人的に言えば、 まず、有権者の代表である議員は、制限なし。(有権者には、若者も高齢者もいるんだから各層から出ればいい。)選ばれるかどうかは候補者しだいただし、「行政」の代表である大臣や知事、市長は、行政職員である公務員に定年制があるんなら、引退しても当然だと思う。もし、意欲も体力にも自信のある方が「続投」したいなら、(一般の公務員がそうであるように)いったん退職後に再雇用の「非常勤嘱託扱い」で、安い給料で働いていただく。 議員にはないが、知事や市長にはちゃんと「退職金」が出るんだから、それで文句はないはず。(40年勤めた保育園長より、任期4年の市長の退職金が多いのには納得いかん…)
2007年05月26日
コメント(0)
-
映画・「博士の愛した数式」
先日、TVでやってた、映画「博士の愛した数式」 原作と違うのが、成長して数学教師になった「ルート君」が、新しい担任の生徒に「数学の世界の魅力」を語るところ。「教科書にはのってません」「試験にも出ません」「ノートはとらなくて構いません」…と前置きしながら、試験勉強では得られない数学を「博士」の思い出とともに生徒に語る…。いいねー。 ただ一つ、突っ込みを入れると、最初に書いた√の説明。√1= +1 × +1√1= -1 × -1これは違う。1 = +√1 × +√11 = -√1 × -√1が正しい。1 も√1も、結局は「1」で同じだから、たいした違いに見えないが、√2 = -2 × -2を考えてみれば、明らかに間違いだと分かる。原作者の小川洋子さんは、岡山出身で、早稲田の文学部OB。文系の人が数学を語る作品を作ると、こうも数学的になるのかと感心してしまうが、映画脚本家としては、もうちょっと数学を勉強してほしかった。大学で、よく言われること。生物学は限りなく化学である。化学は限りなく物理学である。物理学は限りなく数学である。数学は限りなく哲学である。…確かに。哲学であり、芸術でもある。証明の美しさにこだわる「博士」と小川洋子さんに拍手。
2007年05月22日
コメント(0)
-
「もったいない」のは…?
高知で胴体着陸したボンバル機を、修理して飛ばすんだという。「モッタイナイ」が国際語になる時代だが、人命より機体のほうがモッタイナイ?本来なら、「車輪が出せない」という「万が一」の(はずの)事態に、フェイルセイフであるはずの「手動」でさえ出せなかった。「万が一」がダブる確率は「億が一」(毎日2往復したとして年間1500フライト。億の単位まで飛ぶなら約7万年)「7万年に一度の事故」を起こして、機長の操縦技術のおかげで死者を出さずにすんだだけで、会社は喜ばなければならない。滑走路で炎上して、片付け費用が発生するのを回避できただけでも「もうけ」と考えて、機体はスクラップやろ。普通は。(機体をケチるなら、機長にういたお金の半分あげて当然じゃ?)'85年の日航ジャンボ墜落事故のとき、以前の「しりもち」着陸の修理が不備で、圧力隔壁が壊れたのが原因とされた。胴体着陸を「しりもち」レベルで考えてるのか? 全日空。そんな飛行機の就航を認めるのか? 国交省。「この機は事故で胴体着陸しましたが、死者を出さなかった縁起のいい飛行機です」ちゃんと表示して、「それでも乗る人」だけ乗せるんだろうな…。(それでもアナタは乗りますか?)※【5月14日11時59分配信 毎日新聞】 全日空のボンバルディア機の胴体着陸事故で、同社は14日、高知空港に駐機したままの事故機の修理を始めた。応急処置後に、31日に自力飛行で大阪(伊丹)空港に移して、本格的な修理をする予定。早ければ9月下旬に再就航する。
2007年05月22日
コメント(2)
-
フェイルセーフ ~事故るのを前提に
先日のジェットコースターの事故。全国で点検が進んだら、あっちでも、こっちでも。 「一番怖い」鷲羽山ハイランドも、同型のスタンディングコースターの車軸交換をしていなかったという。怖いだけでなく、本当に危ない奴だった。(韓国の遊園地で、観覧車の転落事故もあったが、観覧車でも危ないぞ) 金属疲労による破断、という発表があるが、 たしかに、直接原因が金属疲労にあるにしても、そこをチェックすれば安全だ、というわけではない。 数学的に言えば、「必要条件」ではあるが、けっして「十分条件」ではない。(何をもって十分か、というのは難しいけれど) 人間でも、健康診断で大丈夫だったのに急に病気をすることはある。 車で新品のタイヤがパンクすることもある。 新品のPCが、20世紀の「Windows98」モデルより先に潰れることもある。 点検でトラブルを排除するのには限界がある。 ただ、報道されているコースターの、レール●&車輪↓の構造。(断面的に) A B ↓ ↓C →●・・・・・・・・・・・・●←D ↑ ↑ E F 2本の走行レールを、上下左右の6本の車輪で支えている。(一つ一つの車輪は、レールをかむように凹型になっている。)6本とも正常であれば、安定するが、もし、Cが脱落すれば、左方向のプレッシャーがなくなって右に脱線する。もし、Eが脱落すれば、右上方向に跳ね上がる。1本欠けただけで確実に脱線する、というのは、設計段階で「欠陥」といっていいのではないか? あの「タイタニック号」は、設計上、船体が隔壁で遮断され、浸水が4区画までなら沈没しない構造になっていた。(中途半端に氷山をかわしたため、横に5区画ぶんの亀裂から浸水して沈没したのだが、正面衝突で前部4区画だけの大破なら沈まずにすんだかも知れない) ジェット旅客機でも、エンジンが止まっても墜落はせず、車輪が出なくて胴体着陸しても客室が潰れない構造になっている。某ボ○バル機事故の場合、電動で車輪が出なかった上に、手動でも動かず、胴体着陸。 (主翼を持たないヘリコプターでさえ、エンジンが停止しても着陸できるという。) エレベーターのワイヤーが切れても、落下せず、途中の階でブレーキがかかるようになってる(…のが普通だが、某シ○ドラー社は危ない)。 機械というのは、必ず故障するものだ、人間は必ずミスるものだ、という前提で考えたら、たとえ1本の車軸が折れても、車体がひっくり返らない構造は最低必要だと思う。これをフェイルセイフという。「万が一」がダブる確率は「億が一」 ○ンバル機の場合。1:電動で車輪を出す。2:手動で車輪を出す。までがアウトだったけれど、3:機長の腕で胴体着陸。が機能して死者が出ていない。しかし、機長が○○だった、とかいう事態だと、3が一番危ない。(事実、過去に、機体トラブルがないのに、逆噴射で機体を海に落とし死傷者を出した機長がいた。これも副操縦士が「機長止めてください!」と止めなかったら、もっと大惨事になっただろうから、それも一つのフェイルセイフである。) チャイルドシートをつけずに、お子さんをだっこして運転してるお母さん、あなたが一番危ないよ! 事故っても、大事なお子さんは守る、という意志を持たなきゃ。
2007年05月17日
コメント(0)
-

在来タンポポ
日本在来種のタンポポ(このへんでは、カンサイタンポポなど)は、花の咲くシーズンが限られていて、だいたいGW頃が盛り。 ただ、最近、咲くのが早いように思う。(画像は4月上旬。) ときどき、「外来種セイヨウタンポポとの生存競争に負けて繁殖地域が減った」というような説明をする参考書があるが、 けっして、競争に負けたわけでないので、カンサイタンポポの名誉のためにコメントを。 そもそもは、カンサイタンポポとセイヨウタンポポの好む条件が違い、 開発が続いてカンサイタンポポが好む条件の場所が日本から(とくに都会で)減っていった、ということ。人間がカンサイタンポポの縄張りを潰して、セイヨウタンポポの縄張りを作ってやったようなもの。 繁殖力旺盛なセイヨウタンポポでも、カンサイタンポポの縄張りまで侵入して乗っ取るほどの根性はない。 (いくら世界チャンピオンでも、安藤美姫を砂浜に連れて行って浅尾美和に挑戦しろ、というのは無理な話。) カンサイタンポポが好むのは、植物相(といっても背の低い草)の豊富な、土壌が有機物の分解で酸性になっているような場所。他の花の花粉で種を作るため、群生することが多い。(うちのタンポポは、滋賀県で田んぼの脇にあったのを取ってきたやつ。雑草だらけの我が家では根付いてます。) セイヨウタンポポは、どこでも空き地に生えて、1本だけでも種を飛ばすことができるのが特徴。ブルドーザーでひっくり返したような場所にでも生える。(「高い工場の壁の下で~」という歌詞は、セイヨウタンポポか…?)
2007年05月16日
コメント(2)
-
泡の力
主夫の知恵シリーズ(?) 「夏向き掃除」で並べた洗浄剤のうち、「カビ○ラー」は、もらい物(生協で「詰め替え」を買う以外はたいがいもらい物)ですが、 あれば便利で使うけれど、わざわざ買うのはもったいない。 シュシュッと一吹き、泡の力でカビを真っ白…。 CMを真に受けたら「泡」が漂白してるような印象を受けるが、実際は「泡」自体は役にたってない。 塩素漂白剤そのものは、次亜塩素酸から分離した塩素の酸化力で菌を殺すものだけれど、もともとあわ立つものではない。界面活性剤を加えてあわ立つようになっている。 なぜ界面活性剤を加えるかというと、表面張力を小さくして細かい隙間に入っていきやすくするため。泡立つのは、その結果であって、むしろ、泡の表面は風呂場のタイル目地から離れているわけだから、実際の漂白には働いていない。 特別にハンドスプレーのカビ○ラーを買わなくても、ボトルのキッチンハ○ターをプリンカップに少量とって、筆で目地に塗れば、安くついて効果的。(プ○チンプリンの爪を折ってた…というオチは無しで) ちなみに、ドラム式洗濯機の洗濯物。基準量の洗剤ではほとんど泡はたちませんが、ちゃんと汚れは落ちてます。CMほど「真っ白」になるはずはないけど。 (昔は「刷毛塗り式」のカ○キラーがあったけれど、中止。シュシュッと飛ばすほうが簡単で、よく売れる。横着モノが多いぞ、日本人。泡になったらたくさん使うので減るのも早くて、メーカーの儲けになる)
2007年05月13日
コメント(0)
-
「安全神話」
エキスポランドのスタンディングコースターが事故を起こして、安全性が問われている。今迄経験した一番怖いコースターは、鷲羽山ハイランド。スタンディングもあるが、目玉でも何でもないコースターがかなり怖い。場所が瀬戸内海を望むハイランドで、実際の遊具の規模に比べてかなり高い所を走る気分が味わえる。何よりの恐怖は、設備がボロい!観覧車でも「ネジが取れて落ちるんじゃ…?」と怖がる子ども達。所々にネジの外れた箇所あり(そこから風が入ってくる)同じ倉敷市内で、岡山県が公費を注ぎ込んで赤字を出してる「チボリ」の乗り物なんぞ、ちょろいちょろい。かつて最高速を誇ったこともある、スペイン村の「ピレネー」なんぞは笑えるわ。怖さが楽しさである絶叫マシーンは、実際に死ぬことがない裏付けがあってこそ。「機械は必ず故障するもの」 「人間は必ずミスをするもの」それを認めないのが「神話」、(誰がいつ神様になったんだ…)、「安全神話」なんて、はじめから存在させてはいけない。人や機械のやることだと認識して、命とりにしないのが知恵というもの。
2007年05月12日
コメント(2)
-
安倍さんのお供え
8日に安倍首相が靖国神社の大祭で「真榊」奉納したことについてのコメント。 「…国のために戦って亡くなられた方々のご冥福をお祈り…」 (いつもの話題だが、) 靖国神社に合祀されている戦死者は、「軍神」としてまつられてる。(何「柱」、というのは神様の数え方) 「神様」の「ご冥福」を祈ったら失礼やろ…。神様が暗黒の冥途をさまよってるとお考え? で、それを突っ込まないのか、宗教法人・靖国神社の神主さんは? じつは「ただのイベント業者」だと、自覚してたりして…。(過去の「玉串料訴訟」で違憲判決の中、ときどき「合憲」の判決がでたものは、慰霊祭が「世俗的な行事であって」、必ずしも宗教行事への支出と言えない、という理屈。つまり「単なるイベント扱い」。イベント業者と見なされた各地の護国神社の皆さんは、それで平気なんかい?)(例えば、日曜礼拝でお念仏を唱える人は、牧師さんに注意されると思う)
2007年05月08日
コメント(0)
-

ゆりかご
こどもの日にちなんで、「ゆりかご」(ベルト・モリゾ)マネの絵では黒が印象的だった、モリゾの代表作品です。
2007年05月05日
コメント(0)
-
高校野球特待生
いわゆる「野球特待生」が高校野球界をさわがせている。 届け出たのが3百何十校、7千何百人。 加盟校の1割が学生野球憲章に「違反」だという。 「強豪校」も多い(まあ、特待生で有力選手を集めて弱けりゃ、集める意味がないんだが) 駒大苫小牧とか、常葉菊川とか、《成金みたいに》強豪校になったところは、「まあ、あるわな…」と思うが、 平安とか帝京とか、古豪といわれる伝統校。そんなことしなくても「名前」で選手は集まってくるだろうに…、と思うのは私だけ? 「なぜ野球部だけ?」という疑問は、とうぜんあると思う。 選手の高校生に罪があるわけじゃないが、そもそも「高校野球だけ特別」なのが原因である。 「野球部でない」 バスケットや陸上などの高校生選手は、夏のインターハイめざしてがんばっている。インターハイは「全国高等学校体育連盟」(高体連)の主催で、「夏の甲子園」(選手権)大会は、朝日新聞社と高野連が主催。(選抜大会は毎日新聞社) スポンサーがついて、全試合・完全ナマ中継(主催者系列の朝日放送だけでなく、公共放送のNHKまで) これだけの「特別待遇」をされているならば、「コマーシャル目的」の部活について厳しい規制があってもしかたない。 もし、A森Y田が「卓球はいいのに野球は駄目なのか?」というならば、卓球部と同じように、野球部も高野連から抜けて、高体連の「インターハイ」に入れてもらうようにすればいい。 それなら誰も文句は言うまい。 それにしても、特待生なしで、公立の広島商業や熊本工業、最近では長崎・清峰、愛媛・川之江など、甲子園で活躍してるけどねー。
2007年05月03日
コメント(0)
-
買ったらアカン、ステルス戦闘機
米軍の誇る、最新鋭ステルス戦闘機、「F22Aラプター」。先日、沖縄で演習して話題になったが、これを日本に配備する計画があるという。1機250億円(+オプションあり)。見た目にはカッコイイのかも知れないが、これには落とし穴がある。ステルスの目的はレーダーに映らないこと。そのために犠牲にしたものは多い。まず安定性。レーダーからの電波をはね返さないために、主翼は平面的、垂直尾翼は「垂直」でない。ま正面から見た時に、機体からの「突き出し」部分が偏っている。普通に考えて、脚の配置が偏った椅子が安定するはずがない。赤外線を感知されないように、排気口は真後ろでなく上に付いている。(燃費も悪いやろなー)つまりは、不安定な椅子に体を傾けて立つようなもの。総飛行時間が短いから、安全性のデータがない。(あっても軍事機密)本当に「専守防衛」なら、かつての「F4ファントム」のほうが向いてるんじゃないか…?ちなみに、その前の「F104」はスマートなだけで、主翼が短く、見るからに不安定だったから、ファントムを初めて見たときは、えらくしっかりした飛行機に見えた記憶があり。(…あくまで素人考えですよ。)「敵地」に潜入して爆弾を落として帰ってくるのがステルスの意義で、目的を持って攻撃してくる敵を迎撃するのは無理なんじゃないか?(わざわざ迎撃機を目指して飛んでくる奴はいない)オプション別で250億は高すぎる。 那覇空港を発着する民間機にとっても、管制官にしても、レーダーに映らないステルス機がウロチョロしたら大変だ。 米国みたいに、基地が砂漠にある広い国と、横田を筆頭に都市圏に基地がある日本を同列に考えるところで、間違いがある。
2007年05月01日
コメント(2)
-
「総合科」医院
新聞報道によると、「町のお医者さん」として、「総合科」をつくる方針があるらしい。 「総合」といえば、総てを合わせ持ったもののはずだけれど、 じゃあ、この「総合科」は、いま全国で不足している小児科や産婦人科をカバーできるんだろうか? 医師免許そのものは、眼科だろうが耳鼻科だろうが同じだから、「一定の知識と技術」のとりかた次第? (医師免許を持っていても、小児科や産婦人科は収入に比べてリスクが大きいから開業する医師が不足してるんだと思うけれど、「総合科」だと、小児科や産婦人科の患者をみてくれるんだろうか? 診なけりゃ「総合」といえない、というなら、たぶん「総合」なんて看板を欲しがる医院がない。どうだろうな…) 獣医師は、骨折だろうと白内障だろうと感染症だろうとみてくれるよ…。「高度な治療」は専門病院に頼むとしても、「医師がいなくて手遅れになるのを防ぐ」ぐらいの受付はしてほしいな。【京都新聞記事より】厚生労働省は1日、家庭医のように高齢者などの初期診療に当たる開業医を対象に「総合科」(仮称)を創設する方針を固めた。一定の知識と技術を備えれば、総合科の表示を掲げることができるようにする。75歳以上が加入する後期高齢者医療制度がスタートする来年度の導入を目指しており、今後の診療報酬改定で大きな検討課題になりそうだ。
2007年05月01日
コメント(2)
全13件 (13件中 1-13件目)
1