2008年01月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
中国残留邦人の年金
戦前の「国策」で中国「満蒙開拓」に渡り、敗戦で置き去りにされた「残留孤児」の帰国に対して、国の責任で救済制度が出来たという。 国民年金を、無条件で「満額」支給する。等の制度。「国策」で放置されたわけだから、国の責任は当然。(さらには「国策企業」でしっかり儲けた財閥系もちゃんと負担すべきもの) 国の制度が機能すれば、生活保護を自治体が負担している分が軽減されるので、市役所も助かる。(生活保護法第四条で、他の制度をすべて活用したあとに申請することになっている)※ただし、国民年金だけで暮らせるほど、日本の年金は甘くない。 これに対して、国内で「高度成長」の時代に「国策」で進められた建設ラッシュの中で、いろんな場所で活躍した日雇いの建設労働者が、ろくに保険も年金も掛けられず、高齢化して仕事ができなくなって生活保護を受けている人は多い。大阪市(とくに西成)は日本一の保護地域と言っていい。(それだけ被保護が多いならホームレスなどしてないか、というと、ホームレスも多い。) 行政として、ちゃんと社会保険制度を完備させる責任は「中国残留」と変わらないと思う。 派遣労働の自由化が「国策」で進められて、無年金のワーキングプアが増えているのも、今のうちに「その恩恵を受けた人達」の責任で対策しないとえらいことになる。
2008年01月31日
コメント(0)
-
「反対だから野党」なのか、「野党だから反対」なのか
ガソリン税などの「道路特定財源」について、「暫定税率」の「暫定期間」が3月末で失効する。 ほおっておけば、「暫定」期間が終わって、ガソリン税は「本来税率」にもどる。 これに対し、「道路建設は必要だからまだまだ増税しなくちゃ」というのが政府側。(すなわち与党側) 対する野党側は「継続は不要」で一致。で、いろいろもめている。 「第二名神」をはじめとする「無駄遣い」のための増税はいらん、というのは当然あるけれど、暫定増税の延長について、賛否が与野党できっちり分かれる現象は不自然。 とくに「国民新党」は、小泉内閣の「郵政民営化」に逆らって「刺客」と戦って当選した人たちである。 小泉内閣で、竹中平蔵氏が「民営化したら法人税が入って国の財源が潤う」と主張していたことを思えば、小泉チルドレンなどにとっては 「民営化した道路公団は金を稼いで法人税を納めてくれる存在」でなければならない。 国の税金で高速道路を作る、なんて、民間企業にあるまじき予算に反対して当然。特定財源に固執するのは理屈に合わんのじゃ? (本気で「郵政民営化で財政が潤う」と思ってないことを、もう認めちゃうのか?) 逆に、「郵政族」の後押しで当選した国民新党のほうが、「特定財源」に賛同しても当然のように思う。 「理屈」で賛否を言ってるのか、賛否が先にあって「理由」さがしをしてるのか…。(国政マニフェストが「女性専用車両」だというような人たちには、どうでもいい政策なんだろうが)
2008年01月30日
コメント(2)
-

右折して…あかんのか
京都市のゴミ最終処分場(埋立地)。『エコランド 音羽の杜』 入口。(カタカナを使えばおしゃれだという…安易なネーミングやなあ、あいかわらず) 左上は、道路標示。京都市が立てている看板では、右に行けば「エコランド」 で、曲がろうとすると、「右折進入禁止」と、当のエコランドが「自主掲示」した看板。 (小さくて見づらいけれど、右下) お役所の「なわばり」関係で…?ただの方向表示板であって、べつに「交通標識」ではないから、(右折禁止の標識はない)べつに入っても捕まるわけじゃないけれど。しかし、ここに「一般車」が入ってくることはあるんだろうか?(「持ち込みゴミ」は、埋立地直接でなく、清掃工場行きだと思うが…)※清掃工場で「焼却」した灰や、粉砕した不燃ごみの処分場に、燃やしてもない粉砕してもない固形ゴミを持ち込んだら、「エコ」になるまい)
2008年01月29日
コメント(2)
-
およそ、3
かつて、学習指導要領の「コロコロ改定」の際に批判をあびた、「円周率はおよそ3」 円周率そのものが「無理数」のものを、「小数」で概数表示したものだから、機械的に、「3.14」が「3」より正しい、とは言えない。 たとえば「半径百km」の小惑星の体積は、といったら、いくら円周率を細かく出しても、元になる「半径」のほうがかなりおおざっぱな概数。 (V=4/3・πr^3の)公式を使うのに、どうせ概数なんだから、(おまけに小惑星が「完全な球」でもないし)「π=約3」を使って「約4百万立方km」と計算したらいい。 これに対して、「錐体(円錐や角錐)の体積」。「底面積×高さ÷3」の「3」は、概数ではなく、「きっちり3」である。 高校で「積分」を使って、それまで「暗記」していた、体積や面積の公式の数字が「裏付け」のあるものだと納得できた時は、純粋に楽しい。(こういう、新たな知識獲得の「楽しさ」を教えられるかどうかが、教育者の存在意義だと思います) ただ、四角錐の体積を中学生に教える数学の先生。「逆ピラミッド型の水槽」に水を入れて、メスシリンダーで計る…という「モデル」を使う人は結構多いらしい。 (しかし、小学生にやらせるか…?) たしかに、生徒さんたちの印象には残るけど、実験誤差を考えたら「およそ3」にしかならない。ちょっと工夫が欲しいな…。(工夫の中身は、続きへ…f^_^;)
2008年01月26日
コメント(4)
-
「ハンドボール」方式 比例代表名簿
オリンピック予選やりなおしが話題の「ハンドボール」 高校時代、体育でやったぐらいだが、「サッカーを手でやる」以外のルールの特徴が、「選手交替は、自由」いちいちタイムをかけず、審判の確認もなしに、「1人の選手がコートを出たら、替わりの選手が入れる」「何回交替してもOK」 試合の流れを見て、攻め込まれそうなときには「守備要員」を投入したり、ボールを取ったら一気に「攻撃メンバー」で攻めたりもできる。 これを聞いて思い出した、参議院比例代表選挙。(衆議院も議員の繰上げは同じだが) 現在は、誰かが辞めたら、「次の人」が「上」から順に繰り上がる。いわば「サッカー方式」で、辞めた人は戻れない。参議院の「非拘束名簿」方式では「上」になろうと、こういう人も出てくる) 国民の利益全体を考えたら、「ハンドボール方式」で、「社会福祉」が課題のときには「そういうプロ」を投入し、「エネルギー」が課題ならば「そういうプロ」を投入する。論議についていけずに居眠りするような議員は外す。「議席数」のトータルは変わらないから、選挙民の意思には反しない。(1議席に5人の議員がいても、議員歳費は1人分)「議員経験者」の肩書きが増えれば、「陳腐」になって「希少価値」が減る。(数が少ないから、○○センセイと呼ばれて増長するし、利権亡者が生まれる。)竹下さんみたいに、当選してから一度も登院せずに、任期まで病床で過ごす、なんてこともしなくてすむ。(S村T蔵議員の出番はあるだろうか)
2008年01月25日
コメント(1)
-
「白衣の天使」ではない。~ナイチンゲールの功績
たぶん、多くの人々が「白衣の天使」の元祖のイメージをもっている、F・ナイチンゲール。 じつは、彼女自身は、病院の経営には関与しているが、ナースの仕事はしていない。 大地主の娘であった、彼女の功績は、現場(ほとんどは海外の植民地に派遣された)兵士の待遇改善。 (by井野瀬久美惠・甲南大教授) ナポレオン戦争の後、世界大戦までの英国軍は、ずっと「応募制」をとってきた。「食うに困って軍隊入り」した兵士の状況を、本国にいるほとんどの国民は知らされていない。 「寝るところがあるだけマシ」というような、ワーキングプアの受け皿で構成されていた英国軍は、植民地で「弱いものいじめ」をしているぶんには偉そうにしてられるが、本格的な戦闘には弱かった。 クリミア戦争で苦戦する現場レポの中で、兵士を「使い捨て」にして平気な「偉い人」(大臣にコネがあった)に対して、生活・衛生・教育環境の改善を訴え、必要な物資の調達のために私財もつぎこみ、現場の実情を国民に伝えた。 とうぜん、国のほうはこれを歓迎しないが、しかし、結果的にはクリミア戦争の後、英国軍は勝利を重ねることになる。「人間らしい」兵士でなけりゃ、まともな軍隊も育たない。 (もちろん、軍隊だけの話ではない。) ちなみに、在日米軍の場合、刑事事件で逮捕・投獄された兵士が「思いやり予算」で厚遇されている。(スチーム暖房の部屋に、ステーキ・デザート付きの食事) 派遣先のアフガン、イラクで「劣化ウラン弾」やら報復テロの危険に晒されるより、日本の刑務所の居心地が良けりゃ、どうなるか…。想像に難くない。「そのレベル」の兵隊が、沖縄や横須賀をうろついているし、岩国をうろつかせるために、市民むけ予算を削る国もある。
2008年01月25日
コメント(2)
-
霊視の「裏づけ」って…?
フジテレビの放送で、「スピリチュアル」の倫理違反が、BPO放送倫理検証委員会で指摘されたニュース。 そもそもが、こういう占い系迷信番組が堂々と電波にのってるのか理解できないが、さいきんのH木K子や、かつてのG保A子みたいに、「根拠なく、ズバリ指摘する」ことを、「手間がかかっても納得できるまで考える」ことの苦手な現代人が歓迎するんでしょう。 視聴率につながり、スポンサーがつけば、それがすべて。タバコやサラ金のコマーシャルみたいに「占いの信じすぎにはご注意ください」ぐらいのテロップが必要かな。「楽しむための星占い」ぐらいなら、かわいいもので。 ところで、この委員会。『裏付けなく美容室を「経営難」と断定し』って… 裏づけを取って判断するんなら「霊視」とはいわんやろう。(G保A子は、ちゃんとリサーチして番組に臨んでたらしいが)オカルト番組を認める前提で指導してもなあ。【放送界の自主チェック機関である放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会(川端和治委員長)は21日、7月にフジテレビ系で放送された「27時間テレビ」で放送倫理違反があったと認定する「意見」を発表した。コーナーは「スピリチュアルカウンセラー」を名乗るタレントの江原啓之氏が、東北地方在住の美容室経営の女性を「霊視」し、アドバイスなどをする内容。同委は、裏付けなく美容室を「経営難」と断定し、女性本人の了解を得ないで「カウンセリング」を受けさせたことを問題視。「『スピリチュアルカウンセリング』なるものを面白く見せるため、一方的に出演させた人の生活状況を十分な裏付けも取らずおとしめた」と指摘した。 さらに、「面白さを求めて『スピリチュアルカウンセリング』をPRするような構成・演出は避けるべきだ」として、霊視や占いを安易に取り上げることにも警鐘を鳴らした。同局には3カ月以内に改善策などの提出を求めている。 フジテレビは「ご迷惑をお掛けしたことを改めておわび申し上げる」とコメントした。】(時事通信社) しかし、この番組に「出演」した美容室経営者さん。お笑いTVに何を期待したんだろう。
2008年01月24日
コメント(1)
-

今年も春から「偽装」 ~再生紙年賀状
(偽装したのは、去年ですが) 年賀はがきの「再生紙」の「古紙混入率」偽装。 「赤福」の製造日偽装は「新鮮さ」を偽る目的だったが、「古紙」の割合を偽装しても、製品価値には結びつかない。(むしろ、古紙を使わないほうが「上質」といえる) 「これだけ古紙を使ってますよ」というアピールの問題。しかし、「再生紙」と表示のあるハガキのほうが白く見える。 単に日数で変色しただけかも知れないけど、昔のハガキって、そんなに白くなかったように思う。※「はがき用修正液」といって、ちょっとクリーム色がかったのがあった。さいきん、テープが幅をきかせて、あまり見ないけど。「漂白」に余分なエネルギーを使ったら、環境に悪いけどなー。アピールのためのリサイクルか?
2008年01月23日
コメント(4)
-
スキーは「直滑降」だ 続続続
さいきんのカービングスキーは、エッジがカーブしてるので、膝をまげて雪面に「カーブの内側」(だいたいは「谷がわ」)にエッジを引っ掛けたら、自然に曲がれるらしい。(自分で履いたことがないので「らしい」としか言えない) エッジを鋭角に入れようと思えば、上体は傾けず、膝から下を傾けて、板の底の角度を取ればいい。(もちろん「前傾」はしたまま) このへんは、スノボの兄ちゃんがボードの両側を交互に使いながら、上体を安定させてるのが参考になりそう。 ボードでは絶対にできないのが「ストック」 右にターンしたいとき、体を前に伸ばして、右前方に狙いをつけて、ストックを突くのとあわせ、(ストックをコンパスの針にして)小さく跳び上がるつもりで体をうかせて、そのまま右にむいて着地すると、かなり「直角」のターンができます。パラレルで回ったほうが楽なんですが、ボードの人達の目前で、直角(鋭角)ターンを決めると、ちょっと気持ちよかったりします。 「二泊三日」スキーヤーで、このくらいは充分楽しめます。(と言っても、最終日は子供たちは半日券で自由に滑ってるのに、オヤジは朝から温泉で骨休め。子連れで夜行は難しいので、早朝発の「半日+1日」で一日半しか滑れない) あー、久しぶりにスキー行きてぇー…。
2008年01月21日
コメント(3)
-
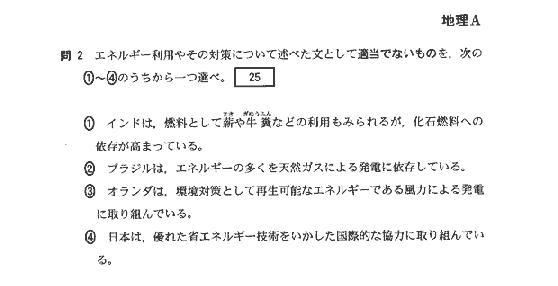
「取り組んでいる」 ~センター試験「地理A」 続
続いてまた、センター試験「地理A」 さすがに世の中の動きには敏感な教科ではある。(教科書の暗記より、日頃のニュースに親しんでなくちゃ)「地球環境」のテーマは避けて通れない。(避けて通ろうとする奴に大学生になってほしくない)当然、入試にも反映されるけれど、 もちろん、ブラジルが天然ガスに依存してるわけはないから、「正解」はわかるのだけれど、 じゃあ、日本って、省エネルギーに国際貢献してるのか? 「取り組んでいる」というのは、便利な言葉やなあ…、というのが実感できてしまう。 (選挙の公約で「…に取り組みます」というのも要注意だが) ついでに ビンの回収で地球的課題として必要なのは、「リユース」(再使用)だと思うのだけれど、あえて「リサイクル」(再資源)を強調するか…。 たしかに、使い捨て(ワンウェイ)のビンはリサイクルボックスで集められてはいるけれど、実際には、ドイツの飲料容器はガラスびんとPETボトルの合計で、「ワンウェイ」より「リターナブル」容器のほうが主流。(缶ビールは、ドイツでは邪道らしい。) 間違いではないけれど、正しいといえるのか?
2008年01月20日
コメント(2)
-
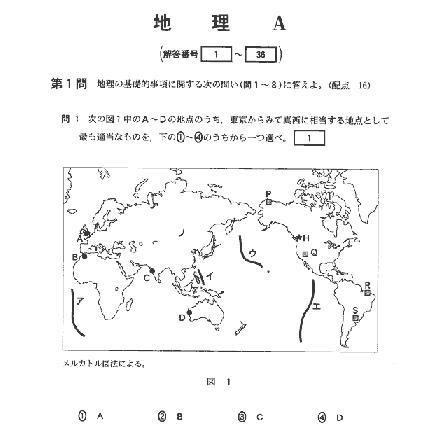
日本の「真西」は? ~センター入試「地理A」
さっそく問題を解いてみた。 とりあえずは、地理A。いきなり、最初の問題で疑問。(いちゃもん?)「東京から見て真西」にある場所。を選ぶ。 たとえば春分の日没に、「真西」を見れば、とうぜん、水平線に沈む「太陽」(東京から水平線は見えないが)がある。 地球は丸いんだから、「真西」の方向(たとえばレーザーを水平に発射するとき)は、「宇宙空間」を通って太陽にむかう。(地球は回っているから、その時々で方向は変わるが) 出題者としては、「東京から弾道ミサイルを真西に発射したときの着弾点の候補」というイメージなんだろうが、(正解がCだということは) 普通、民間人がGPSを使って旅客機に「西に1万km」とセットしたら、メルカトル図法の左方向に(緯度を維持しながら)進んで、Bに向かう。(探検家が北極星や方位磁石を使って西を目指しても) (目的地をセットして、最短距離を飛ぶならば、地球の周囲で「円弧」を描いて飛ぶんだろうが) 入試センターの出題者にとって、「GPS」や「方位磁石」より、「弾道ミサイル」のほうが「自然に西を目指す手段」なんだろうか? (湾岸戦争のときに、某宗教団体が「クウェートの方向に手かざし」を行ったというが、「どっち」を向けて手をかざしたんだろう? 手かざしのパワーは重力で曲がるのか…) ※「正距方位図法」でみれば 東京から真西がインドで真東がハワイの方向になります…(このへんが、受験生の立場と、気楽に見る立場の違いですが、受験会場で突っ込みはできんな~ 「空気」を読めば、「小学生ならまっすぐ左に進むだろうが、高校生なら地球が丸いことは知ってるから、北半球ではだんだん南に曲がるぐらい理解できてるだろう」という意図はうかがえる。でも、それは、中学生のレベルじゃない?)
2008年01月20日
コメント(5)
-
センター試験
今年も「センター試験」の季節。 私の時代には、「共通一次」の前で、マークシートなど縁がなかった。(正直いうと、アレがなかったから現役合格できた。とくに数学。 私の場合、納得できんものは徹底的に出来ん、という性格で、「数3」あたりになると手がでない。「複素数」なんか、勘弁してよ…。農学部では使わんし…。 …なもんで、平均点が低い「難関校」ほど、「納得できる」部分で勝負できた。) しかし、マークシートって、採点は楽だけれど、「マークシートに合わせた出題」というのに無理がある。「証明」問題に「部分点」など入る余地もない。 「リスニング」のテストで、会場ごとに不公平が出ないようにと「全員に使い捨ての機械」を配る、なんて、無駄そのもの。 本当に「リスニング」の実力が必要なら、必要とする大学が「二次試験」で使えばすむこと。「マークシート」で回答できる程度の出題のために、リスニング機を使い捨てするか…? ときどき、翌日の新聞に掲載される出題を解いてみますが、「地理」なんか、世の中30年前とだいぶ状況が変わってるのに、受験生よりいい点が取れたりする。4択だもん。 「そんなわけないやん」と突っ込みながら「消去法」で1つずつ外すだけで。ほとんどできちゃう。 (「突っ込みできる問題」が出てないか、また解いてみよう…)
2008年01月19日
コメント(2)
-
京阪電車「祇園四条」駅
先日、京都市地下鉄・東西線の延伸で「太秦天神川」まで開業。たしか、「洛西ニュータウン」まで伸ばして、市立芸大や、京大「桂坂キャンパス」も…という話があったなー、と思って調べていたら、見つけたニュース。 京阪電車が「四条」「五条」「丸太町」の駅名を、京都市地下鉄と混同しないよう変更するとか。 京阪のほうが歴史のあるのに、あとから出来た京都市地下鉄が、阪急「烏丸駅」と接続する四条烏丸に「四条駅」を作ったのがややこしい原因。 理屈から言えば、京都市地下鉄が「四条烏丸」駅に名称変更するのがスジだと思うけど。 京阪「三条」駅に接続する地下鉄の駅名を「三条」でなく「三条京阪」とするぐらいなら、阪急「烏丸」駅に接続する駅は「烏丸阪急」でもいいはず。 (しかし、京阪電車に乗ろうとして「三条京阪」駅の改札に入った人はいないんだろうか? 最近は「ICOCA」でどっちも入れるから、切符が違うといって遮断機が閉じない)【京阪電気鉄道は6日、京都市内3駅の駅名変更を発表した。丸太町を「神宮丸太町」に、四条を「祇園四条」に、五条を「清水五条」にそれぞれ変え、観光客に駅の立地をわかりやすく伝えるとしている。3駅とも駅名変更は設置以来初めてで、2008年度中の中之島線開通と同時に実施する。】【駅名変更する3駅は、いずれも京都の主要駅で、五条駅は京阪電鉄が運輸を始めた1910(明治43)年からの歴史を持つ。これまでの駅名は、市民らに長く親しまれてきたが、地下鉄烏丸線に同じ名前の駅があるため、混同する観光客も多かったという。新駅名は観光客の認知度が高く、最寄りの平安神宮、祇園地区、清水寺からそれぞれ採用した。】京都新聞電子版 JR西日本みたいに「地元に費用負担」を負わせないのは立派かな。 でも、平安神宮に京阪電車で行くなら「丸太町」より「三条」のほうでしょ。鳥居も南側にあるし。特急も停まるし。 (丸太町まで乗ってくれたほうが、京阪としては儲かるが…。)
2008年01月19日
コメント(2)
-
あっかるーい、パナソニック?
ちょっと前のニュースで、松下電器のブランドが、「パナソニック」に統一されるということ。 「水戸黄門」の始まるときには、「明るいナショナ~ル♪」のCMソングが流れたものだったが。(「ズバリ当てましょう」という買い物クイズもありました) グローバルの時代に「ナショナル」というと、「国営企業か?」という印象もうけるし、「HITACHI」や「TOSHIBA」などに比べて、「MATSUSHITA」は欧米人に語呂が悪い…。 名前が変わる前に「松下」製の欠陥製品はすべてケリをつけてほしいものだけど。 「豊田市」のように、創立者の名前が企業名になり、地名にもなっていく、というのから比べたら、松下幸之助のような「大物」の名前をあえて残さないのも英断なのかもしれない。 本田宗一郎氏が、「最大の失敗」は、会社名に「本田の名前」を残したことだ、と悔いたそうで、 三重県鈴鹿市が、豊田市に対抗して「本田市」はどうだ?と起案したとき、真っ先にトンデモナイと反発したとか。 一方で、何が何でも「名前を残したい」人たちって、いるもんですね。「ム●オハウス」とか…。(JR西日本が、滋賀県「南草津」駅の開業時、「立命館前」にしようと提案して、地元から反発をうけたことがあり。いちおう「京都の大学」だからねー…)
2008年01月18日
コメント(0)
-
埋葬法と「散骨」
日本人ほど「遺骨」を大事にする(こだわる)国民はいない、 …と言われる。(比較の対象が欧米人であり、東南アジアやアフリカがどうかは知らない) 火葬場のカマを1000°Cまで上げれば、ダイオキシンは発生しないが、「骨」が残らないとクレームがあるので、ギリギリ800度に抑えてるという。(外国では「灰」だけに)焼き上がった「遺骨」を、「勝手に埋める」のは、埋葬法に違反して処罰されるが、「埋めずに持っている」のは合法。(信長が朝倉氏の髑髏に金箔を張って、お椀を作るようなのは、一応「合法」。ヒンシュクを買って謀反を招くのはともかく) ※死体損壊は犯罪だが、手続きして火葬した遺骨は、「死体」ではない最近増えている「散骨」も、「埋葬」ではないので規制する法律はない。さすがに「人骨」をばらまくのは事件に巻き込まれる恐れがあるが、少量の「灰」なら自由。「灰」を使ってペンダントを作って身につける人もいる。火葬場に「1000度コース」があれば助かる人も多いと思う。(土葬から火葬への「進化」を思えば、骨から灰の進化は小さいのでは?)散骨や自然葬についても、悪徳業者はいるので、「楽だから」という安易な気持ちでやらないことが肝心。(「樹木葬」した遺骨を野犬が掘り返したりのトラブルもあるという。)墓に納めるか、自然に返すかは、考え方次第。ちゃんと考えた上で、「流されて」やるのでなければ、形式にこだわる必要はない。「○○しないと祟りがある」とか、「子孫が不幸になる」とか、カルトや悪徳石材業者に振り回されるような生き方を、すでに750年前の親鸞上人がたしなめて「占いや迷信に頼るな」と断言した。21世紀の日本人、もっと考えよう。頭は生きてるうちに使わんと、死んだら使えんよ。
2008年01月17日
コメント(10)
-
お年玉年賀ハガキ
昔は、1月15日は、「成人の日」であり、 お年玉くじ年賀はがきの抽選日でもあり、 三十三間堂の「通し矢」の日でもあった。「松の内」というのが1月15日までで、門松などの正月飾りを外す。正月気分も終わり。という。「左義長」というのがあって、竹を組んで火をつける(のが基本で、書初めの半紙を燃やしたり、餅やみかんを焼いて食べたら病気しないとか、いろいろあるらしい) で、お年玉はがきは(切手シートしか当たったことがない)発表がないので、はがきを見たら、1月27日? 「成人の日」がマンデー移行してから、第二日曜なんだと思ってたが…まだ売ってるんやね、年賀はがき。 そのための延期か?「いつまで正月気分なんだ!」って、民間会社になったらクレームは来ないということかな。「1月15日」というのが、だんだん「なんでもない日」になっていく。「小正月」の行事、何かありましたっけね。
2008年01月16日
コメント(4)
-
雪印と三菱自動車
先日のHBC杯ジャンプで男子準優勝の岡部孝信選手。 所属チームは、長野五輪からかわらず「雪印」だった。(長野のジャンプ団体は、船木以外の3人とも雪印)昨年の漢字に選ばれた「偽」は、雪印が大先輩。トップメーカーの不祥事で、原田選手も岡部選手も、「活動自粛」のとばっちりを受けた。「亀田」のボクシングみたいに、しょっちゅう試合があるわけでない種目とちがって、限られたシーズンに集中して大会があるスキーの場合は、活動停止期間があるのは重い。いっぽうで、リコール隠しが問題になった三菱パジェロ。これが「パリダカ」ラリーを自粛した話は聞いたことがない。「雪印スキー部」に偽装や食中毒の責任があるはずないが、「三菱パジェロ」は、そのまんま、当事者だった。(もちろん、篠塚選手や増岡選手に責任があるわけではない)自動車メーカーと食品メーカーの対応が、ずいぶん違う。(食中毒を出した雪印はともかく、「赤福」で「実害」は出ていない)「輸出産業」に対して、行政指導は甘すぎる。(赤福のアンコ以上に)バイオディーゼルで「パリダカ」に挑もうとして、「大会中止」にあった片山右京チーム。残念な気はするけど、「パリダカ」そのものが環境に悪い大会なんじゃないか?と、いつも映像をみて思う。
2008年01月15日
コメント(3)
-
家庭用電源で車の充電…屋外コンセントは?
トヨタが、家庭用コンセントで充電できるハイブリッド車の発売計画、のニュース。 ガソリン代は高いし、とくに都会で信号待ちなどの多いところでは、アイドリングも長くなるので、ハイブリッド車は効果的。 たぶん、オール電化をすすめる電力会社も、「深夜電力で充電」を奨めることになるはず。 ところで、簡単に充電できる、となると、予想されるのは、ホテルやレストランの駐車場などでの充電サービス、という「まとも」なものの他、深夜のPA等の自販機コンセントから勝手に充電する「盗電」携帯電話の充電ぐらいなら、たいした電力じゃないけれど、自動車の電池は大きいぞ。屋外コンセントのあるお宅は、蓋にカギをつけるとか考えなくちゃいけないかも。(屋外コンセントがなけりゃ、この車を買っても自宅で充電できん…。自転車なら持ち込んで充電できるけど)
2008年01月15日
コメント(3)
-
スキーは「直滑降」だ 続続
中級コースになると、斜度がちょっとあるのと、斜面の凹凸が目立つ。コブをうまく使ってターンを決めると、カッコイイ。(ゲレンデスキーなんてのは、ほとんどが「格好つけ」みたいなもん)その前に、小さい凹凸は「膝の屈伸」で越える。(モーグルの里谷選手をお手本)初級の直滑降練習で、おもいっきり前傾してたのを、ここで初めて、身体をおこす。左右の振りも、膝を使えるようになると、ずいぶん自由ができるし、ちょっと膝を傾けるのを覚えると、パラレルターンの時のエッジの練習に使える。「ハの字」の欠点は、自転車の補助輪と同じく、「底面積」を広げてしまうこと。パラレルがボーゲンと根本的に違うのは「重心を底面の外に出す」こと。開いた脚の内側に体重を乗せる癖をつけたら、抜けるのに苦労する。後で抜く癖なら、初めからつけないのが一番。シュテムターンだといって、曲がるたびに開け、閉じろと言われたら、面倒だわ(コーチ料のために余分に時間かけてるんじゃないか…?)じつは体重の軽い子供の場合、パラレルより、「ウェーデルン」のほうが身につけやすいようにも思います。「ハの字」は止まるための技、と割り切って、滑りまくるのが「二泊三日」スキーヤーの上達法。「いくつのワザを身につけたか」が問題ではない。
2008年01月14日
コメント(3)
-
HBC杯ジャンプ「マッチ」
久しぶりにTVでスキーを見た。(たまたま) HBC杯ジャンプ大会。(日替わりでSTVやHTVの大会があるとか)ジャンプをゴルフみたいに「マッチ」でやるのは邪道だろうと思いながらも、長野五輪の金メダリスト、岡部孝信と船木和喜の勝負といったら見逃せない(それがスポンサーの狙いか)トーナメントだから、「最長不倒」を出しても組み合わせ次第で決勝進出できない。その中で、女子の山田いずみ選手が準決勝決勝と132mの大ジャンプを重ねたのはスゴイ。ちなみに男子の決勝最長不倒は126m。(K点120m) トリノで原田選手が「体重200g不足」の失格に泣いたけど、ジャンプでの「体重」はそれほどの影響をもつんだなー、と感心しました。(もちろん、体重だけでなく、山田選手の力とワザなんですが) 女子選手が男子の中で戦えるのは「競艇」ぐらいしか思い浮かびませんが、(ミシェル・ウィーでも日本の男子ゴルフ予選通過できんのが現実)今後、ジャンプの競技人口、増えるかな。(山田選手の所属の「神戸クリニック」って、どんなサポートしてるんだろう)
2008年01月14日
コメント(5)
-
悪い「なまはげ」は、いねーがー!
秋田名物の「なまはげ」が、温泉の女湯にはいりこんだ事件 酔っ払いに甘いのが日本人の体質(?)だけど、そもそも、 「観光用なまはげ」が観光旅館を回る、というのは、平気なんだろうか…。お金を払って宿泊してるお客は、そのレベルの「なまはげ」で満足してるの?支配人は、酔っ払いの「なまはげ」で、お客にサービスを提供できてると思ってるのかな。 京都で、にわか仕立ての「なんとか鉾」を作って祇園祭に参加しようとしたら、怒られるで…。(「舞妓体験」のお嬢さんを町に出すときには、「本物ではありません」と注意書きをつけるとか)【組合によると、観光サービスとして温泉郷周辺の町内会の男性5人が扮(ふん)したなまはげが午後8時半過ぎに旅館ロビーで舞を披露。うち20代の男1人が抜け出して大浴場に入り、女性客数人の体を触った。男は振る舞われたお神酒などで酔っていたという。女性客の家族から苦情を受け、町内会長らが謝罪した。】(毎日jp)より 「保育園のサンタクロース」みたいなもん?
2008年01月12日
コメント(0)
-
スキーは「直滑降」だ 続
実践編スキー板はそもそも真っすぐ進むようにできている。わざわざ「斜め」に滑るのは、高等技術。漢字の「木」より「板」を先に習ってどうするんだ? …というのが、「ハの字」から始めない理由。直滑降から始めるメリットは、とにかく「本数」をこなせる。一日券の元を取れ、という貧乏性もあるが、回数を滑らないと面白くない。そこそここなしたら、カーブの練習へ。物理学的に、スキー板は、雪を圧縮するほどよく滑る。 直滑降から「右」に回りたければ、「左」を前に出せばいい。左足に体重をかけたら自然に右に曲がっていく。(左手でグーを握って押し出せ、というと自然に左足に力が入ります)曲がった後は、ほっといても「重力」で「下」に向く。これだけでも、「初級ゲレンデ」はすいすい。「ハの字」で苦戦してるスクールのお嬢さん達を尻目に、うちの子達はぶっ飛ばす。(いや、考えすぎかもしれないけど、)簡単に滑れたらコーチ料が高く思われるから、わざとボーゲンに時間かけてるんじゃないか?と思ってしまう。いくらでも機会のある雪国育ちと違って、「二泊三日」で帰る者は、翌年までにカンを忘れないために、「その年のこと」はしっかり身につけないと無駄になるんですよ。
2008年01月12日
コメント(6)
-
スキーは「直滑降」だ
最近、暖冬とスキー人口の減少で、スキー場も苦戦しているらしい。 北陸や信州で、ちょいといけるところに住んでいるならまだしも、関西人には半日がかり。宿泊費もいるし、たまに雪が多ければ、高速が規制されて足止めをくらう。 二泊三日ぐらいでシーズンを過ごすようだと、1時間の滑走も貴重。子連れでコーチするのも、「早くマスターしてもらう」のが一番。でないと親が滑れない。で、理系の練習法。スキーもスケートも、滑る理屈は同じ。「圧力により氷点下で解ける氷」によって摩擦係数が下がったものを、重力や慣性の法則を利用して、ただの「滑る」をコントロールして「滑走」にする。 私の若い時分は、やたらと「ハの字」をやらされた。貴重な時間をエッチラオッチラと「ハの字」では勿体ない。 手っ取り早くマスターする秘訣。1.「すいたスキー場」を選ぶ。できるだけ、ボーダーの少ないところ。2.リフト券を1日券で買う。3.初級ゲレンデに上って、すいたところを狙って「直滑降」 (ストックを両脇に抱えて前傾姿勢を保って滑り降りる。お手本は、オリンピックのアルペン種目のゴールイン前の映像) ※怖がらなければ、いくらスピードがでても、初級コースであれば、いずれ下でとまる。 これを何度か繰り返せば「かっこよく滑り降りる楽しさ」が身につく。こまかい技術はそのあとついてくる。
2008年01月12日
コメント(3)
-
「七草」、「七福神」、「ラッキーセブン」
1月は、7日に「七草粥」 さらに10日の「十日ゑびす」をはじめとする「七福神」めぐりが行われる。 七草は、「せりごぎょう…」の和歌が有名だが、とくに指定があるわけではないので、わざわざスーパーでパックを買う必要はなし。 七福神は、ゑびす様が日本の神様で、あとはインドや中国由来の神様が仲良く宝船に乗りあってる、インタナショナルなもの。 なぜ「七」なのか。 昔から、「7」については「神秘の数」として知られており、西洋のラッキーセブンも同じ。 たとえば「ある数」が、「2008」の約数かどうかを見分けるのに、「2」や「5」は、其々、末尾が2や5の倍数ならOK。(2も5も10の約数だから)「3」や「9」は、各桁の数字を合計して、其々、3や9の倍数ならOK。「6」は、3と2の公倍数だから、双方の判断を組み合わせればOK。「4」は、100の約数だから、「下2桁」が4の倍数であればOK。「8」は、200の約数だから、4の倍数のうちで、百の位が偶数ならばOK。 「2008」は、これで見れば、2,4,8、の倍数だとわかります。 (昔は、中学校の数学でやりましたが、いまはどうか…?)「7」の場合は、いろいろあるようですが、面倒だし、結局は、思い出す手間よりもそのまま割り算してしまえ、ということになる。 7匹の子ヤギ、7人の小人、7人の侍、ウルトラセブン、ヤマトナデシコ七変化…、 みなさん、7がお好きです。
2008年01月09日
コメント(0)
-
セクハラの基準は…
JR東日本が、「裸祭り」のポスターの掲示拒否のニュース。 JR西日本は、岡山・西大寺の裸祭り「会陽」(えよう)」でしっかり客をあつめにゃならんから、 関西方面は毎年PRが欠かせない。 ポスターがセクハラ扱いされた話は聞いたことがないけれど。 (私の祖父や伯父は「福男」になったことあり。常連でしたから…。)中高生が「部活」で参加するところもあるらしい。 じつは、私は、このニュースのおかげで初めて「蘇民祭(そみんさい)」というものを知ったから、そういう人がそこそこいるなら、PRにはなってるのかもしれない。(「王に756号を打たれた鈴木」かい…) 「蘇民」自体は、京都でも、祇園祭のちまきに「蘇民將来之子孫也」と書かれた札が貼ってあるぐらい有名ですが。 【JR東日本盛岡支社の佐藤英喜・販売促進課副課長は「セクハラが問題になる中、公共の場でのポスター掲示の基準は厳しくなっている」と説明する。そのうえで「単純に裸がダメというわけではないが、胸毛などに特に女性が不快に感じる図柄で、見たくないものを見せるのはセクハラ」と判断したという。】(毎日) そういえば、岡山では、「胸毛いっぱいの福男」って、聞かないねー…伯父もヒゲは濃かったが、胸毛は薄かった。 東北・岩手ではけっこうポピュラーな絵柄なんだろうか…。
2008年01月08日
コメント(8)
-
一部で全部
健康食品の広告の定番。 『私は○○を毎日続けたら、●●が完治しました』(横浜のYさん談)など「○○が●●に効きます」という表現は『薬事法』に触れるので、『薬品』として登録されてない健康食品の広告には使えない。 ただし、『私は○○を飲んで回復しました』という「体験談」をしゃべるのは勝手。 Yさんに因果関係を検証する義務はないし、『私』が回復したからといって『みんな』に効くとは言ってない。「あの人に効いたなら私も…」と信じたほうの「早とちり」。クロレラにしても、トルマリンにしても、「なんとか還元水」にしても、納豆ダイエットにしても。(そういえば、ひところ通販のブームになったア●トロニック、どこへ行ったんだろう?) 受験シーズン、『私は○○』が、『みんな○○』ではないからね。
2008年01月07日
コメント(0)
-
「初日の出」&地動説
今年は、元旦早々から電車に乗っていたため、 「初日の出」は車中で迎えました。 もちろん、京都盆地に「地平線」はない。 盆地を「南北」に走る電車だと、「初日」の影を何度も過ぎるので、何度も「初日」をおがむことに…? 西山に陽が射しても、まだ日陰の中にいたりする。 「お日様」にいちばん近い側が、いちばん日の出が遅い。 何か教訓めいたことを考えます。 いまどき、【「天動説」を信じている中学生が3割以上】という話もあるけれど、 とうぜん、「日の出」とは、地球の自転で「日なた」に出てくる瞬間。 日の出を待つ人々が、じつは「日のあたる場所」に向かってる。 人生、「待つ」だけでなく「向かっていく」ことも必要だよ、ということも。 地球に乗っかってるだけで、日の当たるところに向かっていくありがたさも。 天候の悪いのを知らされながら、越年登山で命を落とした方もいらしゃいますが、 毎日同じ日は昇る。(なんていう割り切りをできないのが、その道の人か…)
2008年01月06日
コメント(2)
-

「新・大阪」か、「新大阪」か…
年始の新幹線は、Uターン客でいっぱい。 年末に初めて「500系」に乗り、年始に初めて「N700系」に乗りました。 N700系は、表示パネルも大きくて(ふつうの700系が小さいのかどうか、覚えてないだけかも)読みやすいです。 「全車禁煙席」で、スモーカーは限られた喫煙所で固まっているのかどうか…、ということは、降りてから気づきました。 で、乗ってるときに気づいたこと。 (新年早々から、しょうもない小ネタですが、)「新神戸」の英語表示が「Shin-Kobe」に対して、 「新大阪」の英語表示が「Shin-osaka」。 「Shin」は接頭語で、「Kobe」も「Osaka」も固有名詞じゃないのか…?(ちなみに、「新横浜」も「Shin-yokohama」と小文字でした。 「新大阪」や「新横浜」は、それだけで地名として認知されてるけれど、「新神戸」は、まだ「新しくつくった神戸の駅」という扱い?(「のぞみ」の停車駅でないので「西明石」とか「三河安城」がどうなってるのかは不明) JR西日本と東海でルールが違うのかも知れないけれど、こういうのは、「Shin-Osaka」に統一しないと、 「Shinagawa」を「しん・あがわ」と読む人がいそうな気がするのは、私だけ?
2008年01月05日
コメント(1)
-
正月は、やっぱり「箱根駅伝」 だが
お正月も、だんだん知人が減ってくるとすることがなくなってきます。 (まったくいなくなるわけでなく、ちょっと声をかけられるところにいない、も含めて) お正月のTV番組も、レベルの低いお笑いばっかりやな… ということになると、 「駅伝」とか、「ラグビー」とか、「筋書きのないドラマ」。 今年の「箱根駅伝」は、往路の段階で、最後の4区5区にかけ実力校が相次いでタスキ渡し。 最後まで展開が読めない、見ごたえのあるレース。 (出かけようと思いながら、動けん…) 過去映像では、スピーカーつきジープ(自衛隊の提供)の「監督車」が後ろから声をかけながら走ってたのが、いっとき、なくなってたが、(早稲田の櫛部君がフラフラになってタスキをつないだ時にはなかった) ことしは、走ってた。乗用車の屋根に小さいスピーカーつけたやつ。 売り上げ好調の某社の提供で…? 大学陸上部の頂点の選手たちが、20km走るのに、いちいちコーチのスピーカー指示を必要とするんだろうか? スポンサーの提供車を目立たせるためには、静かに走ってたんではまずい、という陸上競技の中身と「別」なところに、配置の有無の基準を置いてるとしたら、 情けないぞ、関東学生陸連。 しかし、この大会がメジャーになるから、西脇とか報徳とか、関西の有力高から、みんな「関東」の大学にいくようになって、関西勢はなかなか大学駅伝(全日本など)で目立たない。 そのわりに、箱根駅伝経験者って、「渡辺康幸」とか「実井謙二郎」とか、「スーパースター」が卒業後、活躍してないように思う。 この大会のために無理をして、選手寿命を縮めてるんじゃないだろうか。
2008年01月02日
コメント(6)
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-12 17:20:55)
-
-
-

- ひとりごと
- 今日の気になるもの 11/14
- (2025-11-14 13:07:40)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「クマさっさと絶滅させろ」“過激派”…
- (2025-11-14 17:00:04)
-







