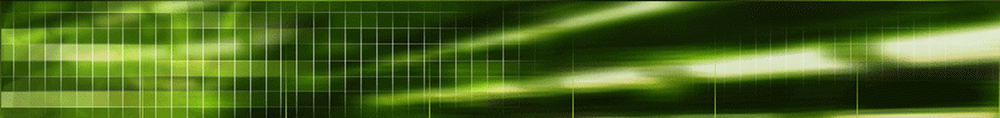OYOZRE 【CTISAKE】
OYOZRE
噂は、所詮噂。
在りもしない噂。
では、在りもしない噂は何故生まれる?
それは、本当に噂か?
噂に、真実は無いのか?
噂は発展すると伝説化する。
根拠は無いものがほとんどだろうが
決して、OYOZREだと、決め付けること無かれ
【CTISAKE】
「お嬢さん」
私は不意に誰かに呼ばれた。
私は坂井知美。22歳のOLだ。
今時間は午後5時を過ぎた所、私は帰りの電車を待つためホームに居る。
そこで私は誰かに呼ばれた。
お嬢さん、としか聞こえてこなかったが
すぐに私だという事が分かった。
「・・・・私?」
「えぇ、あなたです。」
私に話しかけて来たのは変わった身形の青年だった。
背が高く、白いコートを着て、背中に大きな白い木の箱を背負っている。
顔は銀髪に隠れて見えにくいが髪の間から切れ長の目が私を見据えている。
私は少し気になったが、直後に電車が来た。
「この電車に、乗られるのですか?」
私は電車の扉が開いて中に入ろうとしたが、急に前に進まなくなった。
今は午後5時だ、こんなに人が少ないわけが無い。
なのに異様に空いているのだ、別の車両にはチラホラと人の姿は確認できるが
心なしか皆、落ち着かない様子だった。
そして先ほどの青年も、この電車に乗り込んだ。
「予感というのはアテになります、物事を決める際に、どういう予感をしたかで、人は、少なくとも、無意識に最良の方へと、衝き動かされるからです。」
「・・・・?何を言ってるの?」
「・・・・おかしいと、思っているんでしょう?この電車・・・さっきまでホームには沢山の人が居ましたが、今は居ません。私達2人を除いて」
「それは・・・・」
白い木箱を床に降ろし、座席に座りながら青年は言った。
ホームには人っ子一人居ない。
さっきまで疎らではあったが人は居た。この青年と会う前には沢山の人がホームで待っていた。
今は、誰も、人の気配さえも・・・しない。
「もうすぐ、出発しますね・・・降りないんですか?」
「えっ・・・」
「予感に忠実になりなさいな・・・的中しては、遅いですよ?」
「・・・・」
扉が閉まり、電車が発進する。
私は酷く後悔している。何故かは分からない。
特にあまり人が居ないだけで、別に何の変わりようも無いのに・・・
私は・・・物凄く後悔をした。
どうしてこんなに不安に駆られるんだろう・・・
降りていれば良かった・・・降りていれば・・・
「落ち着かないのは、後悔しているからですね?」
「えぇ・・・少しね・・・」
「何故です?」
「嫌な・・・予感がするから・・・」
「ほう・・・」
青年は不意に白い木箱に触れる、すると木箱がひとりでに開いた。
木箱の中には、ずいぶんと厚い本が隙間無くぎっしりと置かれている。
青年は木箱の中から本を一冊取り出し、右手にペンを持ちながらその本を開いた。
私はその本が何なのか凄く気になった。
「その本は何が書いてあるの?」
「まだ何も書かれていません。まだ取材は終わってはいませんから」
「へぇ・・・でも取材って何の取材なの?」
「簡単に言うと、都市伝説・・・でしょうかね」
ここで私は少し疑問に思った。
この青年は座りながら何も書いていないページにペンを走らせている。
何故この青年は今ここで本を書いているんだろう・・・
書くことが全部頭に入っているようにスラスラとペンを走らせる。
私は気になりながらも、自分の気を落ち着かせるため座席に座った。
他の車両に乗っている人は何をしているだろう・・・
この異様な空間で・・・私のような考えを廻らせているんだろうか
私は青年に尋ねてみた。
「他の車両に人居たけど・・・何してるのかしらね?」
「さぁ・・・見てきてはいかがですか?私も、少し絵を描きたいもので。」
「絵って・・・なんの?」
「私が描くモノは、あなたも目の当たりにする事が、できますから。」
そう青年は言って、クククと笑う。
私はあまり気にせず、前の車両に向かおうとした時、青年が不意に私を呼び止めた。
私は何だと思いながら青年の方へ再び振り返ると、木箱に手を入れ、何かを探っていた。
「あなたに、これを差し上げましょう」
青年はそう言うと木箱の中から飴玉を取り出し、私に差し出した。
「・・・?ありがとう・・・」
「それを食べるか食べないかはあなた次第です。」
青年の意味有り気な口調に、私は感付いた。
「予感を・・・信じれば良いの?」
「フフフ・・・いってらっしゃい」
私は飴玉をポケットの中に入れ、別の車両へと移ってみた。
するとそこには、女性の老人と眼鏡をかけたサラリーマンが座席に座っていた。
広い車両の中にたった2人・・・それは先ほどの車両でも同じことね・・・
2人は私の顔をチラリと見たが、気には留めなかった。
私は2人にこの状況について尋ねてみた。
「あの・・・お婆さん、この電車・・・どこか可笑しいとは思いませんか?」
「・・・・そうねぇ、確かにいつものよりかは人は少ないわねぇ・・・」
ゆっくりと落ち着いた口調で老人は答えた。
だが、やはり少し挙動不審な態度から、この異様な人の少なさに違和感を覚えているようだ。
もう一方のサラリーマンの男性にも同じような事を尋ねたが、雑誌を見たままで何も言わない。
仕方なく私はもう一つ前の車両に向かう事にした。
この車両には誰も居なかった、だけど何故だろう・・・人の声がする・・・
なんだか呻き声みたいだけど・・・
次の車両からかな・・・
私は次の瞬間足が動かなくなった。
この誰も居ない車両に次の車両から誰かが入ってきた。
両目にハサミが2個突き刺さっていて、口が耳まで裂けている男が・・・
私は声が出なくなった。一瞬でパニック状態に陥り、逃げることさえできなくなった。
男は大量に血を流しながらゆっくりと此方に歩み寄ろうとしたが、そのまま前倒れになって動かなくなった。
私は力無く座り込んだが、まだ頭の中はパニック状態で状況の理解がまるで出来ないで居た。
助けを呼ばなきゃいけないのに、声が出ない。
男は動かなくなったのに、震えがとまらない。
男の側に赤いボロボロの服を着た、口が耳まで裂けた女が私を見下ろしているからだ。
「あっ・・・たっ・・・たっ・・・」
助けてと言えない・・・上手く喋る事ができない・・・
全身が震えてる、冷や汗も出てる。
女は私を見下ろしながらケタケタ笑っている。
目は潰れているらしく、目から血が涙のように出ている。
手には錆び付いた血だらけの鎌を持っていて、今さっきその男の口を鎌で無理矢理引き裂いたようであった。
私は後ろに少しずつ下がりながら、ゆっくりと立ち上がる。
まだ脚が震えて上手く立てない・・・中腰くらいの体勢になった時、ポケットから青年から貰った飴玉が床に落ちた。
私は慌ててそれを拾おうとしたが、拾われてしまった。
女が・・・口裂け女が・・・私の目と鼻の先に居る・・・
声が出ない。汗も出ない。動けない。
震えることさえも出来ない。
完全に止まってしまった。
女は飴玉を拾うと、警戒しながらも口に頬張った。
私から離れ、飴玉の味を堪能している。
その時、私の頭の中であの青年の声が聞こえた。
『走れ』
私の体がスッと軽くなり、すぐさま後ろに振り向き走り出した。
向かうのはあの青年の居た車両。
私は必死の形相で振り向かずに走った。
あのお婆さんとサラリーマンの男性の居る車両まで走ってくると
お婆さんが私に向かって「どうしたの!?」と聞いてくるが
私は無視した。止まれなかった。
止まったらもう二度と走れないと思ったからだ。
そして私はあの青年の居る車両に辿りついた。
息を切らし、床に座り込む私に青年は
「予感は、アテに、なりましたか?」
と聞いてきた。
私は今あった事に付いて話そうとしたが
青年は続けた。
「あなたが出会った女は・・・どのような姿でしたか?絵に色も塗りたいので、服の色や髪の色なども教えてくれますか?」
私は絶句した。
この青年は初めからあの女がこの電車の中に居る事を知っていた・・・
だから何の躊躇いも無くこの電車に乗った・・・
全てはあの女の事を・・・本に書き記す為に・・・・
私は声を荒げて叫んだ。
「どうして・・・どうしてあの女がここに居る事を教えてくれなかったの!!?」
「申し訳ありません。私は、意地悪なもので。」
「どうかしてる・・・」
「ですが、私なりに、警告はしたつもりですよ?」
私は何も言い返せなかった。
あまりに後悔している自分が居たのだから・・・
ここに居ると決めたのは私であって、それで勝手に後悔したのも私。
自分の予感を疑った私のせい・・・
青年は隣の車両へ行く扉を横目で見据えながら呟いた。
「もう、足止めは、できませんねぇ」
「えっ・・・!!」
私は隣の車両を扉の窓から覗いた。
サラリーマンの男性は既に口を耳まで引き裂かれ死んでいた。
そして、あのお婆さんが今まさに錆び付いた鎌で口を裂かれて居る。
私は吐き気がし、もう見ることはできなくなった。
涙も出てきた。
このまま死んでしまうんだろうか。
何故この青年はこんなに落ち着いて居られるのだろう。
青年は扉の窓越しにあの女を確認すると、また本にサラサラと何か描き始めた。
「髪はざんばら髪の黒、服はボロボロの赤、口は裂けている、飴玉も効果有り・・・間違い、ないようだ」
そう言うと青年は不適な笑みを浮かべた。
ペンを動かす速度はどんどん速くなっていっている。
「噂は真、だが・・・まだ書き足りないですね・・・」
青年のペンを動かす手が止まる。
そして数ページの白紙の部分を残し、本を勢い良く閉じた。
「お嬢さん、助かりたいのなら、ある言葉を3回唱えるのです。」
「えっ?・・・ある言葉って・・・何なの?」
「あなたも幼い頃聞いた事があるでしょう、女の子は、そういうの好きそうですし。」
口裂け女の撃退法・・・
口裂け女に向かってポマードと3回唱える
すると口裂け女は逃げ出す・・・・
私は幼い頃友達から聞いたことがある。でも・・・そんなのただの子供の作った噂・・・
たしかに有名だけど、噂なんて所詮噂でしか無いもの・・・
でも・・・
私が考え込むと、青年は私の顔を覗き込み、こう囁いた。
「迷う余裕があるのは構いません。結論が出せないのなら、予感を信じてみませんか?」
「予感・・・」
「唱えれば助かるかも知れないし、助からないかも知れない。その迷いは全て、撃退法其の物が単なる噂であるからです。」
「そう、噂なのよ・・・あんなの全部子供が作り出した噂・・・」
「そうやって悩んでいても、相手は待ってはくれませんよ?・・・いや、もう遅いか」
「ひっ!・・・」
車両の扉が勢い良く開かれる。
隣の車両の二人を殺して、口裂け女が入ってくる。
私達を・・・殺しに・・・
気付けば私は反射的にこう叫んでいた。
「ポ、ポマード!ポマード!ポマード!!」
目を瞑りながら何回叫んだろうか
殺されたくなかったから、死にたくなかったから
私の頭の中は恐怖で埋め尽くされていたからだ。
叫び続けてから何分経ったのだろう、私はそっと目を開けてみた
口裂け女の姿はそこには無かった。
青年はまた座席に座り、本を書いている。
まるで先ほどの事など、何も無かったかのように。
あれは夢?いや、夢なんかじゃない。
でも・・・口裂け女は消えている・・・
私が何か青年に問いかけようとした時、電車の扉が開いた。
青年は白い木箱を背負い、電車から降りて行った。
私にこう囁いて
「無事、本を書き上げる事ができました。有難うございます。」
私はゾッとして、急いで電車から降りた。
電車から降りると同時に扉が閉まり、動き出そうとした時、私は電車の方へと振り向いた。
口裂け女が電車の中から私を見つめ、笑っている。
そして電車は発進した。笑う口裂け女を乗せたまま。
力無くホームに座り込む私に青年はこう言った。
「アレは、いわば噂の塊と言った所でしょうか・・・今や口裂け女を信じる者など誰も居ない。ですが、一度知った者には頭から離れないほどの強い印象が残るんでしょうね」
「私も・・・覚えてた・・・」
「アレが伝説ですよ、伝説は、知る者が全員忘れなければ、消えることはありません。したがって、口裂け女もまた、消えることはありません。」
青年は言い終えると私の前から消えていった。
これは全て現実・・・噂であって噂じゃない・・・
あの後、私はしばらく電車には乗れなくなった。
私の記憶にへばり付く、あの女。
何故あの時笑っていたのだろう・・・
今も私の頭から離れない。忘れたい、早く忘れたい。
そして数日が過ぎ、私はまた電車で通勤する事にした。
何事も無く訪れる日常、私はあの出来事なんてもう頭にほとんど無かった。
今日も仕事が終わった、もう大丈夫。
何の不安も恐怖もない、早く家に帰ろう。
そして私は帰り道、あの女に再び出会う。
血の滴る錆びた鎌を、私に見せ付けて。
ニタッと笑う裂けた口に、私は動けなくなった。
殺られた。
END
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔34帖 若菜 59〕
- (2025-11-28 13:25:20)
-
-
-

- 美術館・展覧会・ギャラリー
- あと3日!
- (2025-11-28 06:57:07)
-
-
-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)
- 岡山道中2024(2)倉敷を歩く1
- (2025-11-28 17:45:35)
-
© Rakuten Group, Inc.