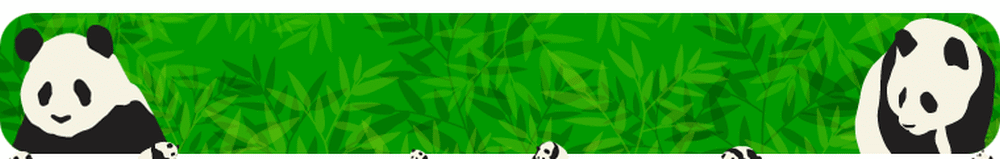ガンダムOO 小説 『ハロ』
凍てつくような雪の日の朝だった。刹那が目覚めると何故か
ハロがいた。何者かが地球の刹那のマンションにハロを送り
込んで来たのだった。刹那はハロを見つめながら頭をかかえ
ていた。ピンポーン。ピンポーン。とインターホンが鳴って、
ドアを開けるとロックオンが断りも無く部屋の中に入って来た。
「ハロ~。会いたかったよ。」
両手を広げてまるで運命の再会かの様にロックオンはハロ
を抱きしめた。
「お前が送りつけて来たのか?」
刹那が聞くと、ロックオンは
「実はアレルヤがやきもちやきでね。ハロばかり可愛がって
いると怒って、目を放した隙に連れ去ってしまったんだよ。」
「やきもちだけでそんな事をするのか?」
「アレルヤはハレルヤに変わると凄くいじわるなんだ。」
ロックオンは微笑んで言った。そして刹那の手をとり、
「ハロが無事で本当に良かった。刹那ありがとう。」
と、刹那の唇に突然口づけをした。
「俺に触れるな。」
刹那は怒った。
「ごめん。嬉しかったんで、つい・・・」
ロックオンは謝ったが、刹那は許さなかった。
「出て行け。」
押し殺した声でうつむきながら、拳を握り締めて言った。
刹那はファーストキスを奪われて、動揺を隠すのに必死
だった。すると、ハロが
「セツナ ナクナ ナクナ ・・・」
と、刹那の足元にすり寄って来た。
刹那はその愛くるしさにほんの少しだけ心が癒されて、
ハロを抱き上げようかとも思ったが、ロックオンのペットに
慰められている自分が恥ずかしいような気がして、困惑した
まま、ただ黙ってハロを見つめているだけだった。
「刹那、本当に悪かった。」
ロックオンがすまなさそうに微笑んで言った。
「悪気はなかったんだ。ほんの1秒唇に触れただけのキス
なんて挨拶がわりのようなものだろ。まさか初めてでもある
まいし・・・そんなに怒らないでくれよ。」
「帰れ!!」
刹那は怒って、ロックオンを突き飛ばした。
「初めてで悪かったな。帰れ!!」
そういったものの刹那は少し頬が赤らむのを感じ、余計に
腹立たしくなった。それを見られる事が恥ずかしくなって
刹那は部屋を飛び出した。
外は雪だった。
昨晩から降り積もった雪は大地を覆い、街を包み込むように
総てを白に変えていた。
刹那はこの汚れた世界が雪によって浄化されるような気が
して立ち止まった。
空から雪の妖精が舞い降りて刹那の汚れた心を清めていく。
刹那は空に顔を向けて、ゆらゆらと舞い降りる雪が肌に溶け
ていくのを感じていた。
刹那は雪になりたいと思った。
汚れの無い純粋な心の持ち主だったら素直になれたかも
知れない。でも、自分は汚れている。
幼い頃、故郷では戦争で多くの人々が死んだ。
親も兄弟も友達も皆、殺されていった。
刹那は命じられるままに人を殺した事を今でも後悔している。
善悪を誰も教えてはくれなかった。
神の名の下に総てが許されると教えられていたのだ。
幼い頃に、汚してしまった心は一生もとに戻らない。
刹那は血に染まる前の自分に戻りたいと思った。
雪のように真っ白な心だった頃に戻りたいと願った。
携帯が鳴った。刹那は携帯に出た。
「もしもし、僕、アレルヤだけど・・・実はハロに時限爆弾が
仕掛けられているんだ。その時限爆弾はある言葉を言うと
タイマーが作動して一分後に爆発する。その言葉は・・・
う、痛い、頭が痛い。ハレルヤ、やめて、うぅ・・・」
「おい、どうしたんだ?大丈夫か?」
「アハハハ・・・・この体は俺様のものだ。ロックオンなんか
死んじまえ。あんな奴、吹っ飛ばされちまえ。ギャハハ・・・」
刹那は携帯を切ると、慌ててマンションに戻ろうと思った。
ロックオンが心配でたまらなく胸が張裂けそうだった。
刹那は走った。昨夜降り積もった雪で、舗道は凍っていて
何度も転んだが刹那は走り続けた。ロックオンのもとへ・・・
彼を死なせてはいけない。
かたくなに心を閉ざしていた刹那に唯一優しくしてくれた。
独りぼっちでいる刹那にいつも声をかけてくれた。
彼の優しさが太陽のように眩しくて、出会った日からずっと
魅かれていた。でも、幼い頃から大人たちに虐待され、
裏切られ、人を信じる事をやめてしまった刹那にとって
彼の好意は眩し過ぎた。素直になれなかった。
太陽のように笑う彼を死なせてはいけない。
だが、マンションに辿り着いた時にはもう、ロックオンの
姿はなかった。刹那は不安に押し潰されそうになった。
するとその時、背後から大きな手で目隠しをされ、
「だ~れだ。」
と、能天気な声で耳元で囁かれた。
「ロックオン?・・・ふざけるな!」
突然の出来事に刹那は驚いて振り返えると、無邪気な
笑顔がそこにあった。
「ロックオン何処に行って・・・」
刹那は涙が溢れそうになった。言葉にならない感情を
押し殺そうと刹那は必死に目を擦った。
「ごめん。まだ怒ってるのか?気になって探してたんだぞ。」
ロックオンは刹那の両肩に手を置いて、優しい眼差しで
刹那の顔を覗き込んだ。
「ロックオン、ハロに時限爆弾が仕掛けられているって
アレルヤから電話があった。ある言葉を言うとタイマーが
作動するって。」
「本当か?ある言葉ってなんだ?」
「分からない。でも、すぐに分解して爆弾を取り外そう。」
刹那はドライバーを持って、ハロを捕まえようとした。
「ハロ、ハロ、コワイ、コワイ、ブンカイ、キライ、キライ・・・」
ハロは部屋中を逃げまわった。
「ハロおいで。怖くなんかないよ。大丈夫だから。」
ロックオンがそう言うとハロはロックオンの胸に跳び込んだ。
「ハロ、ハロ、セツナ、コワイ」
「よしよし、大丈夫だからね。良い子にしてろよ。」
ロックオンはハロの頭を優しく撫でて抱きしめた後、
ハロを押さえつけて、
「刹那、やれっ。」
と言った。
刹那はハロの体を無理やりこじ開けると、小型時限爆弾が
埋め込まれていた。タイマーはまだ作動しておらず、60秒
にセットされたままだった。刹那が幼い頃、周りの大人たち
はよく爆弾を作っていた。自爆テロ用からバスをリモコンで
吹き飛ばすタイプの物まで様々な爆弾を作っていた。
刹那は見よう見まねで覚えた爆弾に関する知識があったので
普通の人より詳しかった。このタイプの時限爆弾は下手に
取り出すとトラップが作動するのでハロから切り離せない。
まずは黄色い線を切って、次に赤か青のどちらかを切るの
だが、失敗すればその場で爆発する仕組みになっている。
刹那には爆弾処理の経験がないので、黄色が安全という
保証も無い。多分大丈夫だろうと思うだけで最初の一本が
トラップだったら、それで終わりだ。刹那はいざとなると
切る勇気がなくて、手が止まってしまった。
一瞬の躊躇の隙にハロがまたジタバタ暴れだした。
「おい!こら!動くなよ。」
ロックオンがハロをぎゅっと押さえつけて言った。
「良い子にしてたら後でご褒美をやるからおとなしくしてろよ。
ハロ、愛してるから。」
すると、ピー!という警告音が鳴り響いた後にカチッと
音がして、タイマーが作動し始めた。
アレルヤが言っていたある言葉とは『愛してる』だったのだ。
もはや躊躇している暇は無かった。刹那は黄色い線を切った。
何も起こらなかった。第一段階クリア。刹那は安堵して溜息
をついた。しかし後2本のうち1本を切らなければならない。
次は2分の1の確率でトラップだ。タイマーは39,38,37・・・
無情に時を刻んでいる。もう一度配線を確認する時間は無い。
刹那は赤か青かどちらにするか迷った。
いっそハロを窓から放り投げれば、自分たちは助かるかも
知れないが、街の人々にケガ人や死人が出てしまう。
一般人を巻き込むわけにはいかない。それに今、ハロを
見捨てたらロックオンが悲しむ。まるで家族のように
可愛がっているのに・・・
ロックオンには家族がいない。昔、刹那の仲間が殺したから。
そのことを知った時のロックオンの顔が忘れられない。殺意
に満ちた瞳で憎しみをぶつけて来た時、彼に殺されたいと
刹那は思った。自分には使命があるから生きているけれど
彼の為なら死ねる。ハロを助けなければならない。
刹那は赤い線を切った。
すると、ピー!という警告音とともにいきなりタイマーが
00に変わり点滅した。トラップにひっかかったのだ。
「危ない!」
ロックオンが叫んで刹那を突き飛ばすように押し倒し、かばう
ように覆いかぶさった。死ぬと思った瞬間、パンッ!とまるで
クラッカーを鳴らした音が聞こえ、刹那たちは死ななかった。
不思議に思って恐る恐る振り返って見ると、時限爆弾から
花火が上がっていた。シューシューと火花を散らして花火は
ハロの頭上で綺麗な花を咲かせていた。また同時にハロから
ポンポンっとハート型の小さなチョコレートが飛び出していた。
「何だ?これ。」
二人は起き上がり、呆れてその情景を見つめていた。
しばらくしてロックオンがハロから飛び出してくるチョコレート
の一つを拾ってこう言った。
「今日はバレンタインデーだったっけ?」
その時、ロックオンの携帯が鳴った。アレルヤからだった。
ロックオンは最初不機嫌そうにアレルヤの話を怒って聞いて
いたが、やがて笑い出した。そして、
「刹那にかわってだってさ。」
と言って携帯を刹那に手渡した。刹那がいぶかしげに耳に
当てると、アレルヤは
「ロックオンへのバレンタインのプレゼントだよ。刹那。君は
きっとチョコレートなんて用意してないと思ったから、代わり
に僕が用意したのさ。じゃ、頑張ってね。」
刹那が何か言おうとするとプチッと携帯は切られてしまった。
「いたずらだったってさ。マジで死ぬかと思ったのにな。」
ロックオンは笑顔でそう言った。
「時限爆弾が爆発すると思った瞬間、とっさにお前を守りたい
と思ったんだ。ハロの事は忘れてたよ。誰よりもハロが好き
だったのに、死を前にして、俺の命よりもハロよりもお前の
ほうが大切だって気付いたんだ。」
ロックオンはまっすぐに刹那を見つめた。
「俺はロックオンの事を・・・」
刹那が自分の思いを伝えなければと口を開いたものの
伝えたい想いがいっぱいありすぎて、真っ赤になって黙って
しまった時、ロックオンは刹那の唇に唇を重ねた。刹那は
驚いて目を見開いたがすぐに目を閉じた。ロックオンの舌が
刹那の舌に絡んでくる。初めての濃厚なキスを刹那は目を
閉じたまま受け入れた。ゆっくりと優しく押し倒され、キスを
しながら服を脱がされていく。首筋から胸に移動する唇に
刹那はくすぐったさを感じた。ピンク色の可愛らしい突起は
舌で転がされてツンッと立った。
「感じやすいんだな。」
ロックオンが意地悪く言った。刹那はカァッと赤くなって、
その場から逃げ出したくなったが、押しのけようとした手を
掴まれて、そのままひっくり返された。いきなり後ろ向きに
されたかと思うと一番恥ずかしい部分にキスされた。
「や、やめろ!」
刹那が抵抗してもロックオンはおかまいなしに舌を這わせ
てくる。舌が入り込む感覚に刹那は眩暈を感じた。
「あっ。ああ~。もう、いやだ。なんでそこばっかり。」
「たっぷりと慣らさなくちゃ。初めてなんだろ?」
「ああああ~」
刹那はイってしまった。ロックオンは刹那の放った白い液体
を指で拭い取り、刹那の中に塗りたくった。たった指一本でも
刹那の中は狭く二本入れるのは難しかった。だがロックオン
はゆっくりと時間をかけて指を二本入れた。刹那はさっき
イったばかりなのにまたイキそうになっていた。ロックオンが
十分に慣らしたのを確認して刹那の中に入ってきた。
「ああああああ~」
刹那は挿入された痛みに喘いだ。自分の身体を引き裂く
ような初めて味わう痛みに刹那は涙を浮かべた。
「痛いか?」
ロックオンが心配そうに刹那を見ていた。ロックオンはまだ
動いていない。刹那を気遣って入れたままじっとしている。
刹那はロックオンの首に手をまわしてしがみついた。
「好きだ。ロックオン。もう、ずっと前から好きだった。」
「知ってたさ。」
ロックオンは刹那に口づけした。舌を絡ませながら刹那は
蕩けるような感覚を味わった。不思議と痛くなくなった。
「動いていい?」
ロックオンが聞くと刹那はコクンとうなずいた。ゆっくりと
気遣うようにロックオンが動く。刹那は声をあげてロックオン
にしがみついていた。やがて動きが激しくなるにつれて
刹那の意識は何処かに飛んでしまった。頭の中が一瞬
真っ白になった時、二人同時に果てた。終わった後、
ロックオンは刹那の身体を優しくティッシュで拭いてくれた。
「良かった。あんまり切れてない。」
ロックオンがぐったりしている刹那に微笑みかけた。刹那は
眠気に勝てずにそのまま眠ってしまった。
刹那が目覚めるとハロがいた。外は雪だった。寝ぼけた頭
でぼんやりと夢だったのかと刹那は思った。闇の中で孤独
に生きてきた刹那に太陽の眩しい光が注ぎ込んだ。
「やっと目が覚めたか。よく寝てたな。」
ロックオンが背後から刹那の顔を覗き込んだ。
太陽はすぐ傍にいた。刹那はロックオンの手を掴み、
太陽に微笑みかけた。
(完)

ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
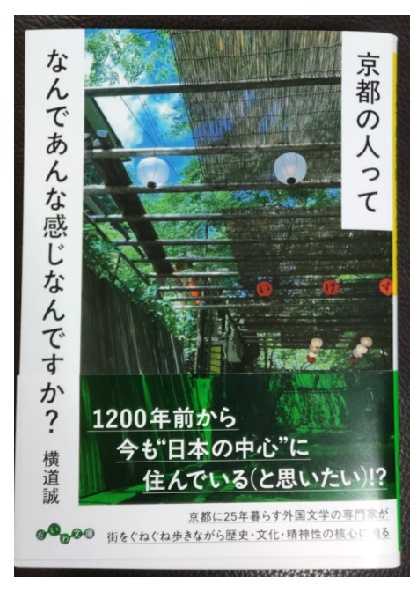
- 最近、読んだ本を教えて!
- タイトルを貫き通して欲しかった
- (2025-12-03 11:30:22)
-
-
-

- 読書
- [年賀状作成ツール etc.]|[楽天…
- (2025-12-04 22:26:18)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 『 REAL 15 』 井上雄彦
- (2025-11-24 15:48:35)
-
© Rakuten Group, Inc.