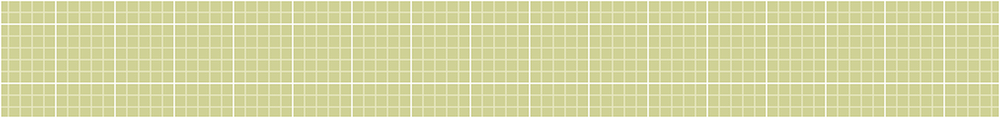2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年09月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
鯖(さば)と寄生虫
旅行の2日目は昼すぎまで玉の湯さんでゆっくりした後、別府に移動。別府と言えばやっぱりまずは「温泉!」という事で温泉番付で何度も「西の横綱」になったという泥湯の明礬温泉「別府温泉保養ランド」へ。さすがに泥湯はユニークで肌ざわりの心地よさがくせになりそうでした。次に別府と言えば「関さば、関あじ、城下カレイ!」という事で、夕食は大分のブランド魚を堪能しようという事になりました。するとT君から「関さば」の刺身は「鯖寿司」のように酢でしめていないけど寄生虫は大丈夫?という質問がありました。私は ・鯖にいる寄生虫・アニサキスは胃液の中で 生きているくらいなので酢では死なない。 (酢でしめても寄生虫リスクは一緒) ・鯖寿司の寄生虫対策は、下処理の仕方にあったはず。と答えて、その日はみんなでおいしく「関さば」に舌鼓をうったのですがそう言えば、(知識のない料理人が出す場合を除いて)全国的に鯖の刺身を食べるという習慣のある地域はあまり聞いたことがないのでちょっと調べてみました。すると、 ・アニサキスはサバの内臓部分に寄生。 サバが死ぬと内蔵から身の方へ移動。 ・活けじめした状態で速やかに内臓を 取り除けばリスクは少なくなる。 ・関さばは「一本釣り漁法」「活けじめ」 なので鮮度が良い。 ・関さばは回遊性が低く豊予海峡に根付く程度が高いため、 南方海域への回遊中にアニサキスが寄生する 危険性は低いと言われている。・・・なるほど、やはり生食する地域にはそれなりのノウハウがあったのですね。納得です。ただ、関さばとは言え、リスクはゼロではないと思いますので、やはり食べる場合は自己責任で、信頼のできるお店で食べるというのが一番だと思います。▼追記ちなみに、伝統的なアニサキスの予防策としては「凍結」があります。 ・鮭はアニサキスのリスクが高いので ルイべにして食べますし、 明太子の材料のスケトウダラの卵巣も 必ず一旦凍結したものを使います。その他に「切り刻む」という方法もあります。 ・昔の人がよく噛んで食べなさい・・・と 言ったのは寄生虫対策の意味もあったと 聞いたことがあります。 ・イカソーメンや鯵のたたきも 寄生虫対策?と思っています。もちろん、一番簡単で確実な予防法は「加熱」です。(^^;;
2008.09.11
コメント(6)
-

由布院 玉の湯
学生時代の友人3人と毎年恒例の旅行に行って来ました。(^^今回は1泊2日だったのでちょっと贅沢して由布院 玉の湯で宿泊。評判のお宿だけに部屋や風呂、食事はさすがに素晴らしかったです。 でも、最初の期待値も大きかっただけに (それなりの値段だったので) 食事やお風呂に特別びっくりする という事はなかったのですが ・部屋の縁側(テラス?)での 友人との楽しい会話。 ・朝起きると窓の外で ざわざわと揺れる雑木林 ・・・まどろみの後の気持ちの良い目覚め。 ・まったりとした時間を味わいながら 食べる朝食。 と、いった上質の空間を 玉の湯さんで体験できた事には一同 大感激でした。その裏には ・客室18室に対して100人以上のスタッフ配置。 ・ほどよい距離感を保った接客。 ・ゆったりと余裕を持った室内。 ・調光、季節の花、雑木林を上手に使ったさりげない演出。 ・チェックインは午後1時から。 朝食は11時までOK。 チェックアウトも午後0時まで・・と余裕の時間配分。などなど、 素敵な時間と空間を 創り出すための さまざまな配慮と工夫がありました。なかなか、ハードの部分で感動するという体験はこの年(今年で50歳です)になってくると最近はあまりないのですがこういった極上の時間を味わうことができるともう一度リピートしてみたい気持ちがふつふつと沸いてきます。機能的なシティーホテルもいいけど、やっぱり旅館がいいなぁ~。つくづく感じた1日でした。
2008.09.09
コメント(10)
全2件 (2件中 1-2件目)
1