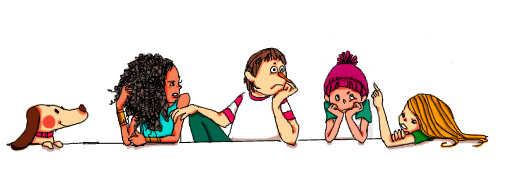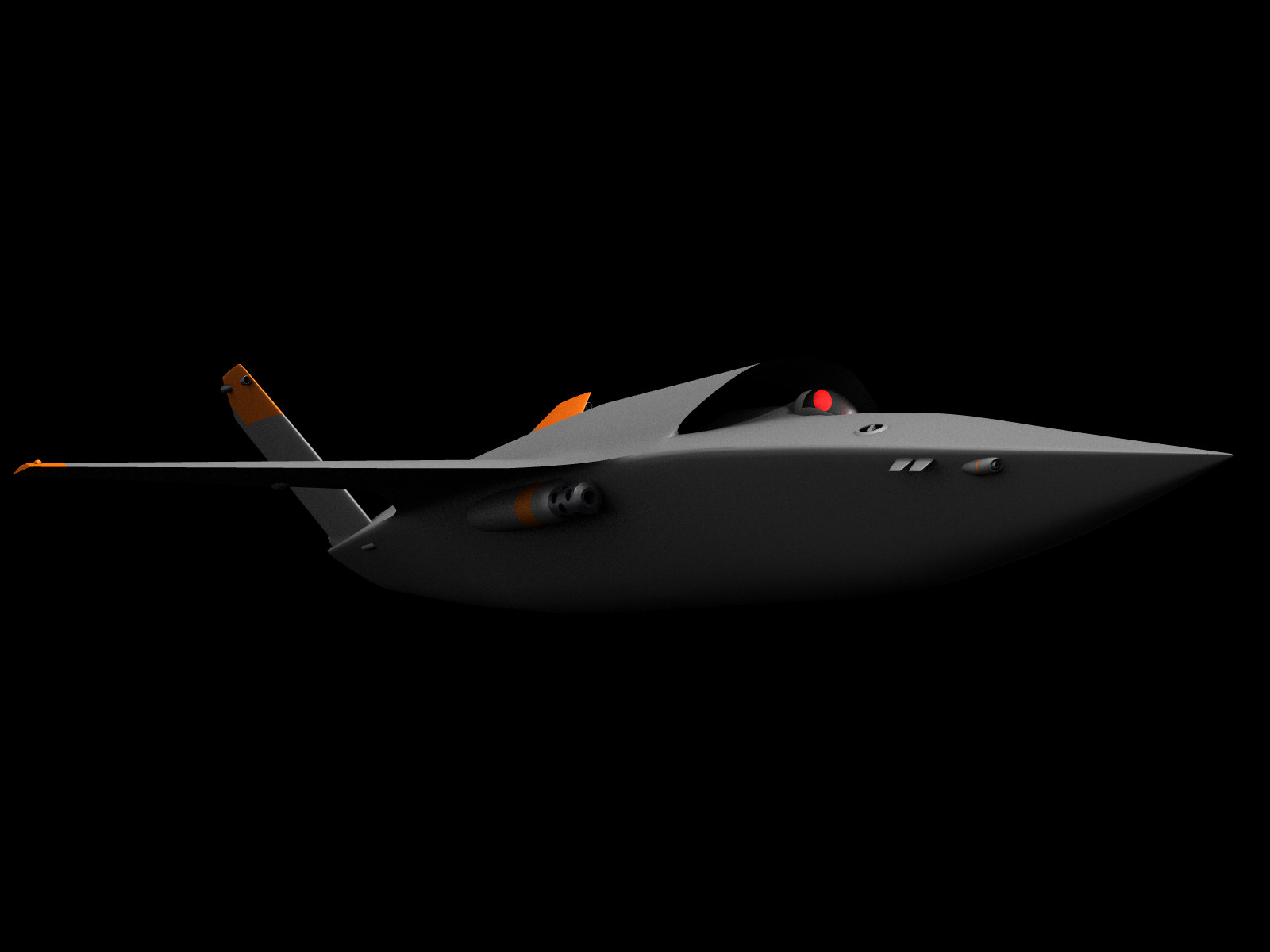2-1肢体不自由の理解
肢体不自由
と聞くと体が動かないイメージを抱く人が多いが、まったく動かない人は少なく
体は動いても体をうまく動かせない状態の人が大半である。
こういった運動障害の他に、姿勢を維持することが困難であったり、体の変形・硬縮、
一部の欠損などがあり、体全体として活動に制限が生じるため、
肢体不自由
と呼ばれる。
肢体不自由
の状態は実に多様であり、支援技術の導入も、それに対する正しい理解が必要である。
・
肢体不自由
は体が動かないというよりも、コントロール出来ない状態であると
考える必要がある。
・
肢体不自由
には様々な原因と症状がある。
【1】 肢体不自由
の実態
(1)肢体不住の人の数
・動くことの障害は、 肢体不自由
と呼ばれる。平成13年度の厚生労働省調査では、
全国の18歳以上の 肢体不自由 者数(在宅)は、1,749,000人、
18歳未満の 肢体不自由 児数(在宅)は、47,700人と推計されている。
全国の18歳以上の 肢体不自由 者数(在宅)は、1,749,000人、
18歳未満の 肢体不自由 児数(在宅)は、47,700人と推計されている。
(2) 肢体不自由
の原因と種類
・
「脳」からの命令は、「脊髄[せきずい]」-「抹消[まっしょう]神経」-「筋肉」と伝わり、
「関節」に運動が起こる。このメカニズムの一部に障害がると 肢体不自由 が生じる。
「関節」に運動が起こる。このメカニズムの一部に障害がると 肢体不自由 が生じる。
a)
脳損傷
脳が損傷を受ける原因には以下のものがある。
・脳血管がつまることで起こる脳梗塞。
・脳血管が破裂するおとで起こる脳出血。
・交通事故などで脳に強い外圧を受けることで起こる脳外傷。
・受胎から生後4週までに何らかの原因で脳に損傷が起こる 脳性まひ
(CP)。
・脳腫瘍。
・脳と脊髄を結ぶ神経の病気である筋萎縮性側索硬化症( ALS
)など。
脳損傷による症状は損傷を受けた部位によって異なる。
・脳の損傷部位と反対側にまひが生じる。
・広範囲に脳が損傷を受けると全身のまひ(四肢まひ)が起こることがある。
・脳に損傷を受けると、言語障害、記憶障害、認知障害などを合併する場合もある。
b)
脊髄損傷
・脊髄が損傷を受ける原因は、交通事故やスポーツなどの外傷、脊髄の炎症など。
・脊髄が途中で分断されると損傷部位以下の運動はできなくなり感覚も消失。
・頚椎など行為になるほど障害が重くなる。
・運動障害以外にも、尿や便の排泄障害や体温調整が難しくなったりする。
・脊髄の損傷は知的障害や認知障害の直接の原因にはならない。
c)
末梢神経の損傷
・末梢神経が損傷を受ける原因は、神経圧迫、外傷、欠陥障害など。
・抹消神経に支配される部位がまひする。
d)
筋肉の病気
・筋肉の病気としてよく知られるのは 筋ジストロフィー
。
・ 筋ジストロフィー
は筋肉が萎縮するため、歩行障害や呼吸障害が起こる。
e)
骨や関節の病気
・骨や関節が病気にかかる原因は骨腫瘍、関節炎、リュウマチなど。
・その部分の腫れや痛みにより関節運動の制限が起こり、その結果、関節が固まったまま動かなくなることがある。
(3) 肢体不自由
の特徴
a)
意思どおりに体が動かない障害
・麻痺:いわゆる体を動かせない状態。
b)
意思に反して体が動く障害( 不随意運動
の発現)
・
振戦:曲げる筋肉と伸ばす筋肉というような拮抗した筋肉が交互に不随意に収縮を繰り返すために生じる
比較的リズミカルな無目的な運動。目標物に近づくにつれて大きくなる振戦は 企図振戦 と呼ばれる。
比較的リズミカルな無目的な運動。目標物に近づくにつれて大きくなる振戦は 企図振戦 と呼ばれる。
・ アテトーゼ
運動:ゆっくとした運動で、捻れたり、曲がったり、伸びたりなどの様々な運動が組み合わされてみられ、
緊張にともなって起こりやすい傾向がある。
緊張にともなって起こりやすい傾向がある。
・痙攣[けいれん]:前進の筋、または筋群の発作性の筋肉収縮。
・パーキンソン症状:振戦と硬直(固縮)と運動緩慢さらに無動の状態。
・失調症状:強調した運度の障害と平衡障害によって、複雑な運動が円滑に行えない状態。
c)
四肢の変形や欠損
・発生時の障害による生まれつきの四肢変形は欠損。
・事故による切断。
d)
姿勢保持の障害
・定頸困難、座位困難などの障害がある。
・ 筋ジストロフィー
は筋肉が萎縮するため、歩行障害や呼吸障害が起こる。
【2】 肢体不自由
への対処
・リハビリテーション:理学療法、作業療法などの機能回復訓練。
・残存機能の活用:上肢が使えないなら下肢でといった具合に残された機能を活用。
・補装具や自助具の活用:手が届かない場合、棒を持つなど、動きを補助する道具の利用。
・支援技術の活用
【3】 肢体不自由
のある人の支援のポイント
・僅かでも随意的に動かせる場所があれば、支援技術の利用に結びつくので、
様々な部位の動きの評価が重要。
様々な部位の動きの評価が重要。
・自分の体の動きに気づいていない人もいるので、動きを評価する場合は鏡やカメラで動きを
フィードバックすることが重要。
フィードバックすることが重要。
・リラックスした状態だと出来る運動が、構えると出来なくなることが多いので、
緊張しない状態を作り出すことが重要。
緊張しない状態を作り出すことが重要。
・姿勢によっては運動の開始が遅れてしまう場合があるので、気長に待つ態度が必要。
© Rakuten Group, Inc.