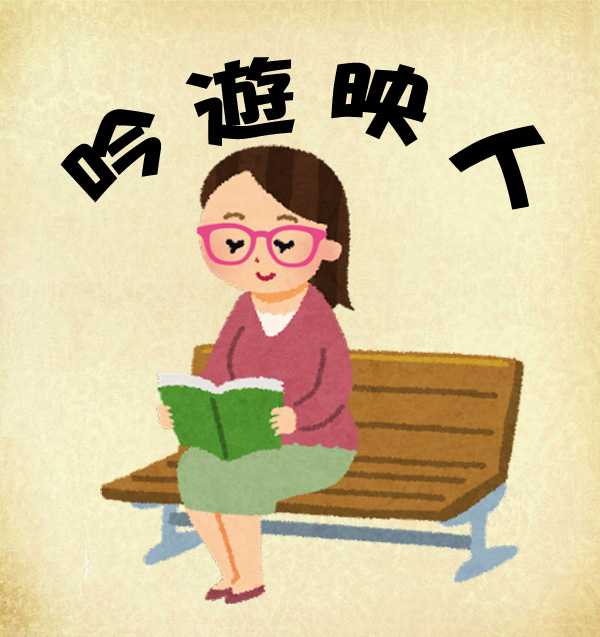PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
その他
(7)映画/アクション
(77)映画/ヒューマン
(97)映画/ホラー
(35)映画/パニック
(25)映画/歴史・伝記
(32)映画/冒険&ファンタジー
(41)映画/ラブ
(47)映画/戦争・史実
(41)映画/SF
(55)映画/青春
(23)映画/アニメ
(24)映画/サスペンス&スリラー
(143)映画/時代劇
(21)映画/西部劇
(4)映画/TVドラマ
(29)映画/コメディ
(15)映画/ミュージカル
(1)映画/ドキュメンタリー
(3)映画/犯罪
(12)映画/バイオレンス
(9)映画/ヒッチコック作品
(8)映画/寅さんの『男はつらいよ』
(8)読書案内
(217)仏レポ
(2)コラム紹介
(120)竜馬とゆく
(9)名歌と遊ぶ
(70)名句と遊ぶ
(288)風天俳句
(5)名文に酔う
(16)ほめ言葉
(3)教え
(42)吟遊映人ア・ラ・カルト
(13)江畔翁を偲ぶ
(12)ガンバレ受験生!
(5)オススメの本
(3)月下書人(小説)
(6)写伝人(写真)
(6)写真
(18)名曲に酔う
(1)名画と遊ぶ
(2)訃報
(11)舞台
(1)神社・寺院・史跡
(12)テーマパーク
(2)カフェ&スイーツ
(21)要約
(23)聖地巡礼
(1)発見
(8)体験談
(1)お気に入り
(1)ヘルス&ビューティー
(3)読書初心者
(5)カテゴリ: 竜馬とゆく
【竜馬とゆく(竜馬がゆく)7】

~龍馬になれなかった男たち~
今回は『竜馬がゆく』のはじまりについて書いてみたい。
司馬遼太郎ファンなら「週刊司馬遼太郎(週刊朝日MOOK)」はご存知であろう。実際は週刊ではないのだが、不定期で刊行されており現在9巻になる。
各巻で司馬小説を扱ういわゆるムック本であるが、もちろん「竜馬がゆく」も取り上げられている。
週刊司馬遼太郎七巻であげられた「竜馬がゆく」のテーマは『龍馬になれなかった男たち』である。何ともシビレるタイトルではないか!竜馬好きのツボを絶妙におさえるあたりは、編集者の非凡なる手練手管をおおいに感じるのだ。
著名な作家が「名作は作家の力だけでは生まれない。そこに名編集者がいてはじめて名作が生まれるのである。」と書いていたがその通りであろう。司馬さんの場合は、名編集者和田宏氏あり、そういうことなのだ。
不定期なムック本が9巻まで続いているのは、ひとえに編集者の力に他ならないと思う。
『僕は学者じゃなく、小説家。この小説は僕の竜馬で、自由な竜馬を書くよ』
司馬さんの中には「主人公に負けない、自由な若き竜馬さんがいた。」という。
ではなぜ竜馬なのかと問われれば、
『坂本竜馬をえらんだのは、日本史が所有している「青春」のなかで、世界のどの民族の前に出しても十分に共感をよぶに足る青春は、坂本竜馬のそれしかない、という気持ちでかいている。』
そう司馬さんは答えた。
ではどうやって『僕の竜馬』を書いたのか。司馬さんは、高知から戻る飛行機の中で、眼下に広がる瀬戸内海の島々を見ながら語ったという。
『たとえば島の歴史や産業など、目に見えるものを丹念に調べていくのが歴史研究家の仕事だとすれば、私のような小説家の仕事は、島と島の間にありますね。いまは何も見えない海底を想像して書くことだと思います。』
ひとつ加えさせていただければ、司馬氏のひと声で日本中の古本屋が資料をかき集めたそうだ。「竜馬がゆく」でも古書や参考文献など、それこそトラック一杯分の資料が集められた。「竜馬がゆく」はその上に書かれているというわけだ。つまり膨大な英知から成る『想像』というわけなのである。
和田宏氏はそれをして司馬氏の「状況分析能力」という。
ところで「竜馬がゆく」のきっかけは何かというとそれがケッサクなのだ。
新聞記者の後輩であった渡辺司郎氏は高知の出身。新たな小説のテーマを考えていた司馬さんに『龍馬を書いてほしいのになあ』とつぶやいた。
それこそが執筆のきっかけというのだ。こういうのを「妙」というのであろう。『竜馬がゆく』はこの妙からはじまったというわけだ。
実に名作というものは、度重なる編集会議からはじまるものだけではないらしい。
そして「妙」の起こりを思った。きっと司馬さんも渡辺司郎さんも和田宏さんも、龍馬になりたかったのだろうなあ。だからみんなの気が妙を起したのだろう。
竜馬好きの多くも龍馬になりたかった。その気が『竜馬がゆく』を不朽の名作に仕立て上げたのだろう。
誰も龍馬になれなかった。龍馬になれなかった男たちは『竜馬』に惜しみない愛を注ぐ。司馬さんの『僕の竜馬』は、我々には『僕たちの竜馬』なのだ。みんな竜馬が大好きなのだ。


~龍馬になれなかった男たち~
今回は『竜馬がゆく』のはじまりについて書いてみたい。
司馬遼太郎ファンなら「週刊司馬遼太郎(週刊朝日MOOK)」はご存知であろう。実際は週刊ではないのだが、不定期で刊行されており現在9巻になる。
各巻で司馬小説を扱ういわゆるムック本であるが、もちろん「竜馬がゆく」も取り上げられている。
週刊司馬遼太郎七巻であげられた「竜馬がゆく」のテーマは『龍馬になれなかった男たち』である。何ともシビレるタイトルではないか!竜馬好きのツボを絶妙におさえるあたりは、編集者の非凡なる手練手管をおおいに感じるのだ。
著名な作家が「名作は作家の力だけでは生まれない。そこに名編集者がいてはじめて名作が生まれるのである。」と書いていたがその通りであろう。司馬さんの場合は、名編集者和田宏氏あり、そういうことなのだ。
不定期なムック本が9巻まで続いているのは、ひとえに編集者の力に他ならないと思う。
『僕は学者じゃなく、小説家。この小説は僕の竜馬で、自由な竜馬を書くよ』
司馬さんの中には「主人公に負けない、自由な若き竜馬さんがいた。」という。
ではなぜ竜馬なのかと問われれば、
『坂本竜馬をえらんだのは、日本史が所有している「青春」のなかで、世界のどの民族の前に出しても十分に共感をよぶに足る青春は、坂本竜馬のそれしかない、という気持ちでかいている。』
そう司馬さんは答えた。
ではどうやって『僕の竜馬』を書いたのか。司馬さんは、高知から戻る飛行機の中で、眼下に広がる瀬戸内海の島々を見ながら語ったという。
『たとえば島の歴史や産業など、目に見えるものを丹念に調べていくのが歴史研究家の仕事だとすれば、私のような小説家の仕事は、島と島の間にありますね。いまは何も見えない海底を想像して書くことだと思います。』
ひとつ加えさせていただければ、司馬氏のひと声で日本中の古本屋が資料をかき集めたそうだ。「竜馬がゆく」でも古書や参考文献など、それこそトラック一杯分の資料が集められた。「竜馬がゆく」はその上に書かれているというわけだ。つまり膨大な英知から成る『想像』というわけなのである。
和田宏氏はそれをして司馬氏の「状況分析能力」という。
ところで「竜馬がゆく」のきっかけは何かというとそれがケッサクなのだ。
新聞記者の後輩であった渡辺司郎氏は高知の出身。新たな小説のテーマを考えていた司馬さんに『龍馬を書いてほしいのになあ』とつぶやいた。
それこそが執筆のきっかけというのだ。こういうのを「妙」というのであろう。『竜馬がゆく』はこの妙からはじまったというわけだ。
実に名作というものは、度重なる編集会議からはじまるものだけではないらしい。
そして「妙」の起こりを思った。きっと司馬さんも渡辺司郎さんも和田宏さんも、龍馬になりたかったのだろうなあ。だからみんなの気が妙を起したのだろう。
竜馬好きの多くも龍馬になりたかった。その気が『竜馬がゆく』を不朽の名作に仕立て上げたのだろう。
誰も龍馬になれなかった。龍馬になれなかった男たちは『竜馬』に惜しみない愛を注ぐ。司馬さんの『僕の竜馬』は、我々には『僕たちの竜馬』なのだ。みんな竜馬が大好きなのだ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[竜馬とゆく] カテゴリの最新記事
-
『竜馬がゆく』より。竜馬とゆく9 2013.08.07
-
『竜馬がゆく』より。竜馬とゆく8 2013.07.23
-
『竜馬がゆく』より。竜馬とゆく6 2013.07.08
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.