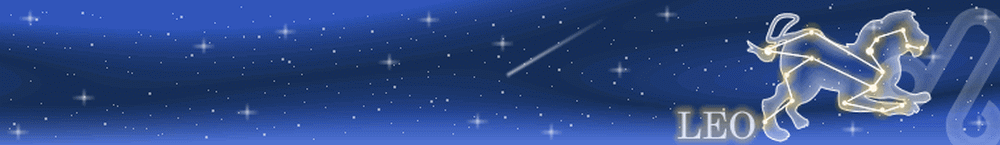2007年に劇場で観た映画
「武士の一分」
この作品を、夫婦の愛情を描いた作品とみるか、封建社会の息の詰まるような下級武士の生活を描いているとみるかは、観た人それぞれに違うだろう。
主役の三村新之丞を演じた木村拓哉だが、失明する以前は現代劇のような調子で演じていた。しかし、失明してからは、それなりに上手く演じていた。
毒味役で失明したなら、当然、労災だろうと思うのは現代に生きているからだ。当時は、お役ご免で路頭に迷うのが普通だったのだろう。結局は殿様の鶴の一声で、禄はそのままということになった。
この映画、脇役陣が主役を見事に盛り立てていた。叔母役の桃井かおり、直接の上司の小林稔侍、敵役の板東美津五郎、道場主の緒方拳らの円熟した演技が、この作品を奥深い物にしている。特に中間に扮した笹野高史の演技が光っていた。彼がこの映画の陰の主役といえる。
庄内弁の「・・・でがんす」という方言が新鮮だった。標準語に直せば、・・・で御座います、というところだろう。江戸の話ではなく、東北の小藩という設定がよかった。日本全国に藩があり、それぞれ武士道を追求していたのだ。
小さいことは言いたくないが、当時の既婚女性は眉を落として、お歯黒をしていた。そこは現代風にしてあるのだろう。リアリティを追求すればよいと言うものでもない。
主人公が食事をして、お茶で茶碗を洗って食卓代わりにしていたお膳にしまっていた。これは箱膳という物だろう。聞いたことはあったが、実際に使っているところを初めて見た。家族の食器を一緒に流しで洗うようになったのは、明治以降のことだろう。この辺りの時代考証はよくできていた。
「蒼き狼」
全てがモンゴルでのロケだけあって、草原や河の美しさが光っていた。モンゴルの陸軍兵士も撮影に協力したという騎馬隊と騎馬隊の戦闘シーンは、砂煙を上げての迫力ある凄いシーンだった。
ストーリーは、父親を殺されたテムジンが、苦労してやがてモンゴルを統一していくという話だ。もう一つ裏に父と子というテーマがある。
このところハリウッド製のCGを使ったシーンばかりを見せつけられているので、実写の凄さは矢に当たって落馬するシーンや馬ごともんどり打って倒れるシーンなど、枚挙にいとまがないくらいだった。
話は面白いのだが、出てくる俳優達が全部日本人だったので、違和感があったのも事実だ。日本人が幾ら同じモンゴロイドだからといっても、やはりモンゴル人とは顔が違う。
反町隆史さんがチンギス・ハーンに扮していたが、歴史の教科書などで見る平べったい顔のチンギス・ハーンとは余りにも違っていた。
これは、先年観た「トロイ」でも感じたことだ。アメリカ人が古代のギリシャ人を演じても、しっくりと来なかった。
その国の歴史映画は、やはりその国の人達によって、その国の言語で作るのが一番良いだろう。
「パイレーツ・オブ・カリビアン -ワールド・エンド-」
第1部に比べると、だんだん画面がリアルになって来ているし、おどけた場面も少なく内容もシリアスだ。
特に冒頭での公開処刑の場面は、子供に見せてもよいのだろうかと疑問に思った。助けが来るのだろうと思っていたが、結局来なかった。この映画はウオルト・ディズニー社が作っているのだが。
大きな渦に巻き込まれながらの海戦シーンは迫力があった。コンピュータ技術の粋を集めたような出来映えだった。これだけ迫力あるシーンが展開されると、演技している俳優陣もそれに負けてはいられない。
幽霊船を見ていて、あの伝説を使っているなと気付いた。西洋に伝わる「フライング・ダッチマン(さまよえるオランダ人)」だ。幽霊船伝説は、海洋小説には必ずと言っていいほど出てくるものだ。
さて、長い映画が終わったと思って直ぐに席を立った人は、重要な部分を見逃してしまう。エンドクレジット(スタッフやキャストの名前などが、延々と続くアレだ)が終わってから、10年後のヒロインとその子供が出てくる。
2人は断崖に佇み、遙か遠い水平線を見つめている。今回の主役達のシリーズは完結したようだが、次はこの少年を主人公にして、新しい物語が始まりそうだ。だから、わざわざエンドクレジットの後に持ってきたのかもしれない。
「夕凪の街 桜の国」
被爆者から見た戦後を、昭和30年初頭と平成19年の2つの時代で描いている。
この映画のヒロインは、田中麗奈と麻生久美子の二人が演じている。この二人が出会うことは決してない。
前半部分は、昭和30年代に「夕凪の街」、つまり広島市に生きた女性の話だった。この女性を演じていたのが、麻生久美子だった。
原爆で、妹を失いながら生き残ってしまった苦しさを見事に演じていた。彼女が口ずさむ「死んだはずだよ、おとみさん、生きていたとは・・・」は、哀愁を帯びていた。その女性は若くして死んでしまうが、被爆者の思いを語っていた。
後半は、平成19年の現在を生きる田中麗奈が、自分のルーツを探す旅で始まる。田中麗奈は、広島とは掛け離れた東京「桜の国」で育った。彼女は、自分の父が広島に行くのを付けて行き、自分と原爆の関係を知る。麻生久美子は、田中麗奈の伯母さんだった。
佐々部監督は、昨年の「出口のない海」とは違った視点で、戦争の惨さを描いている。「夕凪の街 桜の国」は、「出口のない海」に比べると随分地味な映画だが、戦争の被害が世代を超えて続く恐ろしさと悲しさを、十二分に描いていると言える。