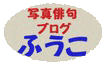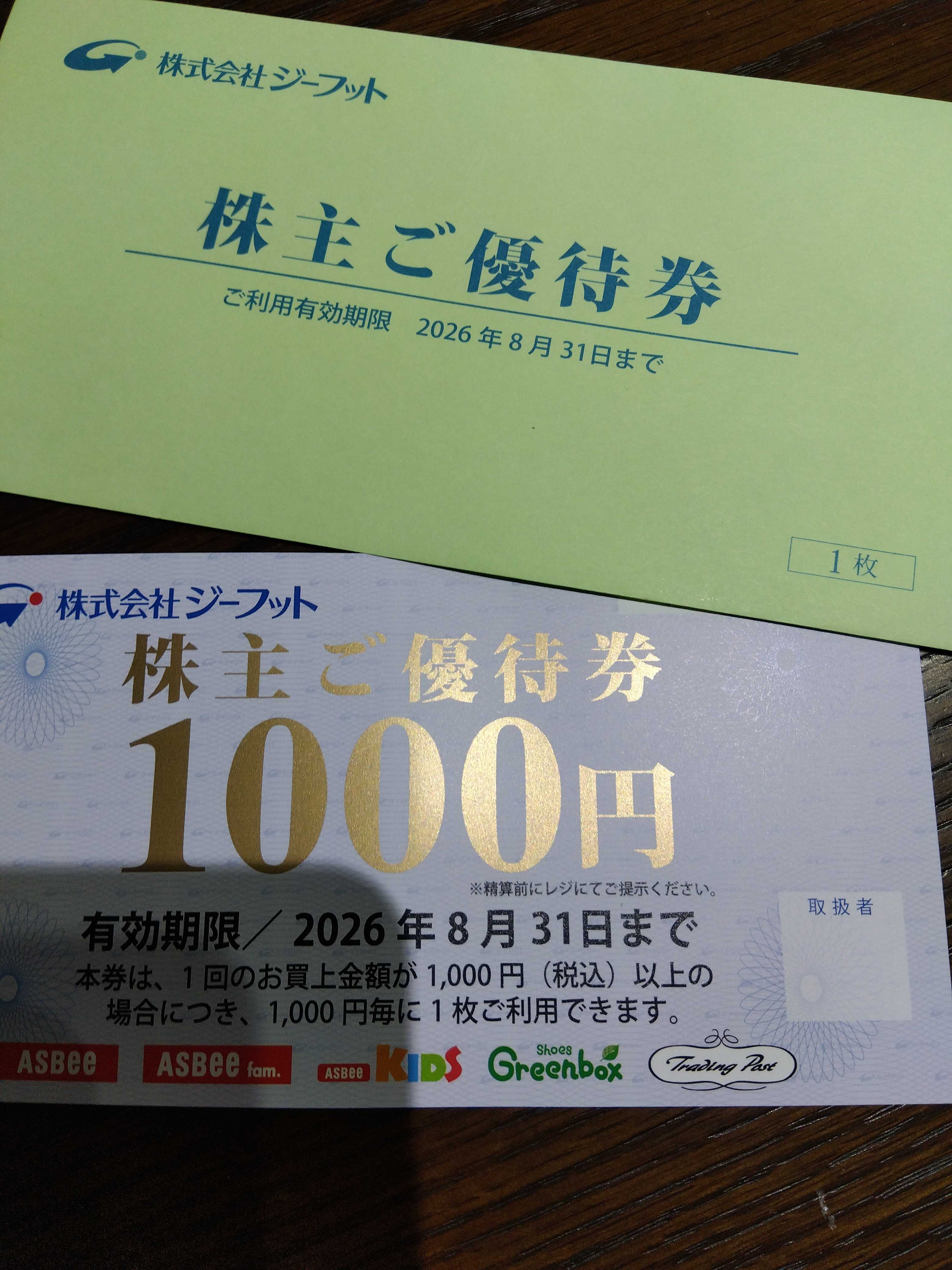2023年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
【自分の弱点や短所に大らかになる】
【自分の弱点や短所に大らかになる】 性格的に、完璧主義な人、あるいはより完璧を求めたがる人は、自分の弱点を 人に知られたくない、と思いがちです。 それよりも、自分の強みを積極的に先に出したほうがいいのですが、自分を守 りたい気持ちが強すぎて、弱点はなるべく知られたくないと思うのです。 子どもでも、よくはずかしがりやのタイプがいます。 はずかしがりやは、自分のみっともない姿や、失敗した自分を人に見られたく ない、という気持ちが強いものです。 それでも、ちょっとだけ勇気を出して人前で話してみれば、失敗してもそれが 周囲から好かれることもあります。 つまり、周囲は自分の弱点をありのままに出してくれたその勇気に、心の拍手 を送りたくなるのです。 その意味でも人間関係では、ありのままの自分を出した方が好かれるのです。 もちろん、わがままで人の気持ちを考えない自分を出すのは、いいことではあ りません。 ありのままとは、自分を飾らないということです。 よくも悪くも飾ってしまうと、表面的に他人との関係がうまくいっても、最後 に残るのは疲れきった自分です。 それでは、今の人生を楽しむこともできません。 自分を出すと、相手が離れていくのが恐いからと思って、ありのままの自分を 隠すエネルギーを使うより、好きなものは好き、嫌いなことはきらい、と言う ことに勇気を出すことにエネルギーを使うべきです。 それが、自分を高めることにもつながっていくでしょう。 もう一つは、自分の弱点に大らかである人ほど、物事を楽天的に考えることに 抵抗を感じません。 完璧主義に考えるタイプの人は、一つの失敗や弱点を大きくとらえがちです。 そのために、つい物事を悲観的に考えたくなるのです。 ところが、ありのままの自分を出すのが苦にならない人は、自分の弱点に寛容 であると同時に、他人に対しても寛容な関係でいられるのです。 自分には、こんな弱点もあるけど強みもあるんだ、という自己認識を持つ人は まわりからの好感度は高いものです。 さらに、いろんなことを楽しむ時間を過ごすこともできます。 弱点だらけの自分でも、それなりに頑張っていこう、と思うことが大切です。 (by ハートリンクス)
2023年01月31日
コメント(0)
-
【いくつになっても、学ぶことを忘れない】
【いくつになっても、学ぶことを忘れない】 明治維新の原動力となった、西郷隆盛や吉田松陰という人たちに、大きな影響 を与えたといわれるのが、佐藤一斎という思想家です。 とくに、『言志四録』という書物は、当時、多くの若者に読まれました。 西郷隆盛の政治信念もこの書物によるものが大きいといわれています。 薩摩藩主の命令に背いて島流しの刑に処せられたとき、この書物を何度も読ん でいます。 吉田松陰は、密航の罪で牢屋に入れられてもこの書物を読み続け、他の囚人た ちに文字を教えたりしています。 佐藤一斎は「知行合一」を重んじています。 これは、学問で得た知識を行動に移さなければ、人格者とはいえない、という ものです。 つまり、人から信頼されるには、学問で人間性を磨き、行動するべきである、 ということです。 西郷隆盛が、明治政府で大臣になり何年かぶりに、鹿児島に帰郷したときの話 です。 途中、大きな荷車が山道に差しかかり、立ち往生していました。 それを見た西郷は、上着を脱いで「私も手伝いましょう」と声をかけ、荷車を 押しました。 荷車は無事、峠を越すことができました。荷主はその人が西郷さんだとわかり とても恐縮したそうです。 「敬天愛人」という言葉を、座右の銘としていた西郷さんらしい行動力です。 佐藤一斎は、「学問をしているなら、人格者でないはずはない」という考えを 持っていました。 ここが西洋の学問と、日本の学問の違いです。 西洋では、自分と外の世界を別々にとらえることを学問としていますが、日本 では、自分と学問、つまり人格と学問を表裏一体のものと考えています。 近代は、日本も西洋学問の影響を受けていますが、それでも老荘思想や仏教の 教えがいまだに、日本人の心の拠りどころになっています。 日本を代表する企業、京セラの創業者、稲盛和夫さんは60歳のときに、得度 をして僧侶になりました。 そのために、街を托鉢する行をすすんでおこないました。 冬の寒空での托鉢は厳しく、足裏はひび割れながらの行だったそうです。 このように、利他の心という仏教の教えを、行動に移しています。 年齢に関係なく何かを学び続ければ、現実と遊離した物事のとらえ方、考え方 はしなくなります。 電子技術中心の時代でも、学ぶことを忘れなければ、自分の人格形成もできる に違いありません。 (by ハートリンクス)
2023年01月30日
コメント(0)
-
【無理をして相手に合わせない】
【無理をして相手に合わせない】 人は、誰もが認められたい、という意識を持っています。 人から認めてもらうことで、自分の存在を実感できるからです。 人をほめることがなぜ必要か、という理由もこれがあるからです。 また、認めてもらいたい、という気持ちが人の期待に応えたいという気持ちを 起こしてくれます。 しかし、これらの思いが強すぎると無理をすることになります。 これは、自分の正直な気持を隠すことになり、自分を傷つけていることと同じ です。 これは恋愛でもよくあることです。 自分の好きな人から、嫌われるのが恐いから、相手が喜ぶなら自分の気持ちに フタをします。 また、親子関係でも同じで、子どもが親の期待に応えたいために、嫌いな習い 事に一生懸命になる、あるいは、親が子どもから嫌われたくないと、子どもの わがままを何でも受け入れてしまう、などです。 相手のためなら、自分が我慢をしてもかまわない、というのも一時的なもので あれば、相手との信頼を得て、お互いがハッピーになることもあるでしょう。 しかし、そうではなく、無理をしてまで相手に合わせるのは、過剰適応をして いることになります。 自分に無理をして相手に合わせているとき、本人は緊張し不安な気持ちです。 ストレスはたまるばかりで、その状態のままだと、生きていることも楽しいと いう気分にはなれません。 本当の意味で、相手に認められたい、と思うなら自分のダメなところ、弱点や 短所をありのままに伝えるなり、うまく表現するのが一番です。 恋愛なら、それで相手から嫌われるなら、それまでの人だったのです。 親子関係、友人関係なら、自分をさらけ出してはじめてつよい絆が生まれるで しょう。 もちろん、自分に無理をさせることも必要なときがあります。 ただ、しっかりとした目的や目標があってこそ行うべきものです。 認めてもらいたい、という気持ちが起きたときは、もっと自分が成長するべき ときが来た、と考えましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月29日
コメント(0)
-
【幸運な人ほど自分の苦労を笑える】
【幸運な人ほど自分の苦労を笑える】 世界の鉄鋼王と呼ばれた、アンドリュー・カーネギーが言いました。 『財産より、もっと尊いのは明るい性格です。 困ったことがあっても、笑いで吹っ飛ばしてしまおう』 どんな人にも、苦労をする時期というものがあります。 そのような苦労をした経験があるからこそ、人並あるいは人並み以上の幸せを 手にしているものです。 その苦労をしているとき、自分より恵まれている人の悪口を言うのか、その人 を目標にしてさらに頑張ろうと思うのかは、人によって違います。 そして、人の悪口を言ったりその思いが強い人は、幸運は逃げていきます。 カーネギーは、自分が大変なときでも明るい気持ちになることが、最も大事な ことだと述べているのです。 明るい気持ちでいると、人をねたんだり悪口を言うことがいかに無駄なことで あるかがわかるのです。 カーネギーは、13歳のとき両親とアメリカに移住しています。 貧しかったので貧民街に住むことになり、カーネギーも綿織物の工場で働きま した。1日12時間、週に6日働いたそうです。 性格は明るく、楽天的で、本を読むのが好きでした。 近くに無料で本を貸してくれる人がいて、時間を見つけて読書したのです。 この当時の体験が、鉄鋼王カーネギーの基礎をつくったともいえます。 本から得た知識はたくさんありますが、それ以上に彼の明るい性格と、不満を 言わないで毎日を生きることの大切さを、読書を通して学んだのです。 人の悪口を言い続けていると、自分のまわりの人のネガティブなところばかり を見るようになります。 そうなると、見る世界の視野にはネガティブなことに敏感になり、自分自身も 欠点だらけの人間だ、と思ってしまうのです。 明るい性格は、他人や自分のいいところもよく見るようになり、また、いいと ころを見るように心がければ、性格も明るくなっていきます。 毎日毎日を、そのような気持ちで過ごしていくことが、幸運を呼ぶことになる という法則です。 (by ハートリンクス)
2023年01月28日
コメント(0)
-
【森羅万象が教えること】
【森羅万象が教えること】 仏教の経典に、『山川草木のすべてに仏性がある』 〈「一切衆生 悉有仏性」(いっさいしゅじょう しつうぶっしょう)〉 という文言があります。 これは森羅万象、自然の営みや雨風、鳥や花を含むすべてのものに仏様の命が 宿っている、という意味です。 この教えに、何人かの優れた僧侶が、 「自分に仏性があることに、気づくことができなかった。 この喜びを多くの人々に伝えよう」 と考え、そのおかげで悩みや病気で苦しむ人たちが、救われてきました。 あるお寺に、父親が中学生ぐらいの息子を連れ、話を聞いてください、と訪ね てきました。 穏やかな感じのお父さんで、その後ろには、うつむいている息子さんが立って います。 和尚さんは、笑顔でどんなことでしょう? と話を聞きました。 内容は、その男の子が登校拒否で家に閉じこもっている。 理由を聞いても言わないので、このままではいけないと思いこのお寺に来た、 というものでした。 和尚さんは、 「そうですか、わたしは教育家ではないからよくわかりませんが、今日はしば らく、庭を眺めてゆっくりしていきなさい」と言いました。 それから、父親と息子は腰をかけて、庭の木々や咲いている花を、互いに言葉 交わすこともなく、座っているだけでした。 二時間ほどすると、 「父親がこれで失礼します。また伺ってもいいでしょうか?」と聞きました。 和尚さんは、「どうぞ、いつでもお出で下さい」とにこやかに答えました。 一ヶ月が過ぎ、その父と息子がやってきました。 同じように、何を話すでもなく二時間ほどいて帰りした。 このことが繰り返されて、半年が過ぎました。 次に親子が訪問したとき、お父さんが菓子折りを手にしていました。 「おかげで、息子が学校に行くようになりました。ありがとうございました」 と言いました。 いきさつはこうでした。親子の家からお寺までは車で一時間かかります。 移動の車中ではほとんど何も話さなかったそうです。 三度目にお寺に来る途中、父親は息子が子どもときの話をしました。 それから、少しずつ息子が話すようになったというのです。 息子が言うのには、お父さんとお寺の庭を眺めている時間が楽しかった、 もう一度、学校に行って勉強したい、ということでした。 和尚さんは、この親子に何も説教などしてはいません。 しかし、親子二人きりでお寺の庭を眺めているうちに、だんだん心が通い合う ような気がしてきた、と息子は父親に話してくれました。 和尚さんは、「山川草木ことごとく仏性あり」の言葉を思い出していました。 人の心に仏性があるように、寺の木々や花にも仏性がある。 親子は自然に触れることで、親子本来の命のつながりと、自分の中にある仏性 に気づくことができたのです。 登校拒否の原因は分かりませんが、それも自分の仏性に気づくための出来事で あったのかもしれません。 悩みがあり、弱気になることがあっても、自然の一部から答えを見つけること もできるのです。 (by ハートリンクス)
2023年01月27日
コメント(0)
-
【心の回復力をつける】
【心の回復力をつける】 優秀なビジネスマンでも、心が一度折れてしまうと、なかなか立ち直れないと いうケースがあります。 この傾向はどの国でも同じで、とくに近年は技術系の分野で働く人にも、心の 不調を訴えることもあります。 その心の問題を解決するために、グーグル社では社員がいつでも自由にマイン ドフルネスができるように、「瞑想ルーム」をつくりました。 その成果は顕著で、考えがまとまらないとき、壁に突き当たって抜けだせない などのときにリセットできる人が増えたそうです。 職場には、いろいろな問題があります。 ストレスといっても、小さな要因が複雑に影響し合っていることが多く、本人 が気づかないうちに、心にダメージを受けていることもあります。 気がついたら、仕事を休まなければならなくなっていた、というケースもあり ます。 このときに重要なのが、心の回復力です。 体の筋肉は鍛えれば強くなり、休養をすれば回復しますが、心は違います。 心は鍛えて、ハガネのように強くなるものではないからです。 心は、弾力性、柔軟性が強さのバロメーターです。 弾力性や柔軟性とは、考え方であり思考の仕方です。 たとえば、経済的に貧しく病気がちな人は、成功できないかというとそうでは ありません。 生活が困窮していて、病弱でも成功者になることはできます。 そのカギを握るのが、心の回復力です。 レジリエンスともいいますが、悩みや問題に直面したときでも、適応できる力 が心の回復力です。 その方法としてマインドフルネスの効果は実証されています。 現代心理学でも、この心の回復力を高めるには、どんな方法があるか研究され ていますが、その中の一つが「感謝すること」です。 感謝とは感情です。 今まで気づかなかったことでも、何かに恵まれていることがわかったときは、 「本当にありがたい」、という感情が生まれます。 これが感謝です。 感謝の感情がなぜ、心の回復力に必要であるかといいますと、まず不安や怒り のような悪感情を中和してくれるからです。 さらに、幸福感を高めてくれます。 次に、血圧が適正になり、免疫力が戻り、体が健康になります。 そして、利他の心、他者のことを思いやる寛容さが生まれるのです。 マインドフルネスを続けていくと、これらのことが少しずつ実感できるように なります。 どんな環境にある人も、心の回復力を高めることができます。 そのためにも、自分の心と向き合う時間をつくってみましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月26日
コメント(0)
-
【自分の生き方を貫く】
【自分の生き方を貫く】 アップル創業者の一人、スティーブ・ジョブズが生前、スタンフォード大学で スピーチをしました。 『人生の時間は限られています。 他人の考えに飲み込まれて、自分を忘れてはいけません。 自分の心と直感に素直に生きることが重要です』 人の意見に左右されるような生き方ではなく、自分の考えをしっかりと持った 生き方をしてください、というメッセージです。 つまり、「自己という個性を持つ、自分にしかできない生き方を求めなさい」 ということでもあると思います。 人間ですから、迷ったり悩んだりすることは当然のことですが、それでも自分 にしかできない生き方をするには、自分の心に素直になることが大切です。 ただ、自分の生き方を貫くとは、「自分が、自分が」という自分第一、自己中心 で考えることではありません。 ジョブズが若い頃、心の拠りどころとしていた禅の曹洞宗の開祖・道元の教え の中に「他人に頼らずに生きなさい」というのがあります。 現実に、他人の意見や考え方に影響を受けることもあります。 それが迷いになり、自分の考えは正しいのだろうかという不安を感じることも あるでしょう。 しかし、自分が人生の主人公である、という思いがあれば、自分らしい生き方 ができるのです。 他人に頼らずに生きるとは、人の協力を求めてはいけないということではなく、 人に依存してはいけない、ということです。 人やモノに依存することが当たり前になると、問題が起き失敗したときの責任 は自分にはない、と考えてしまいます。 しかし、自分が主人公だという考えが軸にあれば、責任はすべて自分にある、 と反省し、そこから新しい次のステップに行こうと思います。 自分の生き方を貫くとは、自分の人生に責任を持つことであり、自分を大切に することでもあるのです。 (by ハートリンクス)
2023年01月25日
コメント(0)
-
【自分の能力の、いかし方】
【自分の能力の、いかし方】 人には自分では気づかない能力が隠されていることがあります。 ただ好きなだけで、たいしたことはないと思っていても、他からすると優れた 技術に見えることがあるのです。 江戸時代の話です。町の路地裏に長屋がありました。 長屋の行き止まりの家に、貧乏な大工が住んでいました。 腕はいいのですが酒が好きで、自分が気に入った仕事しかせず、稼ぎも少なく 家賃は溜まっていくばかりです。 家主は、他にもいくつか長屋を貸していて、家賃を支払えない人には厳しい取 り立てもしないという人格者でした。 ただ、この大工には何とか仕事をさせたい、と考えあることを思いつきます。 次の日、家主が大工の家を訪れました。大工は相変わらず酒を飲んでいます。 「何しにきたんです? 家賃の催促ですか?」 「いや、今日は違う。お前に相談があって来たんだ」 「相談?」 「お前は、もともと大工の腕はいい。今のままでは宝の持ち腐れだ。 これからは、私が毎日お前に酒を一本ずつ飲ませてやる。 それに、家賃もまけてやる。そのかわり、私の言うことを聞きなさい」 家主は言いました。 「夕方酒を飲ませるから、朝起きたら道具をかついで、長屋中を一軒一軒訪ね て、台所の流しが壊れていないか、戸がガタガタしていないか、屋根から雨 が漏れていないかを聞いて、悪いところがあったら修繕してくれ。 ただし、その手間賃はもらってはダメだ。それは私が払ってやるから」 「そんなことは簡単です。さっそくやりましょう」 次の日から、大工は道具箱をかつぎ、長屋をまわって修理をやり始めます。 長屋の住民たちは、とても喜んでくれました。 しかも、タダでは申し訳ない、と言って気の毒がり野菜や魚、それに昼の食事 まで出してくれ、しばらくすると家主が払ってくれる手間賃が残るようになり ました。 そして、大工の評判は他の町にも広がっていき、とうとう自分だけでは仕事を こなしきれなくなり、弟子を何人も抱えるようになりました。 家主の計画は想像以上の結果をもたらし、大工は自分の家を建てるまでに成功 し、家主の持つ長屋も住みやすいという評判が広がり、長屋を増やしました。 大工と家主の両方が豊かになれたのは、家主が大工の能力をいかそう、と考え たからです。 大工は、それをきっかけにして自分の能力を発揮することができ、さらに自分 の仕事が人のために役立ち、喜んでもらえることが嬉しかったのです。 これは、家主の大工への利他の心から始まり、大工自身も人のためになる仕事 の喜びを知る、という良い連鎖がかみ合った事例です。 どんな人にも、何かの能力は必ずあるはずです。 その能力は、善用されてはじめていかされ、その人の人生をよい方向に導いて くれます。 周囲から喜んでもらうことが、生き方を変える力にもなるのです。 (by ハートリンクス)
2023年01月24日
コメント(0)
-
【人生を左右する感情ホルモンの力】
【人生を左右する感情ホルモンの力】 これからは、いかに健康で長生きするか、の時代です。 健康寿命が長いほど、幸福感を味わう時間も長くなります。 認知症にならないためには、生活習慣病を予防すると同時に、心の健康にも気 をつけることが大切です。 たとえば、認知症を防止するには、次のような考え方をしないほうがよい、と いわれています。 それは、消極的、閉鎖的、短気、頑固、理屈っぽい、完全主義というものです。 これは、考え方というより感情の問題ともいえます。 人の体に肌があるように、いつまでも若々しくありたいと願い、手足顔など肌 の手入れをします。 感情とは、心の肌です。つまり、その感情にも手入れは必要です。 感情の手入れとは、消極的、閉鎖的、短気、頑固、理屈っぽい、完全主義、の 逆の考えをするように習慣づけることです。 認知症の専門医の方が講演会でこんな話をされました。 ある、ご夫婦の会話です。 十五夜の月の夜です。 「お父さーん! 月がとってもきれいよ、早くきてみたらどう?」 「そんなことたり前。十五夜の月は丸いと決まっているよ」 梅の花が咲く季節です。 「いい匂いがすると思ったら、お父さん、梅が咲いていますよ」 「1月も末ごろになれば、梅は咲くんだ」 相手の言葉に共感しない、自然の不思議な営みに感動しない、常に理屈で物事 を考えていると、感謝や感動や感激することがなくなり、心も硬直化する。 これが、専門医の見解です。 考え方に柔軟さがなくなると、小さなことにすぐイライラして、不安になり、 この感情が、脳からアドレナリンというホルモンが分泌されます。 アドレナリンが増えると、もともとサラサラ流れていた血液がドロドロになり 血圧が上昇します。 それでも、その状態を中和してくれるのが、セロトニンというホルモンです。 セロトニンは、喜びや感謝や感動という感情を感知すると分泌されます。 心身の健康には、体と心と感情が互いにうまく関連し合うことが必要です。 このことを見つめ直し、健康寿命を長く維持しましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月23日
コメント(0)
-
【グチの効能】
【グチの効能】 人と会話をしていて、グチばかり聞かされていると、その人と話すのも苦痛に に感じることがあります。 グチは、他人の悪口や不満といった内容がほとんどで、気持ちが明るくなるこ ともありません。 しかし、少しのグチなら、それなりの気分転換になりガス抜き効果も期待でき ます。 ある新婚夫婦がいました。職場結婚です。 週末の夕食のとき、ご主人がこう言いました。 「得意先の〇〇課長には、困ったもんだ。自分の都合ばかり押しつけて ホントに苦労するよ。どうにかならないかな~」 聞いている奥さんは、 「そうそう、〇〇課長さん、昔からそうだったのよね~」 同じ会社にいたので、事情もよく分かってくれています。 グチの対象になった課長さんはかわいそうですが、このときの会話でご主人も ストレスが発散できてスッキリしました。 奥さんも、ご主人の仕事の大変さがわかりお互いの気持ちも、つながりが深く なりました。 このように、グチも限定的で聞いてくれる相手も受け入れてくれる範囲なら、 効果はあります。 すべての人がこのような条件ではありませんが、グチも発散の仕方しだいで、 心のリフレッシュにもなります。 感情の波は誰にもありますが、その波も激しい波になると心の負担になって、 健康にも影響を及ぼします。 とくに、怒りや恐怖、悲しみの感情は心を急激に乱します。 「怒り」「恐怖」「悲しみ」という文字には、「心」の文字が含まれています。 また、「恨む」「憎む」「憤る」という文字にも「心へん」が含まれています。 これら、心を乱す感情を日常的に持っていると、心身は不調となります。 適度に発散してリセットできる方法を知っていると、人生の効率はグンとよく なります。 グチを言う相手がいなくても、音楽や芸術、自然界と親しむ時間が心を癒して くれるものです。 音楽や芸術の分野は、右脳によい刺激を与えてくれます。 仕事では、多くは論理的な考えになりがちで、感情の乱れの原因になります。 これは、左脳を酷使している状態で、バランスをとる意味でも休息をとる際は 右脳の働きをいかすことが大切です。 グチの効能と同じように、感情と心のバランスをしっかりとりましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月22日
コメント(0)
-
【人が変わることを望む人ほど、自分を変えない】
【人が変わることを望む人ほど、自分を変えない】 自分の考えは正しいのに、相手が分かってくれない。 だから腹が立ってしょうがない。 この構図が対人関係の悩みを象徴するものです。 しかし、よく考えてみると相手もこちらに対して、同じように思っていること がほとんどです。 こういう場合、相手と自分の立場の違い、力関係によってどちらかが表面上は 事をおさめることが多いものです。 しかし、根本的に解決はせず、片方はストレスとして残ってしまいます。 そして、どちらがよい悪いという判断を下すこともできません。 本来、人にはその人の生き方というものがあり、それが一番だと思っているの ですから、自分の考えを相手に押しつけるのは無理なことなのです。 さらに、自分がそのことで悩むように、相手も悩んでいるのも事実です。 解決法は、自分が今までとは違う、新たな考え方をすることです。 「今までとは違う考え方をしたほうがいいですよ」、と言うと中には自分が負 けたように感じる人がいます。 「だから、私は変わらない、相手が変わるべき」、というタイプです。 それではいつまでたっても、人間的成長は期待できないでしょう。 今までの自分とは違う考えができたとき、それが成長したことになります。 禅の言葉に「我逢人」(がほうじん)というのがあります。 『我、人と逢うなり』と読みます。 この世は人と人で成り立っています。 つまり、「人は人と何らかの関わり合わなければ、生きていけない」のです。 自分は正しいのに相手がわかってくれない、といつも悩みを抱えていては、人 との出逢いを楽しむこともできないでしょう。 人との出逢いがあるから、心が通じ合い、相手を思いやることの喜びを感じる こともできます。 自分を変えることは、結局は自分が人間的に成長することにもなるのです。 (by ハートリンクス)
2023年01月21日
コメント(0)
-
【ツイてる人のクセ】
【ツイてる人のクセ】 落ちているゴミに気づいたとき、ゴミを拾う人ほどゴミは捨てない、という 法則があります。 ゴミは、必ずゴミ箱に入れる。これがマナーです。 中には、公共の場所でも平気でゴミを捨てる人がいますが、それは自分の運を 捨てているようなものです。 トイレを使ったら、使う前よりもキレイにして出ることを社則にしている企業 があります。もちろんこのような企業は繁栄しています。 個人も企業も、社会的なルールやマナーをきちんと守るという精神があれば、 周囲から信頼を得ることになるのです。 経営コンサルタントの船井幸雄さんが、社会人としてよい習慣とはどんなもの かについて、「がんばりグセ」と「思いやりグセ」だと述べています。 とくに、「思いやりグセ」は、人間性を高める習慣としてとくに重要である、と しています。 ゴミを捨てないというマナーも、社会への思いやりがあれば、当然守るべき事 になります。 ところが、自分は思いやりがあるほうだ、と思っていてもつい口に出している よくない言葉、「人に嫌われる発言十か条」というのがあるそうです。 1、あなたの考えには反対だ。 2、あなたが信じているあの人は嫌いだ。 3、そんなことは誰にもできる 4、そのことなら、私のほうがよく知っている 5、あなたの失敗の理由はこうだ 6、私はこのことについては詳しいのだ 7、あなたは、このように約束したではないか 8、私にやらせてみなさい 9、私も昔はあなたのように考えたものだ 10、それはあなたのひがみだよ 人から好かれる、あるいは信頼を得るにはこの十か条の反対のことを習慣にす ればよい、ということになります。 ツイてる人生とは、他者との関係が土台になってつくられていきます。 いい人とのいい出会いがなければ、ツイている人生も幸運な人生も送ること はできません。 「他を思いやる心」は人間関係を乗り切る万能薬です。 ツイてる人生を送るためにも、思いやりグセを身につけましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月20日
コメント(0)
-
【ストレスに敏感にならないために】
【ストレスに敏感にならないために】 ストレスに敏感な人ほど、ストレスを溜める傾向があるようです。 つまり、いつもストレスがある人、あるいはそう思っている人は、ストレスに 敏感に反応しています。 一般的に、まじめ過ぎるタイプの人は、他の人が何も感じない出来事でもスト レスとして感じるものです。 まじめであることは、とても素晴らしいことですが、正義感の強さから自分に 対してつい厳しい気持ちになるのです。 ストレスに敏感な人の考え方には、ある特徴が見られます。 1、自分にとってイヤなことがあったとき、それを大きくとらえてしまって、 よいことをあまり見ようとしないところがあります。 むかし失敗したことはしっかり覚えているのに、成功したことはあまり覚え ていません。 2、白か黒か、ゼロか完全か、物事を完全主義的に考えたがります。 たとえば、家の掃除をしていて7割ぐらいが済んでいたのに、急用があり出 かけることになったときも、ゼロだと思ったりします。 仕事についても同じように、途中までできていても全部を終えないとゼロと 思ってしまいます。 このように、ストレスというのは受け取り方ひとつで、心にダメージを与える ものなのです。 ところが、ストレスとうまくつき合っている人は、これらのような受け取り方 はしていません。 イヤなことがあっても、 「こんなこともあるものだ、あまり気にしないでおこう」ととらえます。 さらに、失敗経験も記憶しながら、成功体験もきちんと覚えているのです。 また、仕事など中途半端に終わってしまうことがあっても、 「それはそれで仕方ないことだ、途中まではできたからそれでいい」、という 考えができます。 ストレスを感じることはあっても、溜めないようになるには、ストレスとの 距離を置こう、と考えることも必要です。 何かイヤなことがあったそのとき、「あ、イヤだな」と感じるものです。 そのままだと、イヤだという感情がストレスに直結します。 しかし、イヤなことがあって、「あ、イヤだな」と感じたら、一回深呼吸して その感情から離れてみるのです。 ちょうど、道を歩いていたら小さな石ころあって、それを避けて通るような 気持ちです。 イヤな感情も、一つの石ころだと思えば、気持ちはグンと変わるはずです。 生きている以上、ストレスはありますが、過敏に反応する必要はないのです。 (by ハートリンクス)
2023年01月19日
コメント(0)
-
【不満の中に成長のヒントがある】
【不満の中に成長のヒントがある】 人によって、不満の内容はいろいろです。 今生きている場所や、いる環境への不満、あるいは人への不満もあります。 それらの不満がすべてでなくても、ある程度解消されないとストレスに変わり ます。 ただ、外的要因への不満なら、自分の力でその場所から移ることは可能です。 また、人に対する不満でも、相手がこちらに気分を害するようなことをする、 また、そんな言葉を言ってくるなら、自分から距離を置けばどうにかなるもの です。 それ以上なら、ハラスメントの問題になりますから対処法も違ってきます。 いちばんは、相手が自分にして欲しいことをしてくれない不満です。 この不満が、なによりストレスになりやすいようです。 もし、このことで今悩んでいる人がいるとします。 一つの打開策として、自分にして欲しいことのレベルを正しいものにすること をおすすめします。 「自分のわがままを求めているのではないか」、と考え、求めていることの 7割ぐらいまで下げてみたら、OKとしよう、と思ってみるのです。 とりあえず、この目線で見直すと自分の不満というものにも、客観的な気持ち になれるかもしれません。 また、不満とは満たされていないことへの、反動の感情です。 私の願いは満たされなければならない、という考えを軸に持つ人ほど、不満に に対して敏感になります。 じつは、不満というものにも、そこに何かを学び、人間的に成長するヒントが あるのです。 それは、「自分は相手に求めてはいるが、逆に、相手のして欲しいことに自分は きちんと応えているか」、と考えることです。 相手と自分が、互いにして欲しいことはどんなことだろう? と思いやる心が あれば、不満という感情は生まれないでしょう。 その理由は、お互いが『利他の心』を持っているからです。 自分が相手にして欲しいことより、相手が自分にして欲しいことは何か。 これを考えてあげること、これが利他の心です。 生まれたばかりの赤ちゃんが泣くと、母親は子どもは何をして欲しいのか、と 思います。 このとき母親は、ただ子どものことだけを思いやっています。 利他の心とは、条件なしの思いやりの心のことです。 この気持ちになれるなら、不満というストレスはなくなるに違いありません。 (by ハートリンクス)
2023年01月18日
コメント(0)
-
【自分の感情を、意識的によくしたいとき】
【自分の感情を、意識的によくしたいとき】 フランスの哲学者、アランが「幸福論」という著書で、こう述べています。 『悲観主義は気分に属し、楽観主義は意志に属する』 気分とは感情のことです。 意志とは、思考、意識、理性のことです。 気分や感情は、理屈抜きで生じます。 しかし、怒りの感情が生じたら、人によっては理性を意識的にはたらかせて、 「怒ってはいけない、冷静になろう」と思うことができます。 一般的には、このような人を「あの人は、大人ですね」と評価します。 アランが言いたいのは、 「たいていの人は何か不愉快なことがあると、怒ったりするものだ。 あるいは、落ち込こんで相手を憎んだりする。 これは気分や感情の影響を受けやすい性格で、どちらかというと、意志が 強い人とはいえない』 ということです。このような人間の特質から、 『悲観主義は気分に属し、楽観主義は意志に属する』と唱えました。 問題は、人によっては他の人と同じように不愉快なことがあっても、感情的に ならずに、いつも冷静に振る舞う人もいる。 そんな人は、なぜそうできるのか。あるいは、生まれつきそういう性格なのか です。 アランは、哲学者として「人には自分の意思で、感情を制御する力がある」 と考えたのです。 職場に、相性の悪い同僚がいたとします。 そんなとき、嫌いだから敵対心むき出しで仕事をしても、いい仕事はできない ものです。 「私はあの人が嫌いだから、私は不愉快だ」と思っているのは、気分の世界で 争っているのと同じです。 それより、相手に不愉快な感情を持つことはやめよう、気にしないでおこう、 と自分を意識的に、気分の世界から遠ざけることは賢明な対処法です。 その対処法を習慣になるように心がければ、しだいに物事を楽観的にとらえる ようにもなれるでしょう。 「あの人にも、どこかいいところがあるのかもしれない。 今の私には、それは分からないから、しばらく心から解き放とう」 という気持ちになる、これが楽観的なとらえ方です。 楽観主義とは、自分がラクになるように考える、という意味ではありません。 物事の展開がよくなるように考えることであり、自分も相手も傷つけないよう うに考えるのが、楽観主義ということです。 自分ときちんと向き合うための悲観主義も、ときによっては必要です。 しかし、そこで止まったままでは成長は難しいものになります。 感情に支配されず、物事を多方面からとらえるためにも、どうすればよくなる のか、という意識を持ち続けましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月17日
コメント(0)
-
【人生の楽しみ方】
【人生の楽しみ方】 「人生は楽しいものだ」と思っている人は、この社会にはたくさんいるに違い ありません。 人生が楽しい、生きていることが楽しい、つまり、幸せを感じている、という ことです。 人の幸せには、三つの種類があるという説があります。 一つは、健康であること 次は、人とのつながりがあり、そこに愛があること。 最後に、お金や成功があること。 もちろん、三つのすべてが揃っていなくても、幸せを感じる方もいらっしゃる と思います。 ただ、いちばん大切なのは、この三つに関係なく環境がどうであれ、今、生き ていることが楽しい、と思うことは誰でもできるということです。 「人生は楽しい」と思っている人は、理屈抜きで「人生を楽しもう」と考えて います。 これが、人生を楽しむコツです。 たとえば、「仕事をするために生きている」、と考えるなら、つまらない人生に なってしまうでしょう。 しかし、「生きていくために仕事をする」と思えば、どうすれば仕事を楽しむ ことができるだろうか、と考えそこに工夫が生まれます。 たとえば、嫌いな仕事を仕方なくやっているとします。 嫌いなので、現実から逃げたくなり、そのためにお酒や賭け事にのめり込む人 もいます。 いっぽう、嫌いな仕事の中にも自分の能力を活かせることがあるのでは、と考 えそれを見つけて、仕事自体が楽しくなった人もいるはずです。 聖路加病院の理事長を務められた、日野原重明さんが尊敬していたとされる、 ウイリアム・オスラーというカナダの医学者の言葉に、次のようなものがあり ます。 『成功への第一歩は、 どんな職業であろうとも、 その仕事に、興味を持つことです』 ウイリアム・オスラーは、興味というのは向こうからやってくるものではなく 自分の方から、何か興味をそそられるものはないだろうか、と主体的に自分の 心を向かわせることも大切ではないか、と問いかけているようです。 人生の楽しみ方とは、どうすれば楽しくなるか、という心の積極性を持つこと から始まるのではないでしょうか。 (by ハートリンクス)
2023年01月16日
コメント(0)
-
【本当の後悔はポジティブなもの】
【本当の後悔はポジティブなもの】 『後悔、先にたたず』、という言葉があります。 あとで、悔やまないように、精一杯やるべきことをしておく、という箴言で よく聞く言葉です。 やれる限りのことをすれば、結果はどうであっても後悔しない、という意味も あります。 それでも、人は「もっとやっておけばよかった」という言葉を口にします。 ただ、このように思うことで、自分を慰めることにもなります。 中には、後悔の念に苛まれて、自分を責めてしまう人もいます。 このタイプは、まじめ過ぎる性格の人に多いようです。 自分を責め続けると、自己嫌悪になり、自分の存在に意味を感じなくなる場合 もあります。 ところが、本当の後悔とは、自分を責めたり、自己を否定することではないの です。 「もっと、やっておけばよかった。よし、一から出直して頑張ろう!」 というように、心をリセットして考えるのが本当の後悔の仕方です。 その意味では、真の後悔とはポジティブなものでもあるのです。 禅の言葉に、『放下著』(ほうげじゃく)というのがあります。 これは、簡単に言いますと、「捨てなさい」ということです。 問題は、何を捨てるのか、ということになりますが、それはモノであったり 心であったりします。 余計なモノを、一つずつ捨てていけば、何もなくなりますが、それでも、感情 や心(とくに、悪感情、執着心)を捨てるのはなかなか難しいものです。 捨てようとしても、捨てられないという執着の心に、「エイッ!」と喝を入れる ための言葉が、『放下著』だと考えてみましょう。 過去への執着心が後悔です。 執着心を捨てるとは、執着の心を断つということと同じです。 自分の未練がましい後悔の心を断とう、と決めることが捨てるということにも なるのです。 決心とは決断する(執着の心を断つと決める)ことだと言った人がいますが、 その通りだと思います。 人の感情や心は複雑で、いつも揺れ動きます。 それでも、何かを決めなければならないとき、があります。 つまり、何かを捨てないといけないとき、があるのです。 その心境になれば、物事をポジティブなものに見ることができるのです。 不要なモノは捨て、リセットして、前向きに生きていきましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月15日
コメント(0)
-
【報われない努力をする人のクセ】
【報われない努力をする人のクセ】 受験や就職試験が迫ってくると、誰もが頑張ろうという気持ちになり、努力し ます。 受験と就職試験に限ったことではありませんが、せっかく努力したのに報われ なかった、とガックリくることもあります。 一方、そんなに頑張らなければと思わずに、よい結果を出せる人も意外に多く います。 それは、能力の違いなのか、というとそうとは言い切れないのです。 よくあるのが、努力するのはキツイこと、ツライことでなければならない、と 口には出さなくても、そう思い込んでいることです。 本人もそうですが、周囲もそう思っています。 もちろん、大変なこともありますが、すべてがキツイ、ツライものだとすると 努力する喜びを感じることはできなくなります。 「努力するのは、楽しいものだ」という要素もある程度、自分の中に持つほう が、努力に要するエネルギー効率は上がります。 努力することは楽しい、と考える人は、努力の仕方に必ず工夫をしています。 「努力は大変だけど、楽しくやることもできるはず。 じゃぁ、どんな工夫をすればいいか、考えてみよう」 と、自分に合った努力のスタイルを形づくることができるのです。 ある人は、IT関係の企業の試験を受けたいと思っています。 ただ、プログラミングに少し苦手意識あります。 そこで、その苦手意識を克服するために、あることを考えました。 すると、好きなゲームがあったので、それを自分の好きなようにアレンジでき ないか、と思いつき、やっていくうちにある手法をみつけました。 それから、プログラミングが面白くなり、試験にも合格できました。 よく、努力が報われなかったとき、たいていは「自分の努力が足りなかった」 と思いがちです。 それは、事実かもしれませんが、自分を責めるのは賢明ではありません。 「ここまでやれたのは、よかった。次は、もう少し工夫をしよう」という反省 であれば、その経験は財産になるでしょう。 脳科学者の中野信子さんが次のように語っています。 『人は、その努力の先に見返りを求めます。 見返りを求めて、苦しい努力を重ねていくと、何も得られなかったときに、 人を恨むんですね。 そういうのはやめましょう。滅私奉公のような努力をして何かを達成するの のではなくて、その努力は楽しいことなんだ。 その道を歩いていること自体が楽しい、というように思って欲しいです』 受験も、就職試験も長い人生では、節目の一場面です。 生きていくには、それなりの努力をしなければいけないものです。 そして、努力するのも楽しい、と感じるのが豊かに生きることになるのでは、 と思います。 (by ハートリンクス)
2023年01月14日
コメント(0)
-
【幸せを呼ぶ感情、幸せが逃げる感情】
【幸せを呼ぶ感情、幸せが逃げる感情】 人は感情で生きていますが、感情を生み出すのは心です。 心の持ち方しだいで、同じ出来事に出会っても起きる感情は、まったく違って きます。 たとえば、最近買った新車を事故でぶつけられた人が、二人いたとします。 一人は、「やっと手に入れた車なのに、とても悔しい」とぶつかってきた相手に 怒っています。 もう一人は、「ケガをしない事故で助かった。ラッキーだった」とぶつかった人 に怒らずに、さらに、相手に「大丈夫ですか?」と気づかっています。 ブッダは、生老病死を人間の四大苦悩と考え、その苦しみから脱却するための 方法を説きましたが、その方法とは簡単にいうと「心を養う」ことでした。 たしかに、経典などにはいろいろな戒律や守るべきことも書かれていますが、 最後は人とは、「心しだいであること」に行き着きます。 人が穏やかに、幸せに満ちた暮らしをするにはどうすればよいか、を説いた 教えがあります。 この教えの特徴には、四つのことをしなければいい、と示しています。 ・一つは、贅沢を求めない。 (少しのものにでも満足する。人間の欲望には際限がない。) ・二つ目は、人には干渉し過ぎない。 (相手との距離を適度に保つ。干渉のし過ぎは争いのもと。) ・三つ目は、荒々しい感情を起こさない。 (怒りの感情は相手も自分も傷つく。怒りは口論や争いのもと。) ・最後は、人のものをうらやましいと思わない。 (他人のものに興味をもたない。自分にもよいものはたくさんある。) このように、ブッダが説いているのは、今では常識的なことなのです。 これは、ルールというより心がけです。 日常の生活を、どんな心がまえで過ごしていくか、生活信条のようなつもりで 認識しておけば、徐々に幸せを呼び込む生き方ができると思います。 (by ハートリンクス)
2023年01月13日
コメント(0)
-
【失敗から学ぶ人が夢をかなえる理由】
【失敗から学ぶ人が夢をかなえる理由】 アメリカの26代大統領だった、セオドア・ルーズベルトが次のように語って います。 『失敗をしない人間とは、何もしない人のことである』 彼は、子どものころ虚弱で喘息がありました。 これではいけないと体を鍛え、後に政治家にまでなりました。 結婚して子どもを授かりますが、出産してすぐ妻は病気で亡くなるという辛い 経験をします。 たいていは、何かで躓き失敗したとき、もうダメだ、とあきらめるものです。 しかし、「もう一度やり直して、失敗を挽回したい!」と思う人もいます。 このように思う人は、すでに失敗から学んでいるのです。 ルーズベルトも冒頭の言葉にあるように、失敗の連続だったに違いありません。 彼は、日本の思想家である新渡戸稲造の本に影響を受けています。 新渡戸稲造の著書「武士道」という本を読んで感銘をうけ、知人や友人にその 本を配っていたという話もあります。 この本に書かれてあるのは、行動することの重要性です。 また、日本を代表する経営者、稲盛和夫さんが愛読した、ロバート・シュラー という人が書いた本には、失敗に対する考え方が述べられています。 ・失敗とは、不名誉なことではなく、勇敢に挑戦したあなたの態度は高く評価 される。 ・失敗とは、人生を無駄にしたという意味ではなく、もう一度新しい気持ちで 出直すチャンスを与えられたのだ。 ・失敗とは、やり方を変えるべきだ、というサインなのだ。 ・失敗とは、もうあきらめなさいという意味ではなく、もっと努力しなさいと という意味だ。 ・失敗とは、けっして終点ではないのだ。 夢を実現している人の共通点は、失敗しても学ぶべきことを見つけて、行動に 移していることなのです。 (by ハートリンクス)
2023年01月12日
コメント(0)
-
【自然界と親しむことが心を癒します】
【自然界と親しむことが心を癒します】 都会の周辺で生活する人たちが、多くなりました。 そのために、大都会のホテルでは部屋も自然界にいるような空間を、人工的に 作ろうというブームが起きています。 現代人は、自然界とますます遠くなっています。 その影響で、いろんな病気も新しく生じるようになりました。 たとえば、花粉症も以前はほとんど流行っていませんでした。 1964年東京でオリンピックが開催される頃から、新幹線や高速道路が作られ 道路もほとんど舗装され、それまで山の樹木から吐き出されていた花粉も土に 吸収されずに、ビルの壁や舗装された道路に上に常時散乱し、それを人の呼吸 で、体内にはいり込んで花粉症が広まったといわれています。 このように、私たちはいつのまにか自然界から離れてしまって、森林浴をする 機会も少なくなったのです。 自然の樹木には、フィトンチッドと呼ばれる物質が放出されているそうです。 森にいくと、独特のよい香りがありますが、これがそのフィトンチッドです。 殺菌力があり、落ち葉の悪臭などを吸収し分解する力があります。 同事に、人間にとっても気持ちに安らぎをもたらし、ストレスで傷んだ心を癒 す効果があるのです。 また、植物や海や空の写真を部屋に飾っておくだけでも、乱れた感情を静めて くれる効果もあります。 心理学でも、緑は、癒しと安らぎ、優しさの感情をもたらす色。 青は、落ち着きと誠実さと、そう快感をもたらす色。 黄色は、希望や軽快さ、元気をもたらす色。 橙色は、陽気で明るく、あたたかさをもたらす色です。 自然界は、このような傾向の色でいっぱいです。 つまり自然界の役割は、人間の病気や心を癒すことでもあるのです。 こんな話もあります。 ニュートンが万有引力に気づいたのは、木からリンゴが落ちるところを見たか らですが、当時、ヨーロッパではペストという伝染病が大流行していました。 そこで、ニュートンはペストから身を守るために、故郷に帰って森林浴の毎日 を過ごしていたのです。 1年半ほどの自然界の中で思索を深めている間に、万有引力や微積分など歴史 に残る法則を発見しています。 これも森林浴のおかげだといえるでしょう。 自然界と親しむ時間をできるだけ多くして、心身の健康を守りましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月11日
コメント(0)
-
【どこにいても孤立しない人】
【どこにいても孤立しない人】 一人で過ごすのがいいと思って生きている人がいます。 孤独が好きなタイプの人なのかもしれません。 しかし、孤独が好きでも周囲から慕われている人もいます。 つまり孤立していない人です。 『論語』という古典に、次のような言葉があります。 「徳は孤ならず、必ず隣(となり)あり」 どのような意味かというと、 「徳を備えている人は孤立しません。必ず慕う人が現われてきますから」 「徳を備えている人」つまり徳のある人とは、人格者、立派な人柄である人、 ということです。 現代では、その人の価値は仕事の能力を最優先に考える傾向がありますが、 以前は、人格本位の世の中でした。 では、「徳」というのは具体的にどのようなものなのでしょうか。 それは、思いやりがあり、謙虚である。感謝の言葉を忘れず、他の人のために なる生き方をしている・・・、などです。 江戸時代に生きた良寛和尚という人も、徳をもった人格者です。 良寛は、新潟の村の名主の子として生まれましたが、若くして出家しました。 修行を積み、位の高い僧侶になりましたが、その地位や名誉を捨てて、生涯を 一人の和尚として過ごします。 良寛は、どこに行っても村人から慕われていたので、まわりには子どもは村人 たちが何かにつけて集まりました。その良寛が語っています。 ・男というのは、相手の女性との考えが違っていたら、まず、自分の意見を言 う前に、相手の話をしっかり聞くべきです。 ・子どもたちには、美しいところもあれば、そうでないところもあります。 よいところもあれば、悪いところもあるでしょう。 それでも、その両方を認めて、寛容な心で育てることが大切です。 このように、対人関係や子どもの教育について村人たちに分かりやすく、話し ています。これが徳のある人の特徴の一つかもしれません。 「徳」という言葉自体、耳にする機会も少なくなりましたが、どのような時代 になっても、徳のある人を大切にすることを忘れてはいけないと思います。 (by ハートリンクス)
2023年01月10日
コメント(0)
-
【コミュニケーション上手になろう】
【コミュニケーション上手になろう】 コミュニケーションの不足が原因で、人間関係に悩む人は多くいます。 一説では、社会人の悩みの6割から7割ぐらいが、社内職場や所属する集団で の人間関係にあるというデータもあります。 相手はこちらのことを分ってくれている、と思っていたのにまったく違ってい た、などの原因も多いようです。自分と接する人たちのすべてと、気持ちが通 じあうことはとても難しいものです。 ただ、仕事では最低限のコミュニケーションは不可欠です。 一方通行のままでは、片方に心の負担とストレスが生まれたりします。 仕事中のコミュニケーションも、仕事の休憩中などの時間帯でうまく作られる こともあります。 雑談を通して、相手の気持ちや考えていることがわかると、安心して話せる人 だ、と感じそこからからよいコミュニケーションを作れるようにもなります。 中には、自分の言いたいことをはっきり言って、そのときは感情的になっても それがかえって互いを理解するきっかけになるケースもあります。 ただ、いつも雑談だけ終わるようだと、よい関係にはなりにくくなります。 コミュニケーションをうまくとるために、大切なことがあります。 一つは、相手に対する最低限度の敬意をもつこと。 次に、お互いの立場の違いに応じた距離を置くこと。 そして、言葉の表現の仕方に気をつけること。 とりあえず、この三つだけでもポイントにすれば、悪い関係にはならないと言 えるでしょう。 言葉の表現の仕方についてですが、これを言えば相手が傷つくかもしれないと 思う場合は、表現法を変えることです。 頭ごなしに、「それは間違いです」という言い方より、「その考え方も正しいと は思うけど、別の考え方もできると思う」と、相手を肯定することを忘れない ことです。 相手の意見を肯定するのは、相手への最低限度の敬意をはらうことです。 コミュニケーションも、言葉の使い方・表現の仕方で大きく変わります。 ある程度は会話の際の、語彙力を持っておくべきでしょう。 また、もう一つあるとすれば、物事に対する『自分の考え』をきちんと持って おくのも重要なことです。 これは、相手の意見は受け入れないというのではなく、常日頃自分は何を基準 に考えるか、どんな価値観をもっているか、ということです。 これは、日常の自分と対話のようなことをしていないと、作れないものです。 寝る間際まで、スマホを見るより、今日はどんな一日だったのか、など自分を 見つめる時間をせめて3分でも持つように心がけましょう。 コミュニケーション上手な人ほど、自分と対話する時間をしっかりとっている のです。 (by ハートリンクス)
2023年01月09日
コメント(0)
-
【心の余裕のつくり方】
【心の余裕のつくり方】 仕事もプライベートも、いつも時間に追われてばかりいると、いつのまにか心 に余裕がなくなります。 すると、自分の思った通りにならなかったり、何かの話で自分とは違う意見を 聞いたとき、つい怒ってしまいます。 人は、心に余裕がないとき、気持ちのゆとりがないときほど短気になります。 つまり視野が狭くなっているのです。 本当は、きちんと順序立てて考えることができるのですが、つい感情的になり ます。 さらに、冷静さがないために、普通の何もないときに少しだけ感じている不安 なことも、こういう状況になるとよけいにイライラした気持ちになるのです。 これは、誰もが経験することです。 それだけ、人の心は敏感なものでもあるのです。 もし、そのような状態になったら、とりあえず自分の心を落ちつかせることを いちばんに考えましょう。 落ち着かせるために、とてもいい禅の言葉があります。 それは、「両忘」(りょうぼう)という言葉です。 意味は、白か黒かのどちらかでなくてはならない、という短絡的な感情を捨て、 「まあ、どちらでもいいじゃないか、こだわりを忘れてみようよ」ということ です。 気持ちに余裕がないと、自分の好き嫌いの判断をして、物事を善と悪のどちら かに決めてしまいたくなります。 つまり、二者択一で物事を見て、結果を早く求めたくなるのです。 しかし、世の中はそう簡単なものではありません。 白か黒か、善か悪か、というこだわりと決めつける心を少し緩めることも必要 です。 人は生きている以上、悩みや不安はゼロにはなりません。 ただ、悩みや不安はあっても心の余裕を持つことはできます。 怒りっぽいとき、心の余裕がないときは呼吸が浅くなっています。 こんなときほど、深呼吸をして、コーヒーやお茶を飲む時間をつくるのです。 その時間が、自分の気持ちを自身で見つめることになり、心に余裕がうまれる 習慣にもつながります。 (by ハートリンクス)
2023年01月08日
コメント(0)
-
【小さなきっかけも、チャンスに変わる】
【小さなきっかけも、チャンスに変わる】 どんな小さな頼まれ事でも、誠実に取り組んでいけば、そこから仕事運がどん どんどん開いていくことがあります。 人から何かを頼まれるのも、人間関係というものがあるからです。 直接相手を知らなくても、誰かを介して一つの仕事が舞い込んでくるこという もあります。 人の縁とは不思議ですが、その縁のおかげで人生が一変することも現実に起き るのです。 アンパンマンの作者、やなせたかしさんがまだ無名の頃、こんなエピソードが があります。 当時、有名な手塚治虫の「千夜一夜物語」の制作に協力して欲しいと頼まれ、 そのスタッフになりました。 表面上は、美術監督というものだったのですが、やなせさんは何をしていいの かピンとこなかったのでした。 手塚さんからは、キャラクターのデザインを描いて下さい、ということです。 そして、打ち合わせがあり「まず、イメージボードを描いてください」と言わ れたのですが、何のことなのかわかりませんでした。 結局、それはシナリオを読み、そのシーンを絵にすることだと教えてもらって やなせさんの仕事が始まったのです。 しかし、現実には雑用の仕事もたくさんありましたが、どの仕事も誠実に取り 組んでいきました。当然、徹夜の続きの毎日だったそうです。 そして、「千夜一夜物語」は完成しました。 手塚さんはそのお礼にと、「何か、短編アニメを一本、自由に作って下さい」 やなせさんに依頼したのでした。 そのときのやなせさんの作品が、「やさしいライオン」というものでした。 ところが、この作品があるコンクールで受賞することになったのです。 これがきっかけになり、「アンパンマン」のテレビ放映につながり、その後の やなせさんの人生は大きく変わっていくのです。 さらに、誠実にキャラクターデザインを描いてきたことがアンパンマンでも いかされて、次々にたくさんのキャラクターを生み出していきました。 やなせさんは、『チャンスは誰にでも平等にある』と語っています。 チャンスはつかむものです。 さらに、チャンスをつかむには、小さな仕事でも誠実に取り組むことがとても 大事なことです。 また、仕事への誠実な姿勢というのは、周囲にいる人に伝わるものです。 それを見た人が、小さくてもチャンスのきっかけを持ってきてくれます。 チャンスをつかめるような生き方をめざしましょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月07日
コメント(0)
-
【悩み解決のコツは、生活リズムを整えること】
【悩み解決のコツは、生活リズムを整えること】 明日のミーティングで、嫌いなプレゼンテーションをしなければいけない、 とか、朝一番に苦手な取引先との打ち合わせがあるなど、気が進まない予定が あるとき、前の夜は不安で眠れないものです。 不安なことがあると、明日を迎えることがイヤです。 朝が来るのが怖い、という気持ちになります。 それでも、仕事ですから逃げることはできません。 そして、そんな一日が無事に終わるとホッとした気持ちになります。 その夜は、緊張もほぐれてつい遅くまで起きていて、夜更かしをする。 こんな経験のある方も多いと思います。 人のメンタルはとても敏感で複雑です。 仕事でもプライベートも、うまくいっているときは毎日に充実感を覚え、夜も ぐっすりと眠れるものです。 しかし、このサイクルが何かで狂ってしまうと、夜眠れなくなったりします。 ところが、うまくいっているときも、何か問題があるときも、その影響を受け ずに、淡々と日々を送っている人も意外にたくさんいます。 そのような人の特徴は、一日の生活がリズム化、サイクル化されているという ことです。 つまり、生活習慣が整っているのです。 テレビタレントで著名なタモリさんですが、もう75歳を過ぎています。 タモリさんは、仕事が忙しくてもそうでないときも、朝は必ず6時頃に起きる そうです。 それから、自分で朝食の準備をするといいます。 夜も、早く寝るという生活スタイルです。 このような生活習慣があるために、緊張の絶えない仕事でもきちんとこなして いるのです。 『習慣は第二の天性となり、その習慣が天性の10倍の力を持つことになる』 という言葉があります。 もちろん習慣にも、よいもの、よくないものがあります。 良い習慣も悪い習慣も、第二の天性になり考え方の形成にも影響を与えるもの なのです。 生活のリズムが整ってくると、自分自身の心も安定し穏やかな一日を過ごせる ようになります。 また、そのリズムが習慣になれば、問題や悩みがあってもどうにか乗りこえて いくこともできるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月06日
コメント(0)
-
【人間関係を新しくする】
【人間関係を新しくする】 一年の初めは、人間関係を新しく見直す時期です。 いつもは、苦手と思っていた相手がいたとしても、新しい年なら気持ちも切り かえやすくなります。 たとえば、嫌いという感情をどうしても抱いてしまう人がいるとします。 嫌いになった原因があってのことなら、仕方のないことです。 どちらかに非があったのかもしれないのと、一方的にこちらが思い込んでいる ことがあるかもしれません。 そもそも、人に対して「嫌い」という気持ちになるのは、相性の問題です。 相性が合わないとは、自分という人格と相手の人格のソリが合っていない、と いうことです。 考え方や好みの違いを含めて、人格があまりに違い過ぎると水と油のように、 交わることができなきなります。 ただ、嫌いになるのは、悪いことではありません。 嫌いなのは悪いことだ、となると、自分は悪い人になってしまいます。 自分にとって、嫌いな人がいるのは特におかしなことでもないのです。 嫌いなら、距離を置く。 これがきちんとできれば、あまり気にする必要もないでしょう。 そのような気持ちになってみると、不思議なことに嫌いだと思っていた人が、 ちょっとしたきっかけで、うまくつき合えるようにもなるのです。 江戸時代、武芸の大家に柳生宗矩(やぎゅうむねのり)という人がいました。 この人物が次のような言葉を残しています。 『普通の人は、人との縁があっても、縁に気づかない。 その上の人も、縁があっても、その縁を活かすことができない。 しかし、優れた人物は、袖ふれあう多生の縁を活かすことができる』 今でも「袖ふれあうも多生の縁」という言葉を聞くことがあります。 この言葉の意味は、道を歩いていると、着物の袖が触れあうような少しのこと でも、前世からの因縁があるのだ。 だから、人とのご縁は大事にしたいものだ、ということです。 柳生宗矩は、「優れた人は、人との縁を活かす人」と言いました。 これも深く考えるなら、自分にとって嫌な人であっても、そこには何かの意味 があるのではないか。 さらに、その縁をどのように活かすのかは、その人の人間的な力量である。 これが、彼の言いたいことかもしれません。 現代は、他者とつながることは簡単です。 その分、人との関係性も希薄なものになりました。 嫌いな人、苦手な人がいたなら、まず距離を置いてみましょう。 距離をおくことで、その相手が自分にとってどんな存在であるのか、今まで 気づけなかったことがわかるかもしれません。 この気づきが、人との縁をいかすことになる。 これからの時代は、人間関係のあり方が変わってくるような気がします。 (by ハートリンクス)
2023年01月05日
コメント(0)
-
【人のために譲る気持ちが、自分のためになる】
【人のために譲る気持ちが、自分のためになる】 自分中心の考え方に慣れてくると、人のために何かをしたい、という心がなく なります。 それは人のために何かをすると、自分が損をしたような気分になるからです。 仏教ではそのような間違った心を正すために、「利他の心」の大切さを説いて います。 仏教のお話に、人のために譲ることが、結局は自分のためになるという説話が あります。 ある人が、地獄とは一体どんなところなのか、と興味を持ち見に行きました。 行ってみると、ちょうど食事の時間でした。 見ると、大きなテーブルの真ん中にはごちそうがたくさん置かれています。 しかし、すわっている人はなぜか痩せこけています。 一人ひとりの横には、2メートルぐらい長い箸がありました。 ここでは、その長い箸を使って食べるルールがあるのです。 食事が始まると、みんなわれ先に食べたいと、長い箸で料理をつかんで自分の 口に運ぼうとしますが、なかなか口に入れることができません。 食事の時間は終わりましたが、誰も食べることはできませんでした。 今度は、極楽に行ってみました。ここも食事の時間です。 大きなテーブルには、地獄と同じように中央にたくさんのごちそうが置かれ、 それぞれには2メートルの長い箸が与えられています。 つまり、情景は地獄とまったく同じなのです。 しかし、すわっている人たちは、みんなニコニコしてふくよかな体つきです。 食事が始まりました。すると、長い箸で食べ物をつかんだ人が正面の人に、 「あなたから先に食べてください」と言いながら、相手の口に料理を運んでく れています。 「どうもありがとう。今度は私があなたに食べさせてあげましょう」と言いな がら、お互いが譲り合い食事をしています。 みんな、おいしい、ありがとう、と言って食事の時間は終わりました。 このように、地獄も極楽も環境や条件は同じなのに、そこにいる人たちが譲る 心で相手のために行動すれば、自分もその恩恵を受けることになります。 「利他の心」の意味が、この物語に表れています。 「人のため、他者のため」、という言葉を聞いたときになぜか、自分が損をし たような気持ちになるのは、心のどこかに「自分の欲得ありき」の考えがある のかもしれません。 自分のことを第一にするよりも、自分以外の人のために、何ができるかを考え る習慣が、結局は自分の幸福を手に入れることになるようです。 (by ハートリンクス)
2023年01月04日
コメント(0)
-
【人に喜んでもらうことが、自分の幸せ】
【人に喜んでもらうことが、自分の幸せ】 ある作家の娘さんが通う幼稚園が、リンゴ園をもっていました。 収穫も終わった頃、娘さんの家にたくさんのリンゴが送られて来ました。 せっかく育ったリンゴなので、園児たちの家族の人たちにも食べてもらおう、 というのです。 受け取った作家の家では、すべてを食べきれないので、知り合いの人や日頃 お世話になっている人たちに、おすそ分けとしてリンゴを送りました。 しばらくすると、作家さんの家に宅急便でミカンが送られて来たといいます。 お礼の連絡をすると、美味しいリンゴを送ってもらったのだから、そのお返し にミカンを食べて下さいということでした。 そのミカンも家ではすべて食べ切れないので、今度は違う友人たちにミカン を送りました。 すると、今度はそのお礼にと、リンゴが送られてきました。 キリスト教の新約聖書に、 『与えよ、さらば与えられん』という言葉があります。 「まず、与えましょう。そうすればあなたにも与えられるでしょう」と説かれ ています。 ビジネスや一般的な取引となる、経済活動の考え方にあるのは、自分の利益を もたらすためにどうするか、これが先にあります。 自分の利益を得るために、相手がある、という図式です。 これは正当で間違ったものではありませんが、すべてをこの考えで進めていく と、損得勘定ありきになってしまいます。 ビジネスも取引もそれに関わる仕事は、人が行うものである以上、人間の心の 温かさや、相手を思う気遣いという要素がなければ、殺伐とした社会になって しまうでしょう。 ブッダや、キリストが生きた時代は、人種差別や性差別の社会でした。 キリストは「与えよ、さらば与えられん」と説き、ブッダは「慈悲の心を与え よ、それが成仏への道」であると説きました。 人が生きていくために、いちばん大切なのは、 「他者と自分とが互いにいかしあうこと」です。 「まず、相手に喜んでもらおう」、という心から生じる行為、行動が自分の幸 せとなって戻ってきます。 「与えるものが、与えられる」。これをモットーにすると、自分自身も幸せに なれると思います。 (by ハートリンクス)
2023年01月03日
コメント(0)
-
【生き方上手な毎日を送ろう】
【生き方上手な毎日を送ろう】 年の初めは、自分なりに目標を決めてもっと自分を高めよう、と思う人も多い のではないでしょうか? 宇宙は誕生以来、どんどん膨張し成長しているという説があります。 地球が一年の時間をかけて、太陽のまわりを一周するように、人もそれなりに 成長していくべきかもしれません。 今年の年末頃、自分はどれくらい人間的に成長しているのだろうか、と想像す るだけでワクワクする人も多数おられることでしょう。 成長のためには自己研鑽を持続していくことが必要です。 ただ、その自己研鑽も自分にとって苦しいものだと、かえって逆効果です。 自分を磨いていくことそのものが楽しくなければ、持続させることは困難なも のになってしまいます。 自分を研鑽し、そのための毎日の生活を楽しいものにすることが、生き方上手 な人なのです。 また、楽しい生活というのはけっしてラクなもの、安易なものだと決めつける のもよくありません。 スポーツ選手が、上達するためにきつい練習に取り組めるのは、そこに何かの 楽しみを自分で見つけているからです。 そのような人が、一流の選手に成長しているのです。 中国の思想家、老子の言葉に、 『上善は水の如し』というものがあります。 「上善」(じょうぜん)とは、いちばん理想的な生き方を意味しています。 つまり、人が人として幸せになるための理想的な生き方をしたいならば、水に 学びましょう、ということです。 水はどんな形をした器にも、きれいに柔軟に形を変えていきます。 次に、水は謙虚です。 たとえば高い所から低い所へと、自然に流れていきます。 さらに、水は静かに流れていきますが、そこにはとても大きなエネルギーを 持っています。 人が、自分自身を高めて、自己研鑽するには水のように、 1、柔軟であること 2、謙虚であること 3、内に秘めたエネルギーがあると知ること 最低でも、この三つのことを学ぶなら、人として成長し幸福な人生を送ること もできるでしょう。 毎日の生活でも、この三つを行動の指針とするなら、メリハリのある充実した 時間を過ごすことができます。 (by ハートリンクス)
2023年01月02日
コメント(0)
-
【「現在感謝」で、未来を変えていこう】
【「現在感謝」で、未来を変えていこう】 新しい年を迎えると、多くの人は「今年こそ、よい一年でありたい」という 気持ちになるものです。 よい一年とするには、今までの自分の考えや行動を振り返り、その上で新しい 目標を立て努力していくことが必要です。 しかし、その前に大切な心構えが必要です。 それは、「今に感謝すること」つまり、「現在感謝の心」です。 人は、どうしても当たり前のことに慣れてくると、何も思わなくなります。 たとえば、息をすることが当たり前だと思う人には、呼吸のありがたさを感じ ません。 しかし、喘息の病気がある人にとっては、咳をすると苦しくなり普通に呼吸が できることは、とてもありがたいと思います。 病気をしてはじめて、健康なのはありがたいことだ、と感謝できます。 どんな事にも感謝できるようになると、不平や不満を持たずに生きられるよう になります。 感謝の心があるとき、自分が生きていることにも何かの意味がある、と考える ようになるのです。 すると、他者に喜んでもらいたいという、人本来の衝動が生まれ、人から自分 が感謝されるような生き方をしたい、という気持ちになります。 この気持ちが、自分の未来をよい方向に向かわせてくれるのです。 ブッダの教えに、 『山川草木ことごとく仏性あり』というのがあります。 これは、「人を含めた自然界のものすべてには、仏の命が宿っている」という 意味です。 しかし、現実に生きているとそのような深いところまで、人はなかなか考える ことはありません。 それでも、自分にも神様や仏様の命が宿っている、と少しでも考えてみると、 そのときだけは家族や周囲の人たちに感謝の念が起きるものです。 つまり、日頃は忙しく人間らしい気持ちを忘れることがあっても、たまにでも 自分の心を静かに見直すこともできるのです。 現在感謝の気持ちを起こすと、そこには気持ちの余裕が生まれます。 それをくり返していく間に、心が乱れることがあっても、すぐに修正できる力 がついてくるに違いありません。 小さくても、感謝の気持ちになることが、いずれは恵まれた人生を送ることに なるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年01月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1