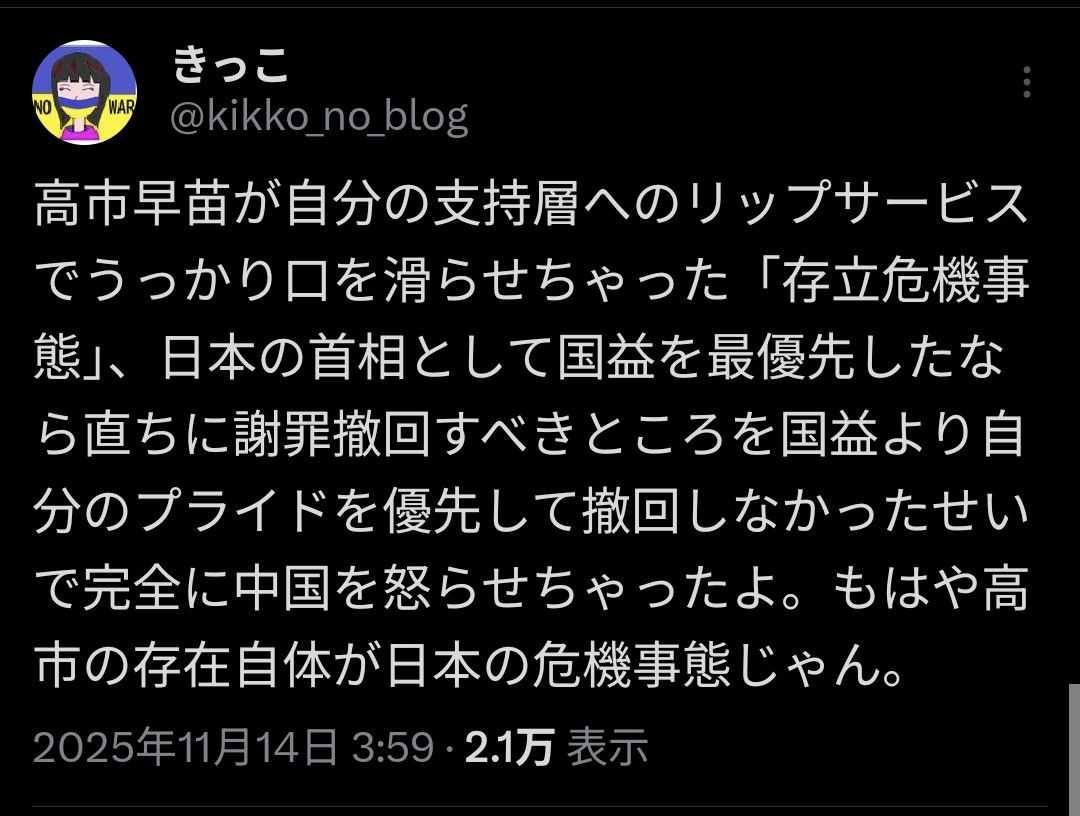2023年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
【ストレスは悪だと決めつけない】
【ストレスは悪だと決めつけない】 孔子や老子、キリストやブッダやアリストテレスが生きていた時代も、人には ストレスというものがありました。 その当時、ストレスというとらえ方があったかどうかはわかりませんが、悩み や憂いという心の中での葛藤はあったと思います。 このストレスは、どんなにお金持ちで健康な人にもあるものです。 世界的なお金持ちだった、ロックフェラーが日本を訪れたとき、インタビュー があり、「何か悩みがありますか? ロックフェラーさんぐらいの人なら幸せ しかないでしょうね」と聞いたそうです。 そのときの答えは、お金が世界中にあり、そのために自分の財産がどのくらい あるかわからない、これが最大の悩みです、というものでした。 普通の人からすれば理解できませんが、このように誰もが悩みやストレスを抱 えているのです。 このストレスも溜まっていくと、心も体も疲れます。 心理学でも医学の世界でも、ストレスが溜まったら発散させることがいい方法 であると考えます。 しかし、発散するための具体的なやり方がわからない人もいれば、そのための 時間やお金の余裕のない人もいるのです。 このことから、「ストレスは発散しなければいけない」、という考え方に固執し ないで、気楽に考えることも大事です。 まず、いちばん手っ取り早いのは、寝ることです。横になり休むことです。 それでも眠れないなら、体を少し温めしばらくすれば体温が下がり、眠くなり ます。 ブッダは、人は生老病死という四つの苦から逃れることはできない、と説いて いますが、「そもそも生きていること自体がストレスだから、仕方がないのだ」 というぐらいの気持ちになれば、ストレスを恐れることもなくなります。 ただ、ブッダは、生きることは苦しいものだとしても、考え方しだいでは生き ていくのは素晴らしいものですよ、と考え説いています。 つまり、ストレスがあっても、そのストレスは悪である、消すべきである、と 思うこともできますが、ストレスが生じたのはそれなりの理由があるから。 その理由がわかれば、ストレスから解放され、自分も磨かれる・・・。 私たちも、このような気持ちになってストレスをとらえてもよいのです。 「何か最近、ストレスが溜まってきたようだな」と気づいたら、そろそろ休む べきときがきたんだ、という穏やかな気持ちになってみましょう。 ストレスを人生に活かしていく、という人生観も必要です。 (by ハートリンクス)
2023年03月31日
コメント(0)
-
【感謝の気持ちを表現して得すること】
【感謝の気持ちを表現して得すること】 誰にでも、心の中にはいつも感謝をしている人がいると思います。 しかし、その気持ちを実際ことばに出すとなると、結構勇気がいります。 感謝はしていても、表現するのはなんとなく気恥ずかしいと思うのも国民性が あるからでしょうか。 それでも、その気持ちを伝えることはとても大切で、尊いことなのです。 感謝の気持ちを表現して相手に伝えると、得をします。 損得の価値観で考えるのはよくないことかもしれませんが、それでもいろんな 意味で自分にとって、現実に得をするのです。 まず、相手から喜ばれます。 喜んでもらうと、次は相手もこちらを喜ばせようという気持ちになるのです。 次に、感謝の気持ちを伝えると、心が謙虚になります。 「あなたのおかげです」という気持ちになると、プライドにこだわる心がなく なります。 さらには、気分が明るくなり、元気なプラスエネルギーが生まれます。 活力のあるエネルギーは、体のリズムを調えてくれます。 次は、寛容な心になることができます。 感謝すると、相手に欠点があっても欠点に対するこだわりがなくなります。 すると、その欠点さえも長所に見えてくるのです。 そして、感謝の言葉を述べた自分を好きになることができます。 多少の勇気を必要とはしましたが、自分の正直な思いをきちんと伝えたことに 自信もつきます。 また、自分の表情がよくなります。 心の状態は顔つきに表れます。表情がよくなると周囲に与える雰囲気も変える 力になります。 最後ですが、人間関係がよくなります。 相手との人間関係だけでなく、相手のまわりの人との関係もよくなります。 感謝された相手は、他の人にも感謝した人のことをほめるようになり、それが 人のつながりをさらに広くしていくのです。 このように、人に感謝をすると得をしますが、相手も同じくらいの得をするの です。 これは、「与えよ。さらば与えられん」の法則に合致しているからです。 実利的に得をすることが、人としての徳を積むことに変わっていきます。 感謝すると、自分も周囲の人も幸せになることができます。 (by ハートリンクス)
2023年03月30日
コメント(2)
-
【自分の感情には責任を持つ】
【自分の感情には責任を持つ】 人には、喜怒哀楽の感情をはじめとして複雑でいろいろな感情が、一日中流れ ています。 心理学でいう、顕在意識(または現在意識)よりも、さらに敏感に動き回って いるのがこの感情です。 何かいいことがあったり、ラッキーなことが起きたりしたときなど、いい気分 になります。 ところが、予期しない悪い出来事があり、仕事でミスをしたときなどは、落ち 込んだりします。 このように、外の条件や出来事の良し悪しの影響を受けているのが、私たちの 感情なのです。 かといって、感情の流れるままに生きていくのは、成熟した人間とはいえない のかもしれません。 よく、「あの人は、思慮分別のできる人だ」という言い方をしますが、周囲の人 からそんな評価をされる人は、少なくとも感情に流されている言動はしない人 なのです。 ただ、この世界にはいろんな人がいて、相手との言葉のやりとりや会話の中で、 相手が気づいてなくてもこちらが傷つくようなことを言って来る人もいます。 また、反対に自分は相手を傷つけようとまったく思っていないのに、ちょっと した言葉で相手に不快な思いをさせてしまうこともあります。 それでも、「心の中で起きた感情は自分の責任である」という考えを持っておく のも大事なことです。 もちろん、何か意図的に相手を不快にさせようとするのは、問題外です。 それは、社会のルールマナーから逸脱しているのですから、別の対応がなされ るべきでしょう。 人の心はとても不思議で、日ごろからどんな考えをしているかで、自分の話す 言葉の傾向や語彙が決まります。 こちらは相手を傷つけようと思っていないのに、つい一言、言わなくてもいい ことを言う人がいます。 そのタイプの人は、何かにつけて心の中では自分はダメな人間だ、だから私は 人から好かれないのだ、という意味のことをつぶやいているのです。 これは、自分の価値を自分で下げているようなものです。 背景にあるのは、自己肯定感の低さです。 人は、自分で自分の価値を下げる必要はないのです。 「私は私なりの生き方がある」「私は自分の考えをいつも大事にしたい」という 自分の軸は持っておくべきです。 ただし、自信過剰になり、自分は誰よりも優れているという考えでは、誰から も相手にされません。 バランスのとれた自己肯定感のある人は、人に対しても自分に対しても、凛と した雰囲気があり、感情のコントロールがうまくできています。 つまり、感情のコントロールのうまい人は、自分の感情にも責任を持てる人だ と言えると思います。 (by ハートリンクス)
2023年03月29日
コメント(0)
-
【嫌いな人、苦手な人との接し方】
【嫌いな人、苦手な人との接し方】 人の社会は、個人と個人の集合体です。 家族や気の合う友人同士の関係では、自分の感情をある程度思うように伝える ことができます。 また、そこから生じる悩みはありますが、言いたいことが言えるからこそ悩む こともあります。 しかし、職場や学校などでは自分の好き嫌いに関係なく、与えられた組織では そこにいる人たちから逃げることはできません。 ここに人間関係の難しさがあります。 とくに、職場では自分の上司は自分で選ぶことはできず、自分が苦手なタイプ の人だったりすると、気が重くなります。 そのようなとき、その相手を気にし過ぎたり、相手に合わせるために自分を抑 えたりすることは、自分を傷つけることになりかねません。 そのことでの悩みを軽くするには、自己と他者との距離感をどうすれば適度に 保てるのか、これを考えてみるのも一つの方法です。 ドイツの哲学者、ショーペンハウエルという人が作った寓話に、「ヤマアラシ のジレンマ」というのがあります。 ヤマアラシは背中に針状の毛を持っています。冬の寒いときは、お互いの体を くっつけ合おうとしますが、相手の尖った毛が刺さるので離れてしまいます。 それでも、やっぱり寒いのでまた近づこうとするのですが、また刺さります。 そんなことを繰り返すうちに、ちょうどいい距離を見つけることができた、と いうお話です。 この適度な距離を、人間関係で保つことの必要性を説くために、この「ヤマア ラシのジレンマ」の話を引用することがよくあります。 では具体的に、現実の問題としてこの適度な距離は、どうすれば見つかるので しょうか。 まず、人はすべての人と仲良くできるものではない、と知ることです。 好きな人がいるように、嫌いな人がいても当然のことだと考えるのです。 こう考えるだけで、嫌いである・苦手であるという、感情にとらわれることが 軽減できます。 次に、相手も人です。 どんな人にも長所あるいはポジティブな点の一つや二つはあるものだ、と考え るのです。 あえて、その長所やポジティブさを見つけようとする必要はありません。 そう思うだけでよいのです。そのうち、気づくこともあるはずです。 また、必要以上に気を遣うことは不要ですが、どうしても会話をする必要に迫 られたら、攻撃口調にならずむしろ誠実な言葉使いで話すことです。 ため口よりも、敬語を混ぜながら話すようにするのがコツです。 話すとき相手の目を見ることができないなら、目より上の眉や額をみるぐらい の感じがよいでしょう。 これらのことを、頭に入れて接していけばいいと思います。 また、人間関係は自分を磨く砥石である、と考えておきましょう。 いろんな人と接することで、自分の人間性も高まっていくものです。 (by ハートリンクス)
2023年03月28日
コメント(0)
-
【うまくいかないことが心を強くする】
【うまくいかないことが心を強くする】 自分がめざす目標があると、実現のためにどんな計画を立てて行動をするべき か、をきちんと決めたくなります。 これが、本気で目標を持つということだといえるでしょう。 目標を実現させたいという切実な思いが、計画をたてる行動を起こさせてくれ ます。 ところが、計画を立ててそれを実行するだけで目標が実現できるほど、世の中 は簡単ではない、ということに多くの人が気づきます。 つまり、その過程では予期しない困難や障害が起きることもあるのです。 人によっては、これらの問題が起きたことをあきらめる理由にして、いろいろ な事情があったから、やっぱりやめると結論をだしてしまうのです。 一方では、問題が起きた現実をきちんと受け止めて、どうしてそれらの困難な ことや障害が起きたのかを考える人もいます。 あきらめるタイプの人は、問題が起きたことを事実として認めてはいますが、 そこでストップして、あきらめるという結論をだしています。 ところが、あきらめないタイプの人は、起きてしまった問題から次に進むため のヒントを見つけようとします。 では、どうしてこのような考え方の違いが生まれるのでしょうか。 いちばんは、「目標を実現させる」という、心の熱量の差です。 あきらめない人は、起きた問題の先に、目標を実現したときの自分の姿を心に イメージとして描いているのです。 ですから、少々の問題が起きるのは当たり前だという、覚悟があるのです。 その覚悟の本気度が、心の熱量です。 人が、何かをやろうと決めたとき、成功する人と失敗する人の大きな違いは、 このことなのです。 成功する人は、物事に取り組むたびに、その過程で問題が起きた理由は何か、 という分析をしながら、自分の心をたくましく鍛えています。 この自分の心を鍛えることがつらくて大変だと考えるのか、鍛えることが自分 のためだと考えるのか、この違いが人生を左右することもあります。 うまくいかないことに直面したら、自分はなぜその目標を立てたのか、原点に かえることが大切です。 (by ハートリンクス)
2023年03月27日
コメント(0)
-
【人間関係に疲れたら】
【人間関係に疲れたら】 人間関係がうまくいかないと、仕事に集中できないだけでなく心身に悪い影響 を及ぼします。 対処法には、いろいろなものがありますが、大きくは次のことがいえます。 一つは、人間関係に疲れたときは、「自分を見つめる」ということです。 自分を見つめるとは、それまでとは違う視点で考えるということです。 人間関係がこじれる理由は、相手が自分の意に反した言動をするからです。 つまり、自分の思い通りにならないのです。 また、相手(とくに上司)から傷つけられているときは、人間関係では大きな 問題です。不要な気遣い、緊張がありストレスに直結します。 パワハラに近い言動を受けることもあります。 このようなときには、人は自分の思った通りにならない、と認識し直すことが 大切です。 認識し直すとは、自分が変わるという意味を含みます。 これは黒を白に変えるというのではなく、自分の中に一つ別の視点を持つ、と いうことです。 たとえば、相手がどうであろうとかまわない、どう思われても自分は自分だ、 と自分らしさを失わないように考える。 つまり、それまでの自分の考え方を広げる・深めるというイメージです。 これができるようになると、気がラクになります。 すると、怒りの感情にも流されにくくなるのです。 また、誰かに相談者がいれば、解決に近づくこともできます。 もし、近くに信頼のおける人がいれば、なおいいと思います。 最後に週に一度は、気分を変えるために独自のリフレッシュの時間を持つこと も必要です。 ヨガやストレッチなど、自分に合った時間を過ごすことです。 人の社会でなくならないのが人間関係の悩みです。 しかし、これは生きていく上では、誰もが経験することなのです。 ただ、この経験があるからこそ、人間として学ぶこともたくさんあると考える なら、ここに人生の意味を見いだすことができます。 「人間関係で悩むことを恐れない」。 こう思えば、人生の課題を乗り越える力にもなるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月26日
コメント(0)
-
【人をうらやむ気持ちとの向き合い方】
【人をうらやむ気持ちとの向き合い方】 幸せになりたい、と多くの人は願っています。 しかし、一方では自分より恵まれた人がいると、「羨ましい」と感じることも あります。 この人をうらやむ気持ちが極端に強くなると、人の不幸さえ望んだりするよう になります。 その思いがある限り、その人自身は幸せになることはできません。 人の不幸を願うこと自体、心の中は暗いマイナスのエネルギーに埋め尽くされ ているようなものです。 それは、幸せになりたいと願っていながら、実際は不幸への道を進んでいくの と同じです。 この羨ましい気持ちをプラスに生かすことが、最も大切なことだいえます。 「私もあの人のように、たくさん稼ぎたい」といううらやむ気持ちがあるなら 今以上の努力をしよう、と考え発奮材料にすることがプラスに生かすことなの です。 このとき、心の中はプラスのエネルギーが生まれ、努力することも苦ではなく なり、むしろ明るい気持ちで過ごせます。 少なくとも他人の不幸を望む必要を感じていません。 もう一つは、自分は幸せだなと思える理由をさがしておくことです。 つまり、人より何か恵まれているところがあるのではないか、という気持ちで 自分自身を見直すのです。 すると、人に対してうらやむことがあっても、人にはない自分だけが恵まれて いるところに気づくかもしれないからです。 たとえば、自分より年収が2倍の人がいたとします。 でも、その人には病気があり現在、仕事をしながら治療を受けています。 しかし、自分はいたって健康である。 これだけをみても、恵まれていることに気づきます。 そして、これからも健康な体を維持していこう、と思えばいいのです。 人には、このように他者と自分を比べて、何かで劣っている自分をより強く 感じて、人が不幸になることを願う心をもつこともできますが、反対に人より 恵まれているところを見つけ、自分の幸せを求めようという心になることもで きます。 大切なのは、自分の心の中に、暗くマイナスのエネルギーを持つ生き方がよい のか、明るくプラスのエネルギーを持つ生き方を選ぶか、なのです。 人生を損得で判断するのはいいことではありませんが、マイナスエネルギーで 生きていくのはもったいないことです。 しかも、自分ではマイナスエネルギーを持って生きていると気づかないことも あります。 自分は普段、どんな心の状態で生活しているかを見つめる時間を持つことも、 大切なことだと思います。 (by ハートリンクス)
2023年03月25日
コメント(0)
-
【幸福生活の秘訣】
【幸福生活の秘訣】 昔、あるところにとても裕福な国がありました。 この国の王様には、賢い王子がいました。 ただ、王子は何が不足なのか幸福ではなく、いつも浮かない顔をしています。 心配した王は、王子に聞きました。 「お前の欲しいものはすべて手に入るのに、どうして幸福ではないのか? 何か秘密や悩みでもあるのか?」 王子は答えました。 「とくに秘密や悩みがあるわけではないのですが、自分の人生になぜか喜びが 感じられないのです」 そこで王は、国中に布令(ふれ)を出し、王子を幸福にした者にはいくらでも 褒美を与えるという募集をしました。 まもなく、ひとりの魔術師がやってきて、 「私が王子様を幸福にいたしましょう」と申し出たのです。 そして、王のゆるしを得て王子を別室に案内し、白紙に白い絵の具で文字を書 きました。 「王子様、この紙を暗室に持っていき、ロウソクの灯を紙の下にかざし文字を あぶり出してください。それを読み、書いてある通りになさいませ。 きっとあなたは今日から幸福になれます」 王子はさっそく、暗い部屋を準備させロウソクをともし、魔術師が書いた紙を 灯の上であぶり出したのです。 白い絵の具で描かれた文字は青色に変わり、次の文字があらわれました。 『毎日一度は、誰かに親切をしなさい』 王子は、ああこれだ! これが幸福になるための秘密だったのだ、と気づいた のです。 その日から、王子は幸福な生活を過ごせるようになりました。 他者のために尽すのは、自分のために尽すことである。 これを仏教では、「利他の心」といいます。 また、「尽す」というのは、何か自分が犠牲になるのではなく、親切をする ことだけでよいのです。 自分との利害関係がある、ないにこだわらず、ただ親切をするのです。 毎日の生活をするうえで、親切なことをしよう、という気持ちでいる人と、人 の悪口言い、いつも不平不満の気持ちでいる人と、どちらが幸せか? その答えを知ることができる寓話です。 国の王子様に限らず、一般社会に生きる私たちにもいえることのようです。 (by ハートリンクス)
2023年03月24日
コメント(0)
-
【生きがいは自己を生かせば味わえる】
【生きがいは自己を生かせば味わえる】 人は自分のやりたいことがあり、それが生かされると生きていてよかった、と しみじみ感じるものです。 これが、いわゆる「生きがい」というものだと思います。 その意味では、人生において生きがいのある人と、そうでない人の違いは天と 地ほどの差があるとも言えるでしょう。 かといって、社会のために多くの人のために何かをする、という大きなことで はありません。 自分自身が喜びを感じることができることであれば、どんなことでも構わない のです。 50代の男性Kさんは、現在、「不登校の子を持つ親を支える会」のサポーター です。 Kさんが18歳のとき、両親は事業の失敗が原因で命を絶ちました。 周囲の目を避けるため、お姉さんと住む家を離れました。 それから仕事をかけ持ちしながら働き、どうにか一人立ちできるようになり、 30歳で小さなデザイン会社を立ち上げました。 そこまでの道のりは簡単なものではなく、勤めていた会社では給料が遅れたり するなどもあり、10社ぐらい転職したほどです。 ただ、18歳ときの体験から「どんなときでも明るい自分でいよう」と心に決め ていたのです。 そんな性格から、40代のころ「悩みを持つ人たちの話を聞いてもらいたい」 と頼まれるようになったのです。 それから人の話しを聞く技法「傾聴」の講座を受けたりもしました。 ひきこもりの10代の子の話を聞いたり、ときにはデザインの技術を教えなが ら話し相手になっています。 このKさんのように、生きがいとは自分が生かされ、それによって他者を支え て、相手が喜びを感じてくれることでもあるのです。 また、自分が生かされることで自身も喜びを感じているのです。 自分が得意なこと好きなことが、誰かのために生かされることは、幸せな生き 方となり、生きがいにもなり得るでしょう。 今の自分でも何か生かせることはないだろうか、たまにはそんな視点で人生を 考えてみしょう。 生きがいがあれば、生命の躍動感をしみじみ味わうことができます。 (by ハートリンクス)
2023年03月23日
コメント(0)
-
【聡明な人ほど正解を求めない】
【聡明な人ほど正解を求めない】 よく、オフィスなどで書類を机の上に雑然と置いている人を見かけます。 最近は、デジタル化で以前ほどこのような光景は見かけなくなりましたが、 それでも中には、どうしても片づけられない人もいます。 かといって、何かのときには必要な資料をいともたやすく見つけたりします。 つまり、周囲からすると見苦しくきちんと整頓しておいてほしい、と思ったり するのですが、本人は雑然とした状態がよいのです。 このように、人によってそれぞれの価値観があるのです。 人は、物事に対しては自分の正解のようなものを持っています。 はっきりしたものでなくて、だいたいこんな方向が自分にとっては正解だ、と いう基準があります。 そして何かのときに、自分が正解であるべきと思っていることとの食い違いが 生じたとき、感情的な対応をしてしまうのです。 その食い違いが立て続けにおきると、イライラして相手に対して攻撃口調での 会話になることもあります。 人にはそれぞれ個性があるように、価値観にも違いがあります。 もちろん、共通した価値観があればそれをもとに寄りそうこともできます。 それでも、価値観が合わないなと感じ、しかも毎日その人と一緒の仕事をしな ければならなくなると、感情的になるばかりです。 では、どうすればいいのでしょうか? そんなときは、「ああ、こんな価値観の人もいるんだ」と、相手と距離をおいて みることです。 どんな人も、最初から「~であるべきだ」という価値観を持っていたわけでは ありません。 育った環境や、性格によっていつのまにか、自分の正解という価値観が作られ てきただけなのです。 聡明な性格の人は、自分と違う価値観の人と意見がまったく合わなくても、む しろ、「なぜ合わないのか?」と興味を持ちます。 聡明さとは、相手の意見を聞く力があり理解力があるということ。 つまり、相手の性格を冷静に受け止めることができるので、感情的になる必要 はないと割りきる力があるのです。 さらに、聡明な人の特徴は落ち着いていて、穏やかな感じさえします。 つまり、人生にはこれだ、という正解を求めようとはしていません。 この件では自分はこう思っているから、この考えでなければダメ、という自分 の価値観を相手に押しつけている限り、かえって周囲から反発を受けるように なるのです。 (by ハートリンクス)
2023年03月22日
コメント(0)
-
【人と自分を比べない】
【人と自分を比べない】 人が人を評価するとき、「あの人は他の人に比べて〇〇が優れている」という 分析の仕方が一般的です。 とくに、企業での採用試験などはこの比較評価というものがあることで、より 優秀な人材を会社のために確保することができます。 このような場合の、多数の中から比較して評価することは、理にかなっている ものです。 そうでなければ、採用される人も切磋琢磨する努力をしなくなるでしょう。 しかし、その枠組みの中で長く生きていると、自分と同じ組織にいる他の人と、 無意識の内につい比べるようになります。 これは仕方ないことかもしれません。 ただ、自分と他者の比較をすることにこだわると、結果として自分のストレス になるのはよいことではありません。 いったん、自分が望んだ組織に入った以上は、いかに自分を向上させていけば よいかを考えて実行していくのが大切なことです。 野球ファンの方や多くの人は、WBC野球で盛り上がっています。 侍ジャパンを指導している栗山監督も、プロ野球選手としてスタートした当時 は苦労されたそうです。 教員免許を取得しましたが、野球選手になる夢を捨て切れずに、入団テストを 受けてこの世界に飛び込んだのでした。 ドラフト外で入団しますが、実際まわりには自分よりもはるかに優れた人たち ばかりでした。 さらに、2年目にメニエール病に罹ってしまったのです。 結果も出ない日々が続いたころ、2軍の監督さんから言われました。 『人と比べるな。 他の選手と比べるよりも、まず今日よりも明日、明日よりもあさってと、 少しでもお前の野球がうまくなっていけばいい』 この言葉に勇気づけられて、しだいに結果が出るようになったといいます。 この監督さんも、巨人にテスト生として入団してはじめてレギュラーになった という人だったのです。 その経験のある監督さんから信じてもらえたことが嬉しく、喜んでもらおうと 思いながら練習に励んだそうです。 人は他者と比較されることに慣れてくると、比較の世界でしか自分を見ること ができなくなります。 そして、かりに結果を出しても、自分よりさらに上の人が現われれば、自分の 評価は変わります。つまり自分が生きるのは相対評価の世界なのです。 しかし、相対評価ではなく「今日よりは明日、明日よりはあさって、少しでも 向上する」のは、自分という絶対評価の世界で生きることになるのです。 これが、個性を生かすということかもしれません。 自分が向上することは、何より楽しいものです。 もちろん、「野球が楽しい」、という境地に行き着くまでには、大変な練習量と 自己管理能力が必要です。 それでも野球の楽しさを味わえるなら、それらの多くの努力も苦にはならない のです。 人との比較で悩んだりする前に、「どうすれば自分が成長するか」ここに意識 を集めて毎日を送っていけば、生活そのものに充実感を覚えることもできるに 違いありません。 (by ハートリンクス)
2023年03月21日
コメント(0)
-
【自分の欠点を過度に気にしない】
【自分の欠点を過度に気にしない】 少しの失敗で落ち込みやすい人ほど、自分の欠点に敏感です。 その上に、より完璧さをいつも求めたいという気持ちが強いのです。 自分を向上させたいという意欲がありながら、失敗したら自分を責めてしまう ところがあるのです。 それが高じて、失敗してはいけない、という重圧をいつも感じるようになって いきます。 そして、「失敗したらどうしよう」という不安が頭から離れなくなり、心配性 の自分がとてもつらくなる、という悪循環に陥るのです。 30代のT子さんは看護師です。 T子さんは20歳のとき強迫性障害になりました。 原因は、過度の不安や心配を繰り返しているうちに、誰かが不安になることを 耳元でささやいているような感じになったからです。 当時は、看護学生でとても忙しい毎日だったのです。 いつのまにか、家を出る前に何度も戸締りをしたり、手を洗っても汚れが落ち ていないような気がして、手洗いに何十分も時間をかけていました。 心療内科で治療を受けたりしましたが、症状は一進一退でした。 そんなときに、ある助言がありました。 「先のことをいろいろ心配するより、今という現実を大切にしたらどう?」 この言葉で、気持ちがスッと抜けて楽になったのです。 看護師になりたい人は、責任感も強く、より完璧になるのも当然のことです。 ただ、過度に自分を追い詰めていくと、自己肯定感が低くなり本来の自分とは ほど遠くなるために、このような症状になることがあります。 禅の世界に「即今、当処、自己」(そっこん、とうしょ、じこ)という言葉が あります。 T子さんが、立ち直るきっかけになった言葉と同じ意味で、「この一瞬、一瞬に できることを大切にしていく」ということです。 つまり、先のことを心配するのが自分の欠点であるなら、それを気にするより 今、現実にやることをやり、その時間を大切にかみしめて過ごしていく。 この生活のリズムが確立すれば、自分の欠点も自然に気にならなくなります。 さらに、自己肯定感もバランスがとれてくると、欠点のある自分であっても、 それもまた自分のよいところではないのか、と感じるようになるのです。 欠点も長所もあるのが人である、という気持ちをもつことも、生きていく上で は大切なことです。 (by ハートリンクス)
2023年03月20日
コメント(0)
-
【感謝体質は運が向上する】
【感謝体質は運が向上する】 感謝することは大切なことだとわかっていても、人から「感謝しなさい」と言 われると、ついかしこまったりします。 とくに今の時代では、この感謝の仕方がよくわからない、という人が多いかも しれません。 正確には、「どんなふうにすれば、感謝したい気持ちが湧くのかわからない」 ということです。 「感謝」の語源は「感恩報謝」というものだといわれています。 「感恩」には、受けた恩をありがたいと思う、という意味があり、「報謝」に は受けた恩に報いる、という意味があります。 人や自然界などを含むすべての、人・モノ・事から受けた恩に対して、心から 礼をもって報いる、これが「感謝」です。 感謝することが、ふだんの生活に溶け込んでいる人は、運がよい方に向いてい きます。 たとえば、人から何かの施しを受けたら、その人に「ありがとうございます、 心から感謝します」と気持ちをこめて言います。 すると相手は、そんな気持ちで礼を尽くして言ってくれるなら、もっと何かを 与えてあげよう、あるいは、もっとよくなるような手助けをしてあげよう、と いう気持ちになります。 つまり、感謝をしたらそれだけ、またいいことが還ってくるという、いい循環 が生まれるのです。 これが、運が向上することの形です。 お釈迦様は、なかなか感謝できない人のために次のように説きました。 それは『知恩・感恩・報恩』という三つを理解しなさい、というものです。 「知恩」とは、自分がいろんなことから支えられていることを知るということ です。 これが分かれば自然に「感恩」という感謝の気持ちが生まれてきます。 感謝の気持ちが生まれたら、次に恩に報いたいな、という「報恩」の気持ちが 生まれます。 つまり、お釈迦様は自分以外のものから受けた「恩」を、しっかり受け止める ことの大切さを説かれたのです。 「感謝」したくなる気持ちになるには、「恩」というキーワードを理解すること です。 あらゆることに感謝できるなら、運は向上していくに違いありません。 (by ハートリンクス)
2023年03月19日
コメント(0)
-
【心のほぐし方】
【心のほぐし方】 仕事でトラブルがある、人との関係がわずらわしい、家族間での意思の疎通が うまくいかない、など大きな問題ではなくてもいろいろなことが重なってくる と、頭の芯が痛くなります。 このような心の状態にも、適切ないい刺激を与えると軽くなります。 つまり、これが心の凝りをほぐすことになるのです。 たとえば肩こりという症状があります。 肩の筋肉に血流がうまく流れないままだと、うっ血し痛みが生まれます。 一番大きな原因は、パソコンの使い過ぎからくるものです。 肩の筋肉を同じ状態のままにしているため、血液が流れないからです。 肩こりは、体を適度に動かさないために生じることと、他には心の緊張が続き 無意識に肩に力を入れ過ぎることからも生じます。 たんに体を動かさないのが原因なら、一時間に5分ぐらい休憩し肩を回すなど のストレッチである程度は解消するでしょう。 では、心の緊張などが原因で肩が凝る、あるいは体のどこかが痛くなるなどの とき、対処法はどんなものがあるでしょうか? 方法の一つとして効果があるのが、心をほぐすことです。 具体的に心の凝りをほぐすために、簡単にできること。 それは、自分で自分をほめることです。 これが、手っ取り早くできる方法です。 次のように自分に声をかけます。 「疲れていても、よく頑張っている。 泣きたいときや、怒りたいときも耐えている。 人が我慢できないことも、ちゃんと受け止めている。 本当に、よくやっている」 というような意味の自分なりの言葉で、自分自身をねぎらうのです。 これだけでも気持ちがラクになります。 また、自分と同じように頑張っているな、と思う人がいたらこちらからその人 に、「いつも大変そうですね、・・・」と、いうほめ言葉で声をかけるのもよい と思います。 自分をねぎらい、誰かをねぎらうことで、凝り固まった心はほぐれます。 これも、ストレス解消のアイテムとして身につけておきましょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月18日
コメント(0)
-
【よいときもわるいときもあわてない】
【よいときもわるいときもあわてない】 生きていれば、人生にはよいときもあれば、何をやってもうまくいかないとき があります。 とくに、何をやってもどんどん悪い方にいってしまうとき、何とかしなければ と焦り、あわてふためいてしまいます。 しかし、そんなときほど焦らず、静かに時間の流れに乗るような気持ちでいる ことが大切です。 イチローさんが、現役のころ次のようなことを話しています。 『普段の自分でいることが、僕の支えです。 ヒットをたくさん打つから好調、何打席もヒットが出ないから不調という のでは、自分らしいバッティングはできません。 それはあくまでも、他人の評価です。 いけないのは、何打席も打てないことを次の打席に持ち込むことです。 いつも平静でいられるためには、「普段の自分」を保っておくことです』 普段の平静な自分を保つために、打席での特徴的な動作をルーティーン化させ ていたのです。 禅語に、『日日是好日』(にちにちこれこうじつ)という言葉があります。 人生には、晴れの日もあれば、雨の日もあり、曇りの日、嵐の日もあります。 晴れの日を楽しむように、雨の日は雨の日を楽しむ。 どんなときも楽しむ。 それでも楽しみがないなら、楽しみがないことを楽しむ。 これが『日日是好日』ということだと思います。 イチローさんも、このような心境だったに違いありません。 よく、幸福と不幸は背中合わせのものである、ということを聞きます。 幸せの裏には不幸があり、不幸の裏に幸せがある。 人生では何が起きるかわからない、一喜一憂せずに、その時々を楽しみながら 生きていこう、という考え方です。 これもまた、『日日是好日』と同じように、生きる境遇に関係なく、あわてずに 生きていくのが大切であるということなのです。 よくないときの心構えができていると、好調なときでも浮つくような考えは 起きないものです。 つまり、よくないときほどあわてずに、自分自身が鍛えられるいい機会でも あるのです。 (by ハートリンクス)
2023年03月17日
コメント(0)
-
【不完全でも、満足すれば幸せ】
【不完全でも、満足すれば幸せ】 中国の古典のひとつ「菜根譚」(さいこんたん)に、次の一節があります。 『目の前に起きる出来事に足るを知る人は、悟りに近づく心境の人です。 しかし、足るを知らずにもっともっとと欲しがる人は、同じ出来事にも 不満の種にしか見えません』 原文では、悟りに近づく心境のことを「仙鏡」(せんきょう)と書かれていま すが、これは仏教の世界では悟りの世界を意味します。 また、もっともっとと欲しがる心のことを「凡鏡」(ぼんきょう)と書かれ、 これは迷いの世界を意味します。 つまり、この菜根譚での一節は中国の思想家・老子が説いている、 『足るを知る者は富む』という言葉に共通しています。 目の前の事、置かれている生活環境など、自分に関わる一切の出来事が不完全 で不足していても受け入れ、それなりに満足できる人は幸福な人。 しかし、現実では欲しいものは欲しいと思い、手に入れたいと考えるのが世の 常です。 今のような、便利なのが当たり前の社会で暮らしていると、何かが不足したり すると世の中は混乱してしまいます。 たとえば、今度の冬は鳥インフルエンザが流行したために、卵が不足するとい う社会問題になっています。 卵は安価で、いつでも手に入るという社会の仕組みに人々は慣れてしまったの です。 このように、食料品や生活物資の不足も、何かのきっかけで不足したとき、人 の心の習慣をすぐに変えるのはとても難しいのです。 ただ、ものは考えようでこのようなモノ不足のときに、不満を感じてもそれに 対応できるような心の準備をしておく、よい機会でもあるのです。 それには、考え方を少しだけずらす視点をつくっておくのがよい方法です。 それは心の持ち方の修正をするということです。 人はだいたいの傾向として、完全であることに対して憧れる生きものです。 とくに、完全主義の強い性格の人ほど、自分が決めたことにほど遠い結果だと ストレスを感じます。 そこを、ハードルを下げることでストレスは減り、不足していてもそれなりに 満足感をおぼえることができるものなのです。 そのためには、「これくらいで上等だ」「まあまあだけど、これでいい」という とらえ方もできる自分を持つことです。 このような気持ちになる回数を増やしていけば、モノの考え方に幅が出てくる でしょう。 心の習慣を変えるには、極端ではなく身近にできることから、少しずつ修正し ていくようにすれば、よけいなストレスに悩まされることはありません。 (by ハートリンクス)
2023年03月16日
コメント(0)
-
【「ねばならない」、の気持ちは苦しみのもと】
【「ねばならない」、の気持ちは苦しみのもと】 「明日も仕事に行かなければいけない」「明日も学校に行かなければならない」 と、このように、何かをしなければいけない、という意識で自分の一日の行動 を決めている人は多いのではないでしょうか。 むしろ、この意識があるからこそ人は生きているといえるかもしれません。 これは一つの義務で、やりたくなくてもしなければいけないことなのです。 そして、自分に課せられた責任ということもできます。 もちろんこれは、ある程度は社会として必要なものです。 ただ、この「~しなければならない」という気持ちが強すぎて、自分を窮屈に してしまうと、心のバランスが失われることになります。 代表的な例は、スポーツに関連したものです。 高校や大学などのアマチュアスポーツでは、伝統的に優れた特定のスポーツが あり、「何としても今度の試合では優勝に近い結果を出さなければならない」 という「結果」を求めます。 これが、選手たちのプレッシャーになり本番の試合では日頃の実力が発揮でき なかった事例はたくさんあります。 反対に、このプレッシャーのおかげで選手たちは、ふだんの練習のとき以上の 力を出して思わぬいい成績を残したという例もあります。 つまり、この「何としても~しなければ」という意識には、功罪の両方が潜む ものなのです。 この傾向は、これまでもかなり多く見られました。 しかし、最近ではこれとは違うメンタル指導者が現れています。 その特徴は、試合を楽しむこと。 勝負に勝つことは大切なことだが、それがすべてではない、ということ。 この二つに集約されます。 これは今からの新しい時代に求められるメンタル志向だといえます。 なぜなら、この考え方は一般社会人にも当てはめてみると、実に有効な考え方 でもあるのです。 つまりこうです。 一つは仕事を楽しむこと。 人生で成功するのは大切なことだが、それがすべてではない。 成功するかどうかより、幸せであるかどうかが大切だ。 このような考え方です。 「~しなければならない」「~でなければならない」という意識だけでは、最後 は、自分を縛ることになり生きづらくなる、ということです。 それよりも、どうすれば学校も仕事も楽しくなるのか? と考えるのが大事な ことなのです。 どうせやるなら、楽しんだほうがいい、という考え方。 これは苦しまないための、最も有効な考え方だといえるでしょう。 そう思うと、よけいに努力してがんばろう! という前向きな意識も生まれて くるのです。 自分で自分を縛りつけずに、もっと解放された気分になりましょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月15日
コメント(0)
-
【まじめさの中にも、リラックスを忘れない】
【まじめさの中にも、リラックスを忘れない】 心のリズムが乱れると感情が安定しなくなり、ちょっとしたことにもイライラ するものです。 そのような人に共通しているのが、きまじめで責任感が強いことです。 きまじめでありながら、責任感が人より強いために、他者への気遣いもできる ことから誠実さも魅力として持っています。 ところが、それらのよいところがあるのに、まじめさと責任感にも自分の限界 を超えてしまうと、これがストレスに変わってしまうことがあります。 これは、「責任はすべて自分にある」、と過大に受け止めるからです。 責任を感じること自体は、自分を鍛えていく上で大切な要素ですが、それが度 を過ぎると、自分自身を傷つけてしまうのです。 これは、自分に対してどこか緊張した心があるからです。 緊張とは、「失敗してはいけない」という不安から生じる感情の高ぶりです。 入学試験や就職試験でもそうですが、ほとんどの人はこの「緊張」という経験 をしています。 緊張するのは悪いことでもなく、当たり前に生まれる心の状態です。 また、この緊張が適度なものであるからこそ、いい結果も生まれるのです。 弓矢の弦も、引っ張られてはじめてその勢いで矢が飛びます。 引っ張られ過ぎれば弦は切れ、引っ張られる力が不足すれば矢は飛びません。 つまり、最大であり限界の少し手前のところ、これが適度な緊張なのです。 適度である、というのはそこに余裕があるということです。 これが、「リラックス」です。 リラックスするというのは、気持ちや心に力みがない。 力が入り過ぎていない状態です。 さらに、このリラックスしていることが、通常の力以上のものを発揮させてく れます。 また、リラックスするとそこに置かれている状況を、冷静に感じ取ることにも なり、むしろ楽しむような心境にさえなれるのです。 緊張することと、リラックスすることをうまく使い分けることは、生きていく 上においても、質の高い人生を過ごせることになるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月14日
コメント(0)
-
【自分を大切にする生き方とは】
【自分を大切にする生き方とは】 カルフォルニアに、100歳を超えたアンディおじいちゃんがいました。 彼はセーフウェイという大きなスーパーの、乳製品部門のマネージャーを務め ました。 ニックネームは「チーズおじいちゃん」です。 人生は、チーズつくりのようなものだと、人生訓を考えました。 その中に次のような言葉があります。 1、人生はデリケートなもの。だから自分を大切にしよう。 2、あなたの家族は、人生でもっとも貴重なものです。 3、今すぐお金を節約しましょう。そのお金は後で使いましょう。 4、本当の自分になることを恐れてはいけません。 5、愛は、いつも簡単ではありません。ときには努力も必要です。 6、どんな状況でも、何か笑えるものを見つけよう。 7、むずかしく考えすぎずに、肩の力を抜こう。 8、自分を幸せと落胆のどちらに導くか、決めるのはあなたです。 人には、自分自身のために決める力があるのです。 自分を大切にするとは、どんなことなのか。 これは、何かに迷い悩んだりすることがあっても、考えすぎず肩の力を抜いて リラックスすることです。 そのためにも、その日を無駄に過ごさないように心がけることです。 アメリカの牧師、ロバート・ジョーンズ・バーデットさんが述べています。 『人間には、一週間の中で二日だけ悩まずにすむ日があります。 怖れや不安におびえなくてもよい二日です。 その一日は、きのう。 そして、もう一日は、あしたです』 これは、今日という日を、恐れと不安の日にしてはいけないということです。 人はなぜか、きのうのことに後悔して、あした起きる出来事に不安を感じる ものです。 そんな毎日を送っていては、自分を大切にした生き方とは言えないのです。 チーズおじいちゃんが教えてくれたことの一つでも、心に言い聞かせていく。 すなわち、この習慣が自分を大切にすることになるのです。 (by ハートリンクス)
2023年03月13日
コメント(0)
-
【思い通りにいかなくても怒らない】
【思い通りにいかなくても怒らない】 たいていの人は、自分の思い通りにならないとイライラした気持ちになりがち です。 とくに、自分は正しいことをやっているのに、相手が間違ったことをしている ために、自分にその責任がかかってくるときなど、怒りさえ覚えます。 このような経験をした方も多いのではないでしょうか? 世の中とは、自分が思っているようにはいかないものなのです。 ただ、そこであきらめてしまうことは、必ずしもいいとは限りません。 精神科医の斎藤茂太さんが、イライラクヨクヨせずに、毎日をできるだけ充実 した気分で暮らすための心がけをあげています。 その中に、『人は変わらないものだと諦観しよう』と述べました。 諦観(ていかん、もしくは、たいかん、とも読みます)とは、見極めるという 意味があります。 よく、あきらめることだと勘違いすることもありますが、「そういうものだ」 とあきらめに近い思いがありながらも、見極める心境のことです。 たとえば、自分中心で考えてばかりいる人がいたとします。 その人に変わって欲しい、と思っても相手にその気がないなら、変わることは できなません。 むしろ、「あの人はそんな考えをする人である」、と見極めてしまう。 この諦観で、その人に対するイライラの感情はゼロにはならなくても、静める ことはできます。 もう一つが、今お話したように相手を見極めたときに、自分自身が変わった、 ということになります。 つまり、自分が変わればよいのです。 相手に対する見方が変わったというのは、自分が変わったということにもなり ます。 また、自分自身も他者から見たとき、もしかしたら「あの人は、頑固な人だ」 思われているかもしれません。 このように、こちらが特定の誰かに変わって欲しいと思っていても、一方では 自分も他の誰かから、変わって欲しいと思われていることがよくあるのです。 こんなたとえがあります。 人は、自分の首の前と後ろに、カゴをいつも下げている。 前にあるカゴには、人の欠点がたくさんあり、いつも目についてしまう。 後ろにあるカゴには、自分の欠点が入っている。 また、目の前のカゴは大きく、後ろには小さいカゴしか下げていない。 目の前にある人の欠点は目につきますが、後ろの自分の欠点はほとんど見ない し気づかないものなのです。 そうではない人もいるのですが、往々にしてその傾向があるのが人です。 思い通りに行かないことがストレスなら、人や物事に対する見方を変える機会 になるかもしれません。 思い通りにならないときこそ、自分を高めることができるときだ、と考える。 そう考えるとイライラの気持ちも穏やかなものに変わっていくのです。 (by ハートリンクス)
2023年03月12日
コメント(0)
-
【孤独な自分を嫌いにならない】
【孤独な自分を嫌いにならない】 まわりの人たちとよい関係をつくることができて、その場の雰囲気を乱さない タイプの人をよく見かけます。 しかし、心の奥では意外にもストレスを抱えていることがあります。 それなりの立場があり、リーダー的な存在である人に、このような傾向ストレ スがあるようです。 自分の意見はさておき、みんなが白と言えば白の意見を述べ、黒ならそれに近 いように振る舞い、意見が半々なときは中立の立場をとる人です。 本当はハッキリとした意見があるのに、言えば全体の空気を乱してしまうので はないかと気を遣っているのです。 つまり、本当の自分を抑え続けているのです。 この状態が続くと、ストレスはたまるいっぽうです。 そして、「私のことを誰も理解してくれないのはなぜ?」というような気持ちが 強くなっていきます。 これがストレスになるのです。 自分だけが苦しんでいるのに、誰にもわかってもらえない悔しさを感じ、また、 意見をはっきり言えない自分を嫌っています。 これらがまとまって、次は孤独という別のストレスになっているのです。 一見すると、自分のことより他人のことを気にしていて、やさしくていい人の ように思えます。 しかし、よく考えると自分を抑えてまで、他人に合わせて自分を苦しめる必要 はないのです。 そもそも孤独感というのは、自分と他者との人間関係を前提として感じるもの です。 自分は一人が好きだ、人と関わり合うのは好きじゃない、と考える人にとって 孤独はイヤだ、などと最初から思わないのです。 また、孤独は寂しいなどとも考えないのです。 つまり、孤独感をストレスと感じている自分の生き方を少し変えることが大切 なのです。 人間関係の基本は、相手と自分の感じ方、意見に違いがあって当然だ、と認識 することです。 「みんなはそう思うかもしれないけど、私は少し違う」と相手を認めて、批判 せず傷つけないような言い方で、自己主張できる自分になるべきです。 そんな自分になれば、「私のことを誰も理解してくれない」という、気持ちも 起きないようになります。 テレビドラマや映画では主役となる、「主人公」が必ず登場します。 この「主人公」というのは、もとは禅の言葉から来ているそうです。 むかし、ある高名な禅僧が自分に問いかけるときに、自分に対して「主人公」 という言葉を使っていたことに由来しています。 つまり、自分の人生は自分のためのものであり、「自分が人生の主人公」でな ければならない、と考えたのです。 周囲と調和することは大切ですが、「自分の人生は自分のものである」、と自覚 するのはもっと大切なことです。 孤独を愉しむことも、生き方の一つだと思ってみましょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月11日
コメント(0)
-
【夢を実現させる法則】
【夢を実現させる法則】 人は夢をみることができる生きものです。 夢があると、生きる力が湧いてきて、その夢を実現するための方法を必死で 考えるようになります。 ウォルト・ディズニーが夢を現実のものにするには、4つの法則があると語り ました。 まず、好奇心。 次に、勇気。 そして、継続。 最後に、自信。 厳密に言えば、好奇心と勇気と継続だと思います。 自信は、この三つが揃えば自然に生まれる心だからです。 ウォルト・ディズニーがディズニーランドを創ったのは、55歳のときです。 すでに、人生の峠を越えたと言われてもおかしくない年齢でした。 彼は、好奇心と勇気と、それを続ける継続の力を引き出してきました。 若いとき、漫画家になりたいと夢をもって新聞社に入りました。 そこでは、「君にはセンスがない」と言われて解雇されました。 すると、友人とデザイン会社を始めましたがうまくいきません。 その次にアニメの会社をつくりますが、資金が不足して倒産しました。 それでも、マンガを基本にした夢は捨てきれなかったといいます。 そして、アニメのキャラクター「ミッキーマウス」を考えついたのでした。 会社は大きくなり、子どもや大人が家族で楽しめる「夢の国」を創りたい、と 計画を立てたのが53歳のときです。 その資金を工面するために、銀行に融資の申し込みをしますが、何回も断られ そのたびに企画書を書き直して、融資を受けることができました。 そして、「ディズニーランド」はスタートしました。 一年目に400万人の来園者があり、大成功です。 日本では1957年に、三越本店の屋上で期間限定で「ディズニーランド」を 開園し、それから25年かかり「東京ディズニーランド」が生まれました。 ウォルト・ディズニーは次のような言葉を残しています。 『夢があるなら、実現できます。 あなたにしか、かなえられない夢があるのです』 夢を実現するための法則は、とてもシンプルです。 『好奇心と勇気を継続』し、そこから「自信」が生まれる、という法則は誰に でも共通するものなのです。 (by ハートリンクス)
2023年03月10日
コメント(0)
-
【苦労と努力で人は成長する】
【苦労と努力で人は成長する】 学生時代は、先生や親から「もっと勉強しなさい、努力しなさい」と言われ、 社会人になれば、上司から「もっと努力しなさい、苦労しなさい」と言われた ります。 ただ、最近では就職したばかりの若者に、このような言い方をするのは少なく なる傾向があるようです。 「苦労」や「努力」という言葉からは、ストレスにつながる響きがあります。 理由は、プレッシャーや精神的な苦痛をともなうからでしょう。 本当は苦労も努力も楽しめるもの、として受け取ればモチベーションは高まる はずです。 このような意味で次の言葉に触れると、少し気分はかわります。 経営コンサルタントの小宮一慶(かずよし)さんの文章です。 苦労と努力の違い 人には苦労と努力の両方が必要 人が宝石の原石なら 努力は宝石を大きくする 苦労は原石を磨く 苦労によって、原石は磨き削られ、光り輝く宝石となる 努力だけの人は、宝石は大きいがトゲがある 苦労だけの人は、トゲはないが宝石が小さい 人という宝石の原石には 苦労と努力の両方が必要 まず、自分とは宝石の原石という存在であると知ること。 ここが一番大切なところです。 人というダイヤモンドは、原石ままでは価値がありません。 磨かれて、削られてはじめてその価値が大きくなります。 自分は努力をしたのだ、という自負心の背後には、つらくても努力してきた から私は偉いのだ、という天狗の心があるのです。 その天狗の心がトゲです。 自分は苦労したのだ、という自画自賛の背後には、つらくても苦労に耐えて きたから私は偉いのだという、狭い視野の心があるのです。 その狭い視野の心では、宝石としての価値は小さいのです。 苦労とは行動というエネルギーであり、努力とは自分の内面を掘り下げていく エネルギーです。 自分という存在は、宝石の原石なのだから、行動しながら心を練り上げていけ ば大きな価値のある人間になることができるのです。 そして、もっとも大切なのが、苦労も努力もエネルギーは必要ですが、楽しい ものであるということです。 今日からWBCの野球の試合がスタートしますが、選手たちは優勝を目指して きつい練習をしてきました。 しかし、試合そのものを楽しいと感じているのです。 試合というプレーを通して自分の能力を発揮することが楽しい。 そのための練習をするのです。 しかも、技術の向上とそれに必要なメンタルの使い方も訓練しています。 苦労と努力は結局は楽しいものだ、と思えることが最高の生き方です。 (by ハートリンクス)
2023年03月09日
コメント(0)
-
【幸せが逃げていく生き方】
【幸せが逃げていく生き方】 誰もが幸せになりたいと思っています。 そのために、イヤなことがあってもストレスと格闘しながら毎日仕事に取り組 んでいます。 ところが、幸せを求めているのに、実際は幸せが逃げていくような生き方をし ていることがよくあるのです。 これは、自分では気づいていません。 では、幸せの求め方のどんなところが間違っているのでしょうか。 経済評論家で公認会計士の勝間和代さんは、明るい口調での発言で人気の あるコメンテーターの一人です。 この勝間さんが著書の中で、幸福な人と不幸な人の比較をしています。 その中からいくつか要約してみました。 (幸福の源泉について) 幸福な人…幸せの基準を単一のものに求めず、「稼ぐ」「使う」「愛する」「愛さ れる」の循環が構築できるように分散して使う。そのため、特定の 仕事や家庭にしがみつかず、何かが悪くなっても対応できる。 不幸な人…幸せの源泉を何か特定の一番身近なもの、例えば仕事や、子ども、 恋人などに一極集中してしまう。その結果、環境変化が起きたり、 状況が悪くなると、一気に不幸になってしまう。 (理解力と感情の使い方について) 幸福な人…他人の悪口、非難などが、めぐりめぐって自分の足かせになること を理解している。そのため、ネガティブなことや批判的なことは口 にせず、不満がある時は問題の解決につながるような建設的な批判 をするよう心がけている。 不幸な人…不満があると、相手の欠点を見つけて批判、非難を言い、一時的な 精神のやすらぎを得る。ただ、その結果自分は何も変わっていない のに、自分がよくできると勘違いし、もっと自分を安心させるため に他人を批判するようになる。 (幸せの基準について) 幸福な人…幸せの基準は自分にあり、自分の中で喜びを感じること。 自分の持ち味や特性を生かせることは何かを自覚して選び、集中し て伸ばしていく。その結果周りも、その人を応援したくなる。 不幸な人…幸せの基準を外から見える自分に求め、年収や社会的立場などの ランクにとらわれてしまう。 その結果、ランク主義者しか、周りに集まらなくなる。 (勝間和代著「不幸になる生き方」集英社新書) 勝間さんは転職を繰り返しながら、シングルマザーとしての人生を歩んできま した。 30代のとき、強いストレスからメニエール病、十二指腸潰瘍となりますが、 そこから再起しています。 幸せの基準は自分自身の中にあります。 ただ、世界は比較競争で成り立っていることもあり、どうしても収入や地位と いう“ものさし”(基準)になってしまいます。 収入や地位が高いことはよいことですが、人の心が感じる幸せの基準は個々に よって違っているはずなのです。 収入や地位というものが高くなくても、とても幸せだと思って生きている人も たくさん存在しています。 幸せの基準をもう一度見直してみましょう。 もしかすると、今までの求め方にどこか間違っていたところに気づくかもしれ ません。 (by ハートリンクス)
2023年03月08日
コメント(0)
-
【どんなときも楽しく生きる】
【どんなときも楽しく生きる】 心理学者の加藤諦三さんが、次のように語りました。 『イライラするのは、心の外側で今起きていることにイライラしているの ではない。 外で起きていることを通して、もともとイライラしている心の中が刺激 されているだけである。 イライラするのは、その人の「心の土台」の問題である。 「心の土台」が憎しみである限り、イライラからは逃れられない』 心の土台というのは、その人がいつも考えていることがプラス側なのか、また マイナス側なのかということです。 または、考え方の傾向とも言えるでしょう。 人生は辛いもの、という思考が基本にあるなら、辛いというところから人生を 眺めます。 人生は楽しいもの、と思うことを軸に考える人は楽しいという世界から自分を 見つめます。 中には、生きていれば辛いこともあれば、楽しいこともある。 だからクヨクヨしないで、ボチボチ生きていこう、と思っている人もいます。 つまりいずれが、正しいか正しくないか、という問題ではありません。 また、別の心理学の専門家は、 『世の中には、幸福も不幸もない。 あるのは、本人がどう感じるか、それだけのことである』と言います。 多少、つれない表現ですが言われてみればそうだ、と思うこともできます。 自分のまわりに起きる出来事のひとつひとつを、グレーのレンズで見るのか、 透明のレンズで見るのか、レンズの色によって見える世界が違ってきます。 いちばん大切なのは、モノの考え方や見方がその人の心に大きな影響を与えて いくことです。 現実があり、そこから何を感じとるかで心の状態も変わります。 また、最悪だ、と思える状況がきっかけになり成功や幸福を手にすることも あるのです。 ある女性が失恋をして、イライラを解消するために行ったこともないパチンコ 店がたまたま目に止まり、気晴らしにやってみようと思いました。 結果はひどいもので、財布は空っぽになりました。 イライラはさらに増幅し、パチンコ店を出たとたん一人の男性にぶつかってし まいました。男性も仕事のことでイライラしていました。 ぶつかってお互いは口論になりました。 ところが、相手をよく見ると、高校生のときのクラスメートだったのです。 それがきっかけになり、二人は結婚しました。 二人の間に生まれたのが、後の書道家・武田双雲さんです。 このように、一時期の不幸と思える出来事も、いつ幸福に転じるかわからない のです。 どんなときも、何があっても、自分が生きていることには意味がある。 どうせなら、楽しく生きていこう、という人生観を持つか持たないか。 「生きるのは辛く苦しい」か「生きているだけで意味があるから感謝しよう」 の、どちらの考えを選ぶのか、自分しだいなのです。 (by ハートリンクス)
2023年03月07日
コメント(0)
-
【疲れたら時間の使い方を見直そう】
【疲れたら時間の使い方を見直そう】 疲れてくると、時間のたつのが遅く感じます。 反対に、調子がいいときは、一日があっという間に過ぎてしまいます。 このように、時の流れの感じ方と心身の状態はつながっています。 疲れたら休息をとるべきなのですが、真面目で責任感の強い人は仕事を優先し がちです。 本当は、そういう場合はあえて、休もうと決めるだけでラクになります。 これは、時間を区切ることによって、今の自分のつらい状態の終わりが見えて くるからです。 マラソンでも、ゴールが見えてくると不思議とまた元気になれます。 これと同じことなのです。 アメリカのある企業での調査ですが、2週間以上の長期の休みが決まっている 人は、約2か月も前から幸福度が高まるのだそうです。 「あと、2か月すれば長いバカンスで海外旅行ができる」、こう思うと何か幸せ を感じるというのです。 このように、時間を区切ることで、心の状態は変化すると知っておけば、時間 の使い方、時間に対する考え方に工夫も生まれます。 心と体が疲れやすくなるのは、仕事をするのと休息をするバランスがくずれて いるからです。 この調整がうまくできる人は、心が疲れたら体を動かしたり、体が疲れている ときは、体を休めつつ心のケアもする、などいろいろな工夫をしています。 大切なのは、リラックスできる時間をつくること。 次に、自分の好きなことを持つこと。(趣味やスポーツなど) そして、深呼吸をするクセを持つこと。 とりあえず、これだけでもやってみると、心身の疲れは最低限度に抑えること ができるでしょう。 愚痴や弱音を吐くことも、すべて悪いことではありません。 愚痴や弱音を言うときの心は、素直な状態になっているときです。 素直に自分の弱さを認めると、ラクになれます。 また、タメ息はよくないと言われますが、タメ息は呼吸が浅くなっているから 生じる反応です。 息を吐き出して、新しい酸素を吸入するためにタメ息をしています。 しかし、タメ息ばっかりつきたくなるのは、どこかに異常がある可能性もあり ますから、病院の診察を受けたほうがよいかもしれません。 穏やかな心になるためにも時間を区切り、その上で時間の使い方に工夫をして みましょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月06日
コメント(0)
-
【ストレスを消すには好きなことに集中する】
【ストレスを消すには好きなことに集中する】 神道に「中今」(なかいま)という言葉があります。 「中今」とは、今現在を大切にして生きることが人の正しい生き方である、と いうことです。 神道は日本独特の思想文化で、仏教やキリスト教、イスラム教という宗教とは 少し違った成り立ちがあります。 お正月には、ほとんどの人が近くの神社に初詣に行きます。 お寺や仏閣とは雰囲気とは違い、神々しい気持ちになります。 神道は、清く正しく明るい心の持ち主になろう、という文化でもあるのです。 さらに、「中今」の考えは過去(先祖)を敬い、感謝して今現在に生きること が、未来につながるというものです。 つまり、「今」の連続が過去・現在・未来ということです。 さて、今現在を大切にして生きるとは、具体的にはどんなことなのでしょう? それは、自分の好きなことに集中する、ということです。 自分の好きなことに集中し、その世界に没頭しているときは、ストレスがない 状態です。しかも楽しく、時間の流れを忘れています。 このような時間を週に1~2日過ごすだけで、仕事や人間関係のストレスを消 すことができるのです。 どんな人にも、自分が好きなことの一つや二つはあるはずです。 お酒や賭け事は別にして、大自然にふれたり、スポーツを楽しんだりいろいろ なものがあります。 楽しいな、と思える好きなことを続けていくと、「今現在を生きているなぁ」 と感じることが多くなります。 それが、感性を日常生活の中で磨いていることになるのです。 たとえば、食事をするときですが、テレビやスマホを見ながらではなく、でき れば、家族との会話だけにして、その上で、食べることに集中するために料理 を味わう。これを習慣にするだけでも違います。 料理を口に入れたら、味わいを楽しむ。 これを意識的に行い続けると、「中今」の感覚が身についていきます。 生きている以上、何かのストレスや悩みはついてきますが、それでも溜まった 疲れや心の垢を落としていくのは大切なことです。 好きなことに集中し、ストレスを消していきましょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月05日
コメント(0)
-
【内気でもよい人間関係はつくれる】
【内気でもよい人間関係はつくれる】 自分の気持ちを表に出すことが苦手な人がいます。 周囲には控えめな印象を与えているのですが、反面、自分の意見をはっきりと 言えないために、損をすることもあります。 内気な人には、優しい気持ちをもっている人が多いようです。 相手から嫌われるような言い方をするわけでもなく、言われたことに反対もせ ず敵を作るタイプの人ではありません。 ただ、内気なために自分のよさが人に伝わりにくいという点で、もったいない とも言えます。 なかには、内気な自分から脱皮したいと思っている人がいるかもしれません。 しかし、少しだけ考えを変えれば内気な自分から抜け出せることはできます。 内気であるのは、人と会う、話すことに不安を感じやすいからです。 自分が相手からどのように思われるのか、これがとても気になるのです。 もし、自分が「変な人だな」と思われたら恥ずかしい、と思っています。 つまり、自分のことを気にしすぎているのです。 ただ、これは自意識過剰の状態と同じことなのです。 控えめであるのに、自意識過剰という自分を変えるには、自分は相手のことを どのように思っているか、をより強く考えることです。 つまり、自分のことよりも相手のことを強く考えることで、自意識過剰な自分 が気にならなくなるのです。 さらに、相手との新しい関係が生まれることを楽しもうと考えれば、前向きな 気持ちにもなれるでしょう。 ただし、人間関係をつくることに焦りは禁物です。 よい人間関係をつくりたいと思うとき、相手と自分との価値観や人生観などが 極端に違っていたり、話していて違和感があるなら避けるべきです。 よい人間関係の基本は、互いが適度な距離を保ち、信頼できることです。 人間関係について、思想家である孔子が次のように言いました。 『和して同ぜず』 これは、人と仲良くして同調することはあっても、何でもかんでも同調せず、 自己の主体性を持ちなさない、という意味です。 自分を偽り、無理をしてまで相手に合わせる必要はないのです。 この「和して同ぜず」の心がしっかりすれするほど、内気な自分ではなく自分 の考えも胸を張って言えるような、自信のある生き方ができるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月04日
コメント(0)
-
【心配するより、楽しくなることを考える】
【心配するより、楽しくなることを考える】 人は、将来のことを想像するとき、「この先どうなるのだろうか?」と不安な ことを考えます。 この場合に感じる不安は、今の幸せを守りたいあるいは、今よりも恵まれない 状態にはしたくないという守りのための思いです。 この点では、しごく当然の心のはたらきといえます。 将来の生活を守りたいがために、不安があるならそれを少しでも減らしておこ うという備えです。 問題は、その不安に振り回され、今現実の生活が苦しいものになるようでは、 本来の「不安」の役割が果たされていないことになります。 ちょっとしたことですが、人は案外このように不安に振り回されている、ある いは不安に押しつぶされやすいものです。 心配もこれと同じです。 つまり、悪いことが起きることを予想しているのです。 しかし、これは一種の自己暗示だと言うことができます。 ただこれは、不安を避ける努力をする一方で、不安や心配なことが起きること を予想するという自己矛盾とも言えるのです。 人の心は、不思議かつ複雑です。 このような自己矛盾を、人は往々にして持っているものです。 また、この不安や心配なことが解消されても、それはネガティブな感情が一時 的に減っただけで、幸福になれるというわけでもありません。 これらを解決するには、不安や心配なことを予想するより、楽しいことや期待 できることをより多く予想し、考えることが最も効果があります。 人は、どんなに幸福になっても、不安と心配なことをまったく考えないという ことはできません。 それはそのままにして、別のところで楽しく期待できることをたくさん考える ようにするのです。 不安な気持ちを忘れるとか、捨てるというようなイメージを描くのではなく、 ポジティブなことを選択するのです。 この考えは、人や物事に対する感情の持ち方に応用することもできます。 不平不満、怒りなどが生じたとき、それらを消すことは簡単ではありません。 ネガティブな感情に流されない努力はしながら、一方では、ポジティブな感情 を選んでいくように、自分に言い聞かせる(自己暗示をかける)のです。 人は、毎日を感情のサイクルの中で生きています。 自分にとって害となる感情より、得する感情を選べるようになること。 もちろん、それなりに時間をかけて自分で心のトレーニングをすることは必要 です。 ただこれも、自分の幸せのためと思えば、楽しみながら取り組むこともできる と思います。 (by ハートリンクス)
2023年03月03日
コメント(0)
-
【健康な心にフタをする感情とは】
【健康な心にフタをする感情とは】 体にどこか悪いところがあり、あるいはケガなどで体の一部が自由にならない ときでも、心だけは健康に保つことができます。 また、心に何かのモヤモヤがあったりすると、体の具合が悪くなることがあり ます。 このように、体の健康も大切ですが心の健康はさらに大切です。 ブッダは、修行僧が悟りを得ようとして禅定(瞑想)をするとき、五つの煩悩 があるから気をつけなさいと言いました。 つまり、修行の妨げや障害になる五つのことがどんなものかを示しました。 また、普通に暮らす庶民においても、同じ五つの煩悩によって心が乱されるの で注意するようにと教えています。 『五蓋』(ごがい)というものでわかりやすく言えば、次のようなことです。 つまり、人間の健康な心に蓋(ふた)をしてしまう、五つの感情です。 1、欲張ること。 欲張ると、他人からよく見られたいと見栄を張り、身の丈にあった生活が できなくなる。 2、小さなことに怒ること。 自分の思い通りにいかないことがあると、すぐに怒る。 怒りは、相手を不愉快にして自分も傷つけている。 3、小さな過ちに、クヨクヨして嘆くこと。 クヨクヨしても嘆いても、何も変わらない。次にすることを考えること。 4、他人の過ちに、イライラすること。 感情が乱れたままでは、おちついた心にはなれない。 おちついた心でなければ、物事の正しい判断ができない。 5、他人をすぐに疑うこと。 人を疑う気持ちがあるのは、自分に自信がない証拠である。 心が弱いということだから、物事をやり通すことができない。 これらの五つが、本来の健康な心にフタをする障害の心です。 注目すべき点は、修行僧も民衆も共通している内容であることです。 ブッダは、仏の道を目ざす修行僧も現世で暮らす一般の人々も同じ人間として 見ています。 立場に関係なく、尊い存在として見ているのです。 ブッダの考え方は、現代の西洋心理学をはじめ、他の古典思想との共通点が多 くあります。 このような考えがあることを知っておくだけでも、自分の心の状態がおかしく なったときに、役立つこともあると思います。 (by ハートリンクス)
2023年03月02日
コメント(0)
-
【相手目線の仕事が成功のコツ】
【相手目線の仕事が成功のコツ】 この世の中では、仕事の目的の一つはお客様に喜んでもらうことです。 物品販売でも、飲食店のようなサービス業でもみんな同じです。 仕事をするときは、いかにして買ってもらうかを考えます。 どんなにいい商品でも、売る側のまごころが伝わらなければ買ってもらうこと はできません。 まったく同じ商品を売る人が何人かいても、売り上げの多いか少ないかの違い が生じます。 以前はよく、「商品を売るのではない、自分を売り込め」と言われていた時代 もありました。 今は、こうした考えもあまり聞かなくなりました。 こんな話があります。 ある住宅販売会社の営業マンKさんは、毎月ほとんど売上額がトップです。 ただ、営業トークは人並以下です。それでも成績がよいのです。 それには、理由がありました。 展示会の会場に、一戸建て住宅を購入したいというお客が見えました。 ひと通り、展示された住宅内を見て回ったお客との相談が始まります。 すでにKさんの他にも、別の営業マンが接客しています。 あるご夫婦を、Kさんが接客することになりました。 玄関から、キッチン、リビング、寝室などのどんな間取りを希望されるのかを 聞いていきます。 Kさんが、ご夫婦の希望を聞きながらある見取り図を描きはじめます。 すると、そのご夫婦が少し驚いたような感じになりました。 よく見ると、話しを聞きながらまっ白な図面に、Kさんから見て逆さまの絵を 描き始めたのです。 つまり、対面するお客様が見やすいように、見取り図と文字を逆から描く特技 を持っていたのです。 じつはKさんは、最初は口下手だったこともあり、なかなか営業成績が上がり ませんでした。 そこで、人とは違う何か別の技術を身につけよう、と考えたのがこの逆さまに 描くことだったのです。 対面するお客と、提案にしたい自分の意思の疎通をはかれば、きっと売り上げ も伸びるに違いないと考え訓練したのです。 相手目線で考えるようになると、相手の気持ちがよく伝わってくるようになり Kさんはお客からの信用と信頼を得ることになりました。 相手目線とは、相手の立場になって自分の問題として考えることです。 これは、人間関係においても同じことがいえます。 自分の意見を持って話し合うことも必要ですが、それ以上に相手の意見を相手 の身になって聞く姿勢があれば、感情的になりにくいのです。 相手の身になっているので、相手を理解できたことの喜びが、感情より勝って いるために、いら立つことも少なくなります。 仕事の成功は、自分の幸せの大きな要素です。 相手目線で物事をながめれば、対人関係でのムダな争いもなくなるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年03月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1