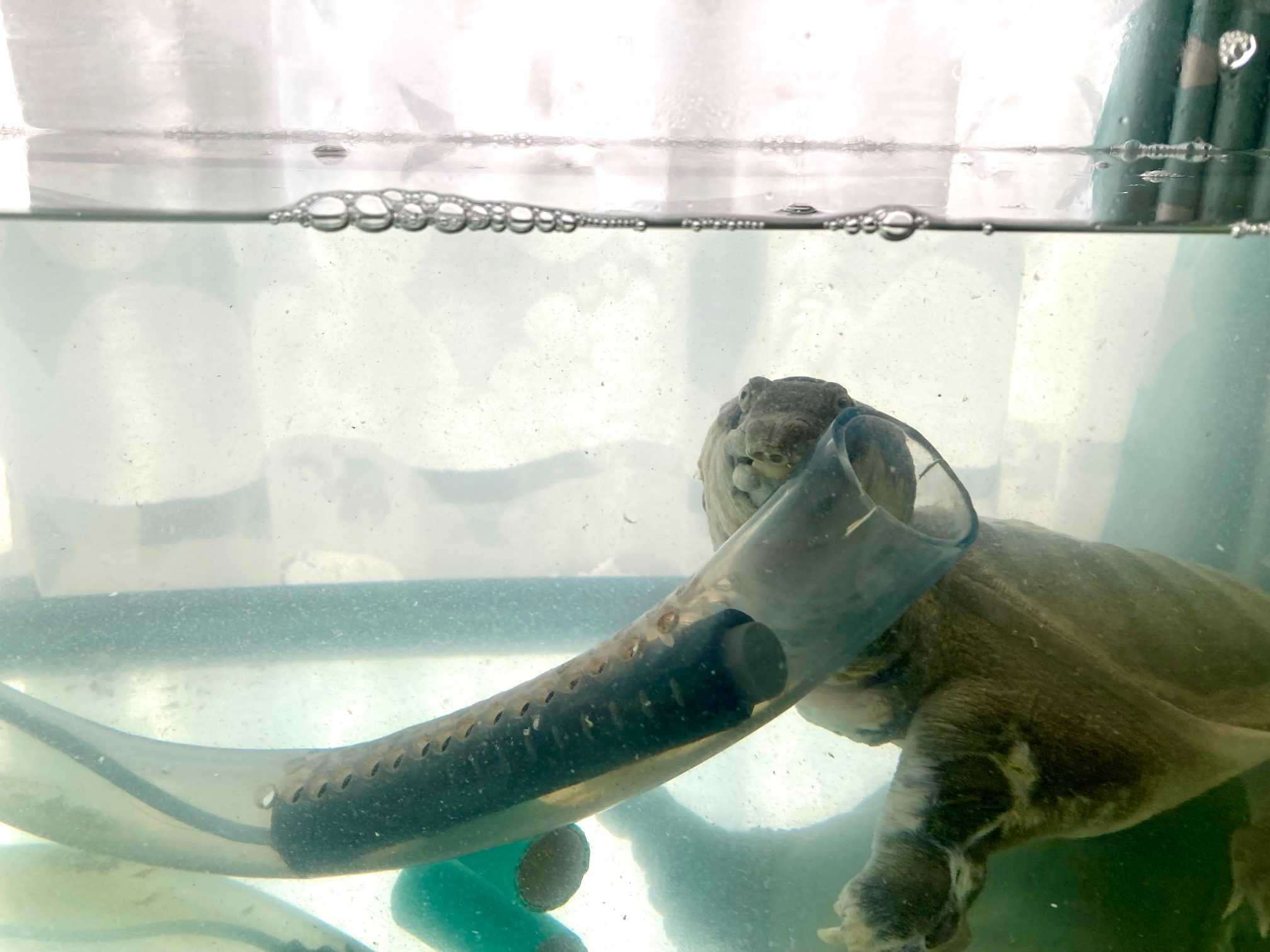2023年05月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
【能力は「好き」から伸びる】
【能力は「好き」から伸びる】 プロスポーツに限らず、アマチュアでも活躍しているスポーツマンには、ある 特徴があります。 それは、子どものときそのスポーツが好きだった、ということです。 ゴルフでも、卓球でも子どものときに「好き」だったのです。 好きなことをやって、たまたま上手にできたとき、それを見ていた親や家族が 喜んでくれ、ほめてくれます。 それが、嬉しくてどんどん好きになって、本当に上手になりずば抜けた能力を 発揮できるのです。 しかし、最初は好きではなかったものでも、やっているうちにだんだん好きに なって、それが仕事になったという例もあります。 ある人は、父親が陶芸家でした。 子どもの頃は、焼き物そのものにあまり興味はありませんでした。 社会人になると、流通関連企業の社員になりました。 仕事が休みの日、たまたま高名な陶芸家の作品に接することがありました。 そのとき、父親の作品とはまったく違う作風だったために、それが印象に残り ました。 その後、勤めていた会社の経営が思わしくなく、次の仕事を探さなくては、と 思っていたのでした。 そんなある日、以前興味を持った陶芸家の個展が催されることを知り、会場に 足を運んだのです。 それが、きっかけになり実家に帰り、父親の跡を継ごうと決めました。 しかし、簡単な世界ではありません。 粘土をこねたり、釜の火入れや雑用で追われる毎日です。 それでも、何年かやっているうちに、作品を創ることの楽しさを感じるように なってきたのです。 このように、もともと好きではなかったものでも、興味を持ったことがきっか けになり、楽しくなることもあるのです。 中国の思想家・老子は、次のように言いました。 「どんなことでも、地道にやっていけば、自分の好きな分野で世の中の 役に立っているものだ」 最初は好きではなかった仕事でも、やり続けていくとしだいに夢中になってい くこともあります。 この繰り返しを通して、仕事が好きになり、楽しさと面白さを味わうことがで きます。 今の仕事が自分に向いていないものでも、懸命に取り組んでいけば好きになる かもしれません。 大切なのは、目の前の仕事をきちんとやる、ということだと思います。 (by ハートリンクス)
2023年05月31日
コメント(0)
-
【自分は幸せだと思うことから、いい人生が始まる】
【自分は幸せだと思うことから、いい人生が始まる】 「自分は今、不幸だから子どもにだけは幸せになってほしい」と願っている人 がいるかもしれません。 この思いは、親心として美しいものです。 ところが、子を持つ親の方にもいろんな考えの人がいます。 「私は人より恵まれてはいないかもしれないが、幸せだと思う」と考えている 親は、「学校の成績がよくなくても元気でいてくれることが幸せ」と感じている のです。 今現在の生活レベルが標準以下であっても、幸せを感じて生きている人はたく さんいます。 そもそも標準という基準で、人の幸不幸は決まるものではありません。 大事なことは、「今、私は幸せです」という価値観を持つことです。 自分が幸せだ、と思えるから子どもの成績がどうであれ、元気でいてくれるの が嬉しい、幸せ、と感じるのです。 つまり、今の自分の生活に満足はしていなくても、感謝はできるという人生観 のようなものがあるのです。 人の生活のレベルに上限はなく、どこまで行っても満足はできないのです。 それより、今の生活は十分ではないが、これで良しとしよう、という考えが心 に落ち着きをもたらしてくれます。 収入が十分ではない、家も車ももっといいものを手に入れたい、今の生活には 不満だらけだ、という気持ちで過ごしている限り幸せにはなれないでしょう。 ある心理学者が次のように語りました。 幸せになれる心の条件 「自分にないものを、自分の幸せにとって必要なもの」と思うのではなく 「自分にはないにもかかわらず、幸せだ」と思うことが、幸せになれる 心の条件なのです。 自分の人生を不満の世界からばかり見つめていると、しだいに心の元気はなく なります。 しかし、人生を肯定して認める世界から見つめると、現実を受け入れることが できるようになり、心は元気になっていきます。 どんな世界から自分を眺めるかで、幸せになることも不幸になることもできる のです。 (by ハートリンクス)
2023年05月30日
コメント(0)
-
【人の欠点ばかり見る人は、ストレスに弱い】
【人の欠点ばかり見る人は、ストレスに弱い】 人の心は不思議で、仕事やプライベートがうまくいっているときは、余裕があ るためか相手の欠点には寛容になれます。 たとえば、気が短くてすぐにイライラする人が目の前にいても、「そんなとこ ろもあるんだな」と、さらりと受け流せるのです。 しかし、何かの理由で自分に余裕がないときに、目の前にそんな人がいると、 イライラした気持ちになります。 このように、自分の心が不安定なときは相手の欠点が気になるのです。 つまり、自分の心の状態がいいときは、相手の欠点は気にならないのに、悪い ときは気になってしまう、これが一般的に言えることです。 このことから、人には少なからず心の習性があることがわかります。 別の見方をすれば、人の欠点ばかり目につくときは、自分で気をつけるように するときである、と気づく人は成長しているのです。 中には、相手がどんな状態でも自分の心を安定させ、いつも余裕を持っている 人がいます。 こんな人の特徴は、人の長所を見つけるのがとても早く、うまいのです。 「あの人は、いつもニコニコしているなあ、いい人のようだなあ、」と感じて いることが多いのです。 「立ち向かう人の心は鏡なり」という聖徳太子の言葉があります。 相手にイヤなところがあると思うのは、自分にも同じようなところがある。 という意味です。 しかし、相手のよいところを見ていこう、という気持ちになれば、自分のよい ところがわかるようになるのです。 さらに、人のよいところを見ようと思うから、よいところが見えるのです。 この価値観を持てるなら、相手に欠点があっても気にならなくなります。 人の欠点を見つけるのは簡単で、長所を見つけるのは難しいと思いがちです。 しかし、「あの人の長所は、どんなところかな?」という意識を持って人を見る 習慣がある人は、ストレスにも強いのです。 そして、人の欠点がすぐ目につくのは、それだけ人のマイナス面を多く見るこ とになり、当然ストレスは溜まりやすくなり、ストレスにも弱くなるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月29日
コメント(0)
-
【逆境のときに考えておくこと】
【逆境のときに考えておくこと】 実業家で、以前は内閣官房参与を務めた田坂広志という人が、次のようなこと を述べています。 『何が起こったか それが、我々の人生を分けるのではない 起こったことを、どう解釈するか、 それが、我々の人生を分ける』 生きていれば、一生を左右するような大きな問題に直面することがあります。 田坂さんが、つぎのようなエピソードを紹介しています。 ある男性が、アメリカに出張中、交通事故に巻き込まれ左足を切断するほどの 大けがをしました。 その人は、自分の人生は終わった、と落ち込んでいます。 日本から奥さんが駆けつけてきて、 「あなた! よかったわね! 命は助かった! 右足は残ったじゃない!」 と言ってご主人を抱きしめたという話です。 人生の一大時のとき、起きたことをどう解釈するかで、その後の生き方は変わ ります。 同時に、逆境のときにそれは自分がもっと強くなるための機会である、と考え ることができるかどうかです。 シェークスピアの言葉に、 『幸も不幸もない、要は心の持ち方一つなのだ』というものがあります。 少し突き放した感じのする言葉ですが、真理のようなものが含まれていると思 います。 小さなことでも、大きなことでもシェークスピアの言葉が自分の価値観にまで なっていれば、逆境を乗り越える力も生まれてくるでしょう。 「物事のとらえ方」が、長い目でみると自分の人生をつくっていくことになる のです。 (by ハートリンクス)
2023年05月28日
コメント(0)
-
【言葉の力】
【言葉の力】 ブッダの教えの中には、「愛語」がいかに大切なものかが説かれています。 「愛語」とは、愛のこもった言葉であり、やさしさのある言葉です。 ときによっては、その言葉が人を元気にすることさえあります。 「法華経」というお経には、 『思いを蓄えて言語するは愛語なり』という一文があります。 これは、ただ表面的な心のこもっていない薄っぺらな優しい言葉ではなく、 心の底から、相手のことを思いやり、赤ちゃんを抱くようなつもりで語る言葉 が愛語である、という意味です。 もちろん、ときによっては厳しい言葉が愛語になることもあるでしょう。 厳しさの中に愛がこもっているなら、愛語となるのです。 空海は真言宗の開祖ですが、こんな教えを残しています。 「たとえ、一瞬であっても、清らかな愛のある言葉で念じるなら、その思いは 諸仏、諸菩薩に必ず通じる」 これは、心のこもった言葉を使うような習慣を持ち念じるなら、その気持ちは 自分の幸せに通じる、ということです。 ある真言宗のお寺に、医師を目ざす大学医学部の学生が訪ねてきました。 お寺の住職は、医学博士でもあり本も出してあったことから、その学生は著書 を読んでやってきたのです。 聞くと、彼は白血病になり、医師からは余命宣告を受けたそうです。 医師になろうとしている自分が、もう生きられないと宣告されたのです。 どうにかしたいと考え、このお寺を訪ね、「修行させてください」と願い出ま した。 真言宗には護摩行があり、それは炎の前で真言を唱え続ける行です。 1回の行が約2時間かかるそうです。 一週間がたちました。彼は「気分がとてもよくなりました」と言い、来たとき よりも精気を取り戻し、寺を去りました。 それからしばらくすると、 「先生、おかげさまで元気になりました。本当にありがとうございました」 という、連絡がありました。 今では、ある大学の教授として医療と研究に従事しているそうです。 愛語とは、人に対して心のこもった言葉を発するだけではありません。 自分自身にも、誠実な気持ちで語りかけること、これも愛語です。 苦しいことや、つらいことを包み込むような言葉を自分に言って聞かせること も愛語なのです。 言葉に力があることを知れば、簡単に人の悪口など言わなくなるものです。 それが、自分の人生にとってはとてもよいことなのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月27日
コメント(0)
-
【失敗してもそのあとが大事】
【失敗してもそのあとが大事】 アメリカの16代大統領、エイブラハム・リンカーンは「奴隷解放の父」とも 称され、一説ではアメリカ史上最もすぐれた大統領だと言われています。 その彼が次の言葉を残しました。 『君がつまずいてしまったことに興味はない そこから立ち上がることに関心があるのだ』 どんな人も、失敗してつまずくことがあります。 大事なのは、その後どうするかなのです。 もちろん、その内容にもよりますが、立ち上れないぐらいの失敗があった人も いるかもしれません。 それでも、立ち上がることから逃げないほうがよいのです。 一時的には逃げて、静かな心になるまで時間が必要な場合もありますが、最後 は再び立ち上がることが必要です。 ある作家の人の話です。 若い頃ですが、翻訳家になりたいという目標を立てました。 翻訳家になるには、検定試験を受けなければなりません。 そして、その試験を受けましたが最初のときは、合格するために1点だけ足り なかったそうです。 1点の違いで不合格なら、次も受けたいと思うものです。 そして、2回目の検定試験を受けました。 ところが、このときも1点の不足でした。 さすがに、投げ出したくなったそうです。 そんなときに、ある言葉に出会いました。 「人生で最も輝かしい日は、いわゆる成功した日ではなく、敗北から再び 立ち直ろうと決心した日なのです」 この言葉を支えに、3回目の試験に臨みました。 ところがこれも1点不足。心が折れそうになりましたが、この言葉のおかげで 頑張れました。 そして、4回目も5回目も6回目も不合格でした。しかもすべてが1点不足。 そのたびに、この言葉が支えでした。 ついに7回目で合格したそうです。 たしかに「もう一度がんばろう」という気持ちには、誰にもなれます。 しかし、3回4回5回6回7回と続けるためには、根気と勇気が必要です。 根気と勇気を奮うたびに、生きる力が養われていくのです。 同じことに何度も挑戦するだけではなく、病気であったり仕事だったり、離婚 などの失敗があっても、再起する心意気を忘れていけません。 人は、へこんだり、またガンバロウという気持ちを行ったり来たりしながら、 落ちつくべきところにたどり着きます。 その生き方はカッコ悪いかもしれませんが、自分にとっては価値ある生き方に なるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月26日
コメント(0)
-
【悩みから抜け出すヒント】
【悩みから抜け出すヒント】 音楽や絵画など一流の作品にふれると、心が洗われ言葉では表現できないよう なスッキリとした気持ちになります。 それは癒されていることでもあり、よどんでいた心が浄化されたようなものに 近い感覚です。 神社や仏閣にお参りしたときに感じる、清められたすがすがしい感じとは少し 違います。 人は何か心に悩みやあり、壁に当たったときにはそこから抜け出したくなるも のです。 一時的には、何も考えられない、何もできない、何もしたくないときさえあり ます。 そういうときに、一流の芸術に接すると立ち直るきっかけをつかむことができ たりします。 これが芸術の力です。 世界的に有名な音楽家のベートーベンは、自身も病気を抱えて悩み作曲ができ なくなりますが、自らの作品にその思いを表現することで、悩みを乗り超えて います。 『悲愴』の弦楽四重奏曲第十四番・十五番には、耳が聞こえない悲しさが表現 されているそうです。 そのような気持ちのこもった音楽を聴いた人々は、力をもらったり癒されたり します。 音楽など自分で作りだす能力がない人も、自分の代わりになって曲を作ってく れている、自分の苦しみをわかってくれている、このことに感動するのです。 つまり、音楽などの芸術品が、悩んでいる自分を昇華させてくれるのです。 これは、クラシック音楽だけにとどまらず、悩む青少年がポップミュージック などを聴いて元気になることと同じです。 何かで悩み、気持ちがへこんだときには、自分なりの解決法をもっておくのは とても助かります。 自分を励ます曲を毎日聴くことで、くじけそうな心もなくなります。 このような生活のリズムがある若者は、大人になっても何かの壁に直面しても 大丈夫です。 へこんだりしても、そこから抜け出せる術(すべ)を学んでいるからです。 悩みから抜け出すヒントは、「自分の私生活のリズムの中にある」と、考える ことが自分を強くしてくれます。 (by ハートリンクス)
2023年05月25日
コメント(0)
-
【心の余裕とは、心の目線を一つ上げること】
【心の余裕とは、心の目線を一つ上げること】 人前で話すことがあるとき、あがり症の人は心の余裕がなくなります。 この状態のことをパニックといいます。 人前で話してうまくできなかったら、みんなからバカにされて恥ずかしい、と いう気持ちで頭の中がいっぱいになり、何もできなくなるのです。 まじめな人ほどなりやすいのが、パニック症です。 一生懸命にしないといけない、という気持ちがかえって緊張させるのです。 パニックにならないためには、日頃から自分自身を客観的に見るクセをもって おくと、人前であがることはなくなります。 「自分を客観的に見る」とは、心の目線を一つ上げるということです。 兄弟でお笑い芸人をやっているコンビがいます。 あるときコントをしていると、突然お兄さんがパニックになり、言葉が出てこ なくなりました。 兄弟なので、そのときはどうにかできたのですが、そんなことが何度か起きる と相方の弟も不安になります。 ある日、何かで明石家さんまさんにこのことを話すことがありました。 すると、さんまさんはお兄さんに向かって言いました。 「お前は、パニックマンだ!」とあだ名をつけました。 このさんまさんの言葉に、お兄さんは救われてパニック症状が消えたのです。 人の心は、ちょっとした他者からの言葉で変わることがあります。 そのときの「お前は、パニックマンだ」という言葉で、自分を客観視できる ようになったのです。 菜根譚という古典の作者である、洪自誠(こうじせい)は、逆境に負けないた めには、人生の王道を知っておくとよいと述べています。 三つのことがあり、一つは、人生は何が起きるかわからない、このときは大地 足をつけて、慌てないようにしておこうと日頃から思っておくこと。 次は、人生ではいろんな危機に見舞われてもいいように、具体的な対処法を考 えておくこと。つまり、今でいえばリスクマネジメントです。 最後は、人生を味わうには心の余裕を持っておくこと。 人生を味わうとは、よいことにも悪いことにも、一喜一憂せず物事の流れに飲 みこまれないように、冷静さを忘れないで生きていくことです。 現実は、ほとんどの人が、自分のまわりに起きた出来事や事象に惑わされたり します。 それは仕方のないことですが多くの人は、そのときに思った感情に流されてし まい、それで終わっています。 しかし、人によっては自分が取った行動はあれでよかったのか、または、なぜ 問題が起きたのか、などと客観性のある目線で判断し考えているのです。 この習性が、心の余裕をつくり出してくれます。 心の余裕があるかないかは、日頃の自分の考え方に影響されるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月24日
コメント(0)
-
【平凡な一日が幸せな日】
【平凡な一日が幸せな日】 いいこともあれば、悪いこともある。山もあれば谷もあるのが人生だ。 と、わかってはいても、よくない出来事が立て続けに起きると、落ち込んだり します。 そんなとき「この頃は、いいことが一つもない」とつぶやいているものです。 ただ、嬉しいことやよかったことも起きたのですが、そのことはとうに忘れて います。 人生は、苦しいことばかり、悩みの連続だ、と思っている人は多いかもしれま せん。 しかし、一年前の自分が、どんなことで悩んでいたかを覚えている人はあまり いないのだそうです。 日記をつけていればわかりますが、それでも、いつも何かで悩んで苦しんでい ることは意外と少ないのです。 今の世の中は、ネガティブな情報が氾濫しています。 そのような種類の情報にふれる毎日の連続です。 すると、他人の不幸がいつのまにか、自分の毎日に重なるように錯覚してしま うことがあります。 誰かと誰かが結婚した、などおめでたいニュースもありますが、そのあとには 誰かと誰かが憎しみあっている、離婚したらしい、などの情報があります。 そもそも、たくさんの人が生きているのですから、たくさんの出来事があって 当然です。 そのたくさんの人たちも、毎日毎日が悪いことばかりに出会っているわけでも ないのに、ネガティブな情報を知るたびに、自分の気持ちがどんどんその方向 に流されていくのです。 人生とは、何事もなく平凡に過ごしている日が圧倒的に多いものだ、と考えて みましょう。 そう思えば、何事もなく平凡であることがありがたいことになるのです。 よいことがあれば、もっとありがたいなと思い、悪いことがあっても生きてい るだけでもありがたい、という考えを習慣にすればよいのです。 どんな考え方を習慣にするかで、人の人生観は変わってきます。 「生きていたって、楽しいことは一つもない」という人生観なら、そのような 人生を送ることになるでしょう。 しかし、「生きているなら、平凡な毎日でも、どんなことがあっても私は幸せだ と思うようにしよう」、という人生観なら、そんな人生になるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月23日
コメント(0)
-
【人生に必要なもの】
【人生に必要なもの】 大切な自分の人生にとって必要なもの、それは人によって違いはありますが、 その内の一つをあげれば、それは「仕事」だと思います。 ここでいう仕事は、イヤイヤながらするものという意味ではなく、やりがいの あるもの、生きがいとなるものという要素が多分に含まれています。 日本人の寿命は世界的に長寿だと言われています。 しかし、江戸時代当時は、50歳前後が平均寿命でした。 生まれてすぐに亡くなる新生児もかなりいたそうで、当時はまだ医療技術が遅 れていたことも原因です。 江戸時代の就業の内訳を今と比べると、とても面白く感じます。 仕事に就く人々の9割は、農業・漁業・林業・商業でした。 しかも特徴は、家族のみんなでやっていたのです。 子どもが大きくなり、結婚して子どもが生まれると、祖父母が子どもの面倒を みるのです。 祖父母も孫の面倒をみるのが生きがいだったのです。 つまり、死ぬまで何かの仕事をして一生を終える、これが人生だったのです。 ところが、現代は多くがサラリーマンですから、定年を迎えたら仕事をしなく なり、何をしてよいかわからない、という人たちもいるようです。 これからの時代は、サラリーマン時代の技術や専門的な知識を、ネットを通し て発揮することが、生きがいになっていくでしょう。 新しい人生にとって、必要なものは何かについて、ある大学の学長さんが薦め ていることが二つあります。 一つは、人との交流です。 それも新しい他者との交流が必要ではないか、ということです。 サラリーマン時代は、一つの組織の中や業界の中という、限られた小さな社会 での人との交流が中心でした。 これからは、そんな枠を取り払って自由に広範囲にいろんな人たちと交流する ことが自分の価値を上げることになると言います。 もう一つは、本を読むことです。 これは新しい知識を得るためではなく、人格陶冶のための本を読むことに重点 を置くということを薦めています。 知識よりも、教養や人間力を高めるために学ぶのです。 「人の一生は、人生の後半をいかに過ごすかで決まる」、という考え方がありま す。 若い時代に経験したことから学んだ、自分なりのルールや価値観を生かすのは 人生の後半でしかできないこと、という考えです。 定年になっても、現役を退いても、その後に生きがいを感じることが心の充足 となるでしょう。 (by ハートリンクス)
2023年05月22日
コメント(0)
-
【逆境に強い人と、弱い人の違い】
【逆境に強い人と、弱い人の違い】 逆境にも病気だったり、貧しさだったり人によってそれぞれです。 逆境の経験がある人は、生きるか死ぬかというレベルあるいはそれに近い体験 があります。 日本を代表する経営者の一人、稲盛和夫さんは大学に進学するころ肺の病気に かかり挫折しています。 日本マクドナルドの藤田田さんも、若い頃肺結核になり人生をあきらめたこと があります。 当時は、現代のような医療技術はなく薬もない時代でした。 孫正義さんは、事業を起こしてまもなく肝炎になり余命宣告を受けています。 このような体験をした人が、その後どうして立ち上ることができたかというと 一つは、そのときの苦境に被害者意識を強く持たなかったことです。 「どうして私が、このような目に遭うのか」と、普通なら考え悲嘆にくれてし まうものです。 もちろん先ほどの人たちも一時的には、そんな心境にはなりましたが、そこで 終わることはありませんでした。 さらに、逆境や苦境を「悪いもの、悪いこと」とはとらえませんでした。 たしかに「どうして病気になったのだろう?」という思いはあったでしょう。 その思いは、疑問であると同時に、自分に与えられた何かの意味があるもの、 として見ていたのです。 逆境や苦境は、生きていれば誰にでもやってきます。 しかし、人生は善か悪かに区別できるものではありません。 逆境や苦境は、見た目は善ではないかもしれませんが、その背景にあるものを 見ていけば、悪とは言えずそれを乗り越え解決する方法は見つかります。 逆境に弱い人は、見た目が悪であることだけを見て、その奥にあるものを見よ うとはしないのです。 見ないようにするのはラクですが、成長もできません。 「逆境の奥には何かあるのではないか」、の意識は向上したいという心から生ま れます。 その向上心も、考え方の習性によって経験とともにつくられていきます。 (by ハートリンクス)
2023年05月21日
コメント(0)
-
【やりたいことを実現させる法則】
【やりたいことを実現させる法則】 大人になったらやりたいことをやろう、と子どもの頃に思っていても、大人に なってみると実現していないことがあります。 作家の中谷彰宏さんが、次のようなことを言いました。 何かをやりたいと思う人が一万人います。 そのやりたいことを始める人は、そのうちの百人です。 そのための努力を続ける人は、そのうちの一人です。 つまり、「何かをやりたいな」、という願望を持ったとしても、やり続ける人は とても少ないということです。 『継続は力なり』と、よく言われるように続けることは難しいものです。 ただ、続ける人がいたなら、そのチャンスは誰にでも平等にあると考えること ができます。 自分で決めたことをやり続ける人の考え方には、ある特徴があります。 目標を立てますが、目標に向かっていくときの気持ちのつくり方が普通の人と 違っていることです。 立てた目標は未来のことですが、「実現したらいかに楽しく嬉しいか」、という ところから自分を見るのです。 たとえば、半年後にハワイに旅行に行こう、という目標があるとします。 そのためにはお金を貯めなければならないので、食べたいものを我慢したり 買いたい洋服も我慢して節約します。 ハワイに行くためなら、我慢も節約も苦にはならないのです。 むしろ、そのように頑張れる自分が頼もしく思えたりします。 ところが同じ目標でも、「実現しても楽しくなく嬉しくもない」というところ から自分を見ていくとエネルギーは生まれないのです。 たとえば、会社命令で半年後に売上を今より3割アップするように言われたと します。 そのときに思うのは、仕事とはいえ半年の間はプレッシャーがかかり、残業し ている自分の姿をイメージしたりします。 何かをやりたいという目標があるとき、実現するための過程を楽しくできる人 は続けることができますが、楽しくできない人は続かないのです。 努力という言葉を聞くたびに、大変だ、キツイだろうな、という気持ちになり やすい人は多いかもしれません。 しかし、努力の先に喜べる自分の姿を想像できる人は、どんな人生であれ楽し める人です。 どんなことでも、「楽しみながらやってみよう」、という考えでスタートしてみ ましょう。 (by ハートリンクス)
2023年05月20日
コメント(0)
-
【完全を求めることをやめれば、ラクになる】
【完全を求めることをやめれば、ラクになる】 世の中には、完全主義や完璧主義をモットーにしている人が、意外にたくさん いるようです。 とくに、仕事に必要な書類を含めデジタル社会が浸透していくほど、間違いや ミスが許されなくなります。 その風潮が、人の考え方にも影響するようになったからです。 しかし、今の日本に多くの外国人が観光で訪れる理由を考えると、本来、人間 は不完全のほうが美しく、のびやかに生きていくものなのです。 仏教をもとにいろんな宗派が、日本に持ち込まれましたがとくに、日本の美術 や文化は外国人からとても人気があります。 たとえば、最近は茶道のお茶や茶碗に人気があります。 お茶の味もですが、抹茶茶碗に興味を持つ外国人が多いのです。 西洋の美は、左右対称が基本です。 ところが、禅から生まれた茶道の茶碗の形は歪んでいて、色にもムラがありま すが、一見ぶさいくな形の美、つまり不完全な美が人の心を癒してくれます。 こんな話があります。 人は、なぜ完全完璧を求めたくなるのでしょうか? その訳は、もともと人間は不安を抱えて生きているから、その裏返しとして 完全完璧を求めるのだ、という話です。 心の仕組みから考えると、これには一理あります。 ただ本来、物事はうまくいかないもの、完全ではないものだから、努力しても 意味がないという考えではいけないのです。 頑張ってもうまくいかないなら、もっと頑張って努力する必要があり、それを 通して人格の向上が得られるのです。 「自分は完全でなくてもいい」と思えば、気持ちはラクになります。 その上で、できる努力をしていけばいい、と考えれば不安になっても「やれる だけの努力をすればいいじゃないか」というラクな気持ちになれるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月19日
コメント(0)
-
【感情が豊かな人ほど、幸福度が高い】
【感情が豊かな人ほど、幸福度が高い】 人に対する思いやりの深い人は、相手のことを自分のことのように考えてくれ ます。 人にやさしくできる人も同じような特徴があるようです。 なぜそんな人になれるのかというと、一言でいえば感情が豊かだからです。 感情が豊かであるとは、繊細であるとか感受性が敏感であるということだけで はありません。 思いやりがなく人に冷たい人であっても、繊細で感受性が敏感な人はたくさん います。 感情が豊かな人とは、自分を含めて相手を包み込むことができる人です。 人の感情のもとになるのは、一つは感性です。 感性が磨かれると、感情は豊かになるのです。 「磨かれるというのは、刺激を受けることだ」と考えれば分かりやすいと思い ます。 そのことがよく分かるのが、幼い子どもたちの行動です。 とくに、子どもを、海や川につれていくとてもはしゃいで興奮し喜びます。 小中学生になっても、大人になってもキャンプに行けば楽しくなります。 このような体験が、感性を磨くことになるのです。 海や川に行くとどうして楽しいかというと、自然界というものに感動している からでしょう。 大自然が感動を与えて、刺激を与えてくれているのです。 太陽の恵みや、海の青さ、雲の美しさをじかに体験できます。 夜は、月と星座の輝きを見て、自分の存在が悠久なものに感じられます。 樹木には、小さな虫や鳥などが住みついているのを見て、命の大切さを知って 感動するのです。 フランスの哲学者、パスカルが「人間は考える葦である」と有名な言葉を残し ています。 この言葉の前段に、次のようなことを述べています。 「人間は一本の葦にすぎない。 自然界では最も弱い存在だ。 しかし、それは考える葦である」 人間は自然界の中で一番弱い存在だから、自然界に感動できるのです。 弱い存在でありながら考える力がすぐれているので、寒さや暑さに耐える知恵 を持つようになったのです。 現代はストレス社会ですが、大自然に接すると癒されて、疲れていた心や体も 元気に回復できます。 そのときに、自然のありがたさと、自分が幸せであることに気づくのです。 この感性が、感情の豊かさにつながっていきます。 大自然に包まれて人は生きていけるように、人もお互いを包みこんでいくこと が大切です。 自然界の営みに感動できる心を忘れない。 これが感情を豊かなものにし、幸福度を強めてくれると思います (by ハートリンクス)
2023年05月18日
コメント(0)
-
【自分の「生」を大切にする】
【自分の「生」を大切にする】 仕事での失敗、あるいは事業がうまくいかずに倒産したり、病気で仕事も家庭 も失うような大きな挫折を味わうと、生きることさえつらく感じるものです。 それでも人は立ち上ることができるものです。 Aさんは、「生きていてもどうしようもない、死にたい」と悩んでいました。 Aさんの友人が、Yさんという人に一度話を聞いてもらったらどうか、と言う のでYさんの家を訪ねました。 Yさんは歌人で名僧・良寛の研究者です。 たまたまその日は、自宅でお弟子さんたちへの講義中で、一時間ほど待つこと になりました。 客間に通されるとそこには掛け軸が飾ってあります。 こんなことが書かれてありました。 『学規』 一、ふかくこの生を愛すべし 一、かへりみて己を知るべし 一、学芸を以て性を養うべし 一、日々新面目あるべし この訓には、次のような意味があります。 一、ふかくこの生を愛すべし 「この生」とは、自分の命のことです。自分の命をいとおしいと思えば、人 としてのあるべき姿がわかる。 一、かへりみて己を知るべし 自分は今まで何をしてきたのか、これから何ができるのか、真剣に反省する こと。すべてはそこから始まる。 一、学芸を以て性を養ふべし 学問と芸術に精進すること。それが自己を磨き、人格を向上させる。 一、日々新面目あるべし 過去の自分にとどまってはいけない。日々努力を重ね、新しい自分を創って いけ。人の生は躍動してやまないものである。 Aさんは、掛け軸をじっと見つめていました。 しばらくすると、講義を終えたYさんが部屋に来て、「用件は何でしょう?」 と尋ねました。 Aさんの話はこんなものでした。 「商売が行き詰り死を決意しました。その前に先生にお話を聞いてもらおうと 思いお訪ねしたのです。しかし、もう用件は終わりました。 床の間の軸を拝見して死ぬことはやめました。ありがとうございました」。 と言って立ち去ったそうです。 掛け軸の書の作者は、会津八一(あいづやいち)という人物です。 早稲田大学の教授で、仏教美術の史家、歌人、書家です。 「学規」は教え子たちのために与えた言葉でした。 会津八一は、正岡子規とも交流があったといわれています。 Yさんは、この会津八一のお弟子さんだったのです。 この「学規」は明治時代に作られ、現代の若者がどう受けとるかはわかりませ んが、人生訓としての価値は十分にあると思います。 根本にあるのは、自分の命はいとおしいものである、ということです。 この自覚があれば、反省する謙虚さが生まれ、成長意欲も湧き他者の気持ちも 理解できるようになります。 生きていくというのは、自分を大切にすることでもあると思います。 (by ハートリンクス)
2023年05月17日
コメント(0)
-
【快適な心で日々を過ごすには】
【快適な心で日々を過ごすには】 心も体も健康でありたいと誰もが思います。 心身が健康であるには、生命のエネルギーが必要です。 そのためには、朝はギリギリまで寝ていたり、あわてて家を出るような生活は 避けなければなりません。 ある脳外科医の話では、頭がさえるためにはいくつかの習慣が必要である、と 述べています。 快適な毎日を過ごすには、心の準備が必要です。 つまり、脳の状態がスッキリしていてやる気満々であることが理想です。 普通の生活から少しかけ離れた世界で生きている、修行中のお坊さんの毎日が どんなものかを知るとそこにヒントがあります。 たとえば、修行する禅僧は、朝起きたら、身支度をしてお堂に行き大きな声で お経を読むのだそうです。 それが終わると、朝食であるお粥を食べ、食器を洗いそのあと坐禅をします。 それから境内の掃除をしたり、師匠から言われた雑用を片づけていきます。 この一日の流れをみると、脳外科医がすすめる生活リズムの型があります。 つまり、ある程度決められている安定した生活を習慣にすると、脳の状態も落 ち着き、それが心を静めることになるというのです。 快適であるとは、気持ちいいとかエアコンのきいた部屋で心地よさを感じる、 ということではなく、心が乱れずにストレスを感じない状態のことです。 仕事であるなら、仕事に淡々と取り組み集中することです。 つまり、朝起きたら体を動かすことから始まり、それから部屋の片づけを行い 食事のあと、仕事に取り組む。 この一連の流れを淡々と行い、できれば丁寧に行うことをリズム化する。 これでエネルギーが生まれるのです。 夜の睡眠も、日中の行動が安定していれば、ぐっすり眠れると思います。 快適に過ごすには、自分に合った生活のリズムを作っていくことが大切なこと です。 (by ハートリンクス)
2023年05月16日
コメント(0)
-
【人の悪意から身を守るには】
【人の悪意から身を守るには】 ハラスメントやいじめが問題になっています。 悪意によって傷つけられた心のキズは、簡単に消えるものではありません。 言った側、やった側は、「そんなつもりで言ったのではない」「そんなつもりは なかった」と言い訳をします。 『自分がされてイヤなことは、人にもしない』、というルールを守ればこのよう な問題は起きないのですが、人間の難しさがここにあります。 やさしい性格の人ほど、誰かから攻撃を受けたら落ち込んでしまいます。 そして、原因は自分にあるのではないか、と思い悩んでしまいます。 こんなときは、自分が悪いのではないか、と一途に思わないことが大切です。 何かはっきりした原因があるなら話は別ですが、多くは単なる嫌がらせに近い ものです。 また、誰かに相談することで、気がラクになることもあります。 場合にもよりますが、上司に相談しても期待できない、とりあってくれない、 という事例もよくあります。 親しい友人のなかに、相談できる人がいればそれもよいでしょう。 話して打ち明ければ、心は軽くなり解決の糸口を見つけることもできます。 とにかく自分を見失わずに、自分の心が強くなる機会だと考えることも大切な ことです。 いちばん大事なことがあります。それは、 「攻撃を受けても、私には味方がたくさんいる、応援してくれる人もいっぱい いる、手を差し伸べてくれる人がたくさんいる」。 と、これを信じることです。 仏教に、『因縁果』(いんねんか)という言葉があります。 物事には、原因があり結果があることを、「因果の法則」といいます。 しかし、原因(因)があり、結果(果)が生まれるには、その過程には「縁」 があります。 誰かと口論になったとします。 口論という結果(事象)があるのは、原因(理由)があるからですが、口論に なるには、相手が自分の言うことを聞いてくれなかった、などの原因があった らです。 しかし、分析をすればたとえばどちらかが、そのときたまたま不機嫌だった、 という縁(きっかけ)があったからです。 よくあるのは、因と縁が混じりあってしまい口論になることです。 ここで、「因」と「縁」を切り離して考えてみると、いままで気づかなかった た、感情のすれ違いに気づきます。 もっと日頃から、相手の言いたいことを聞いてあげていればよかったな、と いう気づきです。 つまり、よい縁をつくれば争うことも減るのです。 誰かから、悪意のある攻撃を受けるのは、大きい小さいに関係なく「縁」と なるものがあったからです。 その悪い縁から遠ざかり、離れることも攻撃を受けないための方法です。 反対に、人から好かれることを考えてみると、大きい小さいに関係なく「縁」 の中に好かれる要素があるからです。 そのような良い縁であるなら、近づいていくことは問題ないでしょう。 いわれのない攻撃を受ければ苦しく、悲しくなると思います。 それでも、私にはそれに負けない心があり、味方がたくさんいると信じる。 これが何よりも大切なことです。 (by ハートリンクス)
2023年05月15日
コメント(0)
-
【下から目線で生きてみる】
【下から目線で生きてみる】 小さな子どもたちが、大人に向かって何かを話すとき、下から上を見る目線に なります。 このときの表情にはとても愛らしいものがあります。 そこには、安心して話せるという信頼感があるように感じます。 大人になると、こういう気持ちになることは難しいものです。 同じ目線で話すことより、上から目線で話すことを無意識的に行っていること が多いのです。 人間関係がうまい人の特徴は、この「目線」のバランスがとれています。 人に対して小さなものであっても、批評や批判をすることがクセになっている 人は、無意識で上から目線になっています。 そんな人ほど一人になると、「自分はどうしてこんな性格なのか」というよう な自分を否定する気持ちが強いのです。 「本当は自分は立派な人間であるべきなのに、それができない自分が悔しい」 と自分を責めながら、他者に対しても批判したくなる。 これは、自分を否定するなら、自分以外の人も批判しないとバランスがとれな いからです。 禅の言葉に、「無縄自縛」(むじょうじばく)というものがあります。 じっさいは、自分を縛る縄などないのに、まるであるかのように思い込み自分 を縛っている、という意味です。 自分はダメな人間だと思い込んで、自分を否定し、あの人は自分のことをよく 思っていない、という想像や思い込みで自分や相手を縛りつけているのです。 このような無縄自縛の心は、どんなことも「こうあるべきだ」という考えから 生じます。 また、「こうあるべきだ」という価値基準を持っていたほうが、ラクなのです。 人と人とがわかり合うためには、相手を信じる心をどこかに持っていなければ なりませんが、それには小さな冒険が必要です。 もし、信じて痛い目にあったら困る、という危険もゼロではないしょう。 このことから、人は「こうあるべきだ」の基準を持ちたがるのです。 ただ、相手はどんな人かわからないが、思い込みはせずにそのままを見よう、 という気持ちになると、無縄自縛になることはないでしょう。 いちばんいいのは、子どものような下から目線で考えていく気持ちを忘れない でおくことなのかもしれません。 それが無理なら、せめて同じ目線で相手のことを思ってみるのです。 下から目線になるには、「生きているだけで、ありがたい」という気持ちをもつ ことがいい方法です。 (by ハートリンクス)
2023年05月14日
コメント(0)
-
【目を閉じて静かな時間を持つ効用】
【目を閉じて静かな時間を持つ効用】 これからの時代は電子技術がもっと進化していくそうです。 そのおかげで、今以上に生活は便利になり、快適な気分で過ごせるようになる といわれています。 反面、人の心よりも人工知能の働きが重要視されてくると、人の心の温かさに 直接触れることが少なくなってくるかもしれません。 すると、心のふれあいが減り、メンタルの健康維持が難しくなってきます。 以前は、心療内科や神経内科など心の病に関する診療科はありませんでした。 精神科という大まかな診療科に含まれていました。 しかし、時代とともに心の不調を訴える人が多くなり、今の医療があります。 これからは、心の不調をいかに予防するかがとても大切になってきます。 心が不調にならないためには、一日のうち数分でも目を閉じて静かな時間を 過ごすことが必要です。 一般的には、瞑想ともいいますが人によっては、「瞑想」ということばを聞く と何かスピリチュアル的なイメージを持つ方もいます。 しかし、目を閉じて静かな時間を過ごすことには精神的な効能があるのです。 すでにアメリカの保健福祉省公衆衛生局にある衛生センター(NCCIH)では、 瞑想の医学的な効能について研究されています。 NCCIHのことは、日本の厚生省でも紹介されていますが、これら統合医療の 情報を発信していくという事業を行っています。 たとえば、坐禅も瞑想の一つの形です。 瞑想をすると、どんな効能があるのでしょうか。 まず、心が落ちつきます。 心の落ち着きが感情を制御し、集中力が向上します。 その結果、自分自身に対する洞察力が身につきます。 他者との一体感が深まるようになります。 脳波がアルファー波の状態になり、癒しの脳内ホルモンが分泌されます。 ストレスが減り、体内細胞の免疫力が活性化されます。 もちろん、わずかな時間でも実践することから始まります。 時には、スマホのスイッチを切り、外からの雑音を遮断する時間もあったほう がよいのです。 静かな時間の中に身を置き、「自分の人生をどのように生きればよいか」など、 ふだんは思わないことを考えると心が癒されるものです。 (by ハートリンクス)
2023年05月13日
コメント(0)
-
【今の恵みに気づくと元気が出る】
【今の恵みに気づくと元気が出る】 朝起きて、家族とご飯を食べて学校に行く、仕事に行く。 このような生活のリズムを送る人がほとんどだと思います。 何げないことですが、この生活も恵みであると思えばありがたさを感じ、元気 になれます。 今、世界の人口は80億4500万人だそうですが、その中で飢餓状態にある人 は8億2000万人と言われています。 地球に住む人たちの約1割が、いつも空腹をかかえていることになります。 食べるものがあり、仕事があり、家族がいて、寝るところがある。 これが最低の生活環境だとしても、飢餓状態にある人たちにしてみれば、幸福 な生活に思えるかもしれません。 恵まれている、いない、の基準はあいまいですが、食べることさえ自由になら ない人たちに比べれば、今の私たちの生活は恵まれています。 何かのことで落ち込んだりしていても、過酷な状態の中にいる人のことを思え ば頑張ることもできます。 禅の名僧である、良寛和尚という人が言いました。 『欲がなければ、すべてに事足ります。 しかし、欲しがる心があれば、満足することができなくなり、 いつかは行き詰まるのです』 ここでいう欲とは、必要以上の欲のことです。 名誉欲、金銭欲、所有欲などです。 そうかと言って、欲を持つことが悪いということではありません。 欲があるから、目標を立てて頑張ろう、という気持ちになれます。 問題は、必要以上の欲を持つほど、当たり前のことにもありがたさを感じなく なるもの、だから気をつけよう、良寛は言います。 生きていくために必要な、最低の欲が満たされなくても、恵まれていることが 一つや二つはあるのではないか、そこに「ありがたいことだ」、いう心を持つ。 この心さえあれば、少々の悩み事も乗り越えることができ、元気をとりもどす こともできるのではないでしょうか。 (by ハートリンクス)
2023年05月12日
コメント(0)
-
【自分の生かし方】
【自分の生かし方】 「自分のいいところをもっと仕事に生かしたい」と思っていながら、具体的に どうすればいいかわからずに、行動できない人がいます。 もちろん、自分を生かしたい欲求があること自体、成長意欲を表われですから いいことであるのは間違いありません。 こういうときは、何か具体的な行動を起こさなければ、自分のよさを発揮する ことはできないのです。 たとえば、会社の上司へ 「こんな事業計画を考えたのですが、見てもらえますか?」というアクション を起こすなど、自分から提案していく姿勢が必要です。 たとえば、自分は料理が好きでおいしいチャーハンを食べたいけど、作り方が よくわからない人がいるとします。 すると、今はスマホなどで検索すればすぐにわかります。 つまり、おいしいチャーハンのレシピの情報をさがせばよいのです。 あるいは、スーパーかコンビニで冷凍チャーハンを買ってきて、それに自分独 自の味付けをするとか、トッピングをするなどの工夫もできるでしょう。 今の社会は、情報は満ちあふれています。 そのたくさんの情報から、自分に適したものを選択すればよいように、自分の 生かし方も、自分の得意な分野で具体的な情報を選びそれに近づく努力が必要 です。 ただ、知り得た情報をそのまま行動に移すだけでは、何かの問題が起きたとき すぐにあきらめたりします。 それは、苦労せずに得た情報を知っただけだからです。 得た情報は自分に合ったものにしていかなければなりません。 そして、創意や工夫をして自分独自のものにアレンジする必要があります。 そうすれば、情報選択の力が洗練され自分の能力を生かせるようになります。 それだけではなく、視野が広がり得意分野に関連した異業種の情報にも接する 機会が増えてくるでしょう。 つまり、視野が広がると自分の可能性も広がるようになります。 能力の広がりは、人間性の成長につながっていきます。 自信過剰にならない限り、魅力的な人間になることができるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月11日
コメント(0)
-
【人間関係は勝ち負けで決まらない】
【人間関係は勝ち負けで決まらない】 相手が自分の思うようにならないときに感じるストレス。 これが人間関係の悩みの一つです。 また、相手が自分のことをわかってくれないとき、これも同じようにストレス になります。 よく人間関係がこじれて仲裁に入ったとき、よく聞くのが「相手が変わらない なら、私も変わることができない」という言葉です。 つまり、相手が先に変わることを求めていて、それなら自分も変わってもいい というものです。 こうなると、勝ち負けの世界の考え方です。 先に自分が変わると何か負けてしまったかのように思い込んでいるのです。 しかし、よく考えてみると自分がそう思っているように、相手も同じ考えなの ですから、これではどこまで行っても平行線で解決は困難です。 ところが、中には「自分が変われば、相手も変わってくれるかもしれない」と 考える人がいるのです。 じつは、この考え方が人間関係の問題を解決する道につながっています。 この事実から、『他人を変えることはできない、それよりも自分が変わるほうが いい。しかもそのほうが自分も成長できる』、という人間関係解決の法則を知る ことになります。 今の日本は、就業人口が約6000万人だそうです。 この内、約2250万人が何かの疾病を抱え、一番多いのは高血圧が368万人、 その他、糖尿病などがあります。メンタルヘルスでは74万人です。 ただ、メンタルが原因で高血圧や胃腸病になる人もかなりいることを考えると 人間関係がうまくいかずに、体の不調になる人も相当数いるのが現実です。 相手が変わらないから、自分は変わらない、という感情は心を疲れさせます。 つまり、自分のイライラは相手のせいだ、という考えが「自分は損をさせられ ているから負けたくない」、と考え相手を攻撃する原因にしているのです。 「自分が先に変わることがいい」、という考えになれば、ストレスから解放され ます。 自分が変わることは、相手に負けることではなく、損をすることでもない。 むしろ、自己成長し得をすることになるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月10日
コメント(0)
-
【人生の質を高めるためには】
【人生の質を高めるには】 皆さんの中には、自分の人生をどのように生きていこうか? と考えている人 もいらっしゃるのではないでしょうか。 あまり深く考えないようにしている人もいれば、たまに考えることがある人、 さまざまだと思います。 子ども時代から、お医者さんになりたいとか、調理師になりたいなど具体的な 夢を持って追い続ける人もいます。もちろん人それぞれです。 大人になれば、漠然とでも「何のために生きているか」を考えることはあると 思います。 人生の質を高めるには、なるべく早く自分の生き方の方向性を決めておくほう がよいようです。 とくに、サラリーマンとして長く生きてきた人は、仕事そのものが生きる目的 のように思うのではないでしょうか。 芸術の世界では、死ぬまで作品を創ることができますから、仕事が生きる目的 になり得ます。 また、企業の経営者の中には現役を退いた後、まったくの異業種で自分がやり たかったことを起業する人もいます。 ヤマト運輸の小倉昌男さんのように、70歳で会社を後進に譲り、新たに福祉の 事業を生涯の仕事にするケースもあります。 人は自分の生涯を通して取り組む、「ライフテーマ」のようなものを持っておく ことが、人生の質を高めていきます。 毎日の生活を維持していくための仕事であっても、根底には自分のライフテーマ を持っておくと、生きるとはどういうものかを知ることができます。 人は、日々暮らしながら生きていくものです。 ただ、暮らすことと、生きることには違いがあり、どちらも大切にするべきこと です。 単に、お金をたくさん儲けたいだけのための人生ではなく、儲かったお金を何に 使うかを考えなければ、人生の質を高めることはできないでしょう。 ライフテーマがあれば、自分の生活もそれに向かって進む毎日を過ごしていく ことができます。 この過ごし方が、生きるエネルギーになり、生きることにも喜びを感じるよう になるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月09日
コメント(0)
-
【人とうまくつきあうコツ】
【人とうまくつきあうコツ】 AIやSNSの重要性が、さらに広まりそうな社会になりました。 ただそれでも、人と人との関係性が私たちの幸せにつながることは変わらない と思います。 メールやLINEを使ったコミュニケションのあり方は、すでに当たり前です。 しかし、一方では直接的に人とふれあいたい、と思う人もたくさんいます。 アメリカのハーバード大学の研究によりますと、人間関係がうまくいかず失業 した人の数は、仕事がうまくできないために失業した人の2倍だそうです。 つまり、人間関係がいかに難しいものなのか、これは何千年も変わらないよう です。 もう一つカーネギー研究所という機関での調査ですが、仕事上での成功の要因 として、本人の知能や技術力が15%で、85%は仕事での人間関係をうまく行 える人だ、という結果があります。 つまり、自分と他者がいかにうまくやっていけるか、これはとても重要な問題 だといえます。 人とうまくやっていくためには、いくつかのコツがあります。 一つは、人と相対するときや会話するとき、あるいは話を聞くときは、無表情 や険しい顔をしないことです。 笑顔であるのが理想ですが、そうはいかないこともあるでしょう。 もし笑顔が無理なら、せめて微笑みはマナーとして持っておきたいものです。 そうしなければ、相手は心を開いてはくれません。 また、相手の名前を覚えておくことも大切です。 もう一つは、相手へのリスペクトです。 過大なリスペクトはよくないですが、相手が信頼を寄せてくれる程度のことは 心得ておくべきです。 これらが、相手を気分よくしてくれるのです。しかも、最も簡単で有効です。 また、老子の言葉の中にも人間関係をよくするための教えがあります。 それは、『他人には、寛大であれ』というものです。 人は、なぜか他者の失敗やしくじりに過剰に反応しがちです。 どうしても、イライラするのです。 それくらい、他人に寛大になるのは大変難しいことかもしれません。 これは家族間でも同じです。 ただ、『寛大になりましょう』、というのは『受け入れなければいけない』、と いうことではありません。 「あの人にはあんなところがあるんだな」、というレベルでよいのです。 そう思えば、腹が立ったりイライラすることもなくなると思います。 このとらえ方が、相手を『受けて止める』ということです。 あえて、受け入れるのではなく、相手のことを冷静に事実として認めることで 十分です。 他者に寛大になると、自分自身への肯定感がアップします。 感情を込めすぎずに相手を認めると、自分にも冷静になれるからです。 すぐにはできなくても、くり返していくうちに自分の変化に気づくことができ ると思います。 (by ハートリンクス)
2023年05月08日
コメント(0)
-
【心の力は、ものの見方と考え方で決まる】
【心の力は、ものの見方と考え方で決まる】 どんな人も、人生で味わう不幸の量は大して変わらないと言う人がいます。 どんなにお金持ちでも、お金をたくさん持っていなくても、健康であっても 病気ばかりしていても、与えられた不幸の量は変わらない。 同じように、受け取った幸せの量も変わらない。 そんなことがあるはずはない、と思われる方も多いでしょう。 しかし、たとえば同じ不幸な出来事に出会った二人がいたとします。 同じ不幸であっても、苦しみやつらさの感じ方は違うのです。 海外旅行に行った二人の若者がいました。 目的地の国の空港に着きました。 長い時間飛行機に乗っていたので、体も心も少しだけ疲れたので、入国手続き を終えたあと、コーヒーでも飲もうということになりました。 くつろいでいると、ニコニコした女性が近づきどこからきたのですか? と 尋ねてきます。 二人は、日本から来たと答えると相手は「そうですか。楽しんでください」。 というとその場を立ち去りました。 気づくと、テーブルに置いていたショルダーバッグがなくなっていました。 わずかな時間のあいだに、二人ともバッグを盗まれたのです。 バッグには、お金とクレジットカードが入っていました。 ただ、パスポートだけはズボンのポケットに入れていたので無事でした。 気づいた二人は驚き、「大変なことになったどうしよう?」とパニックです。 ただ、しばらくすると、一時はオロオロしていた二人でしたが、受け止め方は 違っていました。 一人は、「命までは取られなくてよかった」と言います。 もう一人は、「せっかくの旅行もだいなしだ」と不機嫌です。 どちらも災難にあって不幸な出来事は同じですが、ストレスの大きさはかなり 違っています。 このような事態に直面したとき、怒りと不安の気持ちのままなのか、不幸中の 幸いだ、という気持ちになるかで二人の気分は異なっています。 怒りと不安が続くとき、心のエネルギーは弱まるばかりです。 いっぽう、命があるだけでもよかったと思えるなら、心も元気になれるかもし れません 人が生きていく境遇や、環境はそれぞれです。 どのような出来事に出会ったとしても、その時々の心の持ち方によって、人生 の中味は変わってくるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月07日
コメント(0)
-
【小さな悩みでも、たくさん抱えない】
【小さな悩みでも、たくさん抱えない】 生きていれば悩みの一つや二つぐらいは、誰もが抱えているものです。 悩みといっても人それぞれですから、他人からみればかわいい悩みに思えるこ ともあるでしょう。 最近はネットニュースでたくさんの事件や事故の情報が流れています。 ひと昔前は、ラジオかテレビ、あるいは新聞で得る情報がほとんどでしたが、 今は違います。 一時間前の事件や事故でもすぐにわかる時代です。 とくに事件の内容の多くは、人と人の間で起きるトラブルばかりです。 人間関係のもつれから、中傷や恋愛問題などいろいろです。 それらも初めのうちは、小さな悩み程度のことだったのが、だんだんと過熱し てしまい暴行や傷害のような事件になっていきます。 このような事件に巻き込まれないためにも、人間関係での悩みも小さいことだ からと放っておくのも考えものです。 森の中にそびえ立つ大きな木は、雨や風に打たれても何十年、何百年も生きて いますが、これらの巨木でさえ小さな害虫が住み着くと、いつのまにか倒れる ことがあります。 一匹の害虫なら影響はありませんが、何百匹の害虫から攻撃を受け続けると、 大きな木でも死んでしまうのです。 人間関係の悩みにも、大きい小さいがあります。 ただ、小さな悩みだからといってたくさん抱えるのは、心を傷つける原因にも なります。 たとえば、小さなことでイライラしてしまうなら、そのイライラもせめて気に ならない心の持ち方をするべきです。 アメリカの作家、デール・カーネギーに一人の友人がいました。 友人の職業は、カーネギーと同じ作家です。 その友人は、自分の部屋で原稿を書いているとき、空調設備から出る音が気に なって仕方がありませんでした。 あるとき、彼は数人の友らとキャンプに出かけることになりました。 キャンプですから焚火をします。 焚火の炎が燃えさかり、パチパチと音をたてていますが心地よく感じます。 友人は、そのときこの音は自分の部屋で執筆中に空調から出る音とよく似てい るな、と思ったそうです。 そして、焚火の音は好きなのに、空調の音はどうして嫌いなんだろう? と、キャンプから戻ってきてから思ったのです。 さすがにカーネギーの友人は、考えることが違っていました。 彼は、「焚火の音は気持ちが落ち着く。空調の音も似ているな。気にしないで 寝ることにしよう」と自分に言い聞かせました。 すると、その夜からぐっすりと眠れるようになり、執筆のときも空調の音が気 にならなくなりました。 この話には、悩みを悩みのまませず、気にしなくなるためのヒントが隠されて います。 そのヒントとは「なぜ、イライラするのか?」と、自分に聞いていることです。 自問自答することで、悩んで乱れている心を冷静になって見直しているのです。 これは、心のはたらきをうまく使う、よい例の一つだと言えるでしょう。 このように、小さな悩みでも心の使い方によって、悩みが悩みでなくなり解決 できることもあるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月06日
コメント(0)
-
【人の長所をほめると、自分も成長する】
【人の長所をほめると、自分も成長する】 学校でも塾でも、生徒の学力を伸ばすにはほめることが、大切な教育法の一つ です。 教育でも一般社会でも、ほめて伸ばしていく、つまり長所伸展法で効果を出す ことができます。 さらによいのは、その教育者が教育を通して磨かれていくことです。 教育の原点は育児にあります。 「育児」とは「育自」であると言う人もいますが、これは真実かもしれません。 子どもを育てることで、ひいては自分も成長し磨かれるという意味です。 最近は、性の多様化で必ずしも子どもを育てる生き方がすべてではない、とい う価値観があります。 これも大事なことです。 それでも、子どもを育てる環境にない人も、仕事では部下を教育することはあ ると思います。 人間社会では、どんな立場になっても人を育てることに関わることは避けられ ないのです。 人の長所を重点的に見ていく人は、相手をほめたくなります。 ほめるというと上から目線のようにも感じますが、相手のことをすばらしい、 賞賛したくなるものです。 そのような気持ちで人を見ているうちに、自分自身が物事を肯定的に見るよう になっていきます。 人の心にはこのような不思議な力があります。 いっぽう、人は誰かを批評しながら暗に批判的な目で相手を見ることを、気づ かないうちにやっています。 人の欠点を指摘すると、自分が正しいと錯覚するのです。 そして、これは誰もが陥りやすくラクな考えです。 そのような価値観のままでは、人間関係でいつも問題を抱えるようになってし まいます。 なぜかというと、人の欠点ばかり見ていると、つい相手を裁いてしまう心理に なるからです。 それでは、人との関係はよいかたちにはならないでしょう。 人の長所を見るとき、そこに意思をはたらかせることが必要です。 「あの人には、どんな長所があるのだろうか?」という意思の作業がなければ 無理です。 その意思の作業が自分自身を磨いていきます。 教育には、何かを教えることと、その人の能力と長所を見つけて引き出すこと の役割があり、結果的に教える側の人も進展成長することになるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月05日
コメント(0)
-
【人生はもっと楽しく生きられる】
【人生はもっと楽しく生きられる】 人は何か悩みがあると、暗い気分になりその状態が続いたり解決できないとき は、しだいに元気もなくなります。 ものごとを楽天的に思う人は、悩みがあるとどちらかというと「どうにかなる だろう」と考えることが多いようです。 ですが、悲観的に考える人は、「どうすればいいのだろう」と不安に思うこと が多いものです。 鎌倉時代に一遍上人(いっぺんしょうにん)という人がいました。 “時宗”の開祖と言われる人物です。 一遍上人は、人生は修行ではなく「遊行」(ゆぎょう)であると考えました。 当時、仏教の宗派にはいろんなものがありましたが、「人生は遊行」というのは 型破りだったといえます。 人生は修行であり厳しいものだと考えるより、観光めぐりをするような気持ち で生きていこう、というのです。 その考えから「踊り念仏」といって、踊りながら念仏を唱えることを広めたの でした。 踊りながら念仏を唱えれば、ふさぎ込むこともなく明るい気持ちになれる。 さらに、人生は苦しいだけのものではなく、もっと楽しいものである、という 教えです。 よく「観光旅行に行きましょう」、というCMを目にすることがあります。 この「観光」というのは、「観音さまの光を観る」ということが語源になって いるそうです。 観音さまとは、観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)のことで、現世に生きる人々 の悩みや苦しみ、お願いごとをかなえてくれる慈悲深い仏さまのことです。 この観世音菩薩さまから放たれる救いの光を観に行くのが観光です。 このことから、仏教の教えの根底には人生は楽しく生きていくことができる、 という大きな意味があるのです。 悩みばっかりの人生でも、たまには「人生は遊行なのだ」と考えれば心もラク になります。 (by ハートリンクス)
2023年05月04日
コメント(0)
-
【もっと語ろう】
【もっと語ろう】 心のモヤモヤ、ちょっとした意見の違いからくる人との関係悪化など、小さな ことでも気持ちが落ち着かないことがあります。 それが、いつも不機嫌な自分になってしまう原因になります。 不機嫌とは、感情の状態が安定していないときです。 とくに喜怒哀楽の中の、「怒」と「哀」が極端に強いときです。 そのようなときは、「喜」や「楽」の感情はほとんど存在しません。 つまり、健康的な感情より、不健康な感情に染まっているときが不機嫌なとき なのです。 その点、今ではSNSのやり取りで少しはスッキリ感を味わうことができます。 しかし、現実に相手を前にして話すことでしか通じないこともあるのです。 女性弁護士の大平光代さんは、かつてはご自身も非行少女で自殺未遂の経験も あります。 その大平さんが人と語ることの大切さや、悩める人の話しを聞くことがいかに 重要であるかを次のように語っています。 『子どもも大人も、心の病を持たれている方はたくさんいます。 心の病を持っておられる方は、自分の思いを人に話すだけで軽減できるんで すが、話す場所がないんですね。 聞いているだけでいいんです。 同じ目線で、同じ心で相手のお話を聞く。 「うん、うん」とうなずく。それが大切なんです』。 悩みのある人ほど、人に相談しても解決できない、考えているものです。 しかし、自分の思いを人に語ることで、自分の気持ちが落ち着くのです。 心理学者の間でも、人に語ることで精神的な動揺が収まると言われています。 「語る」ことで、わかっていたつもりのことが大切だったのだ、と改めて気が つきます。 語る相手がいない、と思っている人がいるかもしれません。 しかし、普段は表面的なつきあいだけの友人でも、なかには話を聞いてくれる かもしれないのです。 こちらから声をかけて、雑談でも話すことから始めてもよいと思います。 今まで深い話をしたことがない人でも、意外とまじめに対応してくれる可能性 はあります。 その関係ができた上でなら、SNSのやり取りも大切になってくると思います。 (by ハートリンクス)
2023年05月03日
コメント(0)
-
【苦手なことには、自分を生かすヒントがある】
【苦手なことには、自分を生かすヒントがある】 人はたまに、自分の苦手なことを強調して、できないことの言い訳にする場合 があります。 たとえば仕事でいうと、事務作業が得意な人が営業職に配置換えになることが あるとします。 そういうとき、「私は人に話したりすることが苦手だから、営業をしても成果を あげられるはずがない・・・」という言い訳です。 これは、適材適所の考えからいけば間違ってはいません。 ただ、たまたま会社の事情で営業の社員が足りないときなどは、協力の必要も あります。 しかし、指示を受けた人にしてみれば、自分にできないことをさせられるのは 苦痛になるのです。 自分には営業のセンスはなく、性格的にも人に話せないし変えられないものだ から、と思っています。 ただ、性格というのは習慣によってつくられるものでもあるのです。 そして、その習慣を変えていく努力ができるのが人です。 自分の習慣を変えよう、という意志があれば一度では無理でも、少しずつ変え ていくことはできるでしょう。 「自分が苦手なことをすることは、つらいことだ」と考えればこれからの仕事 も、苦痛なものになるかもしれません。 それでも人の成長は、その人の能力が生かされることで成し遂げられます。 自分にとって苦手と思えることも、見方を変えれば成長するまたとない機会に なるでしょう。 苦手なことだから、私はできないと思ってしまえばそれは自己限定をすること と同じです。 社会運動家の石川 洋(よう)さんの言葉に次のようなものがあります。 つらいことが多いのは 感謝を知らないから 苦しいことが多いのは 自分に甘えがあるから 悲しいことが多いのは 自分のことしかわからないから 心配することが多いのは 今を懸命に生きていないから 生きていれば、いろんなことがありますが、受け止める人によって次の行動が 違ってきます。 苦手なことがあるなら、そこには伸びるヒントがあり、長所があればもっと伸 ばしていこう、と考えられ自分を生かすことになるのです。 (by ハートリンクス)
2023年05月02日
コメント(0)
-
【いいことを思うから、いいことが起きる】
【いいことを思うから、いいことが起きる】 アメリカの心理学者、ジョセフ・マーフィーは20冊以上の著作があります。 日本では、有名文化人の一人であった渡部昇一(ペンネーム・大島淳一)さん が翻訳した「眠りながら成功する」(上・下)は今でも読まれています。 このジョセフ・マーフィーの代表的な言葉が、 「いいことを思えばいいことが起き、悪いことを思えば悪いことが起きる。 だから、いいことを思おう」。というものです。 そんな簡単なことで、いいことが起きるなら世の中はもっと平和なはず、と 考える人も多いでしょう。 しかし、よくよく考えれば、いいことを思わなければいいことは起きない。 この理論は正しいものだといえます。 人の思い、想念、心には不思議な力があります。 アメリカのエルマー・ケイツという心理学博士がある実験をしています。 液体空気で冷やしたガラス管の中に、いろんな心理状態の人の息を吹き込んで もらいました。その結果は次のようなものです。 普通の状態の人の息の管では、揮発性の物質が固まり無色に近い液体となり、 無害です。 一方、怒っている人の息の管には、栗色の滓が残りその液体をマウスに注射し たところ神経過敏の状態になりました。 さらに、激怒した人のものだと数分で死んでしまいました。 また、人がクヨクヨする、イライラする、心配事で眠れないなどのとき、消化 器官に潰瘍ができたりするのも生理学的には、感情や心が心身に影響を与える からなのです。 もちろん、いいことばかりを考えて生きていくのは、現実に不可能です。 よくないことを考え想像することから、危険から逃れ生命の安全を守る技術が 生まれるものです。 人は感情のバランスをとりながら生きています。 いいことを考えることもあれば、悪いことを考えることもあります。 大事なことは、自分が日頃考えていることです。 生きていてもいいことがない、あるいは生きていればいいことがある・・・。 悪いこともあれば、いいこともある、など人それぞれです。 それでも、少しでもたくさんいいことが起きるように考えて、生きていこうと 思ったほうがしあわせになれるはずです。 (by ハートリンクス)
2023年05月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-14 18:01:08)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- 丸大食品:ショッピングモールに:自…
- (2025-11-14 18:28:23)
-