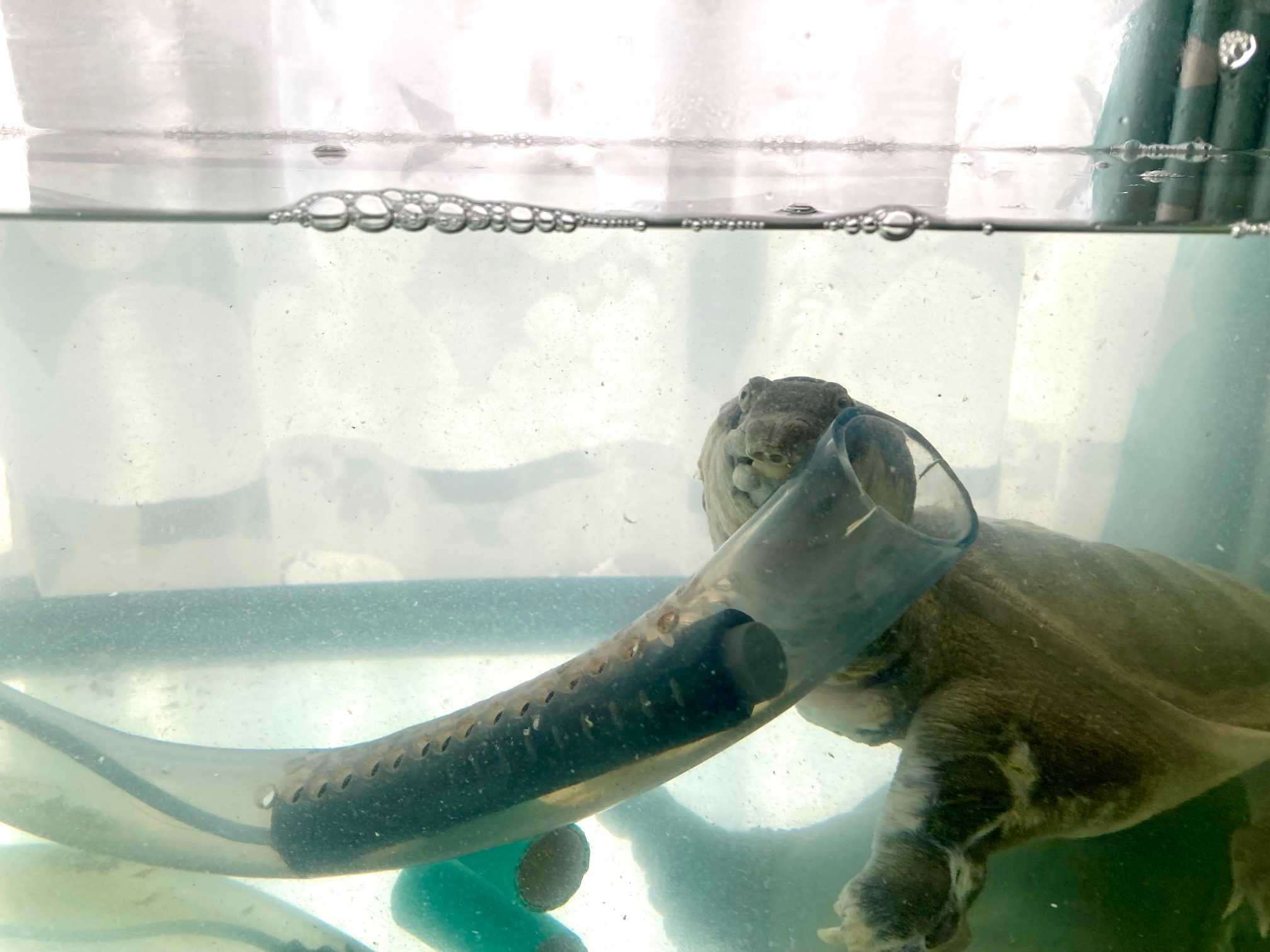2024年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
【ストレスを自己成長の種にする秘訣】
【ストレスを自己成長の種にする秘訣】 「ストレスがなければいいのに」と思う人は多いかもしれません。 しかし、ストレスがなくなることはなく、いかに減らしながらうまくつき 合うかを考えたほうが賢明です。 ストレスとうまくつき合うには、ストレスを悪者ではなくむしろ自己成長 の機会であるととらえることが大切です。 人には、自分を変える心の能力が3つあります。 1. 自分を客観視できる能力 感情をそのまま言葉や行動に出さずに、冷静になる力です。 2. 逆説的に、自分をあきらめることで成長の道が開ける 失敗やミスをした時、「今のままではだめだ、もっと強くなるべきだ」 と考えることです。 つまり、弱かった自分をあきらめれば前に進む力が生まれるのです。 3. 思い込みとこだわりを捨てる能力 これらを捨てると、柔軟で純粋な心になり視野が広がります。 禅の言葉に「把手共行」(はしゅきょうこう)があります。 これは、現実の自分と、心の中の自分が協力して進むべき道を示してい ます。 たとえば、不安やイライラを感じる自己とは別に、自信にあふれる自己も 存在しています。 弱い自分とは別に、頑張れる自分を探し出そうとするのが、「把手共行」 であり、自分を変えることができるのは、自分だという意味です。 まず、自分には3つの能力があることを信じましょう。 そのうえで、「把手共行」の道を進めばストレスが自己成長の種に変わって いくでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月30日
コメント(0)
-
【感情の仕組みを知ろう】
【感情の仕組みを知ろう】 ある大学の教授が、人間の感情は二層構造になっているのではないか、と 語っています。 これは、ストレスは少なくいつも気持ちが安定している人は感情の使い分け 能力が優れているということです。 1. 上層の感情:日常の出来事に一つ一つ反応し、時には一喜一憂する感情 があります。 2. 下層の感情:「変わらない自分、淡々とした自分」が存在します。 これは、気持ちの切り替えがうまい人の特徴ともいえます。 たとえば、プロ野球などでホームランを打ったバッターは、喜びを隠さずに ニコニコした表情をします。 しかし、ゲームが終われば翌日の試合のために準備をし、練習を行います。 本番ではやるべきことに集中し、終われば気持ちをリセットできるのです。 大きな木も、風が吹けば枝が揺れますが、地中の根は揺れないことに似てい ます。 しかし、一喜一憂することに影響を受けやすく、気持ちの切り替えがうまく できない人もいます。 アメリカの社会学者、アーリー・ホックシールドによると、人間の労働には 体を動かす肉体労働と、頭を使う頭脳労働がありますが、もう一つ感情労働 というものがあると言います。 感情労働に従事する人は、その人の体調が悪い時でも笑顔で接することを要 求されます。 たとえば、教師や看護師や接客業などの仕事に就く人たちです。 笑顔を求められる時間が長く続くと、感情のバランスが崩れ燃え尽き症候群 になってしまうこともあります。 そうならないためには、仕事を終えた後に感情のメンテナンスを自分で行う ことが大切です。 一人になれる時と場所を持っておく、あるいは癒しを感じる自分独自の工夫 をして、自分を見つめる時間を必ず見つける生活を習慣化するのが大事です。 (by ハートリンクス)
2024年04月29日
コメント(0)
-
【成功体験より失敗体験に価値がある】
【成功体験より失敗体験に価値がある】 夢や目標が達成できなかった時、心には目に見えない傷が残ります。 また、スポーツでは思わぬ故障やけがに遭うこともあります。 しかし、時間が過ぎていくに従いその時はつらかったことも、良い体験 となり成長できるものです。 多くの人は、成功は良いこと、失敗は良くないものと決めつける傾向が ありますが、成功や失敗には善悪の区別はないのです。 昔、平戸藩の藩主だった松浦静山が次のようなことを語りました。 「価値に不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」 この言葉が広く知られるようになったのは、プロ野球の元監督だった野村 克也さんが著書などで紹介したことが始まりです。 たまたま、苦労も努力もせずに成功して、物事が予想以上にうまくいく時 もあります。 かりに、偶然に成功することがあったとしても、失敗したことに偶然はな いということです。 つまり、失敗には必ず原因があることを指しています。 失敗した原因を深く分析することで、どこが悪かったのか何が不足していた のか、行うべき工夫があったのではないかを見極められます。 さらに、この一連の流れを通して、失敗したことに大きな意味があり新しい 価値を見いだすことになるのです。 成功の体験をすることも大切ですが、失敗体験には未知の可能性が潜んで いると考えましょう。 失敗から学ぼうとするには、勇気がなければできません。 失敗から学びを得たときは、勇気を一つ手にしたことになると考えれば、 前向き思考が身につき人生は豊かなものとなるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月28日
コメント(0)
-
【臍下丹田呼吸法の効果】
【臍下丹田呼吸法の効果】 ある、進学塾では授業の前に数分間、特別な呼吸をさせています。 『息を吸う(5秒)。息を止める(3秒)。息を吐く(8秒)。』 これを、「5・3・8の呼吸法」とも言いますが、この呼吸法を続けて いくうちに、塾生の集中力がアップして成績がよくなったそうです。 ヨガや禅の世界でも呼吸の重要性を教えていますが、これは呼吸を整える ための方法です。 呼吸と感情と思考には相関関係があります。 呼吸を正しく整えると、不思議なことに自律神経のバランスがとれるよう になります。 たとえば、感情が高ぶっている時、緊張している時など深呼吸するだけで 気持ちに落ち着きを取り戻せます。 もっともわかりやすいのは、血圧を測定する時です。 血圧値が思った以上に高い時など、ゆっくり深呼吸をするとほぼ正常値に なります。 これも、呼吸と血圧の相関関係があるという証拠です。 また、イライラしている時は、呼吸が浅くなっています。 呼吸が浅く、血流は少なくなり酸素も不足しているため、血圧が高くなり 血管に負担をかけてしまいます。 このような状態が続くと、内臓疾患にかかりやすい体質になっていきます。 もちろん、偏った食生活にも原因がありますが、感情の起伏が激しい場合 も影響を受けます。 健康であるためには、感情や心のエネルギーの好循環が大切です。 心配や不安をいつも抱えたままでは、体のどこかに異変が生まれます。 常日頃、小さなことにも感謝できる人は顔色が良く、体のどこかに多少の 不具合があっても元気に過ごしています。 人との会話でも、明るい話題と楽しい内容を心がけるだけで、感情と心の 循環がよくなり、結果的に豊かな人生を送ることにつながっていきます。 呼吸を整える習慣を身につけましょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月27日
コメント(0)
-
【ストレスを味方にする生き方】
【ストレスを味方にする生き方】 ストレスを悪いものと考えずに、よい刺激剤としてとらえている人ほど 人生を楽しんでいます。 ストレスは、人生のスパイスとも言われ、少なすぎると人生は味気なく なり、多すぎるとバランスを崩します。 ある作家が、ストレスについて次のように語りました。 1:ストレスを持つことは仕方ないですが、持ち続けることはやめておき ましょう。 2:ストレスを持つことが悪いのではなく、ため込むことがよくないこと だと理解しましょう。 3:適度なストレスは、実力以上の能力を発揮させる原動力になります。 4:幸福な人、成功している人、一流の人と言われる人は、ストレスの 避け方が上手ではなく、吐き出し方が上手なのです。 5:ストレスを発散するために、お酒を飲み美味しいものを食べるのも かまいません。 しかし、過度な発散は新たにストレスを生み逆効果です。 このように、ストレスを敵だと考えるより、ストレスが生じたら自分を高 めるためのヒントが隠されているととらえることが前向きな生き方です。 神経科学者の青砥瑞人さんも、「ストレスは自分を成長させてくれる大切な 養分になってくれる」と語っています。 また、ストレスを感じにくい人の中にはストレスの強い仕事を選んでいる ケースもあります。 好きな仕事だからといって、夜更かしをして偏った食生活を続けていくと 気づかないうちに、心や体を酷使することになります。 ストレスを味方にするための考え方として、自分がストレスを感じている ことに気づくことが重要です。 もし、ストレスを感じたら、文字に書き出して俯瞰してみましょう。 客観的に見ることで、大した問題ではないと気づくこともあります。 (by ハートリンクス)
2024年04月26日
コメント(0)
-
【態度価値】
【態度価値】 ある男性が、小さな食料品店を経営していました。 しかし、売り上げは伸びず蓄えていたお金もなくなり、借金が増えるばか りでした。 このままでは店を閉めなければならず、とりあえず銀行から必要なお金を を借りようと、肩を落としトボトボと歩いていました。 沈痛な気持ちで歩く途中、前方から両足のない男性がローラースケートの ついた台に座り、手に持った棒を使いながらこちらに向かって来ました。 たぶん何かの用事でもあったのでしょう。 そのうち、何気なく目と目があいました。 すると、ローラースケートの人は肩を落としながら歩く彼に、笑顔で声を かけたのでした。 「おはようございます! よい朝ですね!」と挨拶しました。 この挨拶に、彼は体中に電流が走ったような気がしました。 私には歩ける足が2本あるのに、商売がうまくいかないからと人生を嘆い ているが、あの人は笑顔で堂々としている……。 何と自分は恥ずかしい人間なのだ、と思うとそれまでの不安はどこかに消 えてしまいました。 その日から彼は、この日の出来事を家の洗面所にある鏡の横に書いて貼り つけ、毎朝、気持ちを強く持って再起したそうです。 この話には二つのことが示されています。 1. 困難を乗り越える態度。 商売に自信をなくした人が、体の不自由な人との出会いで仕事がうまくい かないぐらいでクヨクヨせずに頑張ろうと思ったことです。 これは、できないと思っていたことでも、何かの出来事がきっかけになり 困難を乗りこえようとする態度です。 2. 境遇を受け入れる態度。 足のない人がローラースケートの台に座っている境遇でありながら、 それを自分の運命として受け止めていることです。 仕事をする自由を奪われ、わずかな楽しみさえ奪われても、その境遇を 受け止める態度があり、環境や境遇に恵まれなくても、どのような態度 で前向きに進んでいくかは、本人が決めることができます。 この態度のことを、オーストリアの精神科医、ヴィクトール・フランクル は『態度価値』と名づけました。 態度価値とは物事の受け止め方、とらえ方、であり感受性のことです。 一般的に感受性が豊かというと、神経が細かいという意味にとらえますが、 物事の受け止め方は人それぞれです。 生きていくには、「たくましい感受性」も必要です。 感受性を習慣化し、感受習性を向上させていけば幸福につながる態度価値 を身につけることができます。 (by ハートリンクス)
2024年04月25日
コメント(0)
-
【心の整理力】
【心の整理力】 よく、平常心を持とうと言いますが、これはどんな時も普段通りにあわ てずに、その時々にやるべきことを冷静に判断するという意味です。 人の心は様々な刺激を受けることで刻々と変化します。 特に現代は、多くの情報を受けて発信することに追われ、自分を見つめる 時間も少なくなっています。 元サッカーの日本代表でキャプテンを務めた、長谷部誠選手が以前「心を 整える」という本を出しました。 彼は目立った性格ではなく、何かの特徴がある個性的な選手という印象は ありませんでしたが、チームをまとめていました。 当時の監督からも、大きな信頼を寄せられていて期待にも応えました。 その理由として彼は、キャプテンとしてメンタルのトレーニングを続けて いたのです。 それは、一日30分自分だけの時間をつくり、その日を振り返りプレーの 反省、生活態度について自分を見つめ直していました。 この習慣により、正確で冷静な判断を下す整理力を身につけました。 サッカーにおいては、誰にボールを回し、自分はどの方向に動けばよいか を判断する能力が求められます。 彼は、ゲームでは自分の動きを判断し、各選手に指示を出していました。 自己振り返りの時間が少ない人ほどストレスを感じやすくなります 一般の人もたった15分でも、自己振り返りを行うことで、心の整理力を 養うことができます。 たとえば、反省すべきことに5分、感謝すべきことに5分、新たにやる べきことに5分、というようにテーマを決めて行うと効果的です。 (by ハートリンクス)
2024年04月24日
コメント(0)
-
【先用後利の生き方をしよう】
【先用後利の生き方をしよう】 江戸時代に、各家庭に「置き薬」というシステムがありました。 当時はコンビニやドラッグストアはなく、病気になった時のためにいく つかの薬を備えておき、巡回訪問で未使用の薬を引き取り、新しいもの に交換する仕組みがありました。 いまでも地域によっては、このシステムが活用しています。 置き薬の販売形態が生まれたのは江戸時代で、今から330年ほど前と言 われています。 富山藩の二代目藩主・前田正甫(まさとし)が江戸城内で腹痛に苦しむ他 の藩主に、富山藩の薬を服用させたところ、痛みがすぐに治まりそれから 富山藩の薬の評判が広がっていきました。 さらに諸国の大名が薬の行商を懇願し置き薬の行商が始まりました。 この行商の販売方法は「先用後利」の精神を取り入れ、病気を治すこと が先で、利(お金)は後でいいという考えでした。 そのため、行商の人はたくさんの薬を背負って歩くという、大変な仕事 でした。 この富山の商人たちが伝えてきたのが、「七楽の教え」です。 『楽すれば 楽が邪魔して楽ならず、楽せぬ楽が はるか楽楽』 というものです。「楽」の文字が七つあることから七楽の教えと言われました。 楽をしようとすると、その心が邪魔をして結局、楽はできないことを示し ています。 そのかわりコツコツ努力するのが楽につながる道であり、勤勉を大切にし、 与えることを先にするのが人の道ともいえるでしょう。 利益を追求するよりも、善行を重視し正しい行動を優先することが何より も大切なことです。 (by ハートリンクス)
2024年04月23日
コメント(0)
-
【不自由から工夫が生まれる】
【不自由から工夫が生まれる】 作曲家の中島薫さんは、 「人間には、誰にも欠点やマイナスの部分がありますが、問題はそれを どうプラスに転化するか、どう自分特有の武器にしていくかです」。 と語っています。 彼は、自分のハンディを逆転のチャンスととらえ、積極的な人生を築いた 人です。 中島さんは、3歳の時に小児まひになり、左手が少し不自由になりました。 しかしその後も、手のことを自分の欠点だとは特に思わなかったそうです。 小学校3年生になり、一つの壁にぶつかりました。 音楽の授業で縦笛を吹くことになりましたが、左手のせいでうまく音が出 せませんでした。 彼は、そのことをお母さんに相談しました。 「ようするに、ちゃんと音が出たらいいわけでしょう。 それなら右手と左手を反対にして吹いてみたら? それでうまくいけばいいんじゃない」 と、お母さんはアドバイスしました。 お母さんの言葉に従って練習を重ねた結果、彼は縦笛が上手に吹けるよう になりました。 すると、笛の演奏に大きな自信が生まれて、県の音楽のコンクールの独奏 部門で優勝するほどまでに成長しました。 もし自分の左手が普通の人と同じだったら、縦笛は上達しなかったかもし れないと彼は考えました。 ハンディがあるからこそ、みんなと違う方法で頑張ろうという気持ちにが 生まれ、探求心や向上心に満ちた個性を育ててくれたのです。 何かの弱点やハンディキャップがあっても、自分のやりたいことをあきら める必要はありません。 一時的に、そのような気持ちになることがあっても、弱点やハンディが長 所や武器に転じることもあるのです。 人生において、どのような心の持ち方や考え方をするかは、大きな岐路と なります。 (by ハートリンクス)
2024年04月22日
コメント(0)
-
【他人と同じ立場で考える】
【他人と同じ立場で考える】 山口県の詩人、金子みすゞさんの記念館館長である矢崎節夫さんが、 ある小学校の生徒たちが、ネパールの学校建設基金に協力してくれた ことに感謝の意を示すため、学校を訪問する計画を立てました。 その前日、先生は生徒たちに次のようなお願いをしました。 「明日は使っていない鉛筆で、ネパールの小学生にプレゼントしても いい鉛筆があったら、持ってきてください。 ネパールの小学生は、鉛筆を持っていない子もいるのです」。 矢崎さんの訪問日がやってきました。 クラスの子どもたちはそれぞれ鉛筆を持ってきました。 しかし、ある少女が持って来た2本の鉛筆はきれいに削られていました。 先生は「使っていない鉛筆を持って来なかったのはなぜかな?」と尋ね ました。 少女は次のように答えました。 「ネパールの子が鉛筆を持っていないなら、鉛筆削りも持っていないと 思って削ってきたの」。 先生も、近くにいた矢崎さんも驚き感動しました。 その少女は、鉛筆を使う同じ小学生の人の立場になっていたのです。 禅には「同事」という言葉があります。 これは、「事を同じくする」という意味で、相手と同じ立場に自分も立つ ことを指します。 たとえば、寄付をするというと、口には出さなくても上から目線の気持ち になることがあります。 困っている相手と同じ気持ちになり、同じ目線で考えることが大切です。 たとえば、子どもが見る風景と大人が見る風景は違います。 それは目の高さが違うからです。 大人が小さな子どもと話す時は、しゃがんで子どもと同じ目の高さで話す と子どもの安心感が高まります。 相手と同じ目線になることで、信頼関係が築かれ一体感が生まれます。 (by ハートリンクス)
2024年04月21日
コメント(0)
-
【幸せから遠くなる理由】
【幸せから遠くなる理由】 私たちは、心の底では幸せになりたいと思っていても、自分では気づかな いうちに幸せから遠ざかる思いや、行動をすることがあります。 その大きな理由は、思考習慣・行動習慣です。 幸せから遠ざかる五つの条件というのがあります。 1:いつも不平不満を言う。 なぜ幸せが逃げていくのでしょうか。 それは、この感情から明るく陽気な気分は起きないからです。 幸せであるには陽気であることが大事です。 2:人の嫌がることをする。 このような人は嫌われてしまいます。 幸せは自分の努力と、人の力で運ばれてきます。 人からよい感情をもらえなければ、幸せにはなれないものです。 3:ミスや間違いをした人を責める。 他人の気持ちになって考える余裕がない時、人を責めたくなります。 相手に対する寛容さがないため、幸福も人も自然に離れていきます。 4:物事を否定的にしか見ない。 狭い視野のままでは否定的な思考になり、職場や家庭で絶えず変化する 出来事の悪い側面しか見えなくなります。 悪い出来事から良い結果が生まれることもあり、一方通行的な見方では 窮屈な心になっていきます。 5:ストレスを発散する時、人や物に当たる。 ストレスの対処法にはその人の人柄が表れ、自分の感情に適度な距離を 保つことがストレスは抑制されます。 自己管理する能力が弱い人ほど、責任回避に走りがちです。 上記の五つの条件とは逆のことを行えば、思考習慣も行動習慣も改善され、 幸せな人生を送れるようになるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月20日
コメント(0)
-
【負け組でも逆転できる】
【負け組でも逆転できる】 目標としていた企業や学校の試験に落ちた、あるいは病気で勉強できな かった、などの経験をした人がいます。 やる気がなくて目標を達成できなかったのであれば、自己責任ですから 仕方ありませんが、自分の力ではどうしようもない理由であきらめること もあります。 しかし、大きな発見や発明をした人たちに共通しているのは、どのような 原因であろうと、負け組と呼ばれ落ちこぼれの状態から逆転していること です。 ところが、視点を変えれば落ちこぼれたから、考え方が鍛えられて別の力 が生まれ、物事や人生に対する姿勢が変わったのも事実です。 たとえば、遺伝学の世界で大きな発見をしたメンデルは、チェコスロバ キアの貧しい農家に生まれました。 賢い子どもだったので、修道院に見習いとして入り哲学や数学、鉱物学、 植物学などを学び25歳で司祭になりました。 さらに、彼は教授になるための試験を受けますが、結果は不合格でした。 この時点では、メンデルは落ちこぼれの立場です。 それから30歳でウィーン大学に2年間留学し、物理学や植物解剖学を学 びそこで遺伝についての興味を持つようになりました。 研究者としてエンドウを植えて遺伝解明のための実験を始めました。 34歳から8年にわたり実験を行い、エンドウを28000本植え調べ研究 結果を「遺伝の法則」として発表しますが、彼の身分が修道士であるこ とから、学会からは相手にされませんでした。 この期間の実験は、熱意と忍耐力なしで行うことはできませんでしたが、 彼は学会の冷たい反応に、心が折れそうになりました。 そんな時、彼が所属する修道院の院長が亡くなり、メンデルは新しい修道 院の責任者として仕事に就きました。 そのために研究を続けることはできず、15年後に彼は61歳で生涯を終え たのです。 ところが、さらに16年が過ぎるとオランダの学者など3名が、メンデル と同じ内容の遺伝の法則を発見しました。 この時から、メンデルの「遺伝の法則」の偉大さが世界中で認められ、 世界の科学に大きな影響を与えました。 彼の生存中には認められませんでしたが、努力は報われたのです。 落ちこぼれでも、努力を続ければ世の中に貢献できる生き方は誰でも 行えるものです。 (by ハートリンクス)
2024年04月19日
コメント(0)
-
【ストレスを味方にする】
【ストレスを味方にする】 ストレスはなくそうとするより、まず減らすことを考えるほうが楽です。 なぜかストレスを目の敵のようにとらえてしまう人が多いようです。 もちろん、ストレスはあるよりないほうがいいのですが、ストレスに対 して嫌悪感を強く抱きすぎると、ストレスを作ったあの人が悪い、あの 出来事が悪い、と偏った考えになりやすくなります。 末期がんと診断された患者さんを対象に、ある調査が行われました。 がんと徹底して闘ったケースと、がんと闘わずに受け入れた場合とを 比較して、どちらが長生きできたか、というものです。 結果は、「がんと闘った患者さん」より、「がんと闘わない患者さん」の ほうが長生きできました。 分析によれば、がんと闘うこと自体ストレスになり、医学的にはその時 にストレスホルモンが分泌され、それががんの免疫力を低下させるとい うものです。 ただ、除去できる原因には、短期間で集中的に戦うのが有効とも言われ ています。しかし、除去できない原因と徹底して闘えば、ストレスは強く なるそうです。 つまり、変えられないストレスには、「闘う」より「受け入れる」ほうが 対処法としては効果があるかもしれません。 病気を受け入れるとは、心の態度を変えることであり、「病気とともに生 きていく」という姿勢です。 もちろん、このように思うことは簡単ではないでしょう。 それでも、「そう思ってみようか」、と考えるだけでもストレスは軽くなる のではないでしょうか。 精神科医の斎藤茂太さんは、「無病息災」よりも「一病息災」の気持ちを もったほうがいいと述べています。 また、別の精神科医は、「病気は人生のパートナーと考えられるようにな ると、自分が病気であることのストレスは消失する」と語っています。 医学の力だけでなく、自分の心の力を信じるのも大切なことです。 (by ハートリンクス)
2024年04月18日
コメント(0)
-
【運命を変える力】
【運命を変える力】 運命は、自分の意志や努力で変えられないものではありません。 もちろん、人には生まれながらにして天命というものがあります。 人として生まれたこと、両親を通して生まれてきたこと。 これは自分の力ではどうしようもなく、自分で選ぶこともできません。 天命はどうしようもありませんが、運命は自分の力で変えられます。 つまり、自分しだいで運命をつくりあげていくことができるのです。 たとえば、シャープの創業者である早川徳次さんという人がいます。 彼は2歳の頃、両親が病気のために養子に出されますが、養母も4歳の 時に亡くなりました。 小学校2年の時、学校には通わせてもらえず夜遅くまでマッチ貼りの内職 をしていましたが、近所の井上さんという目の不自由な女性が金属加工を するかざり屋に丁稚奉公を紹介してくれました。 19歳で丁稚奉公をした店から独立し、水道の器具やシャープペンシルを 発明して、200名の社員を抱える会社の経営者になりました。 しかし、関東大震災で妻と二人の息子を亡くし、工場も焼失しました。 それでも、ラジオの受信機を製品化して再起しました。 彼は、丁稚奉公を紹介してくれた目の不自由な井上さんに、恩返しをした いという信念を持ち、目の不自由な人たちが働ける工場もつくりました。 彼は晩年、次のようなことを述べています。 「人生の幸せは自分の力だけで勝ちとれるものではない。 知らず知らずのうちに、いろんな人や社会のお世話になって 築かれていくものである。 これは一つの借りである。 返さなくてもすむ借りかもしれないが、 私は感謝して返していきたい」 運命を変えるきっかけというものは、その人の心しだいで見つかり、心 の持ち方によって運命を変えていくことができます。 (by ハートリンクス)
2024年04月17日
コメント(0)
-
【自分の中にあるいくつかの性格】
【自分の中にあるいくつかの性格】 人の性格は多様です。 有名な心理学者ユングは、まず外交的か内向的で人間の性格を考察 しました。 ある高校のスポーツ部の監督は、全国制覇を10回以上達成し、指導を 通じて人の性格を三つに分析しました。1.絶望あきらめ型 苦しくなると、「もうダメだ、無理だ」思うタイプ。2.消極的納得型 「いやだけど、しょうがないからやるか」という姿勢を持つタイプ。3.積極的プラス思考型 「この苦しみが自分を磨いてくれる。これを乗りこえれば一つ賢く なり成長できる」と信じるタイプ。 結局、歴史に名を残すような偉人や人物は、3番目の人間から生まれる 傾向があり、どのタイプの人間になるかは、考え方ひとつです。 このように、どのようなタイプになるかは自分次第なのです。 さらにこの三つは、ひとりの中に性格の一部としてすべてを本質的に持 っています。 つまり、「弱気な自分」「やらないといけないと思う自分」「苦しくても頑 張るぞという強気な自分」が存在しますが、大切なのは、人は積極的思考 型の人間になれなくても、本来、三つの性格を持っており、弱気な自分を 恥ずかしく思う必要はないのです。 また、人によっては、向上心をもって、積極的な生き方をしなければ ならない、と考えるかもしれませんが、今の自分に合わない枠に、無理 して入ろうとすると逆に生きづらくなります。 弱気な自分になる時があってもいい、と考えれば心も軽くなります。 それは、柳の枝が風に吹かれ、折れそうで折れないしなやかな状態だと いえるでしょう。 そのしなやかさが強さとなることを忘れずに、自分を受け入れていきま しょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月16日
コメント(0)
-
【物を大切にする心】
【物を大切にする心】 昔、ブッダの弟子に、阿難(あなん)という人がいました。 彼は、美男子で非常に人気がありました。 その彼が、ある国の王様から依頼を受け、お城で仕える人たちのため に説法をしました。 お城には500人の女性がおり、阿難の説法を聞いて感動しました。 女性たちは、そのお礼に王様からもらった高価な衣を、阿難に布施と としてプレゼントしました。 次の日、王様は朝食の準備をしている女性たちが、古い衣を着ていること に驚き、 「なぜ、私が与えた新しい衣を着ないのだ」と問いました。 すると、 「阿難様からお話を聞かせていただいたお礼に、布施いたしました」 と答えました。 王様は腹を立て、阿難を城に呼びつけました。 「お前は、500枚もの衣を受け取ったと聞くが、なぜそんなに多くの衣が 必要なのだ」 「お釈迦様には、たくさんの弟子がいますので、みなさんの気持ちをあり がたく受け取り、みんなと分け合いたいと思います」 と、阿難が答えました。 王様は、ブッダの名前を出されると反論できません。 しかしここで黙ってしまうのも悔しいと思い、さらに聞きます。 「では、今まで着ていた衣は捨てるのか」 「捨てません、下着に作り替えます」 「では、古い下着はどうするのだ」 「縫い合わせて、敷き布団にします」 「それまで使っていた布団はどうする」 「敷物にします」 「古い敷物はどうする」 「足を拭く雑巾にします」 「古くなった雑巾はどうする」 「細かく裂いて、床や壁に塗る泥に混ぜます」 さらに阿難は続けて言いました。 「私たちは、施しを受けた物を決して無駄にはいたしません」 王様は、ブッダの弟子たちが物を大切に生かしていることを知り、 ブッダに対し、さらに尊敬の気持ちを抱くようになりました。 仏教に深くかかわってきた日本は、ブッダの教えの影響を強く受け、 物を大切にすることを学んできました。 以前、ノーベル平和賞を受賞したケニア生まれのワンガリー・マータイ さんという環境保護の活動家が日本に来た時、『もったいない』という 考え方に驚き感激したそうです。 どんな物でも生かしきれないことがないように見つめ直し、大切にする 心を育てていくのは大切なことです。 (by ハートリンクス)
2024年04月15日
コメント(0)
-
【心の風通しを良くする】
【心の風通しを良くする】 植物や樹木は、風をほどよく受けないと順調に成長できません。 地上では風や太陽の光を栄養源として吸収し、その後、根は深く広が っていきます。 人も同じように、心の風通しを良くしなければ豊かな人生を送るのは難 しいでしょう。 老子の言葉に、 「深根固柢、長生久視の道なり」 (しんこんこてい、ちょうせいきゅうしの道なり)というのがあります。 これは、心の根を深く張り、基盤を固めることで、物事を長期的に見る 視点を持ち、長寿を迎えることになるという意味です。 樹木や果実の枝を成長させるためには、剪定という作業が必要です。 たとえば、リンゴやミカンの木は、ある時期に間引き剪定を行います。 これにより、不要な枝を切り落とし、風通しを良くします。 「果断」という言葉がありますが、果実を思い切り刈り込むことを指し ています。 よく「勇猛果敢」という言葉を使いますが、「勇猛果断」とも言います。 果断の「断」は断捨離の「断」でもあります。 断捨離はヨガの教えでは、断は不要なモノを断つ。捨は不要なモノを捨て る。離は執着から離れる、という意味があります。 私たちの人生においても同様に、「果断」しなければならない時があり、 身の回りの不要な物だけではなく、心の中の不要な感情を断ち切ることが 大切です。 高い樹木は、しっかりとした根を持つことで成長します。 私たちも、心の風通しを良くし、快適な人生を送りましょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月14日
コメント(0)
-
【心の免疫力を高める秘訣】
【心の免疫力を高める秘訣】 体が病気に罹るように、心も病気になることがあります。 最初は小さなものでも、放っておくとしだいに大きくなります。 また心には知覚神経がないため、痛みは感じませんが不安や、イライラ を感じます。 さらに、体力があるように、心にも力があります。 体の健康のためには運動が大事ですが、心にも運動が必要です。 心を鍛えれば癒される力も強くなります。 では、心の運動というのは具体的にはどんなものでしょうか。 それは、プラスエネルギーを生む、笑いや泣くという感情の刺激です。 たとえば映画を観て、笑ったり泣いたりすることも心に良い刺激を与え くれます。 また、心を鍛えるためには、逆風のような少しきつめの経験をすることも 必要です。 リッツ・カールトンホテルの社長が次のようなことを言いました。 『船の行き先を決めるのは、風の向きではない。 帆の張り方である。 そして、穏やかな海では、優秀な船長も、船乗りも育つことはない』 帆の張り方、というのは心の持ち方です。 風の向きによって、帆の張り方を変えるように、いろんな出来事に応じた 心の持ち方が鍵となります。 人生には、いろんな風が吹きます。 風の力を利用し、風と同じ方向に進むべき時、また風とは反対の方向に進 む時があるかもしれません。 その時のために、心の運動を行うという生活のリズムを持っておけば、心 の免疫力と細胞の新陳代謝も高め、回復力を強くしてくれるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月13日
コメント(0)
-
【幸福な人は自分にイライラしない】
【幸福な人は自分にイライラしない】 幸福度の高い人は、自分に対してイラ立ちを感じない傾向があります。 理由の一つに自分の性格に寛容で、自己肯定感を持っているからです。 逆に幸福度が低い人は、イラ立つことが多く自分に対して厳しさを求め たがり、他人にも厳しさを求めるところがあります。 そのうえ口には出さないためストレスは残ります。 たとえば、私たちがイライラを感じるのはどんな時でしょうか? ある調査では、次のようなデータがあげられました。 1、相手が遅刻した時 2、誰かと会話していると、急に相手がタメ口になった時 3、マナーモードにしておくべき場所で、携帯音がした時 4、車を運転中、割り込みをされた時 5、レストランで、オーダーを聞きに来るのが遅い時 では、これらのことになぜイライラを感じるのでしょうか。 1、相手が遅刻……約束は守るべきもの 2、タメ口で話す……人に対する礼儀がなっていない 3、マナーモードにしておくべき……周りの迷惑を考えていない 4、車の割り込み……自分のことしか考えていない 5、オーダーを聞きに来ない……お客に不快感を与えている 1、2は個人のことに関わるものですが、3、4、5は社会的なことに 関係しています。 個人的なことにイラ立ちを感じるのは「自分の思い通りにならないこと」 で、社会的なことにイラ立ちを感じるのは、自分は守っているのに他の 人が守らないのは不公平だと思い、そこに不条理さを感じています。 これは、社会正義という意識の高さの現れです。 ただ、自分が直接被害を受けないものでも、社会正義の意識は大切ですが 頻繁にイライラする必要はないかもしれません。 このように自分がどんなことにイラ立ちを感じるか、その傾向を知ること により自分を第三者の目線で眺めることもできます。 自分の性格の特徴を知れば、生きづらさを感じることもなくなるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月12日
コメント(0)
-
【やさしさを行動に移す勇気を持とう】
【やさしさを行動に移す勇気を持とう】 困っている人がいたら助けてあげたいと思っても、恥ずかしい気持ちが 起きて行動に移せない時があります。 それでも勇気を出して行動する人もいます。 元アナウンサーの鈴木健二さんは、以前「気配りのすすめ」というベス トセラーの本を書きました。 その中に、やさしさや思いやりがいかに大切かを述べたエピソードがあり ます。 知的な障がいのある兄をもつ、小学1年生のT君の話です。 入学式の日、T君の隣に左腕が不自由な小児麻痺の子が座りました。 体育の授業がはじめての時、手の不自由な子は着替えに30分もかかって しまいました。 2回目の体育の時でした。手の不自由な子は他の子どもたちに遅れないで 並んでいます。どうしてだろう、と思った先生は次の体育の授業が始まる 前にそっと陰から様子を見ました。 するとT君が、一生懸命になって手の不自由な子の着替えを手伝ってい るのです。着替えが終わると、二人は一緒に校庭に駆けていきました。 数ヵ月がたち、七夕の日が授業参観日でした。 先生は、前もって子どもたちに「願いごと」を書かせて、教室にある笹に 下げておきました。 参観日当日、先生はお母さんたちの前でみんなが書いた願いごとの短冊を、一枚ずつ読んでいきます。 「おもちゃをかってください」「おこずかいをちょうだい」といったこと が書かれています。 その中に、一枚だけ次のようなことが書かれていました。 「かみさま、ぼくのとなりのこのうでをなおしてあげてください」 これはT君が書いたものでした。先生はこの短冊を読み、涙を我慢でき なくなり、体育の時間の出来事をお母さんたちに話しました。 先生の話が終わると、手の不自由な子のお母さんが突然飛び込んできて T君の首にしがみついて泣きながら、 「坊や、ありがとう、ありがとう、ありがとう、」と言いました。 T君は、自分のお兄ちゃんが知的な障がいをもっている環境の中で、人 として大切なことを学んでいたにちがいありません。 私たちは、やさしさや思いやりを行動で表わす勇気を持つことによって、 人としての生き方を学んでいくのだと思います。 (by ハートリンクス)
2024年04月11日
コメント(0)
-
【自分の可能性にフタをしない】
【自分の可能性にフタをしない】 人には自分では気づかない能力を持っていることがあります。 潜在能力とも言いますが、あるきっかけで人生を左右するような技術 や能力が発揮されることもあります。 たとえば、明石家さんまさんの付き人だったジミー大西さんは、運転手 として採用されました。 ところが、絵を描く才能があることに目覚め、今では画家として活躍し ています。 このように隠れている才能や能力を発揮する一方で、持っている能力を 自分から妨げている人もいます。 ある美容室のチェーンには200以上の店舗があります。 その中には売り上げの高い店もあれば、低い店もあります。 社長さんが、売り上げを上げるための方法を尋ねたところ、売り上げの 低い店長さんたちが共通して言ったことがあります。 1.「お客が来ないのは、場所が悪いから」(環境) 2.「リピーター率が悪いのは、いい美容師がいないから」(人材) 3.「売り上げが伸びないのは、不景気だから」(お金) つまり、彼らは売り上げが低い理由を外部に求めていました。 そこで、社長さんは言いました。 「自分が原因になってください!」。 この言葉は、原因を外に求めてはいけないことを強く訴えています。 触発された店長さんは自身の行動を見直し、売り上げを伸ばすことに 成功しました。 人生の諸問題においても同じことが言えます。 できない理由や失敗した理由があっても、正当化する人は自分が悪い のではないと考え、自分を守ろうとする傾向があります。 しかし、自分の可能性を信じる力を高めるには、言い訳という可能性を 妨げる考えを改めることが大切です。 (by ハートリンクス)
2024年04月10日
コメント(0)
-
【悲しみをやさしさで包み込む】
【悲しみをやさしさで包み込む】 悲しみをやさしさで包みこむには、強い心が必要です。 また、強い心は歯を食いしばって悲しみに耐えるという一面もあります。 ただ『悲しみの中にも聖地がある』という言葉もあるように、悲しい出来事 を通してやさしい心が育てられることもあります。 江戸時代の俳人、小林一茶は庶民に親しまれる俳句を数多く残しました。 我と来て 遊べや親の ない雀 雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る 一茶は長野で生まれ、3歳の時に母親を亡くし、祖母に育てられました。 父親はやさしい性格で、気の弱い人でした。 8歳の時に継母が来て、男の子が生まれますが、じつの子どもを可愛がり 彼は継母とはうまくいきませんでした。 13歳の時に俳句を習いましたが、継母の希望で15歳になると江戸に奉公 に出されることになりました。 江戸での仕事は、各地を渡り歩く奉公生活で厳しいものでした。 それでも、故郷で習った俳句は彼の支えになり、勉強を続けました。 すると28歳の時には、俳句の宗匠になりました。 俳人としての日々を送り、50歳を過ぎ長野に戻って結婚をしました。 相手は28歳の女性でした。 ところが、幸せな一茶に生まれたばかりの長男が亡くなるという不幸な 出来事が起きました。 その後4人の子どもに恵まれますが、その内の3人は2年足らずで亡くなり 一番下の子どもだけになりました。 さらに、妻も37歳で亡くなってしまい、老いた一茶は悲しみに打ちひしが れました。 しかし、家族を失う悲しみを経験し、一茶の句には奥深さが高まったのかも しれません。 『やせ蛙 負けるな一茶 これにあり』の句は、長男を亡くした時に詠んだ 俳句とも言われています。 彼は、悲しみを受け止めながら、俳句にはやさしさのある言葉で包みました。 俳句を通して、悲しみの中から心の強さを育てました。 悲しいことも、やさしさ包み込む心をもつ人でありたいものです。 (by ハートリンクス)
2024年04月09日
コメント(0)
-
【視野を広くすると寛容になれる】
【視野を広くすると寛容になれる】 自分に厳しいことは、人間性を磨くために必要なことです。 そのうえで他人への寛容な心を持って接していけば、よい人間関係を保つ ことできます。 まじめな人ほど、自分に厳しい傾向がありますが、その反作用として他人 にも同じ厳しさを求めてしまうことがあります。 ある歴史小説家の作品に、次のような話があります。 主人公は若い武士で、自分に厳しく正義感が強い性格です。 上役や藩からも信頼される仕事ぶりでした。 ある時、彼は上役の一人が不正を行っていることを知り糾弾するのですが、 証拠が不十分ということになり上役は罪に問われませんでした。 この事件が原因で、上役と衝突し仕事も取り上げられ、浪人生活を送る ことになったのです。 しばらくすると縁があり、ある老人の家で過ごすことになりました。 彼は、正義が通らない世の中に失望した自分の胸の内を、その老人に話 し続けました。 何日か過ぎたある日、老人が彼に語りました。 「あなたの話はよくわかりますが、ただ一つだけわからないことがある。 あなたは、世の中の悪いことばかりを言うが、自分が悪いことを一言も 云わない。 たしかに、世間は汚い世界ではあるが、考えてみなさい。この世間とい うのは、あなた自身から始まるのだ。賤しい世間であるにせよその責任 の一半は、あなたにもあるのです。 世間は、人間の集まりである以上、自分の責任ではないと云える人は誰 もいないのですよ」。 世の中は、悪いことが横行するような社会であってなりません。 ただ、この老人が若者に伝えたかったのは、不正を糾弾するのは大事な ことに違いないが、その不正を許す仕組みに嘆くだけではなく、現実の 世の中を広く見渡すことも必要だ、ということです。 世の中をつくっているのも自分だから、もう少し気持ちに余裕を持ちな さいということを伝えたかったのです。 寛容であるためには、視野を広くしておくことが必要です。 世の中は、不条理なことだらけだと思えばたしかにそうですが、その 社会で生きていくのも私たちです。 まじめさと寛容さのバランスを身につけていきたいものです。 (by ハートリンクス)
2024年04月08日
コメント(0)
-
【自己肯定は反省から生まれる】
【自己肯定は反省から生まれる】 生きていると、予期しない出来事に遭遇します。 突然の不幸な出来事や、つらいことが起きると、その出来事に振り回され 冷静な自分を見失うことがあります。 何かに取り組んでいても、成功もあれば思わぬ事情で失敗することもあり ます。 人によっては、過ぎ去ったことにクヨクヨして立ち上れないようなことが あるかもしれません。 どんな時も一喜一憂しない心を持っておきたいものです。 「反省すれど後悔せず」という言葉を残した人がいます。 この人物は天台宗の源信という僧で、親鸞聖人の師である法然上人に大 きな影響を与えたといわれています。 反省しても後悔のしすぎはよくない、という意味ですが、世の中は自分の 思い通りに行かないもので、今日はお金持ちでも、明日は貧乏になるかも しれません。 反省から生まれるのは、自己肯定の心ですが、後悔から生まれるのは、自己 否定の心です。 もちろん、誰でも後悔の念を抱くことはありますが、後悔しすぎて自分を 責めるのは自分を傷つけていることになります。 後悔はどこかで断ち切り、これからの生き方の肥やしにすることで、自分 の成長につながります。 私たちは、いろいろな体験を通して生きる力を身につけていきます。 「反省すれど後悔せず」の精神で、前向きに生きていきましょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月07日
コメント(0)
-
【執着心を捨てる秘訣】
【執着心を捨てる秘訣】 ブッダは、執着心をなくしていけば正しい生き方ができ、そのためには 正しい心を持つことの重要性を説きました。 これを『正道』(しょうどう)と教えています。 人が生きていくとき、何事も自分の思い通りにならないものです。 日々の生活でも、喜怒哀楽の感情に振り回されると、執着する心が生ま れストレスも起きやすくなります。 アメリカのある銀行で起きたことです。 駐車場は地下にありますが、利用者は窓口で駐車券にスタンプをもらえ ば料金は無料です。 しかし、利用者の一部が少額なお金を引き出してスタンプをもらい、他の 店で買い物をするようになりました。 そこで、銀行はそのシステムをやめて、駐車料を有料にしたのです。 ある日、このシステムに変わったことを知らない年配のお客が来て、トラ ブルになりました。 しかし、窓口の行員は、お客に横柄な対応をしてしまったのです。 客は、自分の口座から預金額の全部420万ドルを引き出し、向かいにある 別の銀行に預けました。 窓口の行員はトラブルを前向きな問題として考えればよかったのですが、 駐車料が有料であることに執着し、お客の気持ちを考えませんでした。 つまり行員は、お客からのクレームに感情が乱れ、駐車場のシステムにこだ わりストレスを感じて、横柄な態度をとってしまったのです。 そのため420万ドルの預金を失いました。 ストレスは、血液を酸化させ血管を痛めて老化を促進します。 しかし、前向きな心があれば、喜びや笑いの感情になりやすくストレスも 感じにくくなります。 ブッダは、心の執着を捨てるためには、前向きな心が大切だと説きます。 つまり、脳科学的にもブッダの教えは理にかなっていると言えるでしょう。 執着心を捨てるためには、不安なことを考えすぎず、笑うことや喜ぶことを 優先する生活を送りましょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月06日
コメント(0)
-
【随人観美】
【随人観美】 ある小学校の始業式で、校長先生が次のような話をしました。 『1年のスタートにあたって、「随人観美」という言葉を紹介します。 私たちは人に寄りそいながら生きていますから、人とのふれあいが 大切です。 まずは、あいさつをすることでふれあいは深まります。 これが「随人」です。 そして、人は誰しもキラリと光る美しい面を持っています。相手の 良いところをしっかりと認め合うことが必要です。 相手のよさを見つけられる人になりたいものです。 これが「観美」です。まずはあいさつから始めていきましょう』 校長先生の言葉は、大人社会にも参考になります。 「随人観美」とは禅の言葉で、私たちは、長所と短所の両方を持って います。 しかし、人は相手の欠点に目が行きがちですが、美点も必ずあります。 「その人に随(したが)って、美を観ずる」とは、その人でなければ 持っていない美点や良いところを見つけ出すことです。 人間関係は人とのふれあいから始まりますが、どちらかが先に相手の 心に近づいていく必要があります。 もちろん、人見知りしやすい性格の人は、自分から積極的に近づけな いため、ふれあう機会が少ないかもしれません。 それでも相手と気持ちが通じ合えば、うまくつき合えるものです。 他人の美点を見つけるためには、相手への偏見や思い込みをなくす必要 があります。 それには心の謙虚さが大切です。 最初から人を疑いの目で見ず、相手のよさを探し出す気持ちが、自分の 人間性を深め、信頼を高めることになるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月05日
コメント(0)
-
【悪感情とのつき合い方】
【悪感情とのつき合い方】 怒ってはいけないとわかっていても、つい怒りの感情を抱くことがあり ます。 昔、小さなことに腹を立てる人がいました。そこでブッダの説法を聞き にいきました。ブッダは次のように話しました。 「この世には三通りの人がいる。 水に書いた文字のような人で、流れて形がなくなるように、人の悪口 や不快な言葉を聞いても、さらりと手放す人。 次は、砂に書いた文字のような人で、時々腹を立てるが、しばらくす ると、怒りが速やかに消える人。 最後は、岩に書いた文字のような人で、時々腹をたてて、その怒りを 長く持ち続け、岩に刻んだ文字のように怒りが消えない人です。 さて、みなさんはどれに当てはまりますか? そして、その怒りのために苦しんでいるのは誰でしょうか?」 この説法を聞いた男は自分のことだと気がつき、声を上げました。 「お釈迦さま、私はもう怒りで家族も自分も傷つけたくありません。 どうすればよいでしょう。」 ブッダは言いました。 「怒りの言葉を口から出すのは、下等の人間です。 歯を食いしばって、口から出さないのは中等の人間です。 胸は怒りでいっぱいでも、顔に表さないのが上等の人間です。 怒りの気持ちを抑えて、優しく話すことを心がけなさい。」 仏教に「十善道」「十悪道」というのがあります。 「十悪道」とは、殺生・盗み・邪淫・妄語・狂言・悪口・二枚舌・貪欲 怒り・邪見です。 「十善道」とは、「十悪道」をしないことだと教えています。 怒りの感情を吞み込んで笑顔になるのは難しいことですが、他の悪感情 から逃れられるかもしれません。 感情に支配されないためには、感情から一歩引いて自分自身を客観的に 見つめることが大切です。 この時間を一日に数回でも持つことにより、しだいに感情の影響を受け にくくなるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月04日
コメント(0)
-
【柔らかで弱いものには徳がある】
【柔らかで弱いものには徳がある】 赤ちゃんは、素直で、ありのままの自分を表現します。 いつも笑顔で、時おり泣くこともありますが、それは感情を伝える メッセージです。 言葉は使えませんが、心と体には柔らかさに満ちています。 老子の言葉に「柔弱の徳」というものがあり、次のように語っています。 『人が生まれるときは柔らかく、死ぬときは固くなる。 植物が生きているときは、柔らかくしなやかである。 つまり、柔らかさとやさしさは命の友なのだ。 木の幹は固く下にあり、枝や葉などやさしく弱いものは上にある。 固くて下位にあるものより、やさしく弱いものが上位にあるのだ。』 つまり、人は赤ちゃんとして生まれたときが、いちばん徳を持っている 状態なのです。 しかし、人は大人になるにしたがって、心は怒りや恨みの感情に振り回 されるようになり、本来持っている徳が隠れてしまいます。 では、どのような気持ちで生きていけばよいのでしょうか。 船井幸雄さんは、「人生とは、車を運転するようなものだ」と述べてい ます。 生まれてすぐは、親から生きてくためのことを教わります。 これは、自動車学校に通っているようなものです。 次に、社会人になるためにたくさんのことを学びますが、これは勉強し て試験を受ける時期であり、仮免許の時にあたります。 やがて、社会に巣立ち家庭を築くようになります。 最初は、初心者マークを貼りますが、しだいに上手になり行きたいとこ ろに行けるようになるのです。 山あり谷あり、急カーブありの道でもどうにか目的地につくには、運転 技術のレベルによっては要する時間も変わるでしょう。 この時、運転者に「柔弱の徳」の精神があれば、思い通りの人生を走れ るのです。 大人になっても、柔らかさとやさしさを忘れずに持ち続けることが、 人生を思い通りに歩む秘訣です。 (by ハートリンクス)
2024年04月03日
コメント(0)
-
【やり抜く力は自己信頼から生まれる】
【やり抜く力は自己信頼から生まれる】 目標を達成するためには、あきらめずに最後まで努力を続けることが 必要です。 自己信頼は一時的なものではなく、持続的は信念によって本物の力を生 み出します。 何年か前、あるテレビ番組で、自己信頼が高い人に共通する特徴が紹介 されました。 1. 失敗のすべてを自分のせいだと考えない。 一般的には、責任を転嫁するのは良いことではない、と思いがちです。 しかし、「失敗した原因は、自分じゃなく状況が悪かった。このまま努力 を続ければ何とかなるだろう」と、楽天的にとらえることも大切です。 2. つらいときは人を頼っている。 つらいことがあれば多くの人は我慢をします。 しかし、自分を追い詰めすぎず、誰かに助けてほしい、と考える傾向が あります。 3. 感情に振り回されない。 結果がよければ嬉しくなり、失敗すれば悲しくなりますが、一喜一憂せ ずに、冷静に対処します。 仏教に次のような物語があります。 雨が降らず、水も干上がっている池に一匹の亀がいました。 もう少しで死にそうですが、空から見ていた鳥が、亀を救おうと一本の 木の枝をくわえて、亀のそばに舞い降りてきて言いました。 「この枝に嚙みついていなさい。そうすれば水のある池まで連れていって あげよう」 亀は言われた通りにすると、鳥は枝をくわえた亀を持ち上げて、飛んでい きました。 すると、その姿を地上から見ていた人たちが、 「あれは何をしているんだ、おかしなことをしているものだ」と笑い ました。 亀は、自分が笑い者にされていると怒りだし、文句を言おうと思わず 口を開きましたが、亀は地上に落ちて死にました。 これは、他人の目を気にして一喜一憂することの愚かさを教えてくれる 話です。 自己信頼の力を養うためには、楽天的な考えを持ち、他人への協力の依 頼に気を使わず、感情に振り回されないことが大切です。 (by ハートリンクス)
2024年04月02日
コメント(0)
-
【気にしすぎることの利点】
【気にしすぎることの利点】 まじめな人に共通する特徴として、くよくよするところがあげられます。 小さなことが気になり、物事を消極的に想像し、不安になるのです。 しかし、精神科医の中には、 「くよくよ性のいい側面は、心の準備ができていることだ」と分析する人 もいます。 これは、最悪のことを予測し、対応ができるという利点があります。 くよくよタイプの人には、真面目な反面、自分に自信を持てず人と比較 して落ち込むという傾向があります。 もし、くよくよ性で悩んでいる人がいたら、無理して直そうとせず気持 ちの切り替えがうまくできないだけだ、と考えてみましょう。 ブッダの言葉に、「過去は、現在におさまる」というものがあります。 過去に起きた出来事を変えることはできませんが、その出来事をどのよ うに受け止めるかは自分次第であるという意味です。 人は、つらい過去の思い出を、記憶の奥から引き出すことがあります。 例えば、「なぜ、あんなことをしたのだろう」「どうして、ひどい目に遭 うのだろう」と悔やむことがあります。 たしかに、つらい過去はあるのですが、厳密に言えば「過去をつらいと 思う自分がここにいる」だけなのです。 自分の記憶の中にある過去に縛られていては、心の成長は止まってしま います。 つらかった過去を肯定し、受け入れることでくよくよ性の利点が現れ豊 かな人生を送ることになるでしょう。 (by ハートリンクス)
2024年04月01日
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1