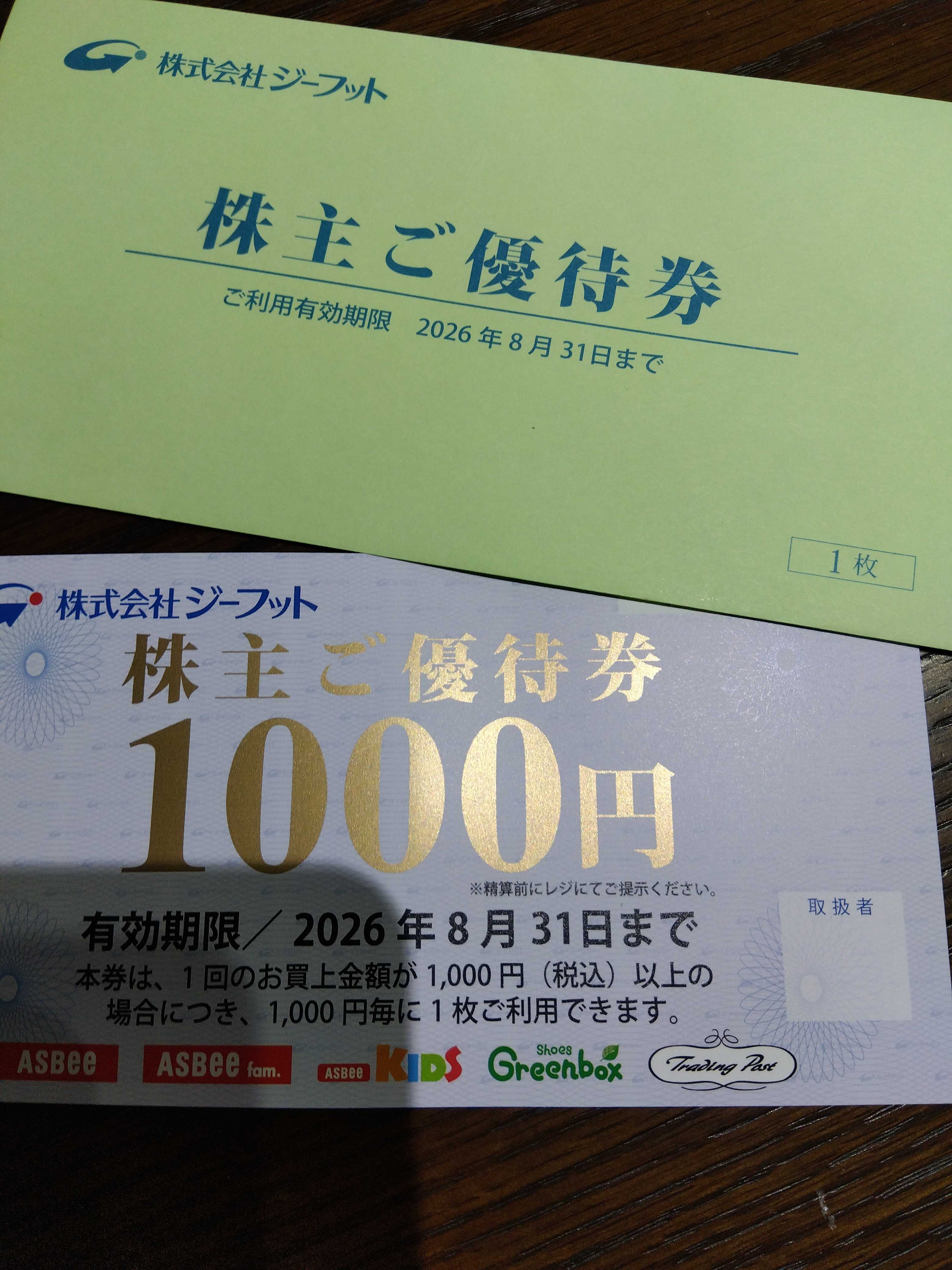全1378件 (1378件中 1-50件目)
-
あれから・・・
あの震災から1年。帰宅困難者にはなったけれど,直接的な被害はほとんどなかったものの,震災前とは気分を筆頭に,さまざまなものが変わってしまって,日常は流れて行くけれど,今も元には戻らない。そんな中,1月末に父が89歳で老衰のため他界した。17年の介護生活の末,自宅で最期を看取った。晩年の10か月ほどは大きな病はないものの徐々に衰弱していく日々で,看取るということの想像以上の困難さを感じる毎日だった。今,四十九日の法要も終えて,新たなスタートを切ったところ。母の介護は続くけれど・・・。
2012年03月12日
-
お見舞い申し上げます
大変な災害になっているようです。被災された皆様にお見舞いを申し上げます。都心の高層ビル勤務なので,大きく揺れ,パソコンの画面を見ていると船酔いしたように気分が悪くなりました。様子見の意味で食事を先に済ませ,動き始めた地下鉄で途中駅まで行き,残り半分を3時間かけて歩いて帰宅しました。幸い,途中に地震の影響はなく,停電もなかったので,安心して歩けましたが,地下鉄で踏ん張っていた足に疲れが出て,寒さも加わり,足がけいれんを起こしたりしました。しかし,自治体の機関だけでなく,個人商店でもトイレや休憩場所を提供してくれているところをたくさん見ましたし,水や食料などを配ってくれるところなどもあって,助けられました。建物の損壊が出たり,停電などが起こった場合に同じように歩けるかというと,とても不安になります。銀座ではヒッチハイクを試みている女性グループもありましたが,幟を立て,そろいのヘルメットをかぶって十人前後のグループで集団で歩いて帰宅する会社があるのをたくさん見ました。これが一番正しい方法のような気がしました。
2011年03月13日
-
若きヘルパーに
父は要介護5の認定から3年,多くの動作は介助がなければできない。しかし,最近はアルツハイマーの症状も進み,周辺症状として介助に対する拒否も強くなってきた。ヘルパーは日替わりでいろいろな人が来るのだけれど,多くの人はまだ若く,少し茶髪だったり,耳にピアスの穴が開いていたりするが,わがままな父を宥めたり煽てたりしながら,上手に介護してくれてありがたい。 わがままも 動かぬ体も抱きとめる 若きヘルパーの胸の広さよ
2010年02月14日
-
三十一文字
ここのところちょっと気になるあれこれを三十一文字にまとめている。今は専ら介護絡みのものばかりになるが,少しずつここでつぶやいてみようと思う。必ずしも短歌とまでは言えず,狂歌と呼ぶ方がふさわしいものもあろうかと思うが,ここでは区別せず,三十一文字ということで・・・。ケアマネ,ヘルパー,リハビリ,デイサービス,ショートステイetc.etc.・・・介護関係者と打ち合わせをしているとカタカナ言葉の多さにうんざりする。被介護者にとっては耳慣れない言葉が多いはずで,これらの用語が誰のために使われているのか,少なからず疑問を感じる。 この国の制度の遅れ示すように 介護用語は横文字ばかり
2010年02月05日
-
健気にも・・・
梅雨最中の6月下旬,突風とスコールのような雨に打たれて,都心の横断歩道脇に高く伸びていたタチアオイの一群れは無惨になぎ倒されていた。ところが,翌日朝からすっかり晴れると,タチアオイは,昼休みには,正にすっくという感じで起き上がり,凛とした姿を見せていた。 雨過ぎて 葵の再び立ち上がる
2009年07月15日
-
黒いスナフキン
最近はゴミの分別が進み,駅に置かれたゴミ箱も,雑誌・新聞や缶・ペットボトル等はきちんと分けられていることが多い。そうしたゴミ箱から,雑誌や新聞を抜き取って読むサラリーマンの姿も決して珍しくはないが,一方で,これらをたくさん集めて売り,日々の暮らしのための現金を得ようとするホームレスと呼ばれる人たちも目立つようになってきた。冷たい風が吹き,都内でもかなりの雪が降った夜,仕事帰りに地下鉄の駅で出合ったのも,全身黒ずくめのスナフキンといった出で立ちの,そんなホームレスの一人だった。 服装とコーディネイトしたかのような真っ黒なキャリーケースをゴミ箱の脇に引き寄せたのを目の端で捉えて,ああまたか,と深く気に留めることもなく,その後ろを通過しようとしたとき,彼の右手が,キャリーケースの引き手の辺りから,細長く銀色に光るものを真上に向かって抜き出すのが目に入り,思わずドキリとした。 彼が手にしていたのは長さが6,70センチもありそうな,細長いU字型のゴミ挟みだった。彼は,それを器用に操りながら,細長い投入口から,きっとその日の夕食に代わるであろう新聞や雑誌を次々に取り出し,キャリーケースの上に積み上げ,ひもで括って何事もなかったかのように立ち去っていった。
2009年03月05日
-
ご無沙汰しました
ただでさえ忙しい師走というのに,父が腸閉塞を起こし,10日深夜に救急搬送,緊急手術を受ける事態となり,職場等,周りにも多大な迷惑をかけつつ,彼方此方を飛び回る日々を過ごしていた。 それでも,緊急入院は,緊急事態が解消すれば打ち切られるのであって,早々に明日,退院の見込みがつくところまでたどり着き,今後の在宅介護に不安を抱きつつも一息ついている。 その間,消防庁の救急相談(#7119),いわゆるたらい回し問題に関わる搬送システム,差額ベッド,高齢者医療と介護保険の関係等等,いろいろな体験をし,思うこともさまざまあった。 それらについては,機会があれば,別途書いてみたいと思う。
2008年12月20日
-
闇にうごめく影
心配された「猛烈な台風」の接近もなく,文字通り爽やかな秋晴れの日が続く。日が短くなってとっぷりと暮れた帰宅時,すっかり舗装された歩道の上に,街路樹のためにわずかに顔を覗かせている地面には,いろいろな草が生い茂り,その中からは集く虫の音が,か細いながらもしっかりと耳に届く。そんな如何にも秋の夜長らしい雰囲気に浸っていると,バス停脇の草むらが突然ガサゴソと何やら大きな生き物の気配に激しく揺れ動く。さすがにギョッとして後ずさりながら見ると,這い蹲るように屈み込み,手のひらでそうっと地面を探っている高齢の男性が姿を現した。作業服姿の彼の,ゴム手袋で武装された左手には,近所のコンビニのレジ袋が握られている。そこで初めて彼の目的に気づく。そう,もちろんギンナンである。大型車両も多く行き交う4車線の道路脇に並ぶ街路樹は,確かに東京都の木,イチョウである。その根元に転がる,わずかに薄茶色を帯びた小さな鈴のような丸い実は,人や車に踏みつぶされて独特のにおいを発して,その存在を知らせていることに私も気づいていなかった訳ではないし,早朝には実際に拾っている人の姿を見ることも多い。が,時間が変わるとこんなにも不気味な所業になるものかと,そのことに少なからず驚かされた。
2008年10月04日
-
理由
エッセイ集には書いたことだが,携帯電話でメールを打つことには,非常に苦手意識があるので,緊急に必要があるときにしか打たないことにしている。なぜこれほどまでに苦手なのか,自分で考えてみたのだが,その結果,原因として,文字入力の煩雑さに思い到った。いわゆるテンキーをア行,カ行と割り付けることは,仕事で同じような作業をしていた経験があるので,私にとってもさほど難しいことではない。しかし,一つのキーに割り当てられている文字が多すぎ,打ちたい文字を呼び出すのに何度もキーを押さなくてはならない点は何とも煩わしい。例えば,「者」という文字を打つのに,「ま」,「み」,「む」,「め」という四文字を見送って「も」を出し,「の」を出すために同じ作業をもう一度繰り返して,さらに漢字変換までとなると何度キーを押さなくてはならないのか,ほとんど耐え難いものがある。これにカタカナや数字を混ぜようとすると,さらに入力モードの切り替えまで入り,もう訳がわからなくなる。しかもそれを右手の親指一本かせいぜい二本の指で操作しなければならないのがまた苦痛である。そして,このように入力に時間がかかり過ぎると,思考停止の状態になってしまい,思い浮かんでいたはずの文章を見失ってしまうのだ。この点,パソコンのJIS規格キーボードなら,私の場合はローマ字入力をしているので一文字を出すのに二文字ほど打たなければならないが,両手の指を使って立て続けにキーを連打すれば,おそらく手書きするより早いくらい瞬時に入力が終わり,文章が頭に浮かぶスピードとのズレを感じる間もなく文字にすることが可能なので,全く入力のストレスを感じず,文章を練ることに集中できる。慣れと言ってしまえばそれまでのことかもしれないが,私の場合,習熟するまで携帯電話でメールを打ち続ける気力は既に失われている。
2008年09月11日
-
タイムトラベル
「俺の軍服は,どこへやったんだ?」今朝の父の第一声である。この言葉からすると,今朝の父は,昭和20年ころの記憶の中をさまよっているらしい。「軍服なんて見たことないよ。」それとなく否定してみるが,全く納得していない様子で,「昨日帰って来ただろう。そのとき着てたやつだ。」と続ける。父は要介護5,ほとんど寝たきりなのだ。「帰って来たって,どこから?」と尋ねると「俺が部隊から戻ったのは昨日だろう?」と言う。「戦争が終わってもう60年以上過ぎてるんだよ。」と,やんわり否定してみるが,やはり全く理解できない様子で,不満そうな顔でしきりに首を捻っている。数日前,父は,昭和50年ころの記憶の中にいた。やはり朝の第一声が「俺の車はどこに停めたかな。」だった。不審に思いながらも,ありのままに「車はもう10年以上も前に処分したじゃない。」と答えると,如何にも困った様子で言った。「仕事に行かなきゃならんのに,どうするんだ。」父が仕事を辞めてから既に13年の月日が流れている。広い意味での認知症の症状である。少なくとも3年くらい前からこういう状況は始まっていた。父の行動がおかしいと思い始めたある日,目の前にいる私に向かって,突然父が尋ねた。「菜摘はまだ学校から帰らんのか?」どきりとしながらも,質問の意味を図りかねて聞いた。「目の前にいる私は誰なの?」答えは象徴的かつ衝撃的だった。「お前は妹だろうが。」話を続ける中で,そのときの父にとっての私は,小学生くらいの少女の姿であるらしいと思い至る。父はそういった時間の記憶の中にいるのだった。最初のうちは,こちらも状況を飲み込めず,しっかりしてよ,とばかりにむきになって訂正し,言い合ったりしたが,それは父を苛立たせるだけであると気づいた。強く否定するのではなく,ある程度受け止めながら噛み合わない会話を続けるうち,自分でも混乱するのであろう,やがて父は黙り込んでしまう。そして,そのまま時間がすぎると,そのような会話など,すっかり忘れてしまうのだということをこちらが学んだ。父の意識は,自由に時間を飛び越えて,遠い過去を一瞬にして引き寄せる。歳を重ね,そう,父はタイムトラベラーになったのだ。さて,明日の父は,どの時代に目覚めるのだろうか。
2008年06月22日
-
不穏な駅前
クリニックに寄って帰宅する途中,地下鉄の改札口の前で酸素ボンベを背負った尋常ではない出で立ちの消防士の姿にドッキリする。それでも,消防士は,まるで場違いのように一人きりだし,構内に全く緊迫した様子もないので特に気にせず,バスターミナルへ向かう。と,階段を上りきったところで,赤色灯に包まれて呆然とする。ターミナルは救急車やパトカーと,8台くらいのいろいろな消防車で埋め尽くされていた。消防のアナウンスによれば,地下鉄の回送電車で黄色い(?)液体が撒かれているとの通報があったという。目の前の光景と,そのアナウンスとで,突然くっきりと地下鉄サリン事件を思い出してしまった。一時は地下鉄も部分的に運転を見合わせたようだが,特にニュースにもならなかったので,悪い悪戯というところだろうか。それにしても,台風も地震も続くけれど,一番荒れているのは人の心ではないかと思わせるような殺伐とした事件が多すぎる…。
2008年05月12日
-
気になっちゃって
新人たちがそろそろ現場に出てくる季節を迎えている。売店等,あちこちで「研修中」や若葉マークのプレートをつけた初々しい姿を見かけることも多い。今朝の丸の内線の運転手もそういったうちの一人だったのかもしれない。ある駅に着いたとき,少しオーバーランをし,緊急停止装置が働いたようで,プププという非常音とともに急ブレーキがかかった。その後,電車をバックさせたのだが,このときも普段以上にガクッガクッと妙な揺れ方をした。そういったことの影響か,その後の進行は少々遅れがちになった。登校や出勤の時間帯,乗客は遅れに寛容ではないのが常だ。そこで,すかさず車掌がお詫びの車内放送を入れた。「お忙しのところ,誠に申し訳ございません。」ん?私の聞き違いだろうか。普通なら「お急ぎのところ…」と言う場面である。しかし,聞き違いではなかった。駅毎に電車の遅れは大きくなり,そのたび車内アナウンスは繰り返されたのだが,何度聞いてもはっきりと「お忙しのところ…」と言っているのだ。状況からいって,やはり「お急ぎのところ」が正しいだろうし,どうしても「忙しい」を使いたいのであれば「お忙しいところ」と,「の」を抜いて欲しい,「お忙しのところ」というのは何だか滑稽な感じだけど…などと気になってしまって,今朝の車内読書タイムは失われてしまったのだった。
2008年04月25日
-
確定申告
先週のことだが,いわゆる「住宅ローン特別控除」を受けるために,初めて確定申告をした。これまでも申告をすれば医療費控除を受けることはできたと思うのだが,その労力と控除額とが見合わないような気がして放置していたのだが,住宅ローンの場合は控除額が大きいので申告しないわけにはいかない。学生時代に家業について青色申告をしていた経験はあるが,確定申告は初めてである。雑誌を立ち読みし,インターネットで作成するのが良さそうだと判断し,資料をそろえて深夜に挑戦する。計算等について,数字の入力に気を使う場面はあったものの,案外簡単に作成できたし,プリントアウトすると必要な資料や送付先の宛名書き用紙までそろっていたので,郵送することも考えたが,万が一不備を指摘されると面倒なので,朝一番乗りで窓口に持参する。と,非常にあっけなく受理されてしまった。「おおよそ2か月くらいで還付されます。」とのこと。これなら郵送でもよかったかと思う。また,ネットで直接申告をすることも可能であるということで,提出資料の免除等さまざまな特典も宣伝されているが,事前の登録やカードリーダー等の設備が必要であり,初期費用が発生することになるので,今回は見送った。今後医療費等で毎年申告をするようならば検討の余地はあるかもしれない。
2008年03月10日
-
終日勤務
休日当番で,終日勤務。昨日に続いて強風が吹き荒れた一日。通勤途中の歩道で,自転車で抜いていった若い男性のキャップが強風に舞い上がり,私の肩越しに後方へ飛ばされていった。普段は静かな休日の執務室も,風がドアを揺する音が,時折びっくりするくらいに響く。気温も下がって来て,閑散とした執務室は暖房の効果も薄く,なかなか暖まらないまま過ごす。帰宅後,母親が気にしていた雛人形を略式で飾る。さて,今週は長い一週間になりそうだ。
2008年02月24日
-
春一番は煙霧の中
午前中,両親の介護の関係で,あちこちで話を聞く。休日になると思わぬ所からの連絡も入ってくるし,平日は見ることが出来ない両親の日中の暮らしぶりも実感できる。介護保険の担当者とかかりつけ医師との意見が真っ向から対立していることもあって,プロでもないのに間に入った立場で,悩みは深まる一方だ。午後になって,急に空が暗くなってきてはいた。一雨来るかと洗濯物を気にしながら,時折外を眺めていた。近所で何か大きな物が転がる金属的な音がしたので,ふと目を上げると,窓の外は茶色っぽく煙っている。送電線も洗濯物も大きく揺れていて,風が強いのに気づく。あまりの空気のけむり方の方に驚き,ベランダに出ると,強風は台風のように物凄く,乾燥しきった土埃を大きく巻き上げているのだった。慌てて洗濯物を何とか取り込み,しっかりと戸締まりをする。その僅かな時間の間だけでも,全身埃っぽくなってしまった感じがする。このような煙霧現象は初めての経験である。激しすぎる春一番は,ひとしきり吹き荒れて,やがて徐々に収まり,夕方には天気も回復して青空が戻った。
2008年02月23日
-
節分の雪景色
予報どおりの積雪。冷え込みも厳しい節分となった。夕方覘いた近所の広場は雪遊びに興じる人で賑わっていた。小さなかまくらに大きな雪だるま,ソリを持ち出した子どもたちもいた。雪国の人には叱られそうだが,東京では滅多にないことなので,大人でも心が弾んでしまう。
2008年02月03日
-
しゅ,出版社が…
新年早々,こんな日記を書くことになるとは思わなかったのだが,多くの方に応援していただいだ,私の処女作「聞こえるようにひとりごと」の出版社である新風舎の再生手続申請のニュースが流れた。事実上の経営破綻である。再生の見込みがあって,作成中の本については出版するとはいうが…。個人的には2刷分の在庫の管理をしてもらっているはずであり,今後の成り行きを注視しなければならないと考えているが,昨年秋ころからの訴訟のニュースが入ったときから,実はこういう事態をある程度予想していた。私自身の経験から言っても,細かいトラブルが多い会社ではあったが,出版業界というものは,よほどの大手でない限り,かなり微妙な商売をしているのではないかと感じている。原稿料を踏み倒されたなどという話は身の周りにいくらでもあるものだ。誠実な商売をしてもらわなければならないのは勿論であるけれど,出版社の経営基盤などというものは,多分私たちが想像している以上に脆いものではないかと実感させられるニュースであった。
2008年01月07日
-
どこまで続くか…
日記の更新を怠っている。いや,彼方此方見て回ることもなかなかできない状態が続いているが,その理由は,仕事ではなく,介護の負担が大変になり,自分の時間を持つことができないためである。日常生活に差し支えがない程度の睡眠時間を確保しようとすると,ノートPCを開く時間がほとんど取れなくなっている。父はいきなり要介護5,その介護を担ってきた母にも認知症の症状が現れ,介護認定を受けることになり,要支援1となった。こうなったら,ここも介護日記にでもすればよいのだが,介護の日々の実態は,なかなか他人に語れるものでもなく…。
2007年12月03日
-
仙崖さん
6時前に仕事を終えることができたので,金曜日は7時まで公開されている出光美術館へ,仙崖展を見に行く。久々の改装なった美術館が,どのように変化しているかも気になるところだったが,陶片の展示室が整理され,入りやすい雰囲気になった点を除けば,展示スペースには大きな変化を感じさせず,ゆったりと見て歩くことができる余裕はそのままだし,一服できる休憩スペースもこれまでどおり確保されていて安心した。さて,「仙崖さん」である。数年前に,同じ美術館で見て,白隠の再来とも言われたその禅画の優しい面白さの虜になった。例えば,「月ハ」と書かれているけれど画面には月は描かれておらず,子供と一緒に,何かを指差し,見ている者もついつられて笑ってしまいそうな笑顔の人だけがいる。また例えば,菊の画が描かれていて,キクというけれど耳は無し,ハはあるけれど飲み食いするわけで無しといった詞が添えられている。禅画なのだから,もちろんそこには深い教えが込められているのだが,そういうことをひとまず置いて,素朴で明るい画を愉しみたい。まるで駄洒落のような詞を味わいたい。ほっと心が緩み,ついニヤリとさせられ,温かい気持ちになる。画も詞も,余分な物をすっかり削ぎ落とした,研ぎ澄まされたともいうべきものである。しかし,味わっているうちにそこに込められた意味を考えさせられ,自分のあり方を振り返らされる,そんな力を持っている。「週末エッセイスト」としては,表現というもののあるべき姿について,いろいろな想いが呼び起こされるものである。
2007年10月19日
-
朗読会
「<ライブセッション>リンボウ先生、明治の文豪を読む」を聴きに,横浜の近代文学館へ行く。チェンバロの演奏と師匠による「作家の朗読」という組み合わせだ。朗読作品は,漱石の『夢十夜』,子規の『歌よみに与ふる書』,鏡花の『妙の宮』,村井弦斎の『食道楽』,鴎外の『ぢいさんばあさん』というラインアップ。私にとっては馴染みの薄い作品もあったが,約百年も前に生まれたものというのに,古さを感じさせず,すっかりストーリー展開に引き込まれてしまった。チェンバロの演奏は,朗読の前後にまとめられていて,贅沢なひとときを演出していたと思う。ただし,個人的には朗読の余韻に浸っているときに,自分の感覚とはかなり離れたイメージの曲が演奏された部分があって,少し残念に思われた。いずれにしても,手つかずのままになっていた『食道楽』辺りから,読んでみようと思った。今年の秋は,読書の秋にしよう。
2007年10月08日
-
当たっちゃった
思いがけないことに,気まぐれで締め切りの前日にネットで応募したサ○トリーの「氷出し碾茶セット」が当たった。包みを開けると,パンフレットと共に,日本茶に似合いの深い緑色も美しい箱と,茶器を飾る真紅の組み紐,真空パックの碾茶(茶葉)等が現れる。茶器は,濾過をする部分を中心に背の高いフラスコを逆向きで重ねたような,予想外にシンプルな構造である。ガラス器を想像していたのだが,主にPET樹脂でできていたのは少なからず残念である。しかし,氷出しでお茶を淹れるには,この数日の気温は低すぎる。茶葉の鮮度が落ちないうちに,もう一度暑い日が来てほしいと思うが,さすがに無理のようだ。
2007年10月07日
-
時節は秋
ここ数日の涼しさに,秋の訪れを感じてはいたはずだが,定時退庁日だというので午後6時前に職場を後にすると,外がすっかり暗くなっていることに驚かされる。残暑の厳しさに季節を忘れていたが,いつの間にかずいぶん日が短くなったものだ。メールを開くと,なじみの古書店からは,恒例の神田古本まつりが,今年は10月26日から始まるという案内が届いていた。通りかかった食料品店では,ボジョレーヌーボーの予約票を配っている。気の早いことに,文具店には来年のカレンダーや手帳が並び始める。引っ越し以来,通勤途中に自然の中から季節を感じる機会はめっきり少なくなったが,それでも,ここのところ微かに銀杏が香るようになってきた。
2007年10月03日
-
神無月は
冷たい雨が降る週末を越えて10月が始まった。つい先日までの猛暑ですっかり後回しにしてしまった衣替えだが,今日などは上着等,何か羽織る物が欲しくなる。10月の声を聞くと,急に今年の残り時間が気になり始めるのは私だけだろうか。秋には何かと行事も多く気忙しく過ごしてしまうせいもあろうし,日ごとに加速度的に早くなる日暮れが1日を短く感じさせるせいもあろう。いずれにしても,やるべきことが気になるだけでなく,旅行に観劇にと心誘われる機会も増えてどんどん落ち着かない気分に追い込まれてしまう。ただ,今年も紅葉は遅く,都心辺りでは12月になるというから,少しのんびり構えるのもよいかもしれないなどと考えてみる。残り時間に変わりはないのだけれど…。
2007年10月01日
-
月観る月
地球温暖化の深刻さを感じさせる夏日が続いていた9月だが,秋の彼岸も中日が過ぎて,急に風の色が変わったように感じられる。まさに「暑さ寒さも彼岸まで」というように気温が下がり,ここ2,3日は曇りがちで時折雨も降っていた。それにもかかわらず,昨夜はよく晴れて,美しい中秋の名月を愉しむことができた。今日もより丸い月が出ていたが雲にぼやけて見えた。実は満月は明日27日であって,昨夜はまだ少し欠けているのが目で見てもわかったのだが,旧暦8月15日という日付けこそが大切なのであって,満月にこだわらないところが面白いと思う。本来なら「芋名月」であるが,我が家の夕食のメニューは栗ご飯であった。
2007年09月26日
-
講座 歴史の歩き方
仕事を定時で打ち切って,ダッシュでよみうりホールへ。林望師匠のコンサートを断念して参加することにした講座 歴史の歩き方の「『六歌仙』の時代―『万葉集』から『古今集」の世界へ」を聴きに駆けつける。講座は二部構成で,前半は多田一臣氏による「『仮名序』の文学史」,後半は小町谷照彦氏による「六歌仙 歌と伝承」という内容だった。多田氏の講座は,まさに万葉集から古今集までの,和歌の歴史の概要を辿るもので,とても早口で駆け足の講演だったが,内容は盛り沢山ながら整理されていてわかりやすかった。小町谷氏の講座は,六歌仙に古今集の仮名序を中心としていろいろな面からアプローチするもので,苦心作のレジュメも素晴らしく,とても面白い講演だった。お名前のせいか,小野小町が特にお気に入りのようで熱が入っていたことと,お気に入りの蔵書のご自慢などに親近感を持てた。受講者は圧倒的に年配者が多く,常連も多いように見受けられたにもかかわらず,講座の前半など,度々携帯電話の呼び出し音が鳴るといったマナー違反がかなりあったことは残念。そして困ったことは,現在では入手困難な本のいくつかを読みたくて仕方がなくなっていることである。
2007年09月14日
-

「本物」のモアイ
書店に行くつもりで訪れた丸の内,地下鉄の改札を出た所のあちらこちらに貼られたポスターで,丸ビルに「本物」のモアイ像が来ていることを思い出し,立ち寄ることにする。東京駅側から広場へ出ると,ほぼこちらを向いた形でモアイ像が立っていた。確かに大きな石像ではあるが,もっと背の高い物であろうと勝手な想像をしていたので,何だか可愛らしく感じられる。正面から眺めると,何と言っても黒い瞳に,珊瑚をはめ込んで作られた真っ白な白目の先端が顔からはみ出さんばかりの大きな眼に引きつけられる。眼の上には,出っ張ってはいるものの極めて狭い額,そして両眼の間には鼻筋の通った大きな鼻がくっきりと表情を作っているのだが,口については,鼻の下に緩やかな弧を描く膨らみがうっすらとあるだけで判然としない。 太い首の下には,顔に比して小さめの胴があるが足は見えない。肩だか胸だかわからない膨らみの他にはぷっくりとしたお腹に大きな臍だけが目立つ。その臍の下に大きな掌が指をきれいに伸ばした形で行儀良く添えられている。横へ回ると高い鼻と大きな耳が目立つ。が,シャープな顎のラインと,長い腕もなかなか美しい。ところが,後ろへ回って驚いた。モアイ像の背中には一面に細かな模様が刻まれ,陰陽を表すかのように向かって右側は白く,左側は黒く塗り分けられている。テレビで何度か見たモアイ像だが,これまでその背中を意識して見たことはなかったかもしれない。それにしてもこれほどの細工がなされているとは予想もしないことだった。その模様が何を意味しているのかわからなかったが,多くのことを物語っているように感じられる。ただ,残念だったのは,今回展示されているモアイ像には歴史がないということだ。確かにイースター島で,現地の人によって,その島の石に刻まれ,マナ(霊力)まで与えられたものであることには偽りはなく,その点では「本物」と言って間違いではないのかもしれない。しかし,わざわざ「本物」と言うとき,我々素人がイメージするものは,はるか昔に先住民たちが刻んだものであって,わずか数年前に意図的に作られたものではないだろう。
2007年09月13日
-
文楽デビュー
友人を通じ,大夫の入門解説付きで文楽というものを初めて体験した。 演目は,三大名作のうちの一つ「菅原伝授手習鏡(すがわらでんじゅてならいかがみ)」である。今回の公演は初段と二段目のみなので,本当の意味でのクライマックスは抜きであったが,大夫の熱演,三味線の迫力,人形のしなやかな動き,その一つ一つが私の想像を超えていた。そして,さらにそれらが三位一体となって作り出す世界は,今まで触れたことのないものであって,新しい世界に踏み込んだ興奮を感じ,大変面白いものであった。 大夫の説明で特に興味を惹いたのは2点。 まず,大夫は一人で何役も演じるが,それぞれ声色を使うわけではなく,自分の声のまま,息を使い分けることで演じ分けるのだという点だ。その内容は,私の力では文章で表現できないが,実演によってよくわかった。人間の話し方というものは,年齢,性別,身分によって異なるが,その差が,実は,息づかいの違いによって感じられるものらしいと気づかされ,面白い体験だった。 もう1つ意外だったのは,大夫,三味線,人形の三者は,決して合わせようとしてはいけないのだという点だ。三者がぴったりと寄り添うことこそがよいのかと思っていたが,それではその演技は死んでしまうのだという。それぞれが自身の精一杯の力を出し合って,その息が自然に合う,それが理想型であるようだ。実際に舞台を観ると三者のコラボレーションは,共演ではなく,競演というべきものと感じられた。 語り物として,物語の面白さは勿論,掛詞など言葉遊び的な要素もふんだんにあってこちらにも興味をそそられた。それにしても,昔の人たちは何と贅沢に時間を使ったことだろう。
2007年09月10日
-
ようやく夏休み
公私ともに余裕がない日が続き,自分の時間がほとんど持てない状況が続いている。とはいえ,8月は結局一度も日記を書かなかったことに今ごろ気づくのは,我ながら少々情けない。遅ればせながら3日から3日間の夏季休暇を取る。もっとも,例年のように旅行や山籠もりなどできない。今日は,父の往診が終わったあと,ちょっと書店へ出かけ,林望師匠の連載が載っている岩○書店の「○書」を入手し,カフェでカプチーノで一服して息抜きをする。明日は自分の部屋の片付けをしたいと思うのだが…。
2007年09月03日
-
7月16日
3連休最終日の朝,地震の揺れを感じた。揺れは小さかったが,ずいぶん長い時間続くように思われた。それでも,それほどの恐怖も危険も感じなかったので,ニュースを見るまでは,あのような大惨事になっているとは全く思わなかった。自分の感覚の身勝手さを情けなく思う。被災者の方々へ,お見舞いを申し上げたい。台風通過の後だったということも被害を拡大する原因になったのかもしれないが,土砂崩れや家屋の倒壊規模の大きさに,自然の力の強大さを見せつけられた。かつて「天災は忘れたころに…」と言ったものだが,前回の中越地震から3年,能登半島沖地震の記憶も生々しいうちに,このような災害が襲ってくるとは,誰が予想したであろう。そうして,また,自身の防災への備えを確認する日となった。
2007年07月17日
-
行方定めず
定時に職場を出たその日に限って,人身事故の影響で通勤電車の運行ダイヤは大きく乱れていた。 それでも,特に急ぐ必要もなかったのでのんびりと文庫本など開いていると,終点の一つ手前である駅を出た後,いつものように次の駅を知らせる車内放送が聞こえてきた。 お決まりの台詞でダイヤの乱れを詫び,次が終点であることを告げたところまではいつもと同じだったのだが,普段であれば続いて何番線に入線するのか,降車口が左右どちらになるかの案内があるところ,その日の放送では,ダイヤが乱れているため,まだ入線するホームがどちらかわからない,決まり次第案内する,と言ったので驚いた。 確かに,最後のポイントの切り替えで済むことであろうが,既に手前の駅を発車し,終点を目指してひたすら走っている車内である。行方を定めぬ危ういものに身を任せたまま暗闇の中へと無謀に飛び込んで行くようで,落ち着かない気分になった。
2007年06月24日
-
困った新人くん
この時期になると,4月入社の新人たちも,すっかり職場になじんだころだろうと思うのだが。月曜日の夜,家路を急ぐ人々で込み合う電車の中で聞こえてきたスーツ姿のビジネスマン2人の会話である。1人は入社して間もないという感じの若者,もう1人はその教育担当者と思しき30歳前後の男性である。若者 「やっぱ,月曜は辛いっスね。」先輩 「ああ,休みはすぐに終わっちゃうだろう?また仕事かと思うと嫌になることもあるよなあ。」若者 「ホント,日曜はあっという間に過ぎちゃいますよね。月曜は,全然やる気出ないっスよ。一日ぼうっとしてますモン。で,火曜には復活してくるんっスけど。」先輩 「火曜にはなあ,頑張ってもらわないと。」若者 「で,水曜は中だるみっていうのかな,疲れが出て,だる~くなってきません?モチベーション,ガーッと下がりますよね。」先輩 「ん?」若者 「それで,木曜は休みが近づいてくるから,よしもう一頑張りするか,と力入るんっスけど,金曜になると,もう仕事が手に付かないっていうか,遊ぶことばっか考えちゃうんっスよ」先輩 「…(絶句)。」先輩の困惑しきった表情には思わず吹き出しそうになった。身近にも困った新人くんがいるのだが,直接の指導者としてこういう若者を一人前の社会人に育てるのは,かなり大変そうだ。
2007年06月23日
-
手取額は減り続ける…
休日当番で終日勤務。だからぼやくというわけでもないが,口座に振り込まれた今月分の給料から,住民税が跳ね上がっていて,手取額が減っている。わかりきっていたこととは言え,現実の数字をみるとやはり少なからぬ衝撃を受ける。税源移譲のためだから,その分所得税が減っていて実害はないというが,実感と違うのはなぜだろう。今年はこれに定率減税の廃止が加わるので,手取額は確実に減っていく。一方で,物価の上昇等もあって負担はじわじわと増えてくる。景気回復が聞こえてくる中で,きちんと仕事をしていても,毎年手取額が減少していくことに,何とも納得ができないのは,私だけではないと思うのだが。
2007年06月17日
-
『すべてを否定しない生き方』
約1か月ぶりに夕学を受講する。 雅楽師,東儀秀樹の「すべてを否定しない生き方」である。同名の書籍が上梓されていることは知っているものの読んではいなかったのだが,自分と同い年である彼が語る「生き方」なるものに興味を持ったので,受講することにした。白いシャツにジーンズ姿で飄々と登場した雅楽師は,笙,篳篥,龍笛の音色なども交えながら,静かでありながらも些か早口で,思いつくままという感じで語った。宮内省を飛び出し,国境やジャンルを超えて共演する彼の演奏活動から,ボーダレスを目指す演奏家なのだろうという私の勝手な認識を彼は冒頭で強く否定した。「すべてを否定しない」とは「すべてを肯定する」こととは全く違い,個々の違いを認めながらそれに迎合するのではなく,自他の境界線を見極めた上で自分をしっかり持っていられることであるという。穏やかな印象の口調とは逆に,楽家の血筋と宮内庁楽府で鍛え上げた技術に裏打ちされた雅楽のスキルに対する絶対的な自信や,あらゆる面で揺るがない確固たる自分のスタンスを持つ強さが言葉の端々に現れる。目標を定め,それに向かって一直線に突っ走るのではなく,目標を持たずにキョロキョロしながら今を面白がってあちらこちらへ寄り道をすることが大切ではないかと語りかけ,思い立ったことはやってみる,壁にぶつかったときは先に進まない方が良いのかもしれないと考えてよじ登って無理に乗り越えようとするのではなく,後戻りすることを恥ずかしいと思わない,自分の好き嫌いをはっきりさせた上で集団の中にいられればよい等等の言葉は,私の心の中の,普段は黙殺し,押さえ込んできた部分を刺激した。今はいろいろな事に興味が広がっていて,趣味もどんどん増えているという点は,私の現状と似ていると感じた。詳しくは語られなかったが,政治や教育に対する意見もいろいろあるようであったし,余談として出た雅楽用語が一般の生活の中に溶け込んでいる例についての話も面白く, それらについて書かれているという著書を読んでみたくなったのは,見事に宣伝戦略に引っ掛けられたということらしい。
2007年06月06日
-
奏楽堂にて
師匠が特別出演するということもあって,上野公園内にある旧東京音楽学校奏楽堂で行われた「イタリアバロック声楽曲の夕べ3」を聴きにいく。前半はいろいろな歌い手が代わる代わる登場して,モンテヴェルディやカッチー二等のさまざまな曲を歌う。私などには必ずしもなじみのある曲とはいえないものも多かった。師匠もここではバリトン歌手として,チェンバロの伴奏のもとパスクィーニの「静かな憩いのうちに」を披露した。プロの中に入るとさすがに声量等に違いがあるのを感じるが,テクニックには着実な進歩が感じられ,努力を続けておられることが推察される。後半は,やはり私は寡聞にして知らなかったのだが,ヘンデルのオペラ「アルチーナ」という曲のハイライトで構成されていた。師匠は,あらすじを朗読して物語を進行させる役割を担う。物語自体は,魔女の呪縛を愛の力で解き放つ…といったファンタジーともいうべき作品だったが,その分わかりやすかった。もっとも,今回の一番の楽しみは,重要文化財である奏楽堂で演奏を聴けることであった。奏楽堂は,1890年に建てられた日本最古の様式音楽ホールで,移転の危機を乗り越えて,現在の場所で今でも定期演奏会等が行われいる。美しい木造の建物自体はこれまでにも見学したことがあったのだが,残念ながらそこで演奏を聴く機会がなかった。パンフレットによれば,その昔,滝廉太郎がピアノを弾き,山田耕筰が歌曲を歌い,三浦環が日本人による初のオペラ公演でデビューを飾ったというその舞台での演奏を一度生で聴いてみたいと思っていたものが,今回思わぬ形で実現したのだった。今回は声楽曲で,伴奏のリコーダーやチェンバロなどの音の響きは,評判通り柔らかで潤いがあり温かい。一方で,魔女が投げ捨てた杖が床に落ちたときなどは,強く反響した。今度は,舞台正面にあるパイプオルガンの音や,室内楽曲などを聴いてみたいと思った。
2007年06月01日
-
肉筆浮世絵のすべて
18日(金),アフター5にふと思い立って出光美術館に立ち寄り,「肉筆浮世絵のすべて」展を鑑賞する。 おおむね菱川師宣から葛飾北斎までという流れの中で,美人図を中心とした華やかな作品が多く,目を楽しませてくれる。 美人たちのポーズは,ある程度パターン化されていて,褄を取る手が異様に小さかったり,着物の裾からつま先がチラリと見えたりという状況は多くの作品に共通している。それでも線の強さや太さ,身体のバランスなどに,かなり絵師の個性が出ることを実感する。個人的には,女性のふくよかさを感じさせる宮川長春の作品などがよかった。 着物の柄の緻密さ繊細さは,会場でも指摘されていたが,現代から見ても大胆かつ斬新なデザインも多い。 胸元を緩めて涼を取る姿に限らず,美人たちはいずれも艶っぽく魅力的である。 以下は,少々ネタバレ的になる。 また,構図や表現が面白いものもかなりあった。巷で人気を博した「笠森おせん」の表情は何とも言えないお侠な感じに描かれているし,初公開という北斎の「樵夫図」は画面からはみ出すほどまっすぐに高くのびた樹木とそれをいわゆる股覗きスタイルで見ている樵夫という取り合わせに思わずニヤリとさせられるし,同じく初公開の「亀と蟹図」の構図と緻密な描写のテクニックには,さすが北斎と唸らされる。 現在の展示は27日(日)まで,大幅に展示替えが行われて後期が30日(水)から7月1日(日)まで開催される予定であるので,後期も是非観てみたいと思う。
2007年05月21日
-
熱気あふれるカラオケ
前の年度から続いていた大きな仕事が一つ,ようやく一段落したので,少人数ながら打ち上げが行われた。 軽い食事の後,2時間のカラオケ。 一仕事終えたという目出度さよりも,溜まりに溜まったストレスの発散…という雰囲気になったが,少人数に限ったことで,そういう羽目の外し方ができたのだろうと思う。 冷房が利かないカラオケルームの蒸し暑さと,翌日の仕事が歯止めとなって,予定の時間できっちり終了。自宅が近くなったこともあり,早めに帰宅することができた。週末までに読まなくてはならない論文が一本あるのだけれど…。
2007年05月15日
-
師匠の講演会
昨夜,久々に師匠林望の講演を聴きに出かけた。丸ビルホールで行われた夕学五十講中のひとつで,「言葉をみがく、心をみがく~日本人としてのアイデンティティを見直そう~」というテーマだった。 その内容を一言でいうならば,「もっと日本の古典文学を読もう」ということになろうか。 自分が遣う言葉を美しくするためには,言葉に対するセンスをみがくことが重要であり,センスをみがくためには,世界的にも類を見ない,千年の伝統を持ち「もののあはれ」に代表される情緒纏綿たる日本古典文学の素養を身につけることが役立つ,といった論旨で,『枕草子』を例にとり,古典文学は実は面白いものなので,もっと沢山読もうという提案であった。 昨秋ころから自分も個人的に『枕草子』に興味を持っているので,ラジオ講座に続いて今回の講演でも師匠が『枕草子』を例にとったことに,手前勝手に師弟のつながりを感じて密かに喜んだ。 90分の講演に続く30分の質疑応答では,古典文学を読み解くためのこつや,日本語の乱れが指摘されている現状についての質問等もあって時間が不足するくらいで,週末エッセイストとしては,かなり触発されるものを感じたのだが,自宅に戻ると,如何ともし難い現実が待っていた…。
2007年05月10日
-
新居で悪戦苦闘
大型連休の前に引っ越しを強行した。広くはないが,住環境は改善したものの,らくらくパックを使ったにもかかわらず,思わぬ事態がいろいろと出来していて,荷物の整理もまだまだやらなくてはならないことばかりである。両親との完全同居となって,家事も介護も,負担は予想以上に増えた。仕事も連休中に当番に当たっていたりして,やらなくてはならないことばかりである。ネット環境は整ったものの,ゆっくり日記を書く時間は,当分取れそうもない。
2007年05月05日
-
今週末に
急を要する仕事が立て続けに入ってバタバタしているが,この週末を利用して住まいを移すことにした。さまざまな作業が必要だし,ネットの接続環境も変わるので,落ち着くまで,当分の間,書き込みを休むことにする。大型連休の後半ころから再開できればと思う。
2007年04月19日
-
桜の京都
本来は,リンボウ師匠のコンサートを聴きに行く目的で新幹線や宿の手配をしていたのだが,諸般の事情で間に合わなくなり,それでも,この際気分転換に友人とのんびり花見をしようと京都まで出かける。予報と異なり,良く晴れて初夏を思わせる陽射しに恵まれ,時間がない土曜日は,寺町通り辺りにあるなじみの古書肆や菓子舗巡りをする。街中のソメイヨシノも予想以上に楽しめる様子で翌日への期待が高まる。 夕食後に入った南座近くにある老舗の喫茶店では,途中で女優の中野良子の一行がふらりと現れ,背中合わせの席に彼女が座った。思ったよりも少し荒れた声で気ままなおしゃべりをする彼女も,途中で街中のサクラを愉しんできた様子であった。 日曜日,前日からの,タクシー運転手の話を総合して,まず鴨川辺りの散策の予定を植物園まで範囲を広げる。これが大正解で,鴨川の川縁も植物園も,ソメイヨシノもかなり残っている上に,八重桜も含めてさまざまな種類のサクラが盛りを迎えていた。川辺には水鳥や亀等もたくさん遊んでいてこれも楽しい。 その後は予定どおりに平安神宮に戻り,何やら神事が行われているらしくゆかしい装束の人びとが居並んでいる中で参拝後,神苑を巡る。こちらはさらに見頃という感じのさまざまなサクラがあふれている。人出も多いものの押し合うほどの混雑ではなく,お抹茶や桜(はな)みくじを愉しむくらいの余裕もあり,神苑を出るときには,ちょうど,先ほどの装束の人々が退出してくるのにも出合う。 お昼過ぎの地震には驚かされたが混乱もなく予定の行動をして,夕日が残るうちに新幹線で京都を後にした。
2007年04月15日
-
完全にダウン
咳などでほとんど眠れなかったこともあり,朝からグッタリ。熱も出て,頭がガンガンと痛い。明日は休めないので,大事を取って今日は一日休む。医者に行って薬をもらうが,午後には38度8分にまで熱が上がり,ぼうっとしてしまう。ひたすら眠ったのと薬が効いたのか,この時間には熱は37度5分に下がってきた。明日に備えて今夜は早めに眠ろうと思う。
2007年04月03日
-
ゴホ,ゴホ…
朝起きたら,やたらに喉が痛い。鏡で覗くと赤く腫れている。熱はないので,ただの風邪だろうと思うが,しつこい咳に一日悩まされる。東京では昨日に続いて黄砂が観測されたという。まさかその影響ではないと思うのだが,完璧に体力を奪われたので,今日はこれで休むことにする。
2007年04月02日
-
片付けの一日
4月下旬に引っ越しをする予定となった。古いために何かと不便なので,父の介護に苦労をしている母の負担を軽減しようと考えたからである。ついては荷物の整理が必要である。ついつい荷物を増やしてしまったし,和室の生活から洋間の生活へと変更するので,大胆に整理しないといけないのだが,これがなかなか大変である。とにかく不要品だけでも処分しようと,まずは本の整理を始めたのだが,ミカン箱1箱分の書籍を古書店に売ることにし,その3倍くらいの本を処分することにしたが,家の中はそれほど片付いた印象がない。これではどういうことになるのだか…。
2007年04月01日
-
桜は満開
普段と同じ土曜日,外回りの用事を済ます。あちらこちらで満開の桜を見かけるが,ゆっくりと眺める状況ではなかった。夜になって風が強くなり,花散らしの風かと少々気を揉む。
2007年03月31日
-
年度末
実質的な年度末。定年で退職する人は今日でお別れである。しかし,仕事もたっぷりあって,終日バタバタとしていた。アフター6,職場で簡単に送別の宴。別れを惜しみ,遅くまで続いた。
2007年03月30日
-
ソメイヨシノ満開
予想外の仕事が入って,今日も余裕がなくなってしまい,普段以上に忙しい。日中は汗ばむほどの暖かさとなってきて,桜が大分咲いているようだと思ったら,東京では満開宣言が出たらしい。満開宣言は八分咲きで出されると聞いたが,やはり,満開というには今一歩という印象である。国会通りなどはまだまだという感じだ。それでも,週末は人出も多いだろうし,天候もいささか心配なので,思い切って帰りに北の丸公園辺りを少し散策する。ソメイヨシノはやはり八分咲きというところだろうと思うがなかなか美しく,一方,遅い時間にもかかわらず人出もかなり多い。写真はそのときの1枚。真ん中あたりに写っている小さなオレンジ色の塔は東京タワーである。三脚もないし,すっかり暗くなってしまったので,なかなか綺麗に撮れない。
2007年03月29日
-
ちょっと一息…
いわゆる年度末の忙しさが続く。予想外に雑用も多く,どうもバタバタと駆け回っている感じで落ち着かない。4月,5月の休日勤務の割り当てがようやく決まる。それにしても今年は発表が遅すぎて,予定が決まらず気を揉んだ。明後日,もう一山越えなくてはいけないけれど,今日仕事はひとつ峠を越えた感じで,6時過ぎには打ち切って,久しぶりに念願のマッサージを受けにいく。揉んでもらうと,予想以上に全身が凝り固まっているのを感じる。マッサージで少し楽になったので,あと2日,頑張ろう。
2007年03月28日
-
送別会
今週は仕事もギッシリつまっているのだが,昼休みも付随的な仕事の会議があった。新たな仕事が生まれそうだ…。なかなかみんなの日程が合わず,年度末が迫った今日になってようやく職場の送別会が行われた。毎年のことながら,異動する人と残る人と,どっちが多いのか…というほどの状況になる。宴会に先だってのミーティングも含めて,この一年のあれこれを思い出したり,これからのあり方を思ったり,いろいろと考えさせられることが多い話をたくさん聞けた。このメンバーでの仕事もあと3日。しっかりと締めくくりたい。帰りに見た状況ではソメイヨシノも大分咲いてきたようだ。自宅に到着する直前に雨がぱらつき始めた。
2007年03月27日
-
風向きが変わった?
朝は京浜東北線が止まっていたが,帰りは東海道線が止まっていた。月曜日の通勤から,このようなトラブルが続くといささか気分が滅入ってしまう。三月もいよいよ最終週に突入。やるべきことは多いので,気を引き締めて行こうと思う。いろいろと気になることが多かったのだが,思いの外,難問がいくつか解消に向かっていて救われそうだ。春一番の後の激しい南風を「花起こし」というと聞いた。昨日の午前中辺りまでの風がそうだったようだ。今日は,ソメイヨシノもどんどん開き始めたように見えた。この後の強い風は「花散らし」となる。「花起こし」,「花散らし」…,こういう言語感覚を大切にしたいと思う。
2007年03月26日
-
母校の桜
午前中は片付けものを少し。しかし,天気が悪いので捗らない。昼過ぎまで降っていた雨も上がったので,早すぎることはわかっていたけれど,母校の桜を見に行く。母校校庭の周辺はソメイヨシノがグルリと囲んでいるので,満開ともなれば,それは美しい。けれども,今日のところは,木によっては咲いているものもあるけれど,多くはまだまだほんの蕾で,見ごろにはほど遠い。それでも,同期の友人と母校を散策するのは楽しかった。
2007年03月25日
全1378件 (1378件中 1-50件目)