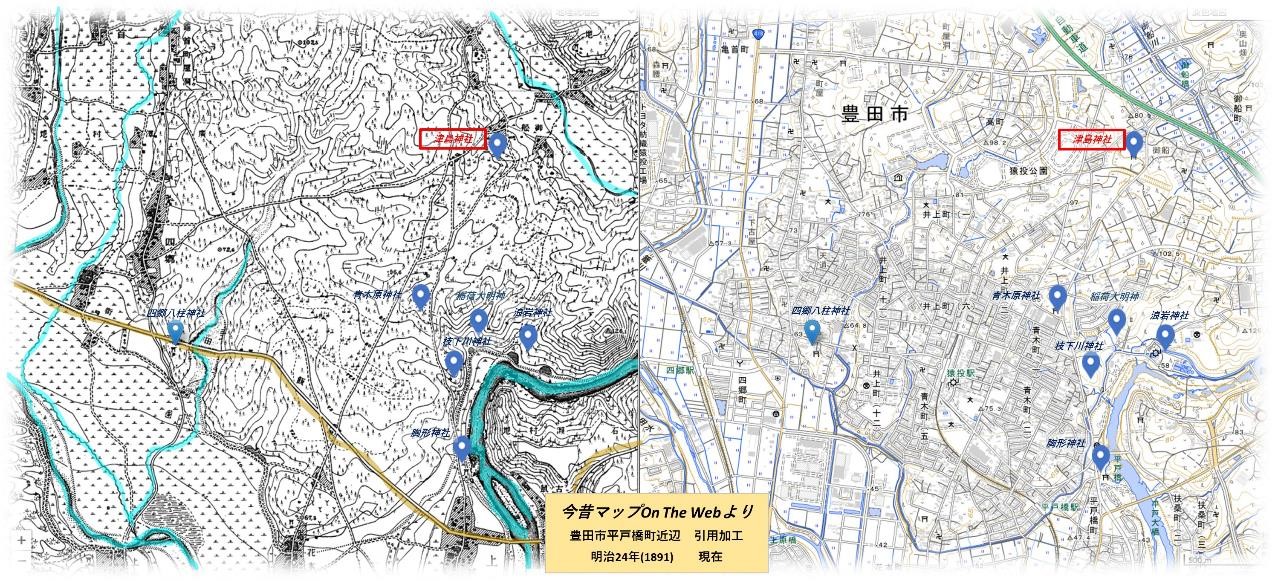あの女
総務のドアをあけようとすると、マグカップを片手に、ドアをあけようとした野辺山にぶつかりそうになった。
「あっ、すみません。」
「なにをそんなに慌ててるの?」
「いえ、そんな。」
野辺山は、意味深な含み笑いをうかべながら、愛用のキテイちゃんのマグカップを持って、給湯室に消えた。
総務経理でたちあがっているのは、野辺山のパソコンだけだ。それも、彼女自身、いま着いたばかりで、画面はパスワード入力画面のままだ。
では、だれがメッセンジャーでメッセージを送ったのか?
その日も、普通に一日がはじまった。しかし、メッセンジャーがどうして、たちあがったのか。あのメッセージは、だれが?それが、のどにささったトゲみたく、気になって仕方なかった。
ぼーっと仕事に手がつかないでいると、突然、メッセンジャーが開き、松林がでてきた。
「だいじょうぶ?」
「なにが?」
「だいじょうぶならいいんだけど。」
柴は意味不明なメッセンジャーに、たしかに松林の名前がでたので打ったが、会社から標準装備でインストールされているわけでないメッセンジャーをどうして、松林は使っているのか?
経理に、そのあたりに気をきかせる人間は、柴の知る限りいない。
「柴君、例の資料はできてるね。」
一瞬、柴の頭が白くなった。あの夢のおかげで、すっかり明日の会議用の資料づくりを忘れていた。
「今日中に用意します。」
部長の境は、親会社の山田物産からの出向であったが、常に、親会社しか見ていない。あすの会議も、山田物産財務部とのミーテイングの資料づくりを柴に頼んでいた。
楽勝で、資料は用意できるつもであったが、おとといは休み、きのうは、松林と早くに会社をあとにしたため、まったく手をつけていなかった。
かなりの量の資料を、エクセルですでに作成、保存してあるデータを、プレゼン用にパワーポイントに落として、なおかつ、会議資料を別紙で用意する。
「柴さん、こちらの資料、おもちしました。」
みると松林だ。すでにデータでもらっている書類をアウトプットしてもってきてくれたらしい。
「あっ、これはもう」
そういいかけたところで、メモのポストイットがついているのに気が付いた。
「おひる、いっしょにたべない?」
食べたいのは、やまやまだが、資料づくりが優先だ。それに、この時期は冬の賞与の査定に大きく影響する。
柴は内線をかけた。
「すみません。きょうはむつかしいですね」
「またで、お願いします。」
電子メールは、プライベートではいっさい、使わないようにしている。というのも、どこで、内容が読まれているかわからないからだ。
昼、みんな席をはずし、一人のこった席で、柴は作業をつづけた。そのとき、松林が、おにぎり2個と、ペットボトルのウーロン茶を買ってきてくれた。
おにぎりは、おかかとうめだった。うめは苦手な柴だったが、松林の心遣いに、胸が熱くなった。
夕方、定時になっても、できあがらなかった。うまく、パワーポイントのフォーマットにおさまりきらない。無理をすると、レイアウトがくずれ、やりなおしになる。
時間はいたずらに過ぎていき、できたのは終電のでた10分後であった。
資料一式を、部長の境の机の上に置いた。
ふーっ。
宝くじあたれば、こんなことしなくてもいいんだよなあ。でも、頑張っちまうんだよなあ。
部長席の隣のソファに座り、足を伸ばして背伸びをした。
天井の蛍光灯は柴の机の上以外はすべて、消されている。
いつも、70人くらいいる事務所であるが、こうしてみると、広いと思った。
ふと松林のことを思い出す。なんだか、不思議な女にであってしまったもんだ。柴は時間をみて、電車にはもう間に合わないとわかると、いったん事務所をでて、給湯室脇にある自動販売機で缶コーヒーを一缶100円硬貨をいれる。ガタンッという音が誰もいない、暗い廊下に響き渡る。
その缶コーヒーを手に、また、ソファーにもどった。時間は1時。15分くらい、休んでかえるか。柴は思った。
自分の引き出しから、お裾分けでまわってきた、ヨックモックと坂角ゆかりをだし、ほあばった。
お腹がすいたのも、ここまでくると、睡魔のほうが勝ってくる。
もうちょっとひと休みするか。そう思うと、まぶたが急激に降下をはじめた。15分くらいはいいか。そう思ううちに意識は朦朧となっていった。
ふと気が付くと、あの酒場だ。そして、また、あの女がいる。
よく見ると、松林とは全然かんじが違う。
「いらっしゃい」
「なんですか?いらっしゃいって?」
「まあ、気にしないで。残業大変だわね。」
「なんで、あなた?そのことを?」
聞くだけ無駄なことはよくわかっていた。
「もう、わたしがあなたに言うことはないわ。あとはうまく」
ちょっと、あなた、まってくれ。
声にだして言おうとしても、声が出ない。その女は、そのバーから出ていった。
「ちょっと、おきて。」
気が付くと、松林の部屋だった。
© Rakuten Group, Inc.