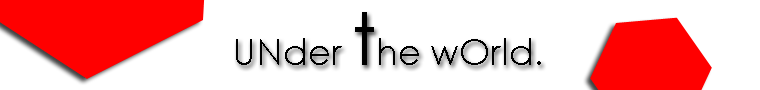PR
X
フリーページ
2025.11
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.06
2025.05
2025.04
2025.03
2025.02
2025.05
2025.04
2025.03
2025.02
テーマ: ニュース(95816)
カテゴリ: ありり
基本。
基本的な昔からの教えである。
そうみてほしい。
ちなみによく知られている聖徳太子も。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90
あたりまえのようにあった教え。これにより日本はバランスに秀でていた。
十善。
仏教の「戒」とは「よい習慣を身につける」という意味。
十善戒
不偸盗(ふちゅうとう)・・・ものを盗まない
不邪婬(ふじゃいん)・・・・男女の道を乱さない
不妄語(ふもうご)・・・・・うそをつかない
不綺語(ふきご)・・・・・・無意味なおしゃべりをしない
不悪口(ふあっく)・・・・・乱暴なことばを使わない
不両舌(ふりょうぜつ)・・・筋の通らないことを言わない
不慳貪(ふけんどん)・・・・欲深いことをしない
不瞋恚(ふしんに)・・・・・耐え忍んで怒らない
不邪見(ふじゃけん)・・・・まちがった考え方をしない
たしかにこれは日常で美徳とされている行為、行動である。
日本では昔からこのようなことはおじいちゃん、おばあちゃんから教えらてきたこと。
あたりまえのこと。
基本を忘れている。
諸行無常
生滅の法は苦であるとされているが、生滅するから苦なのではない。生滅する存在であるにもかかわらず、それを常住なものであると観るから苦が生じるのである。この点を忘れてはならないとするのが仏教の基本的立場である。
諸法無我
一切のものには我としてとらえられるものはない。これを徹底して自己について深め、目に見えるもの見えないものを含めて一切の縁起によって生かされてある現実を生きることを教えている。
このような共々に生かされて生きているという自覚の中にこそ、他者に対する慈悲の働きがありうるのである。
仏典の中にも「神」が出てくる場面が多いが、絶対者としての神ではなく、縁起によって現れたものと見るべきであろう。その意味で、仏教は他の宗教と根本的な違いを持っている。
無常と無我の自覚。
↓
涅槃寂静10-24を示す単位。
諸行無常、諸法無我の事実を自覚することが、この涅槃寂静のすがたである。
無常と無我とを自覚して、それによる生活を行うことこそ、煩悩をまったく寂滅することのできた安住の境地である。
無常の真実に目覚めないもの、無我の事実をしらないで自己をつかまえているものの刹那を追い求めている生活も、無常や無我を身にしみて知りながら、それを知ることによってかえってよりどころを失って、よりどころとしての常住や自我を追い求めて苦悩している生活も、いずれも煩悩による苦の生活である。
それを克服して、いっさいの差別(しゃべつ)と対立の底に、いっさいが本来平等である事実を自覚することのできる境地、それこそ悟りであるというのが、涅槃寂静印の示すものである。
涅槃とはいっさいのとらわれ、しかも、いわれなきとらわれ(辺見)から解放された絶待自由の境地である。
これは、縁起の法に生かされて生きている私たちが、互いに相依相関の関係にあることの自覚であり、積極的な利他活動として転回されなくてはならない。
この意味で、この涅槃寂静は仏教が他の教えと異なるものとして法印といわれるのである。
ウィキより。
1024
国連デー(United Nations Day)
国際デーの一つ。1948(昭和23)年から実施。
1945(昭和20)年、ソ連の国際連合憲章への批准により、発効に必要な20か国の批准が得られたため、国連憲章が発効し、国際連合が発足した。
日本は1956(昭和31)年に加入が認められた。
1971(昭和46)年の国連総会で、国連加盟国はこの日を公的な休日として記念するよう勧告された。
改めて国際連合を正常化せねばならない。
やはり人々のチカラ。
単体で存在してるのではない、自然環境も含め。
真剣にいまこの世界を憂い考えている人達のなにかのヒントになれば幸いです。
改編:最終更新日時 2007.10.08 04:27:01
基本的な昔からの教えである。
そうみてほしい。
ちなみによく知られている聖徳太子も。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90
あたりまえのようにあった教え。これにより日本はバランスに秀でていた。
十善。
仏教の「戒」とは「よい習慣を身につける」という意味。
十善戒
不偸盗(ふちゅうとう)・・・ものを盗まない
不邪婬(ふじゃいん)・・・・男女の道を乱さない
不妄語(ふもうご)・・・・・うそをつかない
不綺語(ふきご)・・・・・・無意味なおしゃべりをしない
不悪口(ふあっく)・・・・・乱暴なことばを使わない
不両舌(ふりょうぜつ)・・・筋の通らないことを言わない
不慳貪(ふけんどん)・・・・欲深いことをしない
不瞋恚(ふしんに)・・・・・耐え忍んで怒らない
不邪見(ふじゃけん)・・・・まちがった考え方をしない
たしかにこれは日常で美徳とされている行為、行動である。
日本では昔からこのようなことはおじいちゃん、おばあちゃんから教えらてきたこと。
あたりまえのこと。
基本を忘れている。
諸行無常
生滅の法は苦であるとされているが、生滅するから苦なのではない。生滅する存在であるにもかかわらず、それを常住なものであると観るから苦が生じるのである。この点を忘れてはならないとするのが仏教の基本的立場である。
諸法無我
一切のものには我としてとらえられるものはない。これを徹底して自己について深め、目に見えるもの見えないものを含めて一切の縁起によって生かされてある現実を生きることを教えている。
このような共々に生かされて生きているという自覚の中にこそ、他者に対する慈悲の働きがありうるのである。
仏典の中にも「神」が出てくる場面が多いが、絶対者としての神ではなく、縁起によって現れたものと見るべきであろう。その意味で、仏教は他の宗教と根本的な違いを持っている。
無常と無我の自覚。
↓
涅槃寂静10-24を示す単位。
諸行無常、諸法無我の事実を自覚することが、この涅槃寂静のすがたである。
無常と無我とを自覚して、それによる生活を行うことこそ、煩悩をまったく寂滅することのできた安住の境地である。
無常の真実に目覚めないもの、無我の事実をしらないで自己をつかまえているものの刹那を追い求めている生活も、無常や無我を身にしみて知りながら、それを知ることによってかえってよりどころを失って、よりどころとしての常住や自我を追い求めて苦悩している生活も、いずれも煩悩による苦の生活である。
それを克服して、いっさいの差別(しゃべつ)と対立の底に、いっさいが本来平等である事実を自覚することのできる境地、それこそ悟りであるというのが、涅槃寂静印の示すものである。
涅槃とはいっさいのとらわれ、しかも、いわれなきとらわれ(辺見)から解放された絶待自由の境地である。
これは、縁起の法に生かされて生きている私たちが、互いに相依相関の関係にあることの自覚であり、積極的な利他活動として転回されなくてはならない。
この意味で、この涅槃寂静は仏教が他の教えと異なるものとして法印といわれるのである。
ウィキより。
1024
国連デー(United Nations Day)
国際デーの一つ。1948(昭和23)年から実施。
1945(昭和20)年、ソ連の国際連合憲章への批准により、発効に必要な20か国の批准が得られたため、国連憲章が発効し、国際連合が発足した。
日本は1956(昭和31)年に加入が認められた。
1971(昭和46)年の国連総会で、国連加盟国はこの日を公的な休日として記念するよう勧告された。
改めて国際連合を正常化せねばならない。
やはり人々のチカラ。
単体で存在してるのではない、自然環境も含め。
真剣にいまこの世界を憂い考えている人達のなにかのヒントになれば幸いです。
改編:最終更新日時 2007.10.08 04:27:01
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.10.08 05:01:07
[ありり] カテゴリの最新記事
-
これからの世界。 2007.12.31
-
この世界のこと。ヽ(´∀`)9 ビシ!! 2007.12.09
-
法輪がまわっていない。 2007.10.09
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.