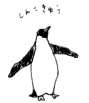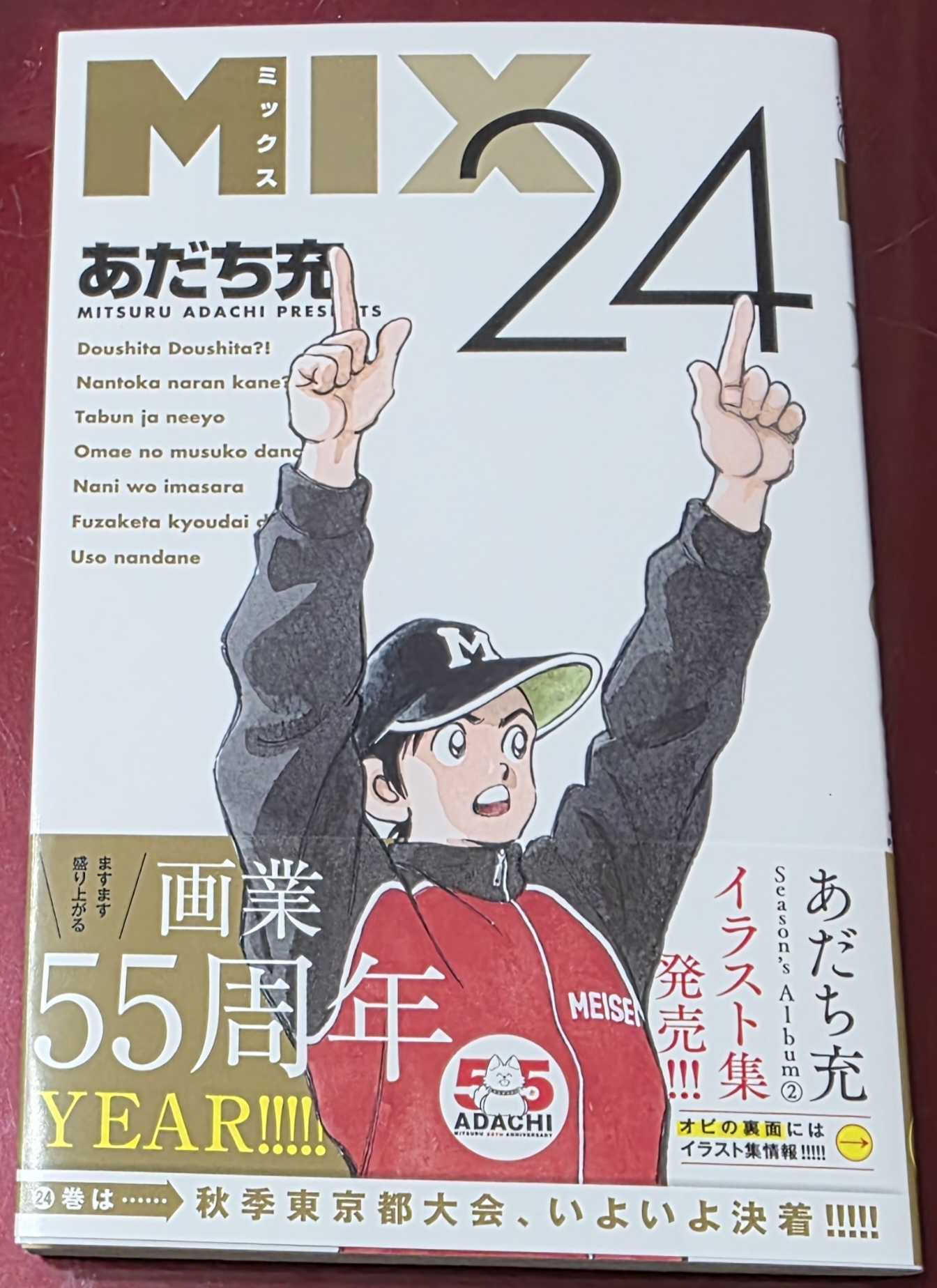2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年01月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-

「マイノリティ・リポート」録画して観ました。
劇場公開時、トム・クルーズ&スピルバーグ監督ということでかなり期待して観に行った覚えがあります。…そのわりに結末がうろ覚え…またまた新たな気持ちで観ることが出来ました。(あはは) design by sa-ku-ra*SF未来物って気持ちが設定に追いつくまで時間がかかるー。とはいえ、サスペンス調の物語なので展開はスリリング。物語全体を包む緊張感が心地良く、そのうえ先の展開が全然読めない…(笑)実は登場人物たちの名前を覚えるだけで(横文字だと覚えにくい)あっぷあっぷだったりして…?トム・クルーズの名前がどーんと前面に押し出されているけど、これ…コリン・ファレルも出てたんだね。コリン・ファレル…当時、映画を観て「なかなかいい役者では…」なんて思ったもののまだ役者名まで覚えていませんでした。今では主役も張れるようになったものね。とはいえ、その後今ひとつの役柄ばかりなのが残念無念ー。「フォーン・ブース」なんて最高にはまり役だ!!と思ったんだけどその後が続きませんね。が、頑張れっ!話が脱線してしまいました。犯罪予知なんてことが可能になったら…それは夢みたいなシステムです。本当に完成したならそれは犯罪抑制に繋がるでしょうか。それともそのシステムを掻い潜ろうとする「悪」が生まれるのでしょうか。どんなに世のなかが発展しようと、人の心が育たない限りいたちごっこに過ぎないのかも…なんてラストを観て感じました。明日から二月ですね。外ではまた雪が降り始めてます。まだまだ春は遠そうかな~・・・
2006.01.31
コメント(10)
-

「オリバー・ツイスト」観てきました。
*あらすじに触れているのでご注意を!*飢えと疲労で死に掛けていたオリバーを救ったのは盗みを生業としているフィネガンと彼に使われる少年たちでした。盗みは悪いこと。フィネガンだって、決して善意からオリバーを救ったわけではなく、むしろオリバーをスリとして育て上げ、利用しようとしていたのでしょう。でも…あんなに大勢の人が行き交う街で、オリバーの存在にやっと気づいてくれたのは、かつてオリバーと同じような境遇に立っていたと思われる“早業の”ドジャーだけでした。ドジャーがオリバーをフィネガンの元へ連れて行かなかったら…オリバーは路上で、飢え死にするのを待つしかなかったかもしれません。オリバーの持つ純粋さ。それは誰もが生まれたときには持っているものだと思います。けれどその日食べるパンを手にするために、それを切り売りしなければならないとしたら?生きる為と割り切りながら、自分の良心と向き合う日々が辛くないわけがない。オリバーはその純粋さを失う前に、心優しい紳士に助けられるけれど…。ドジャー達はその後どうしたんだろう。そのことばかり、気に掛かってしまう柊です。原作未読なんですが、読んだらそれがわかるでしょうか。「恩を忘れてはいけないよ」…というフィネガンの台詞。それはオリバーの口を封じる為の、あくまで利己的な心が告げる台詞ですがオリバーにはとても重たい言葉として、いつまでも忘れられない言葉になるのでしょう。*「オリバー・ツイスト」公式HPは→こちら design by sa-ku-ra*新聞連載小説としてずっと読んできた宮部みゆきさんの「名もなき毒」、柊が購読している新聞でも今日、最終回を迎えました。第一回からずーっと切り抜き続けた小説って初めてです。明日からはもう、この習慣もなくなるんですね。読む楽しみがなくなって、寂しいような、解放されるような…??(笑)
2006.01.30
コメント(8)
-

『予知夢』東野圭吾著 読みました。
前作『探偵ガリレオ』のトリックが物理、化学といった分野に限定されていたのに対し、こちらは大分オカルトめいた展開、あり。 design by sa-ku-ra*前作同様に、予知夢、幽霊、ポルターガイストといった怪現象を科学的に検証していく…って展開なんですが、事件によっては物理学者の肩書きを必要とせずとも解決できるものもあるようなー??(何故、そこで民間人(とはいえ物理学者)に解決を求めるのか? 警察、頼りなさ過ぎるぞ!…なんて感情は横に置いといて。)まあ、そのおかげといってはナンですが、前作に比べて大分親しみやすさを覚えるようになりました。ワトソン役の草薙刑事も登場時に比べると大分人柄が丸く…いやユニークになったような。うんうん、その調子。理系オンチという設定、万歳!なのに探偵ガリレオこと、物理学者湯川氏は相変わらず無愛想。うーん、彼に肩を並べるほどの天才肌の学生の出現とか、彼が最も苦手とする子供のお守りを長期間任される羽目に陥るとか、なーんとかして困らしてやりたい。ぎゃふん、と言わせてみたい!そのポーカーフェイスを崩してやりたい~!!と、どーも意地悪な感情を持ってしまうのは何故だろう。これはある意味、愛情の裏返しだったりするのでしょうか。むむ…そんなこんなで、これで心置きなく『容疑者Xの献身』を読む準備が整いました早く順番よ、回ってこーい!待っているぞ~。噂にきいたところによると、『探偵ガリレオ』、『予知夢』を読まずとも、全然大丈夫らしいです→『容疑者…』登場人物はシリーズから借りてきているけれども、お話の感じはまったく違うらしい…。なんだ、なんだ。そーだったのか期待してます、直木賞受賞作。
2006.01.29
コメント(10)
-

毛糸で編んだ巾着袋、完成!
双子の子供たちに頼まれて、毛糸で巾着袋を編みました design by sa-ku-ra*同じものを二つ作る、というのはなんだか疲れますー。完成するまで「まだかー、まだかー、本なんか読んでる場合じゃないでしょ!」…と、責め立てられ、落ち着かない日々を過ごしてきましたが、そんな催促から解放され、やっと落ち着いて本を読むことができまする~。万歳!努力の甲斐あって、子供たちはすごく喜んでくれました。喜びの余り、さっそくいろんなものを詰め込んでますが、「あ、あんまり物を入れすぎると毛糸が伸びちゃうよ」という注意事項は全然耳に入ってないみたいです。し、知らないぞ~。修理は受け付けませんからね~。
2006.01.29
コメント(8)
-

『探偵ガリレオ』東野圭吾著 読みました。
うーん、うーん、うーん・・・。すべては横溝正史に嵌った直後にこれを読んでしまった私が悪かった…としか言えない決して、面白くないわけじゃないんですが…のめり込むとこまでいけなかった。短編集だから、というわけじゃないんだろうけども「トリックがすべて」という感触になかなかついていけませんでした。 design by sa-ku-ra* 探偵役が物理学助教授の湯川氏。つまり犯行現場等の不可解な状況を理系の立場から解き明かしていってくれるわけですが、普段馴染みのない分野のお話だけに「はあ、そーだったんですか~」というテンポでしかついてけなかったこういう場合、ワトソン役(探偵その人でもいいけど)が積極的に読者との間を取り持ってくれたりして、その距離を縮めてくれたりするんですが湯川氏も、湯川氏に事件の相談を持ち込む草薙氏も、あまり愛想が良くないように感じられて…というかどちらもタイプがよく似ていて区別つかない…。柊の場合、理系の助教授で愛想がない…ときたら、森博嗣さんの小説に出てくる犀川助教授が真っ先に頭に浮かんじゃうんでその辺もマイナスイメージに繋がっちゃったのかも。す、すみませんっ。んー。調子の良いときだったら充分楽しみつつ読めたと思うんですが。タイミングが悪かったんだね~。ごめんなさい。m(__)m推理小説の醍醐味ってなんだろう、って考えてみました。もちろんトリック、最後の謎解き、オチは大事でしょう。でも、そのインパクトだけでは“繰り返し読みたくなる”本にはなりません。推理小説に描かれるのは<犯罪>ですが、「面白い!」と思わせる小説には<人物>と<背景>が丁寧に描かれていると柊は思うのです。どこにヒントが潜んでいるかわからないように、人物はもちろん、その人の生活空間、背景の描き方にも気を使う。癖や嗜好品、言葉遣い、その人が触れる道具類…読む側はそれを拾い集め、イメージすることを愉しむのです。決して事件が解決されればそれでいい、とは思ってない。犯人を追い詰めていくまでの過程、登場人物たちの心理描写こそ醍醐味。その部分に手を抜かれちゃうととても空虚な場面しか想像できないので、悲しい。そういった背景や人物の書き込みでいったら翻訳ミステリには敵わないって印象が柊にはあります。翻訳ミステリはその点とても緻密で、読み甲斐あるからです。(最近読んだ中ではセイヤーズ、サラ・ウォーターズ、ミネット・ウォルターズなんかそうでした。)先日来、横溝正史を読んで新鮮に思えたのは犯人に「動機」があることでした。一見不可解で、秩序も何もないように見える連続殺人事件も、犯人とその「動機」がわかった途端、とても理路整然とした世界が見えてくる。それがとても新鮮だったんですよね。コーンウェルの『検屍官』シリーズがベストセラーになって以降、推理小説は「動機」にあまり重点を置かれなくなったように感じてます。あえていうなら「殺すこと自体が目的」の快楽・猟奇的殺人事件物が一気に増えたような。科学捜査の緻密な描写、そして犯罪者にはまったく「心」が存在しなくなり。そして、「動機」が軽視されるに伴って「トリック」や「オチ」のみに重点が置かれる作品も増えてきたかなー。こうなると犯罪を追及していく側にも「心」を感じなくなってきたりして。…ああ、後は想像してみて下さいな。 追記:…とはいえ、柊は推理小説の本格物と呼ばれる分野、大好きなんです!! 自己矛盾、というより自己破綻を来している文章になっちゃってますが その辺はどうぞお目こぼしを~m(__)mどんな小説だって、まずは「人」から。“繰り返し読みたくなる”のは、やっぱりそこに描かれている「人」に会いたいから、だと思います。結末を知っていても繰り返し読みたくなる…そんな作品の代表格はやっぱり北村薫さんでしょうかなんだか無茶苦茶脱線してしまいました。そんなわけで、これから『探偵ガリレオ』に続く『予知夢』を読むところです。大丈夫かな。無事、直木賞を受賞した『容疑者Xの献身』まで辿り着けるかしら?後半、湯川氏の子供嫌いの描写(設定)がユニークだったのでその辺に期待をかけて、読み続けてみたいと思います。
2006.01.28
コメント(12)
-

「欲しい物バトン」に回答してみました♪
arshaさんから欲しい物バトンを受け取りました。うーん、物欲には限りがないので答えるのはとっても難しそう(笑)では、早速。Q1.今やりたい事お仕事探し。なかなかこちらの都合にあうお仕事って見つからない…あうう。Q2.今欲しい物 冷蔵庫。ん十年使ってきた冷蔵庫なのでそろそろ寿命では、と心配。冷凍庫も霜がはってるしなー(冷気が逃げてる証拠?)突然壊れられても困る電化製品ですな。Q3.現実的に考えて今買っても良い物 さ、先立つものが。…あ、宝くじ?(←でも、くじ運がない)Q4.現実的に考えて欲しいし買えるけど買ってない物 買えるなら買ってしまう、堪え性のない柊。わはは。Q5.今欲しい物で高くて買えそうにない物 うん…やっぱり冷蔵庫。それからパソコン。こちらも最近調子が悪いのです。Q6.タダで手に入れたい物 ただ!?…そんな都合の良いことがありうるでしょうかー。Q7.恋人から貰いたい物 夫から、ってことですかね。それなら図書カード。家計を気にせず、心置きなく本が買えたらそれって幸せ~(実は先日、1500円分の図書カードを貰ったのです。うしし)Q8.恋人にあげるとしたら うーんうーんうーん。困ったなあ。Q9.このバトンを5人に回す 答えてみたい方、どうぞバトンを受け取ってください本日のおやつに、チーズタルトを作りました味見してみたら(自分で言うのもなんですが)美味しかったです。思わず家族に内緒で、一人で食べてしまおうかと思いました…^^; design by sa-ku-ra*
2006.01.27
コメント(10)
-

「レジェンド・オブ・ゾロ」観てきました。
娯楽映画のいいところは、何も考えなくていいところエンドマークがついたところで「あ~、面白かったっ!!」って思えたらそれが一番♪ちゃんちゃんばらばらっ!!ってきっとあと ん十年経とうと廃れることはないだろうなーと冒頭シーンを観て思い、(だって、こんなにどきどき、わくわくする出だしってないと思う)乱闘シーンに至っては、ホントにぶん殴りあってるみたいに音が重くて、力が入っていて、観ている方も何故か息切れが~。あああ、私はちっとも動いてないのに、とっても運動してきた後みたいに感じられるのは何故?ご存知「マスク・オブ・ゾロ」の続編です。 design by sa-ku-ra* 前作が怪盗ゾロその人をテーマに描いていたのに対し、今回は「家族」がテーマになっていることもあって、柊は前作以上に楽しめた気がしてます。(けれども、一緒に観に行った夫は「前作の方が楽しかった」と言ってます。この辺は男女間の見方の違いが伺えるかも知れません。ふむ…興味深い)アントニオ・バンデラスとキャサリン・ゼタ・ジョーンズ、この二人のやり取りが可笑しくて、終始にまにま笑ってしまうんですよね。うーん、いいコンビだわ。二人の間には息子が一人生まれていて、この男の子がまた大活躍!しかも可愛い(笑)ゾロの愛馬トルネードも妙にひょうきんな馬でね~こういうキャラクター大好きです *「レジェンド・オブ・ゾロ」公式HPは→こちら制作総指揮はスティーブン・スピルバーグ。次に監督作として公開が控えている作品はミュンヘン柊は「ミュンヘン」も観に行く予定しています。史実に基づいているということ、そしてエリック・バナの演技に期待してます。
2006.01.26
コメント(6)
-

『悪魔が来りて笛を吹く』横溝正史著 読みました。
「金田一耕助はとつぜん、真っ赤に焼けた鉄串を、脳天から ぶちこまれたようなショックをかんじた。」(本文より抜粋)・・・ああ、同じく。ラスト数行を読み終えて…柊は今、腑抜け状態です。このため息は…相次ぐ事件の謎と伏線が見事に解決したことへの感嘆?それとも事件後のなんとも悲しい余韻がもたらすもの?犯人を知らずに読むのもまた、こーんなに苦しいなんて。読みながら、この謎がどう犯人に結びついていくのか、もう知りたくて知りたくて我慢ならず…そうこうしているうちにまた事件が起きて。ぐわー。最早、柊は横溝正史の“毒”から逃れられない予感がするー。面白い。面白すぎる (画像がないようです)この作品、五回は映像化されているようです。過去の配役表を見るとなんだか役者に共通したイメージがあって面白い。“悪魔が来りて笛を吹く”という曲の音色と共に、殺人が繰り返されるお話なので、はたしてそれはどんな曲なのか実際に聴いてみたくなります。映像化された作品の中ではおそらく劇中曲として流れたはず…。映像化されるたびに作曲されたんでしょうか。それとも同じ曲を使用?物語は、宝石商・天銀堂で起きた青酸カリ毒殺事件から始まり、これが旧華族を襲う連続殺人事件と不思議な繋がりを見せて展開していくのですがこの天銀堂事件は実際に昭和23年に起きた帝銀毒殺事件をモチーフにしているそうです。(読んでいてどっかで聞いたことのある事件だな~と思う訳です!)『八つ墓村』も実際に起きた事件に着想を得た、らしいので横溝さんの作品にはこういう例が多いのでしょうかー。横溝さん熱覚めやらず、読了と同時に古本屋へ直行!『本陣殺人事件』と『迷路荘の惨劇』があったので、買ってきちゃいました嵌るとなかなか抜けられないのよね…ううう図書館から東野圭吾さんの『探偵ガリレオ』『予知夢』が届きまして「早速読まねば~!」なんだけど、悪魔の音色が尾を引いてなかなか現代的な展開に入っていけない。ぎゃー、どうしましょ。
2006.01.25
コメント(10)
-

「博士の愛した数式」観てきました。
哀しいというのとも違うのに、涙がじわじわと湧いてきてとまんない。映画館で泣き、今また原作を読み返しながら泣いているわたし。ああ、どうしたんでしょ…涙腺が壊れたのだとしか思えない。 *「博士の愛した数式」公式HPは→こちら宇宙の広さと自分のあまりの小ささに気づいたときの寂しさに似て或いは、言葉にすれば壊れてしまう、そんな美しい風景に出会ったときのように、ただただ、「美しいな」って感じられたことが嬉しくて、それでいて一人心細いようなそんな感情に支配されてます。今。博士が教えてくれること、その言葉、示してくれる愛情…その一つ一つを忘れたくない。聞き逃したくない。見逃したくない。映画を観ながら、私は観客ではなく、一人の生徒になっていました。教えを請いたいと願う相手に対し、謙虚な気持ちと尊敬を示す態度をもって。原作を読んで、心動かされた人に是非、観て欲しい…と思います。柊は原作を読んだとき、最初に「学生の頃に読んでいたら、きっともう少し数学が好きになれた」と思いました。それから、博士の口から語られる数字のお話はなんて素敵なんだろう、と思いもっともっと教えて欲しい…そう、願いました。そんな本の持つ印象がそのまま映画になっていて、とにかく嬉しかったです。数式の持つ美しさ、それを物語として語る小川さんの言葉の美しさ…ただただ感嘆としてしまうばかりです。そして映画を彩るのは春の景色。桜、桃、菜の花、蒲公英…土の匂い。観ていると春が待ち遠しくなってきます。配役は、柊が頭の中に思い描いていた印象とはちょっと違っていたのですがいざ映画を観てしまうと、もう、そのまんまのイメージに変わってる(笑)深津絵里さん、母親役ははじめて、だったそうですが、博士と、√(ルート)少年と、三人で醸しだす雰囲気は原作そのもの、でした。それと対比するように、記憶を積み重ねられるが故に哀しいこともあるのだ、といった雰囲気を全身に漂わせていた浅丘ルリ子さんの演技も数式に負けず劣らず美しかったです。・・・素敵な人です。ここから先は、原作&映画両方をご覧になった人だけに…(伏字にしときます)ルート少年と、博士のお祝いの日に贈られるプレゼントは原作通りに「江夏の野球カード」であって欲しかった…と思うのは原作ファンのこだわりでしょーか(笑)博士がルート少年に対して示す愛情は、柊自身一人の母親として見習わなくちゃ!と思うことばかりです。
2006.01.24
コメント(18)
-

『八つ墓村』横溝正史著 読みました。
映像化された作品を観たことにより、犯人を知りつつ読む…のはやっぱり無念でありまする。このお話の場合、犯人を知りながら読む、ということはつまり事件の根底に流れる迷信や言い伝えに惑わされずに読む…ということ。(つまりとても冷静な目で事件を追っていってしまうということ)「怖いのは嫌だ」と言いつつも、実際は迷信に惑わされたい、怖がりたい、「ぎゃー!」と叫びつつ読みたい、というのが柊の本心だったのだ~ということにやっと気づきました。有名な鍾乳洞のシーンに差し掛かったときはもう、わくわく、どきどきこのあと、どんな結末が待ち受けているのか知っているくせに、それでも辰弥と一緒になって冷や冷やしました~。小竹様、小梅様…一卵性双生児のお婆さん!このキャラクター!ついつい横目で我が家にいる双子の娘を眺め、揃っておばあさんになったところを想像してしまうのでした。ああ、真犯人を知らずに読めていたら!どんなにどんなにラストに興奮したことでしょう~!!何故、もっと早く読まなかったんだろう~。柊の馬鹿馬鹿馬鹿馬鹿っ!!…と後悔先に立たず。学生時代、怖ろしげな表紙絵などものともせずに、本をレジに持っていくべきでした。悔しーい(その一方で江戸川乱歩は結構読み漁っていたのに…矛盾している)それにしても、この事件においての金田一耕助は(本人も言っているように)いいとこなし、なのが残念でありました。「犯人がわかっていたのなら早く言ってくれい!!」というようなジレンマに襲われるのですが、こういうじれったさは探偵小説には付き物なのでしょうね~というより元祖?記憶に新しい稲垣くん金田一を主に頭に思い浮かべながら読みました。どもりながらの台詞、頭を掻き毟ってフケを飛ばすシーン、飄々とした雰囲気など、結構原作通りではまり役かもしれん、と再確認いたしました。渥美清さんが金田一を演じた「八つ墓村」もおぼろに記憶に残っているんですが映像化作品の比較、見比べるのも面白そうだな~と思いました。 それにしても冒頭の「ナショナル懐中電灯」という記述、妙にリアルさを感じて怖かった・・・おーし!今年は出来る限り横溝正史を読み耽るぞっ!! おどろおどろしい作品同様に、著者である横溝正史という人も「怖い人」だと、勝手にイメージを作り上げていたんですがあれは…柊が小学生くらいの頃だったでしょうか。新聞に毎週ミステリにまつわる小話が連載されてて、柊はそれを読むのをとても楽しみにしていたのですが、あるときそこに横溝さんのことが載ったんです。それは横溝さんが閉所恐怖症だった、というエピソード。それを読んだとき、変な話ですが初めて横溝正史という名前に人間くささを感じたのですよね(←えらく失礼な話ですが)…と、同時に閉鎖的な空間で、自身の作り出した恐怖、その想像に囚われて恐怖している作家の図、というのがリアルに頭に浮かんできて背筋がぞっとしたのを思い出します。これまたおぼろな記憶なんで、横溝さんが本当に閉所恐怖症でいらしたのか確かめてみたいのですが…なかなかそういった記述は検索できません。うーん、あの記事はいったい…。真偽の程、またはこのエピソードを詳細にご存知の方、おりませんか~?
2006.01.22
コメント(18)
-

『秘密の花園』三浦しをん著 読みました。
どんなに会話に熱中していようとも、その様子をまるで傍観者のように見つめる、もう一人の自分の存在を感じたりはしませんか。その感じを知っている人なら、この小説から伝わってくる冷たい質感や怖さを自分のことのように錯覚してしまうかもしれないです。子供と大人の中間点。ときに、こちらがぎょっとしてしまう程、大人びた考えを示す少女たち。自分と彼女たちの間にある距離、というより温度差を懐かしいと思うより、哀しいものの様に感じてしまうのはどうしてなのかな。那由多、淑子、翠…閉鎖的な女子高に通う三人の少女たち。柊はどの子に一番共感を覚えただろう…。柊の場合、淑子の気持ちはわかるような気がするけれど、同じような考え方や行動は出来ないないだろうな、と思います。柊には彼女のような、恋に(或いは恋したと思う相手に)自分の何もかもを与えるなんて感情は湧いてこないからむしろ翠が淑子に対して感じる軽蔑、畏怖、嫉妬感の方が共感できます。 幼い頃の記憶に苦しむ多感な那由多、明るい「お嬢様」の笑顔の裏で秘密の恋に悩む淑子、超然としているように見えて熱い思いを秘めた翠。カトリック系の女子校に通う17歳の3人が織りなす心理&青春小説。 (bk1の内容説明文より)しをんさんの『秘密の花園』を読んでいて思いだした小説があります。氷室冴子さんの、うんと初期に書かれた『白い少女たち』という本。ミッション系の閉鎖的な寄宿学校。そこで過ごす三人の少女たち…と、設定が似ているからかな。三人の少女たち一人一人に共感し、落ち込んだりしたときには繰り返し読んだ覚えがあります。しをんさんの『秘密の花園』は氷室さんの小説よりもずっと表現が生々しく、繰り返し読むには重たく感じられるかもしれないなあ、なんて思いました。氷室さんの『さようならアルルカン』も、好きだったなあ~でも、繰り返し繰り返し読んだのは、そういうお年頃だったからなのかな~??
2006.01.21
コメント(6)
-

「THE 有頂天ホテル」観てきました。
いやいやいや…ほんっとびっくり箱みたいな映画でした多彩な登場人物たちと次々に展開されていくエピソード。それが一つの物語として見事に構成されていく様は「さすが!」の一言に尽きます。可笑しいシーンでは劇場のあちこちから笑い声が響いてきて…。それが心地良く感じられるのは三谷さん映画ならではかもしれないです。 *「THE 有頂天ホテル」公式HPは→こちら一つ一つのシーンが長く撮られているためか、まるで舞台を観ているようにも感じられました。台詞の掛け合いから生み出される場の空気、そのテンションを保とうとする緊張感が観ている方にもしっかり伝わってきて気持ちいいです~こんなにたくさん登場人物たちがいるにもかかわらず一人欠けてもこの物語は成り立たない。いいなあ…こんな空気♪役者さん一人一人にも言及したいところだけどネタバレになりそうなのでこの辺で。機会がありましたら是非、劇場に足を運んでみてください≪本日のおやつ≫ 稲田さんのレシピを見ながら…「カラメルりんごのタルト」を作りました。 お菓子に使うりんごはやっぱり紅玉がいいのかな。ふじりんごで作ったらちょっとボケた感じに…??…でもタルト生地がさくさくだったので、満足満足です
2006.01.19
コメント(12)
-

とうとう…!
突然ですが。本日、フードプロセッサーを夫に買ってもらいました 稲田多佳子さんのお菓子レシピ本を眺めるたびに、「ああ、フードプロセッサーがあったならもっと手軽にお菓子作りが楽しめそう…。」とため息ついていた私。夫にお願いするたび「場所取るんじゃないの。何処に置くの?」(ぎく)「一回、二回使って仕舞い込んじゃうんじゃないの?」(ぎくぎく)と言われ、「そ、そうかもしれん…(何といっても飽きっぽい私のことだし)」とそのたび、諦めてきたんだけど。とうとう、粘り勝ち(+衝動買いの勢い)で説得し倒し、買ってもらうことが出来ましたー。わーいわーいお菓子作り目的で買い求めたんだけど、付属のレシピ集など見るとハンバーグの種とか、餃子の種とか、いろんな材料を切る、混ぜる料理に使えるんだね~。包丁の使い方が益々下手くそになりそうな予感もありますが、せっかく買って貰ったのでどんどん利用していこうと思います。う、嬉しい。思わず台所に立ちつつにやけてしまう私です。↓早速、タルト生地(二回分)を作って明日に備えましたわ。ふふふ なんて作業が楽なんでしょう~!!(感動…) 図書館にリクエストしていた本が一冊届きました三浦しをんさんの『秘密の花園』です。
2006.01.18
コメント(12)
-

『マルコの夢』栗田有起著 読みました。
姉の仕事を手伝うためにフランスへ渡った一馬は、 三ツ星レストラン「ル・コント・ブルー」で働くことに。 ある日オーナーからマルコの買いつけを頼まれ、 日本に戻り動きだすが…。(bk1紹介文より)一作読むごとに文章が読みやすくなってきたような…。そのリズムが心地良く感じられ、すいすい前半を読み終えました。なのにびっくり。後半何の予兆もなく?×××な展開に~。「マルコ」という名で呼ばれるきのこの正体は一体なんなのか…と期待を込めて読んでいたので、何故か都合よく事が運んでいく展開にアンフェアなものを感じてしまう柊なのでした。推理小説じゃないので“アンフェア”というのも変ですがうーん、うーん、うーん…前半のテンポがとっても好感触だっただけにこの読後感はちょっと残念です。決して悪いわけじゃないんですけど…気持ちは割り切れません。ただ、「こういう展開がどうこう」というのはあくまで柊の好みの問題なのであんまり参考にはならないと思います~
2006.01.17
コメント(6)
-

『砂漠』伊坂幸太郎著 読みました。
本日、二つ目の日記です。「大学生活は社会に出るまでの執行猶予期間である。」…とはよく聞くフレーズですが。その意味が本当に身に沁みてわかるのは、卒業してからかもしれません。この小説の中では社会が砂漠に例えられてます。砂漠を外から眺めていられる場所、まだ守られている場所(つまり大学)がこの物語の舞台です。 大学のモデルは恐らく東北大でしょう…(笑)そう想像しながら、仙台駅周辺や、欅並木、東北大周辺、国分町界隈を思い浮かべつつ読むのは非常に楽しかったですもう、その一語に尽きるかも☆物語で起きるような事件に巻き込まれることなど、もちろんなかったけれどそれでも大学生の頃ってこんなんだったなあ(?)、なんて懐かしく思い出しながら読みました。あ・・・柊は麻雀を全然やったことないので、ルールも知らなくてそれが唯一読んでて悔しかったです。(頭に思い浮かぶのは何故か『動物のお医者さん』(佐々木倫子著)の家族麻雀のシーンだけ…)自分の側に西嶋くんみたいな主張を持ち、行動する人間がいたらやっぱり感化されるだろうな。少なくとも「自分には関係ない」というような言葉は使わなくなるだろう、と思います。先のことばかり考え過ぎて、行動できない(しない)ところ、柊にもあります。考えることは悪いことではないと思うけれど、考え過ぎて視野が狭くなってる、とは言えそうです。成長していない…というかこれは見直さなくちゃいけないな。「前進前進また前進」…この精神っ!こればっかりは年齢関係なさそう。(以下はちょっと内容に触れます。)実は一番笑ってしまったシーンがあります。それはP285~286にかけての、東堂さんの台詞。 「その美術館。常設展が面白いんだって」これ、台詞のままの意味で受け取ることももちろん出来るけれど、県美術館の常設展に何度も足を運んだことのある人なら多分こう叫ぶと思う。 そんなことはありえないー…!って。いつ行っても変わりばえのしない展示内容のため、常設展会場はいつも無人状態の場所なのです。(少なくとも柊が美術館に足を運んでみると、そうです)柊はここを読んで「よくぞ言ってくれましたっ!」って気分だったけど。ここには著者の痛烈な批判が込められている…とは深読みのし過ぎかしらん。あ!でもカンデンスキーが好き、という人には興味深い展示だと思います。柊はカンデンスキーよりはパウル・クレーの方が好きなのです
2006.01.16
コメント(10)
-

「プライドと偏見」観てきました。
2006年、映画館で最初に観る映画は絶対これにしよう!と決めていました。子供たちの新学期が始まり、「映画館に行きたい行きたい行きたい」と心のうちで唱えながらも、「プライドと偏見」の公開が始まるまでは~と耐えてました。この映画の原作はジェーン・オースティンの『高慢と偏見』(自負と偏見)。これはサマセット・モームが自著『世界の十大小説』で挙げている十大小説の一つです。そう聞いたなら、やっぱり「観てみたい!」と心動かされてしまうではないですか。(あらすじ…紹介文より)18世紀もまもなく終わる頃。イギリスの田舎町に住むベネット家には5人の娘がいた。女には相続権がないため、もしこの家の父親(ドナルド・サザーランド)が死んだら、家も土地も遠縁の男子が継ぐことになり、娘たちは路頭に迷う。母親(ブレンダ・ブレッシン)は娘たちを資産家と結婚させようと躍起になっていた。 *「プライドと偏見」公式HPは→こちらこの辺の事情を飲み込んでおかないと、「何でベネット夫人はあんなに(財産目当ての)結婚にこだわるんだろう~?」と疑問に思っちゃうかもしれない(笑)夫人は財産が目当てというよりも娘の幸せを、彼女なりのやり方で一生懸命考えているんですよね…。この映画では“結婚”が一つ大きなテーマになっています。すでに結婚した身からすると「決して結婚はゴールじゃないんだよ…」なんて意地悪な観方をしちゃったりもするんですが、そうではなくて。多彩な登場人物たちのそれぞれの思惑、プライド、偏見がすれ違う様を(恋模様を)楽しめれば、それでいいのではないかな…と思います。この映画を観て、「結婚とは××では」とか「自分だったら○○」なんて感想を持つこと自体、自分の中にある“プライドと偏見”を見つめなおすことになるのではないでしょうか…?映画の背景を彩るイギリスの風景が美しくて、それをのほほーんと眺めていられたらこんなに幸せなことはない、と思うのにやっぱり人は霞を食べるのでは生きてはいけない生き物なんだな…と。それを思うとちょっと切なくもなります。次女エリザベスを演じるキーラ・ナイトレイが美しく、印象的でした。(彼女を美しく撮ることに賭けたのでは…!と思える程です)父親と言葉を交わすラストシーンはこの映画中一番好きなシーンになりました。この映画を現代版にすると『ブリジット・ジョーンズの日記』になるらしいです(笑)BBCドラマ『高慢と偏見』でダーシー役を演じたコリン・ファースが、『ブリジット・ジョーンズの日記』でもダーシーという役名で出ているのはそういうことだったのか~!と後から知った次第です。コリン・ファース、さぞかしはまり役だったのだろうなあ!と想像できます。BBCドラマの『高慢と偏見』も観てみたいなあNHKBSあたりで放送してくれないでしょうか(笑)この映画でダーシー役を演じたマシュー・マクファディンはコリン・ファースと比較されることになるのでとても演りにくかったのでは、なんて想像します。(柊的にはコリン・ファースが好きです…あはは☆)同じくオースティン原作の『いつか晴れた日に 分別と多感』を観たことあります。物語や設定など『プライドと偏見』にとても良く似ている印象を受けますがこちらの映画ではエマ・トンプソン、ケイト・ウィンスレット、ヒュー・グラント、アラン・リックマンらのやり取りが見応えあります。柊にはアラン・リックマン演じた役柄が、『プライドと偏見』のダーシーに重なって見えたりもしました。どうでしょう・・・?
2006.01.16
コメント(2)
-

チーズケーキに悪戦苦闘…
チーズケーキのレシピ本に触発されて、12cm(丸)のケーキ型を購入しました。 届いてみると…12cmの型ってほんとにちっちゃいんだね~!!びっくりしちゃいました。(「これだとあっという間にぺろりだわ」と思ってしまった)でも、日常使いには丁度いいサイズだと思います…で、昨日早速チーズケーキ作りに挑戦したらこれが大失敗!!泡立てた卵白の混ぜ方が良くなかったのか焼き方の温度調節を間違ったのか。失敗作は子供達がばくばく食べてくれましたが…あまりに悲惨な外見に、写真はもちろんありません(笑)このままでは私の気が(というより食欲が)おさまらない。今日こそは…リベンジ!!再挑戦です。で、さっき出来たのがこれです→見た目、失敗してない~。良かった~。ぶぁんざ~い!!早く食べてみたいけど、一晩寝かせた方が味が落ち着いて美味しいらしい…。待ち時間が辛い…。ぐるぐる…。 *柊の別宅案内 → 我が家に八匹目のあみねこが誕生しました。しばしあみかけ状態で放置されてましたが、子供たちに催促されてようやく完成しました~読書は今、伊坂幸太郎さんの『砂漠』を読んでます。ちょうど真ん中くらいまで読み進みました。伊坂さんは東北大学法学部卒、ということなのでこれはやっぱり東北大学が物語の舞台なのだろうなあ…と想像しながら読んでます
2006.01.15
コメント(8)
-

17歳バトン、回答してみたいと思います。
arshaさんから「17歳バトン」を受け取りましたでは、早速…。 17歳の時、何をしていた?高校生。勉学よりも放課後の生徒会&部活動に忙しい日々を送ってました。 17歳の時、何を考えてた?うーん。当時はいろいろ悩み深かったような気がするんですが大半は忘れてしまいました(笑)とにかく放課後の活動が忙しくって、その日をこなすのに精一杯という感じ。 17歳でやり残したことは?多分ない。あえていうなら勉強でしょうか 17歳に戻れたら何をする。戻りたくない…。戻るなら、米澤さんの小説に出てくる登場人物が望むような省エネ&小市民的高校生活を送ってみたい…。ただただ図書館で黙々と本を消化しているような。(←いいのかそれで) 17歳に戻っていただきたい5人17歳に戻りたい方、是非もらっていってください!それから日記のネタに困っている…という方もどうぞ
2006.01.14
コメント(12)
-

『愚者のエンドロール』米澤穂信著 読みました。
『氷菓』に続く、古典部シリーズ二作目です。 (画像は角川スニーカー文庫版。柊が持っているのは角川文庫版です。) 「廃屋の鍵の掛かった密室で少年が腕を切り落とされ死んでいた。」 …という内容の自主制作映画。 しかし映画はその謎が明かされぬまま未完に終わっている。 古典部の仲間たちはこの映画の結末探しに取り掛かる~というお話。『氷菓』に比べると更にミステリの要素が濃くなっているというかおかげで、ずーんと手応えを感じられて読後に満足感あります本作中に登場するシャーロック・ホームズのお話は全て読んだことがある筈なのに、その結末を忘れているお話があるのが悲しい。うーん…見抜けなかったわ。ラストの欠けているミステリ映画ほど居心地の悪いものはなく。だからその真相を求めて、考察・検討・否定を繰り返す過程は読んでいてホント、心地良いです。だんだんと「必ず真相が掴める筈」という確信を強めていけるからね。こういう論理の構築みたいなのは、柊には無理です。(読むだけで手一杯)やっぱり探偵というのは才能の問題なのかも。実は柊には結末よりも?気になる一文が…。(映画中で)事件の起きた建物の見取り図があるんですが、それを説明する次の文章。 「途中でかすれていて「中村青」までしか読めないが設計士の名前まで 載っている。」(角川文庫P116・四行目)これって綾辻行人さんの館シリーズに登場するあの建築家「中村青司」を意識して書かれたもの…かな~なんて☆以降の文章ではこれに言及するものは何もありません。設計士の名前は本文中とは深い関係がなかったようです。綾辻さんの「館シリーズ」といえばこれでもか、というくらい容赦なく登場人物が死んでしまう(?)…本格ミステリ。それと比較すると「日常の謎」というミステリの分野はそれまでのミステリ=殺人事件という先入観を覆す、新しい切り口を提示してくれたよなあ…なんて改めて感心しちゃうのでした。あ、柊は綾辻さんの「館」シリーズ大好きです♪誤解なきよう…(笑)古典部シリーズ三作目にあたる『クドリャフカの順番』は現在リクエスト中です。これでいつ「入った」と連絡が来ても、心置きなく取り組めます♪ 書店で次の二冊を買いました 『のだめカンタービレ』も14巻目。とうとう新刊で買い求めるようになってしまいました。(12巻目までは古本屋さんをめぐっていた)島本理生さんの『リトル・バイ・リトル』が文庫化したのが嬉しいです。『生まれる森』以降は文庫化を待てずに単行本で買ってしまってるのでもしかして島本さんの本は(アンソロジーは抜かして)全部うちにあったりする?
2006.01.13
コメント(10)
-

今年最初の図書館借り出し+古本屋さんにも足を運ぶ
2006年に入って初めて図書館に足を運びました。借りてきたのは次の本です伊坂幸太郎さんの『砂漠』 栗田有起さんの『マルコの夢』 中島京子さんの『イトウの恋』 わーい、わーい、『砂漠』がやっと巡ってきました 勢いづいて古本屋さんにも足を運んでしまいました。東野圭吾さんの『白夜行』とか、ないかなあ…と願ってましたがなかなかそう都合良くはいきませんねでも、次の二冊を買ってきました。横溝正史の『八つ墓村』と『悪魔が来たりて笛を吹く』 本棚に並んでる黒い背表紙眺めてるだけでも存在感ありますね。他に『犬神家の一族』『女王蜂』が見つかると良かったんだけど…次回の収穫に期待します
2006.01.12
コメント(14)
-

「理由」(日テレバージョン)・・・やっと観ました。
昨年録画したきり、観てなかったのをやっと観ました。観始めて一時間経過。それでも柊は「本編上映はまだか…?」と辛抱強く待ち続けていました。なのになのに…がーん。何だこれは。よくも映画をこんなに切り取ったり編集しなおしたりしてくれましたね。(…って映画本編を観たことないので実際はどうなのかわからないけど。 でも、そんな印象を強く受けました。)柊は宮部さんの原作をどう大林宣彦監督が撮ったのかが観たかったのに。これではただのワイドショーというか、あざといドキュメンタリー番組みたい。なんなの、あの字幕の多さ。ゆるせーん!!監督の撮られた「画」はすごく監督らしい雰囲気があっていいのに。宮部さんの原作の硬質で、しかも多彩な人物たちの視点が交錯する感じがとてもよくまとめられているような気がするのに。なんなんだー、あのぶちぶちと映像も話の流れもぶっちぎるような番組司会者たちの品のないコメントはっ!!映画を映画として流してくれないなら最初から放映なんかするんじゃなーい!とまで思ってしまいました。なんか、久々に怒りが爆発するテレビ観ちゃった。ううう、消化不良。 この気持ちの行き場をどうしてくれる…。…すいません、こんな愚痴日記を書いてしまいました。観るなら映画そのままがお薦めではないか…と↓ でも一番は原作を読むのがいいのではないか…と↓ 図書館から、「リクエスト本が入りました」という連絡が来ました。おおっ!それは伊坂幸太郎さんの『砂漠』だといいな~。そしたら気持ちも持ち直すなあ…
2006.01.11
コメント(10)
-

『こんな映画が、』吉野朔実著 読みました。
本の貸し借りをしている友人からダンボール一箱分の本が届きましたその中にこの本が入っていて、タイトルに惹かれて夢中で読みました。 まさに、「こんな映画が、」あるんだなあ~!!と。「いい映画、見逃してませんか?」…うんうん、見逃してる見逃してる。ああ、この本に紹介されてる映画、全部観たい。誰もがタイトルを知っている(と思われる)映画はリスト中何編か垣間見られる程度。そのうち柊が観たことのある映画はわずか10本に過ぎず。タイトルは知ってるけど未見、或いはタイトルも聞いたことのない映画がいーっぱい紹介されてます。(マイナーな…と思いましたが、柊が知らないだけかもしれないです)借りた本ですが、「この本、自分でも欲しい」と思いました。だってとてもメモしきれないですから…。「ああ、吉野さんだ」と思える映画の観方とか、その映画を紹介しているイラストとか、見ているだけでわくわくしてきます。ううう、こんなガイドブックがあったとは。観てみたいと思ったのは…たとえば…「卵の番人」。ノルウェーのとても不思議な映画らしいです。添えられてる吉野さんのイラスト(映画の一場面?)がそのシュールな雰囲気をとってもよく伝えていて「観てみたい!」一本です。しかし、近所のレンタル屋さんに在庫があるとはとても思えない…「HERAT」。イギリス映画。ホラー映画らしいので、柊は絶対観れない!と思うのですが吉野さんのお話を伺ってると物語が面白そうで惹かれます。「事故で死んだ息子の心臓を移植された相手に、母親がそれを取り戻しに行くお話」…だそう。その過程を想像するだけでぞくぞくしてくる☆「マルセリーノ・パーネ・ヴィーノ」。イタリア映画。こちらは「泣けて笑えて清清しい、心洗われる映画」だそう。紹介されている11人の修道士たちを柊も是非観たいっ!・・・とまあ、あげていったら多分きりがありません。吉野さん、「年間に新作を100本程度しか見ていない」とありましたが柊からすると充分羨ましい数です(笑)ああ~もう、映画が観たいっ!!
2006.01.10
コメント(10)
-

『暗黒童話』乙一著 読みました。
乙一さんの小説を読んでいると背中がざわざわしてきます。残酷な描写に「ううう…」っとよろめきそうになっても、「ヤメロヤメロ、でないと夢に出てくるぞ」と心の声が囁きかけてきても物語の先を知りたがる自分の好奇心を押さえることがどうしても出来ない…。むしろそんな心の中の葛藤を楽しんでいるような、第三者的な視点が自分の中に生じてきて、それが不思議でもあり、心地良くてしょうがないって感じなのです。(あ、危ないかもしれない…。) 突然の事故で記憶と左眼を失ってしまった女子高生の「私」。 臓器移植手術で死者の眼球の提供を受けたのだが、 やがてその左眼は様々な映像を脳裏に再生し始める。 それは、眼が見てきた風景の「記憶」だった…。 私は、その眼球の記憶に導かれて、提供者が生前に住んでいた 町をめざして旅に出る。(bk1内容説明より)これまでに読んだ乙一作品の中でも、もっとも長い小説です。それが嬉しくもあり、「早く読み終わらないことにはこの悪夢がついてまわるー!」といった恐怖もあり…でも読み終わってしまうと寂しい…。残酷な描写がホラーを思わせるのかもしれないけど、柊にとっては乙一さんはミステリーの人。途中途中の伏線の張り方、ハラハラするラストの引っ張り方、最後の最後、物語全体を俯瞰してみせる謎の明かし方…。うう、もう見事すぎて声も出ません。けれども乙一さんの凄いところは謎が明らかになったあとかな…。読者にすれば、「ああ、すっきりした」と解放感・安心感に浸っちゃえばいいとこですが、登場人物たちにはそれ以降も時間が流れているのです。後日談…と言ってしまえばそれまでだけど、そこは「せつなさの乙一」。ぎょっとさせられた描写をも払拭してしまう、主人公からの語りかけ…。そのラスト数ページの描写に、柊はうるうるしてしまいました。この余韻こそ、乙一さんだよなあ…と。…それなのに。そんな感傷もぶっとんでしまうこの文庫版あとがき!涙目になりつつ大爆笑してしまいました。乙一さんってよくわからない…でも、そういうところが好きですこのあとがきで「職業作家として生きるのなら」って書かれてますよね。いつかは、いつかは新作に出会えるって期待していてもいいですよね…?? 余談ながら…柊は作中作として登場する「暗黒童話」から、エドワード・ゴーリーの絵本を想像してしまいました。童話とはいえ、小さな子供が読んだらトラウマになっちゃいそうな内容?あの印象的な挿絵の世界。本屋さんで見かけると、つい手にとって眺めてしまうんだなあ…。 …などなどゴーリーの著作はいっぱいあります…。
2006.01.09
コメント(10)
-

「古畑任三郎ファイナル」+「女王蜂」観ました♪
お正月に観たテレビの感想録、後編です(笑)先ずは「古畑任三郎ファイナル」第一夜「今、甦る死」…見逃しました。再放送を期待してます。ちら、と設定(村の名前とか)や石坂浩二さんの配役を観ると横溝正史(…というより石坂さん演じる金田一)を意識した台本だったのかな~なんて想像を膨らましてしまいます。ああ、見逃したのが悔やまれる~。第二夜「フェアな殺人者」イチロー選手の演技にとにかくびっくりこういうテレビ出演には全然興味のない人だ、というイメージがあるので出演自体、ほんとにびっくりです。(しかも本人役だ)子供と一緒に観てたのですが「イチローって本当は悪い人だったの?」なんて真面目に言うので「これは演技なんだよ~!古畑さんも言ってるよ。同姓同名の別人です、って」なんてあわててフォローしておきました。うーむ、迫真の演技というのもイチロー選手の場合、大変だなあ。俳優さんだったら無条件に誉められるとこだけど、野球選手の場合イメージダウンに繋がっちゃうのでは?なんて余計な心配してしまいました。殺人犯役もなかなか大変。第三夜「ラスト・ダンス」松嶋菜々子さんが双子姉妹を二役で。推理物→双子→入れ替わり…が定石なので展開だけは読めます(笑)どちらかが被害者になるのだろうな…と。あううう、双子姉妹を持つ親としては観ていて心中複雑です。 「もう一人、自分と同じ顔をした人間がいることを想像してみて」 「永遠のライバル」 「小さい頃から、比べられて…」ひゃ~、なんだかわかんないけど「ごめんよごめんよ」と誤りたくなってしまう~。(何故か心の中で言い訳していたりする)小さい頃から、比較したりするまい、とにかく平等!を心がけてきたけれど同じ人間じゃないからこそ、相対し方も違ってくるのだよー。双子とはいえ、性格は全然違う!(親から見れば顔だって同じには見えない)ついつい泣き虫の方ばかり抱っこすることになったり…それは双子に限らず、年の違う兄弟間でもあることではないですか?それを「向こうの方ばかり可愛がって…」て責められたら…うーむ、それはやはりフォローが足りなかったのか~??でもでも「平等」って口で言う以上にずっとずっと難しいのよ。・・・なんて。ガラスの中にもう一人の自分が映し出されるシーンが秀逸、でした。 *「古畑任三郎ファイナル」番組HPは→こちら横溝正史原作の「女王蜂」横溝正史&栗山千明さん観たさに…横溝正史と金田一耕助のやりとりがとてもコミカルなので観ていてちっとも怖くない(笑)(…でもそうじゃないと怖がりな柊はとても観れない)「犬神家…」、「八つ墓村」に比べると原作自体おどろおどろしくないのかな?それは読み比べてみないことにはわからないか…。(読んでみなくちゃ!)栗山さんの容貌にはもうそれだけで存在感があるというか、妖しい魅力があるので、それが堪能出来ただけで柊は大満足です(笑)二役演じられてましたが、着物姿で月琴を弾いているシーンが様になってて美しかったです。謎解きの一番おいしいシーンにさしかかったところで邪魔が入ってしまい、ビデオ鑑賞は一時中断「んぎゃー。犯人は誰じゃ~!!このジレンマをどうしてくれるっ!!」暴れたいのを我慢して夕飯の支度。その後、続きを観たのですが一度切れた緊張の糸はもう元には戻らない…。「そうか、犯人は××だったのかー」と淡々と観てしまった。く、悔しい。稲垣さん演じる金田一シリーズはまだこれからも続くのかな…。次に製作されるとしたら何がいいかな?「悪魔の手毬歌」とか「病院坂の首縊りの家 」とか…み、観てみたいな。臆病な柊は稲垣さん版金田一を観てから、やっとその原作に取り掛かることが出来そうなので(笑)今年こそは『犬神家の一族』『八つ墓村』『女王蜂』、読みたいなああああ。
2006.01.08
コメント(10)
-

『暁の寺 (豊饒の海 三)』三島由紀夫著 読みました。
2005年のうちに読み終わりたいと思っていた「豊饒の海」ですが、とうとう年をまたいでしまいました… 「春の雪」「奔馬」の流れをいったん断ち切るかのように、物語がいきなり海外、タイの国から始まることや、語り手である本多が、物語の空白期間に没頭し、集めたという輪廻転生にまつわる資料とその思想の数々(唯識論や仏教論)に眩暈をおぼえ・・・(平たく言えば理解できず)いったん本を横に置いてしまったのでした。ジン・ジャン姫は本当に清顕、勲らの転生なのだろうか?まるで前世の記憶をそのまま伴って生まれ変わってきたような、謝罪の言葉を口にしたかと思うと、今度はその成長と共にそういった転生のきざしは全く見られなくなっていき…。(むしろ心を持たない人形のように感じるのは何故)なにより女性として転生することに、どんな意味を持たせようというのか。本多でなくても惑わされるでしょう…この状況は。本多自身、「春の雪」「奔馬」とはあきらかに人が違ってきているよう。転生の目撃者、そして傍観者であることに変わりはないのだけれどそのことによって彼は自分自身を生きられなくなっていっているように思えます。また、“老い”を迎えるにあたって彼の場合次第に醜さを帯びていくようです。三島由紀夫の文章が、とても華美であるが故にその対比には身震いを感じたりして。傍観することに疲れた、というのかな。恋をすることに適した人間と、そうでない人間がいるように、激しく生を生き抜ける人と、そうしたくともできない人がいる。それを嫌というほど知っているのは後者の人間で…本多はどうしたって後者。彼なりにそれを脱したいと思っても、運命がそれを許さないみたいです。主観と傍観。若と老。美と醜。恋と肉欲。そして過去と現在…。そんな対極にあるものを美しく、しかも容赦のない言葉で織り上げていく。「暁の寺」はそんな印象でした。(こうして読み進んでくると『春の雪』『奔馬』の方が作品として好きですね)あと、残すところは最終巻である『天人五衰』のみ。この巻で本多は七十六歳になって登場します。これを書き上げたあとに三島由紀夫は自決したのだ…と思うと最後の一文を読むのがとても怖い。
2006.01.07
コメント(6)
-

『明日の記憶』萩原浩著+今年最初に買った本のこと
記憶の死。自分の頭からぽろぽろと、記憶がこぼれ落ちていく様を想像する。そんなの、恐怖以外何物でもない。「助けて」という叫びすら、真っ黒な虚無の穴に吸い取られていくようなそんな気がして主人公と一緒に怯えてしまった。 あさがお、飛行機、いぬ…。それから、腕時計、ペン、ピンセット、名刺、ハンカチ…。主人公が医師から覚えるよう提示された言葉、品物を柊も必死に記憶しながら読みました。数ページ読み進んで、それでも忘れていないか自問するのを繰り返す。一つ、名前が思い出せないとぞっとしてくる。自分の中にどれほどの記憶がちゃんとしまわれているか、確認せずにはいられなくて落ち着かない。そんなはずはない、そんなはずはない。…ああ、焦る。でもちょっとまって。私、読んだ本の内容、片っ端から忘れていってない?それが怖くて、嫌で読書日記をつけ始めたんだっけ。げげげ、本当に大丈夫かしら、私。こういう小説や映画を観たら、やっぱり自分だったら?と置き換えてしまいます。自分だったら…自分がアルツハイマーにおかされていると告知されたら?柊だったら…真っ先に死ぬことを考えてしまうかもしれない。自殺はいけないことだとわかっている。だけど、家族の顔もわからなくなっている自分…それって…本当に私?全然、それが自分だなんて自信を持てっこない。そんな自分を知りたくない。家族に見せたくない。柊の祖母はアルツハイマーで亡くなっているのでいつか自分にもそんなときが来るかもしれないという恐怖は以来ずっとつきまとっています。遺伝かも…とはよく耳にするし。孫の顔もわからずに、何度も何度もトイレに行くのを繰り返し…食事を繰り返し。ここにいるのはおばあちゃん。でも、全然知らない人。どう接していいのかわからなくておろおろしていた小学生の自分を思い出して読んでいて辛くなりました。どんなふうに接すればいいのか本当にわからなかった。その日が来たときのために、自分の身辺を整理して準備するなんてはたして出来るんだろうか。そんな気持ちの強さが自分に、あるだろうか。今の柊に出来ることといえば…アルミの鍋は使わない、緑黄色野菜と魚をいっぱい採って、それから、それから…あと出来ることは?ラスト、どう纏めるつもりだろうと思いながら読みました。込みあげてきたのは涙。それから…不思議なほどの安堵でした。どうしてかなあ…読み終えたとき、柊は『アルジャーノンに花束を』を思い出しました。全然違う物語なのにね。今年、柊が最初に書店で購入した本はこれです。 恩田陸さんの『エンド・ゲーム』…常野物語。『光の帝国』に収録されている「オセロ」の続編です。恩田陸さん、第134回直木賞候補に『蒲公英草紙』が選ばれたそう。選考は1月17日で、候補に選ばれるのは『ユージニア』に続いて二度目。(今回は東野圭吾さんあたりが本命なのかな…?と思われますが まあ、結果が楽しみです。)今後の恩田さんの本の刊行予定は三月…『チョコレートコスモス』(毎日新聞社) 『黒と茶の幻想(文庫版)』(講談社)六月…『訪問者』(祥伝社)、『中庭の出来事』(新潮社) と続きます。『黒と茶の幻想』は去年からずーっと延期されてたのでこれ以上延びないといいなあ(笑)
2006.01.06
コメント(8)
-

やっぱりテレビ漬けのお正月!?
お正月はテレビ漬け…って当たっているかも(笑)ネタバレしているので、録画してまだ未見という方はご注意を。3日の夜はNHKの「土方歳三最期の一日」を観ました。大河ドラマ「新撰組!」の最終回(近藤勇の最期)を観た時は、「このあとも土方は敗走を続けるのだなあ…」なんてまだまだ続きを予感させてくれたけど、これで本当に本当に最後。土方歳三の最期といえば司馬遼太郎の「燃えよ剣」での壮絶な最期を思い出します…。(それとも「新撰組血風録」だったか)武士道、なんて言葉に代表されるような一つの時代の終わりを感じて悲しかったなあ。新政府側から見れば、時代の流れの読めない、頭が固くて野蛮な集団と評されてしまうのかもしれないけど…柊は明治政府の面々より「新撰組」の方に惹かれます。司馬遼太郎版に比べると、思わず「歳~っ!!」なんて叫びたくなるような盛り上がりに欠けてたかもしれないけど…やっぱり悲しかったなあ。近藤勇、沖田総司らに先立たれて、一体どんな気持ちで函館まで渡ってきたのだろう…と思うとね…ううう。 *「土方歳三最期の一日」番組HPは→こちら土方歳三を演じた山本耕史さん。紅白歌合戦での司会で「前川清」さんを「山川清」さんと紹介したりお茶目な一面を見せてくれて面白かったです~ 昨日は録画しておいた「里見八犬伝」を前後編一気に見ました。(録画だとCMをどんどん飛ばせるのがいいところ~)ちらほら聞こえてきた感想にはあまりいい評価を聞かなかったので(笑)あまり期待かけすぎずに娯楽として観たのが良かったのかも。子供と一緒に「(菅野美穂さん演じる)玉梓、怖いよ~っ!」とか叫びながら観てたら結構楽しめました。演じていて楽しいのは断然伏姫より玉梓だろう、と思います。出てくる人出てくる人欲が深かったり、怨霊に乗り移られたり。一方で八犬士たちがだんだんと揃っていく過程などやっぱり物語が面白い…!文章で、自分の好きなように想像を膨らませて読めたならすっごく楽しいだろうなあ~と思います。よ、読みたいっ!その昔、角川映画の八犬伝を観た記憶がうっすら残っています。そこでは夏木マリさん演じる怨霊が退治されるシーンが妙に印象強く。(以降夏木さんをみるとそのシーンばかりが浮かんでしまって…ははは)「八犬伝」をしっかり読んだことがないので、これは柊のイメージですが「八犬伝」といえば怪奇+勧善懲悪の世界。ドラマでは後半「何故、人は相争うのか」とお説教染みてしまってるのがツマラナイ(汗)年の初めに平和を願いたいというメッセージなのでしょうが柊的には未だ答えの出ない難問を投げかけるよりすっぱり「悪」を切り捨てて欲しかったなあ…なんて不遜なこと思ってます。 *「里見八犬伝」番組HPは→こちら あと楽しみにしているのは「古畑任三郎」と横溝正史の「女王蜂」です。「古畑任三郎」は第一夜目は見逃しました。(観たいのが重なってしまい…。いつか再放送されるだろうと期待)第二夜・第三夜を録画し、後日一気に観よう、と思ってます。(CMを飛ばして時間短縮!) *「古畑任三郎ファイナル」番組HPは→こちら横溝正史、放送されるたび原作本に挑戦しようと思うのに未だ願い叶わず「犬神家の一族」「八つ墓村」ときて「女王蜂」…よ、読まねば~!!
2006.01.05
コメント(10)
-

『氷菓』米澤穂信著 読みました。
青春物というと、どうも体育系に負けちゃうけど(?)文化部を舞台にした物語だってちゃんと頑張ってるんだぞ!!…な~んて思えてきて嬉しくなります柊はずっと文化部だったので、つい贔屓目に見てしまうのかも。柊の出身校は運動部の活動がさかんなところで、文化部は肩身が狭く、予算折衝会議のときなんて、微々たる予算を死守するのに必死だったっけ(笑)そんな懐かしい思い出に浸りつつ読みました。 何事にも積極的に関わらない奉太郎が、姉の命令で 入部させられた古典部で、部員の少女の叔父が関わった 三十三年前に起きた事件の真相に迫る。 省エネ少年と好奇心少女が繰り広げる青春ミステリー。 (bk1紹介文より)折木奉太郎くん、千反田えるさんのキャラクターが、『春期限定いちごタルト事件』の小鳩くん、小佐内さんを彷彿とさせますこの古典部シリーズが米澤さんのデビュー作とのことなので、こちらが米澤作品の原点かな?古典部の文集『氷菓』のタイトルに込められた意味とは…?謎があきらかになった後に込みあげてくるのはなかなかせつなく、ほろ苦い感傷でした。学校というとても限られた空間だからこそこんな出来事も起きてしまうのかな。学校という枠から離れることが出来て初めて気づいたことが柊にはたくさんありました。ああ、なんて視野が狭かったことか。自分が思いこんでいたよりも、もっとずっと世界は広かった…!なんて。学校に通っている間にそれに気がついていたらあんなに苦しい思いをせずに済んだかも…と。でも、そんなふうに紆余曲折を繰り返すことこそがあの頃の特権、“若さ”だったりするのかと思うと心中複雑です(笑) 「きっと十年後、この毎日のことを惜しまない。」そんなふうに思える学生時代を、柊は過ごしてきたかしら。そう確信できる「現在」を、今、ちゃんと過ごしているかしら…。初詣に出かけた際、おみくじで「××」を引いた柊は、戌年限定「勝ち犬お守り」というのを買って来ました。お守りにデザインされている「にくきゅう」が可愛くてつい…(そういう理由でお守りを買ってもいいのかどうか…うむむ) *柊の別宅案内 あみねこたちもご挨拶 →
2006.01.03
コメント(6)
-

ご挨拶+『鏡の中は日曜日』殊能将之著 読みました。
昨年中は大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いします 本年最初の読書感想は殊能さんのミステリ。なんといってもあの『ハサミ男』、物議を醸した?『黒い仏』の殊能さんミステリなので油断は禁物読んでいる間も著者が読者のミス・リードを誘おうとてぐすね引いているのをひしひしと感じるのです…ミステリを読むのにあるまじきのんびりスピードで、慎重~に一字一句読み進んでいきました。 ・・・が。やっぱりひっかかってしまった。「ふふふ、今回は引っ掛からなかったぞ」とにんまりした次の瞬間見事に足元すくわれてしまった。えええー!この真相に辿り着ける読者っているの??居られたら尊敬します。柊。読み終えて再び第一章を読み返さずにはいられない。そして気づく気づく。見落とした部分の数々に。確かに、「あれ?」って思ったのよ。その箇所!それなのにそれなのに、その違和感の正体に気づけなかった~!過去に起きた殺人事件と現在との対比、その符合の仕方に脱帽~。「あれ?」と思わせつつ、真相には気づかせないその匙加減が素晴らしいと思います。いつもいつも。きっとそのちょっとした違和感を見落とさず、関連付けられる人だけが「名探偵」と呼ばれるのでしょう…。「名探偵」というのは職業じゃなくて、生まれ持った才能なんだわ、きっと。昨今の“自称”名探偵&ワトソン役はあくの強い人が揃ってますね。京極さんの榎木津探偵(&下僕たち)、麻耶雄嵩さんの木更津探偵(&香川さん)そして殊能さんの石動戯作(&アントニオ)…現代のホームズ&ワトソンたちを読み比べてみるのも面白いのではないかと。参考・引用文献をみると綾辻行人さんの「館」シリーズがずらりと並んでいます。法月さんの解説を読むと、この作品が「館」シリーズへのオマージュ作品らしい…ということがわかります。確かに、この物語に登場する梵貝荘はとても変わった建築物。さて、この真相を見抜けた人はいるかしらん??
2006.01.01
コメント(24)
全29件 (29件中 1-29件目)
1