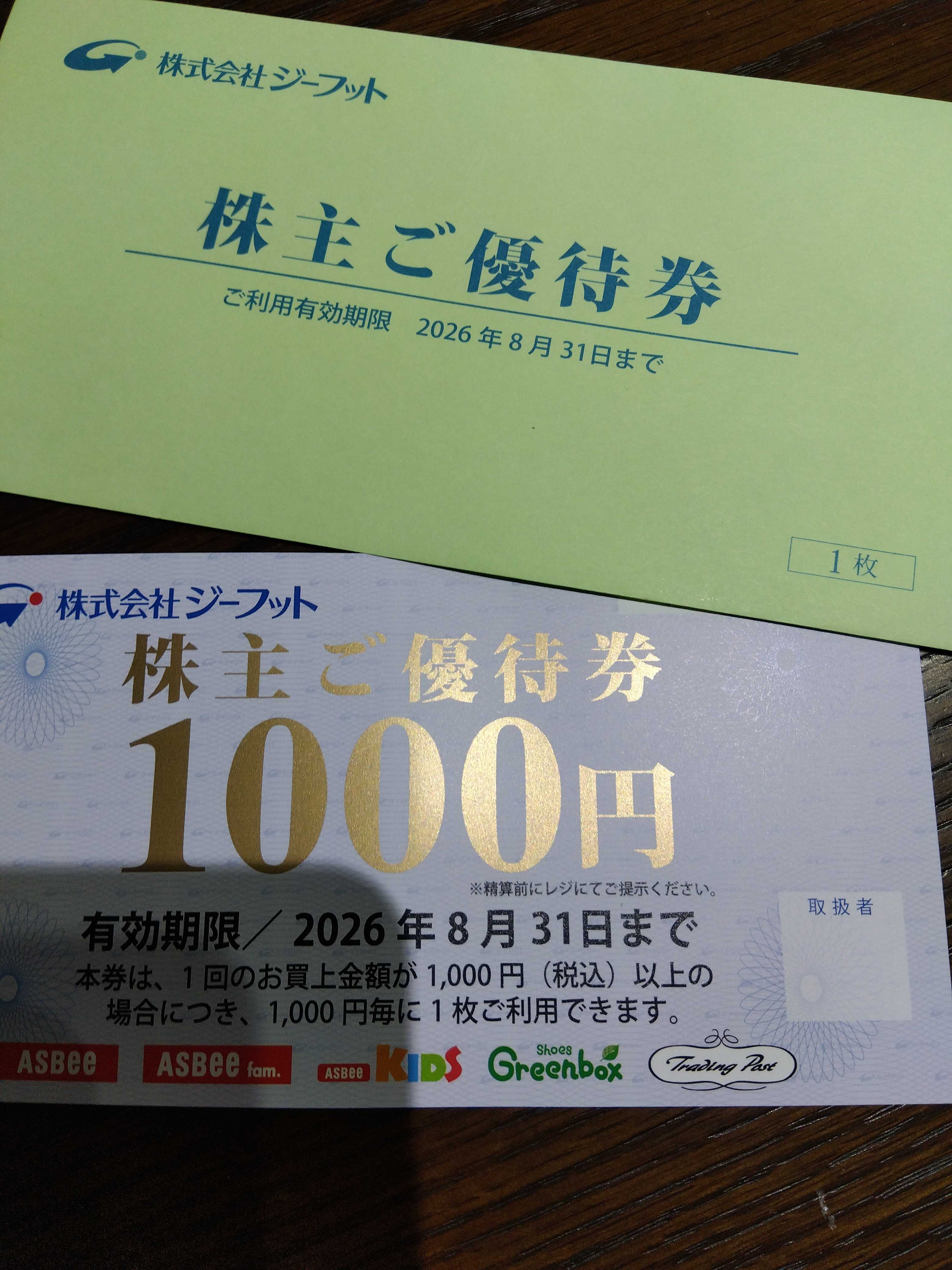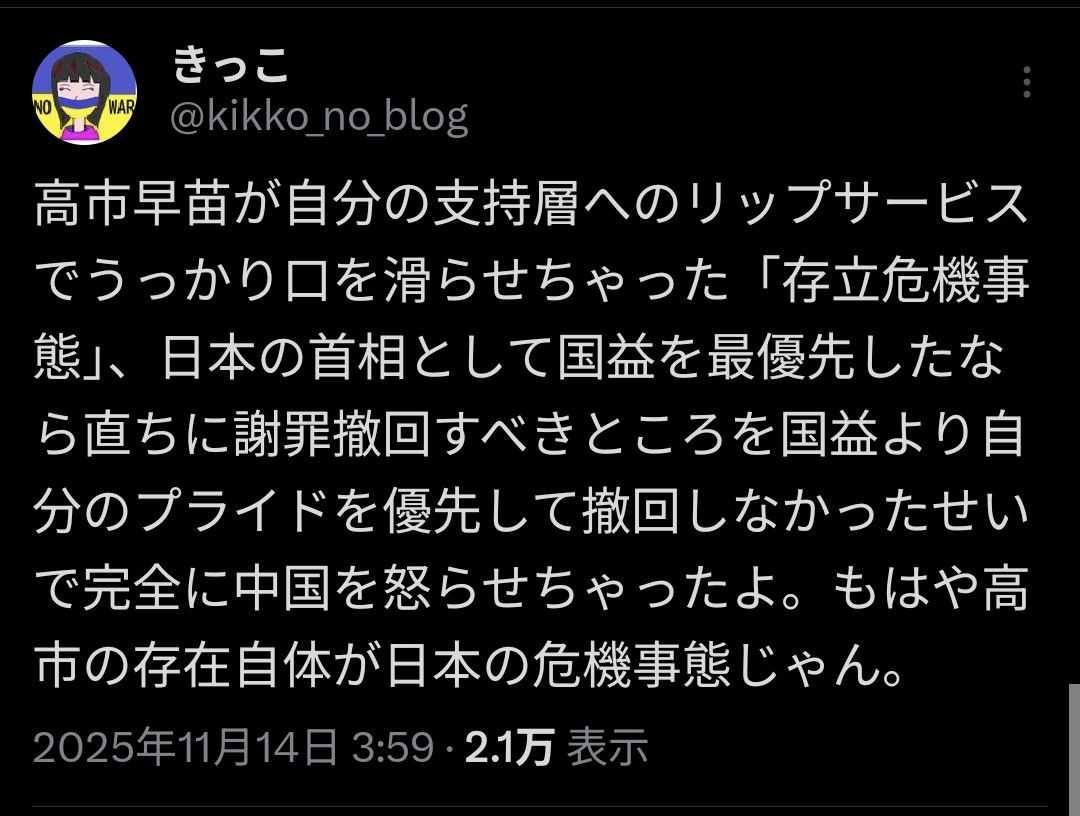2008年08月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
5次元で読む「花ざかりの森」
三島由紀夫の処女作「花ざかりの森」には、ちょっと油断ならないなという思いがある。三島の盛名がなって以後に、十代となって自分はかならず通過するべき文芸家としての三島由紀夫の存在感を認めつつも、この不思議な作家をどう考えれば良いのか持て余し続けてきたように思う。同年輩の小説家、浅田次郎などが手放し絶賛する「事情」もわかる。彼が、三島由紀夫を、さながら文芸世界のスーパースターとして心酔した十代をもっているのは、自分に近しいがゆえにタナゴコロで理解はできるのだ。しかし、三島由紀夫を読み進みその作品世界やさまざまな論評を読めばよむほどこの謎のような人物を3次元ではなく、5次元の軸で理解すべきだと思うようになってきた。戦時下の思春期1941年(昭和16年)、公威は『輔仁会雑誌』の編集長に選ばれる。小説『花ざかりの森』を手がけ、清水文雄に提出。感銘を受けた清水は、自らも同人の『文芸文化』に掲載を決定する。同人は蓮田善明、池田勉、栗山理一など、斉藤清衛門下生で構成されていた。この時、筆名・三島由紀夫を初めて用いる。清水に連れられて日本浪曼派の小説家・保田與重郎(やすだ よじゅうろう)に出会い、以降、日本浪曼派や蓮田善明のロマン主義的傾向の影響の下で詩や小説を発表する。この数行の理解だけでは、「花ざかりの森」が激賞されて1941年時点で処女作として出版刊行された理由を読み解けはしないと思う。この怪力ぶりを、どこか3次元ではなく、5次元で読み解きしてみたい。自分は、新素材のマーケティングではきわめて高いスキルを抱いていると外部から評価されて政府系認定事業者として複数の事業企画書を経済省庁や自治体窓口に提出し認められた過去がある。その理由は、第三次ベンチャーブーム以前に大手商社の物資部も呆れるほどさまざまな新素材や資材系で実働し、調達と新市場を開拓するという実務にかかわっていた。新素材というものは、かならず採用するというぐらい「傾向性」のある市場と当然親しく距離をつめることになる。そのような業界のひとつに、文具流通があった。さまざまなチャンネルの中でも、文具流通は特異な市場だった。わたしの場合、通常の営業行動とは次元が違い尋常な窓口ルート以外、商品開発ルート、事業企画ルート、経営企画ルート、財務ルート、経営上層ルートと、さまざまな交渉チャンネルを横断的に介入するという手法で、このような無茶な切り込みをやる事業者は、前にも後にも少なかったと思う。のちにパソコン通信時代に、営業部屋で、この話題を提供した際に若手営業諸氏から一定瞠目されたのは、営業手法としてもかなり先進的なものを多々含んでいたからだと思っている。つまり、流通についても3次元視線にとどまらず歴史背景や、人脈、コネ、意思決定のプロセスに至るまで緻密に脈をとりながら最後の決済へ寄せてゆくという総合的な営業行動を採用していた。これは新規性の高い開発素材では、不可避な挙動できわめて高いコストを強いられる。つまり大手商社では、販売管理費を忌避したき動機があるゆえに、けして採用しない挙動なのである。彼らは、仕組みで食える。ベンチャー事業者の挙動など、リスクでしかなくせいぜい市場形成期に介入して体力勝負をしかけて成果を海賊行為すればすむと考えるものなのだ。そこであえて自分の流儀を押し通したのであるから、相当幸運にも恵まれていたと思う。話を戻すが、文具流通は結論から言って世間で思われているよりも遥かに不思議な世界だった。表面からはうかがい知れない、戦前の統制経済下でできあがって極めて硬直的なシステムが大手を振ってまかり通っていた。それは今も大差ないかもしれないほどだ。どの業界にも大なり小なり存在するとは思うが、文具業界はその「極右ぶり」が著しい。そう思った。あるとき、文具メーカー中堅下位の経営者の若手と昵懇に話し込む機会があった。これは、わたしの中に相手をそのように誘導できるだけのカードがあったからだ。ノーペア、ブラフでポーカーがやれるような業界ではない。錯綜した工作の果てに、経営者が、じきじきに私とかかわりを抱きたいと思わせる知財上の優位性が相手側事業にうまくジョイントしそうだったのだ。当然、経営者側はわたしを同盟軍に編入しようと胸襟をひろげてきた。その比較的嘱望されて期待値をこめて歓迎をされていた蜜月時期には、経営トップらから文具業界についてさまざまな歴史背景を耳にすることができた。彼らは歴史のある文具事業者の経営トップの子弟であるから、まちがっても現場の営業窓口や資材購買レベルの話題では登場しない事業全史にかかわる話題が登場する。そのとき、三島由紀夫が1941年に処女作「花さかりの森」初版発行するという怪力ぶりについてようやく眼のうつばりが取れる思いが湧いたのである。普段、われわれが資材という意識も抱かずに消費している紙、インキ、ラバー、糊などの資材も戦時経済下では「統制物資」であった。これは歴史を学べば一定知識として理解できる。だが、頭で理解できることが体感レベルで身にしみるというまでに千里の隔たりがある。文具メーカーの経営者は、太平洋戦争開戦前当時の文具製造事業者の存在感はいまでは想像できないだろうと述べた。たとえば卑近なところで、鉛筆や消しゴムのたぐいだ。母親の世代では、運動会で上位入賞者に率先して分け与えられたという。つまり小口現金があれば、するすると就学児童には店頭で買えるという事態になく、鉛筆やノートの入手にも熾烈な競争が働いていたというわけだ。それは大げさにしても、文具資材は、とびきりの奢侈品だったのである。たとえば東京帝国大学工学部航空学科を首席で卒業、三菱内燃機製造株式会社(現在の三菱重工業)に入社した堀越二郎という設計主任が零戦を製作企画する際に、いくら「観念飛行」(いまならばパソコンで実行するシュミレーションを天才設計者の堀越は、頭脳労働で実行していたらしい)の天才的な力量があるとしても、それを設計図に落とし込む紙、鉛筆、消しゴムがなければ設計業務にはならなかっただろう。パソコンとプリンター、プロッターの時代ではない。文具の資材として占める存在感は、今日では考えられないほどにスティタスは高かった。当然、これを扱う文具製造業者は、戦略物資相当を扱う業界として手厚く庇護されていたという。優れて鉛筆の痕跡を消し去る性能の良い消しゴムは、戦時経済下では戦略物資扱いだったというわけである。事実、消しゴムの中に細工された微細な無機材料にいたるまで、文具業界は流通機構に超越して調達が可能だったらしい。これを必要需要規模を遥かに越えて入手し、在庫し、運用すれば、極めて高い高収益事業となりえたわけで、文具業界の寡占傾向は、この「統制経済」時期に形成され戦後を貫徹している。つまり文具製造を表で実行しながら、財務体質は極めて良好となりえる。その時期に、いわゆる事業資産のワクを越えて蓄財し、はては不動産やら各種事業に着手するほどの資産体力を築きあげていたのだという。このような業界の特異な成立背景は、流通や戦後の企業活動だけを眺めていても到底把握はできないのだ。文具製造者の後継者であった、取締役からじかに聞き及ぶながら秀才とはいえど、所詮は十代の学生に過ぎない三島由紀夫が、初版本「花ざかりの森」を刊行するに際して、紙やインキ、装丁資材を一体どのようなワザで調達できたのかを想像して絶句したものである。この稿もふくめて、以下の7月18日からの連続エッセーです。内容の理解のために以下の記事から読み返しくださることを強く推奨します。2008/07/18吉本隆明と「関係の絶対性」
2008年08月31日
コメント(0)
-
リベラルを撃て!
ベトナムに平和を!市民連合というグループが一斉風靡した時代。いわゆるべ平連の時代に、かれらの指導者らが北朝鮮と疎通していたことを何故隠蔽するのだろう。彼らが、「北」を地上の楽園のように謳いあげた流れを、いまだに恨みに思っている北朝鮮系の在日も少なくない。かつての社会党の流れをくむ連中の中にも、北朝鮮に深層でからんでいる連中は、まだまだ大勢いる。小田実が、それらを背景にして東京都知事選挙の候補者に祭りあげられそうになった時期もあった。かれら「市民主義者」のリベラルぶりほどきな臭く、いかがわしく、反進歩的な動きはつねに警戒してきた。左右の選別がやけにお好きな人士は、えてしてこの手の社会階層に多い。反戦、平和を声高にさけんでいる連中をあえて疑ってかかる必要が常にある。彼らが自然発生したグループなどと、ぜったいに思わなかった。彼らは、かならず「後ろの正面」を持ち合わせているあのおなじみの歴史的な動きと同じだった考えてよいだろう。「国家社会主義」という、不思議な国際性。これについて、よほど繊細に考え抜いておかねばならないと思っている。
2008年08月28日
コメント(0)
-

街頭に国家権力が存在するのか?
自分自身は、きわめて非政治的な人間だ。既成政党にも反権力的な党派とも一切縁なくこの年齢になった。その理由の中でも、大きいのは自分の十代に勃発した「反安保闘争」だろう。自分よりも上の年代が、夢中になって奔走したあの70年反安保闘争に、強い不快感があった。いまもあれを懐かしがっている向きが、見かけられることが失笑を禁じえないところである。路上に、何万人もの「にわか社会主義者」とその同伴者が溢れかえるという状況が噴飯ものだったのである。いまひとつの理由は、いまでは想像もできない規模で広まった「べ平連」という市民主義者による活動についての違和感である。「ベトナムに平和を!市民連合」という謀略的な新左翼セクトである。あれを額面どうりに市民の自主参加の開かれた反戦運動団体だなどと今なお信じている人がいたら、語る言葉を持ち合わせられない。当時、そのおめでたい活動ぶりにノンポリの青年たちが、喝采して集会に参加したりしたものだ。その影響力は、いまでは想像できないが、当時の世相を反映したきわめて斬新なモードだったのである。その指導者のひとりであった、小田実はすでに他界している。小田は、出身校の先輩だが、誇らしくもなんともない。自分は、このグループ(実態で新左翼に指揮指導された立派な左翼党派であったと思う)が、極めていかがわしい存在と思えた。以後、政治的な活動を行う組織、サークル、活動、集会には一切近寄らないことにした。彼らの機関紙や、街頭での演説ではしばしば「国家権力の本質」が街頭での暴力的な対決で露呈し、その帰趨が国家権力の無力に大きな影響を生じるというヨタなメッセージが述べられた。いうまでもなく扇情的なのは差し引いても、大ウソである。そんな子供だましのような大ウソを、連日声高に叫び一部は本気でそういうヨタをヨタとして、見分けられなくなって行ったように思う。何万人ものヨタ吹き男たちとその同伴者が、団塊の世代に極めて多かった。これを不名誉なことだったと誰一人として切り出さないのは、なぜだろう。この稿もふくめて、以下の7月18日からの連続エッセーです。内容の理解のために以下の記事から読み返しくださることを強く推奨します。2008/07/18吉本隆明と「関係の絶対性」
2008年08月27日
コメント(4)
-
国家権力素描
権力を語るについて 「国家主義」「国家社会主義」「社会主義」というような大分類だけで精緻に描写できるものだろうか?自分は、到底そんなことが可能だとは思えない。権力の「現在」は、遥かに複雑であろう。政治学で「国家主義」と呼ばれるものと、「社会主義」「国家社会主義」は一体どこが違うのだろうか。「国家社会主義」は「国家主義」と「社会主義」の影響を受けた相互受容的な政治形態だという説明を教室で受けた記憶がある。果たしてそうか。ここで「国家」と、呼称されているものの正体が問題になると思われる。われわれが国際オリンピックなどで国旗を眺めながら、鼓舞される国家シンボルというものは基礎に「国民国家」があるものと信じられている。しかし現実の国家像が古典的な「国民国家」のまま、「民族国家」ままであるなどと信じ込むことは馬鹿げている。そこで国家という語彙に両義的な用いかたを行うこと自体が根本的に間違っているのである。国際オリンピック参加の大国、超大国においてはすでに「国民国家」「民族国家」とまったく違った機制が存在する。いわゆる「超国家主義」と呼ばれる国家の「現在」が存在する。「超国家主義」とは、「民族国家」「国民国家」を超えたという意味ではかならずしもない。「超国家主義」と呼ばれるものは「民族国家」であり「国民国家」であったとしても、内部にその国家のもちあわせている国家意思を壟断するほどの権力意思を内在させていることを指す。「資本主義経済社会」と「社会主義経済圏」を対峙させ、その双方に呼応する「党派」を思い描き、思想に沿って個々の国民がおのおの政治主張をくりかえしているかのようなイメージをふりまく市民主義者が我々の周囲にいまもいることは否定できないが、彼らの国家観は、無知から発したものなのか(欺瞞的な錯誤によるものなのか)古典的な「民族国家」や「国民国家」のイメージで世界の経済現象や領土問題を理解しようとする。これは決定的に違う。「国家主義」における国家の権力意思と、「社会主義」による国家、「国家社会主義」による国家における権力意思は、まったく違った挙動になることには思いを至らせたほうが良い。ひるがえって、わが国はすでに国土の表面にある現実の「国民国家」「民族国家」とは位相の違う「国家社会主義」により国家意思を占有されている。これが私の主張の骨子である。
2008年08月25日
コメント(2)
-
従兄の父他界と「雑感」
年齢が近い従兄の父親が他界した。昨晩は通夜だった。他界された方の遺徳をしのぶなど、そっちのけで親戚の「同窓会」になる。親戚にも情の深いのがいて、疎遠になっていることを生真面目に怒る奴もいる。ツチノコなみに親戚の集まりに参加しない俺には集中攻撃もある。だか、おおむね懐かしい話題交歓だ。こっちが忘れていることを良くおぼえているものだ。彼らの記憶にとどめられている自分の像は、色あせた紙焼き写真のようではあるが真実の片鱗も残している。さて、こちらは状況的に生きている。どちらも真実の姿である。30年前、50年前の真実で現実に生きている自分を読み解きされても困る。しかしたまには、そういう作業も必要かもしれない。夭逝とは言い難いが、バブル期に散った義弟にも話題がおよぶ。彼は短かったが、周囲に強い印象を与えた特異な生きざまだった。人は状況的な生きものだ。良いも悪いも人は「状況的」であって、社会はそんな個人に対して原則寛容ではいない。帰属する家族、地域、組織、結社、信教(教団)の自由というが憲法の謳う「自由」は翻って考えれば国家や社会が、もっとも非寛容的である個人の状況ということだろう。当然といえば、当然である。戦後憲法の箇条に敬意を払うものの、それを額面どうりに受容して「普遍社会」の像を重ね合わせようとしている方ががむしろ異様なのかもしれないと思うことが増えてきた。これはけして観念的なものではなく、具体的なビジネスなどの中で現場と実体験をもとに感じ始めたと思う。
2008年08月24日
コメント(0)
-
日本の戦後も基礎は国家社会主義だ
>目からウロコというような、しかし腑に落ちるはなしです。>花森安治が、そういう筋の人だとは知りませんでした。しかし、左右のみごと(?)なまでの入れ替わりはよくあることで、生涯一貫して自分を貫けるという人もまた少ないのではないかと思っています。msk222さん-----Re[1]:ファシズムに担保された「戦後」(08/20) 左右のいれかわりwいやいや、そういうゲシュタルトチェンジって理解は私はしません。日本は、やはり基礎の部分に国家社会主義の構造を温存してきていますよ。気づいていないだけです。それはWINDOWSが システム設計にDOSをひきづってきたのと似ているかも。この稿もふくめて、以下の7月18日からの連続エッセーです。内容の理解のために以下の記事から読み返しくださることを強く推奨します。2008/07/18吉本隆明と「関係の絶対性」
2008年08月21日
コメント(1)
-
ファシズムに担保された「戦後」
日本で社会主義、ないしは共産主義と呼ばれている「運動」(もしくは陣営)の正体は実のところ 国家社会主義ではないかと思っている。分かりやすく言えば、ファシズムだ。ファシズムが悪いと言っているのではない。ファシズムが、すなわち悪いという短絡的な刷り込みを繰り返してきたものが戦後民主主義と言われるものなのだが、その戦後民主主義が実態で国家社会主義に担保されている。これは語られざる真実だと私は思っている。たとえば、映画「青い山脈」をみて育った団塊の世代をみよ。彼らの一体どこに個人主義へのまっとうな尊厳を尊ぶ魂が存在するだろうか。地域でも、職場でも、彼らの大多数は「タテ社会」への順応と肌身にしみこんだ使役と受苦の構図になんの抵抗もなく馴染む。また、たとえばあの雑誌「暮らしの手帖」だ。あの雑誌の主宰者であった花森安治は戦争にもゆかず、病弱との理由ずけで除隊して戦後に逃げ延びた東京帝国大学出の学士さま。その正体は、大政翼賛会の宣伝担当指導者。ゲッペルスのミニチュアのような存在だった。有名な標語「欲しがりません勝つまでは」というキャッチコピーは、ほかならぬ花森安冶が、企画編集し採取したものだ。戦争を除隊で免れたところは、東京帝国大学法学部卒の作家、三島由紀夫と同様である。彼らの本質は、リベラルでもなんでもない。ずばり 国家社会主義だろう。ようするにファシストなのである。戦後民主主義の底流にあるのは、このようにファシズムに担保されたかぎりでの「リベラル」「社会主義」なのである。そう思っている。
2008年08月20日
コメント(5)
-
風景の死滅
ジェーンフォンダ扮する女流劇作家リリアン・ヘルマンと、バネッサ演じるジュリアは、言ってみれば世界権力のインサイダーに近いユダヤの大富豪の子弟という設定である。冒頭で登場する高級車のエンブレムが、ただちに並みの資産家ではないことを示唆する。いうなれば、国家主義陣営も 国家社会主義陣営も、この才媛たちの祖父の経済権力によって誘導されているものに過ぎなかったのではないだろうか。その彼女たちが社会主義の陣営に身を投じ、一命を捧げて挺身するという構図はハリウッド映画ならずとも話題になる月並みなまでの展開である。日本でも、共産主義や社会主義の陣営で指導的な立場に登りつめる連中は、意外でもなんでもないほど貧困層や窮民階級の人間は少ない。良家の子女たちが、白樺派の「あたらしい村」へ踏み込むような動機で、社会主義陣営に身を投じるというのは、事実そういうことだったようだ。事実、彼らの「理想」とは彼らのスーパーエゴである。彼らが社会主義に「理想」を見いだすということは、彼らが最適化される都合よさが社会主義にはあるかならのだ。まちがっても思想的な普遍性が導くものだと思わないほうがいいだろう。実は、最近宮崎駿があるインタビューで彼もこの種の「理想」をアニメ制作の隠し味として持ち合わせて来たと述べているのを読んだ。それはいかに希釈されていても宮崎駿の作品世界にかならず気配をひそめて同伴しているのだ。この「理想」は、個人におけるそれとは相当ちがっており、早晩われわれを世界の果てまで連行してくれることだろう。
2008年08月18日
コメント(0)
-
唾棄すべき「理想」
30年ぶりに 、ハリウッド映画「ジュリア」をみた。お気に入りのジェーン・フォンダ主演の映画なのに30年以上もの永きにわたって見なかった理由は、バネッサ・レッドグレープという女優が助演女優賞でアカデミー賞を受賞した経緯てんまつが今だに良く分からない。それから後の紛糾ぶりも掴みかねた。映画をみるまえにスキャンダルまみれだったような記憶がある。いま改めてこの映画を通してみて、作品の平板さと所在なげな取り留めなさに一層落胆させられた。篠田正浩監督作品「ゾルゲ」と大差ない。これは失敗作とは言わないまでも、結果的にはハッタリともったいぶりだけが目につく二級映画のような気がする。良くても習作というところだろう。しゅうさく[しふ―] 0【習作】 美術・音楽・文芸などで、練習のために作った作品。エチュード。 この程度の作品が、映画制作者の世界では割合評価されて受賞した映画賞アカデミー賞(助演男優賞)(1978年)ほかゴールデン・グローブ(女優賞(ドラマ))(1977年)LA批評家協会賞(助演男優賞)(1977年)NY批評家協会賞(助演男優賞)(1977年)というのは、映画愛好家にとっての感動とは、ほど遠いところで映像流通が仕切られていることの証左ではある。それは、いつものことなのだ。さらに、この映画のつまらなさは多少思いあたる。さきに述べたように橋爪大三郎教授が、かつての恩師である吉本の思想的理念について言及しているものが重ねあわされる。国家社会主義と国家主義の「すきま」に、社会主義の理想を再生し「理想」をなんとか二本足で直立歩行させようとしたものを営為などと積極的なものとして読み解きせんと観じとったように、映画でも直截は語られないまま、暗示的に社会主義への理念へ向かい撲殺されてしまう年長の才女ジュリアに対する女流劇作家リリアン・ヘルマンの慕情が主題となっている。この同性の恩愛が、われわれの指導的な理念である社会主義の理念に同伴してきた時代相を悪い夢をみるように再現してくれる。教養的な意味合いの深い映画作品なのだ。いまこの映画をみて、70年代にこの作品に出会わなかったことを喜ばしく思う次第だ。橋爪大三郎が、今なお社会主義の理念に期待してリスペクトを抱くように。それがそうであるように映画「ジュリア」においても、その姿をあらわさぬ「幼なじみ」の女性への憧れのような漠たる敬慕が淡く淡く描かれている。それが、われわれを余韻のように占めているあいだは、ある意味で囚われた心はさながら無限地獄にあるようなものなのだ。そこにとどまるかぎり国家主義からも国家社会主義からも、正しく離脱することはできない。映画の冒頭にある寂しく釣り針を垂れる女流劇作家の姿は、報われぬ魂を暗喩している。
2008年08月17日
コメント(0)
-
携帯電話だけがWEBじゃない。
火曜日から長いお盆休みにはいり、ブログの更新も手抜きさせて貰っている。にもかかわらず、こちらには連日ほぼ同じような規模のアクセスがあり不思議な思いがある。日常の雑感を述べているわけではなく、やや時間軸の長い普遍的なテーマを選んで非力なアゴで咀嚼しているようなスタイル。たしかに派手さがないものの固定した読み手を招いているのかもしれないと思う。また、お盆休みで普段読めないブログに回ってきていただいているというようなこともあるのかもしれない。すでに述べたように、双方向コミュニケーションの現在ということでヤフーなどのチャットを徘徊していて大変に勉強になった。ブログで学ぶことと、また違った角度でさまざまに学習できることがあるものだ。たとえば、ヤフーチャットでユーザールームという小部屋がたくさんあるが、このような部屋にも極めて質の高いコミュニケーションを維持しているものが少なくなかった。過去10数年のながきにわたって蓄積してきたスキルや、方法論、情報を惜しげもなくいただいた事も多い。ビジネスや仕事の世界ならば、滅多に生じることではないと思わずにいられない。今日も面白い人にであった。WEBコンテンツと、比較的軽敏な装備だけで自分が歌うカラオケを多重録音してつくってしまうという男性である。こういう人を、検索エンジンだけではみつけたり遭遇することは難しい。しかし、異能に近い才能のある方を探すための漁礁としては、今回の事例ではヤフーチャットは極めて有効だという気がした。彼の話を聞きながら、同時に彼がいかにして必要な情報、資料、データーを入手しているのかというあたりの視点。具体策を質問して聞きだすのである。また、思いがけずに教えてくださる使いこなしの凄いワザもたくさんある。つまり、ことは手製のカラオケをつくるというノウハウだけに留まらないのである。
2008年08月15日
コメント(0)
-

ハリウッド映画の退屈さ
ハリウッド映画監督の中で、最も退屈でつまらないのはスティーブン・スピルバーグだろう。この男のつくる映画は、良くも悪くもハリウッド映画の歴史的な使命を体現しているという気がする。ヒット作を多産しているので、娯楽もの以外にまじめくさったシリアス風なものも多いのだが、踏み込んで鑑賞してみると妙なクセのある映画作品ばかりだ。その持ち味が典型的にあらわれているのは「インディージョーンズ魔宮の伝説」かと思われる。あれは妹夫婦が、見に行って喜んで帰ってきたが背景が読めていないと嘆息した。再婚した監督の女房ケイト・キャプショーKate Capshaw が、映画の中ではヒロインとしてあのムチ使いの名手である東洋考古学者と同伴する映画である。西欧人の冒険家が、大活躍して美人と東洋人の少年と暴れまわる。インドだかアジアだかは、知らないが魔宮には「邪悪な司祭」がいて、人民は魔術にかかったか呪術のせいかマインドコントロールされている世界、それがアジアだ。まあ、好き勝手に描けというものだが、邪悪なものの背後には、当然日本の天皇制も含まれるわけである。そういう構図を、やまほど浴びえてくるハリウッド資本のユダヤ人、それがスピルバーグの正体ではないか。他監督作品でも同様である。「トップガン」でも、「ダークエンジェル」でも主人公たちがまたがっている日本のバイクはカワサキのNINJYAである。日本のバイク愛好家は、マゾヒスティックに喜んでいるらしいが、忍者とは、まさに日本的アジア風景のシンボルという気がする。使うだけ酷使しては、簡単に使い捨てして破壊されてしまうのが日本製バイクの運命である。こう言う細部にハリウッド映画のメタなメッセージがこめられているのは間違いない。映画「カサブランカ」では、からくもスペイン市民戦争時点の状況が汲み上げられていた余地があるが、もはやスピルバーグ監督に至っては露骨なハリウッド政治謀略映画の巨大提供装置に化体してしまっている。慎重に彼の一連の作品を読み解けば、自ずとそれは知れる。
2008年08月10日
コメント(2)
-

われわれを背後から撃つ「我々」
ビデオショップのTSUTAYAが、夏休み恒例なのかDVDレンタルで半額キャンペーンをやっているらしい。いまのところ、レンタルしたいお目当てのソフトが少ないので立ち寄りしていない。もし、映画「カサブランカ」や「ブレードランナー」を見ておられない方がおられたら是非、一度鑑賞されることをお奨めしたい。すでに古典の域にある、両作品だが対比すれば学ぶところは多い。「カサブランカ」は著名な哲学者ウンベルト・エーコによって記号論的に読み解きされて、別途ハリウッド映画作品「薔薇の名前」に化けたという。その構造的な疎通については、よく理解できないのだが、「薔薇の名前」も力作だ。ウンベルト・エーコ(Umberto Eco、1932年1月5日 - )はイタリアの哲学者、小説家、ボローニャ大学教授である。アレッサンドリア生まれ。哲学者としては、記号論の分野で世界的に有名である。トマス・アクィナスの美論についての論文で学位を取得。イタリア放送協会でドキュメンタリー番組のプロデューサーとして勤務した後、大学へ戻り哲学論文ならびに文学作品の精力的な発表を続けている。現実の事件に啓示を受け、小説の執筆を開始。1980年に『薔薇の名前』として発表した。 1981年、同作でストレーガ賞を受賞。「ブレードランナー」に話を戻すが、レプリカントと呼ばれる人造人間たちのキャラクターはいずれも秀逸で人間精神の可能性について輪郭が不明瞭となった時代には、ひとつの人間性についての指標が必要だという意味で、崩壊するわれわれの内面をプロジェクション(投射)しているという風に考えて良いと思う。その意味でも、蛇使い女を背後から射殺するという刑事の描写は、映画史に残るシンボリックな意味合いを帯びていると思う。↓リンクかけています。↓リンクかけています。
2008年08月09日
コメント(0)
-

悲惨な時代の予兆
過去の映画で、くりかえし鑑賞に堪えるものが何作かある。映画「カサブランカ」は、自分にとりこの時代を知る手がかりだった。映画「ブレードランナー」は、信じられないが封切り当時は陰鬱な画像もあいまって、興行収入は振るわなかったという。自分はVHSもDVDも持っている。これも「カサブランカ」に負けない、歴史的な映画作品だと思う。そのほか「薔薇の名前」「エリンブロコビッチ」などをDVDで持っている。作品シナリオも取り寄せている。書物では学び取れないものが、そこにはある。1982年の「ブレードランナー」は、自分自身の生き方に喰い込んできたと正直思う。個人的には、彼らレプリカンとの生死に殉じて生きてきた気分だ。彼らがみたというタンホイザーゲートのオーロラに近いものは、みたような気がしている。冗談だが。しかし、映画が登場して以後世界のSFXは劇的に変化した。これも事実だろう。この映画の登場で、未来都市とカタストローフ大規模破壊映画の基調音が定まったような印象だ。これは「カサブランカ」の背後に仕込まれていた喜劇性、その言葉が当たらないとするならば笑劇性が払底している。つまり、あらかじめ国家社会主義に対峙する志操の持ち主である男女が恋に陥るなどという、洗練された予定調和の兆しはない。蛇使いのショーガールに潜り込んでいたレプリカンの戦士のひとりは、デッカード刑事に追い詰められてガラスのショーウィンドーを蹴破りながら背後から大口径の特殊銃で射殺される。主人公も、悲惨にみじめならば殺されるレプリカンともみじめである。射殺する刑事の魂も悲惨な悲鳴を上げているが、殺されるレプリカンとたちはその誇りの拠り所もない。↓リンクかけています。
2008年08月07日
コメント(0)
-

リックとルイザの時代
映画「カサブランカ」のセピア色したやさしくて悲しい愛をとりあげ、郷ひろみは「あんなに誰かを愛せない」と歌うわけだが、この映画はいわゆる余の悲恋のような描かれかたをしているとは思えない。むしろ現実にうちひしがれていた人が、大多数の時代にスクリーンの上でリックもルイザも生き生きと自身の信念に沿って生きている。国家社会主義の嵐が、吹きすさぶ時代にして彼らは個人の志操を堅持して、拠り所とする大義に向けて行いをまっとうしようとしている風に描かれている。喜劇という言葉があたらないと思われるかもしれないが、原理的にはこのような作品は、悲劇の貌をした喜劇なのかもしれないのだ。映画「カサブランカ」の成功は、この映画に秘められた喜劇性を緻密な作品世界の構築で覆いつくし、それとしれないところまで気配を隠しおおせたところにあると個人的に思っている。韓国映画の「シュリ」では、北の武闘訓練を受けた女性と南の対防諜の捜査員の男性が恋に陥るというムチャな話になっている。あのムチャさに気づく人たちも、映画「カサブランカ」の洗練度には騙される。現実に社会主義国家ができてしまうと、必ずそこには国益が生まれ、国家の指導者たちの個人駅な利害、人民に対する抑圧構造も生まれる。それに対する批判の視点は、共産党の内部では確保できない。むしろ在野の知識人たちの、知的な独立性、徹底性、倫理性によるしかない。さもなければ、革命の本来の目的である、自由を実現したり、人民の幸せを追求したりすることは適わない。こういう確信を、かなり早い段階で吉本さん(吉本隆明)はもっていたと思うのです。このような、人間を解放するための革命はすばらしいことだが、それが現実化すると権力と結びつき、忌まわしいことが起こるという警戒心ーーーーーこれは吉本さんの深い部分だと思うのですがーーーが、彼の思想の骨格をかたちづくることになった。橋爪大三郎「永遠の吉本隆明」吉本の弟子筋にもあたる橋爪教授の筆致が描写する吉本隆明の「思想の骨格」なるものは、すぐれて時代の感受に発しているというわけである。かさねて自分なりに感じ入るのは、そした感受性そのものが、ある種「喜劇的なもの」、さもなくば根底に手放しの「楽天」が含まれているように思われるのだ。スクリーンの中の「やさしくて悲しい愛」をみいだす大衆は、同時にその喜劇的な手放しの開放感、時代の変化を肯定する思いを実感していた。実は、これが曲者だと高度な資本主義の発展段階を状況として生きる「わたし」などは思い至る次第である。
2008年08月04日
コメント(0)
-
赤塚不二夫で行こう!
1935年、満州国(現・中国)の熱河省に生まれる。「バカボンのパパ」のモデルであり憲兵であった父親は終戦直前にソビエト軍に連行されてしまい、残された家族は1946年に母の故郷の奈良県大和郡山市に引き揚げる。1948年、奈良市内の書店で手塚治虫の『ロストワールド』に出会い、漫画の執筆に没頭。12歳で『ダイヤモンド島』というSF巨編を書き上げ、大阪の三春書房という出版社へ最初の持ち込みを行う[2]。1949年、父親が帰国。父の故郷の新潟県に移り中学校を卒業後、市内の看板屋に2年間就職[3][2]。同時に「漫画少年」への投稿も始める。赤塚不二夫が、他界した。ある意味、手塚治虫の死去よりもずっしりと堪えるところがある。手塚は、自分が物心ついたときにはすでに相当メジャーだった。貸し本屋文化もしっているが、手塚は借りたくて借れるというような作家ではなかった。何冊も借りる常連が続々予約していて、小学生の手元にくるのは何ヶ月もあとだった。一方、赤塚不二夫は自分らの世代がファンとして育てたという印象がある。赤塚の出世作の「なまちゃん」は、ちょうど中学生になったぐらいで登場して話題もちきりだったような気がする。そして、あの「おそ松くん」「天才バカボン」が炸裂する。手塚治虫、石ノ森章太郎のアシスタント時代もあって赤塚不二夫は戦後の漫画家の殿堂入りは間違いないだろう。それに赤塚の独自世界は、ちょっと空前絶後のような気がする。ギャグ漫画の文法を書き換えた、そんな気がする。どんな業界に置き換えても、赤塚不二夫ぐらいの「大きな仕事」を残すことは相当むつかしい。文字どうり天才に近いのではないだろうか。
2008年08月02日
コメント(4)
全15件 (15件中 1-15件目)
1