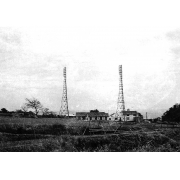暑中お見舞い申し上げます今日からお盆にはいりましたね。
突然ですが 「夫婦鯖」
と書いてどう読みますか?
ふうふさば、めおとさば、みょうとさば? 何れも誤り
なんです
正解は「 さしさば
」と読みます。
勿論 当地方の独特な呼称で全国バージョンではありません。
今日からお盆の諸行事が始まりましたね。
仏様のある御宅の奥様、お母さま方は 精進料理作りで大変
であろうかとお察し致します
さてこの「 夫婦鯖
」近所のスーパで買ってきました。名称は「 さし鯖
」と書いてありました
なんの変哲も無いこの2匹の雌雄鯖の写真をご覧下さい
「なんだ、開き塩鯖2匹じゃあないか!」
詳細な製法は妻にも分らないそうですが、腹を空け内蔵を処理した後,薄塩乾燥?
※味は少し塩鯖とは違うんです。 この商品は盆の期間のみ販売
してあります。
確かに塩鯖2匹なのですが特別な話題というのは 製造法にあるのではないのです
この「夫婦鯖」を食べる権利がある人と、ない人があるという事なのです
お盆の初日の13日、この夫婦鯖を茄子の2枚の葉に乗せて神前にそのままお供えした後、生のまま 家族の中で両親が健在の人
のみ 2匹の切り身をほんの少しを戴きます
その後は塩鯖の調理と同じで適当な切り身にして焼いて食べます。
今度は食べる人は家族全員となりますが仏前には生臭ですので焼いてあってもお供えはしません。
「 両親が健在である
という事は
生ものでも食べられるという事で有難いことだ
」と云われてきました
補足すれば 私の両親が無くても
妻の両親が健在ならば 妻のみがこの権利がある
のです
しかし、最初から家族の内で夫婦、子供の内で両親の一方が揃っていなかったならこの「夫婦鯖」は食べる資格がありませんので購入する意義は生じません。
種々聞いて見るにこの風習があるのは 鳥取県伯耆の国の一部
にあるように思えます。
変わった風習ですね、他の地方でこの風習がありましたら是非ご紹介いただけませんでしょうか。
今日は、今でも残る郷土の「 夫婦鯖
」のお話でした
ちなみに私たち夫婦はまだ両親が健在ですのでこの「 夫婦鯖
」を戴きました
さほど目出度くもなく 今後の 老々介護
が心配です。
面白い風習ですね。
一番びっくりするのは、
今津さんのところ、ご夫婦とも、ご両親がご健在なんですか?
それが一番びっくりです。
僕なんか、25歳の時に母をなくしましたし。
家内も、10数年前に母をなくしました。
長寿の国なんですね。 (2008/08/14 12:50:24 AM)
所変われば?で、独特の風習があるんですね。
ひとつ物知りになりました。
ご夫婦ともご両親ご健在との事、ご長寿でいらっしゃいますね。おめでとうございます。 (2008/08/14 02:09:57 AM)
嬉しい事ですね。
どうか親孝行なさってくださいね。
夫婦鯖は、初めて耳にしました。
そんな風習があるのですね~
こちらは13日の夕方、ご先祖の精霊をお迎えします。
提灯を持ってお墓にお迎えに行きます。
家からはお供え物とお花などですね。
そして、提灯の灯りと共に精霊を家にお連れします。
京都の五山の送り火(大文字焼き)も有名です。
1年に1回里帰りされるご先祖様を家族皆でお迎えし、生前のご恩に感謝します。
今は亡きご先祖の精霊が生家に戻ってきてくださる大切な行事、家族で心からお迎えします。
16日には送火を炊いてお送りします。
我が家は、どちらも両親を亡くしました。
寂しいですが、いつも傍で見ていてくれているような気がします。
(2008/08/14 06:03:35 AM)
>ご両親がご健在・・何よりの宝ですね。
>嬉しい事ですね。
>どうか親孝行なさってくださいね。
★菜の花さんおはよさんです。
どうも親孝行し過ぎてしまってこのザマです。
>夫婦鯖は、初めて耳にしました。
>そんな風習があるのですね~
★頭の隅にでも入れておいて下さいネ
>こちらは13日の夕方、ご先祖の精霊をお迎えします。
★この行事は同じです
>提灯を持ってお墓にお迎えに行きます。
★提灯をですか・・本格的ですね
>家からはお供え物とお花などですね。
>そして、提灯の灯りと共に精霊を家にお連れします。
★我家は私で9代目です、皆お帰りになれば満員御礼です(笑)
>京都の五山の送り火(大文字焼き)も有名です。
>1年に1回里帰りされるご先祖様を家族皆でお迎えし、生前のご恩に感謝します。
>今は亡きご先祖の精霊が生家に戻ってきてくださる大切な行事、家族で心からお迎えします。
>16日には送火を炊いてお送りします。
★それは全国的に有名ですね。
>我が家は、どちらも両親を亡くしました。
>寂しいですが、いつも傍で見ていてくれているような気がします。
★いかにも優しい菜の花さんらしいお気持ちがでています。
-----
奇妙な風習で両親揃っても中止されるご家庭もあるし、お嫁さんが他地方から来られればチャント伝承していなければ自然消滅です。
妻は隣地区から嫁いでいますのでこの風習を既知しておりましたので現在までも維持してまいりました。
特別に面倒な行事でもなく「夫婦さば」を購入すればいいことです ちなみに¥500くらいです。
いつもありがとう、感謝、感謝ですよ (2008/08/14 06:31:42 AM)
>こんばんは、
>面白い風習ですね。
★全く奇妙な風習です、¥雌雄対で500で盆の期間のみ販売しています。
>一番びっくりするのは、
>今津さんのところ、ご夫婦とも、ご両親がご健在なんですか?
>それが一番びっくりです。
>僕なんか、25歳の時に母をなくしましたし。
★青年多感な時代ですね、お気持ち察します。
>家内も、10数年前に母をなくしました。
>長寿の家庭なんですね。
-----
★晩年まで元気で家庭の一助として働いてくれましたがそれでもかろうじて自分のことは自分で始末するようです。老々介護が心配で苦の種(笑)です。
(2008/08/14 06:39:04 AM)
>初めて知りました。
>所変われば?で、独特の風習があるんですね。
>ひとつ物知りになりました。
★妻も隣村から嫁いで来ていますんで子供の頃から「さしさば」を食べてきましたので我家でも抵抗なく盆行事として実施しています。
商品化された「さしさば」一応、雌雄で1対で¥500ですもの。生鯖を自宅で加工する訳でもないのです
>ご夫婦ともご両親ご健在との事、ご長寿でいらっしゃいますね。おめでとうございます。
-----
親孝行がチョイとし過ぎました。老々介護が心配でございます。
都会のお盆は7月ですか?
※オバケカボチャ今月中にはUPの予定です。
まだ成長を続けているようで途中経過は極秘です(笑) いつも感謝で一杯です ありがとうございます。
(2008/08/14 06:52:35 AM)
>無学のわたくし、伯耆の国の意味が解らないので、これから国語辞典と検索をしてみますね。
>無学露呈=野鳥大好きです。
-----
大変ご無礼をしました。
遠方からですと昔の国の呼称なんて死語に近いかも知れません。
聞いたことがあっても「何県の何処地方」と言える方はあまりいないんじゃあないかな?
「伯耆の国」とは鳥取県西部地方を指します東部地方が因幡地方で民話「因幡の白兎」で有名な地方ですね。
伯耆の西が出雲地方です。これは「出雲大社」が存在し全国的に有名ですね。
初めから鳥取県西部地方と表現すればよかったですね。ご指摘ありがとうございました。
(2008/08/14 07:17:06 PM)
PR
カレンダー
コメント新着