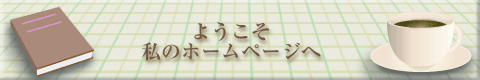全177件 (177件中 1-50件目)
-
かけがえのない地球
「かけがえのない地球」 私達は生まれた この地球に私達は生きている この地球に犬も猫も ライオンも 木や草や 鳥たちもそして 小さな虫だってみんなみんな 生きているのだかえがえのない地球かけがえのない子供達かけがえのない未来昨年、詩をフランス語に翻訳してくれる、というお話があり、長年の思いを急遽、詩にしたためた。地球上に絶え間なく起こる戦を見聞きするにつけ、自分をも含めて、どうしてこうも人間は欲が深いのかと嘆くことが多かった。地球上に存在するものは皆、地球から生まれ出た兄弟姉妹のようなもの。憎み合ったり、恨み合ったりしなくてもいいのに、と素朴な思いもあった。 尤も、昔から兄弟は他人の始まりということも無くはないから、戦が起こるのも無理からぬことかも知れない。 後日、フランス語に翻訳されて届いたものを読むべく、仏文を習得しなかった私は、新横浜駅近くの三省堂に走った。仏和と和仏の辞書を求め読み解いていくと、「地球」が「terre」で女性詞だと気付き我が意を得た思いをした。やはり、「地球はお母さん」だったのだ。2004年、非営利団体<ACE地球の子供>を立ち上げたのも、そんな思いからだった。フォスターペアレントでの、マンスリーのささやかな援助をしていた時、フィリピンの女児から時折届く健気な手紙に胸が締め付けられることもしばしばあった。一人での支援は余りに微力。何とか少しでも多くの支援が出来たら‥。さざなみもいつか大きなうねりになるかもしれない。少しでも仲間を増やす方がいい。そんな思いと共に、次代を担う人達へのささやかな啓蒙活動の一助にも、との思いもあった。 足掛け10年。非営利団体<ACE地球の子供>は、皆様のお力添えで、ささやかながら活動を続けている。 (代表 鎌田紗和)第13回紗羅書展開催!!2013年10月31日(木)~11月3日(日)11:00~18:00銀座大黒屋ギャラリー 6・7 F(地下鉄銀座出口A2・0分)鳩居堂の左2軒隣り主催 紗羅会後援 毎日新聞社 (一般財団法人)日本書道美術院会員50名による、漢字・かな・詩文書作品 75点を展示別に「地球の子供」のチャリティー展示(はがき作品)もあります。多くの方のご来場をお待ちしています。 raku-sa 紗和
2013年10月08日
コメント(0)
-
もう何年振りでしょう・・
第62回浜書展 久々の更新です。 皆様こんばんは。 横浜日本大通りの県民ホールで本日より開催(~8/4まで) 浜書展に出品しています。 最近は自作のものばかり作品にしていますが、 今回は久々に「松尾あつゆき」の俳句を書きました。 ***** 空にはとんぼう いつまでも年とらぬ子が瞼の中 ‥松尾あつゆき句 In the sky Dragonflies Still infants My children in my eyes ***** 松尾あつゆき 長崎で被爆。 妻も子も失っている。 他にこんな句も・・ 今日トンボ群れて仔細なし 原爆を落とした空 妻よまた来たよ こでまりの花だよ ‥‥‥‥ raku-sa SAWA .
2013年07月31日
コメント(0)
-
3月11日金曜日・・・・
この度の東北関東大震災において尊い命を落とされた皆様のご冥福をお祈り申上げます。また、被災された多くの方々に、心からお見舞い申上げます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3月11日金曜日 その日、私は竹橋、浜町、銀座と書展巡りを終えて最後の会場から銀座通りに出たばかり。足元の異様な揺らぎに地震だと直感して天を仰いだ。細いビルが左右にゆらゆらと大きく揺れ、今にも倒れそうで不気味だった。ついに関東大震災が来た、そう感じた私の頭の中を、もろもろのことが駆け廻った。急いでメールと電話を試みるが、勿論通じる筈もない。とっさに携帯電話のテレビをつけてみた。買い換える時、テレビなんか見ないから必要ない、といっていた“ワンセグ”が思い掛けない時に役立った。宮城沖で大地震発生、震度7、津波警報発令!小さい画面に矢継ぎ早に情報が飛び込む。状況をいくらか把握出来た私は、新橋に向かう友人と別れて、銀座から有楽町、そして日比谷に向かい、行き馴れたTホテルに入る。時を待つしかないと帰宅を諦めてロビーのベンチに腰を下ろした。今しがた別れてきた友人や家族への安否確認と、自分の様子を伝えるにはメールしかない。でも、その短い文面が情報を伝え合い安堵することが出来る。電池の残量を気にしながら、電源を落としては又点ける。一度や二度では送れないが、何度か繰返すとふとした時に送信出来る。文明の利器の恩恵に大いに感謝した。所在無く椅子に掛けていると、色々な人の顔が浮かぶ。あの人はこの人は・・と案じながらも、メールを途中で消去した。こういう時は不急の連絡はしない方がいいのだ。ホテルのロビーは、いつの間にか避難客で埋まり、地下も2階への階段にも人が溢れている。でも、さすがに一流!ホテルマン達の対応はお見事この上ない。冷たいお水の差入れを戴き、ホット一息!午後9時半過ぎ、“銀座線開通”の報に、隣合せた人達に挨拶してホテルを出て銀座に向かう。昼間と違って方角がよく判らない。若い女の子のグループの一人に尋ねると、道案内してくれた。途中で見慣れたネオンに気付き、もう大丈夫だから、とお礼を言って小走りで乗り口に向かった。それにしても、こんな大変な時に何とも可愛い女神に出会えたものだ。電車はすし詰め。かなり酩酊の中年男性が、携帯片手に悠長に喋りながら、右へ左へと身体を揺れに任せる。その度に掛ける周囲の乗客への迷惑などはまるで意に介さない。何とも幸せな御仁である。渋谷の東横線の改札口前は大混雑で、電車の開通はいつとも知れず、行列に加わったものの、このままどれ程立っていられるか心もとない。後は持前の精神力で耐えるだけか。1時間余りの後だったか、漸く改札を抜けた。のろのろと動き出した電車で大倉山駅に着いた時は既に零時過ぎ。エレベーターもエスカレーターも止まり、町は薄暗い闇の中に眠っているようであったが、街灯はいつもと変らず灯り、今しがたの地震騒ぎなどはまるで何もなかったかのように、電車から降りた乗客達は、足早に静まりかえった闇に吸われていった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・皆様、長い間大変ご無沙汰致しました。ブログでは失礼しておりましたが、元気に活動しています。書も、<ACE地球の子供>も。<ACE地球の子供>では、東北地方の被災地の皆様への募金を始めております。また、今年度の皆様からお預かりした寄付金は、全て東北地方の方々にお送りする予定です。皆様、どうぞよろしくお願い申上げます。 raku-sa SAWA
2011年05月24日
コメント(0)
-
人生の開拓者に
待っているだけでは 何も出来ない 失敗をおそれず やってみよう 世間体にとらわれず 信じる道を進もう 君が 人生の開拓者になればいい 『人間賛歌 生きているから』 (木耳社) ・・・・・・・・・・・・・・・・・
2009年11月10日
コメント(1)
-
今日ひと日
今日ひと日 今日のため 明日へとつなぐ この刻のため ・・・・・・・・・・・・・・・・ 通い馴れた道にも 何処からか木犀の香りが届く もうそんな季節なのだ 風の冷たさに秋の深まりを覚え 更に一日一日が大切に思われる
2009年10月11日
コメント(0)
-
『生きているから』 ・・一歩
「一歩」 一歩 そして また一歩 踏み出す一歩は 近づく一歩
2009年09月29日
コメント(0)
-
『人間賛歌 生きているから』
小著新刊『人間賛歌 生きているから』をご覧くださった方からお便りが届く。作者にとっては、嬉しいかぎりである。見ず知らずの方から戴くこともあり、小さな本の取り持つご縁に感謝する。中学の恩師からは、「父よ 母よ」にお母様を思い出しました・・とあった。もう半世紀程も前の、その時代を鮮明に記憶に留められているご様子に唯々驚嘆する。時折のぞく、語りかけるような文体に胸が熱くなる。きっと先生は、生徒を前にして話される思いだったのだろう。前回お目に掛かってから早15年、優しく美しいその先生は、今もって生徒の憧れでもある。ああ 父よ 母よちちのみの父は逝きははそばの母も逝き会えなくなって久しいけれど・・先生、どうぞお健やかに ・・・・・・・・・・・・・
2009年09月13日
コメント(1)
-
「生きているから」
暫くの、いえ、1年半ぶりの、長い間のご無沙汰でした。それでもお訪ね下さった方々にはお礼とお詫びを申上げます。さて・・ニュースがあります。その1終戦記念日の今日、いえ、正確には敗戦ですが。8月15日付で上梓しました。人間賛歌『生きているから』(木耳社)書店・筆墨店・ネット等で全国一斉発売です。ご笑覧くだい。本のことはHPにはまだアップしていません。悪しからず・・そのうちにして戴きます。気が付いたらもう、立秋が過ぎていました。もう残暑見舞いなんですね。優秀な猫の手がほしい・・
2009年08月15日
コメント(3)
-
四国路の春
同行二人四国巡礼の旅は、阿波坂東第1番札所霊山寺から始まる。嶮しい山道を登り、崖を下り、八十八寺の霊場を巡る。難行ゆえか、常に同行二人、お大師様とのふたり旅である。手甲脚絆に菅笠の出で立ち。遍路は、その白い装束の下にどんな思いを秘めているのだろうか。・・・・・・・・・・・・・・・四国路の春、山や野に三椏が薄黄色の可愛い花をつけ、桜や桃、菜の花が咲き乱れる頃お遍路さんと行き交う。今は、車で回る人も多くなったようだが、それでもやはり、昔ながらに歩いて廻るお遍路さんも多い。信仰と人情の厚い四国の人たちは、彼等を労い、湯茶などの接待をする。春の風物詩そして「遍路」は春の季語でもある。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お訪ねくださって有難うございます。最近、心無い書込みが多い為、残念ながらコメントをご辞退しております。 raku-sa
2008年04月17日
コメント(0)
-
お雛さま
旧家に生まれたものの、戦後ものごころついた時には、生家は既に没落し、広大な家屋敷と共に豪奢なお雛さまは姿を消していた。季節が来ると、一幅の軸と可愛い立ち雛を飾り、白酒や雛あられを供える。豪華なものといえば活けられた桃の花ぐらいで、ささやかな雛飾りであった。「段飾り」に憧れながらも、友人の家を行ったり来たりしては、それぞれの「お雛さま」を観賞してひな祭りを楽しんだものである。以来、「お雛さま」には不思議な執着を覚える。夫の実家では、戦災に遭うこともなかった田舎の、だだっ広い座敷に飾られた年代ものや新しいものなど数十体はあろうかと思われる、その大降りのお雛さまに瞠った。飾るのも片付けるのも大変なんよ、と何気なくこぼす兄嫁の言葉にさえ、贅沢な悩みだ、と羨望の思いさえ抱いたものである。私は「立ち雛」に心が動く。幼い頃への郷愁かもしれない。修善寺の帰りに立ち寄ったギャラリーでも、和紙で創られた「みちこ人形」のそれを見つけて求めた。今年はその立ち雛を床の間に飾り、三春の「でこ屋敷」で求めた切れ長の目のお雛さまを自分の書斎に飾った。相変わらず、豪奢な「段飾り」には無縁である・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 恐縮ですが、ただいまはコメントをご辞退しています。 書き込みは出来ませんので悪しからずご了承ください。 raku-sa
2008年02月11日
コメント(1)
-
遅ればせながら 「箱根駅伝」
慌しいうちに年を越し、2008年の1月も早半ば。恒例の書展が1月4日から始まり、5日のHオークラでの授賞式と祝賀会を控え、ゆったりとお正月気分に浸る暇も無いくらいだ。それでも、<箱根駅伝>がお正月を運んでくれる。例年、返礼賀状を書きながらテレビで楽しむ。42.195キロを一人で走りぬくマラソンは長い時間、自分との闘いであり、相当厳しいに違いない。しかし、チームプレーの駅伝は、また異なった意味で精神的なハードルは高いだろう。今年もドラマがあった。様々な理由による途中棄権、観ている者も切ない。選手の心中は如何ばかりか。それを示唆する監督も心中穏やかではないだろう。 無理を押して成果を残すか、選手個人の選手生命を思うか・・監督の親心。真っ先に考えるのは、当然、選手の身体と選手生命に他ならない。選手の将来を潰して成果を上げたとて何のことがあろうか。将来に夢を託せばよい。しかし、復路最終の10区に至ってのこととあれば、その落胆を思い 言葉を失う。何よりも、選手の思いに胸が痛む。将来、これをバネとしてどうぞ立ち直って欲しい。必要以上の責任感にさいなまれぬように・・心に大きな傷を残さぬように・・陰を落とさぬように・・糧として逞しく成長すればいい。ひたすら祈る思いである。こうして、我家は例年、「箱根駅伝」を楽しむ。☆・・・・☆・・・・☆・・・・☆・・・・☆小正月の今日、遅ればせながら皆様にご挨拶申し上げます。そして新成人の皆様おめでとうございます。気まぐれな更新のページに、いつも多くの皆様のご訪問を戴き有難うございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。かねがね心に期すことがあり、仕事を少々整理致し、今年は、たまには温泉や音楽を楽しみ、ゆとりをもって見聞を広めながら、勉強と制作に打ち込むつもりです。後進の成長にも、もう少し寄与できることと楽しみにしています。後輩の皆様、一緒にご精進ください。 raku-sa /SAWA
2008年01月15日
コメント(1)
-
ヴァンジの大男たち・・クレマチスの丘
ヴァンジの大男たち ----人間にある限りない未来 時折雷鳴の轟く激しい雨は、レストランを出る時にはすっかりあがり薄日が差していた。エントランスの壁のタイル絵を横に見て庭園に入る。ふかふかに茂った芝生は雨を吸ってか、生き生きとして真っ直ぐに伸びている。ぬかるむことのない広々としたなだらかな斜面に、ヴァンジの彫刻が点在していた。物干し竿を数十本も突き差したような、そんな中に見上げる程の大男が歩いている。いや、動いているわけではないが、本当に歩いているように見えるのだ。傍に立つと、私は小さな子供ほどになってしまう。普段、人の顔をしげしげと観察することはないが、彫刻となれば別、遠慮することなくじっくり眺める。その表情の豊かさに驚く。ある時期から、人間をテーマにおいたというヴァンジならではだ。その顔の殆どは左側に膨らみを持ち、右側の頬肉は少ない。人間の顔は左右対称ではないから、自分はどっちだったか・・と思わず水に映してみる。骨格は頑丈で日本人とは異なる体躯。勿論、作品としてのデフォルメはあるが、その多くは彼と同じイタリア人がモチーフと思える。ユーモラスな大男があちこちにいて楽しい。塀を攀じ登るかと思えば、ガラスに顔をへばりつけ、横たわり、そして屹立する。そのどれもが、大きな眼球を持ち遥か遠くを見詰めている。ヴァンジは、人間に限りない未来のあることを信じ、願い、祈り、それを伝えているのだろう。館内の作品は、リアルな表現で度肝を抜かれるものもあるが、素材の美しさに目を奪われる。ことに、石そのものの美しさを余すところなく生かしきった、といえよう。中でも、椅子に掛けた女性像は、三種類の、美しい見事な御影石で作られていた。一つは頭部、もう一つは花柄の薄いピンクのワンピースに見立てた胴部、そして脚部と使い分けられている。しかも、見る角度によって、観者は三人に出会える。像の左後ろに立てば初々しいおかっぱ頭の少女に、正面近くからは妊婦に、そして左前からやや右背後に至れば、ロッキングチェアーに掛けて寛いでいるような優しい老女に、である。さすが、ミケランジェロの再来とも評され、イタリアを代表する現代彫刻家ジュリアーノ・ヴァンジである。いつかまた、ユーモラスな大男達に会って、一緒にのんびり遠くを眺めたいと思う。もしかしたら、彼らは時空を超えてゆっくりと歩いて来るかもしれない。それは私の一大傑作の生まれる時だろうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・更新をオサボリするうちに、もう師走!今年もあと1ヶ月。なまけていた間にも、お訪ねくださって有難うございました。お寒くなりました。皆様ご自愛ください。 raku-sa☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2007年12月01日
コメント(3)
-
中国旅行 桂林会 in 横浜ランドマーク
桜木町で下車した私は、長いホームの端から端までを注意深く眺めた。が、どのベンチにもKM先生の姿はなかった。改札の外にはベンチがないから、とホームで時間の調整をして戴くようお願いはしたものの、仕事を終えてすぐ、駆け足で電車に飛び乗った。待ち合わせの時間までまだ30分はあるが、既に、改札の外に違いない。階段を駆け下りると、果たして、改札口から少し離れた人込みに遠来の客人を見つけた。どんな時も、人を待たすことのない方である。黒の上下にアイボリーのジャケットとベージュの帽子、見慣れた黒のショルダーバッグ。それにしても、もう片方の肩に掛けた黒い袋の何と大きいことか。駆け寄った私は、挨拶もそこそこに、近くのコインロッカーを勧めた。人込みを通るには余りにも大きすぎる袋である。祈るような思いもあったが、軽いから、と固辞するあたりも以前と少しも変りなかった。その元気さに舌を巻いてしまう。もう一人の友人の到着を待ってランドマークに向かう。 70年前、此処から毎日渋谷に通っていました。KM先生は國學院大學の出身である。70年前! 歴史上の人物と歩いているような錯覚に陥る。私はまだ生まれていない。エスカレーターで登り、動く歩道を歩く。途中から友人が黒い袋を担いだ。右手に横浜の海と係留した「日本丸」や「みなとみらいの」景観が広がる。港は、なぜか旅情を掻き立てる。あの時から丁度20年、中国も炎暑の毎日であった。北京の革命博物館と上海美術館での記念展に参加した折のことである。北京で皆と別れた後、桂林に飛び、漓江下りで悠久の時の流れを楽しむ。杭州の西湖、満月に逆流するという銭塘江、王羲之の故郷 蘭亭、紹興では魯迅の生家と記念館の三味書屋などなど、上海に向かう列車からは、高知学芸高校生が客死した列車事故現場を眺め黙祷。それぞれの記憶は未だ鮮明に残る。NHKの往年の名アナウンサーN氏、平安かな(古筆)の料紙(伝統工芸)では日本一(ならば世界一)の社長K氏、四国徳島の書道家Y氏、私の門下生I、4人は既に泉下の人となってしまった。京都のかな作家で卓球現役選手KM先生と 高校の先生T氏と私を含め総数14人の、14日間の旅であった。観光だけでなく、折々に歌を詠み、俳句を吟じ、漢詩を朗す。Y先生は、帰国後生徒に聞かせるのだと、ウォークマンに実況放送ならぬ解説と感想まで録音する。お酒を飲んでは喋り、喋っては又飲む。誰かが詩を詠むと、俳句を書いたメモが回り自作のものだけでない。杜甫や李白は言うまでもなく阿部仲麻呂に菅原道真・・行く先々で次々に話題は尽きない。正に文人達の集まりである。多分、もう二度と味わうことはないだろう。帰国後数年は 毎年自由が丘に集まって旧交を温めたものだったが・・ 会いたかった! 京都から駆けつけたKM先生の第一声である。手を取り懐かしげに何度も呟く。日本一の高層ビル・ランドマークのホテルのレストランでは、眼下に広がる街の、何処というでもなく、じっと遠くを見つめながら、 皆、早よ~いて(逝って)しまわれましたなあ~ 早すぎる! 一瞬 語気を強めた。それもその筈、最高齢の彼は94歳。今も、卓球の最長老の現役選手である。 今、桂林の旅を思い出し、お酒を飲んでいます。 一人暮らしも20年、今年は元気です。来年はわかりません。 人は、私のことを化け物だとか、怪物だとか言いますが・・そんな手紙を手にした私は、上京の折に合わせての「桂林会」の同窓会を提案した。3人だけの一見寂しいものではあったが、3人には、20年前の、かけがえのない旅人達の笑顔が甦っていた。 ・連れ立ちし友と別れの宴開く 姑姐(くうにゃ)の詠みし詩の沁みゐる
2007年09月01日
コメント(2)
-
暁の空に
あかときの静寂を破る高き一声叢林を抜け空高く吸われゆく何を見 何を思うか暁雲に向かう鳥の一羽こころ 解き放つ暁の空に
2007年07月06日
コメント(2)
-
桜 ・・・春の嵐に
暖冬で桜が早く咲くかと思ったら、早いのは早いけど、とびきり早いという印象でもなかった。ただ温かければ早く咲くという訳でもなく、開花前に気温が低くなることも必要らしい。身の引き締まる寒さを越えなければ開花出来ないとは・・花の命も短い上に、なんとまあ、けなげな花であることか。どちらかと言えば、凛とした梅の花を好んできたが、潔いその散り方と相俟って、今年はとりわけ 桜をいとしく思う。桜といえば西行、と言われるように、西行の和歌には桜を詠んだものが多く、それらはみな人口に膾炙されているが、晩年、西行はこんなことを話した。毎年 桜が咲くと思うだけで 私(西行)は嬉しさに胸が膨らむ。それだけで 私(西行)は生を成就している。桜が咲いて 人々が心浮き立つ時その喜びの中に 私(西行)はいつもいるのだ。 願はくは 花のしたにて春死なむ そのきさらぎの 望月の頃 その願いどおり、皓皓と光る満月の夜、西行は73年の生涯を閉じた。後に俊成は詠う。 願ひおきし 花のしたにて をはりけり 蓮(はちす)の上もたがはざるらむ西行にはこんな歌も残る。 仏には 桜の花をたてまつれ わがのちの世を 人とぶらはば・・・・・・・・・・・・・・・風が鳴る。26年前も春の嵐が吹き荒れた。・さくら散る お洒落な君が図りしか 空には激し 告別の舞 (「春嵐」より)
2007年04月01日
コメント(3)
-
赤ちゃんポストなど・・
「みどりご」・生を受け みどりごは眠る安らけく 窓にライラック揺るる春日に・含(ふふ)まむと 含(ふふ)ませむとて あぐみ合ふ 誇るがに張る乳房まぶしき・おぼつかなき母の腕(かひな)で乳求め みどりごは泣く身をふるはせて新米ママに生まれたばかりの赤ちゃん、おっぱいを飲むのも、飲ませるのも一苦労。それでも やがてどちらとも逞しく成長する。微笑ましい光景。赤ちゃんポストなるものが出現しようとしている。何を考えているのか、浅知恵としか言いようがない。一流紙といわれる新聞大手の「余禄」にさえ、赤ちゃんの人命を尊ぶ・・云々のくだり。何とも情けない限り。対症療法に過ぎない。風邪を引けば風邪薬、頭痛がすれば鎮痛剤、の類と同じ。生命は尊い。守らなければならない。しかし、母親としての義務はどうなるのか、厳粛な生命の誕生にかかわった責任と義務。何よりも、誕生した子供への責任と義務は計り知れない。どんな事情ががあるにせよ、親としての責任を全うすべきもの。母親に限らず、それは父親にも当てはまる。事情を明かせない、明かしたくない、などとのたまう親を決して甘やかせてはならない。子供の命を救済するという心地よく響く言葉の下に、そんな無責任な風潮を社会に根付かせてはならない。何処の誰の子供か判らなく成長していく子供のことを考えれば当然のこと。私には、とても理解することは出来ない。法律的には問題がない、とのお役所の見解だが、法律だけで判断を下すなど・・もう、この国は、救いようのない所まで落ちてしまっているのかも知れない。無茶苦茶・・悲しい限りだ。赤ちゃんポストなど、手紙や物じゃあるまいし、是非もない。どうしても育てられない親のために、受け入れ窓口を作って親子を救済すればいい。押し付けがましい道徳感で縛っている離婚後300日以内の赤ちゃんを前夫の子としている現行の法律。法律で決められているものにも如何に不都合なものがあるか・・顕著な例でもあろう。私は、一歩も譲らない。
2007年03月01日
コメント(2)
-
私 もうぢき鳥になる
いかにも逞しく頑丈そうな太い幹、そのてっぺんからは数本の巨大な枝を伸ばし、細長い形をした無数の葉を付けている。風が吹くと ゆさゆさ揺れて、今にも空へ飛び立ちそうだ。葉の付け根には、薄茶色の鳥の巣のようなものが見える。ビロードでもなく、艶のないスエードに近い風合いの花か稚葉か。大事にくるまれながらも、鮮やかな赤い色の顔がちらちら見え隠れする。初めて目にするそれに近づき覗いてみれば、何と枇杷の実に似た無数の卵、いや卵らしきものである。これはまさしく“たまご”に違いない。そういえば、太い幹には網の目が張り巡らされて鳥の足に似ている。大きな枝を天に向かって広げ、風を孕んで揺れるさまは正に鳥の羽そのまま。前世は鳥類であったか・・いや、鳥になる日を夢見て、ゆさゆさと大きな羽根を広げているのだろう。そして 風が吹くたびに 叫んでいるのだ。わたし もうぢき 鳥になる!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・蘇鉄(そてつ)鉄によって甦るといわれている。ソテツ門の植物は、シダ類の次に現れたもので、顕花植物の裸子植物亜部に属す。隠花植物と顕花植物との間に位置する特殊な存在で、前時代の生命を今まで持続してきた生きた標本である。雌花と雄花があり、ここに記したものは雌花。雄花は天に向かってまっすぐ伸びる花。
2007年01月31日
コメント(2)
-
最期の賀状
中国文学者の第一人者であった 駒田信二先生は、「中国書人伝」というエッセーを、4年間雑誌に書かれたことがあった。(後年『中国書人伝』(芸術新聞社刊)に纏める)それは書法についての論評ではなく、書聖といわれた王羲之や鄭道昭など中国の代表的な書人を取り上げ、古くから言われる「書は人なり」との観点から書人を見つめたものである。「書は本来、彫るもの」であり、中国の書人たちの「書」がそれを教えてくれた、と言われる。「筆を動かして字の(あるいは字に似た)形を書いているだけのもの」は(日本の)書道かもしれないが「書」ではない、と。手厳しいが慧眼と言わざるを得ない。純文学の同人誌『まくた』の題字は、200号の記念に駒田信二先生が揮毫されたものである。さすがに墨は紙背を徹し、深みがあり、何よりも品がいい。厳しさとふくよかな優しさとを併せ持ち、頑固さとどこか可愛らしさをちらりと覗かせる。不遜をお赦しねがって分析を続けさせて戴くならば、唐様(からよう)つまり、中国の書法に則り、始筆は蔵鋒で重く送筆部は静か。慎重な筆遣いが随所に見られ、終筆からは、何事もきちんと対処される几帳面さが窺える。強靭な思想であるがゆえに多くのものを包容しうる、威厳と温かさと品格に満ちた中国文学者<駒田信二>そのままの「書」だと思う。以前、漢詩を編んだ著書を戴いたことがあるが、ページを繰るごとに私は息を飲んだ。誤植のすべてを、ルビの一つ一つまで、赤鉛筆で直されていたのである。地名の横には、東へ○○キロメートルなどと加筆されているものもあり,費やされた時間とエネルギー、その煩しさとを思うと胸が痛む。数年前、同人誌『まくた』が月刊から季刊に変る時表紙のデザインを担当させていただいた。先生の題字を横書きに変え、抽象的な図柄(心象)を下部に入れて一新した。おこがましくも、先生との合作ということになり、記念すべき仕事のひとつとなった。暮れに『まくた・紅柳忌増刊号』が届いた。「書きつづけて死ねばいいんです」との師 駒田信二の言葉そのままに、「まくた」の同人達は頑張って書き続けているようである。扉の、痩身の遺影は、あくまでも清々しく凛々しい。次ページにはタクラマカンの熱砂に咲く紅柳、その2葉の写真に、ウルムチからの帰朝報告会や、千駄木での葬儀を思い出す。あなたはフリーパスですから、と笑顔で出入りをお許しくださったものの、伺ったのはほんの僅かばかりであった。威厳があり、凛として近寄りがたい存在ながらも、その笑顔は実に親しみ深いものであった。結びに、もう落手する術なき先生からの賀状の最期の詩句を引く。「春来還發舊時花」ゆるぎない文字が認(したた)められてあった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新年おめでとうございます。お訪ね下さった多くの皆様、いつもいつも申訳ございません。更新ままならず、お詫び申し上げます。 2007年 元旦 raku-sa
2007年01月01日
コメント(5)
-
ライトアップされた横浜市開港記念会館・・
5時半だというのにもう薄暗い。秋は、日が沈むと一気に闇に包まれる。一際明るいのは、横浜市開港記念会館。ライトアップされた時計塔は、一際明るくオレンジ色に浮かび出ている。官庁街の日本大通り界隈は、ビルから溢れ出た人達が、連れ立って、あるいは私のように1人で思い思いに家路を急ぐ。並木の銀杏も薄闇の中に溶け込んで、黒いシルエットを作り出すだけ。色付き始めたばかりの木々が、溜息のでるような、辺り一面、それは見事な、黄金色の美しい並木にかわるのも間もなくのことだろう。いつの間にか周囲は商店街に変る。横浜スタジアムの林が見え、横浜市庁も視界に入る。左に曲がれば横浜中華街。私は右に曲がり関内駅に向かう。改札口でスイカ(JR用プリペイドカード)をタッチする。改札口の切符挿入口に通さずとも、これだけで入鋏したことになる。いちいち切符を買う必要もなく、誠に便利な代物。最近は、そのチャージ(カードへの入金処理)も必要なくなった。あらかじめ決めた金額以下になると、前もって登録してある金額が、改札を通る時、自動的にチャージできる仕組みになったのである。私は、2千円以下になると、改札口で自動的に5千円チャージ(入金)できるよう登録している。時間と手間が省けて便利といえば便利だが、路線図を眺め、料金を確かめながら切符を買う楽しみもなくなり、味気ないと言えなくもない。また、機械は故障することもあるから、カードの引き落としの請求書が届いた時には注意することも肝要だろう。私は、エスカレーターを使わず階段を上る。最近は、大きく息を吸いながら2段、ゆっくり吐きながら8段登る。暫く前は呼吸が浅くて吐きながら登るのは4段だけだった。それが6段になり、時々は10段登れるようになった。疲れてくると一息で登るのは、4段になり3段に落ちる。身体は正直なものである。庁舎の門を出ればすぐみなとみらい線の日本大通り駅、そのまま乗れば、東横線大倉山駅、我家の最寄り駅に直結している。朝、出勤時は勿論このみなとみらい線を利用するが、帰りは歩く距離を伸ばしたくて遠回りをする。下車駅から我家まで16分。買物すればたっぷり30~40分は歩ける。普段、運動らしきものをしない私の健康志向、せめてもの努力。偏にいい作品をつくりたい一心ともいえよう。
2006年10月19日
コメント(2)
-
再び 横浜日本大通のカフェ・ドウ・ラ・プレス
再び カフェド・ラ・プレス最近、週1回は出かけることになった仕事場近くのフレンチレストラン。以前も紹介したことがあるが、静かないい雰囲気とランチがお気に入り。窓から日本大通りの大銀杏を眺めながら食事が出来るのは、多忙な日常からすれば、暫しの贅沢な時間である。シェフの腕前とセンスの良さからか、お洒落な料理がいい。味もデコレーションも、いつも小さな驚きを与えてくれる。メインデッシュのプレートを飾る付け合せが何ともいい。何時だったか、折れた木の枝のようなチョコレート色の細長いものが出てきた。不思議な思いで恐る恐る口に運ぶと、それは何と歯ごたえのある”ごぼう”である。ビネガーの酸味を加味して、さっぱりした味付けは申し分なかったが、何よりも、その姿に驚きと楽しさが加わった。厚切りの白い大根の時も感動したものである。おでん、ふろふき大根、ぶり大根・・大根はじっくり煮込んで、とろけるように柔らかくしたい。が、少し違う。ナイフを入れると少し硬い。いや、かなり硬い感じだ。さすがのシェフも急ぎすぎたか、と失礼ながら思ったのは大きな過ち。やや硬い大根は、噛むほどに甘味がじゅわあっと口中に広がる何ともいえぬ美味しさ。大根の旨味を改めて実感したものである。あるときはサツマイモ。縦に極く薄く、煎餅状というか長い小判状に削いでから揚げ。チキンのソテーに乗せた2枚のチップは、透明な黄金色をして微かにチキンを透かしている。他の野菜との織り成すハーモニーは、芸術的、いやもう立派な芸術であった。どちらかと言えば、私はあまりしつこいものを好まないが、ホテルでのパーティーとなればフランス料理である。あちこちでかなりの頻度で催されるから、作ってくださったシェフには申し訳ないけれども、少しづつ残しながら戴くのが常となり、平素は、フレンチを敬遠しがちとなったのだが・・。今 認識を改めざるを得ない。この、横浜の日本大通にあるフレンチレストランのシェフは、私の心をすっかり捉えてしまった。素材の持ち味を生かして調理する、手を加え過ぎぬそれは、人の教育にも通じるようにさえ思える。最近富みに、教育論がかまびすしい。それもそのはず、日本人の多くはもうかなり病んでいる。自然治癒には難しい重病と見る。どうしたらいいのか、どうすべきなのか、真剣な論議と対策が望まれよう。深刻な問題である。いつか、これも論じたいと思う。
2006年10月10日
コメント(6)
-
小田急線 入生田(いりゅうだ)の樹林と「鐵牛和尚の寿塔」
小田急線入生田駅からほど近い長興山紹太寺辺りには、小田原市の天然記念物に指定された樹林がある。堂塔は、幕末の火災で焼失したものの、樹林はまぬがれて聖域となって現存する。駅から10分程、参道らしきなだらかな坂道を行くと、趣のある石段に出合う。両側に檜や杉の林が広がり、落葉樹も混在して下草が鬱蒼と茂る。この位ならさほど苦労なく登れそうだ。ほっとして歩を進める。あっ、またあった!そうなのだ、石段がまた現れたのである。半分ほど進んだところで、私は二度目の石段を目にした。次への石段に続く坂道に<行の石組み>がある。参道の中央部分に不揃いの大きさの石が敷かれ、その部分の左右の両側は真っ直ぐな直線を描いている。石組みには真・行・草があり、石の大きさや形状を揃えて規則的に敷きつめていくものを<真>、全く異なる石を揃えずに敷いていくものを<草>とする。この寺は、石組みの両側には直線が美しく伸びる、<行の石組み>であった。樫や椎の落葉が幾重にも重なり、腐葉土臭も漂う。体脂肪の燃焼にはいいだろう。息を深く吸い込んでは、ゆっくりと吐きながら登る。呼吸を整えながら登るとかなり楽になる。とはいえ、些かもてあまし気味の私の前に、もう一つの石段が現れた。これって、なんだか詐欺みたい。疲労感を覚える私は、場所柄をわきまえずに不謹慎な言葉を呟く。いえいえ、心憎い配慮なのだ。半ば超えたところで次の課題を与えて新しい目標に向かわせるそんな大仰なものではないだろう。疲れた参詣者をなだらかな坂道で一息入れさせてくれる。なんとも心憎い限り。所々に生えた苔の美しさに目を奪われながら、石組みの美しさにも心惹かれて歩を進めた。春日局と稲葉一族の墓には向かわず、反対方向の、鉄牛和尚の寿塔へと進む。小田原城主 稲葉正則に招かれて和尚は小田原入りをしたようだ。辺り一面はみかん畑。まだ若い濃緑の実がぎっしりとせめぎあい、枝という枝はみな重そうに垂れている。みかん畑から再び林に入る。せせらぎの音を聴きながら進むと、「百花叢」「石牛塔」「遡回岩」などいくつもの刻銘石に出合う。野鳥が鳴き、やがて清流が現れた。咲き遅れた紫陽花があるかと思えば、赤と白の水引草が涼やかに揺れ、女郎花はまだ蕾ながら、吾亦紅はひっそりと咲く。ここはもう秋たけなわである。「鉄牛和尚の寿塔」は楠の大木の下にあった。一番下の反花座に清花座が乗り、その上の円形板状の塔身に、「開山上銕牛機老和尚寿塔」の文字が刻されている。1712年の和尚の13回忌の折、鉄牛和尚の長寿を祝って建立したそうである。清流に架かる小さな橋を渡ると、枝垂れ桜に出合える。樹齢330年の、天然記念物である。5本の棒に支えられて立つそれは、見るからに逞しい生命力を感じさせる。柵があって傍には寄れないが、遠目にも太い幹の逞しさは伝わってくる。花の季節ではないが、左右に大きく枝を伸ばし、その幹には似合わないしなやかな細い枝が幾本もぶら下がっている。その対比がまた興味深く感じられた。この幹に支えられて、春には華麗な姿のお披露目が叶うのだ。この銘木なら、さぞかし入生田は混雑するに違いない。混雑なんてものではないだろう。自販機の傍に春の名残の破れた幟があった。私はゴミがきらいです。ゴミは各自お持ち帰りください。 長興山しだれ桜(330歳)そういえば平安時代には、こんな歌を詠んだ人もいた。世の中に 絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし ・・・・・・・・・・・・・・・ 更新がなかなか進まないで ご無沙汰続きのページに、 いつもお訪ねくださって有難うございます。 随分涼しくなりましたね。 朝夕は肌寒い時も・・ どうぞ ご自愛ください。 raku-sa
2006年09月22日
コメント(4)
-
横浜みなとみらい線「日本大通り」
東京の渋谷と横浜を結ぶ東横線乗り入れの、横浜と中華街・元町を結ぶみなとみらい線は、「みなとみらい」「馬車道」「日本大通り」などお洒落な駅が多く、休日にはかなりの観光客が訪れているようだ。4月から、「日本大通り」駅を週2回ほど利用している。ホームは多分地下5階位だろうか、朝はエスカレーターに長蛇の列が続く。が、私はそれを尻目に階段を上る。運動らしい運動をしないから、せめて階段くらいは歩いて・・と。その心掛けはいいのだが、かなり骨が折れる。いや、4年ほど前に本当に骨が折れた時は、足の筋肉が落ちてリハビリに苦労した。多分今でも、骨折した右足の方が幾分細いはずである。以来、膝への負担を軽くしたいと考えて少しでも筋力をつけようとの涙ぐましいというか、僅かばかりの努力である。長い階段の果てに改札口、それから地上目指して再び長い階段を上る。地上に出るまでには相当の階段を上ることになり、私にとっては、朝からかなりの運動量だろう。街路に銀杏並木が続き、大桟橋や山下公園も近い。神奈川県庁、横浜地方裁判所、検察庁、横浜開港記念資料館など歴史を感じさせる古い重厚な建築物が点在する静かな官庁街である。近くには、お洒落なレストランも多い。県庁の斜め前、港郵便局前の交差点に位置する新聞博物館・放送ライブラリーの2階、CAFÉ de la PRESSE (カフェ ドウ ラ プレス)もその一つ。店内のディスプレイには絵画にまじり、セーヌ川やパリジェンヌの写真もある。華やかなシャンゼリゼ通り、モンマルトルの丘、ゴッホの家、裏通りのピカソ館、朝市の賑わいや、チーズやフルーツの味まで、パリの旅をを思い出させてくれる。クリーム色のカーテンをベースにボックスには茶色を配し、上品な色合いが落ち着いた雰囲気を作る。レースのカーテンがないことも気分いい。天井は高く、窓越しの街路樹や庁舎は借景となる。大銀杏を眺めてゆっくり食事を楽しむ。ウエイターは黒ズボンに黒の蝶ネクタイ、女性は黒のパンツスーツ。甲高い声が聞こえないのも嬉しい。静かな大人の店なのである。ウイークデイのランチがお勧め。スープ、サラダ、メインディッシュ、フランスパン、それにプチスイーツにドリンクが付く。¥1,050(土日は¥1500)ランチョンマットを敷きナフキンとおしぼりのサービスも。 料理の味もいいし、盛り付けも美しくお洒落なフレンチ。プチスイーツも本格的。私は専らハーブテイをオーダーする。 ・・・・・・・・・・・・・・昨日のメニュー◎カジキマグロのポワレ、 2色のソースで飾りつけ。グリーンソースはほうれん草がベースか、 赤紫色のは、トレビスにワインビネガーで酸味をプラス。 なすを敷き、かじきの上にはオニオンフライが乗る。◎レタスのクーリと赤い葉のヴィネグリット◎コールドコーンスープ、◎苺のショートケーキ+ドリンク
2006年08月30日
コメント(7)
-
新神戸から四国へ・・・「硯(すずり)」
早朝ホテルを出て、新神戸から再び新幹線に乗車、岡山からは瀬戸大橋を渡り四国に入る。轟音と共に通過する大橋、眼前に広がる海、幾層にも連なる島々は、濃緑からやがて青色となって空に同化する。波穏やかな内海は、初夏の日を受けて今日も鏡面のようにきらきらと輝いている。伸びていく白い航跡、漁(すな)どる船の幾隻か。それもこれも心癒すものにはなりえなかった。3ヶ月前母校に向かう時は、春の陽光に包まれ、少なからず、心躍る面持ちで海を渡った。前夜ホテルで催された「美を継ぐ者たち展」の祝賀会の華やぎは既に跡形もない。私は、硯を思いだす。前日ホテル1階にある骨董屋で見つけた硯である。飾り彫りも美しく、かなりの年代物に違いない。到底手の出せる代物(しろもの)ではなかった。愛想のいい店員に会釈して店を出た。そして、もう一面の硯・・・照れくさそうな、遠慮勝ちな義兄の笑顔が浮かぶ。高級品じゃあ ないんじゃきんど 使ってくれるか、私の前に差し出した。それは値打ちがあるとされる古端渓ではなく、見るからに色も新しい、新端渓と呼ばれる物のようであった。硯は採掘した場所や石の種類によって名前が付けられている。古い物が珍重されるが、素人には、古端渓と新端渓を見分けることは至難である。何も解らんきんど・・穏やかな言葉が私の胸に沁みた。初めての個展の時には、横浜まで駆けつけてくれた義兄である。その義兄が言う。また神戸に来るときには寄ってくれ、もう、なごうはないきん。ええ、また帰ってまいりますから、お大事にね。1ヶ月後、私はまた瀬戸大橋を渡った。真夏の太陽は既に沈み、薄黒い海が広がっていた。マイクロバスのシートに身体を埋める。義兄は骨灰と化し、長男に抱かれて生家に向かう。静かに悲しみが私を襲った。拭いても拭いても涙は留まることを知らない。更に深くシートに身体を埋めて私は空を見上げた。
2006年08月28日
コメント(3)
-
神戸・「明日への夢・・美を継ぐ者たち」
更新しないまま5ヶ月。それでも私のページを訪ねて下さる方が大勢いらした。申し訳なくお詫びするばかりである。例年夏に集中的に催されるいくつかの書展も幕を引き、漸く平生を取り戻す季節、大好きな秋の到来である。涼しくなれば体調も取り戻せるだろう。春から夏に掛けて今年は特に体力の低下を意識した。郷里風に言うならば、“ほんまにしんどかったなあ”。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6月20日、初めて新神戸に降り立つ。兵庫県立原田の森ギャラリーでの記念展、オープニングと祝賀会出席のためである。ホテルに荷物を預けて、タクシーでギャラリーに向かう。生憎の雨ながら、街路樹の多い静かな街並は旅の疲れを忘れさせてくれた。記念展は神戸にある「全日本美術新聞社」が、『全日本美術新聞』創刊20周年を記念して主催されたものである。日本画・洋画・彫刻・工芸・書の各分野から「自選ギャラリー」に登場した140名ほどの作家たちの作品を集めての展覧会である。「明日への夢・・美を継ぐ者たち展」確かに、芸術家はすべて美を継ぐ者たちである。タイトルがすっかり気に入った。見応えのある展観であった。さすがに芸術院会員の諸先生のものは、分野は違っていてもそれぞれ素晴らしい世界を構築されている。他の美術館の収蔵品も含まれている程で、素晴らしい一級品ばかりである。やや明るめの採光の中で、しかも露出展示のため間近に鑑賞。彫刻や工芸品はしゃがむと息がかかりそうになる。思わずハンカチを取り出して鼻と口を押さえた。私は、自分の詩の一節を引いた。信じよう自分を 夢はかなう とBelieve in yourself. Dreams come true.中国画宣紙80×70の正方形に近い形である。フレームは洋額を誂えた。既製品はほとんど使わない。現代的ながら品よくあがっていてほっとする。表具をすることを仲間内では「着物を着せる」という。作品を引き立てるのはやはり着物次第ともいえよう。英語ももう20年来書いているから違和感はない。最近は英語を書く人が増えてきたので、逆に私は書くことが少なくなった。天邪鬼なのである。バランスがいいとよく言われる。余白の美というか、以前から白を生かした作風が多い。(相変わらずのPCの腕前。写真掲載はご容赦の程を!)それにしても、いまどき奇特な会社である。掲載料も、出展費用も作家の負担はなかった。すべて“ご招待”なのである。その上 祝儀も受け取らない徹底ぶり。まことに頭の下がる思いである。新企画を楽しみにし、益々の発展を祈るばかりである。
2006年08月25日
コメント(7)
-
母校は元気! (その1)
予讃線を降り立ち、母校を訪問。13年前の講演以来である。校門の傍の松(かいずかいぶき)の翠は変わりなく色濃く鮮やか、黒味がかったでこぼこの幹に年輪の重さを感じる。母校は、2年後百周年を迎える。その歴史を伝える<かいずかいぶき>である。3月も半ばの春というに、気まぐれな空は時折 雪を降らす。凍りつきそうに冷たい空気の中、やや震えながら校内を回る。出会う生徒達は,明るく純真な面持ち。普段接している神奈川の高校生より、心なしか幼い雰囲気を感じる。折しも昼休み頃。全校生徒の、といっても3年生は既に卒業しているから、1・2年生が掃除にいそしんでいる。洗面所では、先生と生徒が一緒になって磨いている。そうそう、これでなくちゃあ。私は意を強くした。卓球練習場を覗いて驚く。隣接する食堂でも、校庭にいたっても、である。毎日ですか?私の問いかけに校長先生は噛締めるように「まいにち!」と。嫌がるでもなく、後輩達は明るく、掃除を楽しんでいるようでさえあった。私はイエローハットの社長さんの話を思い出す。会社を立て直すために、全社を上げてトイレ掃除に取り組んだ社長の話である。およそ経営とは関係ないようではあるが、その行為が社員の意識改革につながり、経営の建て直しに成功した。心がすさむから、と私はトイレをきれいにするよう再三言い続けている。きれいなところを汚す者は少ないが、きたないと余計に汚してしまうものである。見える処だけホースで水を流して掃除をしたように見せかけるそんなふとどき者もいる。何とも情けない話である。何のために掃除をするのか、させるのか。昨今は、子供にトイレ掃除をさせると文句をいう親もいるそうだ。掃除と勉強とは一見関係ないようだけど、実は大変関係深いものである。イエローハットの社長さんは早くにそれに気付いた。勉強だけが能ではないのだ。家庭でも、学校でも、勿論 社会でも。やがて、教室の窓越しに生徒達のシルエットが見えた。校内は静寂に包まれている。午後の授業が開始されたようであった。
2006年03月16日
コメント(4)
-
151回目の日記は百太郎さんに。
今頃気付いたが、前回の日記が150、これが151回目となるようだ。気まぐれに始め、多忙続きの昨今は、休むことが多くなってしまったけれど、いつの間にか150回も書いていたことに驚く。いつもよく訪ねる方々の日記には、驚嘆することが多く、暫し楽しませていただいた後は、どうしてこんなことができるのかと、その技と心意気と美しさに感服してしまう。ところで、今日からついに、冨嶽百太郎さんが、1ヶ月、いや、それ以上かもしれないがお休みに入るという。やはり寂しい。 でも、お気持ちは何となく理解出来る。真面目で何事にも真摯にぶつかっていかれる方だから・・ご本名が付記された日記に、そのお気持ちの深さと重さを感じる。熟慮の上でのことだと思う。またの再開を、そして「コラムDEキビダンゴ」での再会を心待ちにしている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冨嶽百太郎様 三寒四温のこの頃、今日は風の冷たさに震えました。お休みされるのですね。いつもお訪ねする度に啓示を受け、共感していました。私からのbook batom にも、貴重なお時間の中を、これ程までに詳しくご丁寧に受けて戴き恐縮の限りです。 私の処へも度々お訪ねくださり、感謝いたします。温かいメッセージは、いつも心に沁みました。有難うございました。過日のbook baton から読書歴を拝見。やはり、と重厚な内容に納得するばかりです。作家というよりも、更に奥深い思考回路を構築され、その哲学は、すでに百太郎さんお一人のものだけではなく、多くの人たちに影響を与えています。誠実で謙虚で、ものごと全てを真摯に全身で受け止められる。これでもか、これでもか・・と。熟考を重ねた上での休息でしょう。いつの日か、再び、また、「コラムDEキビダンゴ」での再会を心待ちにしています。くれぐれもご自愛を、偏にそれを祈っております。 rakusa/SAWA 拝
2006年03月07日
コメント(3)
-
いのち噴く時
いのち噴く時はその時 人知れず深く静かに沈みゐる時春は芽吹きの時。木も草も、新しい芽を出し、花を咲かせる。ものみな全ていのち噴く時である。けれども、本当のいのち噴く時はいつなのか。顔を出す前の、隠れているその時かもしれない。冬の厳しい寒さにあっても、地中にしっかりと根ざした木や草は、やがて訪れる春に備える。密やかに命を育み、力を蓄えるその長い時が、本当のいのち噴く時なのだ。機が熟し、やがて芽を出し、光を浴びて逞しく成長する。人もまたそうなのだ。夢を抱き、目標に向かって努力する。その積み重ねの日々があればこそ、やがて大輪の花も咲く。裡なる無限の可能性を信じよう。たとえ挫折に出合っても、めげることはない。沈潜の時をどう生かすか、それに全てがかかっていよう。挫折を嘆くなかれ、いのち噴くその時を大切に過ごせ、若者よ!
2006年02月21日
コメント(6)
-
ああ、 1日が26時間であったなら・・
1ヶ月振りの更新。 体調をくずしているのでは・・と。ご心配をお掛けしたようで心苦しい。お蔭さまで、身体は元気です。高熱の流感患者の看病をしても、風邪を貰うこともなく逞しく跳ね返し、電車の中の読書は、専らは睡眠不足を補うことにして、いえ、補う羽目となり・・・だからでしょうか、身体は至って元気!多忙ながら新しい創作への意欲も枯渇することはなく、春本番になれば、また更に加速か・・願わくは、一日の時間をせめて26時間に、などと叶わぬことを口にしながらも、今月初めは大阪に。「書の甲子園」とその授賞式に出席。一年ぶりの梅田で乾杯。3月には愛媛の母校を訪ね、月末には奈良への予定が組まれている。どれも観光とは程遠いけれど、私の仕事は趣味のひとつ。幸いなるかな、である。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・皆様、いつもご訪問有難うございます。写真を駆使しようとデジカメを求めましたが、未だアップには至りません。でも、そのうちに・・したいですね!
2006年02月21日
コメント(6)
-
「志は高く、ハードルは少しづつ高く」青春時代は現在進行形!
人は、自信過剰はいけない、自分を過大評価するな、という。確かにそれは間違いではない。自信を持つのはいいが、過剰は好ましくはないのである。自信過剰になった時、それは堕落への道を歩むことになり、前進への道は閉ざされる。怖いことであり、戒めなければならない。常に、いやせめて時々は、謙虚に自分を見つめる厳しい目を持ちたいものである。けれども、自分のことを過小評価するのもどうだろう。「私なんか、私なんか・」と言って、知らず知らずのうちに、自分の可能性をどんどん潰していく人がいる。こんなにつまらないことはない。「私なんか」と言う癖のある人は、一度「私にも」と言ってみるといい。「私にも出来ますか」「私にも出来るかもしれない」「私にも出来るだろう」という言葉に繋がり、それは、「私にも出来るに違いない」「私にもきっと出来る」と変化していく。更にそれは、「したい」「しよう」という、「目標」を見定めた、より積極的で能動的な意思と行動に結びつき、未来に夢を抱く、若々しい精神に包まれた身体になりはしないだろうか。大いなる夢を抱こう。志は高いほどよい。そしてその夢に向かう目標を決め、コツコツと楽しみながら、少しづつちょっとだけ頑張ればいい。三段跳びは苦しく難しくても、一つ一つのハードルなら飛び越していけるかもしれない。その高さは、気付くと自然に少しづつ高くなっている。段々高くしていくことが、倦むことなく、興味や喜びを増して次への新しいエネルギーに結びつくことにもなるのである。人間の知的好奇心は、その人の能力よりやや高い所において一番活発に働くらしい。そして、新しい好奇心や夢に向かって積極的に生きていく時、心も身体も活性化する。気持ちの持ち方ひとつで生き生きと暮らしていけるのである。私の青春時代は今も現在進行形である。皆さんも《生涯青春・生涯現役》を目指しましょう。志を高く、ハードルを少しづつ高くして。
2006年01月23日
コメント(4)
-
詩に興り 礼に立ち 楽に成る (論語)
冬ばれ。冷たい風を切って駅に向かう。満員電車に飛び乗り・・今日も一日が始まる。川沿いの道を、犬を連れて散歩する人、土手の上の小道を急ぐ自転車、背中にはバックパックが見える。車窓にみる朝の風景に、なぜか泰治の画を思い出す。今日は立ちんぼウなので、いい筋トレになりそう。カシャカシャ カシャカシャ・・何とも騒がしい音が背後から聴こえる。否応なく耳につくが、ヘッドフォンから洩れる音がこんなに大きいとは。この坊やは、さぞかし大音響で音楽を楽しんでいるのだろう。公共の場を、自室と錯覚してしまったらしい。注意するのも、お願いするのも面倒臭くなって、人を掻き分けながら移動した。やれやれ、これで静かになった。メールで仕事の連絡を2件、ご無沙汰のお詫びを友人に2件、携帯も使いこなせば便利この上ない。再び車窓を見ながら思索を廻らす。今日は不思議と本を開く気にはならない。懸案のことをどう処理するか・・あれこれと思いを廻らすうちに目的の駅に到着した。詩に興り、礼に立ち、楽を成す。論語の一節だが、書を読み、学問を積み、人の社会生活には欠かすことの出来ない礼を重んじ、その礼を身に付けることで、人としての骨格も出来るというものだろうか。孔子さまは「楽」を重んじられたが、音楽を代表する趣味教養が人に厚みを加え、円熟味を具えることになるのだろう。再び、「詩に興り、礼に立ち、楽を成す」今年もいい年でありますように、精進あるのみ。
2006年01月12日
コメント(13)
-
初空の雲居にのせむ夢ひとつ
あけましておめでとうございます。今年も皆様にとって佳い年でありますように。新年を寿ぎ、皆様のご健祥をお祈り申し上げます。世界中の子供達が平和に包まれた、夢多き日々を送れますように!核廃絶と恒久の世界平和を!その実現を希求します。・・・・・・・・・・・・・・十分な年越しの用意をすることもなく、慌しいうちに2005年が過ぎてしまいました。こんな年越しは初めてですが。それでも、新年は矢張りいいものです。あらたまの年・・まさしくその思いを致します。改めまして、皆様、旧年中は色々お力添えを賜り、有難うございました。お蔭さまで、年末にもビッグニュースが入り、最後の最後まで本当にいい年でした。本当に感謝あるのみです。以前、葛飾北斎のことを書きましたが、彼のような名人にならずとも、生涯勉強し続けていけば、私ごときでも、少しはましな作品が書けるような気もいたします。それは永久に完成することのない、未完の作品ということになるのでしょうが、少しは満足できるような、その一点を目指して、今年も勉強したいと思っています。 初空の雲居にのせむ夢ひとつ
2006年01月01日
コメント(8)
-
喪中のはがき
師走になると、郵便物の中に、一・二通は喪中のはがきが交じって届くようになる。灰色の線で縁取られたそれを手にする度に、私は心が重くなってしまう。亡くなった方が八十歳以上であれば、天寿を全うされたのだと、些かでもほっとするが、若くして旅立たれていると、たとえ面識はなくとも胸が痛む。まして、子供を亡くされた場合など、葉書を手にしたまま唯、茫然とするのみである。輪廻転生は人の世の常であるとはいえ、子が親に先立つほど残酷なものはない。私の兄や姉も早逝し、両親は子供達を見送った。教員をいていた姉が逝った翌年、法曹界にいた兄が相次いで逝去した朝、幼い私は、母の腕の中で息が詰まりそうになりながら、号泣する母の姿を見た。そして、雄雄しく涙を見せぬ父に、男というものは悲しくても泣いてはいけないのだ、とその時初めて知った。いずれもその悲しみの大きさはいかばかりか。父と母のその悲しみようを未だ忘れることはできない。両親よりも、決して先に死んではならない、と幼いながら強く心に期したのを覚えている。幸いにも父は85で、母は90で鬼籍に入り、その心配はなくなったものの、寂しがりやの子供のためばかりでなく、私を取り巻く多くの人達のために、そして自身の仕事への執着もあってか、後数十年は生き延びたいと思うばかりである。今日もダイレクトメールなど共に、年賀欠礼の挨拶状を二通受け取った。一通目は誰が亡くなったのか記されていない。友人からのものであるが、自身の両親なのか、それとも連れ合いの身内なのか、子供は確かいなかったから・・とあれこれ心配する。もう一方のは、見慣れぬ筆跡である。怪訝に思い裏返してみる。差出人にも覚えがない。本文を読み始め、私は愕然とした。信じられない思いで何度も読み返す。何度見ても、そこには確かに友人の名前が記されてあった。それは友人の夫人からのものであった。迂闊であった。新聞の死亡通知欄も見落としたらしい。私は悪寒が走った。死亡したとある3日前、珍しく彼から電話を受けていた。その朝、依頼された仕事のために能登へ発つことになっていた私は、その旨を伝えて電話を切った。あの時、どんな用件だったのか、何を言おうとしたのか、今となっては知る由もない。いつも多忙を極め、会合も掛け持ち、秘書のスケジュールに合わせて正に東奔西走の日々であったように思う。それでも、都合がつくと個展には訪来、昔の仕事仲間の集まりでたまに顔を合わすときも、芸術の世界はいいねえ、といつもしみじみと話していた。何かにつけて金銭的な思考回路を要する現実的な生活に比して、詩だの歌だのと、文学の話がその大半を占める私の仕事がいいと言った。現実からかけ離れた、苦労知らずの夢のような世界に写ったのだろう。その実、こちらにはこちらの苦労というものがあるのだが。「今度ゆっくりお酒でも飲みましょう」というのが口癖だった。アメリカのC大学の講習会や、パリのホテルでの研修旅行には、生徒を引率して毎年出向き、一年のうち、四、五回は海外出張があったらしい。が、今度ばかりは、二度と再び戻ることのない国に旅立ってしまった。ゆっくりお酒でも、と誘われることも永久になくなった訳である。もしかしたら、あの電話は、旅立ちを予期した、彼の最期の別れの挨拶であったのかもしれない。そういえば、いつもの言葉は聞かれなかった。
2005年12月20日
コメント(3)
-
「これからの教育」を考え発信しよう。
次代を担う子供達への教育について考え、模索し、実践している人が増えている。昨今の社会事情を考えると当然なことと思う。市民レベルで考え、活動を広げていくことが、やがて社会を変える大きな力となるだろう。漣が大きなうねりとなることを願ってささやかでも実践を積み重ねていきたいものだ。懐古趣味で物申す訳ではない。かつての日本に存在した素晴らしいものが、いつの間にか影が薄れ、そして見る影もなく消えていった。礼儀作法ひとつ挙げてもそう言えよう。近年は、「儒教の国」韓国ですら、その影は薄くなりつつあるらしいが。人を教え育てる、という「教育」の根本は何なのか、歯の一つ一つに歯こぼれや変形が見られる頃から、歯車の回転に狂いが生じた。その正常な働きをしない狂った歯車で編み出されるものは、当然、正常な働きを生み出さない。その中で創られかものが正常である訳はないだろう。いびつなものがいびつなものを生み出し、更に歪んだものを編み出していく。何処かでその回転を変えなければならない。その為には、一人一人そのことに気付き、声をあげ、その声を大きくすることであり、それを纏めて大きな力に変えていくことであろう。気付いたことを話し合ううちに、その底流に潜む多くの問題点が浮き彫りになるだろう。大きなうねりも、漣からなるのである。一人一人のささやかな活動こそ大切なのだ。あちこちで声をあげよう。そういう活動が活発になればいい。家庭から、グループから、そして社会へと、その輪の大きくなることを願う。私もその一人である。
2005年12月03日
コメント(6)
-
「巣立ち」・・めでたくもありめでたくもなし?
11月最後の日曜日、私は都内屈指のホテルに出かけた。教え子の結婚披露宴に出席するためである。いつだったか、彼女のことを書いたことはあったが、幼児の頃から書熟に通ってきた生徒である。その彼女が白無垢の打ちかけに角隠しの花嫁姿で迎えてくれた。席に案内されると、私のテーブルには既にお絞りと水の用意がしてあった。さすが、一流ホテル!その細やかな心配りに感心する。普段から話すことに馴れている私は、スピーチを依頼されることが少なくない。この日も例外ではなかった。が、その日は何故か口が渇く。いつになく緊張していたのかもしれない。何度か、喉というより口を湿らせるために私は水を含んだ。これが、サービスなのだ。その他、一事が万事という言葉どおり、終始細やかな配慮の行き届いた心配りにもてなされ、飛び切りのフレンチと共に、心豊かな気分に浸らせて戴いた。終始、明るく、こぼれるほどの笑顔の新郎新婦、一抹の寂しさを漂わせるのは、やはり新婦の父親。娘を嫁がせた経験のある私には、そのお気持ちを察することも出来る。花嫁の親、とりわけ父親にとっては些か残酷なものでもある。「巣立ち」などというものは、めでたくもありめでたくもなし、とも言えようか。だが、大抵はいつの時も、子供には無条件で無償の愛を施す、それが、「親」でもある。
2005年12月02日
コメント(2)
-
「書の甲子園」で文部科学大臣賞! 団体全国準優勝!
第14回国際高校生選抜書展(書の甲子園)で、神奈川県立城山高校が全国準優勝、小谷さんが文部科学大臣奨励賞を受賞。書の甲子園には第1回から参加する常連校。熱気溢れる「書の甲子園」(国際高校生選抜書展)には、全国からだけでなく、海外からも、多くの精鋭作品が集う。11月22日全国一斉に授賞者が発表された。10月に内定通知が届き、校内は驚きと喜びに包まれながらも、発表できぬ辛さにも耐え、HPへのアップも控えたが、中には、話題としての他校のテレビ放映もあったようだ。ごく普通の学校で、ごく普通の活動をして、こんなにも大きな金的を射止めた生徒達、信じられぬ面持ちは私とて同じだった。もう二度とないから・・そんな言葉が飛び交うことが、それを証明していよう。戸惑いながらも、沸き立つように新聞社の取材を受けた生徒達の、嬉しそうな、恥ずかしそうな顔が紙上に並んだ。過去には準大賞も確か5度、優秀賞は10人位、秀作や入選を加えて、例年、団体地区優秀賞の常連校とはなっていたものの、いたって普通の学校の、普通の生徒達である。一度は「大賞」を受賞させたい、と思いながらも、その実力から、夢は夢で終るかも・・と諦めの境地もあり、それでも、全力を出し切ろうと励ます。努力しても、その努力が実るとは限らない。実る保証などないのである。でも、努力をしなければ、その可能性は皆無といえる。だから、ひとつひとつの積み重ねこそ大事なのだ、と。私はいつもそう話している。多忙な年越しも、今年は嬉しさと寂しさが混在する。2月になれば、大阪市立美術館の壁面に生徒達の力作が輝くだろうし、緊張しすぎて挨拶さえ忘れそうになる生徒達が、どんな顔して授賞式に臨むのか・・それもまた楽しみでもある。が、ひとつだけ寂しさも待っている。生徒達が贈ってくれたこの最高の花道を、私はどんな顔で歩けるだろうか。幸せの鳥となって飛び立つことも出来ようが、私には、矢張り、一歩一歩踏みしめて歩くことが似合っているだろう。有難う! 生徒達! よくやったね!♪!♪
2005年11月25日
コメント(4)
-
陰翳礼讃・・南禅寺 (続)
参道を横にそれて石段を数段登った。拝観料を払い、くぐり戸を抜ける。そこにはまだ静寂があった。廊下越しに見る薄暗い部屋の襖には達磨絵が配され、床の間の軸も禅僧らしきもので、どちらも室町時代風。山を拝した日本庭園は、造られたものというよりは、自然のままの趣である。地下水が集められて山から一筋の小川が流れ、水はちょろちょろと音をたてて池に注ぎ込む。鯉はときおり水を弾きながら群れ泳いでいる。庭のそこここに草が生えているのも嬉しかった。紅葉した楓の下をくぐり、池に沿って獣道のような遊歩道を歩く。紅葉した樹木と常緑樹とが混在し、そのコントラストがいい。幾条かの木漏れ日を浴びるだけの熊笹も羊歯も、苔もその生を謳歌していた。暫くして、私は思わず立ち止まった。それは、幽玄の世界を見るようであった。青々と繁る青木の傍に、紛れもなく真っ白い葉をつけた一本の木が生えている。私は自分の目を疑った。ほの暗い林の中で、そこだけがぼうっと明るく見える。白い葉は朴のように大きく、葉脈がくっきり透けて見えた。落葉する前の、幽かに生にしがみついている姿なのかも知れない。その木の下にはまだそれらしき落葉はなかった。「不気味ですね」振り向くと、深いグリーン色のジャケットを着た白髪まじりの男が立っていた。「死人を見るようですね。僕はあまりすきじゃないな」クリーニングの利いた白い Yシャツを着て、襟元には茶系のアスコットタイが覗く。ズボンはセピア色を少し薄くしたような色で、もう少し無造作に着こなした方がいいのに、私はそう思いながら道を譲った。「お好きですか?寺は。 随分ゆっくりご覧になって」「ええ、心が落ち着きますから」私の前を通り抜けながら尋ねる男に、私はぶっきら棒に、そして呟くように応えた。男は、少し不自由な左足をかばいながらも、確かな足取りで去っていった。再び参道に戻ったとき、日は、残された僅かの時間を惜しげもなく降り注ぎ、逆光に浮かぶ紅葉は、複雑な光の屈折の中で、ひときわ私の目を釘付けにした。光を浴びた葉の裏は透けるような赤となり、そこに陰も加わる。明度の微妙に異なる幾種類かの赤と黒とが交錯する。光と影が織り成すその自然の芸術を、どう言い得ようか。参道を登って来る時、私は日を浴びた鮮やかな紅葉に、思わず感動と驚愕の声を漏らした。しかし今、夕日に向かって佇ち、目にする木々のなんと美しいことか。光が美しさを引き出すように、陰もまた、更なる美を演出してくれる。古くからの、日本家屋の設え(しつらえ)がそうであったように。
2005年11月16日
コメント(4)
-
「陰翳礼賛」・・・南禅寺
ホテルを出て坂を下る。信号を越えてリンクライン(琵琶湖疎水)に沿って歩いた。岸の蔦の葉はすっかり紅葉している。昔、舟を運んだという名残か、半分朽ちかけた舟が一艘トロッコに乗せて置かれてあった。勢いよく流れる疎水を橋の下に見遣り、南禅寺の参道に入る。日曜日とあって観光客は多い。道の片側には駐車場からあふれた車の列が続く。その間を縫うようにして大型観光バスがのろのろと走る。両側には湯豆腐を食べさせてくれる店が並び、辛抱強く順番を待つ人がどこの店先にも群れている。ここに来ると名物の湯豆腐を食べたくなるらしい。なだらかな砂利道を通り山門に出る。瓦葺の大屋根は、何度かの補修を受けたとしても、何百年かの風雪に耐えたであろう太いしっかりした柱に支えられていた。その姿は、何者をも寄せ付けぬ近寄り難い厳しさと、何もかも抱きかかえ包み込んでくれそうな、大きくて温かい寛容さを合わせ持っていた。初冬の空に、風鐸は静かにぶら下がっている、私は三好達治の詩を思った。 あはれ花びらながれ/ おみなごに花びらながれ おみなごしめやかに語らひあゆみ・・風鐸の姿静かなれど・・もう喧騒も気にはならなかった。私は暮れかかる初冬の空に吸われていた。「記念写真どうどす?」男が声をかけた。傍らに三脚が置かれ、宣伝用のスタンド写真が数葉飾られている。苦笑しながら、私はその場を離れた。参道を横にそれて石段を数段登った。拝観料を払い、くぐり戸を抜ける。そこにはまだ静寂があった。(続く)
2005年11月12日
コメント(3)
-
「風のさやぎ」
・わが裡の磁石の針は故郷の西を指しをり コスモスの咲く・死に近き義父の笑顔に心置く 車窓に櫨(はぜ)は紅く燃えをり・秋の葉の風のさやぎを聴きしとき ツルゲーネフは甦りくる・交々の憂いは闇をつらぬくか 幽かなる火はまだ裡に秘む・秋深し 京の高雄に照る紅葉 鳥獣戯画の高山寺はも
2005年11月08日
コメント(1)
-
大いなる未来を信じて・・その試練は君を大きく成長させてくれるから。
「いいましたっ!」「死ねとは言いませんが、死ねるものなら死んで来い、といいましたっ」穏やかならぬ言葉である。菊名で東横線から横浜線に乗り換え、空席を一つ見つけて腰を下ろしたばかりの私は、ただならぬ様子の女子高生に目は釘付けとなった。右手で握り占めた携帯電話を耳に押し当て、こちらから、彼女の頭のてっぺんが見えるほど前かがみになっている。おまけに学生鞄にはぽたぽたと涙が落ちているではないか。鼻水も垂れて、どう見ても尋常ではないのである。それに、高校生の下校時間にしては少し早い。きっと友達との諍いなのだろう彼女が電話を切るとまた直ぐに掛かってきた。どうやら同じ人からのようだ。前より増して激しく泣き出し、今度は、通路を隔てた私にも嗚咽が聞こえるようになった。彼女は、左手で鞄を開き、タオルのハンカチを取り出すと、器用に学生鞄の蓋を閉めて涙を拭き、そのままタオルに顔を埋めて泣き続けた。右手に携帯、左手にタオル、そのどちらもしっかりと握り締めている。突然 彼女の声が聴こえてきた。「先生が、教師がそんなこと言っていいんですか・・」彼女は教師と話していたのだ。「いいましたっ!」「死ねとは言いませんが、死ねるものなら死んで来いといいましたっ」一体何があったというのか。尋常ではない。私は直ぐにでも傍に行って、女子高生を抱きしめてやりたくなった。教師が生徒に、しかも携帯電話で何を話しているのか。この様子では、生徒指導というよりは、お互いに感情的になった者同士の諍いに見える。教師も人間ではあるけれども、少なくとも生徒に対峙した時には、どんなときでも、感情的になることを極力慎むべきであろう。生徒に向き合い、表情を確かめながら、話を聞いてやることが先ではないのか。自分の言いたい事は、話をするのはその後である。ましてや、先の「・・死んで来い」のことばは言語道断である。その教師には、指導力も、生徒への愛情のかけらも感じることは出来ない。彼女の学生鞄に付けられたマークと制服が学校名を教えてくれる。横浜市内にある私学である。中学から進学する時の選考基準ともいわれる、いわゆる偏差値なるものは、決して低い方ではない学校である。その学校で、この女の子に何があったというのだろうか。思い煩いながらも、私はただ、その子を見詰めるしかなく、十日市場の駅で彼女が下車するときも、何ひとつ言葉をかけることは出来なかった。大いなる未来を信じ、逞しく生きて欲しい。その試練は、君を大きく成長させてくれるから。私は祈るような思いで制服を見送るだけであった。
2005年11月04日
コメント(6)
-
申し訳ない程度??
「蟹は申し訳ない程度に入っている」蟹ちらしずしを食べていた三十代の人が言った。それを言うなら、「申し訳ない程度」ではなく、「蟹は申し訳程度に入っている」であろう。彼女曰く、申し訳ない、と謝る意があるのかと思った、と。そう言われるとそれでもいいような気がしないでもないが、決してそうではなく、「言い訳や申し開きが出来る程度」転じて「形ばかり」という意味であるから、先の言葉は矢張り、「蟹は申し訳程度に入っている」となり、「申し訳ない」とないをつけるのは誤用となる。辞書を引いてみると、『広辞苑』(岩波)では、・もうし わけ「申分・申訳」・・・いいわけ。いいひらき。 『国語大辞典』(学研) ・もうし・わけ(申し訳)・・「言いわけ」の謙譲語。言い開き。弁解。 (略) 〔申訳無い〕言い訳のしようがない。たいへんすまない。(略) 〔もうしわけ許り〕<連語>ほんのかたちばかり。ほんの少し。 近年こういう誤用が増えてきた。時代と共に「ことば」は変化していくものだ、とは言いながらも、やはり気になるものである。
2005年11月03日
コメント(2)
-
「能登往還」
・金沢を和倉を過ぎていつしかに地方訛の声心地よき・女生徒のいと素朴なる横顔を茜に染めて汽車は走れる・街の灯は魚津あたりか海に浮く 七尾の海に月影も冴え・来世か過去世か現世の縁かと暮れ果つ海に潮鳴りを聴く・奥能登に雨降りしきる 兵の塚詣でむと訪ねけらしも・眼閉じ宇出津(うしつ)の海の遠鳴りを聴きて思ほゆ都落ち人・行く秋を惜しみて時雨る羽根駅に佇ちし我はも 鳶(とんび)しば啼く・野の花を摘みつつ行かな 武士(もののふ)の夢まぼろしか古君(ふるきみ)の里・古君の原にすすきの穂波揺れ 刈田の畦に草紅葉燃ゆ・時空超へ石塔は何語るべし 遠つ神祖(かむおや)を訪ねし人に・はろばろと遠つ神祖を訪ね来し その人の背を濡らす秋雨・奥能登の峠越ゆれば日本海 怒涛逆巻く越前の海・北海の怒涛は我に迫り来る滾つ(たぎつ)心の堰を切るがに・荒海や 逆白波(さかしらなみ)の砕け散る 能登は夕焼 秋暮れむとす・神主も人間ならむ 装束を脱げば現世のことばとなりて・旅人の群るる輪島の朝市の客呼ぶ老婆の皺の深さよ・骨董の店の戸棚に潜みゐる蒔絵の椀は誰が使ひしか・奥能登の入江に鷺の一羽二羽 烏賊釣り船のランプ寂しも・穴水の入江に舫ふ(もやう)帆船のマストは高き秋天を衝く・鵲(かささぎ)の何啄ばむか 奥能登の夕日に向かふ我は旅人・没落を美しきものと言ひくれしそが言の葉の甦りけり・人とふはなべて優しき心根の持ちけるからに苦しみの満つ
2005年10月27日
コメント(6)
-
四季の彩にも似たエールを受けて人はみな明日に繋いでいく。
久し振りに高校の同窓会に出掛ける。仕事のために30分遅れて水道橋の会場に合流した。着いたときは既に宴たけなわ、懐かしい皆の顔が紅潮している。遠く四国を離れて関東に生活の拠点を置く人達ばかりの集いである。今年初参加の人が3人もいる。思わず、あの方だあれ? と35年振りに会う人の名を尋ねて笑われてしまった。記憶力など当てにならないものである。頭の中で、詰襟の学生服を着せてみようとしても、若い顔立ちに直そうとしても、私の脳細胞だけでは記憶を呼び覚ますことが出来なかった。いつの間にか、一人一人の挨拶にも解説をつけて進行役を務めるI、お洒落が嵩じてか、アパレル会社の社長になって頑張っているS、いつ会っても駄々っ子のようで憎めないM,“気は優しくて力持ち”誠実で頼もしく、剣道に加えて少林寺の達人にもなったY、甲斐甲斐しく皆の世話を焼き、終始こまごまと気配りをする、まるで私達のお姉さんのようなYの奥方のIY、学生時代から美人で人気者の、富士の裾野でルームアクセサリー店を営むE、娘の結婚相手を心配するT、人材派遣業で頑張ってるS、などなど。それぞれの顔にはその人の人生が現れていた。高校卒業して数十年という長い間に、大病をして人生観の変わった人もいれば、順風満帆の人もいて、話す内容も話し振りも人生そのものである。一年間の猛勉強をして見事「宅建」の資格を取得した不動産業を営むMなどは、「これで主人がどうかなっても家業は大丈夫ですので・・」とユーモアたっぷりのスピーチで喝采を浴びた。私はといえば、人生を楽しんでいます、などと言い、「うまいこと言うなあ、誰に教わった?」と野次られる始末。前向きに生きてる人は、目の輝きが違うね、と嬉しいことを言ってくれたのは35年振りに再会したK、何事にも真面目に取り組む姿勢は今もって変わりなく、噛みしめるようなに話し方が懐かしかった。宴たけて多弁となりし我等みな 少年少女となりて輝く同じ故郷を持つ者の集まりは楽しい。首都圏に住み古り、「おれはサ、そう言ったけどサ・・」とすっかり東京弁を操るようになったHだって、そのアクセントの違いは時として隠せない。わざと方言を飛ばして笑いをかう者もいるが、「ほんじゃきんどナア」 (※そんなこといっても、だけど、などの逆接)などという懐かしいふるさとの言葉を聞こうものなら、もう一気に30年も40年も前に引き戻されてしまうのである。たとえ見ず知らずの初対面でさえ、関西方面のアクセントを聞き逃すことはなく、耳さとく聴き取ると、急にその人に親しみを感じる。四国出身の人でもいようものなら、旧知に出会ったような気さえする。あちこち旅行をして素晴らしい景色に出合っても、瀬戸内の夕日を忘れることはない。新幹線を降り、岡山で宇野線に乗り換える。今は瀬戸大橋線となったが、その大橋を渡ると四国である。郷里に入る前に、真っ先に瀬戸の海が出迎えてくれる。大小無数の島が、行き交う漁船が、そして優しく穏やかな海が、私をいつでも歓迎してくれるのである。富士も冠雪。木々の色付きも近いだろう。巡り来る美しい四季の彩にも似た、多くの人達のエールを受けて人はみな明日に繋いでゆく。
2005年10月14日
コメント(6)
-
母の手紙
木犀の香に思わず足を止めた。通い馴れた道だから、それが何処から漂ってくるのかすぐ判る。月明かりを受け、艶やかな葉が浮かんで見える。もうそんな季節なのだ。気忙しく通り過ぎることの何と多かったことか。私はもう久しく母の手紙を受け取っていない。丹精の花々のことが克明に記された便りは、遠く離れている私にも、母の生活や庭の様子、そして天候さえも手に取るように伝えてくれる。明治の人らしく、文字が途中で乱れることもなければ、自分の娘に宛てたものでさえも、丁寧な言葉で結ぶ。母は、片道5キロの山道を越えて高等女学校に通った。裁縫よりも読書を好み、袴でテニスに興ずる、どちらかといえば、進歩的な女性であったらしい。それでも、戦後の一時期には仕立物をし、私が高校の時などは、家庭科の裁縫の宿題まで手伝わされることもあった。が、娘のパジャマを半分以上縫わされる羽目になった私を見れば、母は、「歴史は繰り返すのねえ・・」と嘆くかもしれない。秋には少し膨らんだ封書が届いた。中には決まって、懐紙に包まれた金木犀の花が入っている。黄色の可憐な花は、懐紙をうっすらと滲ませ、香をほんのかすかに残すだけとなった、乾涸びた哀れな姿ではあったけれども、添えられた母の短歌と共に、否応なく私を故郷の思い出に浸らせてくれた。薄茶色の染みがいとおしく、飛び散りそうなそれを掌にやさしく包み込み、私は目を閉じて残り香を楽しんだ。故郷を後にする時、花の季節は終り、葉だけがこんもりと繁っていた。今、生家の花も盛りに違いない。惜しげもなく辺りに芳香を撒き散らす花を見上げながら、出来ることなら手折って母の仏前に供えたいと思った。
2005年10月12日
コメント(5)
-
志賀島紀行 「唐国(からくに)の波」 (完)
海岸線に沿って砂浜が広がり、少し高い所に芝生の緑の帯が長く伸びる。今まで見たこともない、一抱えもありそうな、いやそれ以上の、アレカヤシの大株のような樹木が数株、一定の距離を空けて植えられてあった。何という樹なのか、ピンポン玉ほどのオレンジ色の実を無数に着け、白っぽい葉を風にそよがせ、いやでも南国の情緒を醸す。金印のことを忘れて、リゾート地を訪れたような気分に浸った。この島にこんな素敵な所があったとは。私はこの朝ホテルの玄関から乗った、タクシーの運転手の言葉を思い出した。「博多埠頭、志賀島行の船乗り場まで・・」私が告げると、彼はいきなり語気荒く言った。「お客さん、なんで志賀島へ行くとね。なアンもなかですとよ」「・・・・・」「金印かなんか知らんけど、つまらんとこですたい。そりゃあ行けと言われれば行きますばってん、仕事ですから。そいでん、街の方がずっとよか。なんぼでん行くとこあるでっしょ。シーガイヤーとか・・」まあよく喋る男である。私は苦笑するばかりで返す言葉もなかった。運転手は更に続けて言った。「特別金印に興味があえるという変りもんというか・・特別な人は別でっしょうが・・海の中道ならよかですばってん。あそこんには大きい公園があって、レジャーランドになって・・」私は変わり者とも思わないが、レジャーランドに興味はなかった。金印を訪ねようと思い立ち、仕事を終えて羽田から空路福岡入りをしたのである。暮れ残る福岡上空から志賀島の全景が眺められた。当然ながら地図と同じ形の島影を見下ろし、金印への思いを膨らませていた。海の中道も、そこに建つホテルも、雁の巣砂丘もはっきりと見えた。時間があれば、あの砂丘にも行ってみたい。運転手が何と言おうと、その為に博多へやって来たのだから。黙っている私に、その心を推し量ってか、彼はもう行くなとは言わなくなった。祝日とあって往来の車はさほど多くはない。タクシーの窓から見る限り、ビルが林立した街は東京や横浜と大して変わりなかった。ただ、聳える椰子の樹に、南の国に来た実感を覚えるだけである。波打際まで出ると風は思いの外強かった。芝生や砂浜の上で、人々は思い思いに寛いでいる。私も芝生に足を投げ出した。秋天は高く澄み渡り、一片の雲すらない。この分だと素晴らしい夕日を拝めるだろう。沖合いに浮かぶ玄海島の方を眺めた。海辺のレストランで、ウエイターが教えてくれた日没の方角である。日はまだ高い。サンセットショーまで2時間近くあった。果てしなく広い海は、繰り返し繰り返し波を寄せてくる。金印を携えた使者達もこの波を越えて帰ってきたのだ。それにしても、この小さな島に、どうして金印は埋もれていたのだろうか。私の疑問は何ひとつ解明されなかったけれども、金印の眠っていたこの島に入っただけでも満たされた思いはあった。歴史の解明は研究者に任せよう。古のロマンを秘めた私の金印物語を創ってみたら、それもまた楽しいのではあるまいか。光武帝はなくなる僅か2ヶ月前に、倭国の使者と何を話したのだろうか。唐国の波に乗ってきた金印は・・そして卑弥呼は・・規則正しく届く潮騒の音を耳にしながら古代史を思い、沖を眺めた。この波の果てにかの国はあるのか。繰り返し繰り返し寄せてくる波の音は、私をかの国に、金印のふるさと唐国へ誘う調べのように心地よく響いた。夕暮の風は冷気を帯び、更に強く吹き付けてきた。私の髪は先ほどからずっと狂ったようにはね続けている。着てくるべきであった。身をすくめながら、ジャケットをホテルに残してきたことを悔い、スカーフを取り出して首に巻きつけた。いつの間にか黒ずんだ海には、無数の光の胞子が散りばめられ、弾ける音が聴こえてくるように輝きを放つ。そして太陽は、しだいに膨らんできた柔らかな雲に包まれるようにして水平線の彼方に消え、やがて錦の帯も黒い海に飲まれていった。(完)・・・・・・・・・・・長文にお付き合いくださって有難うございました。志賀島紀行「唐国の波」は、これにて終了です。多謝!
2005年10月09日
コメント(3)
-
「玄界灘」・・・志賀島紀行「唐国の波 8」
再びバスに乗って国民休暇村まで戻り、海辺のレストランに入った。視界180度すべて海、一面に広がる玄界灘である。風除けかそれとも波を避けるためか、コンクリートで固められた頑丈そうなテラスが、かなり広いスペースで設けられている。それでも、台風の時などは、波が覆いかぶさるように窓際まで襲ってくるに違いない。閉ざされた窓越しに、穏やかな潮騒の音が届く。ウィンザータイプの木製の椅子に深く腰を下ろし、漸くありつける遅い昼食のために、メニューを開いた。私は名前につられて松花堂の「玄海」を選び、グラスワインを併せて注文した。料理の味も悪くはないが、ここでは、何といっても、窓の外に広がる景色がご馳走である。遥か沖合いの天地を分かつ一本の線は、真っ直ぐなようでいて直線ではなく、緩やかな曲線となって左右の端が下がっている。障害物など何もなく、小さい島が一つ浮かんでいるだけで、見霽かす水平線は地球の丸いことを実感させてくれた。・・・・・・・・・・・玄界灘を渡ってきた引き揚げ船は、接岸することが出来ず沖合いに碇泊した。本土に上陸するためには、小さな船に乗り換えなければならない。波が高く、その小さな船は、波に乗り上げたまま大きく上下する。人々は、船が下がった時に着地できるよう、具合を確かめつつ意を決して飛び降りねばならない。それがどんなに怖いことか、人々の顔がそれを伝える。冬の玄界灘の波の高さがどれほどのものであったか、それは想像に難くない。子供達は、碇泊した船の甲板から、一人づつ木の葉のように揺れる船をめがけて投げ落とされる。一足早く飛び降りて乗り移った男達は、引き揚げ船に乗り合わせたというだけの、見ず知らずの、その子供達を一人一人抱留める役目を果たす。投げ落とす親達も、彼らを信頼して子を託すのである。彼らには互いに、命からがら祖国に引き揚げてきた同胞の日本人という、強い連帯感が存在していたのだろう。何万何十万の人々が越えてきた海、そんな歴史をも飲み込んできた玄界灘である。今、一人で眺めているこの玄界灘を、私はいとおしく思えてならなかった。(後略)「唐国の波」へ続く
2005年10月05日
コメント(2)
-
「終 点」・・・・志賀島紀行「唐国の波 7」
終点1時間余りの後、漸く勝馬行のバスがやって来た。島の突端まで行けば何かに出合えるかもしれない。小さな期待を抱いてバスに乗った。玄界灘の夕日を見たい、そんな思いもあったのである。20分程で国民休暇村に着くと、乗客の殆どは下車した。残るは3人だけである。海沿いの、人家らしきも見当たらない道を曲がりくねるうちに、私は不安に駆られて乗客の一人に尋ねた。「終点には何かありますか?」「僕達も初めてなので分からないんですよ。兎に角行ってみようと思って」応えた後、彼は地図を広げたまあ何とかなるだろう。駄目なら引き返せばいいんだから。そう思ってシートに身体を埋めた。やがてバスは海岸線から外れて田圃の中を走った。行く手の山間に小さな集落が見える。大きな瓦屋根は寺に違いない。暫くしてひっそりしたガソリンスタンドの前でバスは止まった。終点である。やっぱり引き返した方が良さそうである。運転手に折り返しのバスの時刻を確かめてから私はバスを降りた。「歩いていけばヨカトニ」「ここをまあっすぐ行けば10分程で行けるト」「バスなんかに乗ることナカトニ」バス停の傍に居合わせた主婦は口々に言うが、私は到底歩く気にはなれなかった。一緒に降りた学生らしきは、もう山の方に向かって歩き始めている。麓の寺にでも行ってみるつもりなのだろうか。時計はもうすぐ3時を指そうとしている。博多を出てから既に5時間、私は些か疲れていた。漸く出合った自動販売機に硬貨を落とし込む。ガチャンという音を立ててジュースが飛び出してきた。砂に水が音もなく沁みていくように、冷たいジュースは、私の乾いた喉を潤し、空っぽの胃袋に沁み込んでいった。 [玄界灘」へ続く
2005年10月04日
コメント(2)
-
「続・友誼の歌」・・・志賀島紀行「唐国の波 6」
「続 友誼の歌」私は十三、四年も前に訪れた中国を思い出した。たしか玄宗皇帝と楊貴妃との避暑地の宮殿跡、華清池であった。公園となったその一隅に郭沫若(かくまつじゃく)の碑があったのである。三文字か四文字からなるそれは何と書いてあったのか、既に記憶はない。その時私は、気品のある筆跡に魅せられて、雨の中で濡れるのも厭わず佇んで眺めた。集合時間に遅れるから、と連れに促されてしぶしぶ立ち去ったのを覚えている。文化革命の試練を経た後に、初めて郭沫若が世に問うた名著『李白と杜甫』(人民文学出版社)の邦訳(講談社刊)は我家の書棚にも並ぶ。従来とは少しく異なる李白像と杜甫像を打ち立て、それを検証していったその本を、私は興味深く読んだ。詩人であり能筆でも知られる彼の手になる碑、期せずして出合った郭沫若の碑に、私は何か嬉しく懐かしい思いに満たされていった。次のバスまでには大分間があった。乾いた喉を潤したいのに、せっかく据えられているジュースの自動販売機は働いていない。やっと飲み物にありつけると、ほっとして歩み寄ったのに、人に期待を持たせて・・これは一種の詐欺ではないのか。機能しないのならさっさと片付けて欲しい、と思う。空腹は人を怒りっぽくさせるようだ。そんなことさえ何となく腹立たしくなる。こんなことなら、あそこで昼食を済ませてくればよかった。紺地に染め抜いた食事処の「のぼり」を思い出す。が、引き返す元気とてない。今となってはもうバスを待つしかないだろう。いか焼きも、ビールも、一滴の水さえも諦め、思い直して竹林の日陰に腰を下ろして大きく息を吸った。このまま午睡を楽しむのも悪くはない。そう思った時、どこからか一匹のスズメバチが飛来し、頭の上を旋回すると、また何処かへ飛び去っていった。規則正しく潮騒の音が聞こえてくる。潮はもう大分満ちているに違いない。(続
2005年10月02日
コメント(1)
-
続 「方形の謎」・「友誼jの歌」・・志賀島紀行「唐国の波」(5)
天明4年、当時の学問所の館長で町医者出身の儒学者 亀井南冥は、その就任わずか4日後であったにもかかわらず、金印が発見された時には、いちはやく後漢の光武帝が授与されたものだ、と「金印弁」に発表したらしい。「祖先が漢の属国になるはずがない」とか、「鋳つぶして武具の飾りにでも」という過激な声が周囲から出たとき、南冥は、百両出して買い取ってでも金印を守ろうとしたそうである。黒田家からの委託を受けて、金印が、今日なお博物館に無事保管され続けているのは、彼の功績ともいえるだろう。しかしその彼は、8年の館長在任後70歳で没するまでの間、ちょっとしたことがもとで大宰府に蟄居(ちっきょ)する羽目となり、恵まれない晩年を過ごしたようである。金印の輝きとは余りにも対照的で気の毒な思いがする。「友誼の歌」2,35センチの小さな方形の中に秘められた、まだ解き明かされていない金印の謎を思う。博多湾とその海に浮かぶ能古島(のこのしま)を臨み、林を渡る心地よい風に暫し疲れを癒した。家族連れ、グループなど、休日とあって来訪者も結構多い。四阿(あずまや)では初老の男性がスケッチをしている。海に向かって腰を下ろし、時々能古島の方角を眺めているから、多分その島を描いているのだろう。公園の竹林も近景に入っているのだろうか。暫くすると、一際声の高い婦人達が石段を登ってきた。制服姿のタクシーの運転手らしき人の解説を時々頷きながら聞き、印影のレリーフを念入りに触ると、ひとしきり喋り、高笑いの声を響かせながら賑やかに去っていった。四阿の初老の男性は、何事もなかったかのようにスケッチを続けている。自分の世界に入り込んでいれば、外野の喧騒も耳に入ることはないのだろう。よかった、小さな安堵感が私の気持ちを静めた。金印のレリーフの左後方と真後ろに、かなり大きな碑が建てられてある。日中友好の記念のようだが、その一方の筆跡の見事さに誘われて歩みよった。「戦後頻傳(伝)友誼歌 北京聲(声)浪倒銀河・・」品格のある行書で、しかも懐が広い。これを彫った石工(いしく)もかなり熟練したセンスのいい人と見える。ゆったりと時間が流れていった。筆者との思いを共有するかのように、その筆跡に惹かれて私は読み進めていった。「海山雲霧宗朝集 市井霓虹入夜多 ・・」跋(ばつ)には、1955年冬に福岡を訪問、18年後の1974年冬再訪、帰国後この詩をしたためて送ってきた、とある。七言律詩のそれは、郭沫若(かくまつじゃく) のものであった。(続)
2005年09月28日
コメント(4)
-
「方形の謎」・・・志賀島紀行「唐国の波」 (4)
海の反対側に急な石段があり、その右側に「漢委奴國王金印発光處」の石柱が立つ。ちょっと見ると神社のようでもある。四,五十段ほどの石段を上り詰めると、印影のレリーフが置かれてあった。天明4年(1748)2月、金印は灌漑(かんがい)用の溝の修理中に出土したと言われているが、その出土した場所をはっきりとは特定できていない。発見者といわれている百姓 甚兵衛の存在も定かではないのである。甚兵衛が百姓か否か、技師か役人かは知らないが、そんなことよりも、金印がなぜこの島に埋められていたのか、興味は残る。『後漢書倭伝』によれば、「建武中元二年倭國奉貢朝賀使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬」とあり、倭の使者が後漢の光武帝から印を賜ったことが判る。建武中元2年とは、西暦57年のことであり、使節団が印を受けた正月は、なんと光武帝が崩御する僅か2ヶ月前のことである。金印は、「漢」の尺度で方1寸、約2,35センチ平方、純度は22,3グラムと純金に近い。その方形の中に「漢委奴國王」と彫られている印は、押印した時に印泥(一般に使われる朱肉に当たるもの)の朱色の中に印の周囲にそった縁と文字が、白く浮き出る陰刻である。印には、陰陽すなわち白文と朱文があり、一顆(一つ)だけ印す時もあれば、二顆同時に押すときもある。二顆の時は陰陽をセットで、つまり、白文と朱文を用いる。いうまでもなく、文字が白く浮き出るのを白文、朱で印字されるものを朱文といい、白文を上に朱文を下に配する。「陰」の沈む性質と、「陽」の昇る性質で両者は一体化つる、と考える。従って上下を逆に押印することは殆どないといっていい。その逆を見る場合もなくはないが、いたって稀なことである。金印の書体は繆篆(びゅうてん)、篆書と隷書の間くらいといえようか。篆書は美しいが非常に複雑な書体である。書くのも刻するのも容易ではない。古くから実印に用いられている所以なのである。春秋戦国時代を経て、秦の始皇帝が全国統一を成し遂げた秦代、政策の一環として皇帝は通行書体を篆書に定めた。それまでは、それぞれの国が各々の文字を使っていたのである。その後の漢代に至っては、木簡などに見られるように、よりシンプルで、より速く書ける簡便な書体が日常多く使われるようになり、篆書に代わって隷書が主流となっていった。印影の篆書に隷意が加わるのも当然のことといえよう。出土した金印の印文に「印」あるいは「章」の文字がないとか、印の上部についている飾りの印鈕が、亀ではなくて蛇なのはおかしい、という人もいる。更には、印文に「國」字があるのもおかしい、異民族の王には既に授けた「南越王」「鮮卑王」などの印に見られるように印文には「國」ではなく「王」を用い、語の卑弥呼に対しても「親魏倭王」として金印紫綬を与えているではないか、と偽印説が上がっているものの、やはり真印説の要素の方が強く、金印は国宝にも指定されているのである。1千年もの眠りから覚めて出土したこの時の印が、王仁(わに)の伝えたという『論語』にも先駆けて、中国から日本への、初めての漢字伝来を物語るものとして今なお存在することを思えば、古へのロマンは尽きない。いったいこの島の何処で眠っていたのか。どんな行程を経てこの島に辿り着いたのか。そしてまた、この印影は、正しくはどう読めばいいのか。「カンノワノナノコクオウ」でいいのか、「ワノコクオウ」なのか、印文中の「委奴」はヰナ、ワタ、イワ、ワナ、イヌ、イネなのか、「委」はヰ・イ・ワなのか、素人にはもう判らなくなってしまう。「奴」をナ・ノ・ヌなど、どう読むかによっても変ってくるだろう。「委」も本当に日本のことなのか、日本の他にも「倭」の国はあったようだし・・副葬品も何もなく、ただ金印だけが出てくるなんて・・全く謎は深まるばかりである。(続)
2005年09月26日
コメント(3)
-
志賀島紀行「唐国の波」・・・(3) 「金印塚」
「つぎは~ しかのしま~」車内アナウンスの後、バスは大きく揺れて止まった。沙嘴(さし)の向こうに広がっていた陸地に乗り上げたようだ。いよいよ志賀島(しかのしま)である。赤いシャツにベージュ色の小振りのリュックを背負った大学生風の女の子が、運転席の傍に立ち何か尋ねている。「・・小さな塚があるだけ・・公園になって・・」運転手の声は幾分大きい。が、後方の私の所には所々しか聞こえてこない。途切れ途切れの話から推せば、二人連れの彼女達も、どうやら「金印塚」を訪ねるらしい。国民宿舎のある所でバスは止まった。このバスは此処までだという。二人の女の子の降り際に運転手は言った。「この道を真っ直ぐ上って行けばいいから」彼女達に続いて私もバスを降りた。金印公園の傍で下車しようと思っていたのに、此処から先は歩かねばならないらしい。ガードレールに沿って海沿いのゆるやかな勾配をのぼった。沖合いに小さな島が見える。壇一雄の愛したという「能古島」(のこのしま)か。波は穏やかに寄せてくる。南国の秋の日は思いのほか暑く汗ばむほどで、山側の樹木の葉も紅葉にはまだ早い。11月の半ば過ぎぐらいでなければ、美しく色付くことはないのかも知れない。どこからか香ばしい磯の香が漂ってきた。イカの丸焼きか、サザエ・・食いしん坊の私は想像に事欠かない。何処からだろう。匂の所在を確かめるべく私は辺りを見回した。少し前方に「お食事処」と紺地に白く染め抜いた細長い旗が見える。民家そのままの道端の小さな店が、庭先で魚や貝などの海の幸を焼いて客に供していた。先ほどの女の子達も立ち寄っていたが、また帰りにね、と店主らしき人に告げて私は通り過ぎた。喉も渇いているし食指も動くけれど、私は歩くことが任務でもあるかのように、止まることなくそのまま歩を進めた。海べりの大きな岩にカラスが一羽、ずっと止まったままでいる。波がそれほど大きくないとはいえ、波が岩に砕けてもカラスは微動だにしない。いや、しないように見える。濡れ羽色とはこんな色か、カラスの羽は不気味なほど黒く、艶々と光沢があった。ガードレールにつかまって海を眺めた。海は満ちているらしい。波がひたひたと迫ってくるように感じる。波に洗われて角の取れた丸い大小の石が無数に犇めき合い、その石の上に覆い被さった波は、すぐさま石の隙間を走って引いていく。シャアー波の走る音が聞こえてくる。私はまた歩き始めた。海に張り出した山沿いの道のゆるやかなカーブに差しかかると、遠くに赤いシャツとベージュ色の小さなリュックが見えた。もうあんな方に。若者はさすがに足が速い。時々疾走していく自動車に気を配りながらも、幾曲がりかのカーブを越えて、どうにかひとつ目の目的地に到着した。「金印塚」である。(続)
2005年09月22日
コメント(1)
全177件 (177件中 1-50件目)
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- --< 地震に強い構造の・・・ >--日本…
- (2025-11-14 06:08:06)
-
-
-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…
- 金沢旅行 4日目
- (2025-11-12 17:42:15)
-
-
-

- 温泉旅館
- 錦秋の東北へ 米沢・白布温泉 湯滝の…
- (2025-11-13 06:46:38)
-