2022年08月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

いよいよ
NHK NEWSWEBよりおはようございます、紙太材木店の田原です。台風の進路が気になりますが、気になるのはもう一つあってその強さ最大瞬間風速75m/sとか温暖化の影響で強く、大きな台風が増えてくると言われてますから、20年、30年先のことが心配になります。前回、英国の光熱費が年間57万円で大変と書きましたが…今朝のNHKのNEWS WEBで10月の電気料金が大手10社共に過去5年で最高になると報じてました。東海地方の中部電力に限って言えば、昨年の10月と比較すると値上がり幅は33%3%ではありません33%です。因みに東京電力は同27%の値上げ。もちろんガスも上がっていて、東京ガスが昨年比27%東海地方の東邦ガスも同じような値上がりと思われます。NHK NEWSWEBより東京電力のグラフは標準的な家庭とありますが、この標準は電気とガスの両方を使用する家庭が前提ですからオール電化の家では上昇率は同じでも、金額は更に増えます。家計を預かる方は毎月送られてくる電力会社からの請求書から支払っている料金の内訳をご存じかもしれませんが、大きく3つに分けられます。TEPCO 燃料調整費資料1、契約している電力料金単価から計算される電気代2、そこに燃料調整費3,再生可能エネルギー賦課金この3つです。燃料調整費。以前から飛行機ではありましたが、最近はトラックの運送会社も使うようになりました。建築現場に資材を搬入するのにも、上乗せされることもあります。従来はこの燃料調整費金額も小さくマイナスで計算されることもありましたが、昨日の松尾さんのFBに比較表が出てました。松尾さんFBより中部電力は9月の負担は9.43円/Kw月に5kw使う家庭では約5000円の負担増円安とエネルギー価格の高騰のダブルパンチですが、心配なのは秋の10月でこの金額。冬に向かって更にどれだけ上がるのか…燃料調整費は5か月前から3か月前までの3か月間の平均で出します。日銀が9月に金利を上げて円がもう少し高くなっても、燃料調整費に影響が出始めるのは来年の2月からです。今年の冬はヨーロッパも大変ですが、いよいよ日本も他人事ではなくなってきました。
2022年08月31日
コメント(0)
-

必須
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は22度で湿度は79%、涼しく感じます。さすがに8月も最後の週ですからこんなものでしょうか。今日から地元の学校は2学期です。9月には新住協の総会が仙台でありますが、今年もZOOM開催です。2年続けてのZOOmですが、コロナ以前は全国から工務店や設計事務所が集合。わざわざ総会にまで来るのはそれなりにやってるところが大半で、直接会って様々な情報交換をする場でもありました。特に大懇親会やその後の2次会や3次会で意気投合して、互いの会社に訪問したりと日本の住宅の性能向上の広がりに大きく貢献してました。総会の後は・鎌田先生の基調講演・エコワークスの小山社長の脱炭素社会に向けた取り組み (太陽光発電の重要性)・久保田理事の「新住協監修した仙台S邸」 夏の温度測定の報告他通常は総会は持ち回りで全国各地で開催されるので、その地域の会員の建てた住まいの現地見学があるのですが、今回はありません。エコワークスの小山社長と言えばYOUTUBEや新建ハウジングなど様々なメディアで、太陽光パネルの事を発信されてますから一般の方もご存じかもしれません。週末に来られた新規のお客さんもパネルってどうなんでしょうと言われていましたが、紙太材木店の場合、昨年からほぼ100%の方が設置されていますし現在打ち合わせ中の方もその方向です。東京都のパネル設置義務化の件で、メディアや名の知られた人達の反対運動や反対意見などが随分ありました。新築検討者のパネル設置に影響を与えるかもと心配していたのですが、紙太材木店の場合は影響は感じられませんし、多くの方が冷静に本質を見ているように感じます。紙太材木店の場合も以前の方向から変わってきています。以前は、断熱、気密、換気が優先で予算があればパネル設置というスタンスでしたが、現在は、性能(断熱、気密、換気、耐震)を満たしたうえでパネル設置は必須ですよ、というお話をしています。予算的な制約のある方でも、リクシルや東電、京セラなどがやってる屋根貸しの仕組みも条件は厳しくなっていますがあと数年は利用できそうです。自己防衛のためにも新築を検討される方は、パネルについて十分勉強する必要があります。エコワークスの小山さんや東大の前先生などはそのあたりの事を分かりやすく解説してくれていますので、興味のある方はYOUTUBEなどで検索してみてください。30年後、40年後の次の世代の子供たちにしてあげられることがあります。PS今年のイギリスの状況はこんな具合です。標準家庭で年間57万円、日本で耐えられる家庭がどれだけあるでしょう?
2022年08月29日
コメント(0)
-

冷房負荷
リノベーションでも、耐震・断熱気密改修。おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝の美濃地方は23度95%昨日の雨の湿気がそのまま残ったイメージです。前回、大阪での勉強会で冷暖房負荷の事を話しましたが、この時期の冷房負荷についてです。ほとんどの方がエアコンで冷房されます。エアコン冷房の機能は温度を下げることと、湿度を取ることの二つです。温度を下げると湿度も結露されて取れるということは空気の中に水蒸気が混ざっているからで、この二つを一体で考えて冷房負荷がどれだけあるかを考える必要があります。この二つと言うのは水蒸気と言う気体とそれ以外の気体(窒素や酸素、二酸化炭素など)で合わせて空気とします。この時、温度を下げるための負荷を顕熱負荷、湿度を下げるための負荷を潜熱負荷と言います。この顕熱負荷と潜熱負荷は換気によって生じる負荷で、全体の冷房負荷の一部になります。つまりこれ以外にも冷房負荷がありますが、二つに分けて考えると分かりやすくなります。二つとは顕熱と潜熱です。顕熱側は最初に、人です。体温36度で60Kgほどありますから熱が出ています。同時にこの人は発汗したりして水蒸気も出していますから、人の場合、顕熱と潜熱の二つに分け、顕熱側でどれだけ熱が出ているか一人なのか、5人なのか、何人で住んでいるのかで変わってきます。次に内部発熱。これはTVや待機電力、冷蔵庫、照明器具などの設備機器。三つめが日射取得。南の窓、東西の窓それぞれからどれだけのエネルギーが入ってくるか。遮蔽は何でしているかで、その割合が変わってきます。南の窓は太陽高度が高いので庇などで加減ができますが、東西の窓は庇では無理ですから、別の方法で検討する必要があります。四つ目が、外皮でUa値から計算します。これらを合計したのが顕熱負荷となります。そして最後に換気による顕熱負荷。2時間に一回、家中の空気を入れ替えます。外は36度だけれど家の中を28度にしたいとなると、8度の温度差のある空気が30坪程度の家でも150m3くらい入ってきますから、エアコンには一生懸命働いてもらわなければなりません。次は潜熱側。これも最初は人。空調の教科書などには人体発熱量として顕熱、潜熱それぞれどれだけ出ているか書かれています。もちろん、人数で変わってきます。次はやはり内部発熱。内部発熱で潜熱というと、室内干しででる水蒸気。お風呂や熱帯魚や金魚の水槽からも水蒸気が出ます。最後に換気による潜熱負荷。外が36度で湿度が50%あると、空気1Kgあたり19グラム(絶対湿度)ほどの水が含まれています。室内を28度で湿度を60%にしたいとなるとその時の絶対湿度は12グラム。家の中から空気1Kgあたり7グラムの水を取り除かなければなりません。2時間に1回の換気ですから、150m3くらいの空気が入ってきます。上記の顕熱側の負荷と潜熱側の負荷を合計したものが、冷房負荷となります。計算は全てW(ワット)に変換して出します。合計が5000wであれば5Kwと言うことですから、2.5Kwのエアコンが2台必要と言うことになります。外気が40度で60%の湿度の時はどうなんだ?と聞かれても冷房負荷が計算できれば、必要な冷房能力はこれだけですと答えられます。冷暖房負荷は住まいの様々な要素によって異なります。つまり、同じ家はありませんから、個別に計算する必要があります。極端なことを言えば、全く同じ家でも家族の人数や趣味、趣向が異なれば冷房負荷も異なってきます。それと私の家は1種の全熱交換だから大丈夫かというと、そうとばかりは言えません。こちらのさとるパパさんのブログで、先日こんな計算をされてますから参考にしてみてください。自動車の燃費やエアコンのCOPやAPFでもそうですが、一般の使用状況とは異なった条件での数値。これらの数字は信じて当てにしてすると落胆することが時にあります。(いつもかも)車の燃費でしたらすぐに違いは判りますが、熱交換率やAPFは一般の方では正しいかどうかの確認はほぼできません。省エネ機器はあくまで省エネで、必ずしも機能的に優れているとは限りません。もちろん、G2だから、断熱性能等級7だから家中、くまなく涼しい、隅々まで涼しいなんてことは、よう言いません。
2022年08月26日
コメント(0)
-

新住協関西 勉強会
こんばんは紙太材木店の田原です。蒸し暑い夏が戻ってきたような天気です。気温と湿度に加えて日射ですから、現場では立っているだけで汗がしたたり落ちます。朝一、大阪からとんぼ返りで地元の商工会の会議の後に、関市の肥田瀬の家の現場立ち合い。と言うことで、この時間の更新になりました。昨日は新住協関西の勉強会でした。この勉強会は2ヶ月に一度開かれますが、毎回会員の事例発表と講師を呼んでの講習がメイン。かれこれ、10年も続いている勉強会です。会を引っ張ってきたのは、ダイシンビルドの清水社長(新住協理事)二か月ほど前に清水さんから田原さん、今度何か話してよ…と言うことで今回は私が講師となりました。持ち時間は2時間でしたが、事例発表が30分ほど早く終わったので2.5時間。ZOOm参加が25社ほど、リアルで20名くらいでしょうか。一般の方向けではなく関西の新住協の会員向けですからそれなりの内容でないと、こいつはアカンとあとから何を言われるか…中部東海支部の名誉がかかった講義となってしまいました。ということで当初は換気の話しを予定していたのですが、途中、換気はテーマが広すぎることに気づいた次第。そこにたどり着く前に分かってなければならないことが山のようにあって、それらがわかってなければ基礎のない家の話しをするようなことになってしまいます。話した内容は冷暖房負荷とエアコンの顕熱比それに空気線図を使った換気による顕熱負荷と潜熱負荷いわば、空調設計の入り口の部分となりました。空調設計は住宅でも必須ですが、実は教科書的なものがありません。本があってもそれはビルや工場が対象の空調設計。住宅に応用しようとすると、空調機器だけで数百万はかかってしまって現実的ではありません。加えて、住宅向けの空調設計と言うと、学ぶ場所も教えてくれるところもないんですね。私は昨年、全館空調設計講座(ミライの住宅主催)に出てましたから、その時の講座の資料をいくつか使わせてもらいました。代表理事は森亨介さんで同じ岐阜県の鳳建設さんです。森さんは今月発売予定の建築知識ビルダーズにも換気、空調設計術として寄稿されてますから興味のある方はご購入下さい。一般の方にはちょっと難しいかもしれませんが、普通に設計に携わる方でしたら大丈夫でしょう。ということで、終了後は懇親会。3次会くらいまでは覚えているのですが…
2022年08月24日
コメント(0)
-

持続性 継続性
おはようございます、紙太材木店の田原です。お盆あたりから、なんだかすっきりしない天気が続きます。昨夜は雨で今朝も雨は降ってませんが、湿度の高い曇り空です。子供のころはお盆を過ぎた頃から、朝のラジオ体操はランニングシャツ一枚では寒かったのを覚えています。先週、ヤフーのニュースに上のグラフが出ていました。2020年と比較した時の大手HMの1棟の金額で、土地は含みません。積水ハウスと大和ハウスが3%強の上昇。住林は下がっているように見えますが、1棟面積が減少していて他の2社と同程度の値上がりとか…昨年と一昨年を比較した数字ですから、今年は来年にならないと出てきませんが既に積水ハウスは6月に3%大和ハウスもこの10月に同程度の再値上げの予定です。先月の日経の記事によれば、大和ハウスの2021年度の金額は消費税を除いた1棟の平均価格で4300万前後。今年10月に3%の値上げとなると、今年は4430万(除く消費税)の予想となっています。日経新聞とヤフーのニュースでは金額が異なりますが、それほど大きな隔たりは無いでしょう。傾向から見ると積水ハウスは大和ハウスよりもう少し高いと思われますが、積水ハウスは23年1月にかけて更に段階的に価格を上げるとあります。上の2社に加えパナホームとトヨタホーム、それにセキスイハイムなどが軽量鉄骨の構造。工場生産で型式認定などを取得した長期優良住宅が主体紙太材木店ではリフォームもしますが、この手の住宅ははっきり言ってお手上げ…表面的なクロスの張替えや吹付塗装などはできても、構造的な部分に関わる間取りの変更などは構造計算書などがオープンにされていれば何とかできますが、ブラックボックスですから手が出ません。加えて、工場生産で型式認定を取得していれば、現場で構造変更すれば認定は取り消される可能性があります。もちろん、長期優良住宅も…家を建てた自分達だけが住むのならそれでもいいかもしれませんが、次の世代はどうでしょう。間取りを変えたいという要望は、長い間には出てくる可能性の方が高いと思われます。30年か40年程度で建て替えなどと言うことは恐らく考えていないはずで、これらの住宅も構造的には優に50年、60年あるいはそれ以上の寿命があるはずです。長い間には世代や住まい手の都合にあわせて変えられる必要もあるわけで、建てたメーカーしか手出しができないのではなく、技術者の誰もが手を加えられるようなその建物の構造計算のオープン化も必要と考えます。それをクローズにして出さない企業秘密ですからと言うのは、囲い込み戦略と言ってしまえばそれまでですが、住まい手に取っての選択肢は建てたメーカーしかないことになります。日本の建築文化の継続性や持続性を考えれば、その手の囲い込み戦略の限界も近いのではないでしょうか。遠くない将来新築なんて高くて手が出ない、既存住宅のリノベーションが主流という時代が確実に到来します。現在、空き家が800万戸、更にそれが増えていく時代なのですから。
2022年08月22日
コメント(0)
-

自己防衛
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は快晴、20.5度、湿度は90%ありますが爽やかで気持ちのいい朝です。絶対湿度は13g、気温31度の湿度45%とほぼ同じです。今朝の予報でも日中は乾燥してその程度の湿度と言ってましたから、今日は日陰に入れば随分過ごし易い一日になりそうです。7月のイギリスの消費者物価が、40年ぶりに対前年比で10%以上の上昇とか。既に3月の段階で7%上昇してましたから、他所の国のことながら心配してしまいます。日本はいまだに2%ちょっとですが、世界経済が連動していることを考えると今後の消費者物価の動向は目が離せません。多くの方は経験していませんが、73年から74年にかけて石油危機の時の消費者物価の上昇は年率25%狂乱物価なんて言われましたが、日本もそんな時代がありました。原因は中東戦争、アラブとイスラエルの戦争です。歴史は繰り返すと言いますが、今回のウクライナの戦争も似た構図にあります。人間も国家も50年ではそれほど進歩する訳ではなさそうです。これから住まいを建てられる方は日本にもそんな狂乱物価の時代があったなんて、想像もできないかもしれません。50年前はご両親はまだ小中学生。その前の祖父母の方が、丁度家を建てる時代でしょうか…ご存命であれば、当時のお話も何かの参考になるかもしれません。さて、こんな不確実な時代に住まいを建てると決めた以上、自己防衛をきちんと検討する必要があります。簡単に言えば燃費のかからない家を建てるパネルを載せて見せかけの下がった燃費を見るのではなく、素の燃費を見る必要があります。なぜなら、その見せかけの燃費は、補助の入った売電価格で作られています。しかも、その補助は10年しかありません。30代で家を建てれば優に50年以上は住むことになります。(女性の平均寿命は87歳)物価やエネルギー価格の上昇率と自身の給与の上昇率、引退した老後の生活資金や年金を考える必要があります。最初の10年だけ数字が良くても、その後の40年が青色吐息の我慢生活では、健康寿命も縮んでしまいます。住宅価格も上昇する中、ご自分の予算の中で住まいには何が必要で何が余分なのか不要不急のものは削ぎ落して考える必要があります。ある意味、虚飾を排して本質に迫る家づくりでしょうか。長く物価や給与が停滞していた時代。それしか経験してませんが、その時代とは異なった家づくりが求められる時代になりました。パネル搭載は必須ですが、その前に住まいの性能や耐久性をできる限りあげておくことが求められます。
2022年08月19日
コメント(0)
-

資格
おはようございます、紙太材木店の田原です。今日から仕事再開。2022年も既に半分過ぎてますが、夏休みが明けたら残りは4か月半…なんだかあっという間の1年です。先日FBで同業仲間がBISの講習と試験に、名古屋が追加されたことを教えてくれました。もともとは寒冷地である北海道の試験。寒い地域での家づくりに対応した内容になっています。最近でこそ気密ということも一般的に言われるようになりましたが、10年前は気密の後に?が三つくらいつく設計者も多くいました。英語で表記するとvapor barrier直訳すれば水蒸気の関門(障壁)最近でこそ一般的になりましたが、以前は気密シートを貼るイコール窒息住宅、なんてことも言われてました。気密の気を水蒸気の気ではなく、空気の気と誤解して覚えた人もそれなりにいました。従来は北海道や東北で開催されてましたが、昨年初めて埼玉で開催されました。これはチャンスと思ったのですが、別件の予定と重なり行けず…今回は10月に講習、12月に試験ですから、なんとでもなりそうです。北海道や東北の新住協の人達の多くが持ってるBIS資格。関東以西ではそんなに多くないはずで、講習を受けてそれなりの勉強をしないと試験には合格しません。講習を受ければ誰でもという試験とは違います。今回は名古屋だけでなく、西日本の大阪や福岡でも開催されます。高性能で暖かい家が建てたいと思って設計者やHM、工務店に相談すると、経験が無くても「できますよ」になりがちな住宅業界。BISの資格は完全ではありませんが、ある程度の判断材料になると思われます。新住協でもPHJでも、入っているだけの幽霊会員もそれなりにいます。高性能な家づくりは施工経験も大切ですが、最初のスタートである設計者がわかっていなければ絵に描いた餅。来年以降、関東以西での高性能な家づくりではBISの取得がカギになるかもしれません。
2022年08月17日
コメント(0)
-
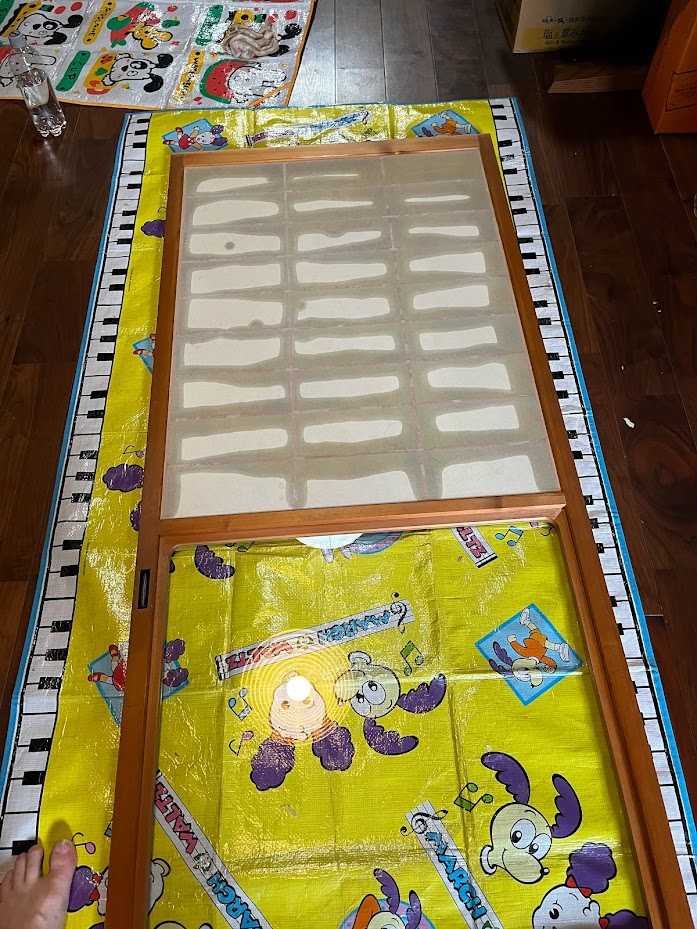
張替えは男!
お盆です、紙太材木店の田原です。せっかくのお盆休みですが、なんだかすっきりしない天気で明日も雨模様の美濃地方です。コロナや猛暑もあって、出かける予定は最初から組んでませんでしたからと言うわけでもありませんが障子の張替え普段、住まい手にお勧めしている障子。紙太材木店で家を建てる方の大半に採用していただいてますが、時折聞かれるのが障子の張替えはどうすれば・・・面白いのは夫婦のうち、ご主人は子供の頃障子の張替えを手伝ったことがあるのに対し、奥様の多くはその経験が無いこと。50代以上の女性の方を除けばほぼ皆無。張替えの事を聞かれるのもほぼ100%奥様。ご主人は子供のころ手伝ったから何とかなるよ…私の場合、母が障子の張替えをしていてそれを手伝うという流れでした。父が障子の張替えをしているのは見たことがありません。家内に聞くと実家では母が障子の張替えをしていて、自分は手伝ったことはないとのこと。手伝いはしてましたけれど、最初から何もかも自分でするのは初めてでしたがやってみれば簡単にできました。半日ほどで8本の障子を張替えました。(障子紙をはがして、桟についたノリは前日に落としてます)念のためネットで張替えの仕方を検索しました。障子紙はホームセンターで購入。その時、障子紙のはがし剤とノリ刷毛、でんぷんノリも一緒に購入。障子紙のコーナーに一式そろってます。ノリはチューブに入ったものもあるので、でんぷんノリにするかチューブ入りのものにするかはお好みです。障子のはがし剤を桟に塗ります。塗れ雑巾で残ったノリや紙を綺麗に拭き取ります。最初に紙の位置決め張り出しの端をテープで留めておきます。(障子紙を買うとその中に仮止め用のテープがついてくる)巻き戻して糊付け糊はこんな程度…障子紙を転がします紙の張り始めのところは紙を少しめくって、糊を後から付けます。定規を当ててカッターナイフで余分な紙を切りますが、その定規で紙と桟の糊を抑えて圧着。完成張ったばかりなので随分、皺やたるみがあるように見えますが、一晩経って乾けばぴんとした張りになります。障子の張替え、仮止めのテープで押さえれば一人で十分張替えができます。カーテンは何年かすれば、色褪せてきたりします。障子も和紙が焼けてきますが、張り替えれば見違えるほど白く明るくなります。しかもそれは自分一人で安価にできます。障子にするかカーテンにするか迷っている奥様、張替えはご主人一人でもできますから是非、障子をご検討ください。
2022年08月15日
コメント(0)
-

誰が?
おはようございます、紙太材木店の田原です。猛暑に続いていきなり台風…その影響からか今朝は雨の美濃地方。暑さが和らぐのはいいのですが、台風となると話は別。現場の台風対策をしなければなりません。羽島の家は大工さんの工事が終わって、内装工事中ですが既に外部の工事は終了していて、足場も取れています。本荘町の家は絶賛大工工事中。外壁の杉板やガルバの工事は終了していますが、軒裏や破風の塗装がまだですから足場はそのまま立ってます。もちろん養生用のネットも取り付けてあります。肥田瀬の家は基礎工事中で、鉄筋の組み立ての最中。どの家も今日中に台風対策しておかねば…先日、日経新聞に出ていた2022年1月1日時点での人口動態調査日本人は前年より0.5%減って、1億2322万3561人減った人数は61万9140人わずかに増えたのは沖縄県のみ。岐阜県は194万人の0.89%のマイナスですから、1万7千人ほどが減ってます。川辺町の人口が1万人ほどですから、一つの町がそっくり無くなったのと同じです。今後も毎年のように、一つの町の人口がなくなっていくのと同じことが続きます。少子高齢化と人口減少の対策は喫緊の課題ですが、政府に妙案や戦略があるように思えませんし、当然空き家問題も関係してきます。このような日本の現状の中でこれから新築を考えている方はどんな家づくりをしたらいいのか?次の世代の人が住みたい、あるいは住んでもいいかなと思う家になるかこりやぁ、あかんとなるかは建てた家の性能次第選んでもらえなければ負の遺産。バナナのたたき売りのように値段を下げても、誰も見向きもしない家となります。だって、人口はどんどん減っていきますから空き家もどんどん増えることになります。その対策は政府にはありません。つまり、お上は当てになりませんから自分達で考えるしかありません。あなたがこれから建てる家は次の世代が喜んで住んでくれる家かどうか?デザインやインテリアが素敵、値段が安いだけでは30年後に選ばれる可能性はほとんどないと言ってもいいでしょう。お子さんにどんな家を残すかもそうですが、次に頭を悩ませるのは自分の両親の家の相続でしょうか。可児市や美濃加茂市の少し古い分譲地を見れば空き家はいたるところにありますが、売れてる気配はほとんどありません。木造の家の解体費用は150万から200万解体すれば固定資産税は3倍から4倍誰が相続したい?
2022年08月12日
コメント(0)
-

意識次第
おはようございます、紙太材木店の田原です。今日も30度越えの美濃地方。ここ数日、通り雨のように日中ザっと降ることもありますが、すぐに止んで気温を下げるところまではいきません。子供の頃は夕立雨が降れば、気温も下がって涼しくなりました。ここ数年はそんな夕立もほとんどありません。温暖化の影響がこんなところにも出ている可能性があります。スペインやポルトガルでは今年の夏、気温が45度を超えたとか…いくら日本より乾燥しているとはいえ45度、日本では湿度が高く35度でも大変ですが、45度で湿度が高かったらと考えると想像すらできません。さて、東京都の太陽光パネルの設置義務化の件。反対意見も多くありますが、パブコメの意見では若い世代ほど賛成意見が多く、年齢が上がるほど反対が多いとか…カリフォルニア州では新築住宅への太陽光パネル設置を義務化して既に2年以上経ちますが、今では次のステップであるオール電化に目標を定めてます。車も電気、家も電気。それをパネルで持続可能な形にするというもので、政策実行スピードが日本に比べはるかに優ってます。もちろん、住民の意識がそちらの方に向いていなければ可能ではない訳で、政治は結局のところ住んでいる人の意識次第というところでしょうか。パネル設置義務化の件、東京都のことも、ましてカリフォルニアの事も遠いどこかの夢の話のように聞こえるかもしれませんが、あと数年したらひょっとして岐阜県でも愛知県でも…しかし、ひょっとしたらではなく高い確率で義務化の方向に行く可能性があります。つまり、ひたひたとあなたの足元に迫っているのは温暖化だけではなく、その対策ももうすぐそこまで来ていると見ていいんじゃないでしょうか。できることはできるだけ性能の高い家を建てること。でなければパネルを設置しても、効果は期待するほどにはなりません。東京大学 前准教授の意見
2022年08月10日
コメント(0)
-

居心地のいい場所、それが難問
おはようございます、紙太材木店の田原です。快晴ですが、少し蒸し暑い朝です。今週初めから夏休みの方もあるとか。建築業界ではさすがに今週からと言う会社は聞いたことがありませんが、職人さんたちは通常日曜日だけが休み。お盆とお正月だけは少し長めに休みを取るため、11日頃から現場は休みとなりそうです。先日、リオタデザインの関本さんとi+iの飯塚さん対談がネットでありました。関本さんが訪れたアルバ・アールトの建物を解説したものです。その中でマイレア邸というアールトの代表作があるのですが、日本の有名な建築家があの建物の良さが全く分からない、図面や間取りを見ても何所がいいのか不明と公言していたのが、実際訪れてみてその空間に身を置いた時、自分の不明を恥じたというエピソードを話してました。有名な建築家でもそうなのかと思った次第。実際のところ住宅の図面は二次元。パースを書いたり、3Dで立体化しても、モニター上でしかそれを見ることはできません。(最近はバーチャル体験できるようなものもあるようですが・・・)残念ながらモニターは二次元の平面ですから立体の3次元を2次元の平面で見るには、何かしらの限界があります。実際、設計しているときは頭の中で考え、自分がその空間の中にいることを想像する訳ですが、そこまでが限界で、その場所に座ったときや立った時の居心地の良さまでは想像できません。居心地の良さと言うのはある意味感性の部類に入るもので、頭の中で考えて想像しても、自分が感じるであろう感性までは想像できません。経験と勘から多分こんな空間にしたら、居心地よく感じるのではないかと想像するのが限界…図面を描いただけで居心地の良さを感じることができるようになればいいのですが、ある意味それは達人の領域。経験と勘を養うには、いろんな建物を訪れ場数を重ねるしかないのかと思う次第。上の写真、右手のたためる椅子に座った時の居心地の良さは写真ではどうやっても伝わらないし、図面を見ただけでもわからないけれど、居心地のいい場所。図面段階では伝わりません。住まいの中でどれだけ居心地のいい場所を作れるか、それが難問。
2022年08月08日
コメント(0)
-

お任せ
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は21度。湿度は93%ですが気持ちのいい朝です。昨日の雨で地面がぐっと冷やされた感がありますから、今朝は事務所の窓を全開にしてます。(連日の猛暑で蚊が来ないことを願うが、代わりに蜂が…)今朝のニュースで、Z世代は環境に配慮が当たり前と報じてました。最近、よく耳にするZ世代そもそも年齢的に何歳か?を知らなかったので調べてみると、1996年から2015年生まれ年齢的には7歳から26歳とのこともうすぐ家を建てる世代と言うことになります。育った環境はおそらく、親の世代が建てた20年ほど前の住宅やマンション、あるいはアパートと言うことになります。20年前の住まいですから、多くはコスト優先の工業製品で作られた住まいで断熱や換気などを意識した家でもありません。そこで育った人たちの意識が環境配慮を優先と言うのは、興味深いものがあります。Z世代ではありませんが、紙太材木店に来られる30前後で新築を検討されている方の多くも意識されているかどうかはわかりませんが自然なものを使いたいという方が大半です。こちらがそれを普通に使っているのでそうなるのかもしれませんが、敢えて合板のフローリングやビニルクロスと言った工業製品を使って欲しいという方はいません。住宅で使用される製品は多種多様ですが、注文住宅(オーダーメイド)と言えど建てる側(HM、工務店)の都合で決められているケースが多くあります。それは住まい手側の都合や好みでは無いという意味です。ある意味、知らず知らずのうちに誘導されてるとも言えます。決めることや考えることは、掃いて捨てるほどもある注文建築。打ち合わせ期間も長期に及び、そこに予算も入ってくるわけでその全てをきっちりと、と言うのは難しいかもしれません。お任せの部分が出てくるのも仕方がありません。だからこそ、そのHMや工務店、あるいは設計者がどんな想いや考えで住宅を建てているかが大切で、住まい手側はそれを知ることが求められます。自分達の考えに照らし合わせてお任せできる方針や基準、あるいは人達か?素敵な写真だけではわかりません。
2022年08月05日
コメント(0)
-

コンパクトに?
おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は尋常じゃない暑さの中、地鎮祭でした。朝の10時からですが既に相当な暑さで、テントが張ってあっても、テントの生地を通して暑さが襲ってくるような感覚…参加された皆様、お疲れさまでした。昨夜は地域の会合でした。業種を越えた会合で、私の住んでいる町の主だった企業の集まりです。毎月開催してますが、今年は町行政の最前線で仕事をしている各課の課長クラスをお招きして、町の現状と将来の課題を講義していただき、その後議論をする流れです。昨夜は上下水道課。課題は耐用年数(40年 )を越えて使用している上下水道管が約30%今後も順次増えていきますが既存のメンテナンスで手一杯で、管を新しいものに変えるだけの財政的余裕が無いというもの。老朽化に伴う漏水が毎年のように繰り返され、そちらの修理で予算と人員が消化されてしまうという状態です。このことは川辺町に限らず、実は日本中で起こっていることです。周辺の町村では、実はもっと深刻になっています。予算的なことを言えば水道法の規定があって、水道料金の値上げでしか現状では対応できない仕組みになっているようです。住んでいる町民は知らないか関心が無いのが共通。残念ながら行政側が公に情報を公開して、議論するという地域はほとんどありません。行政も議会も知ってるけれど、市民町民は知らないという構図で、寝た子を起こすな的な雰囲気がいたるところであります。もちろんあなたの住んでいる地域も似た問題を抱えているはずです。人口減少財政規模の縮小少子高齢化etvこんな状況の中での上下水道や道路の維持管理には限界があります。太平洋戦争中の日本ではありませんが手を広げすぎて伸びきった補給路を維持できないという、どこかで見たことのある構図があります。実は行政側には既に多くのところで対策が練られています。市町村マスタープラン(都市計画マスタープラン)と呼ばれるものです。誰でも思いつくのは、伸びきった補給路(上下水道)は縮小するしかありません。人口や予算が減っていく中、維持管理できる限界はこの辺りまでという数字は既に出ています。これから土地を買って家を建てようとする方は、そのあたりの事もきちんと確認する必要があります。マスタープランにはここから先のエリアは維持管理できなくなったらゴメンナサイのところですなんてことは書いてありませんから、伸びきった補給路の先なのかはご自分で読み解く以外ありません。
2022年08月03日
コメント(0)
-

予算感
おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は体に纏わりつくような空気でした。今朝も既に事務所は29度 湿度60%、外は26.3度で83%鍵をかけ閉め切った事務所はコピーやFAX、冷蔵庫、分電盤etc一つの空間での中に多くの機器があって、その発熱量もそれなりにあることになります。ドアをあけ放っても、涼しくさは感じられません。朝の6時からエアコンと言うことになりました。さて、資材の値上げが止まりません。今度はガラス。サッシはガラスとフレームからできています。LixilやYKK、シャノン、三協立山などがありますが、サッシで使われるガラスは日本板硝子やAGC、セントラル硝子と言ったガラスメーカーのもの。サッシメーカーはガラスメーカーからガラスを購入して、サッシを作ってます。YKKの場合はガラスも自社生産です。既に昨年10月に30%から35%値上げしていますが、今年の10月にも再度の値上げ通告。AGCが40%日本板硝子が30%YKKは自社生産で何も言ってませんが、原料は同じですから遠からず値上げとなるでしょう。このように建築用の資材が次々に値上げになると、建物本体の工事原価も上がります。業界の対応も様々で、中には性能を落とすところも出てきます。断熱材の厚みや種類を変えたり、サッシのグレードを落としたり・・・限られた予算の中で工事をしなければなりませんから、HMや工務店、設計事務所の対応も様々で、どんな対応をするかは会社次第のところがあります。値上げ分を反映させた価格にするところ性能を下げるところ設備を変えるところ仕上げを変えるところetcこのような状況の中で住まい手側としては何をしておく必要があるか?第一に家族で優先順位を話し合うこと。性能なのか、予算なのか、大きさ(間取り)なのか設備なのか、素材なのかここを夫婦で話あっておくことが大切です。ある程度プランがまとまってくると、予算調整は必ず必要になってきます。このプランでは無理と分かった時に、どうするか?HM、工務店サイドでは実はそのことはわかっていて、プランを進めていくケースもあります。プランが固まってにっちもさっちもならない状況をあえて作り出して、決断を迫るというやり方。残念ながらそんなケースも、一定の割合で起こってきます。それを防ぐには(自分たちを守るには)やはり、ある程度予算感を養うことが大切です。G2レベルや断熱性能等級6、あるいはG3レベルならどの程度の予算になりそうか。そこに使う素材は、工業製品なのか自然素材なのかで変わってきますし、設計力やデザイン的な完成度はどれくらいのレベルか建物だけでなく、庭も含めるとどうなるか?自分達が建てたい内容の家を建てようとすると、これくらいはかかりそうだという予算感を得るまではプランの作成には進むべきではありません。HMや設計事務所、工務店を何件か巡ってみると中にはあれ?お値打ちなんてのもあるかもしれませんが、立ち止まって考える必要があります。なぜ安い?この時世資材は値上げラッシュなのに他のHMや工務店より安いのはなぜか?囮の引き寄せ価格?なんてこともあるわけで、安いには安いなりの理由があります。何も勉強せず、何の準備もせず夫婦で何も相談せず、あこがれだけで住宅展示場や見学会に行く時代は遠い昔の話しです。建てる時の費用だけでなく、その家に住むと年間どれくらいのお金が必要か?(冷暖房光熱費)電気代が今の倍になったら?メンテナンス費用はどれくらい見込むか?30代で家を建てると、優に50年以上住むことになります。サッシは一生ものと思っている方も多くいますがサッシの交換も頭に入れておく必要があります。
2022年08月01日
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-
-

- 運気をアップするには?
- 運気アップグッズのオンパレードです…
- (2025-11-13 23:37:54)
-
-
-
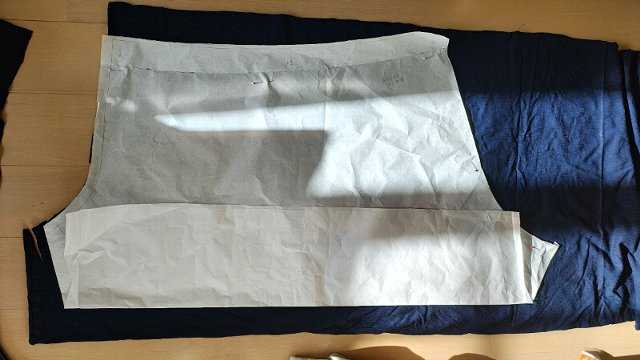
- ☆手作り大好きさん☆
- 続き♪インナーパンツ☆娘ちゃんのお気…
- (2025-11-14 12:00:04)
-
-
-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…
- Snow Man💜出演 CM 11月14日 め…
- (2025-11-14 12:30:04)
-







