2023年02月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

準防火の窓は・・・
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も池に氷が張る寒さですが日中は全国的に暖かくなるとか。名古屋の予想気温は14度。ただ、今日は新住協の理事会で仙台。夜がどれくらいの寒さか?上着を考えねばなりません。さて、週末の打合せ。準防火地域で平屋プラン、使う窓には制限がかかります。準防火対応のサッシとなるのですが、性能やサイズの幅が狭いんですね。制限のないサッシと比べれば、サッシのUw値(熱還流率)の値も普段使用している性能の良いサッシに比べるとワンランク下になります。それと、メーカーによって使えるサッシの大きさが違うので、メーカーを統一しようとすると必要なサッシのサイズが無いということも…ここの窓にはこの大きさの窓が欲しいとなっても、A社のサッシではないけれどB社のものならある。となると一つの建物に3社あるいは4社くらいのサッシメーカーの窓が取りつくことになります。町の中の準防火地域で平屋となると、日射はできるだけ多くとりたい。同じUa値でも、暖房負荷(暖房代)が大きく違ってきます。住まい手に取って最適な温熱環境は人それぞれで、設計時には明確には分かりません。設計時にできることはできる限り性能を上げておき、住まい手の選択肢の幅を広げておくことでしょうか。サッシメーカーさんには市街地では準防火地域に指定される割合が高いので、もう少し性能の良い窓を作っていただければと思います。それと、サイズも。今回のプランでは木製サッシも使う予定ですからデザインと防火の工夫も必要です。
2023年02月27日
コメント(0)
-

五十歩百歩
おはようございます、紙太材木店の田原です。美濃地方、昨日は朝から雪。初めは氷雨が雪に変わった程度。それが徐々に本格的になって一時はどうなるかと心配するほどでしたが、お昼前には何とか収まり午後にはお日様も見られるほどに回復しました。さて、Lineの公開のグループは色々ありますが、高気密のグループに偶々入っています。家づくりを計画している人や現在進行中の方あるいは既に建て実際住んでおられる方等様々な人が参加しています。私自身が発言することは無いのですが、それらの人の意見や考えが設計者としては参考になりますし、ある意味重宝しています。いろんな質問や意見が出ますが昨日の質問は、現在建築中の方で気密は0.5前後、Ua値は0.413階建ての狭小地そこで使うエアコンの性能をどの程度にしたらよいか?エアコンは性能の良いものとそうでないものでは、同じ出力のものでも10万円程度の差が出ます。どうしたもんかと言うもの。悩まれるのも当然です。本来なら設計者と相談と言うことになりますが、暖房負荷や冷房負荷の計算が出来なければ住まい手に納得してもらえるような説明ができませんし、家全体の冷暖房負荷が計算できても各部屋の計算となると、できる方は更に限られてしまいます。南側で日当たりのいいリビングと北側で日当たりは望めない子供室。あるいは、3階建ての狭小地で1階の寝室と2階のリビングでは、冷暖房負荷は大きく異なります。家全体として計算すれば納得の冷暖房負荷でも、各室となると条件が異なりますから冷暖房負荷も当然違ってきます。1種の全熱交換機を使っているから大丈夫と言うわけではありません。換気装置は冷暖房機器ではありませんから個室の冷暖房負荷は、個別で計算する必要があります。その結果によって冷気あるいは暖気をその部屋に1時間当たり、何m3送る必要があるかがわかります。残念ながら冷暖房負荷を計算するには、Ua値や気密だけではできません。エアコンの必要な能力はその計算のできる方でなければ、家電量販店の兄さんやハウスメーカの営業マンに相談するのと50歩百歩でしょう。電気代やガス代、石油や灯油は、今後も世界の経済成長連動しながら上がっていきます。建てる前に自分の家の年間のエネルギー代がどれほどかかる家なのか必要な冷暖房能力はどれだけなのかエビデンスのある説明を聞いておく必要があります。そうでなければ必要もないのに高性能なエアコンを何台か、買わされる羽目になるかもしれません。
2023年02月24日
コメント(0)
-

より上質な
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝はマイナス2.6度の美濃地方、名古屋とは2度程度の差があります。直線距離で北へ40キロほどですが6地域の名古屋と5地域の川辺町では、やはり寒さにも差があります。暖房の仕方、つまりどんな暖房設備で暖房するかは地域によって異なりますし住まいの断熱性能によっても異なります。美濃地方の既存住宅では灯油のファンヒーターがメインで、住まいの断熱性能次第でそこに炬燵やエアコンが加わります。80年代以前に建てられた建物で小さなお子さんがいるケースでは、上記の三つを同時使用されてる場合もあります。断熱性の不足に加え、隙間風も入ってきますからエアコンだけでは温度設定を上げても、一定以上の室温にはなりません。住まいの断熱、気密の性能が上がればエアコンだけでも十分に温まりますが、エアコンからの風は残ります。風と言うのは室内の気温を一定以上にするため暖かい風を1時間当たりに一定量吹き出さないと室温が維持できないので、エアコンから吹き出される暖気です。この吹き出される風に当たると不快を感じる方が多くいます。いくら部屋が暖かくてもその風には当たりたくない。音や風など何も感じず、暖かさだけを感じたい。日本を除いた世界の暖房の定番はセントラルヒーティング。北海道では主流の暖房ですが、北海道以外でこの暖房方式を取っている地域は日本ではありません。あっても例外とお考え下さい。訳せば、集中暖房です。一か所の熱源で温水を作り、各部屋に設置してある機器にパイプで温水を送り部屋を暖めるもの。それなら床暖房と同じでは?と思われるかもしれませんが各部屋に置かれた機器は実は窓の下に置かれます。どういうことかと言うと床だけ温めていては窓から冷気が下りてくるのを防げない…一昔前のアルミのペアガラスサッシの性能は4.6w/m2・K同じように一昔前のグラスウール10Kの性能は、0.5w/m2・K性能は10分の一つまり、厚さに換算するとこのグラスウールが壁の中に20センチの厚さで入っていても、サッシのところでは2センチの厚さしか入っていないのと同じことになります。いくら気密が良くてもこの薄い断熱材の箇所では冷気が侵入してきてしまいます。その冷気は滝のように床へ降りて、床一面に広がっていきます。広がってしまった冷気を温めるより広がる前の冷気を退治した方が楽チン。ということで冷気の発生源である窓の下に暖房器具を設置することになります。サッシの性能は随分と良くなり、トリプルガラスのサッシも各メーカーが出していますが、それでもグラスウール10Kと比較すると半分ほどの性能。(昔のアルミペアに比べれば随分進歩してますが)冷え込みが厳しければ外気の気温にもよりますが程度の差こそあれトリプルガラスでもサッシの下端では冷気を感じます。風を感じたくない音を気にしたくないだけど、十分暖かく過ごしたいそんな方はエアコン暖房ではなく、セントラルヒーティングも選択肢の一つです。
2023年02月22日
コメント(0)
-

目安は?
おはようございます、紙太材木店の田原です。先週の次世代住宅建築ステップアップ研修午前中はM’s建築設計事務所の三澤文子さんの講義。MOKスクールを主宰されていて毎年のようにお世話になっいてましたが、コロナの関係でここ3年ほど休講でした。ようやく今年から再開です。以前橘商店のFBで開催の予定と言うことは知っていましたが、いつからかわかりませんでした。三澤さんから5月20日(土)から始まりますから来なさいね、と。出来の悪い生徒ほど名前を憶えて頂けているようです。講義に出ていた同業仲間2名ほど勧誘しました。今回のような研修に積極的に出てくる実務者は、常に実務者としての向上心のある人間が多いのが特徴です。大学で建築を学んで設計事務所勤めをして木造住宅を設計し始めるとナンニモシラナカッタ…建築の奥深さや己の未熟さが痛感できます。そこで未知の沼に手探りで突き進んでいくか知ってる範囲でほどほどで過ごして楽をするか5年10年15年後にどんな住宅を設計するかは、過ごした年数で大きな違いが出てきます。自分に負荷をかけてきた人は研修や勉強会にストレスを感じませんから、誘って興味があるようなら二つ返事で参加するとなります。そうでない人は何を言っても、あれこれ理由を付けてお断りとなります。そういう意味では新築や大規模な増改築をお考えの方は担当する設計者や工務店の社長が何かの勉強会に出ているかあるいは研修会に定期的に参加しているかは実務者としての姿勢を見る一つの指標になります。どういうことが起こるかと言うと同じ方向を向いている工務店や設計事務所の実務者は研修会や勉強会で定期的に会って懇親会などでは情報交換して親しくなってますから、実は親しい友人関係であったり飲み仲間?であるケースが多いお酒が飲めなくても研修会の後の懇親会には必ず参加という意識の高い実務者もかなりの割合でいますから、飲める飲めないは関係ありません。工務店や設計事務所の実務者の姿勢を見る一つの目安は今月は誰と飲んだんですか?と聞いてみることかもしれませんね(^^♪
2023年02月20日
コメント(0)
-

少し少ない補助金 ぎふ
おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝も冷え込んだ美濃地方川辺町は-3.8度です。名古屋でも氷点下ですから、いくら日中は暖かくなっても立春を過ぎたと言ってもまだまだ寒さは続くようです。三寒四温になるのはまだ少し先ですね。さて、20日が完了報告書の提出期限の環境負荷低減型ぎふの住まい補助金。建築中の関市の肥田瀬の家が該当しているので報告書一式を事務の女性に、県庁まで持っていってもらいました。帰ってきた彼女から、申請担当者の方がUa値0.3の受付は初めてですと言われたと。本当は0.26なんですけど、申請上のサッシの数値が規定されているんですね…郵送でもいいのですが、何か不備があったらと心配ですから。特に今回の環境負荷低減型の補助金は今年から新たにできた制度。一昨年まであったぎふ省エネ補助金と似ていますが、要件と補助額が多少変わりました。環境負荷低減型ぎふの住まい普及事業費補助金補助額は最高40万同じような補助金は地方の行政レベルでも出していて、肥田瀬の家のレベルだと鳥取省エネ補助金は100万+パネル63万(9KW)東京ゼロエミ210万+パネル99万(同上)やまがた健康省エネ 100万+63万(同上)札幌版次世代住宅補助160万信州健康ゼロエネ200万岐阜 40万愛知 0(国の補助金を除く)都会や地方を問わず、なぜこのような省エネで性能の良い個人の家に対して高額な補助金を出すのか?補助金は税金なのにです。省エネで性能の良い家なら次の世代、あるいはその次の世代まで住み継がれていくことが分かっているから。それは地域社会にとっても資産であるという、認識だからに他なりません。だから税金を使ってまで補助金を出します。行政は既に、性能のよい住宅は社会資産であるという認識と考えていいでしょう。一般の方はまだその認識は薄いかもしれませんが、行政はようやく欧州並みの認識になったと言えますがもちろん、それはまだごく一部…。行政によってまだ額の多い少ない、あるなしもありますが、方向としては順次そちらに向かっていくでしょう。更にもう少し先に行くと、既存住宅の改修にも同様な補助が出る時代になります。既に窓の改修に50%の補助が出ています。こちらは設置費用の半分を国が負担してくれる制度です。(超お得)誰もが家を建てる時代、建てていた時代の、終焉の始まりです。現状で800万戸の家が余っていて、2040年には空き家率40%の予測が出ています。5軒に2軒が空き家。つまり、向こう三軒両隣の5軒のうち2軒が空き家です。既存の住宅をいかにきちんとリフォームできるか(断熱、気密、換気、省エネ、耐震etc)新築の住宅であればきちんとした性能の家が建てられるか工務店の手腕が問われる時代の始まりとも言えます。
2023年02月17日
コメント(0)
-

匂いの掃除
おはようございます、紙太材木店の田原です。寒さが帰ってきた美濃地方。今朝は氷点下で、日中もそれほど気温は上がりません。救いは、日差しがあって晴れること。日射が取れて断熱性が良い家なら、昼間は暖房が不要な家になります。さて、先日打合せの時に玄関は寒くなりませんか?と聞かれました。答えは寒さ対策がしてあれば大丈夫ですが、対策がされてなければ寒くなりますし、その他にも匂いの問題が出ます。玄関は人が出入りする場所です。ドアを開ければ外の冷たい空気が一瞬で入ってきます。一般的な家の玄関はそれほど広くありませんし、リビングなどとは何らかの仕切りがありますから閉じられた空間です。狭い空間の空気が人が出入りするたびに、ある意味外の空気と入れ替わるわけで玄関の空気の温度は下がります。加えて床より10~15センチ一段下がっています。玄関ドアの両サイドの外壁に面した基礎コンクリートは室内側から薄い断熱材が張ってあっても、他の壁に比べれば断熱性は低いものになります。ましてや気密がきちんと取れていなければ冷気も侵入してきます。一条工務店でも初期のi-smartでは玄関の基礎コンクリートに、張られたタイルで結露が発生しています。一種の全熱交換だから大丈夫とか床暖だから大丈夫G2だから大丈夫と言う訳ではありません。それと玄関は靴を脱ぐところです。しかも家族全員の靴が、狭い空間の玄関に置かれます。いつも履く靴だけでなく、普段履かない靴も置かれます。当然、匂いも籠りますが同じ匂いが続くと人の嗅覚は鈍くなります。順応と言いますが、1.2分でその匂いは感じなくなってしまいます。匂いが籠っているイコール換気が出来ていないイコール寒い空間イコール結露が発生しやすいですが、住んでいる本人はその匂いをあまり感じない。他人の家に行ったときに玄関に入ると独特の匂いを感じます。靴が何足もあるいは何十足もあるわけですから匂いがして当然なのですが、換気が出来ていれば相当程度匂いは抑えられます。同時に玄関の換気が出来ているということは、匂いのする空気寒い空気が排出され新しい空気つまり暖かい空気、匂いのしない空気が玄関に入ってくることを意味します。そのような設計、対策がなされていることが、玄関には必要です。ご自分ではわかりませんが玄関が寒ければ、匂う玄関と思って間違いはありません。あなたの家の玄関が他の部屋と同じように暖かかければ心配しなくても大丈夫ですが、寒ければご自分では気づいていなくても訪問してきた人は一瞬でその匂いを感じ取ります。玄関と言うことできちんと整理整頓し掃除をして見た目をきれいにしても、設計がNGなら匂いの掃除はできません。
2023年02月15日
コメント(0)
-

3方良しの住まいは
おはようございます、紙太材木店の田原です。最近はパッシブハウスに縁があって先月末には、津市の飯塚さん設計された森大建地産さんのパッシブハウスの申請物件で研修だったことは以前書きました。週末はパッシブハウスのオープンデーと言うことで、一宮の中日サニオンさんでお泊り。工務店仲間と深夜まで建築談義となりました。パッシブハウスもちろん機会があれば建ててみたいですが、鎌田先生の言われるところの住宅におけるF1フォーミュラーカー。一般に普及させるにはハードルが高く建てられる人は限定的。F1カーより性能は一段低くても、十分高性能な家を広く普及させることが大切と鎌田先生は言われてます。実際建てられているパッシブハウスの多くは、経営者の自宅兼モデルハウスや純粋なモデルハウスもかなりありますし、個人の建物の場合でも経営的には利益は全く無い上に時間と労力は想像以上に取られます。それでもパッシブハウスを建てるのは、そこで得た知見が自社の家づくりに活用できるから。海外に住んだことのない人が海外ではこうだ、あーだと言っても始まらないのと同じ構図で、パッシブハウスを建てたことが無いのにそれをどうこう言ってもはじまりません。工務店仲間の中には全棟パッシブハウス、それを標準にすると言ってるところもありますが、相当程度ハードルが高くなりますし価格もほとんど利益のないもの…。きちんと会社が継続できる価格にする必要がありますから、従来の価格では無理でしょう。標準にすることで経営を圧迫するようでは、元も子もありません。ある一定以上の断熱性能レベルであれば、空調設計と日射の制御が(ここがポイントですが)きちんとできていれば、夏も冬も十分満足のいく生活ができます。年間の冷暖房費に違いは出てきますが、室内での暑さ寒さの暮らし易さの感覚はそれほど変わりはありません。新住協もPHJも目指す方向は同じ。低いエネルギーコストで、暮らし易い住まいをより多くの人にしてもらいたい。ついて回る課題はより多くの人の手の届く価格であること。良ければいいというわけでは無いところが頭の痛い所。耐久性やメンテナンス性も考慮し、大工さんをはじめとする職人さんが喜んで仕事に取り組める環境整備も大切。設計者と工務店の経営者の責任は、とても重いものがあります。住まい手も職人さんも工務店も地域社会も次の世代の人達も皆が良かったと思える家が求められる時代です。
2023年02月13日
コメント(0)
-

暖房代を節約して 電気温水器を使う
おはようございます、紙太材木店の田原です。曇り空で4度の美濃地方。一日中、雨か雪で最高気温は7.8度氷雨の降る寒い一日になりそうです。先日、事務所で仕事をしていると配送してきた荷物をどこに置きましょうかとトラックの運転手が来ました。いつもの業者だと置く場所は決まっているので事務所には伝票だけを置きに来るのですが、初めての業者さんでしたから案内するよと倉庫に連れて行きました。荷台の中には様々な建築資材や設備の資材があったのですが、その中に冷蔵庫ほどの大きさのタンクがありました。これって、ひょっとしてエコキュートのタンクじゃなくて、電気温水機器のタンク?ええ、そうですよ。時々配送しますから結構、使ってる家がありますよ。未だに電気温水器・・・田舎では都市ガスが引いてあるところは限られています。給湯は主に台所とお風呂。少し前の昭和の家では、台所はガス瞬間湯沸かし器でガス。お風呂はプロパンガスか灯油ですがプロパンガスは灯油に比べ高いので、勢い、お風呂は灯油と言う家が多いです。ただ、電気温水器は一度設置すれば手間はかかりません。灯油のように補給の電話をする必要はありません。年末、お正月だからと言って残りの量を確認して、電話する必要がありません。ある意味、楽チンなんですね。深夜電力を使えば電気代もお安くなりますが売り込みのうたい文句でした。ただ、時代は昭和から平成、令和へと変わっています。電力会社からの請求書を見れば、電気代が高騰していることは誰の目にも明らかです。昭和な家ですから断熱や気密は考えられていない寒い家。その家では恐らく、電気代を節約するため暖房代を減らしている可能性があります。このブログを読まれている方は全く問題ありませんが、ご自分の実家はどうでしょうか?ご両親が建てた30年ほど前の家では床に断熱材が入っている可能性はかなり低いでしょう。まして、気密なんてという家、自分自身がその家で育ってますから凡その寒さは想像できるでるはずです。年を重ねていくにつれ自分が我慢すればと考えたり、あるいは変化を受け入れる気力が衰え、もう先も長くないからこのままで・・・高い電気代に暖房代を節約する。だけれど、電気温水器が壊れたからとそのまま同じ電気温水器を取り付ける。電気温水器の電気代は、エコキュートの3倍から4倍です。差額の電気代で今より暖房を増やすことができます。エアコンで暖房するか灯油で暖房するかで暖房代は異なりますが。エアコンで暖房すれば、暖房を増やしてもお釣りがくる計算です。電気温水器がまだ使えるからと言うのならせめて温水器が壊れた時には、エコキュートに交換すれば暖房を今より多くしても大丈夫ということを日ごろから伝えておけば、少しは親孝行したと言えるかもしれません。暖房代を節約して電気温水器を使い続ける矛盾。壊れても電気温水器を使い続ける人に、知ってもらいたいものです。
2023年02月10日
コメント(0)
-

紺屋(こうや)の白袴
おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日は暖かい日でしたね。今日も少し気温は下がりますが、予報では14度くらいになるとか。でも、今朝はまだ2度ですからそれなりに寒い朝です。事務所の寒さ対策のご紹介上の写真は事務所の通用口ですが足元にサーキュレーターを置いています。少し勉強されている方は、コールドドラフト対策かと思うかもしれませんね。実際、単板の一枚ガラスですからこの通用口に限らずコールドドラフトが発生します。特に私の座席の背中側と右手側はガラスのなので、事務所の中で一番寒い場所になってます。サーキュレーターはコールドドラフト対策もあるのですが、実はドアクローザーの寿命が来てしっかり閉めることができずスキマが出来てるんですね。約1センチの幅で縦2m分上下で1.4m分なので340cm2の隙間です。340cm2と言うことは18.4センチ角の穴が開いているのと同じです。35坪、115.7m2の家だとC値2.9侵入してくる隙間風の風速は計ってみると毎秒30cm/s0.184x0.184x0.3x36001時間当たり36.5m3の外の空気が入ってきます。事務所の床面積は57.6m2なので36.5m3/57.6m2=0.63床から63cmの高さまでは外気の冷たい空気の溜まり場ということに。いくらエアコンで空気を暖めても膝から下の床に近い所は寒い、冷たい…それでなぜ、サーキュレーター?侵入してきた冷気を吹き飛ばしても室内に入ってくることに変わりはないわけで、結局は床近辺に滞留するなら足元対策は、これでしょ。北海道断熱修行の旅のために購入した雪靴たしかに足元は暖かいんですが、膝から脛あたりまでが寒いんですね。冷気があることに変わりありません。と言うことで、こうなりました。侵入してきた冷気が室内の床近辺に拡散する前に、まとめて薪ストーブにぶつける。及第点が貰えそうな対策ですが、ドアクローザーを早く直せと言われればその通りで紺屋の白袴・・・住まいの寒さの原因は様々ですが隙間風もその一つ。スキマがあれば、いくら断熱材を厚くしてもいくら暖房しても冷気が侵入してきます。中気密なんて言葉がありますが、意味不明な言葉です。
2023年02月08日
コメント(0)
-

最高のはずが最低やったに
おはようございます、紙太材木店の田原です。今日の日中は暖かくなる予報の美濃地方。でも、今は氷点下2度…お昼近くまで寒いですかから、しっかり暖房しましょう。とは言いながら電気代がびっくりするほど上がってますから、難しい所ですが。風邪をひいて病院に行けばそれなりの時間とお金がかかりますし、風邪薬も意外に高いものです。電気代と天秤にかけるわけではありませんが家族の何人かが風邪を引けば、その合計は電気代より高くなります。恐らくこれからも、電気代の上昇が止まることはないでしょう。年に3%上昇すると40円の電気代は10年後には53.7円34.4%上がることになります。あなたの会社の生産性が同じように上がってれば給料も同じように上がりますが、そうでなければ電気代の上昇の方が給料の上昇スピードを上回ることになります。防衛策は3つ。太陽光パネルの設置冷暖房負荷を少なくするための断熱改修歯を食いしばってひたすら我慢・・・新築を検討される方はデザインやインテリアを言う前に、冷暖房負荷がどれくらいあるのか?パネルをどれくらい載せるか?こちらの検討が先です。中古住宅の購入を検討される方は断熱改修にどれくらいかかる家か?パネルは載っているか?断熱改修にかかる費用と改修後の冷暖房負荷はどれくらいになるか?この試算ができる設計者や工務店との相談は必須です。既に家を建ててしまった方もパネル設置の検討は選択肢の一つです。それは試算をしてみればわかりますが、優先度の高い選択肢です。パネルの設置費の投資回収年数は10年以内。電気代が高騰していけば、投資回収年数は更に短くなります。もちろん、中古住宅の購入と同様、断熱改修も選択肢の一つです。売電価格が40円とか30円台だった方は自分の家は大丈夫と思っているかもしれませんが、買取価格が8円になったら支払う電気代がいくらになるかを考えなければなりません。支払う電気代の少ない今のうちに、内窓の設置で更に冷暖房負荷を下げておく。電気代が上がってしまってからでは、恐らくその気にはなりません。内窓の設置で国から50%補助が出るこの政策は、まさにこの人達のためにあるようなもの。過去10年以内に建てられた家でZEH仕様ならそれなりの断熱性はありますが断熱性能等級5.6.7が出てきた今では、既に過去の断熱性の家。しかしその家に内窓を設置すれば、冷暖房負荷にかかる電気代は相当程度削減できます。そんな家に住んでる方こそ、是非一度検討してみてください。自分の家はLOW-Eペアガラスだから大丈夫そう思っている方こそ、検討の余地があります。昨年まで断熱性能等級では最高等級の42025年には残念ながら最低等級になります。更に2030年には既存不適格に…。
2023年02月06日
コメント(0)
-

やらかした失敗
おはようございます、紙太材木店の田原です。まだまだ寒いのに花粉の季節が来たようです。鼻水とくしゃみが、時折出るようになりました。そういえば明日は立春。お彼岸まではまだ間がありますから、暖かかく過ごしましょう。さて、以前紹介した窓の補助金。半分の50%補助で、上限が200万という制度。とてもいい制度で予算規模も相当程度ありますから、多くの人が利用できます。但しちょっと気を付ける点がありますので、お伝えします。私が昔やらかした失敗で、ダイニングキッチンのリフォームです。工事の内容はキッチンの入れ替えと壁天井のクロスの張替え、それにアルミサッシのガラスだけをシングルからペアガラスに交換するというもの。何が起きたかと言うとガラスの結露はほぼ解消しましたが、キッチンの合板フローリングの床に結露が出るようになりました。今ならガラスだけ交換のリスクはわかるのですが、当時はまだ未熟でした。床はリフォームの対象外だったので、床の断熱材の有無を確認してなかったんですね。これはどういうことかと言うとリフォームをする前はサッシのガラス表面で結露することで部屋の空気の除湿をしていたのですが、ペアガラスにすることでガラスの表面温度が上がり、そこでは結露しなくなった訳です。でも、部屋の中の水蒸気はリフォーム前も後も同じように発生しています。となると、部屋の中の水蒸気は温熱的に一番弱い所つまり、部屋の中で一番冷たい所(露点以下の場所)はどこかを探してそこで結露することになります。80年代に建てられた家の多くはHMの家でも、床の断熱材はほぼありません。有っても25ミリ程度でしょうか。合板のフローリングの表面が露点以下になれば結露することになります。さて、では床だけ気を付ければいいのかと言うとそうではありません。目に見えない壁の中も露点以下になれば、結露の可能性が出てきます。もちろん、天井裏にある屋根合板の裏も結露の可能性が出てきます。断熱改修や温熱環境の改善には床、壁、天井、サッシの断熱性のバランスが大事で、どの場所も露点以下にならないような断熱材が入っている必要があります。同時に、水蒸気はとても小さくビニルクロスが張ってあっても透過していきますから、防湿層の設置もセットで考えなければなりません。サッシの断熱強化だけでは断熱のバランスが崩れ、不具合が起こる可能性がありますから設計者と十分相談して、断熱改修を進めて下さい。床の断熱材の有無は、床下点検口から。壁の断熱材の有無は外壁のコンセントボックスを外すと内部が見えますし、床下の外壁周りの土台の上の根太の隙間から。天井は押し入れなどにある屋根裏の点検口から、確認ができます。他人任せにせず、ご自分で確認されることをお勧めします。
2023年02月03日
コメント(0)
-

いくつになっても
おはようございます、紙太材木店の田原です。昨日はマイナス4度、今朝はマイナス3度。10年ほど前の1月は毎日そんな気温だったと記憶してますが、最近はこの温度が続くのは稀。でも、気になって調べてみるとお隣の美濃加茂市の1月の最低気温の平均2013年 -2.1度2003年 -2.1度93年 0度83年 -2.0度2023年は -1.0度記憶と言うのは当てにならないなと…でも、まぁ美濃加茂は隣の町だから川辺町はもう少し低かったかと。昨日は次世代住宅建築ステップアップ研修午後の空調の講義は、ミライの住宅の森さん。160ページのPDFを2時間45分の授業でマスターするというもので、前日に資料が送られてきて宿題と予習をして来いと。この手の研修の参加者は、実は他の研修会や見学会でも会っています。先日の津のPHJや新住協の勉強会、あるいはBISの研修や試験など。これは日本の住宅自体が従来の住まいに比べて大きく変化していることと、もう一つの大きな要因は、住まい手になる方の情報や知識のレベルが格段にアップしていることによるもの。5年ほど前までは実務者と一般の新築検討者ではその情報量や知識の差は10倍以上ありましたが、今では、相当程度。その差は縮まっています。一般の勉強されている方の方が、実務者より知っているケースも見られます。専門知識が必要な分野、例えば医療の現場で言えば外科は外科ですし内科は内科内科でも肝臓が専門であったり、循環器が専門であったりと分かれます。建築も実は分かれていて大きく分ければ、意匠と構造と設備の三つ。住宅で要求される空調は設備系の勉強が必須。でも、設備の勉強をした人の多くは空調設備の大きな会社に行く割合が高く、一般の設計事務所を開設する人の多くは意匠が専門の方が多い。必然的に、住宅設計では空調の事は専門外の人が多くなることに。松尾さんや森さんのように設備を専門に学んで、住宅を専門にしている実務者はそんなに多くはありません。加えて住宅建築の分野での実務者向けの空調設計講座となると、ほぼ皆無。住宅の空調は一種換気や三種換気、全熱交換等いろいろあります。暮らし易い温熱環境、あるいはそれを実現するための省エネな環境をどのように設計し施工するか。一種の全熱交換機があるから大丈夫省エネになるから大丈夫エアコン一台で大丈夫空調を勉強すればするほど、軽々しくは言えません。そのように言われたらなぜ大丈夫なのか、納得のいくまで聞く必要があります。残念ながらまだ、一般の方も勉強しなければなりませんが、実務者はそれ以上に勉強しなければ時代の流れに置いて行かれます。
2023年02月01日
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 家を建てたい!
- 鹿児島県枕崎市寿町【売地】 宅地向…
- (2025-11-14 11:22:24)
-
-
-
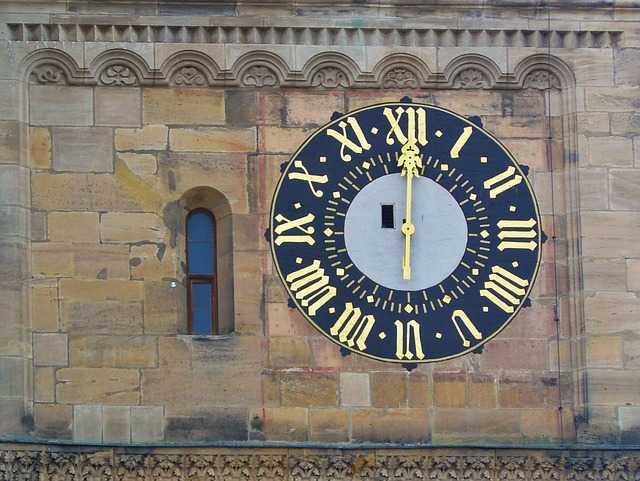
- 風水について
- フライングスター(玄空飛星派)風水…
- (2025-11-10 18:05:38)
-
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- 【感謝祭SALE】澤井珈琲 ドリップパ…
- (2025-11-14 13:00:04)
-







