2021年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

観蔵院 & 嶺北向庚申様
訪問したばかりだったけど、満足できなかった桜を見るために再び鵜の木の増明院を訪ねた3月27日のブラブラ…… 増明院を後にして、こんな道……桜の木がある寺社を頭に描いて歩きます。埋められてしまいましたが、六郷用水の跡です。 女掘(おなぼり)緑地……って言うんだね。 徳川家康の命により、多摩川左岸の六郷領(現在の大田区)を潤す農業用かんがい用水路として開削された由緒ある六郷用水。用水奉行・小泉次大夫が開削したんだと。六郷用水が完成したときに次大夫さんは70歳を越えていたけど、管理能力は抜群だったんでしょう。 昨年、梅の季節に訪問した観蔵院へ…… 観蔵院山門……右に薬師堂 桜ありました。記憶力は低下してるんだけど、良かった。 真言宗智山派・玉川八十八ヶ所霊場第五十七番札所 いつもの1枚…… 本堂にご挨拶して…… 弘法大師様にもご挨拶…… 桜が咲いているとまったく景色が違います。 参道を挟んで左右に並ぶ梅の木……左が紅梅で右が白梅。昨年は梅の時期でした。「昨年2020.2.15訪問時の観蔵院」 増明院の南側……私の後方の女掘緑地へと続く六郷用水の跡。 少し進むと結構な下り坂……六郷用水は前方の上流からこちらに流すため、この場所を最大7.5mも掘り下げて水路としたそうです。ツルハシ⛏とノミだけでの掘削はしんどかったろうな~「女堀(おなぼり)」のいわれには、「人手不足で女性がかりだされた」とか「女性で活気づけた」など諸説あるらしいけど、女性に良い所を見せようと頑張った男性は少なくなかったことでしょう。男ってのは結構単純だから…… 美輪明宏が歌う「ヨイトマケの唄」が浮かぶ。40年以上前に生歌を聞いたことがあります。ヨイトマケとは、滑車の綱を引っ張るときのかけ声「ヨイっと巻け」が語源だと。 話がそれたけど、写真左のコンクリート塀に…… すき間に石段発見…… 嶺北向庚申様……四方除けのために嶺村集落の周囲に置かれた4基の庚申塔の1基。東向・南向・西向を含めて、これで制覇しました。良かった良かった。 細い石段を上ると大小二つの祠…… 明治37年(1904年)の手水盤…… 赤い編み物はお地蔵さんのよだれかけかしら。小さい祠には大きなワラジが…… 駒型の青面金剛像で、踏みつけられた邪鬼、三猿が描かれています。享保7年(1722年)だから300年前の造立。左手前の三猿だけの角柱も庚申塔なのかしら? 小さい祠には三猿だけ……こんなの見たことなかったはず。 嶺北向庚申様の正面は、坂の頂上にあたる場所にある小さな公園……六郷用水跡を左に辿っていくと23日に出会った「嶺西向庚申」があります。 京急蒲田・梅屋敷あたりの散歩日記を書かないとなりませんが、桜を優先してしまいました。きっと明日も桜でしょう。ブツブツも書きたいけど、今日はこれでおしまい。「厚労省」職員さんは「功労賞」をもらえるようにお願いします。統合前の「厚生省」は「更生省」ってところか……やーめた。
2021.03.31
コメント(0)
-

4日後の増明院
3月23日に訪問した増明院だけど、少し早かったので27日に出直してみました……これから初診外来とやらに行かなくちゃならないから、今日はノーコメント。【3月23日】【3月23日】【3月23日】 東京の桜はボチボチ終わり……また来年のお楽しみです。 ※ 「3月23日の増明院」
2021.03.30
コメント(0)
-

大崎観音寺
なぜか置き去りにしていた2月7日のコピ散歩…… 大崎鎮守居木神社参道口の隣に…… 観音寺会館と墓地の間に…… 観音寺参道…… 石段をよっこらしょ……『当初は目黒川居木橋の南に所在していたのが、数度の水害を被り、これを避ける為に元禄年間、一村挙げ現在の高台の地に移転をしたとされます。』 ※ 以下『』内容は天台宗東京教区HPより。 弘治年間(1555~1558年)創建と伝えられ、開山は光海和尚。 山門扁額……金剛山 いつもの一枚…… 観音寺本堂……フルネームは金剛山圓通院観音寺。かつては東雉山松琳院と号したものが、いつの頃か今の名称へ改まったと……本堂後方に居木神社… 本堂扁額……東京三十三観音霊場2番札所『本尊仏は如意輪観世音菩薩でありましたが、滅罪と祈願と分つに至って別堂を設け現本尊仏の釈迦如来を安置…… 本尊の釈迦如来坐像は、像高51.6㎝(一尺七寸)木造・漆箔。玉眼嵌入、肉髻珠と白毫・水晶製。大衣を通肩にまとう定印の像です。胸前部の裏面に記された墨書銘より、江戸時代前期、元禄7年(1694年)の作と知られます。なお本像の両脇侍、文殊・普賢両菩薩像は昭和後期の作です。』 堂内右の観音堂扁額の下に安置されているのが如意輪観音様でしょう。六道それぞれの衆生を救う6体の観音の一尊です。六道は、先日の増明院六地蔵で書きましたが「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人間道」「天道」のこと。お救い下さるそれぞれの観音様は順に「聖(しょう)観音」「千手観音」「馬頭観音」「十一面観音」「不空羂索(ふくうけんさく)観音または准胝(じゅんでい)観音」そして「如意輪観音」でした。 ※ 玉眼「嵌入(かんにゅう)」とは、はめ込むこと。 ※ 「肉髻珠(にっけいしゅ、にっけいじゅ)」とは、頭部正面にある智恵を象徴した朱色の珠(たま)。ほとんどが水晶もしくはガラスの透明な珠で、底を赤く塗って赤色を表現すると。 ※ 「白毫(びゃくごう)」とは、仏の眉間みけんのやや上に生えているとされる白く長く柔らかい毛。「あぁ、おでこにあるな~」この毛は右巻きに丸まってるんだって。伸ばすと、仏身が一丈六尺の仏で一丈五尺もあるそうだが、この白毫からは光明が放たれていると。(浄土真宗大辞典より)『当寺の所在地である大崎の名は江戸時代から有る古い地名で、明治22年に上大崎村と下大崎村・谷山村(ややまむら)居木橋村(いるぎばしむら)桐ケ谷村など、現在のJR 山手線の大崎・五反田・目黒の各駅の周辺が統合されて大崎村の名称になり、明治41年に町制が敷かれて荏原郡大崎町に、昭和7年品川区へ編入されて品川区大崎に、そしてこの旧品川区と荏原区とが昭和22年に合併して現品川区ができ50年が過ぎました。』(天台宗東京教区HPまま) 延宝5年(1677年)造立の笠塔婆型庚申供養塔と、昭和17年(1942年)に造られた馬頭観音像とがあるそうですが、見当たりませんでした。残念…… 右にソメイヨシノ、山門左は枝垂れ桜でしょうが時期が早かったです。 山門で振り返り、一礼して失礼します。 道路に出てから気付いたので戻り…… パチリ……三界萬霊塔でした。 品川区立第一日野小学校跡……山手通りのビルの片隅・西五反田7-2 2010年に移転したらしいけど、併設する品川区立五反田文化センターってのがすごい。「音楽ホール(地下1階)」「スタジオ(1階・5部屋)」「五反田図書館(2階)」に「プラネタリウム(5階)」だって……とてもワクワクしますが、教育にお金をかけるのは良い事です。ただ、コロナ禍にあっての運営は充分にご留意くださいませ。
2021.03.29
コメント(0)
-

桜坂 & 多摩川浅間神社
3月23日、桜を求めてちょこっと散歩…… 桜坂通りの坂下に有慶山東光院……玉川八十八ケ所霊場55番の真言宗智山派の寺院だけど、2017年3月28日に訪問したので山門で合掌して失礼しました。4年も前の事で、寺社にはさほど興味がなかったのでしょう。日記を振り返ったら弘法大師像は単独で撮っていませんでした。しかし、この日訪問した増明院も密蔵院も同宗同派でした。南無大師遍照金剛…… さてさて、桜坂下までくるとこの古そうな石碑……以前は細長い木製の道標だったのに、いつから変わったのか? 桜橋……去年も同じような咲き具合だったかと…… 旧中原街道なんだって…… 石垣にはさまれた切通しの坂道……一生懸命に削ったんですね。大変だったでしょう。坂下方向で遠くは武蔵小杉。 坂上方向……昔は「沼部の大坂」と呼ばれ、勾配がきつく荷車などの通行は大変だったと。そうでしょうね~ 両側の桜が植えられたのは大正時代のようです。 かつては荷車や旅商人の往来でにぎわい、坂道の両側には腰掛け茶屋などがあったと……車を停車させて桜を撮りに降りるドライバー。多くの女性は下から見上げて撮るんだけど、こんな場所では危ないよ~ 右の石ブロックは「オリンピック東京大会記念 国旗掲揚塔」……昭和39年(1964年)10月10日。57年目になるんだけど、時の流れは早い。今年は本当にやるのかしら? 現在の中原街道を越えて多摩川駅方面に……東急多摩川線通過 多摩川浅間神社……ひょっとしたらと行ってみたけど寂しかった。 食行身録之碑……勝海舟の直筆。2019年12月4日の訪問時には撮り忘れたので…… 食行身録(じきぎょう みろく)ってのは宗教家でもあり富士講中興の祖だった伊藤伊兵衛と言う人物の行名らしい。行名とは富士講修行者としての名前で、伊藤食行身録あるいは伊藤食行とも呼んだそうです。 境内に桜の記憶はなかったけど、一応お詣りだけして見晴台に行ってみることに。昨年「燈籠とトイレが新しくなりました」とコメントを頂戴していたのに、すっかり忘れていてた私。次回のために、しっかり頭に刻み込んでおきます。 見晴台から…… 残念ながら富士山は臨めませんでした。 と言うことで、23日の桜巡りは終了です。 この日は寂しかった鵜の木増明院を昨日リベンジしてきましたが、また今度…… ※「2019年12月4日訪問の多摩川浅間神社」
2021.03.28
コメント(0)
-

密蔵院 2021.3
大田区鵜の木の増明院から鵜の木松山公園を抜けた2月23日…… 大田区西嶺町から田園調布南に入ると……昨年同様の景色がありました。 密蔵院…… やっぱり桜には青空が一番…… 花曇りではちっとも引き立ちません。 真言宗智山派・玉川八十八ヶ所霊場 第五十六番札所 山門に国際仏旗がはためいています。 普段は遠慮するのですが、屋根が見えたので墓地に…… 花御堂……ってのは、お釈迦様誕生時の立像を安置する、花で飾った小さいお堂のこと。花に囲まれ、なおかつ桜の木の元に……お釈迦様の誕生日である4月8日(木)に花まつり及び仏生塔入塔霊総供養法要が執り行われるみたいです。 仏生塔……『お釈迦様がお生まれになった時、7歩あゆまれ「天上天下唯我独尊」と唱えられたと伝えられている。これは釈尊ただ一人が尊い存在であるということだけではなく、我々皆一人ひとりが尊い存在であるということである。(後方の石碑より)』 この立派な宝篋印塔(ほうきょういんとう)も、昨年は気付かなかった。ルビは連れ合いのためにふりました。為念 桜がメインだったけど、やっぱり青面金剛は素通りできない私…… 青面金剛及び二童子四夜叉立像……像高91㎝の大型青面金剛像。元禄7年(1694年)の造像。 ちゃんと真言唱えてきました。 レグルス……「KEY COFFEE」の袖看板上部にある電光掲示板に、「路上喫煙は止めましょう」と文字が流れたから、「店内で吸え」ってことだと思い、コーヒーかビールを飲ませてもらおうと入った私。残念ながら「禁煙です」とのこと。2名がランチしてましたが、ドアは開け放ってあり換気対策OKの店でした。 六郷用水跡を多摩川方向にすすみ、東光院を右に行きます。でも、今日はここでおしまい。 ※ 「去年の密蔵院日記・2020.04.07」《おまけ》 田向公園の通り……2月25日8時42分……モーニングに向かった私。 同日の円融寺本堂前…… 昨日、予防のための電気治療に行く途中…… 明日から雨らしいから、桜は今日で見納めかもしれません。どこか行ってこようかしら……
2021.03.27
コメント(0)
-

嶺西向庚申と六郷用水
3月23日の桜見学…… 鵜の木松山公園を後にすると……ディズニーお好きなんですね。 しんせい児童公園……大田区鵜の木を北西に 大田区鵜の木を北西に……左には多摩堤通りが走っているけど、私は裏の道。 カフェ ポルカ……一年中クリスマスなのかな~ 寄ってみたかったけど「禁煙」の上に「CLOSED」でした。 鵜の木3丁目から西嶺町の変則五差路へ……何かあるぞ~ 多摩堤通りを歩かずに大正解!!!……偶然出会えると嬉しい。樹木もいいな~ 嶺西向庚申発見!!!……西嶺町26 四方除けのために嶺村集落の周囲に置かれた4基の庚申塔の内の1基ですね。 嶺白山神社境内の「嶺東向庚申塔」と御嶽神社の近くの「嶺南向庚申」は去年拝見しました。観蔵院の南側にある「嶺北向庚申」は、ここから300mほどの場所だけど、見過ごしていました。駄目だな~ 駒型の庚申塔……邪鬼を踏みつける青面金剛。 六郷用水が流れていた証にしているんでしょう……誰がエサをあげるのか? 可憐な花…… 六郷用水が流れていたあたり。遠くに桜…… この辺りから細い水路が顔を出します。女性の一人散歩が目立ちました。 満開…… 湧水を利用して、現在も人口の流れが造られています。右側は太田図書の敷地。 ここは昨年3月24日に逆から歩きました。 みなさん、見上げて写真を撮ってます。 密蔵院の桜……密蔵院は真言宗智山派だし、この日もお参りさせたいただいて境内を拝見しましたが、今日はここれでおしまい。《独り言》 鶏と海老の炒めランチ……昨晩、とても気分を害したことがあって、重い気持ちを引きずったままだったからでしょう、いつもは美味しい食事なのに今日は不味かった。休肝日を返上して飲んだウイスキーが抜けていないわけではないのに。生きていれば、たまにはこんな日もあるよねと自分に言い聞かせつつも、どうせなら食事は美味しくいただきたいもの。私より辛い思いをした連れ合いはどうだろうか? 明けない夜はない、止まない雨はない、なんて慰めにもならないけど、少しだけでも元気出してね。 こんな環境なら大丈夫でしょうが……地方自治体が独自に実施している宿泊割引などの観光促進策について、政府は4月以降、一人あたり最大7千円分の再生支援をすると。感染が落ち着いているステージ2以下の都道府県に限って観光業を支える狙いだと言うが、人が動けば増えることは実証済みなのに。ワクチン接種だって進んでいないんだから、「得だから行ってね~」と国民をあおる前に、土産物店を含めて観光業に直接支援はできないのか。変異株が急増しているのに、分科会の意見には耳を傾けず平気でいられる政府には腹が立つ。地方自治体の財政支援となるが、サーキットブレーカーとやらも厳重に準備されたし。ズルズル引っ張り続けるのが常だから……
2021.03.26
コメント(0)
-

鵜の木松山公園
以前訪問した増明院に桜を見に行った3月23日…… 住宅街のど真ん中に鎮座する「鵜の木松山公園」入り口…… 去年「鵜の木一丁目古墳」の存在を発見した際、この公園に「横穴墓(おうけつぼ・よこあなぼ)・Tunnel Tomb」があるって知ったので、寄ってみました。 入り口を進むとジグザグのスロープ……右に行ってから左へ折り返すと…… 看板ありました。 公園の工事中に発掘された、古墳時代末期から奈良時代にかけての有力者の墓。この横穴墓は大田区の埋蔵文化財として保存されていると。入り口は透明な樹脂で塞がれていたから、覗いたけど真っ暗で何も見えなかった。照明が点くらしいけど、センサー故障だったのかしら? 大田区周辺に見られる特徴的な切石羨門構造をもつ貴重な横穴墓らしいから、見たかったな~ 台地斜面に横穴を掘ったことが良く分かります。 7号まであったらしいけど、その中でこの6号墓が最も大きいんだと。その他は塞いじゃったみたいでした。大田区周辺の台地斜面では、約260基の横穴墓が発見されているんだって。 スロープを桜の方に歩いて…… 振り返ると……なかなか綺麗でした。 でもって上がると…… 広い広い…… ちょいと遊んで……心地良い風が吹き抜けていきました。 南西方向に松松松……地元では「松山」と呼んでいたこの松林のある広場を、公園として整備したのは平成19年(2007年)。その時に横穴墓が発掘されたのね。 向河原、武蔵小杉のビルを眺め、高台だということがはっきり分かります。古代人がこの広場から見た景色はどんなだったか……大山や富士山はきれいに臨めたでしょう。 北側にも松松松……広さは約2,350坪だって。 北側の松の後方に行ってみたら、丘陵……元は「鵜の木公園」で、整備された松山と合体して「鵜の木松山公園」になったんだって。先輩だから「鵜の木」が先なのね。 大きな井戸……誰が何のために造ったのか? 何か祠があると思いきや…… 水路か??? 祠は、人工の小さな滝を流すんですね。夏には子供たちのジャブジャブ池になるということ……納得。 下りが怖い最近です。こちらからは車椅子やベビーカーは入れませんね。 旧鵜の木公園もそこそこの高台でした。 と言うことで、一山越えてきた私は、以前歩かなかった六郷用水の一部を通って密蔵院に向かいましたが、続きはまた……
2021.03.25
コメント(0)
-

増明院 & 鵜の木一丁目古墳
山門前に見事な桜の木があったな~ と、昨年2月15日に訪問した増明院を尋ねてみることにした昨日です。 増明院山門……立ち並ぶ立派な桜の木々ですが、ちょっと早かったようです。壮観な眺めを期待していたんだけどな~ 山門前右の木だけ…… 部分的にこんな具合…… 真言宗智山派・玉川八十八ケ所霊場58番札所…… きれいきれい…… 東を向いた弘法大師様の後ろから……南無大師遍照金剛 あの大木が咲いたら、本当にきれいだろうな~ 週末にもう一度行ってみるか? 六地蔵……前回は向かわなかった墓地の入り口に。昭和48年奉納「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人間道」「天道」……私たちが生まれ変わる可能性がある六道の世界に出向いて衆生(しゅじょう)を救済してくれるのが地蔵菩薩でした。だから、たいてい墓地内や近くにいらっしゃるのね。六道のどの世界に生まれ変わるかは、生前の行いや思いなどに応じて決まる。地獄道を含む三悪道に生まれ変わらないよう、行いに注意しなければ…… 山門の上を仰いで失礼しました。 増明院の裏側のこの坂を下ると東急多摩川線・鵜の木駅だけど、私の後方に…… 前回見たから寄ってみたら……ななな???なんでやねん!!! 掘られてるじゃないの……しかし、小さいけどこの重機はどうやって上がったの? 鵜の木一丁目古墳……引っ越すのか? それとも再調査か? そして、こんな道を「鵜の木松山公園」に向かいました。その後、ちょうど昨年の今日・24日に訪問した「密蔵院」と「桜坂」を歩いてきましたが、続きは次回…… 昨年の「鵜の木一丁目15番古墳と増明院」 さてさて、今日は何をしましょうか……やらなくちゃならないことはたくさんあるのに、怠け者の私です。あかんな~
2021.03.24
コメント(0)
-

カイドウ咲いた
天気が良いから散歩に行くので、これでおしまい。 10時31分……桜同様に、あっという間に開花しました。美人の代名詞なんだって。 春です。散歩日和です。
2021.03.23
コメント(0)
-

桜開花状況 2021.3.22
先週16日には開花宣言できなかった近隣の桜。18日に車窓から眺めた目黒川の桜も咲いていなかったから、今朝、どうなったか見てきました。 田向公園近くの定点観測所……満開には程遠いけど… オオシマザクラは早いです。 立会川緑道……木々によって個体差がありますが…… これは結構咲いてました。左右に枝を伸ばして、電線が気になるけど大丈夫なんでしょう。 円融寺近くの緑道は、本数がめっきり少なくなったので寂しいけれど、このぐらい咲いていると綺麗です。 この木は部分的開花だったけど春到来です。 円融寺本堂裏の真公稲荷脇……こちらもまだまだ。境内の桜もまだまだでした。 毎年チューリップが並びます……お好きなんですね。 チューリップの花言葉は「思いやり」……赤色は「愛の告白」で、紫色は「不滅の愛」、そして黄色は「望みのない恋」だって。黄色いチューリップをもらったら気を付けましょう……自分に言っているのではありません。為念 でもってモーニング、サラダ半分…… 私の安全地帯……《独り言》 朝日新聞が20・21日に行った、緊急事態宣言の前面解除に関する調査では、「早すぎる」51%、「適切」32%、「遅すぎる」11%だったそうだ。回答者の置かれた立場によって思いが異なるのは当然だが、実のない、口だけ宣言の解除はどうでもいい。「Go Toトラベル」や「感染状況の判断」などなど、政府と知事との責任のなすり合いが繰り返され、ついには「専門家の意見」などと堂々と仰る政府には、これ以上何を期待できるのか。 19日の新規感染者数は「東京」303人、「神奈川」111人、「埼玉」135人。 第3波に突入していった昨年11月11日の数字は「東京」317人、「神奈川」130人、「埼玉」116人。 1ヶ月後の12月11日には「東京」595人、「神奈川」285人、「埼玉」185人になり、12月31日は「東京」1337人、「神奈川」588人、「埼玉」330人。野放し状態で放置したためにその後も伸び続けたのだが、一旦は下がったものの他県においても過去最多を更新するなど増えているのが現状。 加えて新種の変異ウイルスも急増している。新規感染者の数ではなく「病床利用率が低下した」ことを解除の理由にした政府だが、変異ウイルス感染者は、各株ごとに別の部屋で療養にあたると聞く。イギリス型・ブラジル型・南アフリカ型を同室させないのだから、使用病床は圧迫されることになる。「そんなことは分かってる」と言われるだろうが、変化する状況に遅れることなく、くれぐれも同じ轍を踏まぬよう願いたい。 一方、新規感染者増加に伴い、県独自の緊急事態宣言をもって仙台市全域の接待を伴う飲食店などの時短要請と県内全域で不要不急の外出自粛を呼びかけた宮城県の姿勢は評価できる。痛みを伴うことから逃げることなくとった決断は立派。 また、「直前の新型コロナの状況によっては県独自の判断をすることがあり得る」と、東京五輪で使用する県内会場を無観客とする可能性を示した埼玉県知事の考えも理解できる。「嫌だ」と仰る方もおいでだろうが、命と安心安全を担保するのが第一の責務。無観客の判断はまだ先だが、想定されることを事前に描き、県民・国民に伝える姿勢は都知事とは大違い。他人任せや風見鶏のようにフラフラする指導者は大嫌い。 いずれにしても、感染拡大防止のキーマンは我々国民一人一人の日々の行動にかかっていることは明らかだからまだまだ自粛はするけど、しきりに耳にする「サーキットブレーカー」は早々に決めてもらいたい。いつになるか分からないワクチンを待っていては手遅れになるから…… また、つまらないことを呟いてしまった……トホホ
2021.03.22
コメント(0)
-

居木神社 (後編)
2月7日の散歩…… 居木神社(いるぎじんじゃ)社殿左側に梅の花…… すでに品川八幡神社の紅梅も咲いていたし、品川区の梅開花は早かった。 紅白の枝垂れ梅も…… 奥にも鳥居が見えたので行ってみると…… 裏参道……大崎町消防による奉納鳥居。昭和8年(1933年)というのは、大東亜戦争で炎上してしまった社殿竣工の年。鳥居は焼けなかったということです。 一応、表に出てみると…… こちらにも猫がいました。逃げない、人馴れした猫たちでした。 境内に戻ると、こちらにも提灯を下げる用意がなされています。提灯だらけの境内はきれいだろうな~ ちなみに当神社は、2018年に放送された『もみ消して冬』っていう日本テレビのドラマで、山田涼介扮する主人公・北沢秀作が絵馬を奉納するシーンのロケ地だったそうです。見たことなかったし、山田涼介と言われてもピンとこない芸能人音痴の私です。 さてさて、裏参道の鳥居をくぐってすぐ左に…… 右端の祠……石燈籠ですが、上部と下部とで年代に違いが見てとれます。さらに、笠の上の宝珠は左右で違い、右には宝珠の根元の「請花」が見られません。また、左は頭部「火袋」下にあるべき「中台」と「蓮弁」が無くなっちゃったみたいです。元々 対になっていたのではないのかもしれません。変なことが気になる嫌な私です。 道祖神でしょうか……男女の2体。男男、女女はないのかな~ 境内社…… 厳島神社と稲荷神社の2社が並んでいます。 お使いのお狐様を従えた稲荷大明神…… 稲荷神社扁額…… 厳島神社……品川区指定有形文化財『概ね和釘を使っていることなどを合わせ、当初の建造年代は江戸後期で、後年補修を受けたものと推定されます。(同社HPより)』 厳島神社扁額……質の良い彫刻装飾が多用され、彫刻部分以外の柱等にも彩色が施されているという内部の社殿は非公開。正月や例大祭には公開されるんでしょう。 左の厳島神社は、『もとは神社の傍にあった旧居木橋村の名主・松原家に屋敷神として祀られていました。後に居木神社が引き取り、末社としたものであります。』とあるので、引き取った際に土台を作ったと推察。 居木神社社殿前には、こんなのがいくつもありました。 写真のほぼ中央に置かれた古銭形の石。一般的には「銭鉢」と言うけど、これは「知足水鉢」。真ん中の水の溜まる部分を漢字の「口」として、上下左右に書かれた四つの文字と組み合わせると「吾 唯 足 知」=「吾(われ)唯(ただ)足るを知る」と言う言葉になります。『足ることを知る人、貧しといえども富めり。 足ることを知らざる者、富めりといえども貧し。』 満足することを知っている人は、貧しくても心が豊かであり、満足することを知らない人は、裕福であっても心が貧しいと、お釈迦様が亡くなる最後の教えで「仏遺教経」にあると。「知足水鉢」の発祥は、徳川光圀公が送ったと伝えられる、京都の龍安寺にある「知足の蹲踞(つくばい)」らしいです。龍安寺(りょうあんじ)は、臨済宗妙心寺派の寺院らしいから禅宗で用いられる言葉かしら? 公にされている蹲踞は実物大のレプリカらしいけど、連れ合いは見たことがあるかもしれません。「吾(われ)唯(ただ)足るを知る」……際限なく求めず、自分にとっての必要を知ることなのでしょう。1年前のトイレットペーパー騒動は、足るを知らない人が多かった証でした。食べ過ぎもよくありませんから腹八分目……飲み過ぎも要注意でした。 ※ 「蹲踞」=茶室に入る前に手を清めるために置かれる手水鉢。同じ字を書いて「蹲踞(そんきょ)」と言うと、相撲や剣道で試合前後に腰を下ろして向きあう姿勢のこと。低い位置の水鉢の前でしゃがみこむことから「つくばい」と名付けられたのかもしれません。単なる想像です。 石灯籠は弘化2年(1845年)奉納みたいだけど、古さを感じない。 左の樹木は皇太子殿下御成婚記念植樹・平成5年(1993年)6月9日……枝垂れ桜かしら? 28年経ってもあまり伸びません。頑張って大きくなって欲しいものです。 東の大崎駅方面……やはり結構高い所に鎮座していました。鳥居から直進すると…… 居木神社参道口はこちらでした…… と言うことで、今日はこれでおしまい。 憂鬱な雨だけど、たまには降らないとね~
2021.03.21
コメント(0)
-

居木神社 (前編)
品川神社訪問の帰りに、バッテリー切れだったから寄らなかったのでコピット行ってきた2月7日…… 百反坂を少し下って…… 北に向かうと、品川区大崎……電信柱の「アシダ音響」はヘッドホンを作っている会社。 品川区立芳水小学校の裏側のこんな道……トラックの後ろを右に曲がると…… 石段発見……方向感覚だけで行ったから、正しい入社ではなかったみたい。ちなみに、正面の屋根はかつて居木神社の別当寺だった観音寺。 居木神社(いるぎじんじゃ)参道……「居木神社と居木橋貝塚」が、しながわ百景だって……石燈籠と「遷宮(せんぐう)記念碑・昭和8年(1933年)9月」がありますが、『…昭和5年には氏子の崇敬熱意によりご社殿の改築にかかり、同8年9月に竣工されましたが、その荘厳を極めたご社殿も大東亜戦争末期に戦火にて炎上しました。(同社HPより)』残念です。もったいないです。『居木橋遺跡は、居木神社の南方に位置する台地上にあり、縄文時代前期(約六千~五千年前)の貝塚を伴う遺跡で、竪穴住居も多数確認されています。 貝塚は、食用にした貝の殻や魚・獣の骨のほか、土器片などが堆積したもので、当時の生活を知る重要な手がかりを現在の私たちに提供してくれています。 これまでの調査から、多くの縄文土器、石器などが出土していますが、貝類では、海でとれるものの他に、陸でとれるヒダリマキマイイマイ(かたつむり)も発見され注目されました。』……居木橋遺跡は品川区大崎二丁目付近に存在したようだから、神社の少し南側みたいです。(居木神社・大崎3丁目8-20) 東山貝塚同様に目黒川や海に近い高台だから、暮らすのには好条件だったのでしょう。 猫が鎮座……石段の横手は石がごろごろしていると思ったら、溶岩積による富士塚なんだって。富士山はネコと反対方向。昔々は富士山がよく見えたことでしょう。「大崎の鎮守」……創建年代は明らかではないけど、古い記録によると、往古鎮座の地は武蔵國荏原郡居木橋村とあり、現在の山手通り居木橋付近に位置していたと。また、当時は「雉子ノ宮」と称され、境内には「ゆるぎの松」と呼ばれた大木があったと伝えられているそうです。山手通り居木橋付近というと、目黒川が氾濫したりしたから引っ越したのかもしれません。 雉子ノ宮(きじのみや)でいいのかしら? ゆるぎの松は意味不明…… 鳥居の脇に阿吽一対の狛犬…… 大正12年(1923年)奉納…… 手水舎……石段を上がった左。 柄杓は置かれていません…… 水を噴き出しているのは獅子かしら? 左右に裸電球がぶら下がってます……季節の節目や祭事には境内随所に提灯が架けられるようです。見事でしょうね~ 今年もお祭りは我慢かな~ JA東京グループありました…… 居留木橋カボチャ『居木神社を中心とした、桐ヶ谷から居木橋一帯の旧荏原郡大崎村(現在の品川区大崎)は、江戸時代以前から農業の盛んな地域でした。居留木橋カボチャは、江戸時代の始めに沢庵和尚が上方から種を取り寄せ、当地の名主・松原庄左衛門に栽培させたのが始まりという伝承があります。 海岸に近く気候温暖で、適地であったため、甘味のある良質のカボチャが早い時期からとれたことから有名になり、地名としては居木橋であるが、居留木橋カボチャと呼ばれて親しまれました。 果実の大きさは中型で、別名を縮緬カボチャといわれたように、カボチャには十五本ほどの浅い溝がありますが、全面をごつごつとしたこぶで覆われていました。外観に似ず中は黄色く味は美味しく、当時わが国を代表するカボチャでした。 江戸時代から明治の中頃まで、この地方の特産品として長く名声を博し、後世の新種改良の親となりましたが、黒皮早生カボチャの出現や、当地域が宅地化するに及んで、しだいに栽培は減少していきました。』とさ…… 正面に社殿・右に社務所……社務所側のイチョウが御神木らしい。『江戸時代の初期、目黒川氾濫の難を避けるために現在の社地に御動座されました。その折、村内に鎮座の「貴船明神」「春日明神」「子権現」「稲荷明神」の4社をあわせてお祀りし、「五社明神」と称されました。 元禄郷帳に居木橋の石高は230石余、72戸で頭屋(年番)による運営がなされ、郷土の崇敬は篤く祭事は盛んで特に里神楽を催し、秋の大祭には他村よりの参詣も多く社頭は大変賑わったと記されております。(同社HPより)』『明治5年(1872年)、社号を「居木神社」と改め、同6年旧制の「村社」に列格、続いて同29年(1896年)および同42年(1909年)には村内鎮座の「稲荷神社」「川上神社」「本邨神社」の3社6座が合祀されました。』 現在の社殿は昭和53年(1978年)再建…… 居木神社社殿扁額……明治神宮の宮司さんの書です。仲がよろしいのか、両社にJA東京の説明板があるのが理解できます。 主祭神:「日本武尊(やまとたけるのみこと)」 配 祀:「高龗神(たかおかみのかみ)」 「大國主命(おおくにぬしのみこと)」 「倉稲魂命(くらいなたまのみこと)」 「天兒家根命(あめのこやねのみこと)」 「菅丞相(菅原道真)かんのじょうしょう)」 合 祀:「手力雄命(たぢからおのみこと)」 「淀姫命(よどひめのみこと)」 「大山咋命(おおやまくいのみこと)」 江戸消防記念会の奉納……消防記念会、以前見たのはどこでだったか? 社務所の右が「御神輿奉安宝物殿」で、その右が神楽殿…… 社殿左から……梅がさきはじめていましたっけ… ということで、今日はこれでおしまい。後編は明日……モデムの具合が悪かったので、電話したら修理交換に来てくれました。素早い対応はありがたいけど、時間をロスしてしまった今日でした。
2021.03.20
コメント(0)
-

明治神宮 (後編)
前回歩かなかったコースをちょこっと素通りしてきた昨日…… 北池の広場から西神門をくぐって境内…… 南神門から正参道を原宿方面へ…… 正参道途中に「明治神宮御苑」入り口……江戸時代の初めから、大名加藤家・井伊家の下屋敷の庭園だったと。面積約83,000㎡(約25,000坪)の広大な土地に、隔雲亭(明治天皇が皇太后の御休所として建てられ、昭和33年に再建)や南池・菖蒲田・清正井なんかがあると言う。御苑維持協力金500円が惜しかったわけじゃないけど、お腹が空いていたから入苑は見送った私…… 前回見られなかった正参道の大鳥居……突き当り左が北参道で、右が南参道。 高さ12mで木造明神鳥居としては日本一……昭和50年12月23日建替竣工 大鳥居をくぐって南参道を進むと…… 奉献 清酒菰樽(こもだる)……『ここに奉供されています菰樽は、ご縁を以て永年当神宮へ奉納を頂いております甲東会(こうとうかい)を始め、昭和38年に結成された明治神宮全国酒造敬神会会員、また全国各地の敬神の念厚き酒造家より献納されたものであります。(明治神宮)』 しかし、すごい数……飲み切れないな~ なつかしい七笑。女城主は知らないが岐阜県のメーカーだと。『…… 岩村城は、戦国時代の一時期(1571年~)、織田信長の叔母であり“絶世の美女”と語り継がれる「おつやの方」が日本でも珍しく女性の城主として城下を治めていました。 そのストーリーをリスペクトし、岩村城築城800年を記念して誕生した銘柄が「女城主」です。(岩村醸造HPより) 』……「おんな城主 直虎」は知っているよ~ 奉献 葡萄酒樽について『明治天皇御製 よきをとりあしきをすてて外國に おとらぬくにとなすよしもがな「和魂洋才」を旨とし、わが国の伝統のこころを守りつつ、西洋の優れた文物を採り入れた明治時代。御在世中、まさに国民の模範となって近代化を推し進められた明治天皇は、断髪、洋装をはじめ、衣食住の様々な分野において西欧文化を積極的に採り入れられました。食文化においても率先して洋食をお召し上がりになり、西洋酒としては特に葡萄酒をお好みになられました。 ここに奉供されております葡萄酒樽は、ブルゴーニュ東京事務所代表でブルゴーニュ名誉市民、シャトー・ドゥ・シャイイホテル・オーナーでもある佐多保彦氏の呼びかけにより、葡萄酒産地として名高いフランス共和国ブルゴーニュ地方は醸造元各社より献納されたものであります。ご縁により遠く海を越えご奉献頂いた方々に衷心より感謝を申し上げますとともに、御祭神の世界友好への深い御心を戴き、わが国とフランスとの親交が一層深まりますよう祈念致します。明治神宮』……転記は疲れるな~ 目に悪いかもしれない。 ブルゴーニュ最高峰 ロマネ・コンティもあるぞ~ 代々木……『この地には昔から代々樅(もみ)の大木が育ち「代々木」という地名が生まれました。この前の名木「代々木」は昭和20年(1945年)5月の戦禍で惜しくも消失しましたのでその後植継いだものであります。』……「樅ノ木は残った」は山本周五郎。 竹で囲ってあるのが植えつがれた樅木らしい。 戦後76年……よくぞ育ちました。 なぜか南参道途中に石橋……短いから気付かない人もいるでしょう。 神橋(しんきょう)と言うらしい…… 覗き込んだらかすかに水の流れが……御苑内の南池から流れているのかも。 農業協同組合法施行50周年記念事業として、JA東京グループが、東京都神社庁などの協力により、都内50ヶ所の神社などに設置した「江戸・東京の農業野外説明板」 代々木野と周辺の村落『ここ明治神宮の境内は、かつて代々木野といわれ武蔵野の一部で、草深き原野は四季折々の山野草が咲き競っていました。それまで、寒村であった江戸に徳川家康が幕府(1603)を置いた事から、江戸周辺の原野は拓かれ、あちこちに集落が形成されました。 寛永年間(1624〜44)には諸大名の別邸や旗本の屋敷などが作られましたが、代々木野(当境内)には元熊本藩主、加藤忠廣の別邸が造営されました。境内周辺には原宿村・千駄ヶ谷村・代々木村・穏田村・上渋谷村などの集落があり、米、麦、蕎麦などのほか、ナス、ダイコン、ニンジンなど、江戸で不足する野菜類を主に生産し、神田や日本橋に出荷していました。 1867年、江戸幕府が崩壊し、明治政府が誕生すると、かつての大名屋敷の多くは空き家となり、青山周辺は市街化が進んだのに比べ、原宿村など、周辺の村々は、明治中期の頃まで、田園の景観をとどめていました。』(JA東京グループ) この説明板はとても寂しい場所にあったけど、位置は教えてあげません。以前、他の3ヶ所で見つけました。また逢えたらいいかもね。 神宮橋……当時の石材を補修して復元した親柱。石燈籠を現代化したデザインなんだって。ハチ公バスはコンパクトでいいです。 疲れたから転記は断念…… ということで、今日はこれでおしまい。 庭木の枝切してきましょう。
2021.03.19
コメント(0)
-

明治神宮 (前編)
1月16日に訪問しましたが、一方通行の規制中だったこともあり、社殿にお詣りした程度だったから今日も病院帰りにちょこっと寄ってみました。 北参道から入って、参道は進まずに北池方向へ…… 橋があるから池があると思いきや…… 残念ながら水はなし……オタマジャクシかナマズの格好をした池みたい。 池の脇に広大な芝生の公園…… でもって喫煙所。地続きだけど明治神宮の管理地ではないらしく、喫煙可はとってもありがたい。 宝物殿入り口…… 耐震工事施工中でお休みらしい。 わが国初期の鉄筋コンクリート建築で、国の重要文化財。 この松らしきが見事でした。 宝物殿の正面は広い広い……そして気持ちがいい。寝ころんで、日がな一日、青空を眺めていたいものです。 芝生の脇の道を歩いて…… ちょっと裏に入ったら…… 桜咲いてました。今日見た桜はこれだけ…… 至誠館 第二弓道場の脇でした。柔道科や剣道科もあるそうです。 コロナ禍対策は不要……明治神宮社殿の北側です。 道案内があるのもありがたい。方向音痴でも大丈夫…… 前回はスルーした西神門に向かいます。 西神門…… 西手水舎の柱に「ひとりたつ道にいまよりつまづくな まなびの窓をいづるわらはべ」(明治天皇 御製・ぎょせい・明治42年)「むらぎもの心のあへる友のきて おもひくまなくかたりつるかな」(昭憲皇太后 御歌・みうた・明治33年) 西神門鳥居…… 向正面に東神門…… 中途半端だけど今日は簡単日記でおしまい。病院ってところは行くだけで疲れます。情けないな~
2021.03.18
コメント(0)
-

ポルシェ911E
東急線が送れていた昨日、乗り換えも面倒だったし、天気が良かったから広尾から歯医者さんまで歩くことに……でもって途中で久々に出会いました。 ポルシェと言われて真っ先に思い浮かぶモデル。ポルシェと言えばやっぱり911であって、ポルシェの代名詞。本当にポルシェらしい愛すべき車です。 なんとも流麗なスタイリング……水平対向6気筒エンジンをリアの車軸よりも後ろに乗っけたRR。 連れ合いへの補足……「RR」は「Rolls-Royce(ロールス・ロイス)」でも「Road Race(ロードレース)」でもありません。エンジンの置き場所と駆動するタイヤの関係を表します。「RR」は、「Rear engine, Rear wheel Drive」の略で、エンジンを車体の後ろに置いて、後輪を駆動するレイアウト。「FR」は、「Front engine, Rear wheel Drive」……エンジンが前で後輪を駆動。「FF」ってのが「Front engine, Front wheel Drive」……エンジン前置きで、前輪を駆動。サラリーマン時代、雪の日に営業車にチェーンを巻いて出かけようとしたら大失敗。FFだなんて知らないから後輪に付けた苦い経験がありました。だからじゃないけどFF嫌いです。 50年も経った1970年前後の車には見えません。 ひょっとしたらと思い後ろにまわってみましたが911でした。ボディーだけでは見分けがつかない「912」ってのがあるから。エンジンを1.6ℓ4気筒にした911の廉価版である912は、日本に輸入されたのが100台ほど。きっと見かけることはないでしょうが気にはしている私でした。《おまけ》 鶏肉の豆豉(トウチ)炒め……昼前にちょこっと用事を済ませて、ランチ食べてきました。お腹いっぱいだから晩御飯は要らないな~ 明日も病院……面倒だけど行かなくちゃね~
2021.03.17
コメント(2)
-

プロのレシピ 13・ながまるさん お通し
今日は歯医者さんに行くから簡単にこんなの…… ウマズラとタラコ…… この頃から握りが増えだしたかも…和食だけでなく、洋食も中華も勉強する主です。 鮪中落ちと海老…… 鴨ロース…… チビコハダ……好きな連れ合いにはごめんなさ…… サヨリちゃんだったかしら……皮の炙ったの好きなんだけどな~ 寒い時期のキノコ汁はありがたい……柚子も欠かさない大将 そば粉のクレープ巻き……久しぶりだった 煮込み大好き……定番メニューで置いてくれるとありがたいんだけど… 白子と煮凝り……これだけで私は充分。 鰤とカンパチだったかしら…… 小さいけど鮑だよ~ 鯵のオニギリ…… コハダのオニギリ……お通しといっても作り置きじゃない。着席してから握ってくれる。この日は鰹節を乗せてあったのね~ 毎回趣向が違います。 牡蠣の吸い物…… キノコ汁に見えるけど、この日は魚が主役…… 牡蠣と松前漬け……贅沢やな~ 鯵は分かるけど、手前は何だっけな~ ホタルイカ……こんな食べ方したのは初めて。でも美味しい……出汁が命!!! ホタルイカとコハダのお寿司……面白い事するよね~ 贅沢!!!…… 雄の本シシャモ……お通しじゃなかったかも? サービスだったかも…… とにかく、日々お通しを工夫するのは大変でしょう。 鮪……美味しかった~ チビ帆立の和え物と鰤…… コロナ禍にあって営業は大変でしょうが、私にはありがたいお店です。いつも飲むだけで申し訳ありませんが、ありがとうございます。「函館居酒屋・ながまる」さんでした。 電車は遅れているらしいけど、仕方ないから行ってこよう。
2021.03.16
コメント(0)
-

折々のことば 139
夢でもし逢えたら 素敵なことね 大瀧 詠一 うんと遠く離れていても、瞼(まぶた)を閉じればすぐに逢える。それを楽しみに眠れたら、眠ることも素敵になる……。私が死んだら、もし葬式でもしてくれるなら、この曲を流してほしい。そう息子たちには頼んである。もちろん、差別を受けながらしびれるようなブルースを紡ぎだした黒人に憧れ、顔を黒塗りした愛すべき“まがいもの”たち、ラッツ&スターの歌で。 (朝日新聞・折々のことば18・2015.4.18)「はっぴいえんど」時代から好きだった大瀧詠一氏の作品「夢で逢えたら 」……多数のアーティストがカヴァーすることになったが、トップバッターは吉田美奈子。 元々はアン・ルイス用に作った曲だったけど、彼女が拒否したのかお蔵入り。でもって、美奈子氏にまわってきたのだが「人が書いた曲が自分の代表作になるのは嫌」だなんて、当時在籍のレコード会社でのシングルカットを拒否する。1976年に録音された「夢で逢えたら 」は、移籍後の1978年にようやく日の目を見ることに。美奈子氏が歌うことを想定して書いた曲ではないから、そのへんは大瀧氏も理解してたはずだが、彼女の「夢で逢えたら 」は吉田美奈子のものになっていると私は思っている。もし、アン・ルイスが歌っていたらヒットしたかは予測不能だけど、聞いてみたい気はする。 さて、大瀧詠一氏が望んだ「夢で逢えたら」は、ラッツ&スターの最後のシングル。1996年にメンバーが再集結した際、自らプロデュースしてリリースされ、ラッツ&スターは同曲で『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。ラッツ&スターも魅力的なコーラスグループだけど、大瀧氏には足を向けて眠れないでしょう。それにも関わらず、盗撮や薬の不祥事を重ねた田代まさしは恩知らずだ。ちなみに、現在は刑務所で服役中らしいけど反省しなさいね。 そんなことでか? 惜しまれつつ大瀧詠一氏が永眠(2013年12月30日)し、翌年営まれた葬儀の式場で彼を送った「夢で逢えたら」は、大瀧氏自身の声によるものだったと。自らが歌ったバージョンは存在しないとされてきたのに、こっそり作ったのであろう自録のテープをご家族がみつけたらしい。遺族や仲間たちへのサプライズ。そして、今は収録されたアルバムが出ているようだから、ファンへのプレゼントでもある。私も買わなくちゃだめだわな~ 電車にはほとんど乗らないから知らなかったけど、京急蒲田駅で流れるメロディは「夢で逢えたら」とのこと。カバーしたラッツ&スターのメンバー鈴木雅之と桑野信義が大田区出身だかららしい。先月22日に駅近を歩いたのに……知ってたら入場したんだけどな~ 残念!! 夢で逢えたら 作詞・作曲:大瀧詠一『夢でもし逢えたら 素敵なことね あなたに逢えるまで 眠り続けたい あなたはわたしから 遠く離れているけど 逢いたくなったら まぶたをとじるの 夢でもし逢えたら 素敵なことね あなたに逢えるまで 眠り続けたい 薄紫色した 深い眠りに落ち込み わたしは駆け出して あなたを探してる 夢でもし逢えたら 素敵なことね あなたに逢えるまで 眠り続けたい 春風そよそよ 右のほほをなで あなたはわたしの もとへかけてくる 夢でもし逢えたら 素敵なことね あなたに逢えるまで 眠り続けたい あの時にそう 君に逢えたから今まで思っていたことが現実になった 今だから言える きっと言える もう一度君を そっと抱きしめて そして…』 鈴木雅之バージョンを聞いてみました。 やっぱり大瀧詠一バージョン聞いてみたいな~ 今朝、モーニングに行きながら探してみました。(8時50分) 直接幹に咲く方が早いです。 こんなのしかないじゃないの……と思ったら… やっと発見…… 立会川緑道の大門橋から羅刹橋の間で、樹木上部の枝に咲いていたのはこの二つだけでした。首が疲れた~ 今日は開花宣言しません。 ちなみに、去年の私の開花宣言は「2020.03.12」でした。
2021.03.15
コメント(0)
-

世田谷の帰り道 (郷土資料館の石塔)
2月3日の散歩最終回…… 東急世田谷線・世田谷駅……三軒茶屋方向 反対側の上町駅は見えます。350mほどだものね~ シゴーニュさんの前を通ったけど、やっぱりお休みでした。タバコも吸いたかったから喫茶&スナック「シャルマン」に向かう手前で「世田谷代官屋敷」に立ち寄り…… 改修か何かでしばらく休館だったけど開いていたから、無料なのでとりあえず一周した暇人です。 前回2018年3月10日に行った時は梅が終わっていてのでリベンジしたけど、今回は早かったです。残念……無念…… 郷土資料館の入り口わきに……ジオラマを見に行った時には気づいていませんでした。なんでかな~ 左から……『三界萬霊塔』天明5年(1785年):いっさいの衆生の生死輪廻(しょうじりんね)する三種の世界(欲界・色界・無色界)を三界と言います。道しるべを兼ねていて「南 池上道」「北 高井戸宿通り」「東 江戸道」となってます。『地蔵菩薩立像』宝暦6年(1756年):西方浄土への往生の業として唱えられる念仏。若林村の念仏講の人々が建てたようです。側面に「これより南 いけがミみち」とあり、やはり道しるべを兼ねています。『狐の石像』主神に従属して働く神霊や小動物を「使わしめ(神使・神令)」という。狐は稲荷の使わしめだけど、「伊勢屋稲荷に犬の糞」という江戸の諺のように、世田谷の村々でも屋敷神に稲荷を祀ることが多く、これが具現化されて祠の前に鎮座したという。 ※「伊勢屋稲荷に犬の糞」……江戸に多いものという意味らしい。江戸には伊勢出身の商人や稲荷の祠が多かったと。では、犬の糞も多かったのか? 5代将軍・綱吉が生類憐みの令を発した江戸の町には犬が激増。その数10万匹とも伝えられる犬たちは、保護を目的に中野区の巨大犬小屋へ収容される。結果として数は激減し、町に犬の糞はほとんど見られなかったと。 ところが、8代将軍に就任した吉宗が「鷹狩り復活」を宣言し、「鷹狩りの邪魔になるから犬はどこか遠くへ捨てろ」と江戸郊外の鷹場の村に対して命じる。その結果として、郊外鷹場の村の犬たちが江戸市街に大流入し、江戸の町はまた犬だらけになったと。またつまらぬことを勉強してしまった。『庚申塔』享保13年(1728年):六臂三眼の青面金剛 左から……『庚申塔』延享4年(1747年):正面に「西ハ大山道」と彫られていて、旧大山道に面した現・駒沢2-17-1にあったと。側面には「東ハ赤坂道」「右 めくろミち」『庚申塔』文化13年(1816年):正面に「東目黒道」とあり、やっぱり道しるべを兼ねている。側面に「北 府中道」「南 六かう(六郷)道」……現・瀬田1丁目と上野毛3丁目との境になっている駒沢通り付近にあったものらしい。『供養塔』文化10年(1813年):正面に「馬頭観世音」とあるから、命を失った馬を弔うもの。「右 府中道」「左 大山道」とあり、昭和初期、近くにあった火の見やぐら撤去の際に取り外され無量寺門前に移設されたが、昭和42年にこちらに寄贈されたとのこと。無量寺も行ったな~ 左から……『標石』天保7年(1836年):「品川領用水御普請所」とある。寛文2年(1662年)、品川領戸越の細川藩抱屋敷邸内の泉池用にと、仙川用水を分水して戸越用水を開削したが、細川家は寛文6年(1666年)に廃止する。干害に苦しんでいた農民が「この古堀を用水として使わせて」と願い出、許可を与えた幕府は寛文9年(1669年)に水路の拡張工事を行ったと。せっかく拡張されても、上流で数か所の分水所が設けられたりしたため、下流の品川領宿村までの引水量は充分でなく、用水をめぐる争いは絶えなかったそうです。『庚申塔』文政10年(1827年):用賀村下講中によって建立され、やっぱり道しるべも担ってます。真福寺境内に保管されていたのを寄贈されたと。真福寺は無量寺のすぐ隣だけど、なぜか未訪問。近いうちに行ってみましょう。側面に「右り 江戸道」「左り 世田ヶ谷四ツ谷道」 お白洲の近くに…… ミツマタ……帰りに入り口詰所の係員さんに挨拶したら「和紙の原料になるんですよ」と教えてくれました。写真を撮っているのを見られていたみたい。枝の先に花が咲き、その後に同じ場所から3本の枝が伸びるんだって。だからミツマタって言うそうな。ちなみに「満開は今月末ぐらいかな~」と仰っていたとおり、2月22日に訪問した蒲田の妙安寺で丸い花に出会いました。 でもって、こんな道を行くと…… お堂…… 方向感覚を頼りに、いつも違う道を歩こうとする私。以前も出会った記憶はあるけどパチリ。 馬頭観世音菩薩……馬の病気のみなならず、安全を祈る仏様としても信仰されていると。だから道端にあるのね~ 三面八臂かしら……彫りもしっかりした素晴らしい馬頭観音。きれいだけど200年ほどは経っているでしょう。 真言……「おん あみりと どはんば うんはった そわか」 ということで、世田谷ブラブラは終了。 天気は良いけど風が冷たい今日……何をしましょうか……
2021.03.14
コメント(2)
-

勝國寺(しょうこくじ)
駒留八幡神社からブラブラした2月3日…… 国士舘大学世田谷キャンパスの南側を東西に走るこの道、地元の人は「勝国寺坂」と呼んでいるそうな…… 坂の途中に、紅白のコントラストが鮮やかな山門…… 青龍山 勝國寺(しょうこくじ)……真言宗豊山派 高徳の僧侶をむかえて長谷寺の復興をはかろうと考えていた豊臣秀長は、醍醐寺に身をよせていた専誉僧正(せんよそうじょう)を奈良の長谷寺に招き入れる。専誉が真言宗豊山派の第一祖となるのだが、「豊山派」の派名は長谷寺の山号「豊山」から出ています。長谷寺の正式名称は「豊山神楽院長谷寺」……連れ合いの好きな一寺らしいです。さっき、私の後ろから覗いて言ってました。 平安時代、法を求めて遣唐使船に乗って中国へ渡った空海。時の都長安で、空海に密教の奥義を授けてくれたのが青龍寺の恵果阿闍梨。勝國寺の山号はここからきているのかしら? 考え過ぎだわね~ 山門の左脇に地蔵菩薩…… 写真でしか拝見したことはありませんが、総本山・長谷寺からは想像できない鮮やかさ。 玉川八十八ヶ所霊場48番札所……川崎・横浜の30寺ほどは未訪問だけど、都内の霊場は30寺訪問しました。残りの26寺参詣は早くしたいものです。 勝國寺の開基は、天文23年(1554年)に12石を寄進した5代目の世田谷城主・吉良政忠。世田谷城の鬼門除けとして薬師如来を安置し、吉良家代々の祈願所としたのが始まりらしい。 吉良家滅亡後、天正19年(1591年)に徳川家康は12石を寄進。家光も前例により12石を寄進し、3代家綱以後の歴代将軍も同様の朱印状を与えたと。 勝國寺本堂…… 勝國寺のみならず、擁した末寺6ヶ寺も世田谷城を取り巻く砦としての役割を担っていたと。円光院・円乗院・多聞寺・善性寺・密蔵院・泉竜寺のうち、円光院だけは訪問しました。いつか世田谷城の砦寺も制覇したいかも…… 本堂扁額……南無大師遍照金剛 書いていたら、連れ合いが長谷寺の御朱印を見せてくれました。熱心にあっちこっちお参りしてるんやな~ 正面は不動明王みたいです。 基本的に真言宗のご本尊は、大いなる智慧と慈悲をもってすべてのものを照らす根本の仏さま=大日如来だけど、仏教に存在する仏さますべてをひとつも否定することはありません。従って、真言宗寺院のご本尊はさまざまなんです。 同寺の不動明王は目が金であることから目金不動とも呼ばれるんだと。教学院・青目不動を訪問した際、東都五色不動ってのを学習しました。 勝国寺は、もと丸香山薬師院と号し新義真言宗に属していたと。高野山を中心に弘法大師によって広められた真言宗だが、鎌倉時代に頼瑜僧正(らいゆそうじょう)によって新義真言の教えが成立。平安の末期、和歌山に創建された根来寺(ねごろじ)を中心に栄えるが、戦国の戦渦によって多くの僧侶が根来寺を離れることになる。新義真言宗総本山=一乗山大伝法院根来寺 薬師堂…… 薬師堂扁額…… 木造薬師如来立像が安置されていると……寄木造り、像高53.2㎝の像内に、天正20年(1592年)に彩色修理を施した旨を記す文書が納入されていた。吉良頼康(よりやす)のもとへ小田原北条氏より嫁いできた室の持仏であり、吉良氏と薬師信仰とのかかわりを示す仏像だそうです。 無縁供養塔の向こうのお堂は何でしょうか?…… 本堂後方は国士舘……かつては勝國寺の境内だったのでしょう。 本堂右に庫裏ですが、後ろと脇を国士館の建物に囲まれています。 見事な大木も…… 本堂前から…… ということで、今日はこれでおしまい。 落雷を伴った雨はいやだな~ 何をしましょうか……
2021.03.13
コメント(0)
-

折々のことば 138
きみ、ダイヤどころやない。みんな人生のダイヤ狂ったんや。 阪急電鉄の駅員 阪神での激震の直後、大震災とはつゆ知らず、「ダイヤそうとう遅れますよね?」と聞いてきたサラリーマンに駅員が返したことば。人としての無力に打ちのめされても、ツッコミを入れつつ、泣き笑いの会話をすることで、関西人はなんとか上を向くことができた。このユーモアの力が、茫然自失の過酷な現実のなかで泉のように噴きだした。藤尾潔「大震災名言録」から。 (朝日新聞・折々のことば130・2015.8.11) 阪神淡路大震災は平成7年(1995年)1月17日、26年前のこと。「大阪に支店を出すから、事務所を探してこい」と言われ、前日まで候補物件を見て回った私。東京にもどり、一夜明けた朝のニュースを知り「大阪進出はなくなった。ラッキー」と思ったのだが、待ったなしで行かされた。走っている在来線とバスを乗り継いで取引先に出向く。三宮や元町も悲惨だったが須磨区は目を覆う有り様。マグニチュード7.3の地震による倒壊と、火災による焼失は凄まじいものだった。お会いした方々が一様に口にされたのは「生きてて良かった」だが、そこには笑顔もユーモアもなかった。「おい、これテレビで全国に流れるぞ。関西人やねんからなんかボケてみせ、ボケてみせ」「こんだけ応援したっとんのに立ち上がろうとせん。阪神といっしょや」「あんな倒れ方もある、こんな倒れ方もある、建造物倒れ方博覧会や」「大震災名言録」は『「大丈夫だよ」と言葉で伝えるかわりに、周囲を笑わせることで「大丈夫」を伝えるのが関西人。「忘れるくらいなら、笑ってほしい」。笑いをバネに乗り切った、阪神・淡路大震災のユーモア名言録。』らしい。 一方、平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災は11年目に入ったが、復旧・復興はまだまだ。マグニチュード 9.0の日本国内観測史上最大規模地震に加え、大津波と原発事故の三重苦。テレビに映る被災地住民からはユーモアは聞こえてこないが、「生きてて良かった」は西も東も同じだ。 三重苦を克服したヘレン・ケラーの伝記に「不幸のどん底にいるときこそ信じてほしい。世の中にはあなたに出来ることがあるということを」とある。周囲を笑わせることで「大丈夫」を伝えるのが関西人らしいが、自分に出来ることを黙々と重ねて復興に向かう東日本の人たちの姿からはこちらが元気をもらう。 幸いにも不幸のどん底を経験していない私だが、首都直下地震が来たら明るい気持ちを持てるだろうか。きっと暗い顔の日々だろうが、「笑うに笑えないのに笑うしかない」ぐらいの気持ちは持っていたいものだ。生きていたらの話だけど…… ひょっこりひょうたん島 作詞:井上ひさし/山本護久『……苦しいこともあるだろさ 悲しいこともあるだろさ だけど僕らはくじけない 泣くのはいやだ笑っちゃおう……』 昨日 書こうと思っていたけど今日になってしまった…… モーニングの帰りに……桜の仲間かしら? (9時27分) 1991年11月に発売開始した「東京ばな奈」の会社と、セブン-イレブンとのコラボ商品らしい。連れ合いが好きだと言うから、今日も買ってきました。義母中心の食事だから、食べたいときに食べたいものなど食べられない連れ合いの間食用です。好きな時に好きな物を食べて飲む私からの謝罪です。 さてさて、何をしましょうか……
2021.03.12
コメント(0)
-
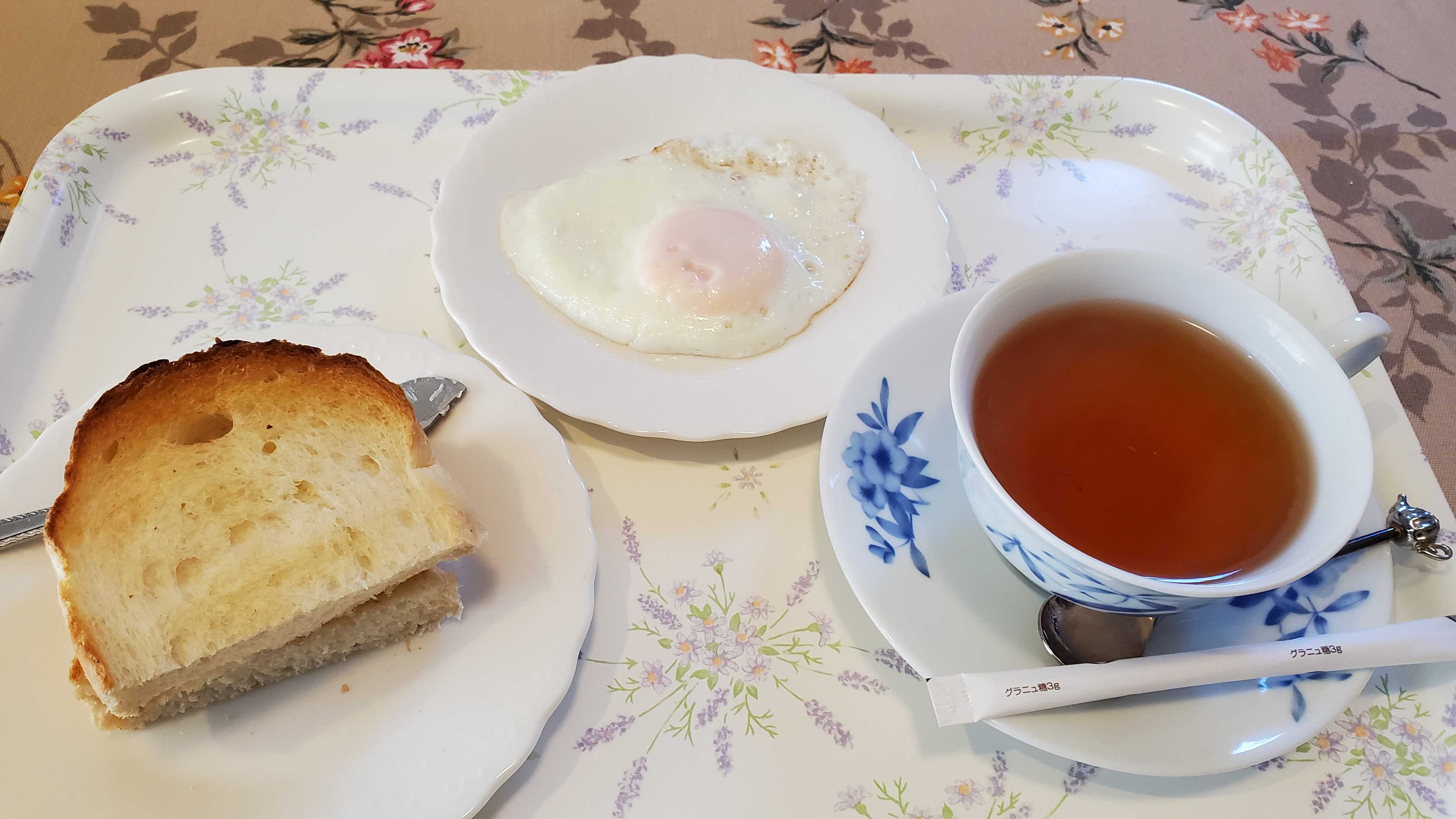
検査……
人間ドックでひっかかったから、大腸内視鏡検査に行ってきた。半日仕事……と言っても仕事をするのは私ではなく病院の検査技師さんや看護師さん。皆さん笑顔で丁寧な対応をくださった。本当にありがたい。 検体を採取されることを覚悟していたけど、なんのなんの、幸いにも大丈夫だった。横になりながら、ディスプレイに映し出される我が身の大腸内を眺めるってのは妙な気分。牛の腸ならホルモンってことだろうけど、私の腸もなかなか綺麗だから食せるかもしれない。なんてアホなことを思いながらの大腸検査でありました。 でもって、最も辛かったのは前日の食事……口にしてはいけない食材ばかり。朝食はこれでおしまい。昼にリンゴ(皮なし)半分と、プリン。夜は素うどんでおしまい。本日夕方5時まで水分だけだったからお腹ペコペコで困った。ということで、帰ってきたのでこれから晩酌。本当は別記事にしたかったけど、時間がないから今日はこれでおしまい。みなさまのご健勝をお祈り申し上げます。 ちなみに、日頃プリンなど食べない私ですが、連れ合いが買ってくれたプリンは美味しかった。東急ストアらしいけど、また買うてな~ 協力と心配とをしてくれた連れ合いに感謝します。おーきにね~
2021.03.11
コメント(0)
-

念空寺
2月3日の世田谷散歩…… 若林中央横断歩道橋……若林稲荷神社から環七を越えるのに使いました。すぐ先を世田谷線が横切るんだけど、タイミング悪かったらしく来なかった。待っているのも疲れるから断念。 若林橋……かつて二級河川が流れていた時代には橋が架かっていたんでしょう。 烏山川緑道……千歳台にある千歳温水プールあたりから、三宿の北沢川緑道との合流地点まで続いている約7㎞の緑道。合流してから東に向かう目黒川になります。合流地点も以前行きましたっけ…… 天神橋ってのは、南150mほどに菅原道真の若林天満宮があるからでしょう。「こちふかば 匂ひおこせよ梅の花 あるじなしとて春な忘れそ」……「主がいないからといって、春を忘れるなよ…」東日本大震災、明日で10年。 中堰橋……河川の流水を制御するための「堰(せき)」が設けられていたのか? 1970年代以降ほぼ全面的に暗渠化され、ほとんどが下水道へ転用されました。 松陰橋……松陰神社の北側です。『緑道の半ば、宮坂一丁目には万葉の小径があり、ここは、万葉集に詠まれた草花が植えられています。(世田谷区HPより)』……「万葉の小径」は、以前訪問した世田谷八幡宮の近くだって。知っていてもあの日は時間切れだった。 国士舘大学世田谷キャンパスの一部が見えてきます。同大学のキャンパスは広い。世田谷4丁目と梅丘2丁目にまたがっていました。 梅だったかしら…… 緑道をそれて、お寺を探す私……どこかしら? おっと行き止まり……変則な道だから分からない。 正面は行き止まりみたいだけど…… この辺にあるはずだとウロウロしたら…… 念空寺……浄土真宗 地域密着型の寺院斎場とのことでした。 国士舘大学キャンパスを迂回すると、路地の奥にお寺……だけど、今日はこれでおしまい。 天気が良いから散歩したいけど、そうもいかないわけがある。今日明日は我慢の私です。連れ合いはお墓参りに出かけました。いつもご苦労様、そしてありがとう。
2021.03.10
コメント(0)
-

若林稲荷神社
駒留八幡神社から世田谷の一部を歩いた2月3日…… 環七から若林2丁目の住宅街に入ると赤い鳥居……白い旗には「正一位福寿稲荷大明神」……なんで「若林稲荷大明神」じゃないの??? (答えは後で…) ちなみに右の建物は、反対側が神楽殿になってます。 鳥居に扁額はありません。 石段を上ると、よく整備されたコンパクトな境内……昭和59年(1984年)に再建された新しくてきれいな社殿。以前の社殿は、やはり昭和20年(1945年)3月10日の空襲で焼失したと。 手水舎も社殿再建時のものなんでしょう。 かつてこの地に鎮座していたのは「福寿稲荷神社」と呼ばれる稲荷社だったけど、代田に鎮座していた「天祖神社(神明社)」を合祀して現在に至っています。明治10年(1877年)に、天祖神社の別当寺であった常林寺が焼失したために合祀とのこと。 だから社殿扁額はこうなってます……創建年代は不詳ながら、江戸時代中期・明和6年(1769年)に社領が寄附されたとの記録があるそうです。戦禍で焼失以前の社殿扁額は「正一位福寿稲荷大明神」だったでしょう。 御祭神は、稲荷神社の「倉稲魂命(うかのみたまのみこと)」と、天祖神社(神明社)の「天照大御神」ということになるはずです。お酒を奉納されたのは、若林天満宮と同じ方々でした。 社殿左奥に大黒天社…… 以前は、大黒天、毘沙門天、弁財天が合祀された社があって、弁天池もあったんだって……インド神話の神様大集合、ってことかしら? 大黒様……中国から密教と一緒に伝わってきた大黒天(マハーカーラ)だから、初期には真言宗や天台宗で信仰されたらしい。目黒駅近くの天台宗寺院・大圓寺は山手七福神の大黒天でした。他の七福神はどうかと振り返ったけど、多摩川は「氷川神社」、荏原は「小山八幡神社」で東海は「品川神社」と、神社ばかりが大黒天でした。 社殿右側に鳥居が見えました…… 招魂社の碑…… 招魂社…… 戦死した人々の霊が祀られている社……戦争反対!!! 軍拡反対!!! 御祭神は護国の英霊…… 横から……丁寧に造られています。 幕が張られているってことは、初午祭が行われたのでしょう。この幕も昭和59年10月吉日だから、社殿再建時の奉納です。 社殿前から……左の神楽殿は2階建てだった。 高台になっていたから眺めは良い。だけど、石段下りるのは要注意の私でした。 さてさて、予防対策で電気治療に行ってこようかしら……
2021.03.09
コメント(0)
-

若林天満宮
2月3日の世田谷散歩…… 駒留八幡神社から環七を北上…… 世田谷通りを越えて最初の歩道橋の脇に…… 若林天満宮……学問にご利益があるとされている菅原道真を祭神とする神社だから「若林北野神社」とも呼ばれます。狭い歩道からそのまま石段を上がるだけ。古くはたいそう賑わったようですが、環七の拡張で参道が失われたと考えられます。現玉垣は昭和34年の奉納だから、そのころ工事があったんでしょう。 社殿正面に「初午 2月3日11時 若林稲荷神社」の貼り紙。当者は稲荷神社じゃないから初午祭りは無縁でしょうけど、若林稲荷神社の宣伝かしら? 散歩に出かける時「今日は初午だよな~」と認識していました。人が多かったら近づかないことを肝に銘じていたけど、幸い祭りには遭遇しませんでした。この後訪問した「若林稲荷神社」でも、祭りの面影はありませんでした。緊急事態宣言中だから中止されたのかもしれません。 社殿扁額……いつから鎮座しているかは不明らしいけど、室町時代・応永8年(1401年)にはここにあったとする記録があるようです。 ちなみに「応永」ってのは、1394年から1428年までの35年間で、日本の元号の中では、昭和と明治に次いで3番目の長さらしい。 室町幕府第3代将軍・足利義満が征夷大将軍を辞官し、足利義持が第4代将軍に就いたのが応永元年だが、この新元号選定に関して、公家達の反発にあったため義満の希望は実現しなかった。そこで、機嫌を損ねた義持は「自分の生きている間には元号を変えさせない」決意をする。息子の義持も父の遺志を継いだのだろう、「義満死去・応永15年」「称光天皇即位・応永20年」に出された改元の議を阻止したとのこと。なぜか、いつも横道にそれる私……あかんあかん 小さな祭事が行われたのか? 奉納のお酒が並んでいます。 社殿右側…… 紅梅がチラホラ…… 白梅もチラホラ…… 社殿左側…… ポツンと境内社……稲荷じゃなさそうだけど、何かしら? やっぱりお稲荷様かしら? ポンプと手水舎…… 世話人さんのお名前がありますから、ご寄付の石碑でしょうが妙に古い。 前は環七…… 環七を世田谷線が横切る「若林踏切」…… 通過中……遮断機はありません。 ようやく行きましたが、またじきにやって来るんだな~ 早く渡りましょう。 淡島通りに向かって、また歩道橋……自動車には良いけど、歩行者には不便。 歩道橋脇を入ると次の目的地……若林天祖神社はまた今度……《おまけ》 シネマカフェの五目湯麺……小雨だったけど、西小山を諦めて早めのランチに行ってきました。禁煙(日・月)の暇を売る店でアイスコーヒーを飲んで新聞読んできた健康的な昼でした。「やれば出来るじゃないですか」と連れ合いに言われちゃいます。
2021.03.08
コメント(0)
-

折々のことば 137
みおつくし(澪標) 古地図の印 川を運行する船が浅瀬に乗り上げて座礁しないよう、昔の水路には河底の深さを示す標識があった。それを古地図では「又+Ⅰのような記号(表記できない)」と表した。大阪市はこれを市章としてきた。ものごとの表面の様子に惑わされず、ほんとうに大事なものを知り、それを守るという志を表す。澪標は「身を尽くす」という語にも通じる。そう、何ごとにも誠意をもってあたるということ。 (朝日新聞・折々のことば28・2015.4.28) 菅首相の長男が勤める「東北新社」による総務官僚への接待問題では、衛星放送認可をめぐる違法性が明らかになった。 外国の個人・法人などの株主が持つ議決権が20%以上の事業者は放送を行えないとする外資規制があり、これに違反した場合は「認定を取り消さなければならない」と定めるルールに違反していたと。 東北新社は、20%をわずかに下回っていた2016年10月に「BS4K」放送の事業者への認定を申請し、総務省は2017年1月にこれを認定した。ところが、同年3月末には再び20%を超えて違法状態となっていたのに、事業者の地位を100%子会社「東北新社メディアサービス」に承継させるという東北新社の申請を、総務省は同年10月に認めていたと。 この決済の最高責任者を問われた総務省幹部の答弁は「この決裁の最上位は、当時の情報流通行政局の山田真貴子局長でございます」ときたもんだ。7万円接待で批判を浴び、体調不良を理由に内閣広報官を辞任した飲み会を断らない山田氏の関与は明白だろう。仕事の出来る人だったのだろうから、外資規制をクリアーしているかは調査して決済するはず。怠ったとすれば怠慢で、目をつぶったとすれば忖度、あるいは圧力が加わったのかもしれないが、いったい誰のために身を尽くしたのか。退任したから今は一般人と政府は擁護するが、怠慢であれ忖度であれ誤った決済をしたことに対する責任はとってもらわねばならない。退職金は没収してもらいたいくらいだ。 沖縄防衛局が2018年3月に発注した「シュワブ(H29)埋立工事」の1~3区において、防衛相が契約変更して工費が増額されていたと。一般競争入札で、2018年2月に大手ゼネコンと沖縄の業者による共同企業体が約259億円で契約したのだが、20年9月までに複数回にわたって契約変更が行われ、416億1136万円に増えていたと。沖縄防衛局が公開しているホームページには当初契約の金額が記されているままで、防衛局窓口で「変更契約調書」を閲覧するか、情報公開請求をしなければ分からないと。変更理由は「計画調整」「現場精査」「計画変更」としか記されていないようで、理由・内容も書かれぬまま変更のたびに増額されるのはなぜか? 別途発注して入札しないのは、時節柄接待、あるいは政治家による圧力があったと受け取られても仕方あるまい。結局、どこの省庁も利権絡みに加担し、少数ではあろうが、政治家や官僚が企業と結託して懐を肥やしている構図が透けて見えるいやな世の中だ。1円であっても、税金の使い道を知る権利が国民にはある。文春に頑張ってもらわねば…… 一方、『内閣官房でコロナ対策を担う「コロナ室」における一般職の1月の平均残業時間は、およそ122時間で、最も長く残業した職員は378時間だった。』と……国民の命を守るために身を尽くして働く官僚・職員には感謝する。働き過ぎて過労死に至らないよう政府が定めた「標識」が月80時間であり、それを遥かに超えている。ほんとうに大事なものは人命だが、政府には標識を守るという志も誠意もないらしい。「コロナ室」で平日にテレワークをした職員はゼロだったと伝えられる。企業にはテレワークを呼びかける政府の実態を知り怒りがこみ上げてくる。いつの世も「身を尽くす」のは国民ということか…… 桜咲いた……たぶんサクランボの実る木(8時26分) 寒緋桜(カンヒザクラ)……だと思う。(8時30分) モクレンも咲いていたのね~ (9時47分) と言うことで、今日はこれでおしまい。 モーニングが早かったからお腹空いたな~
2021.03.07
コメント(0)
-

駒留八幡神社 (後編)
2月3日の世田谷散歩…… 社殿左側の壁際に……寝返りうってるんじゃないよ~ 小さな社が二つ…… (左)菅原社・榛名社・三峯社 (右)御嶽社 稲荷神社…… 稲荷神社扁額……何処の稲荷? 伏見稲荷? 小さいけれど石造のお狐様も…… 社の右わきに「豊受稲荷大明神」の碑…… 豊受稲荷大神を祀る豊受稲荷本宮(ゆたかいなりほんぐう)というのが、千葉県柏市にあるらしい。戦後に京都「伏見稲荷大社」から勧請して創建した新しい歴史の神社で、特徴は「全国でも珍しい神仏混淆(神仏習合)の稲荷神社」とのこと。境内に観音堂もあるそうです。旧水戸街道沿いだから、昔々、営業車で何度も通ったけど記憶にはありません。興味なかったしな~ 左脇には小さな石祠……元々の稲荷社だったのか? まだまだ壁際に並びます…… 大小石祠と石碑…… 女塚社……ちょっと調べたけど、いろいろあるから今日はパス…… 庚申塔の方が気になる私……正面に青面金剛だろうけど、左右側面に一猿。三猿が普通なのにレアでした。江戸時代でしょうが、相当古いものでしょう。 富士講ではないでしょうが、溶岩石らしきが敷き詰められて……「宗円寺開基碑」と、Wikipediaにあった。明治維新後の神仏分離令まで、若宮八幡宮の別当を務めていた「宗円寺」……区画整理の際にこの場所に移されたらしいけど、寺号碑も山門前の道路を挟んだ位置にあったし、分かる気がする。 梅も咲き始めていたっけ…… 本堂左脇から…… 御大典記念樹……どなたの? 大正天皇の御大典記念でした。大正4年(1915年)11月10日に駒沢村青年会により植樹されたそうです。 世田谷の名木百選……百と言っても150件の名木が再選定されているようです。今度マップもらってこようかしら……このクロマツは40番 左の方にあるまっすぐに伸びた雄大なクロマツは高さ28.1m。とにかく立派でした。流石名木百選!! プレートは見なかったけど、駒留八幡神社はせたがや百景にも選ばれています。 さてさて、今日は何をしましょうか……天気はそこそこ…
2021.03.06
コメント(0)
-

駒留八幡神社 (前編)
世田谷区上馬から若林-梅丘あたりをブラブラした2月3日…… 環七を歩いて世田谷通りの手前…… 幾度も訪問する機会はあったけど、寄らずじまいだったから行ってみようと…… 予想以上に広そうな雰囲気……事前には場所しか確認しないし、詳細不明で出かけます。 撮っておけば何とかなると思ったけど、読めない……『…北条左近太郎入道成願は、当時この地の領主で、あつく八幡大神を崇敬し、徳治3年(1308年)社殿を造営し、経筒を納め駒留八幡とあがめたてまつった。 その後世田谷城主吉良頼康は、その子の追福のため、八幡宮に一社相殿として祀り若宮八幡と称した。また、その母常盤を弁財天として祀ったのが、厳島神社である。』(境内の掲示より)……ちょっと分かりにくい…… 世田谷城主・吉良頼康の側室・常盤は、他の側室たちからのつくり話によって頼康から不義の疑いを受ける。でもって常盤は子どもを身ごもったまま自害する。無実を知った頼康は、常磐の死と死産した子を当社に祀ったということでした。イジメは昔からの事ですがいけません。 ここ上馬の鎮守が「駒留八幡神社」で、下馬の鎮守が「駒繋神社」…… 手水舎……左三つ巴紋が入っていました。「巴」は、弓を射るとき手首につける皮革製の道具の形やそこに描かれた文様=「鞆絵(ともえ)」が発祥。武運の神として武家から尊崇された神紋と八幡宮の社紋になっていき、他の神社にも広がったと。「駒留」というのは文字通り馬が止まる意味……北条左近太郎が八幡宮を勧請するために鎮座地を探した方法は「馬を勝手に歩かせ留まったところ」だったと。駒場や駒沢って地名もあるように「駒」=馬との縁が深い地域です。 狛犬……睨まれました。 子どもを守る親の姿はいつも厳めしい。 神楽殿……昭和41年(1966年)の改築らしいけど風格があります。 駒留八幡神社社殿……御祭神は天照大神、応神天皇。 社殿扁額…… 社殿左側に……複数の境内社。 表忠碑……日清戦役~満州事変における地区出身の戦病没者慰霊顕彰。合掌。 細い参道が伸びます…… 戦没者慰霊殿……安らかに眠れますようにと祈りつつも、「死んで神様と呼ばれるよりも 生きてバカだと言われましょうよね…」が頭に浮かぶ私でした。 厳島神社……世田谷城主・吉良頼康が寵愛(ちょうあい)した常盤が弁財天として祀られています。 弁天池を模して、水が溜められるようになっているけど、寂しい…… サギソウ伝説『今から400年以上も昔、世田谷城主 吉良頼康(きらよりやす)には奥沢城主大平出羽守(おおひらでわのかみ)の娘で常盤(ときわ)という美しい側室がいました。常盤姫は頼康の愛を一身に集めていましたが、それをねたましく思った側妾たちは、つくり話によって頼康につげ口をしました。 度重なるつげ口から頼康もそれを本気にして常盤姫に冷たくあたるようになりました。愛情を疑われ、悲しみにくれた姫は死を決意し、幼い頃からかわいがっていた白さぎの足に遺書を結びつけ自分の育った奥沢城へ向けて放しました。 白さぎは奥沢城の近くで狩をしていた頼康の目にとまり、矢で射落とされてしまいました。白さぎの足に結んであった遺書を見て初めて常盤姫の無実を知りいそいで世田谷城に帰りましたが、すでに姫は息をひきとっていました。 その時、白さぎの血のあとから、一本の草が生え、サギに似た白いかれんな花を咲かせました。これがサギソウと呼ばれるようになったのです。』(世田谷区HPより) と言うことで、途中だけど今日はここまで……続きは明日。 さてさて何をしましょうか……雨はいやだな~
2021.03.05
コメント(0)
-

稼穡稲荷神社(かしょくいなりじんじゃ)
1月31日の品川散歩・最終回…… 山手通り・品川図書館前の信号を渡ります……前方の駐車場奥は以前訪問した荏原神社。「南の天王さん」と呼ばれ、品川の南側を守るのが荏原神社で、北側の鎮守が「北の天王さん」と呼ばれる品川神社だと、その時学習しました。 結構疲れていたし、この日は荏原神社再訪はパスしましたが、2年以上前でした。 路地を入ります。 正面は目黒川が流れる場所…… 二基の鳥居と、ご神木……品川区指定天然記念物のイチョウ…… 限られたスペースなので、L字の参道…… 大切に維持されている社殿……東を向いています。別名荏川稲荷ともいい、御祭神は「宇迦能比売命(うかのひめ)」と説明書きにあったけど、「宇迦之売命」じゃなくてこんな表記もあったのね~ 扁額「稼穡稲荷」……『稼は植える、穡は収める、とりいれを意味し、農業の意味である。稼はカセギともよみ、かせぎためると読み替え商売繁盛の神として命名した。(一般財団法人 六行会)』『稼穡(カショク)とは、穀物の植えつけと、取り入れ。種まきと収穫。農業。』だと、デジタル大辞泉にも載ってました。知らんかった~『…この稲荷のはじまりについては、こんな話が伝わっている。薩摩屋敷から六行会がこの土地をゆずりうけたとき稲荷社は北東の旧目黒川の方にあった。そこでそんな隅にあったのをたいそう気にしていた六行会の生みの親ともいえる山本伴曹は、ある夜狐の嫁入りの夢を見た。山本伴曹は荏原神社の神主であった鈴木播磨に頼んで、伏見稲荷さんを分請したというのである。そしてそれは文久元年(1861年)という。…』 旧目黒川の河川工事が行われ、流れを変えた現在も目黒川の脇に鎮座してます。ご縁というものでしょう。 六行会(ろっこうかい)……とっても有意義な活動をされてきました。 南品川宿と呼ばれ東海道第一の宿場として賑わっていた幕末の頃、住民は宿場の仕事が忙しく、自分の家業に従事するこもままならない。それを軽減して凶年や不慮の災害時に対応できるよう、南品川宿の地主たちが基金の積立てを始めたのが六行会の初まり。 明治維新とともに宿場の制度が廃止になると、品川宿の人たちはそれから解放されるが、折角基金で作った家作からの収益金も無駄になる。そこで、これを有益に使うため、新しく始まった教育制度を助成することにした。 大正の末に、町人たちの集会のための「荏川町倶楽部」をつくり、この中に当時東京府下ではじめて「荏川町文庫」という図書館を併設するなど公益事業を展開。 昭和3年に、図書館を倶楽部から独立させ、後に品川町の東京市への併合記念として寄付し、現在の品川図書館に続いている。 平成6年、本会設立150年を機して、地域の文化・教育の発信点としてに寄与したいと願い、品川区と協力して新しい総合ビルを建設、「区立図書館」と「六行会ホール」ならびに集会施設「荏川倶楽部」を新設し、平成8年、東京都教育委員会から寄付行為の変更の許可を得て、新しい展開をしてきた。(一般財団法人六行会HPより抜粋) ちなみに「六行」は会の精神……『人の勤むべき六つの行い「孝・友・睦・姻・任・恤」を表しています。親子愛(孝)にはじまり、兄弟愛(友)夫婦愛(睦)親族愛 (姻)隣人愛(任)そして人類愛(恤)まで、拡げていこうというもの』だそうです。 幹周り4.1m、推定樹齢500~600年の巨木…… ここでも乳根……背後が六行会総合ビル 当日は気付かなかったけど、左に波型の瓦があった。目黒川の氾濫除けかも…… 目黒川にそって新幹線まで戻ってきた所……これ、何なんだろう? 地下に溜まった水を川に放水するためのものかしら? 川沿いを歩けないから迂回…… 光村ビルの敷地に…… 稲荷社…… テナントも入居しているけど、光村印刷の本社ビルらしいから、商売繁盛を祈願して光村さんが祀ったのでしょう。 ここでバッテリーの残りわずかだと表示が登場。もう一ヵ所寄りたかったけど、写真が撮れないので断念。田丸でチャーシューワンタン麺を食べて帰った私でした。朝から何も口にせず出かけたからお腹空いてたけど、なぜかワンタンが通常の倍入っていて苦しかった。おまけしてくれたのかしら? 久しぶりだけど美味しかった~
2021.03.04
コメント(0)
-

折々のことば 136
時の流れがね、落っことしていったものを一番後ろから拾いながらトボトボと行くっていうのが、私には合ってるかなって思うんです 中島みゆき 時代の浮かれの中で目もくれられずまたぎ越されてしまうもの。時代の厚い雲にさえぎられ見えなくなっているもの、時代の勢いの中で置いてきぼりにされたもの。用済みと払い落とされたおがくずのような命の佇(たたず)まいを慈しむ、その落ち穂拾いの小さな足音にこそ耳をそばだてたい。NHK「SONGS」(昨年11月7日)での発言。 (朝日新聞・折々のことば306・2016.2.8) 我が家には、祖母と母の雛人形が2組あったらしい。残念ながら戦禍で焼失し、残ったはこの内裏雛だけらしい。母のとしても90年ほど経っているが、1年中 木箱に幽閉されて暗い押し入れ暮らし。連れ合いに出してもらって、年に数日だけ日の目を見る。1年ぶりの景色はどのように映っていることか。黙って、時の流れが落としていったものを拾っているかもしれない…… 古来日本のしきたりは「左方上位(左側が上席)」だから、雛人形も左側(向かって右側)に偉い人が置かれていました。明治時代になって欧米マナーが日本へ入り、皇室のしきたりが変化し、大正天皇が皇后陛下の右に立って写真を撮影してから現在に至るまで天皇の位置は皇后の右側が決まりとなっていると。そして昭和3年(1928年)昭和天皇が皇后の右にお立ちになった御大典(即位式)の写真が全国的に広まった頃から、雛人形も男雛を右上座に飾るようになったそうです。 我が家は頑固に古来のしきたりに則って並べられます。「桜餅買ってきます」と連れ合いが出かけて行きました。お菓子たくさんあるのに、やっぱり無いとダメなのかしら? 義母の目があるからちゃんとしておかないとならないのでしょう。嫁って立場は辛いな~ 申し訳ないね~ 以前「雛人形をしまうのが遅れると、婚期が遅れるよ」と、義母に言われた連れ合いが「私は結婚してるけど、おかあさんはまだ結婚するのかしら」と呟いていた。あくまで迷信で、「片付けがちゃんとできないと、きちんとした女性になれないから、お嫁さんにもなれないよ」というしつけ教育の言い伝えでしょう。「きちんとした女性」って言葉が現代ではタブーかもしれませんが…… と言うことで、今日は簡単におしまい。何をしましょうか……
2021.03.03
コメント(0)
-

北品川2丁目の子育地蔵と本照寺
すでに3月だというのに、1月31日の散歩日記…… 虚空蔵横丁を正徳寺までもどり、北馬場参道通り商店街を越えて路地へ…… 民家の並ぶ変則路地に…… ポツンと地蔵堂……地元の有志さんに支えられています。 子育地蔵……手入れがよく行き届いたお堂。 優しく美しい子育て地蔵…… 子どもの好きなフィギュアも…… この地蔵のすぐ後ろを流れていた目黒川が氾濫し、川でおぼれて亡くなった子どもの供養にと、大正10年(1921年)7月に建立されました。100年前です。 目黒川は相当蛇行していたようだから、洪水も頻発していたんでしょう。大正15年(1926年)から昭和14年(1939年)にかけて河口から北沢川・烏山川合流点の区間で河川改修が実施され、直線化されたとのこと。 地蔵堂の後ろ……ここを流れていたんだな~ 今は、この地点から私の背後方向・100mほどに目黒川が流れています。 目黒川の川筋だったんでしょう…… 地蔵堂と目黒川との間に走っている山手通り……「環状6号線って言うんだよ」と、先日連れ合いに教えてあげましたっけ。環7・環8は知っていたけど環6って呼び方は知らなかったらしい。そんなことはどうでも良かった……自販機の先に… 寺院発見…… 本照寺山門……当日はまったく気付いていなかったけど、左の石柱にある「蓮華荘」が気になりました。ひょっとして宿坊があるのかしら? 本照寺本堂……東福山と号す真言宗寺院だったが、天文17年(1548年)に池上本門寺第九世東照院日純上人が日蓮宗に改めたと。真言宗から日蓮宗に改宗したのは、当時の住職が日蓮宗の日純との法論に敗退したためだって。ちょっと寂しいな、真言宗。 長福山本照寺……真言宗寺院だった時は「東福山」と号し、日蓮宗に改めた折に「東光山」と改号したそうですが、「長福山」とはこれ如何に??? 単立(たんりつ)寺院に独立されたのかしら? 現在の本堂は南を向いていますが、北方向の北馬場参道通りに「南無妙法蓮華経 東光山 本照寺」と彫られた門柱が残っているらしいから、昔は北向きだったのかも。現在山門となっている山手通りの拡張整備なども影響があったかもしれません。 観音菩薩……指がなくなってしまわれたみたい。修復してくださいませ。 動物之霊供養塔……墓地にではなく、本堂前は珍しい。 ありがとうございました…… 山手通りの向こうは品川図書館…… と言うことで、今日はここまで…… 天気が悪いから何をしましょうか。ノンアルデーだから寂しい。
2021.03.02
コメント(0)
-

唐ヶ崎電波塔と白い月
劇的な解決を望むのではなく、部品を点検しボルトを締め直すように、一つ一つの問題に向き合うしかない。 中島 岳志 完全な制度というものはない。今日ではあたりまえに見える制度も、きしみやひび割れ、腐食や破綻を未然に防いでおこうという、無名の人々による日々の丹念な手入れと手当とによって持ち堪えてきた。「そういう平凡な努力の積み重ねが非凡なんです」と政治・歴史学者は言う。本紙夕刊「一期一会」(昨年9月1日掲載)から。 (朝日新聞・折々のことば718・2017.4.7) 国家公務員倫理法違反となる接待を受けていた山田内閣広報官が、体調不良を理由に辞職した。「菅首相の長男の呼びかけだったから断れなかったのでは?」など擁護する声も聞こえるが、倫理法等さまざまな制度は形骸化している。手入れも監視・管理もせず放置したままでは法そのものに存在意義はない。 法のすき間を突いて誤魔化しもある。政治資金収支報告書への記載が法律で義務づけられている寄付や政治資金パーティーによる収入なんてのは不記載が目立つようだ。発覚すれば訂正しておしまいとする議員もいるが、最初から誤魔化す輩は質が悪い。「同一の団体や企業・個人からの年間5万円を超える寄付」や「1回の政治資金パーティーで20万円を超えるパーティー券の代金」は、金額と相手の名前などを記載する必要があるとするが、小分けにして上限金額以下にして不記載にする例も多いと聞く。庶民の確定申告では数百円でも領収書がなければ認められないのに、法律を作る側は誠に都合のいいものだ。 新型コロナウイルスワクチンの65歳以上への優先接種が4月12日から始まるが、各自治体へ届くワクチンはごく少量だと。どれくらい少量化と言えば『東京都へは、4月中に3回に分け、ワクチン計44箱が供給される予定だ。1箱は195バイアル(瓶)入り。1瓶から5回分のワクチンを採取するので、1人2回接種として2万1450人分となる。(東京新聞)』 東京都内で優先接種の対象となる高齢者は約310万人だから、当初は0.7%の人にしか行き渡らない計算だ。それも4月中に予定の44箱が到着しての話。おまけに、12日までの第一便では約2000人分だと言う。そもそもこれほどまでのワクチン不足を政府は想定していたのか。試行的に行う量としても少なすぎるし、極わずかな接種対象者を選ばねばならない区市町村の対応は厳しいことになる。2便・3便以降の供給スケジュールとて定まっていない。到着分から見切り発車的に開始せざるを得ないだろうが、丁寧に制度を点検し、事あれば即座に改善できる組織であってもらいたい。 西の方では緊急事態宣言が解除された。コロナに対して劇的な解決は望めないことは誰しも承知している。自粛という日々の平凡な努力の積み重ねを継続するしか道はないことを肝に命じ、次の波が訪れないことを切に願う。 (2月24日 15時13分) 手振れしてるんだろうな~ ちょいとお酒飲んだら良かったかも……
2021.03.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1










