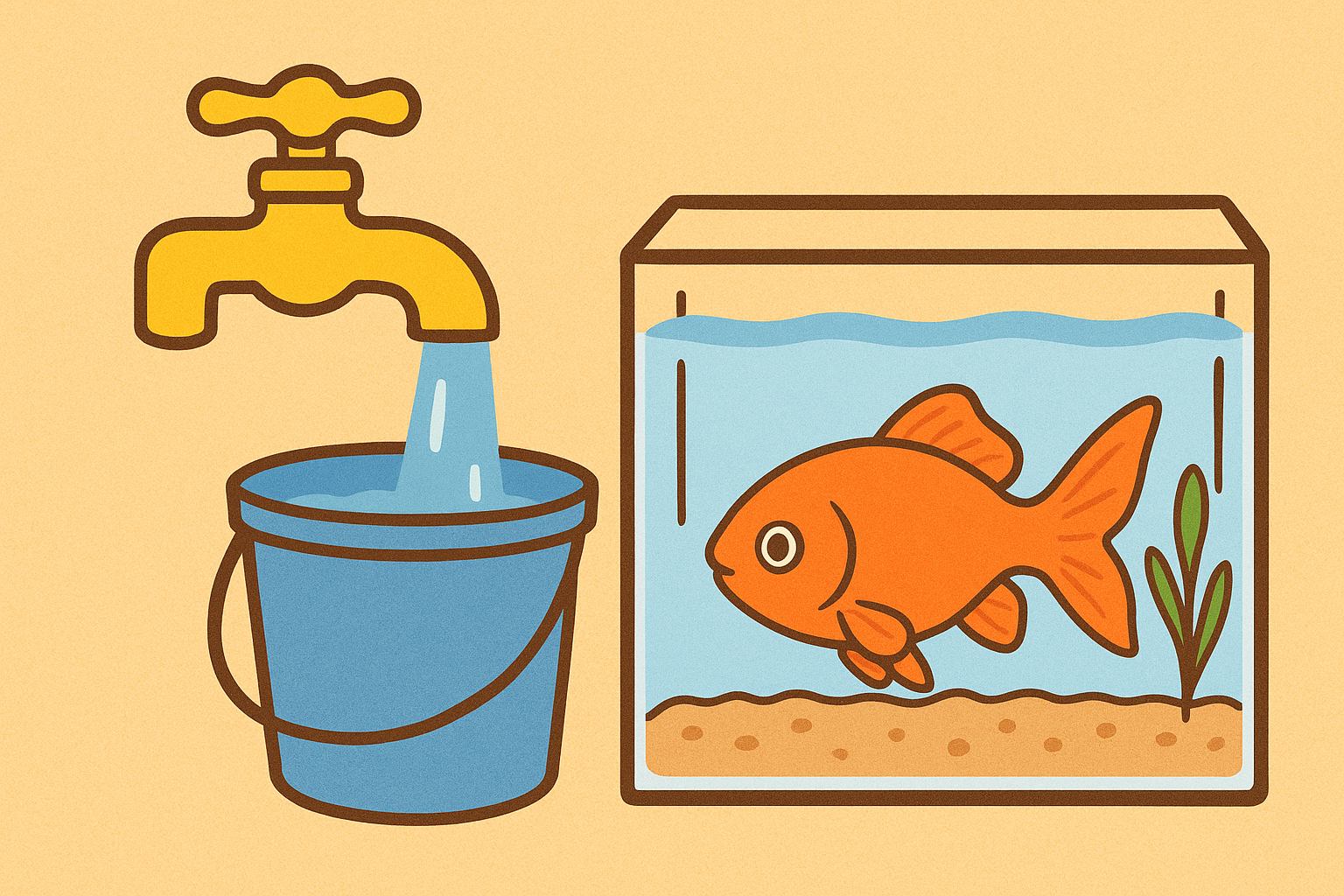高血圧の事 レシピ↓
高血圧症は生活習慣病の代表的な病気です。
日本医師会によると高血圧の患者のうち、
9割以上のケースが、原因が明らかではないようですが、
遺伝的因子と環境因子(生活習慣)が複雑に絡み合い発症するようです。
高血圧症が長く続くと、心筋梗塞、狭心症、
脳卒中を引き起こしてしまいます。
食生活をはじめとした生活習慣を改善することで血圧を下げ、安定化させましょう。
高血圧症 食事のポイント
 肥満解消 (食事やウォーキング・・・一日7000歩は歩きましょう)
肥満解消 (食事やウォーキング・・・一日7000歩は歩きましょう) 飽和脂肪酸(肉脂、バター、ラード、マーガリンなど)
飽和脂肪酸(肉脂、バター、ラード、マーガリンなど)の摂取をなるべく減らす
 食物繊維を多くとる
食物繊維を多くとる 菜食主義的食事
菜食主義的食事(→ 食物繊維・カリウム・マグネシウムが多く脂肪やコレステロールが低いためです)
 ミネラルは、カリウム・カルシウム・マグネシウムを重視
ミネラルは、カリウム・カルシウム・マグネシウムを重視(→よく 「塩分控えめに・・・」と言われますが、
正確には塩分の中に含まれる「ナトリウム」が良くないのです。
カリウムは 体内に過剰に摂取されがちなナトリウムを排泄するは働きがあります)
 不飽和脂肪酸の摂取源は、少量のオリーブ油・ゴマ油や EPAの多い(青い)魚を
不飽和脂肪酸の摂取源は、少量のオリーブ油・ゴマ油や EPAの多い(青い)魚を にんにくは 血圧を下げる (ただし、心臓疾患のある方は注意してください)
にんにくは 血圧を下げる (ただし、心臓疾患のある方は注意してください)玄米菜食(カリウム・マグネシウム・カルシウムが多いもの)
を心がけ、週に2回は魚を食べましょう
 カリウム(ナトリウムの排泄を促す)を多く含む食材は?
カリウム(ナトリウムの排泄を促す)を多く含む食材は? 海藻類 豆類 アボカド さといも・山芋・サツマイモなどのイモ類
海藻類 豆類 アボカド さといも・山芋・サツマイモなどのイモ類 毎日の調味料は厳選する→塩は精製度の低い天然塩を!カリウムをはじめミネラル豊富です
毎日の調味料は厳選する→塩は精製度の低い天然塩を!カリウムをはじめミネラル豊富です砂糖も 黒砂糖にはカリウムをはじめミネラル・鉄が多く含まれます
 マグネシウム(欧米型の食事では不足しやすい)を多く含む食材は?
マグネシウム(欧米型の食事では不足しやすい)を多く含む食材は?アマランサス(ご飯にまぜて普通に炊ける) ごま 大豆製品 干しひじき→ 摂取源でもっとも高い割合を占めるのは穀物なので、
主食は精製度の低い玄米や胚芽米・全粒粉パンにするのがオススメ
 カルシウムを多く含む食材は?
カルシウムを多く含む食材は?
小魚類(田作り・干しえびは、ダントツ)
海藻類→ 酢やレモン・りんごなどに含まれるクエン酸は
カルシウムの吸収率を良くするので、料理で活かしましょう
魚類のオススメは?
さば いわし さんま あじ ぶり サーモン まぐろ
など→ 鮮度のいいものを摂りましょう
青魚に多く含まれるDHAやEPA(不飽和脂肪酸)は、
栄養価がとても高い反面酸化されやすいという弱点があるためです)
→ 調理は、成分をそのまま摂れる刺身が最良 煮魚などでもOK
高温で魚の脂肪分を溶け出させてしまう揚げ物は 好ましくないですよ
穀物や豆類・野菜・果物・海藻などをバランスよく
盛り込んだ食事を摂ることを心がけましょう
 高血圧症に有効な栄養成分
高血圧症に有効な栄養成分以下の成分はなぜ良いのか、まとめてあります。
是非ご一読して、日々の食生活の改善にお役立てください。
カリウム カルシウム マグネシウム カゼイン カテキン タウリン
食物繊維 EPA DHA 多価不飽和脂肪酸 ルチン
 カリウム
~ 血圧を下げ、高血圧症を予防する ~
カリウム
~ 血圧を下げ、高血圧症を予防する ~食塩に含まれるナトリウムの過剰摂取が高血圧症の大きな要因ですが、
カリウムには余分なナトリウムと結びついて体外に排泄する作用があります。
塩分を控え、カリウムの摂取をふやすことはより効果的です。
カリウム? 体内には体重 1kg当たり2gのカリウムがあり、
生命活動を維持するうえで重要な役割を担っています。
ナトリウムの過剰に対し、カリウムのとり方が少ないことが、
高血圧を招く要因になっています。不足に気をつけたいミネラルです。
浸透圧の維持は生命活動の基盤
カリウムはナトリウムと協力して細胞内外液の浸透圧を維持します。
細胞の内側に多いのがカリウム、外側(血液など)に多いのがナトリウムです。
液体は濃度の低いほうへ流れようとしますが、細胞はこの自然な流れに
逆らって細胞内にカリウムをとどめ、細胞外にナトリウムを出して浸透圧を
維持します。浸透圧は、細胞内外の水分やいろいろな成分を調整するはたらきをもっています。
血圧を下げる
ナトリウムのとりすぎは高血圧を招きます。
カリウムにはナトリウムの排泄を促して血圧を下げる作用があります。
食塩を減らすとともに、カリウムの摂取量をふやして
高血圧を予防・治療しましょう。
筋肉の動きをよくする
夏バテはビタミンB1不足が原因といわれますが、
カリウム不足のことも多いのです。カリウムは筋肉でエネルギーづくりにはたらいていますから、
不足すると筋肉の動きが悪くなり、力が出ません。夏場は大量の汗をかきますが、
カリウムが汗といっしょに失われておこる低カリウム血症が、夏バテの原因といわれています。
カリウムは失われやすい
野菜、果物など幅広い食品に含まれるわりに、不足しやすいミネラルです。
調理でも失われ、煮た場合の損失は約30%です。
また、食塩の摂取量が多いとナトリウムとともに排泄されます。
ストレス、慢性的な下痢、利尿剤の長期利用、コーヒー、酒、
甘いものもカリウムを減らします。糖尿病の人も欠乏しやすくなります
カリウムは体内でこんな作用をします
- ナトリウムとともに、水分を引きつけて細胞の浸透圧を維持する。
細胞の内外で物質のやりとりをする。
- ナトリウムによる血圧上昇を抑制する。
- 筋肉の収縮を円滑にする。
- エネルギーの産生にはたらく。
- 腎臓における老廃物の排泄を促す。
- 筋肉細胞に60% があり、ほかに骨、脳、肝臓、心臓、腎臓などに多い。
過剰症 心配ない。腎臓の機能障害では、カリウムの排泄障害から高カリウム血症となる。
上手に摂取するには?
水に溶けやすく、調理による損失も大きいため、
できるだけ生で食べるようにしましょう。加熱の場合には、
煮汁にカリウムが溶け出しているので、煮汁もいっしょに食べます。
また、食塩の摂取が多いと、ナトリウムといっしょにカリウムも
排泄されてしまいますから要注意。
カリウムを多く含む食品 ~ 1日の所要量 2000ミリグラム ~ 単位 グラム・ミリリットル/ミリグラム
刻み昆布 10/820
ほうれん草 100/690
トマトジュース 200/546
小松菜 100/500
さつまいも(蒸切干) 50/490
さわら 100/490m
かんぱち 100/490
春菊 100/460
西洋かぼちゃ 100/450
干しひじき 10/440
特に摂取した方が良い人 高血圧症
 カルシウム
~ 血行を良くし血圧を正常にする ~
カルシウム
~ 血行を良くし血圧を正常にする ~カルシウムが不足すると、貯蔵庫である骨から力ルシウムが流出してはたらきますが、
血管壁にも付着します。これがスムーズな血行を妨げ、高血圧を誘引することになります。
カルシウムをしっかりとって高血圧を予防しましょう。
カルシウム? 健康な骨と歯をつくるほか、
重要な生理作用を担っています。過去20年間日本人の平均的摂取量は
一度もカルシウムの所要量 (600ミリグラム) を満たしたことがなく、
最近でも93%の充足率です。骨組鬆症の予防のためにも充分に摂取したいミネラルです。
骨以外でも大活躍
成人の体内には体重50kgの人で約 1kgのカルシウムがあり、
その99%は骨や歯をつくっています。残りの1%は血液中や筋肉、
神経などにあり、重要な作用をしています。神経のいらだちを抑える
トランキライザー(精神安定剤)のはたらきのほか、筋肉を収縮させて
心臓を規則的に正しく活動させます。不足すると、
副甲状腺ホルモンやビタミンDがはたらいて、骨からカルシウムを急いで放出させ、
血液中のカルシウム濃度を一定に保ちます。骨は、カルシウムの貯蔵庫であり、
摂取量が少なければ減り、多ければ蓄積されます。
肩こり、イライラもカルシウム不足
カルシウムの慢性的な不足状態が続くと、骨のカルシウムが失われ、
成長期であれば歯の質が悪くなったり、あごの骨の発育に影響が出ます。
骨質が薄弱となって腰痛、肩こりがみられ、骨がスカスカになっていきます。
また、血行と血液の性状に支障をきたし、高血圧や動脈硬化の原因にもなります。
だるい、怒りっぽい、イライラもカルシウム不足からおこります。
カルシウム不足を招く要因
肉類など、タンパク質の過剰摂取はカルシウムの排泄量をふやします。
ナトリウムの過剰摂取も同様です。また、肉や加工食品に多く含まれ、
とりすぎの傾向にあるリンは、カルシウムの 2~3倍量を超えてとると、
カルシウムの吸収を抑制します。
体内での作用
- リン、マグネシウムなどとともに骨や歯を形成し、健康を維持する。
- 心臓の鼓動を保ち、筋肉の収縮をスムーズにする。
- 神経の興奮を鎮め、精神を安定させる。
- 血液を固めて出血を防ぐ。
- 各種ホルモンや睡液、胃液などの分泌にはたらく。
- 細胞の分裂、分化を促す。
- 白血球の食菌作用を助ける。
- 体内の鉄の代謝を助ける。
- 体液、血液の恒常性を維持する(微アルカリ性に保つ)
過剰症 過剰に吸収されるととは通常ない。
ビタミンD過剰による過剰吸収では、高カルシウム血症になりやすい。
上手に摂取するには?
吸収率のよい牛乳・乳製品を積極的にとりましょう。
ビタミンDといっしょにとるとさらにカルシウムの吸収はよくなります。
肉のタンパク質、野菜のしゅう酸、豆・穀類のフィチン質、
食物繊維はカルシウムの吸収を阻害します。
偏って多くとりすぎないようにしましょう。
カルシウムを多く含む食品 ~ 1日の所要量 男性600~700ミリグラム 女性60ミリグラム ~ 単位 グラム・ミリリットル/ミリグラム
干しえび 10/710
どじょう 50/550
エメンタールチーズ 30/360
わかさぎ(佃煮) 30/291
うるめいわし(丸干し) 50/285
牛乳 200/231
小松菜 100/170
干しひじき 10/140
がんもどき 50/135
モロヘイヤ 50/130
だいこんの葉 50/130
特に摂取した方が良い人高血圧症
 マグネシウム
~ 毛細血管を広げ、血圧を下げる ~
マグネシウム
~ 毛細血管を広げ、血圧を下げる ~マグネシウムは動脈を弛緩させ、逆にカルシウムは収縮させて
バランスをとっていますが、マグネシウムが不足すると動脈の収縮が起こり、血圧が上がります。
マグネシウムを充分にとることで、血圧を下げ、正常に保ちます。
マグネシウム? 体内で約制種類もの酵素のはたらきを助けています。
カルシウム以上に不足しがちなミネラルです。不足すると心疾患を招きます。充分な摂取を心がけましょう。
心疾患を予防
筋肉の収縮は、筋肉細胞の中にカルシウムが入ることで、
緊張が高まっておこります。このカルシウムの動きを調節しているのが
マグネシウムです。マグネシウムが不足すると、細胞の中にカルシウムが
流れ込みすぎて、筋肉の収縮がうまくいかず、けいれん、
ふるえなどの症状が出ます。神経はイライラと興奮しやすくなります。
筋肉のけいれんが血管壁でおこると、狭心症や心筋梗塞につながりかねません。
実際、マグネシウムに対するカルシウムの摂取比が高まるほど
心臓発作による死亡率が高いと報告されています。
マグネシウムはカルシウムの血管壁への沈着を防いで
動脈硬化を予防したり、正常な血圧の維持、骨の強化にも貢献しています。
カルシウムとのバランスが大事
カルシウムとマグネシウムの理想のバランスは2対1から 3 対 1 です。
カルシウム600~700ミリグラム、マグネシウム240~320ミリグラムという
1日の所要量を満たせれば、合格です。マグネシウムの実際の摂取量は
約200ミリグラムで不足傾向にあります。カルシウムが骨粗鬆症の予防から
多くとるようにすすめられているのに対して、マグネシウムへの
関心はいまひとつです。牛乳を大量に飲む人はマグネシウムの摂取も
心がけましょう。カルシウムが過剰になると、
マグネシウムの吸収を阻害します。
マグネシウム不足を招く要因
ストレスはマグネシウムの必要量を増加させます。肉や加工食品、
清涼飲料水などに含まれるリンを多くとると吸収が妨げられます。
大量のアルコール、利尿剤も不足を招きます。
また、糖尿病患者も欠乏しやすくなります。
体内での作用
- 刺激に対する神経の興奮を鎮め、筋肉の収縮を促す。
- ビタミン B 群とともに、糖質、脂質、タンパク質の代謝や核酸の合成にはたらく。
- 軟組織にカルシウムの沈着するのを防ぐ。
- カルシウムを骨から出す副甲状腺ホルモンの合成に必要。
- 血液を固まりにくくする。
- 体温や血圧を調節する。
- 成人の体内に約30%ある。55%は骨にあり、次いで多いのは筋肉の中。1%は血清中。
過剰症
過剰にとっても腎臓から排泄される。腎臓に障害のある人は過剰症に注意したい。
上手に摂取するには?
マグネシウムと力ルシウムの摂取バランスは1対2~1対3がよいとされています。
カルシウムを大量にとる人はマグネシウムもその分お忘れなく。
ストレスや、激しいスポーツのあと、
また、リンを多く含む加工食品のとりすぎは、マグネシウムの不足をきたしがちです。
 マグネシウムを多く含む食品
マグネシウムを多く含む食品
ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ、落花生) 野菜類(ほうれん草、
ごぼう、かんぴょう、おかひじき、しそ、パセリ)
大豆・豆類(納豆、豆腐、きな粉、いんげん豆、枝豆)
魚介類(かき、さざえ、かつお、すじこ、ほんまぐろ)
果物類(バナナ、干し柿、びわ)
穀類・その他(とうもろこし、干しひじき、小麦胚芽、そば粉)
特に摂取した方が良い人高血圧症
 カゼイン
~ 高血圧症を予防、改善する ~
カゼイン
~ 高血圧症を予防、改善する ~カゼインを充分にとると血圧の上昇が抑制され、
逆に不足すると高血圧から脳卒中へ移行する割合が高くなることが報告されています。
カゼインには体内で力ルシウムの吸収を促進する作用があり、
血圧を下げ、高血圧症を予防します。
カゼインが消化途中でできるCCP(カゼインホスホペプチド)も同様のはたらきがあります。
カゼイン? カルシウムの吸収促進、造血などさまざまな作用
牛乳のタンパク質は非常に栄養価が高く良質ですが、
その75~85%を占めているのがカゼインです。
カゼインは単一の物質でなく、4種のカゼインの複合体です。
ペプチドが生理機能を発揮する カゼインが体内で分解されると、
各種のペプチド(アミノ酸の大きな集合体であるタンパク質が分解されてできる、
アミノ酸の小規模な集合体)ができ、さまざまな作用をします。
カルシウム吸収促進効果のあるCPP(カゼインホスホペプチド)や、
回腸平滑筋の収縮効果のあるカソキシンなど、
その作用は多岐にわたっています。β-カゾモルフィン、
α-カゼインエクソルフィンは鎮痛効果をもつペプチドですが、
腸の蠕動運動を抑制する作用もあります。
食べ物の腸での滞在時間が長くなることで栄養素の消化吸収が良くなり、
やせた人の栄養摂取に有効です。
上手に摂取するには?
牛乳に含まれるタンパク質の約8割がカゼイン。
牛乳・乳製品を毎日欠かさずとるようにしましょう。
牛乳こ含まれる脂肪やコレステロールが気になる人は、
低脂肪タイプの牛乳やヨーグルト、カッテージチーズ、
スキムミルクなどがおすすめです。ビタミンDを多く含む
食品といっしょにとると効果がアップします。
カゼインを多く含む食品
牛乳・乳製品
特に摂取した方が良い人高血圧症
 カテキン
~ 血行を改善し、血圧を下げる ~
カテキン
~ 血行を改善し、血圧を下げる ~静岡県を中心とした調査結果から、お茶が血中コレステロールの増加を
抑制することは明らかで、その作用を発揮するおもな成分はカテキンと
推定されています。
血中のコレステロールや脂質を取り除いて血行をよくし、血圧を低下させます。
なお、カテキンは緑茶成分ですが、紅茶に含まれるテアフラビンにも
血圧上昇を抑制する作用のあることが証明されています。
カテキン? 緑茶の渋味成分です。抗酸化作用を示し、
活性酸素の害を防ぐので、発がん、老化、動脈硬化を抑制する効果があります。
そのほか、細菌の増殖を防ぐ作用や、抗毒素作用もあります。
胃炎や胃潰瘍の原因になる、ヘリコバクター・
ピロリという細菌が死滅することが認められています。
ピロリ菌は狭心症・心筋梗塞との関連が大きいことも知られています。
上手に摂取するには?
カテキンの量は3煎目以降極端に減少するため、
茶葉をとりかえながら、濃いめに入れるのがコツです。
ただし、飲むときは、ややぬるめにしましょう。
熱い温度のものを飲むと、のどや食道の内壁が傷つき、
がんの発生につながる危険性があります。
また、緑茶にはがん予防に役立つ食物繊維やビタミンEなど
水に溶けない成分も豊富に含まれているので、
飲むよりも茶葉を食べるほうが、より効果的です。
カテキンを多く含む食品 ~ 1日の目標摂取量1g ~
緑茶(茶葉100g中に10~18g)
※茶葉3gに100~120gの湯を注ぐと約100ミリグラムのカテキンが摂取できます。
1日の目標量を取るには新しく入れたもので約10杯のお茶が必要です。
特に摂取した方が良い人がん 高血圧症
 タウリン
~ 血圧を下げ、正常に保つ ~
タウリン
~ 血圧を下げ、正常に保つ ~タウリンには交感神経抑制作用があり、食塩によって引き起こされる
高血圧を改善し、血圧を安定させることが報告されています。
タウリンは魚介類に多く含まれていますが、魚介を多く食べる地域に
高血圧症や高血圧が起こす脳卒中などが少ないことも大きな理由の一つです。
タウリン? 血合いにはタウリンが豊富に含まれています。
するめいかの表面についている、白い紛がタウリン。
タンパク質を構成するアミノ酸の一種で、老化防止に効力があると期待されている。
このタウリンの宝庫が魚の血合い部分なのです。
さばでは身の15~16倍、いわしでは5~6倍も多く含まれており、
また、タウリンだけではなく鉄やビタミンA・B群・D群にも多い。
嫌いな人が多い血合いだが、その栄養価を見直して残さず食べましょう。
上手に摂取するには?
下表中の魚介類はコレステロールも多く含んでいますが、
タウリンの血中コレステロール低下作用により心配無用です。
なおタウリンのほかに、メチオニンなど魚介に含まれる
アミノ酸にも同様の作用が期待できます。
タウリンを多く含む食品
貝類(さざえ・とこぶし・帆立貝・あさり)
たこ・ずわいがに・やりいか
まぐろ(血合い)・たい・さば(血合い)
特に摂取した方が良い人高血圧症
 食物繊維
~ 便秘を予防し、血圧を安定させる ~
食物繊維
~ 便秘を予防し、血圧を安定させる ~便秘をすると血圧は上がりやすくなります。食物繊維は便量をふやし、
腸のはたらきを活発にして便秘を予防します。
また、水溶性の食物繊維にはナトリウムを包み込み、
排泄する作用があり、血圧を下げます。特にこの作用は、
アルギン酸(海藻類のヌルヌル成分)に顕著です。
食物繊維? 昔は、食物繊維(ダイエタリーファイバー)
は体の構成成分やエネルギー源にならないため、
無益な食べ物のかすとして扱われていましたが、その後の研究の結果、
現在では「人の消化酵素で消化されない食品中の難消化性成分の総体」と
定義され、五大栄養素(糖質、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル)に
続く、第六の栄養素として重要視されています。
食物繊維は、植物細胞の構成成分を中心に動物性の成分も含み、
水に溶けない「不溶性食物繊維」と水に溶ける「水溶性食物繊維」
に分けられます。自然の食品中のもの以外に、
食品から抽出した成分を加工して機能を高め用いやすくしたもの、
化学物質を合成したものなどがあります。
従来の日本人の食生活では穀物や野菜、いも、豆、
海草が多く動物性脂肪の摂取が少なかったため、食物繊維の不足はありえませんでした。
現代は、食生活の欧米化が進み、精製原料でつくられる加工食品を
多く食べています。その結果、食物繊維の不足から起こる便秘や肥満、
虫歯、虫垂炎や大腸がんなどの腸疾患、高血圧や糖尿病などの
生活習慣病まで、多くの病気を抱えることが多くなっています。
これらの病気の予防と改善には、当然食物繊維の摂取が有効ですが、
食物繊維にも種類があり、生理作用も異なっています。
単一の食品からまとめて取るのではなく、多種類の食品から摂取しましょう。
食物繊維の種類
分類・名称 豊富に含む食品
不溶性食物繊維
野菜 穀類 豆類 小麦フスマ
穀類 豆類 小麦フスマ
未熟な果物 野菜
ココア 小麦フスマ 豆類
ごぼう
きのこ類
えび・かにの殻 イナゴの外皮
セルロース
ヘミセルロース
ペクチン
リグニン
イヌリン
グルカン
キチン ・キトサン
水溶性食物繊維
熟した果物
樹皮 果樹
食物の種子・葉・根など
海藻
ペクチン
植物ガム(グアーガム)
粘質物(マンナン)
海藻多糖類(アルギン酸、
ラミナリン、フコイダン)
その他
動物食品の骨・腱など
コンドロイチン硫酸
コラーゲン
上手に摂取するには?
1食分10g前後を目安に野菜や果物、きのこ、海藻類などを組み合わせて、
多種類の食物繊維をとることがコツ。野菜は生で食べるより、
煮たり炒めたりしたほうが、たくさん食べられます。
けんちん汁など実だくさんの汁物がおすすめ です。
特にアルギン酸が多い褐藻類(昆布、わかめ、ひじき、など)は高血圧に効果的です。
食物繊維を多く含む食品
干し柿 50g/7.0g
いんげん豆(ゆで) 50g/6.7g
ひよこ豆(フライ) 30g/6.3g
あずき(ゆで) 50g/5.9g
オートミール 50g/4.7g
そら豆(フライ) 30g/4.5g
干しひじき 10g/4.3g
甘栗 50g/4.3g
サツマイモ(蒸し) 100g/3.8g
アーモンド(フライ) 30g/3.6g
水溶性食物繊維を多く含む食品 ~ 1日の所要量 2000ミリグラム ~
エシャロット 30g/2.8g
オートミール 50g/1.6g
干しあんず 30g/1.3g
サツマイモ(蒸切干) 30g/1.3g
納豆 50g/1.2g
ごぼう 50g/1.2g
プルーン 50g/1.2g
金時にんじん 30g/1.0g
ライ麦パン 50g/1.0g
ゆり根 30g/1.0g
西洋かぼちゃ 100g/0.9g
アボガド 50g/0.9g
春菊 100g/0.8g
特に摂取した方が良い人がん 高血圧症
 EPA
~ 血液の流れを良くし、血圧を下げる ~
EPA
~ 血液の流れを良くし、血圧を下げる ~EPAは血液を固まりにくくし、血夜の流れをよくすることで知られています。
また、血管を拡張するはたらきも認められています。
収縮をゆるめた血管で血液がさらさらとスムーズに流れれば血圧は下がり、
高血圧症は改造されます。
EPA-エイコサペンタエン酸?
EPAはn-3系列の多価不飽和脂肪酸で、
国際的にはIPAの呼び名が一般的です。
食品からとらなければ人間の体内ではつくることができません。
植物油などα-リノレン酸を含む食品を摂取すると、
体内ではEPA変わります。そのほかに魚の脂肪に多く含まれ、
EPAとしてのおもな供給源は脂肪の多い魚です。抗血栓、
コレステロール低下などの作用により、多くの生活習慣病の予防、
改善に効果があることが解明されています。
高脂肪食なのに血栓性疾患が少ないイヌイット
1970年代に行なわれた調査によれば、イヌイットの脂肪摂取量は
エネルギー比で約40%に達しており、かなりの高脂肪食です。
そしてこれは、デンマーク人とほぼ同じでした。
総コレステロールをみると、イヌイットがデンマーク人の2倍、
血中コレステロール値は同程度です。ところが、
デンマーク人の死亡原因の40%以上を心筋梗塞が占めるのに対して、
イヌイットは動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞などの生活習慣病が大幅に
少ないことがわかったのです。発症率の高いはずの61歳以上でも、
心筋梗塞はわずかに3.6%でした。そして、その理由としてあげられたのは、
イヌイットの食生活の中心となっている魚やアザラシなどから、
EPA、DHAを多く摂取していることでした。
日本でも、千葉県の沿岸漁民と山間部の農民の食生活を調査した報告が
あります。血液中の脂肪酸構成比では漁民のほうが農民よりEPAの比率が高く、
血小板の凝集しやすさをみる検査では、漁民は農民の3分の1でした。
漁民はいわしなどの魚を農民の平均2.5倍摂取し、摂取EPA量は農民の2.7倍です。
魚の不漁の年には血中EPAが減り、血小板が凝集しやすいという結果も認められました。
現代人に多い循環器系、神経系の疾患を予防、改善する<
EPAには血液中の血小板の凝集を抑制し、血栓を溶解させ、
血管を拡張する作用があることがわかっています。さらに、
血中の中性脂肪濃度が高くなるのを抑制し、血管の中を血液がスムーズに流れるようにして、
動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、高血圧といった成人病を予防します。
そのほか、アトピー性皮膚炎、花粉症、気管支ぜんそくなど
アレルギー症状の予防と治療、慢性関節炎などの炎症性疾患の症状改善にも
効果があることが知られています。
体内でEPAから合成される脂肪酸で、EPAと同じく魚の脂肪に多く含まれる
DHAも同様のはたらきをしますが、血液の凝固を抑制する作用はEPAのほうが強く、
悪玉コレステロールを下げる作用はDHAにより強くみられるということです。
また、同じ多価不飽和脂肪酸のアラキドン酸にはこれらの作用と反対の作用があるので、
アラキドン酸が多くなりすぎると成人病の症状が出ることになります。
アラキドン酸のもとになるリノール酸をとりすぎないようにし、
EPAやDHAなどを積極的にとることが、EPA、DHAの特性を生かすことにつながります。
効果的なとり方
EPAは魚の脂肪に含まれる成分なので、あっさりした自身魚より、
いわし、さんま、さばのような脂肪の多い魚に多く含まれる。
まぐろの刺身なら赤身よりとろ、中とろを選ぶとよい。
調理法では、脂肪を外に逃がさないという理由で刺身が最良。煮魚、
グラタンなども悪くない。高温で加熱して脂肪分を溶け出させてしまう
揚げ物はあまり好ましくない。
体内で酸化して過酸化水素ができるのを防ぐため、
β-カロテンの多い緑黄色野菜といっしょにとるのが効果的。
体内での作用
- 血小板の凝集を抑制する。
- 血栓を溶解させる。
- 血管を拡張する。
- 悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールをふやす。
- 血液中の中性脂肪を減らす。
- 抗がん効果がある。
- アラキドン酸の作用を抑制する。
過剰症 血液が凝固しにくくなり、出血が止まりにくくなる。
上手に摂取するには?
魚の脂肪分を逃さないような調理法で食べます。
刺身がいちばんですが、揚げ物や焼き物より、
溶け出した脂肪もいしょにとれる煮物やスープなどがおすすめです。
なお、脂肪は酸化しやすいのが欠点。新鮮なうちに、
酸化を防ぐ野菜といっしょに食べましょう。
但し、鮮度の落ちた魚は逆効果です。
不飽和脂肪酸(EPA、DHA)には動脈硬化や老化を防ぐということで
話題になっていますが、新鮮な魚に限ってのことで、鮮度が落ちると、
不飽和脂肪酸は変質して過酸化脂質になってしまいます。
酸化した脂肪は毒性が強く腐った油脂とも言われ、
動脈硬化を促す有害物質で知られており、血管の内膜を傷つけ、
ここに血小板が凝集して血栓ができやすくなる、というわけです。
動脈硬化予防のために魚を食べたつもりが、
かえって動脈硬化を進行させることになり、
まったく逆効果となってしまいます。傷みかけているような魚には、
くれぐれも手を出さないようにしましょう。
EPAを多く含む食品
青背の魚(はまち まいわし さば さんま
ぶり あじ にしん かつお
さわら) 脂肪の多い魚(まぐろ きんき
まだい はも まぐろとろ
やつめうなぎ)
特に摂取した方が良い人高血圧症
 DHA
~ 中性脂肪を減らし、高血圧症を改善する ~
DHA
~ 中性脂肪を減らし、高血圧症を改善する ~EPAと同様に、血液が固まって血栓が出来るのを防ぐ作用があり、
血圧を下げます。また、脂肪酸合成に関わる酵素の活性を低下させる作用も
明らかで、中性脂肪を減らし、アラキドン酸(しばしばDHAと逆の作用をする)
を抑制することによって高血圧症を改善、予防します。
DHA-ドコサヘキサエン酸? DHAはn-3系列の多価不飽和脂肪酸で、
植物油などα-リノレン酸を含む食品を摂取すると、からだの中でEPAを経て
合成されます。また、EPAと同様に魚の脂肪に多く含まれており、
供給源として期待されるのは脂肪の多い魚です。悪玉コレステロールを減らし、
善玉コレステロールをふやす作用が顕著にみられるほか、
現代人がかかりやすいさまざまな症状、病気を予防、改善する機能があります。
コレステロール、中性脂肪を減らす
魚は冷たい海の中にすむため、魚の脂肪はマイナス45℃という
低温になるまで液状を保ちます。えさとなる植物性プランクトンに含まれるα-リノレン酸が、
魚の体内に蓄積されて、EPA、DHAに変化します。いわし油にはEPA、
DHAともに約10%、まぐろの目の脂肪にDHAが約30%含まれます。
詳しい仕組みはまだわかっていませんが、魚の脂肪をとることにより、
コレステロールの生成が低下し、肝臓から血築中への
コレステロールの分泌が少なくなることが証明されています。
また、DHA、EPAには脂肪酸合成に関与する酵素の活性を低下させる作用があります。
血築中の中性脂肪が低下し、臓器内のアラキドン酸(DHAと逆の作用をすることが多い)も
低下することで、脳卒中、痴呆、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、
高血圧、動脈硬化、慢性炎症性大腸疾患、高脂血症、皮膚炎などの予防、
改善に効果があります。
脳の機能を高める「健脳食」
DHAは脳をはじめとする神経組織に非常に多く含まれ、
脳や神経組織の発育や機能維持に重要な役割を果しています。
人の脳のニューロンという神経細胞の突起の先端にはDHAが含まれています。
ニューロンの突起がつながって神経回路をつくり、情報伝達を行ないますが
DHAが不足すると情報伝達がうまくいかなくなり、学習能力や記憶能力に影響を与えます。
日本の子どもは欧米の子どもより知能指数が高いことが知られていますが、
その理由のひとつは、欧米よりも魚を多く食べているために、
DHAの影響で記憶力と学習能力がすぐれているのではないかとも
考えられています。DHAは、乳幼児の脳の発達や視力の向上に役立っており、
DHAが欠乏すると発育に支障をきたすことがわかっています。
また、老化に伴う学習能力の低下、視力の低下などに関する研究も
進んでおり、アルツハイマー型老人性痴呆症の改善にも
役立つものとみられています。伝統的に魚食民族であった日本人も、
現在は肉類からの脂肪摂取がふえ、魚からのD
HAやEPAの摂取が減っています。健康を考えると、
肉と魚の摂取バランスを見直す必要がありそうです。
体内での採用
- 悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールをふやす。
- 脳・神経組織の機能にかかわる。
- 血小板の凝集を抑制する。
- 血圧を下げる。
- 血液中の中性脂肪を減らす。
- 炎症を抑制する。
- 抗腫療効果がある。
- アラキドン酸の作用を抑制する。
過剰症 血液が凝固しにくくなり、出血が止まりにくくなる。
上手に摂取するには?
DHAを多く含んでいるのは脂肪分の多いごく一般的な魚です。
できるだけ魚を主菜にした献立を心がけましょう。
脂肪は酸化しやすいので、新鮮なものを生で食べるのが効果的。
また揚げ物、焼き魚よりは煮魚やグラタンがおすすめです。
DHAを多く含む食品
魚の脂肪分を逃さないような調理法で食べます。
刺身がいちばんですが、揚げ物や焼き物より、
溶け出した脂肪もいしょにとれる煮物やスープなどがおすすめです。
なお、脂肪は酸化しやすいのが欠点。新鮮なうちに、
酸化を防ぐ野菜といっしょに食べましょう。
但し、鮮度の落ちた魚は逆効果です。
不飽和脂肪酸(EPA、DHA)には動脈硬化や老化を防ぐということで
話題になっていますが、新鮮な魚に限ってのことで、鮮度が落ちると、
不飽和脂肪酸は変質して過酸化脂質になってしまいます。
酸化した脂肪は毒性が強く腐った油脂とも言われ、
動脈硬化を促す有害物質で知られており、血管の内膜を傷つけ、
ここに血小板が凝集して血栓ができやすくなる、というわけです。
動脈硬化予防のために魚を食べたつもりが、
かえって動脈硬化を進行させることになり、
まったく逆効果となってしまいます。傷みかけているような魚には、
くれぐれも手を出さないようにしましょう。
特に摂取した方が良い人高血圧症
 多価不飽和脂肪酸
~ 血行を良くし、血圧を下げる ~
多価不飽和脂肪酸
~ 血行を良くし、血圧を下げる ~リノール酸、α- リノレン酸、γーリノレン酸などの多価不飽和脂肪酸は、
血中コレステロールを減らし、血栓を解消し、
血液の流れをよくする作用があり、高血圧症を改善、
予防することが証明されています。なかでもα-リノレン酸は、
体内でEPA、DHAへと代謝されるので、EPA、DHAの機能も期待できます。
多価不飽和脂肪酸? 不飽和脂肪酸の一種。不飽和脂肪酸は炭素と
水素の結合の仕方の違いで、n-9系、n-6系、n-3系の3つの系列に分かれます。
n-9系を単価(モノ)不飽和脂肪酸、
n-6系とn-3系を併せて多価不飽和脂肪酸と呼びます。
多価不飽和脂肪酸は体内で合成されない(されにくい)必須脂肪酸で、
食品からの摂取が必要です。n-6系には、リノール酸、γ-リノレン酸、
アラキドン酸、n-3系には、α-リノレン酸、EPA、DHAがあります。
 ルチン
~ 血圧を下げる ~
ルチン
~ 血圧を下げる ~血管壁を強くし、血圧降下作用のあることが近年の研究で明らかにされています。
ビタミンCの吸収を助けるはたらきもあり、
高血圧予防として期待される成分です。フラボノイドの一種で、
ビタミンP効果があります。
ルチン? ルチンはビタミンCの研究中に発見されたビタミン様物質で、
ビタミンPの一種です。ジャガイモの花、
中国産の豆のエンジュの葉・つぼみ・未熟果などに含まれています。
食べ物ではそばに特徴的な成分です。
ルチンの効果
ビタミンCとともにはたらき、毛細血管を強くして
毛細血管の透過性の増大を抑えるはたらきがあります。
歯ぐきから出血しやすい、傷が治りにくいなどの欠乏症状が知られています。
動脈硬化、高血圧、痔、脳血管障害などの症状もおこりやすいといわれます。
年をとるとともに毛細血管は弱くなり、透過性が増していきます。
ルチンに予防効果が期待されます。ルチンにはまた、
血圧を上昇させる物質のはたらきを弱める作用があります。
これも高血圧や脳血管障害の予防によい点です。
毛細血管を収縮させる一過性の作用もあり、
この作用を利用した止血薬には、エンジュの葉からの抽出物が利用されています。
1日1食が理想
1日にとりたい量は30ミリグラムといわれています。
1日のうち1食そばを食べると充分にとれる量です。
ルチンは、そばの外側の殻に近い部分ほど多く含まれています。
白いそばより、殻に近い部分を含むそばを食べたほうがたくさんとれます。
ルチンは水溶性のためビタミンB1・B2などとともにゆで汁に溶け出します。
そば湯を飲む昔からの習慣は、健康のためにも理にかなったものです。
ルチンはビタミンCとともにはたらきますから、
Cの豊富な野菜や果物をいっしょに食べるとより効果的です。
そば茶、そば粉を使ったパンケーキの利用もよいでしょう。
ルチンはそばの全草に含まれており、若葉の粉末を利用した健康食品も市販されています。
ルチンは国体内でこんな作用をします
- 毛細血管壁を強くし、透過性が増しすぎるのを抑制する。
- 血圧降下作用がある。
- 血管収縮作用がある。
- ビタミンCの吸収を助け、酸化から守る。
過剰症 心配ない。
性質 水溶性。熱、光、酸素に弱い。
上手に摂取するには?
天然に広く分布していますが、食品としてはとりにくいので、
そばの若葉粉末など市販の健康食品を利用しましょう。
なお、ルチンはビタミンCといっしょにとると効果的です。
ビタミンCはみかん、オレンジなどの柑橘類やいちご、
野菜などに多く含まれています。
ルチンを多く含む食品 ~ 1日の所要量 2000ミリグラム ~
そば(そば湯にとけてしまう) トマト
エンジュ(葉、つぼみ、未熟果)
タバコの葉 じゃがいもの花
特に摂取した方が良い人高血圧症
© Rakuten Group, Inc.