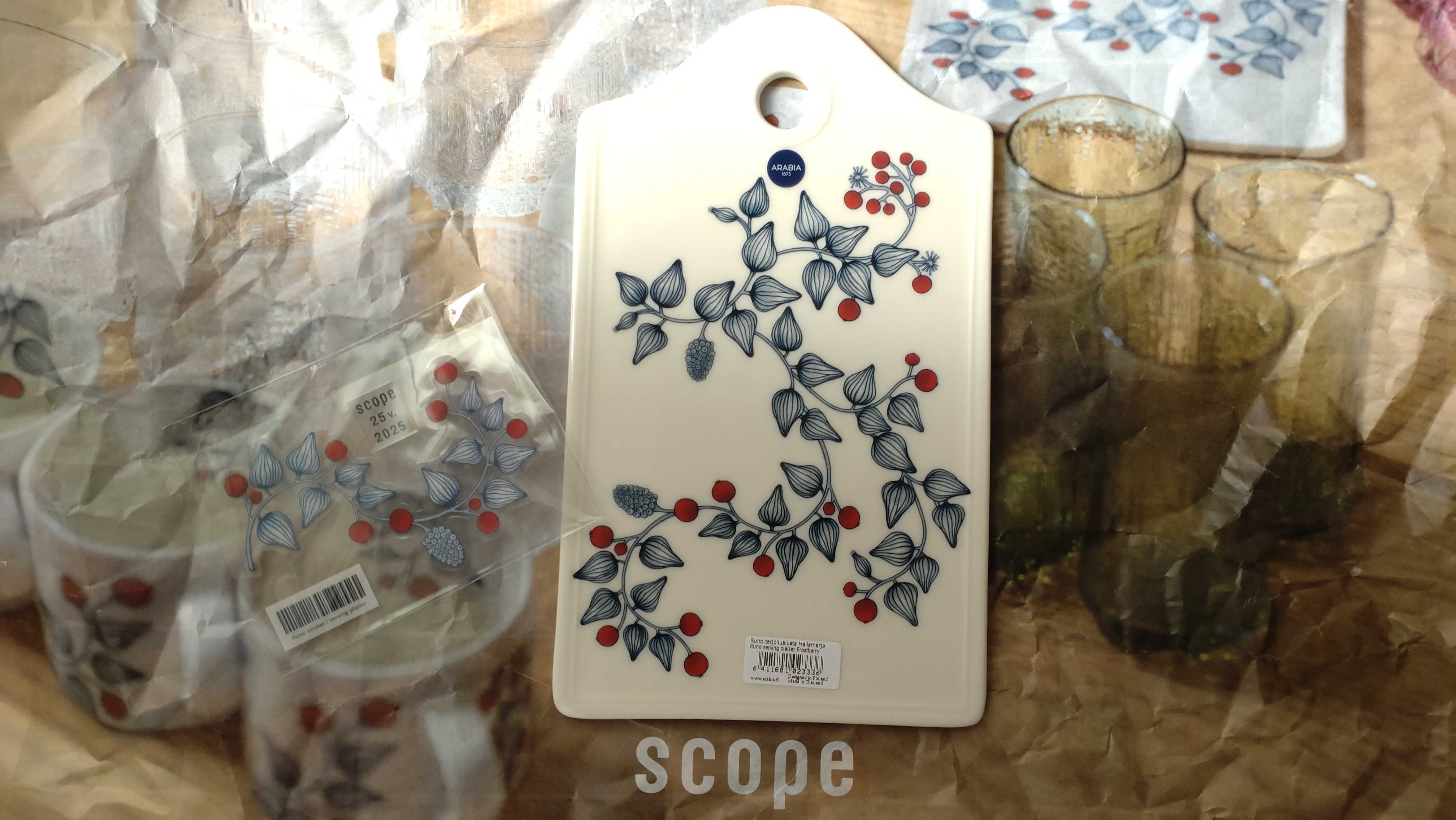2017年03月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

久しぶりに名古屋へ
娘・息子と3名でレゴランド・ジャパンへ行ってきました。弊社の新キャラクター「ダス犬」も活躍していました。
2017.03.27
-
とある法務部員の1日
珍しく早朝出勤したつもりが、意外と人が多い。朝早くからお疲れちゃん&ナニしてんの?電車は空いているし、悪くはない。 朝礼前に呼び出しを受けての作戦会議、その後は別件で某法律事務所へ。昼前一旦帰社し、外部法務セミナーへ。全4回シリーズの最終回でした。OEM契約・ODM契約、ソフトウェア開発委託契約の2コマ。 後半の講師が超べっぴんさんでおったまげた。その後、受講生有志8名で打ち上げ。娘の年齢に近いメンバー~インハウスローヤーまで。バタバタ=充実した1日だったかな。 南海電車に揺られながら・・・
2017.03.22
-
社労士総研 研究プロジェクト報告書
社労士総研の報告書が興味深い。『社会保険労務士の業務が中小企業の コンプライアンス・業績・産業保健に 及ぼす効果に関する調査研究』https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/souken/2017.pdf
2017.03.12
-

日本労務学会例会へ
6年前のこの日、都内で帰宅困難者となっていたことを思い出す。復興はまだまだですね。さて、大経大で開催された日本労務学会の関西部例会に行ってきました。20名弱の参加者だったと思います。ほとんどが大学に所属する研究者。そして場違いな私。第一報告 中井正郎氏(関西経済連合会)「バブル経済崩壊以降の企業法制の制定と企業改革」/コメンテーター 人事労務倶楽部 宮内雅也氏(社会保険労務士)第2報告三輪卓己氏(京都産業大学)「知識労働者のキャリア中期・後期の課題-危機の特徴とその背景-」/コメンテーター 甲南大学 櫻田涼子氏特に三輪先生の報告が素晴らしかった。ヒアリングに基づく実証研究であり、50歳前後に訪れる中年のキャリア危機(≒キャリア・プラトー)を解明しようとの壮大な試み。あくまでも中間報告とのととで、この先が気になる。まさに年男の私がドンピシャ世代。周りを見渡しても、なんとなく理解できる。特に知識労働者が転職や独立する傾向がうかがえるようだ。私自身、(能力不足で)転職経験はないものの、現場営業から始まって、現場経理、新規事業の立ち上げPJ、本社管理部門、労働組合と様々な経験を積ませて頂いた。故に残れているのかも知れない。そして、50歳を目前にして法務担当へ。この先はまだ見えないが、それそろ集大成としたい。
2017.03.11
-
(続)労基署業務を民間委託?
政府の規制改革推進会議は9日、人手不足が深刻化している労働基準監督業務について、社会保険労務士などの民間事業者に一部委託する検討を進めるタスクフォース(主査・八代尚宏昭和女子大特命教授)を設置した。委託対象業務の範囲や民間事業者の権限などを詰め、6月に安倍晋三首相に提出する答申に盛り込む。民間委託を検討するのは、政府が重要課題とする働き方改革の実効性を担保するには、職場環境の監視体制拡充が急務と判断したためだ。同会議議長の大田弘子政策研究大学院大教授は記者会見で「労働基準監督の強化はまさに働き方改革のインフラを強化していくことだ」と指摘した。(2017.3.9 時事通信) わし思うに、新卒採用のエリート監督官集団よりも百戦錬磨の社労士の方が使えるよ。だぶん。彼らの多くはほんまの泥臭い現場を経験していないから。
2017.03.09
-
労基署業務を民間委託?
政府の規制改革推進会議(議長・大田弘子政策研究大学院大教授)は、長時間労働などの監視を強めるため、企業に立ち入り検査する労働基準監督署の業務の一部の民間委託を検討する。各地の労基署は人手不足で監督の目が行き届いていないとの指摘がある。委託先は社会保険労務士を想定、主要国に比べて見劣りする監視体制を強化して働き方改革を後押しする。略(2017.3.7 日本経済新聞)監督官のマンパワー不足は周知の事実。頼みの綱は社労士の行政協力か。助かる駆け出し社労士は多いかも知れないが、であれば監督官として中途採用すべし。社労士はお役所の手先ではないぞよ。
2017.03.08
-
社労士会研修へ
本日は大阪府社労士会の第3回本会議へ。テーマは「労災事案の対処方法」、講師は弁護士の野口 大先生でした。 もともと企業側の立場で実務をされており、社労士向けの研修とあって、いかに労災認定を避けるかという視点。 例えば、労災認定を否定する方向のファクターを集める。労働密度が薄い、在社時間は長いが実労働時間は短い、そんなに業務が存在しない。等 顛末書を書かせて証拠化、死傷病という前提で粛々と処理・・・ん?いろんな意味で勉強になったと思う。 南海電車に揺られながら
2017.03.08
-

成年後見人養成講座
連続5週(土曜日)に渡る講義もようやく終了です。労組在籍中は土曜日を空けることは至難の業、というより100%無理でした。その意味ではこれまで出来なかった事にもチャレンジできそう。機会があれば、成年後見人としての活動も視野に入れたいと考えている。
2017.03.04
全8件 (8件中 1-8件目)
1