2018年09月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

愛車との別れ
長い間、お世話になりました。故障もなく、無事故で過ごせました。ありがとう!
2018.09.29
-

平成30年版 労働経済の分析
本日、厚労省より「平成30年版 労働経済の分析」が公表されました。しかし、ちょっとやそっとでは読めないな。こりゃ。本腰を入れて読み込まないと・・
2018.09.28
-

社労士マンのうた
大阪府社会保険労務士会 制度創設50周年記念チャンネル
2018.09.27
-

裁量労働制で労災(三菱電機)
三菱電機の裁量労働制で働く社員が相次いで労災認定を受けたほか、同社が制度そのものを撤廃したことは、裁量制の対象となる業務の拡大を検討する政府の動きに影響を与えそうだ。「数年で5人の社員が労災認定を受けるのは異常事態」。三菱電機の労働実態に対し、他の電機メーカーからは驚きの声が漏れた。技術者が多い三菱電機は、平成16年からシステムエンジニアや研究職など専門業務や、立案を含む企画業務に幅広く裁量制を適用してきた。厚生労働省の29年調査によると、裁量制で専門業務型を採用している企業の割合は2.5%、企画業務型は1%しかない。(中略)会社への出入りの記録を把握していなかった三菱電機は28年秋頃から、裁量制でも記録を管理することに変更。今春からは、月の残業時間が40時間までは一定額の残業代を支払い、40時間超の場合は超過時間に応じて残業代を上乗せする制度に切り替えた。一方、裁量制で働く人の労働実態を調べる厚労省の専門家検討会が今月20日から始まった。政府は、6月に成立した働き方改革関連法案に裁量制の対象拡大を盛り込む方針だったが、労働時間調査に不適切なデータが見つかり、裁量制の対象拡大を撤回した経緯がある。政府は経済界からの要望もあり、裁量制の対象拡大を目指す方針を変えていない。厚労省検討会の議論を踏まえ、関連法案の国会への提出を目指している。(2018.9.27 産経新聞)欧米ならいざ知らず、日本で労働時間を自らコントロールできる労働者など殆どいないのではないか。本来、自由に出退勤できるはずの管理監督者・・・重役出勤している人など皆無、少なくとも私の周りにはいない。これと同じこと。そういえば、「欧米かっ?」これも最近聞かなくなったな。
2018.09.27
-

ハラスメント防止対策(労働政策審議会)
厚生労働省の労働政策審議会分科会は25日、「パワハラ」や「セクハラ」など職場でのハラスメント(嫌がらせ)を防止するための議論を始めた。パワハラについては規制する法律がなく、労働者側から新法制定を求める声がある一方、何がパワハラに当たるか、「業務上の指導」との線引きも難しく、経済界は厳しい規制に反対している。パワハラをめぐっては、都道府県労働局に対する職場での「いじめ・嫌がらせ」相談が平成28年度に7万件を超え最多を更新。精神障害の労災認定も同年度74件に上っている。この日の分科会では、労働者側の委員が「日本の整備は遅れている。ハラスメントを規制する大きなチャンス」と主張。経営者側の委員は「ハラスメントの定義が不明確だ」と規制に抵抗した。セクハラについては、男女雇用機会均等法で防止対策を講じることが企業の義務とされているが、セクハラ行為そのものを禁止する内容ではない。このため、労政審では防止対策の実効性を向上することを主な論点に挙げている。(2018.9.25 産経新聞)パワハラの概念、法的措置を含めた防止対策などを軸として、本年中の結論取りまとめる予定だとか。法制化を視野に、有識者の先生方には大いに議論して欲しいと思う。
2018.09.25
-

雇用慣行賠償責任保険
セクハラやパワハラなどで企業が従業員に損害賠償を請求された場合に備える「ハラスメント保険」の販売が急増している。セクハラを告発する「#Me Too(私も)運動」の広がりなどを背景に、企業は職場のトラブルを経営リスクとして捉えている。ハラスメント保険は、正式には「雇用慣行賠償責任保険」などと呼ばれる。パワハラやセクハラ行為に対する管理責任や不当解雇をめぐり、企業や役員、管理職が従業員から訴えられた訴訟が対象だ。損害賠償金や慰謝料、訴訟費用などを補償する。保険会社が企業に保険商品を提供し、保険料は企業が負担する。例えば、上司からの度重なる暴言で退職したとして従業員に訴えられ慰謝料を支払った運送業者の事例では、約200万円の保険金が支払われた。男性店長から長期間、体を触られるなどのセクハラを受けたとして女性従業員から訴えられ、慰謝料を支払った飲食店の事例では、約90万円の保険金が支払われた。(2018.9.25 読売新聞)世も末か。
2018.09.25
-

春秋講義へ
京都大学春秋講義(公開講座)へ。「生物多様性を考える」というテーマは私の守備範囲外。少しは知見が広がったような気になっている。世の中にはいろいろな研究をされている先生がおられるのですねー。「カフェテリア ルネ」でランチを済ませ、昔よくお世話になった学生相談所(通称:ガクソウ)に寄ってみた。そうか、今はもう存在しないのですね。あれだけ学生でごった返してしたのに・・・。京大の研究施設になっていました。なにも相談に通ったわけではなく、日雇いバイトを紹介してもらっていました。会場設営、電気工事、警備、イベントスタッフ、エキストラ、夜間のパン工場、お弁当詰め作業、郵便配達、家電製品の配達など。懐かしい。夜は百万遍で飲み会予定だったので、糺の森~下鴨神社をぶらり。いい時間でした。
2018.09.22
-

悪質クレーム分析結果(UAゼンセン)
古巣でもあるUAゼンセンが実施した「悪質クレーム対策(迷惑行為)アンケート調査分析結果 ~サービスする側、受ける側が共に尊重される社会をめざして~」の分析結果が公表されている。これほど大規模な調査は例がなく、反響が大きい。詳しくはUAゼンセンのホームページにて。悪質クレームの実態が明らかとなり、来店客からの迷惑行為に遭遇した経験があると回答したのは全体の約74%。暴言(2万4107件)、何回も同じ内容を繰り返すクレーム(1万4268件)、権威的(説教)態度(1万3317件)、威嚇・脅迫(1万2920件)が上位を占めている。法務関係の業務を担当している関係で、毎日のように顧客とのトラブル案件が持ち込まれる。その多くが初期対応の甘さに起因しているように感じるが、中には無茶苦茶な要求もある。企業も毅然とした対応をすべき。しかしながら、この線引きが実は難しい。
2018.09.22
-

企業に聞く「働き方改革法案」実態調査
エン・ジャパンが実施した 企業に聞く「働き方改革法案」実態調査が公表されている。企業の経営者・人事担当者の「働き方改革法案」の認知度は9割超。そして5割弱が経営に支障が出ると回答している。特に、時間外労働の上限規制、年次有給休暇取得の義務化、同一労働同一賃金の義務化あたりに頭を悩ませているようだ。今回は企業サイドではなく、労働者寄りの法改正だから仕方ないね。
2018.09.21
-

日本FC協会セミナー
新大阪丸ビルにて「フランチャイズ契約におけるリスクマネジメントセミナー」。リスクマネジメントに関する考え方や方法を理解することにより、損失の回避及び損失拡大の防止を行い、不確定要素の軽減及び排除を目指すという内容。フランチャイズ契約における具体的なリスク分析手法について、「情報提供義務」「経営指導・優越的地位の濫用」「店舗事故・過労死」の具体的事例。平時でのリスク予防、問題発生時のリスク管理、訴訟段階でのリスク管理。講師ははフランチャイズ法務に精通した神田孝弁護士。1.リスクマネジメントとは リスクとリスクマネジメント リスクの予測 リスク分析とリスク評価 組織的な体制の構築2.リスク分析手法 契約締結段階でのリスクマネジメント(本部の情報提供義務) 加盟店指導段階でのリスクマネジメント(経営指導・優越的地位の濫用) 第三者との関係でのリスクマネジメント(店舗事故・過労死)
2018.09.19
-

副業解禁、進まず
政府が推進する会社員の副業や兼業について、4分の3以上の企業で認める予定がないことが、厚生労働省所管の独立行政法人、労働政策研究・研修機構の調査で明らかになった。認めない企業の82.7%が「過重労働で本業に支障を来す」と答えた。企業の抵抗感が依然として根強い様子がうかがわれる。調査では75.8%の企業が副業・兼業の許可について「予定なし」と回答。「許可している」は11.2%、「許可を検討している」が8.4%だった。許可しない理由では過重労働のほか、「労働時間の管理・把握が困難」が45.3%と、複数の職場を掛け持ちする中での実務上の問題を挙げた。労働者に対する調査では、副業・兼業を「新しく始めたい」との答えが23.2%、「機会・時間を増やしたい」が13.8%。一方、「するつもりはない」は56.1%だった。副業をしたい理由では「収入を増やしたい」が85.1%でトップ。逆にしたくない理由は「過重労働で本業に支障を来す」が61.6%、「家族や友人と過ごす時間を重視する」が56.5%で上位を占めた。調査は2~3月に実施し、全国の従業員100人以上の企業2260社、労働者1万2355人から回答を得た。政府は1月にガイドラインやモデルとなる就業規則を策定し、原則として副業や兼業を認めるよう企業に求めている。(218.9.13 時事通信)政府の後押しがあっても一向に進む気配がない。労働時間管理は?割増賃金の負担は?労働時短に逆行するのでは?様々な課題がある。憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定する。就業規則で縛ることを禁止するくらいの思い切った施策を打たないと難しいでしょうね。私も週末開業を目論んでいますが・・。はて
2018.09.18
-

丸刈りパワハラ裁判(福岡地裁)
丸刈りにされるなどのパワハラを受けたなどとして、福岡県宗像市の運送会社「大島産業」元社員、高山幹夫さん(40)が、慰謝料や未払いの残業代などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岡田健裁判長)は14日、パワハラなどを認め、会社側に計約1500万円の支払いを命じた。「パワハラはいけないこと。なくしてほしい」。原告の高山さんは判決後の記者会見で訴えた。判決は、高山さんが運送先から戻る途中で温泉に入ったことを理由に丸刈りにされたり、会社の寮から逃げ出した後に所持金が尽きて戻った際、土下座させられたりしたことを認めた。高山さんは当時の状況について「体育会系の部活みたいな感じだった。楽しんでいたので、ブログに載せたのだと思う」と振り返った。その上で、「やられた側は悔しかった。会社には同じようなことをしないでほしい」と訴えた。原告代理人の光永享央(たかひろ)弁護士は「パワハラは、被害者側が客観的な証拠を出さないとなかなか裁判で勝てない。ブログに画像が残っていた今回はある意味、恵まれていた」と話した。(2018.9.14 朝日新聞)私も時折パワハラ相談を受けるが、必ず証拠を残すように口酸っぱく言い続けている。が、殆どの場合、メモ、記録を残していない。ましてやIC録音など。「言った言わない」「指導の一環」例外なく、このような不毛な議論となる。いかに記録が大事か。会社側は控訴を検討しているようだが、証拠が認定される限り、結果は大きくは変らないと思う。
2018.09.15
-

ドラマで学ぶ!!(フリーランスへの業務委託契約編)
労働新聞社さん発信の動画です。よく出来た内容だと思います。
2018.09.15
-

暴言で解雇無効(大阪地裁)
パナソニックの子会社パナソニックアドバンストテクノロジー(大阪府門真市)を解雇された元社員の男性(53)が、解雇の無効と損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁(大森直哉裁判長)であった。大森裁判長は「解雇は合理的理由を欠き無効」と述べ、従業員としての地位を認め、未払い分を含め毎月基本給分の賃金を支払うよう同社に命じた。一方、組合加入を理由とした解雇で不当労働行為に当たるとした主張は認めず、慰謝料などの請求は退けた。判決によると、男性は2007年3月、組合活動に関して当時の社長から「しばき倒すぞ」「人間力ゼロ」などの暴言を受けた。男性は精神的不調を訴えて通院と長期休職を繰り返し、13年12月に解雇された。(時事通信 2018.9.12)解雇無効っても元の職場には戻りにくいのが現状。本当に復職できる方は少ないのではないかと思う。それにしても「しばき倒すぞ」はリアル感が満載。おそらく事実なのでしょう。別件:今日は久しぶりの東京出張。某学会の法務問題研究部会に出席しました。
2018.09.13
-

第1回公認心理師試験へ
雨の中、公認心理師試験へ。会場は近畿大学東大阪キャンパスでした。久し振りの近大通りはお店も相当入れ替わっていて、というか、殆どラーメン激戦区と化していました。「ぽろとこたん」は辛うじて残っていたけど、かの「マンサクラーメン」も姿を消した模様。元気母ちゃんはどうしているのだろう?と。ふと寂しくなる。「キッチンカロリー」を目にした時は安堵の思いでした。西門を潜れば、キャンパスも私の知らない建物ばかりで、近大の勢いと時代の流れを感じました。さて、日本初心理系国家資格の第1回目の試験。60%が合格ラインのところ、解答速報による自己採点では50%強でした。1問1点なら完全にアウトです。事例問題に厚く配点されていたら・・なんて甘い考えです。やはり心理系ベースではない受験者には厳しい結果でした。私のような産業・組織あるいは教育現場系の実務者はしっかりと準備しないといけませんね。来年、再チャレンジしたいと思います。
2018.09.09
-

公認心理師の実質化と産業・組織心理学
産業・組織心理学会の大会シンポジウムへ。名古屋大学は野依記念学術交流館にて。話題はもっぱら公認心理師について。パネリストの顔ぶれからも気合の入れようが窺える。会場より、某大学の名誉教授(重鎮)が長々と同じ質問を繰り返されていた。医師と対等ではない・・と。「指示」に関して。そんなこと会場の参加者は百も承知のこと。まさにKYそのものでした。そういえば、最近「KY」ってあまり聞かなくなりましたね。厚労省 公認心理師制度推進制度推進室長補佐 溝口晃壮氏 「公認心理師資格と産業・組織心理学への期待」日本心理研修センター理事長 村瀬嘉代子氏「公認心理師養成と産業・組織心理学への期待」産業・組織心理学会常任理事 名大 金井篤子教授「公認心理師の実質化と産業・組織心理学の役割」別件:名駅シネマスコーレにて話題作の「カメラを止めるな!」を観たけど、吐きそうに気分が悪くなった。最悪
2018.09.01
-

どうなるの?36協定
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働に ついて留意すべき事項等に関する指針案(イメージ) どこまで進んでいるのか?働き方改革。厚生労働省は、改正労基法第36条第1項で定める労働時間の延長および休日労働について留意すべき事項に関する指針案(イメージ)が示されている。なんじゃ、イメージって。労使に労働時間延長や休日労働を「必要最小限」に留めるよう求めている(当然やわな)。使用者に対し、協定上の時間数を超えて労働させることができる時間内でも、労契法第5条に基づく安全配慮義務を負う可能性に言及。
2018.09.01
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-14 18:01:08)
-
-
-
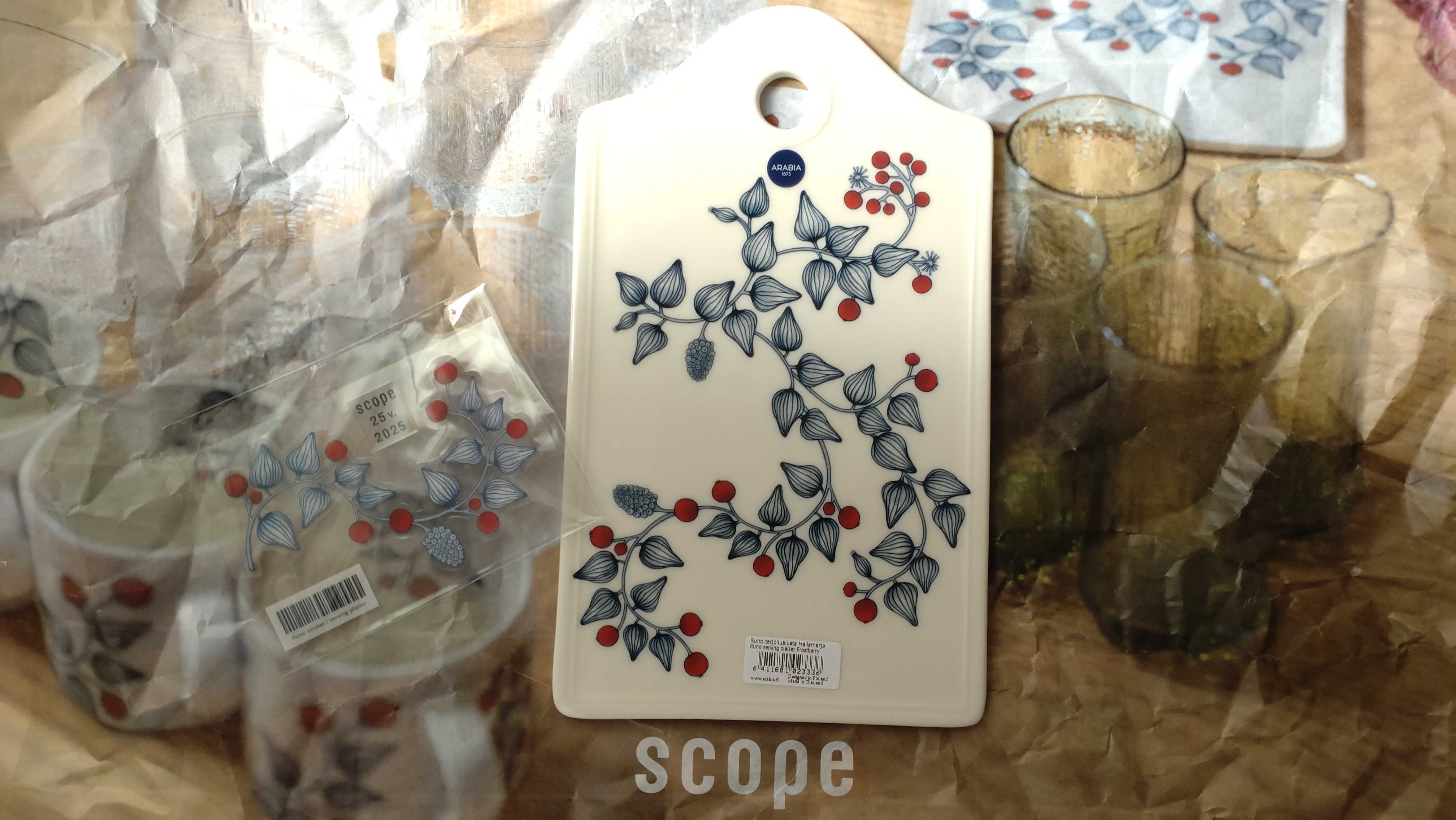
- 楽天市場
- 届きました!scopeさんからフロスト…
- (2025-11-14 21:01:20)
-








