カテゴリ: 学校・教育
それでは、道徳の授業づくり 3つ目の問題点
授業の終わり方がわからない
」というもの。
これも多くの実践事例では、最後に 「教師の説話 」というものを持ってくることが多いようです。しかしこの説話は、ともすると先生の 説教 になりがちです。
「 先生にもこのお話と同じような経験があってね・・・ 」と話しだし、最後には「 だからみんなもこれからこのことに気を付けて生活しようね 」というような 生徒指導(生活指導) で終わってしまうのです。
これはまさに 先生の価値観を押し付け ているわけです。よく「 道徳の授業はオープンエンドで・・・ 」という方がいらっしゃいます。その方法は確かによくわかります。
でもここでもこの 言葉の意味 をよく理解しておく必要があるのです。
道徳における オープンエンド とは、 特定の道徳的価値観 に集約せず、子どもたちのもっと考えたいという意欲や探求心を継続させるようにもっていくことをいいます。
ともすると「 子どもに考えを出させるだけ出して何となく終わる 」ことをオープンエンドと思っていらっしゃる方もいるでしょう。 それは間違いです。
子どもたちは授業が終わっても、その道徳的価値を自分の中で 内省 させながら実生活で実践していきます。これが 道徳の授業から道徳教育 につながるということです。
道徳の授業では 心に種を植 え、授業後の実生活で自分の生き方を考えながら生活を実践していくとき、先生や大人はそれをしっかり導いてあげる、つまり 種から芽が出たら スクスク育つようにしてあげるということなのです。
こう考えると、授業の終わり方は 教師の説話だけ ではありません。音楽を聞いたり、写真や絵を見たりしてじっくりと考えることもできるし、友達ともう一度話したり、あるいはみんな しん として自分ひとりで じっくり考える という時間を設けるというのもいいでしょう。場合によっては、今日の道徳的価値を もう一度振り返ってみる ということもあるでしょう。
どんな方法をとるにしても、オープンエンドの対極にある クローズドエンド 、すなわち「はい」か「いいえ」で結論付ける終わり方ではないということです。
お分かりいただけたでしょうか・・・。
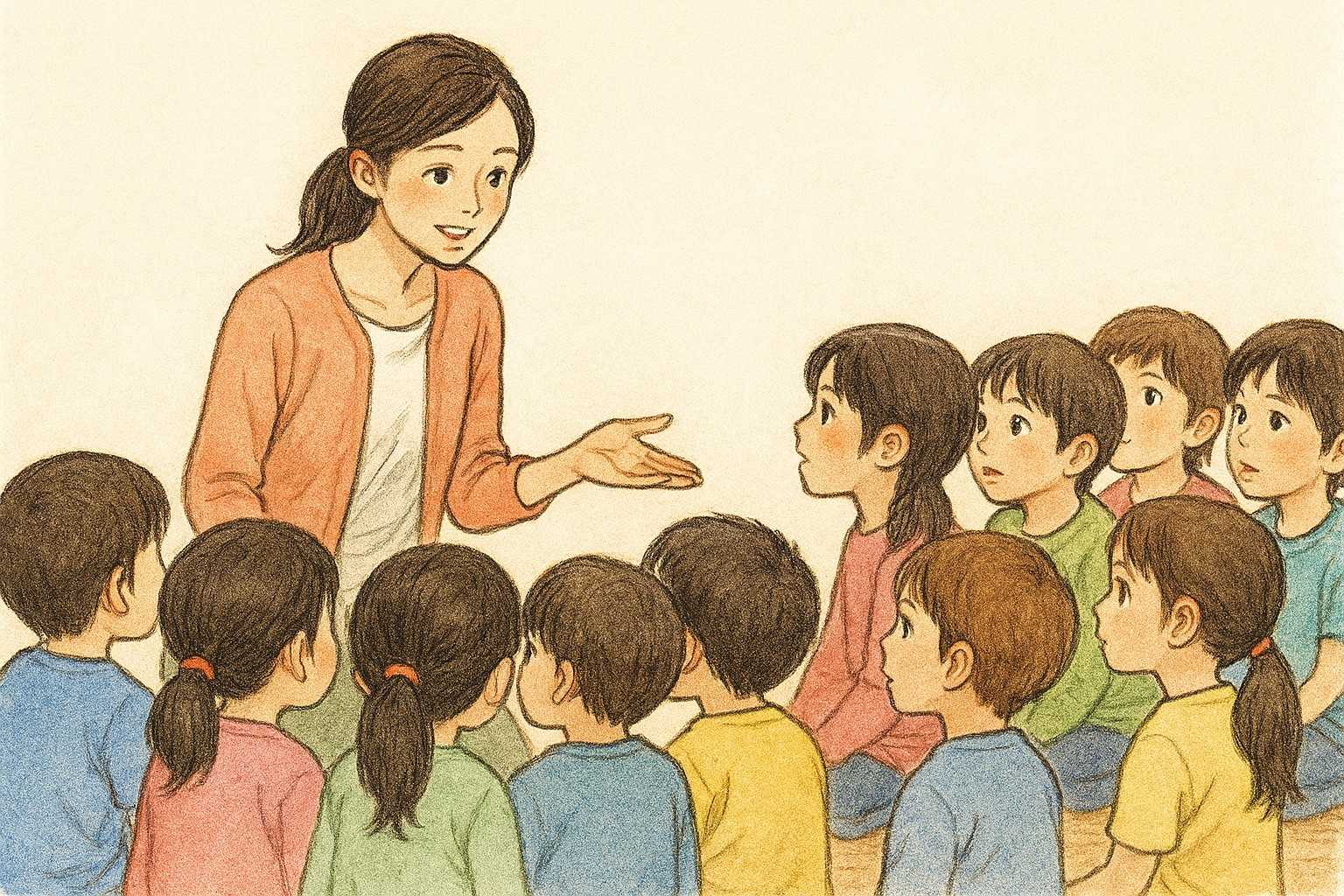
これも多くの実践事例では、最後に 「教師の説話 」というものを持ってくることが多いようです。しかしこの説話は、ともすると先生の 説教 になりがちです。
「 先生にもこのお話と同じような経験があってね・・・ 」と話しだし、最後には「 だからみんなもこれからこのことに気を付けて生活しようね 」というような 生徒指導(生活指導) で終わってしまうのです。
これはまさに 先生の価値観を押し付け ているわけです。よく「 道徳の授業はオープンエンドで・・・ 」という方がいらっしゃいます。その方法は確かによくわかります。
でもここでもこの 言葉の意味 をよく理解しておく必要があるのです。
道徳における オープンエンド とは、 特定の道徳的価値観 に集約せず、子どもたちのもっと考えたいという意欲や探求心を継続させるようにもっていくことをいいます。
ともすると「 子どもに考えを出させるだけ出して何となく終わる 」ことをオープンエンドと思っていらっしゃる方もいるでしょう。 それは間違いです。
子どもたちは授業が終わっても、その道徳的価値を自分の中で 内省 させながら実生活で実践していきます。これが 道徳の授業から道徳教育 につながるということです。
道徳の授業では 心に種を植 え、授業後の実生活で自分の生き方を考えながら生活を実践していくとき、先生や大人はそれをしっかり導いてあげる、つまり 種から芽が出たら スクスク育つようにしてあげるということなのです。
こう考えると、授業の終わり方は 教師の説話だけ ではありません。音楽を聞いたり、写真や絵を見たりしてじっくりと考えることもできるし、友達ともう一度話したり、あるいはみんな しん として自分ひとりで じっくり考える という時間を設けるというのもいいでしょう。場合によっては、今日の道徳的価値を もう一度振り返ってみる ということもあるでしょう。
どんな方法をとるにしても、オープンエンドの対極にある クローズドエンド 、すなわち「はい」か「いいえ」で結論付ける終わり方ではないということです。
お分かりいただけたでしょうか・・・。
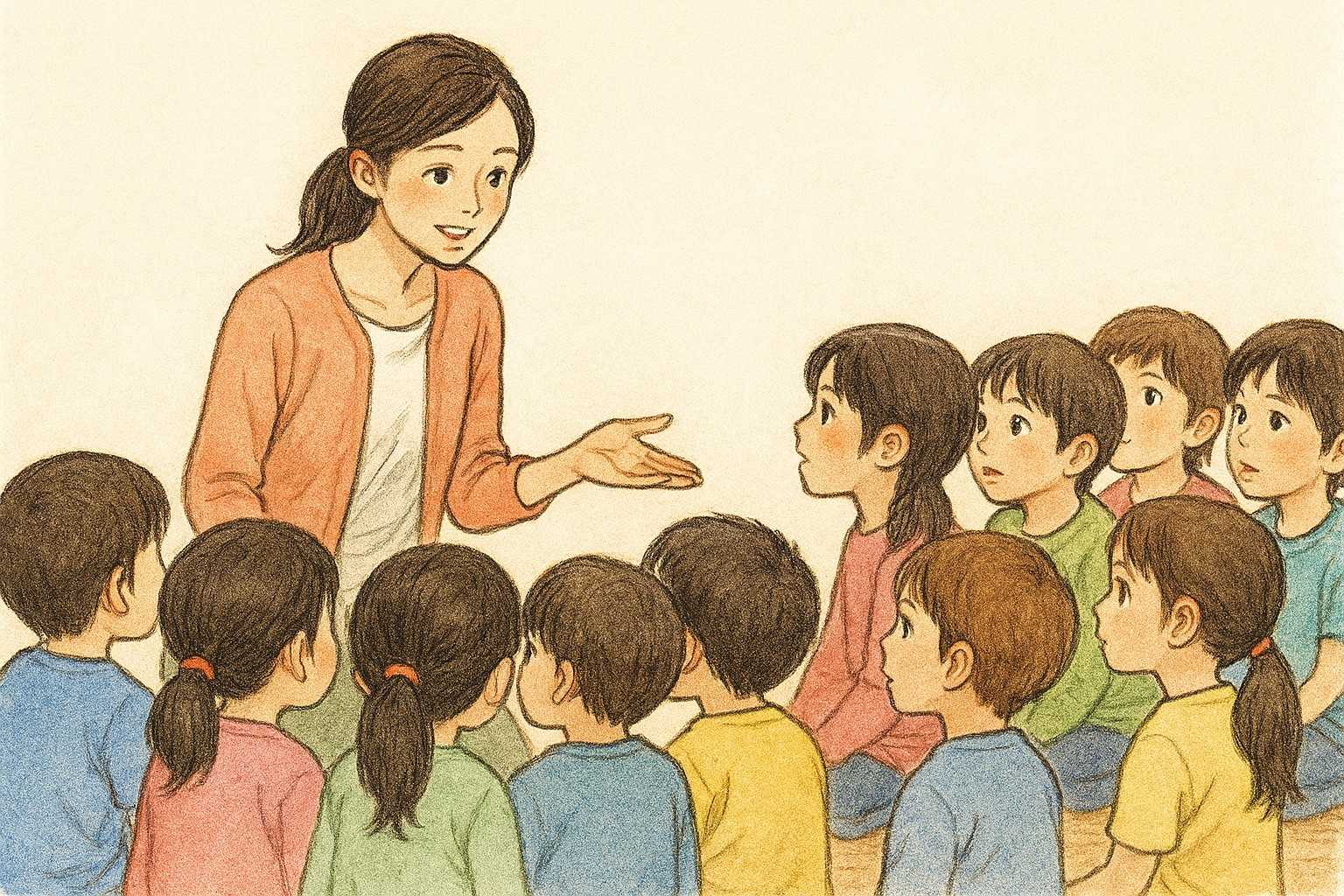
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025年11月13日 05時00分12秒
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









