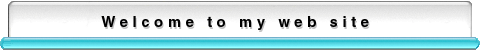子育て奮闘記 1.娘が生まれた頃の事
娘が生まれたのは1990年の梅の咲き始めた頃の東京でした。当時、アメリカで知り合ったアメリカ人の主人と私は日本に越して来て、世田谷で父の所有していたコーヒー店の経営に忙しい毎日を送っていました。休暇もろくに取れないほどで、二人目の妊娠は、あっという間の10ヶ月でした。 通っていた病院の超音波の機械は先生も嘆くほどの古い機種で映像が悪く、何度か超音波を使ってはいただきましたが、妊娠中に娘の眼球が欠損していることは、全く解りませんでした。でもその反面、私も何の不安も無く、予定日を楽しみに過ごしていました。
二人目の出産は話に聞いたとおりとてもスムーズで、病院に到着してからわずか45分で娘が誕生しました。分娩室で聞いた ”あれ?眼はどこだ?”と言う先生の言葉を、今でもはっきり覚えていますが、無事に出産を終えた私は、安堵感につつまれ、その言葉にはたいして気にも止めませんでした。しかし、先生や看護婦さんたちはすぐに娘の眼の異常に気づかれたようです。
風邪をひいて微熱があった私は、体を休めるようにと産後3日間ほど、母乳を与えることも、生まれたばかりの娘を抱くことも止められました。上の娘をアメリカで出産した時は、体をきれいに拭いてもらったばかりの娘をベッドの上で思いっきり抱かせてもらったので、自分の娘を抱けない3日間は非常に長い時間に思えました。看護婦さんにお願いして、一度だけ抱かせてもらいましたが、自分の子供を自由に抱くことができない病院の規則に、憤りとも言える疑問を感じました。新生児室の窓越しに見る娘はピンク色で、眼をしっかりつぶったまま、すやすやと寝ています。しかし、気になることは、2日目になっても眼を開けないことです。”あけたくなったら眼をあけるよ。心配しない。”と楽天的な主人は言ってくれますが、何度足を運んでも、窓越しに見る娘は眼をかたくつぶったままです。”どうしたのかな?眼になにか問題でもあるのかな?”と時の経過と共に不安は広がります。その晩私は、夢でうなされました。娘が眼の見えない、全盲の夢でした。その時、母親の直感とでも言いましょうか、、”この子には、眼が無いんだ!”と言う思いがひらめき、消せども、消せども、頭の中をかけめぐり始めました。
娘と同じ病院にいる私には、先生からは何も話がありませんでしたが、3日目に主人の仕事場に病院から、”お子さんのことで大切な話があるから、すぐに来て下さい。”と連絡が入りました。 後で、伺ったことですが、母親に精神的不安を与えない為の病院側の、最大のご配慮だったようです。店で働く主人に病院から電話をいれると、主人は非常に慌てて病院からの話をしてくれました。主人にしてみても、入院中の私に知らせずに仕事場の主人に連絡が入ったので、私の身にも何か起こったのだと思ったそうです。私はすぐにナースステーションに向かいました。病院の予定表の娘の名前の欄に、”眼科検査、耳鼻科検査”と言った手書きの文字が並んでいました。 ”検査って、、私たちは何も聞いていない、、” 上の子供の出産の時は、検査一つをするにも本人・家族の同意を得て進めるアメリカの医療に慣れていたので、私には寝耳に水とはこのことでした。私たちの知らない間に、娘のことで大変な事実が判明したのは、もう疑う余地もありません。私は婦長さんをつかまえて、”娘に何か問題があったのですか? 教えてください。”とお願いしましたが、婦長さんは私の顔もろくに見ずに、”先生からお話があります。”の一点ばりで、何の情報もいただけません。先生は午後の手術に入った直後で、私は駆けつけてくれた主人と、父と3人で、夕方までの時間を不安な気持ちで相部屋のベッドの上で過ごしました。
先生の説明の準備が出来て、看護婦さんが呼びに来てくださいましたが、”お母さんは、来ないでください。”と言われ、さらにショック。その言葉に、”母親に同席するなとは、一体なんだと思っているんだ。”と怒る主人と、どうしても、自分の耳で確かめずにはいられない私は、看護婦さんが止めるのを振り切って、先生のいらっしゃる部屋へと向かいました。 部屋には先生が2-3人いらしたと思います。日本語の全く出来ない主人と、こういう話は全く苦手とする父を後ろに控え、私は覚悟を決めて、先生と向かい会いました。その時の私に何かの覚悟ができていたのかどうか、自分でも解りませんが、とにかく、私には自分の娘のことでなにか隠されている不安な状態をこれ以上続けることが耐えられなかったのは確かです。
先生がおっしゃったことは、私の直感どうりのことでした。”大変珍しいことですが、娘さんは無眼球と言って、両眼とも欠損しています。”その様な内容のお言葉でした。私は、泣くでもなく、わめくでもなく、頭の中は不思議と冷静で、”では、どうやって育てていったら良いのでしょうか?”とすかさず、問い掛けていました。まるで、ドラマの役を演じているような、そんな光景のような気がしましたが、しかし、これは紛れも無い事実であり、私たちの娘は、眼球を持たずに、全盲で生きることを選んで、この世に生まれてきたのです。
その後の先生との会話は、かなり冷静なものだったと記憶しています。先生方には今後お世話になる、国立小児病院を紹介していただきました。無眼球に関する資料や情報をどうやって集めるのか、私はすでにその様なことを考えていました。先生にはとても気丈なお母さんとの印象を与えたようで、病院への紹介状には、”気丈なお母さんですから、何でも話して上げてください。”とコメントが加えられていたと、後から小児病院の先生にうかがいました。
それから、退院までの3-4日は正直な話、決して楽しいものではありませんでした。体調もあまり優れませんでした。アメリカ人の父親を持つ娘は病院の患者さん達の間でも、”色がピンクね?眼は何色かしらね?”と注目されていたのも、心が痛みました。(ひょっとして、そう感じていたのは、無眼球のことで過敏になりすぎていた、私だけかもしれませんが、、。) 同じ時期に出産されたお母さんたちに混ざって、授乳室で授乳をしていても、”うちの娘は眼球が無いという障害をもって生まれたのだ、、。”と言うことも出来ずに、逆にその事に誰も気づいてくれないようにと思いながら、冷静さを保ち、心臓の鼓動を抑えるのに一生懸命でした。娘の障害の事を隠したい自分がいました。その時の私には、娘の障害を声に出して言う心の準備はできておらず、早く退院して家に帰りたい一心だったのです。
続く
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 子供服ってキリがない!
- BONJOUR SAGAN10%オフクーポン
- (2024-12-01 09:00:12)
-
-
-

- 働きながらの子育て色々
- 感想・ルンルン
- (2024-11-10 22:43:57)
-
-
-

- 0歳児のママ集まれ~
- 11/25限定 抽選で100%Pバック😍ベビー…
- (2024-11-25 19:22:51)
-
© Rakuten Group, Inc.