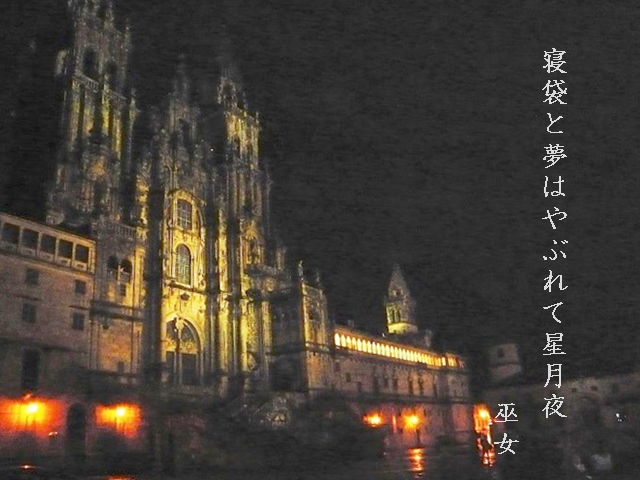(その2)
「しかし、今日も暑くなりそうだ…」
まだ朝の8時前だというのに、もうゆらゆらと陽炎が立ち上る隣の民家の屋根を見ながら那由太は呟いた。
そして、出かける支度を整えると窓を閉めてカギを掛けると、机の上に飾られた写真をちらりと見た。
それは彼がせつなと二人で撮った一番お気に入りの写真である。昨年の夏に二人で行った裏磐梯、そこで撮った写真である。那由太は少しカメラ目線から外れて空の方を見ているが、せつなは黒目がちの目を真っ直ぐにカメラに向けている。
二人の後ろには鮮やかなブルーの水面が見える。「毘沙門沼」だったか…、五色沼の一つで、とても色の鮮やかな沼の脇で撮った一枚である。
せつなの部屋にも、これと同じ写真が飾られていることも那由太は知っていた。 …二人の絆を感じさせてくれる写真。
那由太にとってはとても大切なものであり、せつなに逢えない日が続くと、ついつい見入ってしまう写真なのであった。
今日も調べ物とアルバイトである。就職活動は一時休止であった。
結果的に那由太の道は二社に絞られていた。というか、それだけしか那由太には選択肢が残らなかったのであった。
一社は地元では比較的大きな企業で、服飾関係の会社である。そして、もう一社は先日説明会に出かけていった食品関係の中小企業。那由太にとっては「安全パイ」の会社である。
「就職は地元でするんだ」と言い張っておきながら、就職活動も後手後手になってしまった挙げ句に、最終選考まで残った会社はたった二社であった。
友人達は、いっそ「就職浪人したら?」などと安易なアドバイスをよこしたりする。しかし、那由太は、「どこでも自分が頑張りさえすればいいのだから…」と、本心とも強がりとも言えるような台詞を口にしつつ、あくまで今年中に決めるつもりを強くしていた。
那由太にとっての最優先事項。それは、とにかく今年中に就職を決めること。そして、それは次第に那由太の中で日に日に強くなっていたのである。
何故かというと、それが決まりさえすれば、「次の一歩」が踏み出せそうだったからなのだ。それは彼自身の将来でもあったが、同時に「せつなとの未来」も意味する「一歩」であった。
那由太は机の上の写真立ての前に、せつなから届いた葉書を綺麗に並べて部屋を後にした。ただ、外国人の写真が印刷された、あの一枚だけはカバンに入れて持ち出していた。
今、那由太の頭を占めていたのは、せつなの顔と同じぐらい、その外国人の顔であった。多分100年は経っているであろう、その写真に写った白髪の男性は、鋭い眼差しで斜め前を見つめている。
その視線の方向が、あの写真…せつなと一緒の写真の中の自分と一緒と似ている…と、下らないことに気がつきはしたが、それはどうにもせつなのメッセージを解読するヒントにはなりそうになかった。
「一体誰なんだろう?」
大学で出逢った友人たちに尋ねても、「音楽家か誰かかなあ」というぐらいで、誰も分からない。せつなの専門は美術史だから、芸術家か誰かであろうか、とも思った。
以前、この写真とは違うけれど、こんな写真がいくつか出ている本をせつなが図書館で読んでいたことがあった…。そんなことをうっすらと那由太は記憶していたのだ。しかし、それが何かまでは思い出すに至らなかった。
それで、昨日は図書館で西洋の芸術家を片っ端から調べたが、結局分からず仕舞いであったのだ。
そこで、今日も時間があれば、調べてみようというのが那由太の考えであった。
その日は、幾らか早くアルバイトが上がった。もう一度図書館へ戻って調べようかと思いもしたが、アルバイトの場所から大学は反対方向になってしまい、余りにロスが大きい。午前中に調べた科学者達の中にも、あの人物はいなかった。
「もう、今日はやめておこう。」と、那由太は決めて帰ることにしていた。
那由太はここの所、いつもコンビニの弁当だなと、反省し、今日は自分で料理でもしようかと、帰り道に、駅から少し回り道をして比較的大きなスーパーへと向かった。
夏の日差しはまだまだ強く、六時を回っていても、日差しが肌を焦がすような感じである。「ジリジリ」と音が聞こえてきそうな気さえする。
八月ももう終わりなのに、一段と暑さが増しているようなここ数日であった。
「今日はカレーでも作ってみようか」と、張り切って買い物をすませ、いつもと違う道を家へと向かって歩いていた時であった。向こう側から見覚えのある若い女性がこちらに歩いてくるのが見えた。その娘が、せつなと仲良しの研究室の友達だと分かり、すれ違いざまに那由太は「こんにちは」と声を掛けた。
彼女は顔を上げ、那由太に気づいた。すると、と妙に驚いたような顔でどぎまぎしながら「あ、どうも…」と言うと、足を速めて過ぎ去ってしまった。
那由太はせつなのことを尋ねようかと思ったが、何やら声を掛けられることを拒否するかのような彼女の態度に、タイミングを逸してしまい、去っていくその娘の後ろ姿を見ながら、道の中程に立ちつくしていた。
「あの娘の家って、この駅周りだったっけ? それにしても、急いでたのかな?」
那由太は、何度か会話も交わしたことのあるその娘の態度があまりにぶっきらぼうだったことに釈然とせず、そこからの数百メートルを、とぼとぼと下宿まで歩きながらあれこれと思いを巡らせていた。
アパートの前まで来ると、階段下に回る。
那由太は少し大きめのビニール袋を提げて郵便受けの前に立った。その時、那由太には何となく、予感がしていた。
せつなからの最後の葉書が、今届いている。そんな妙な確信があった。
そして、果たして郵便受けの中に、その葉書はあった。
「御子神那由太 様」
いつものせつなの字である。そして、その下にはとうとう那由太の恐れもし、期待もしていた言葉が記されていた。
「9月3日 一緒に夕陽を。」
その文字は、いつもよりも少しだけ大きく、力強く見えた。
那由太の予想していた通り、とうとう、具体的な日時を示すメッセージがせつなから送られてきたのだ。そして、その隅には…
「i 2 =j 2 =k 2 =ijk=」
と、何かしら数式のようなものが記されていた。
送られてきたそれは、再び既製品のポストカードであったのだが、裏返して写真を見ると、何とそこにはエッフェル塔らしき景色が映っていた。
その場所はフランス、パリであることは言うまでもなかった。消印は…やはり押されていなかった。
覚悟していたこととは言え、那由太は慌ててしまった。何故なら、今日は8月31日である。9月3日まではあと3日しかない。
しかも、まだせつなのメッセージの内容は、よく分からないままである。
「せつなが待っているはずの場所は、まさかフランスってことはないだろう…が、 場合によっては1日では行くことのできない場所になるかも知れない。」
那由太はもう食事を作ることも忘れ、机の前にせつなからの葉書を並べ、頭を抱えてしまった。もう、何度見たか分からないほど眺めた葉書ではあったが、改めてそれを表側にしたり、裏側にしたりして、何かを見つけ出せないだろうか、と彼は必死であった。
そして、もう一度送られてきた順番に丁寧に読み返してみた。
最初の5枚は国内のポストカードである。
1枚目には「旅をしています」と「-5」。写真は栃木県の戦場ヶ原の写真であり、消印も栃木県である。
2枚目は「まだまだ続きそうです。」と「-4」。写真は東尋坊で消印は、これは石川県であった。
そして、3枚目は四万十川に「-3」。そして「就活順調ですか?」消印は高知。 4枚目は鹿児島の消印で、枕崎の海岸が写ったもの。「旅を続けています」と、「-2」である。
しかし、それらを幾ら眺めていていも一向に答えらしいものはは浮かんでこないのだった。
5枚目は那由太とせつなの通う大学のもの。メッセージは「元気です。」と「0」である。「0」を「オー」と読むことも、それ以外の何かに読むことも考えてみたが、今更特に何も閃くことはなかった。そして、これには消印が記されていなかった。
きっとせつなはどこか、旅の途中で「答え」を見つけたのだ。そして、それがきっと待ち合わせの場所なのだ。せつなは、今そこにいて、その場所から自分に向けて最後の数枚を送っているのだろう。
だから、その場所が分からないように消印の無い葉書を…。
知らない間にもう時刻は9時になっていた。
もう1枚は誰のものか分からない古いポートレイト。そして「+α」。「覚えてる?」のメッセージ。
そして、最後の一枚はフランスの景色と数式なのであった。
「i」や「j」「k」は何かのイニシャルだろうかとも思った。しかし、そこについている指数の「2」の意味が分からない。なぜ、二乗するのだろうかと考えてもよく分からない。
最後の「イコール=」の先には何かが当てはまるのだろうか。しかし、それも全く見当がつかないのであった。
幾ら考えても何も浮かんでこない自分に苛立ちを感じる那由太であったが、自分に腹を立てても仕方がないことぐらいは心得ていた。
最もヒントらしいものと言えば、「+α」の古い外国人の写真である。そこに記されたせつなのメッセージ「覚えてる?」が、何を自分に思い出させようとしているのか…。
彼は食事をするのも忘れていた。買ってきたものは、そのままほとんど冷蔵庫に放り込んだままであった。空腹を感じ、食べ残しのパンを囓り、牛乳を飲んだだけで、横になってしまった。
そして、せつなとの思い出をあれこれと思い浮かべていると、切ないような虚しいような妙な感覚に陥って、そのまま知らない間に眠りに落ちていた。
その夜、那由太は夢を見た。那由太はせつなと二人で歩いていた。
何もない白い大地。せつなは那由太の少し前を歩いている。那由太はスーツ姿。せつなはいつものジーンズにパーカーで、トレードマークの赤いキャップを被っている。
那由太はせつなに追いつこうとするが、なかなか思うように前に進めない。スーツが体にまとわりつき、革靴はぬかるみを歩いているように足を取られる。
そして、せつなはこちらを振り向くこともせずに前へ前へと歩いて行ってしまう。「待ってくれよ」と声を出そうとしても、声も出せない。
せつなと自分の距離はどんどんと開いていく。焦れば焦るほど、那由太の足は余計に動かず、せつなの赤いキャップは次第に小さくなっていく。
地平線の向こうに赤い点消えかかる…。
せつながの姿が見えなくなると、もう全てが終わってしまうような気がして…那由太は夢中で叫び声をあげた。
…ベッドから飛び起きた那由太は、周囲を見まわした。
「夢か…。」と呟き、大きく息をついた。
外はもう白々としており、扇風機は虚しく首を振り続けていた。点けたままの電灯を見ながら、那由太は「何だったんだ…」と、溜息ともつかない深い吐息とともに小さく言葉を吐き出した。
「夢の中での叫び声は、せつなに届いたのだろうか…」
そんな朧気な不安のようなものが頭の隅に残り火のように虚しく燻っていた。
もう、時刻は5時過ぎであった。次第に頭がはっきりしてくると、那由太は早速身支度を整えた。彼に残された時間は僅かしかなかった。何とか早いうちに「答え」を見つけ出さなければならないのだった。
那由太の今日とるべき行動は決まっていた。写真の外国人を調べることもあったが、まずは昨日スーパーの帰り道ですれ違ったせつなの友達に会うことであった。
消印の無いせつなからの葉書が、誰かに直接届けられたものであるということは、想像に難くないものであったが、昨日のあの子が「配達人」であろうということは那由太にはピンと来ていた。
ただ、その子を尋ねることで問題を解決することは、せつなからしてみれば不本意であろう…そう考えはした。
しかし…昨夜の夢のせつなの後ろ姿。どことなく淋しそうな後ろ姿…。
那由太に今はあれこれ手段を考えている暇はなかったのである。
「せつなに逢いたい。」彼は今それだけの思いに突き動かされていた。
文学部の棟は、那由太の通う経済学部の棟とは隣り合わせである。那由太は、図書館と文学部棟のどちらもが見える中庭のベンチに座っていた。
「ユッコ」とせつなはその娘を呼んでいたのを那由太は覚えていたが、本名は知らなかった。研究室が同じということは明らかであったので、ひょっとしたらここに張り込んでいれば会えるかも知れないと考えたのであった。
ただ、今は夏休みで講義も行われていない。4年生にもなると、学校に来なくなる者も多い。しかし、昨日その娘を見たということは、地方出身者であれば少なくとも帰省はしていないはずだ。卒業論文のための調べ物などをしてこちらに残っている者はキャンパス内に姿を現すことが多い。特に、美学であるとか美術史であるとかの研究は、「図書館が一番なの。」…これはせつなのいつもの台詞であった。
那由太はそれに賭けた。ただ、だらだらと時間を過ごす訳にもいかなかったので、自分の卒業研究のための専門書を膝の上に置いて、ひたすら待ち続けた。
自分の本も、読むには読んでいたが、人影が見えるたびに顔を上げることになるし、本自体が内容も難しいものなので、2時間ほどで15頁ほどしか進まない。
図書館にある時計台はもう10時30分を指していた。
那由太のいるベンチは、一応木陰にはなっているものの、空には雲一つなく、真夏の日差しが容赦なく照りつけている。そんな所に坐っているのは、那由太一人であり、通り過ぎていく人は物珍しそうな眼差しを投げかけてくる。
那由太は校舎付近に何度か、その娘に良く似た姿を見つけ、「ハッ」と息を飲んだ。しかし、それはいずれも人違いであった。
次第に気温が上がっていき、緊張と暑さで那由太は用意していたペットボトルのお茶を飲み干してしまっていた。しかし、再びのどの渇きを抑えられなくなり、ベンチには荷物をそのままにして、殻のペットボトルを手に持つと、近くにある自動販売機まで出向いて行った。
「ポン、ポン」と、殻のペットボトルを左手の手のひらで叩き、そのままゴミ箱に殻押し込む。財布から硬貨を取り出して、新製品のスポーツドリンクを一本購入し、ボトルとおつりを取るためにしゃがんだ那由太は立ち上がりざま後を振り返った…その時である。
何という幸運であろうか、那由太の後に自販機を利用しようとして立っていたのは「ユッコ」その人であった。
思わず「あっ」と声を上げる那由太。そして、彼の目に入ってきたのは、全く昨日の夕方の再現フィルムを見ているような彼女の表情であった。
ただ、今回は「ユッコ」はその場を立ち去ることはできなかった。彼女は両手に重そうな大版の専門書を数冊抱えていたのである。
那由太の、「ちょっといいですか?」という言葉に俯いたままの彼女は何だか可哀想な気さえするほど縮こまっていた。ただ、那由太はそれに遠慮している場合ではなかった。
那由太はズバリ確信を突く質問を浴びせた。
「せつな…星崎せつなの葉書を届けてくれましたよね。」
やや、カマをかけた感じであったが、那由太の自信たっぷりの言葉に、否定はできないと思ったのであろう「ユッコ」声は小さいながらもはっきりとした返事を返してくれた。
「はい。せつなに頼まれたんです。…でも、ごめんなさい…それ以上の事は言えません。」
その声は小さいながらも非常に強い調子で、それ以上に那由太の追及の手は及びようもないことを感じさせるものであった。那由太は口元まで出かかっていた「今、せつなが何処にいるか知ってますか?」という野暮な質問を喉の奥に押し込んだ。
ペットボトルを握りしめる手に力がこもる。冷たい雫が指と指の間を伝っていくのが感じ取れる。
那由太は言葉を失い、窮してしまった。
先に口を開いたのは意外にも「ユッコ」であった。
「ごめんなさい。何も言えないんです。約束してるから…。でも、那由…あ、御子神さん…頑張って下さい。せつなは待ってます。絶対にせつなの所に行って下さい。せつなは御子神さんのことを本当に大切に思っています…。」
説得力のある重い言葉だった。
那由太はそれに対して、「うん。ありがとう。」というのが精一杯で、彼女に背をむけるとその場を後にし、とぼとぼとベンチまで歩いた。
濃い影がアスファルトの上で小さく那由太の足もとにまとわりついていた。
その日は昼からアルバイトであった。一刻を争う那由太はそれどころではなかったが、どうしても抜けられなくて、那由太は気乗りのしないまま、電車に揺られてアルバイト先のある駅に向かっていた。
車内の冷房は心地よかったが、那由太の心は澱んでいた。あの後、残された時間は図書館に行って例の外国人探しに費やしたが、徒労に終わっていた。
「ひょっとしたら」と、見当をつけた経済学者や外国文学作家の肖像にも、あの白髪の男性はいなかった。
その日は薄暗くなる頃に那由太は下宿に辿り着いた。郵便受けには、朝取り忘れた新聞が差し込んであるだけであった。
部屋に入ると、いつもはあまり見ないテレビのスイッチを入れる。ちょうど7時からのニュースが始まっている。…連日の異常な暑さのために、都市部の冷房がフル回転で、電力量の供給が間に合っていないことをアナウンサーが涼しげな顔で告げていた。
那由太の部屋には縁遠い話だった。きっとこの部屋の温度は軽く30度を超えているであろう、額を流れる汗が温度計替わりである。
Tシャツは汗でびっしょり濡れている。那由太は、あまりの暑さに冷蔵庫の中で眠っていたとっておきのビールを取り出して飲み始めた。
お酒が入ると、気分は幾らか上向きになってきた。
明日はアルバイトも休みだし、研究室に行く用事もない。一日かけて、絶対に謎をといてやる。昨日作り損ねたカレーを、今日は作ろう。好物のカレーを食べれば何か閃くかもしれない…そう思った那由太は、早速カレーの準備を始めた。が、汗も流したい気分になり、「よし、今日は水風呂だ」と、風呂場に行って水道の蛇口をひねった。勢いよく水がほとばしる。
最初は、日中水道管の中で温められていたお湯のようなものが吹き出したが、暫くするとほどよい冷たさになってきた。
那由太は水道を出しっぱなしにして、風呂場を出ると、再び台所に立って玉ねぎの皮をむき始めた。
洗った野菜を切り、玉ねぎとニンニクを炒めて一段落したところである。
鍋に水を入れてあとは煮込むだけ、という所であった。ふと、風呂場の方から音がするのに気づいた。
「しまった。」
那由太は浴槽に水を溜めていたのをすっかり忘れてしまっていたのだ。炒め物の音で風呂場から聞こえてくる水の音に気が付かなかったのだ。
慌てて風呂場に駆け込むと、もう水はとっくに浴槽を超えてザバザバと音を立てて水が溢れ出ていた。
「ま、お湯でなかったのが幸いか…」
蛇口を締めながら、随分と勿体ないことをした…と、少々悔やみもしたが、気を取り直した那由太は、溢れる水で濡れた足をタオルで拭うと、取りあえず、鍋の火を弱火にして汗を流すことにした。
体と頭を洗っても、溢れ出るほど…イヤ、実際に溢れ出ていた浴槽の水は、まだまだたっぷりある。
「ええい。」
と、那由太は一気に浴槽に体を沈めることにした。
勢いよく溢れ出す水。洗い場の椅子や石鹸置きが慌ただしく壁の方に流されていく。
ほどよく冷たい水に浸かると、アルコールも入って火照っていた体が一気に冷やされていく。
「フーッ。」息を飲むような快感である。那由太は子供の頃、よくわざと浴槽のお湯を溢れさせ、父に叱られていたことを思い出した。
「アルキメデスみたいに、何か閃かないかなあ…」
次第に落ち着いていく水面を眺めながら那由太はぼんやりと考えていた。
「で、アルキメデスは何を閃いたんだっけ?」
那由太に、そんな妙な疑問がとりついた。暫く思い出そうとしたが、はっきりと思い出すことができない。
「確か…王冠を沈めて溢れ出す水で王冠の真偽を突きとめたんだっけ。でも、な んで水が溢れたら分かったのかな…。」
那由太は理科音痴で、どうも物理とか化学の話になるとさっぱり苦手なのであった。同じく理科系が苦手なせつなと、よくお互いの無知比べをしたものである。
「でも、せつなは時々やたら詳しいことがあったよな…」
その時、那由太の中に再び何かが甦ろうとした…そんな感覚を自分自身の中に感じた。しかし、残念ながら今回もそれは「気」だけで終わってしまった。
それが何か分からないことにまた歯痒い思いをしたが、取りあえず那由太は先程の疑問を解決しようと考えた。そこから何か閃かないかと思ったのである。
「『ユリイカ』だったっけ。アルキメデスが、閃いた時に発した言葉は…『大発見。見ィーつーけた。』って感じの言葉だったよナ…。」
那由太は、妙なことは覚えているものだ…と、自分に感心しながら、冷えた体を拭きつつ、何かが自分の中でつながり始めている予感を嗅ぎ取っていた。
すっかり、体は冷えて爽快な気分で那由太は風呂からあがり、短パンにTシャツ姿になると、早速カレーの仕上げに入った。
そして、ふと本棚の大型国語辞典に目が止まると、先程の疑問を思い出した。
「アルキメデスって、本当に何を発見して、それで『ユリイカ』って叫んだんだっけな。」
辞典で「アルキメデス」を引けば、さっきの疑問が解決するのでは、と思い、那由太は早速「アルキメデス」という項目を調べてみる。
しかし、残念ながらそこには那由太の疑問を解決するような記事はなかった。「アルキメデスの原理」というのも、那由太が思っていたものとはちょっと違っていた。「古代ギリシアの数学者・物理学者・技術者…か。」
辞典の冒頭の言葉にもう一度目が行っていたその時である。那由太の目が、釘付けになった。
「数学者…そうか、そうだったのか。」
第3章『「夏」の終わり』
9月2日。那由太は大学の図書館の前で、開館の時を今や遅しと待っていた。
「一刻も早く、謎を解かなければ、約束の期日に間に合わないかも知れない。」 気が逸る那由太の頭の中には、次々と過去のシーンが鮮やかに甦っていた。
あれは、確か大学2年生の秋だった…。
那由太とせつなが急接近していた頃である。せつなのメールで呼び出された那由太は図書館で調べ物をしているせつなの所へ行った。せつなはテーブル一杯に本を広げて何か書き物をしている所だった。
その時、那由太は何でせつなに呼び出されたのかは記憶になかったが、喜々として図書館に向かった…その気分は今でもくっきりと心に刻まれている。前々から気になっていた「星崎さん」から呼び出しを受け、逸る気持ちを抑えつつ図書館へ走ったことがついこの間のことのようである。
秋真っ盛りだった。キャンパスはすっかり秋色であり、黄金色に輝く銀杏を窓越しに見ながら、人気のない図書館の片隅で、那由太とせつなは長々と話をしたのだった。
「…つきあい始めの頃は、お互いの身の上や趣味や、幾らでも話をすることがあ ったよな…。」
思い出すだけで胸が苦しくなるような甘い思い出である。
その時のせつなの話である。
「御子神くん、『原風景』って言葉を知ってる?」
せつなの突然の問いかけに、驚いた那由太であった。
「『ゲンフウケイ?』聴いたことはあるけど…」
と、ちょっぴり知ったかぶりをしながら、せつなに話を合わせたことが記憶にある。
せつなは文学的な素養があり、「どこで覚えたのだろうか」と感心させるような、那由太の知らない洒落た言葉をよく知っていた。
聴けば、せつなには「原風景」なる「風景」の記憶があるのだが、それが何処であるかを思い出すことができないということだった。
その時は知っている振りをしたが、気になって後から調べた那由太は、「原風景」が、「記憶の底に残っていて、いつまでもその人に影響を与え続ける『原体験』が風景の形をとったもの…」という意味を後から確認して感心したのだった。
せつなは子供の頃、お父さんを亡くしたのだが、旅行好きのお父さんはことあるごと、あちこちに家族を連れて行ってくれたそうであった。…しかし、幼かったせつなは、自分が行った場所をほとんど覚えていないとのことであった。
ただ、せつなはその中のどこかを、非常に強烈な印象とともに自分の記憶に焼き付いているのだと言った。
それが何処なのかは具体的に記憶にはなく、「風景」と言っても、どちらかというとイメージの方が先行しているのだ…とも言っっていた。
せつなは、「そこに行けば必ず分かる自信はある、」と言っていた…。
そして…
せつなは、「その場所をいつか探しに行こうと思っている」と…。
せつなにとっての『原風景』…そこには「父」の姿があり、「幸せな家族」のあたたかさが重なっているのであろう。それは那由太にとってもよく分かる話であった。しかし、せつなにとっての『原風景』がなぜその場所なのか…それは那由太には到底知り得なかった。
確実に言えることは、その場所がせつなの「原点」だということ…。
せつなは、そこがどこかを母に訊いても、「あまり多くの場所に行ったから一々覚えていない」と、そう言うのだとこぼしてはいた。けれども、那由太は説明するせつなの言葉の調子に、どことなく漂っている嬉しそうな思いを感じ取っていた。
せつなは、いつか自分の力でその「原風景」を探り当てようとしている…。と。
「…セツのやつ、それで、その旅を始めたってことだったんだな…。」
那由太は、あれほど悩んでおきながら…、我ながら大切なことをすっかり忘れていた、と、情け無い思いで一杯であった。
が、それでも、まだ完全につながりきっていない、「せつなとの思い出」と今回の「彼女の問いかけ」、そして「答え」について、もどかしい思いを胸に抱えたまま、図書館の前のベンチに座って時計ばかりを眺めていた。
図書館が開くと、すぐさま那由太は4Fの自然科学のフロアへ走った。
今までは歴史とか哲学、芸術と言った方面にばかり目を向けていた。先日は、科学者を調べはしたが、「数学者」については全くノーマークであった。
階段を駆け上がる那由太は、まだ自分の中で釈然としないものはあったが、何故か妙に確信めいたものを感じていた。
「数学者」きっと、そこに「答え」がある…と。
そして、ほとんど足を踏み入れたことのない「自然科学」のフロアの片隅、「数学史」の書架の前に那由太は立った。天井から流れてくるエアコンのひんやりとした冷気の中に、古い本独特の黴臭いような、薬品臭いような匂いが漂っている。
那由太はそこから何冊かめぼしい本を抜き出した。そしてそれを抱えて、窓際のテーブルへと移動した。
…その時である。那由太には、もう一つの記憶がまざまざと甦り始めていた。
「ここだ。」
あの時…、せつなに呼び出されて自分が来たのは…紛れもなく、この場所であった。あれは、ここのテーブルだったんだ…。
那由太にそう確信させるものが目の前にあった。
窓の外には、まだ色づいてはいないが、美しい銀杏の緑が朝の光を受けて輝いていた。
我が校のシンボルとも言える銀杏の大木が見えるのは、この図書館では…このフロアの、この場所からだけなのだ…。
「数学って、美術とか、宗教とかとつながりが深いのよ。」
あの時せつなと長々と話したのは、「原風景」の話だけではなかった…。
確かあの時…せつなは、美術史のレポートを書くためだ、と言いながら数学史の勉強をしていたのだ。
「三平方の定理で有名なピタゴラスだって、『ピタゴラス教団』だったんだって。 数学は混沌とした世界を説明する神秘的な『術』だったのね。」
あの時の生き生きとしたせつなの顔…知的に輝く黒目がちな瞳…あれがきっかけで、俺はせつなのことを本気で好きになっていったのだった…。
そして、あの時の出来事がきっかけで、きっとせつなも俺のことを…。
「覚えてる?」
那由太は、せつなが葉書に書いていたそのメッセージの意味を、今になって痛いほどに感じていた。
そして那由太の中には、今までそれぞれの「点」としてしか存在していなかったせつなのメッセージと過去の出来事が「線」としてつながり始めていた。
「ウィリアム・ハミルトン」の名前を見つけ出すのに那由太は、それほど時間を要しなかった。予想通り、せつなの葉書に描かれていたその肖像は、
「ウイリアム・ハミルトン1805~1865」
…アイルランドの数学者のものであった。
そこまでくれば、もうゴールは目の前であった。
那由太の持ってきた本には、例の数式は載っていなかったが、那由太はウイリアム・ハミルトンの業績を一つずつ拾いあげ、それを数学事典で調べていった。
「行列代数」「グラスマン代数」「四元数」…那由太にとっては今まで聞いたこともない人物であり、出てくるのも、頭の痛くなるような数学の専門用語ばかりであった。が、その項目の多さからもその人物が数学の世界では偉大な研究者であると言うことは嫌と言うほど分かるのだった。
暫く貪るように本のページを繰っていた彼の目は、黄ばんだ紙の上にとうとう期待するものを発見したのである。
「i 2 =j 2 =k 2 =ijk=」 …四元数の基本式
ハミルトンは、散歩の途中でこの美しい基本式を思いついき、それを運河の橋の欄干に刻みつけた…そんなエピソードもそこには書かれていた。せつなの喜びそうな話である。実にロマンチックで…。
そうである。せつなの書いていた式の最後の=の先を満たす数字は…
「-1」であった。
ただ、喜びと同時に、那由太の心には暗雲が広がり始めていた。
「-1がない…。」
那由太は家へと向かう電車の中で、冷や汗ともつかない、何とも気持ちの悪い汗を背中に感じつつ、どうしようもなく焦っていた。
「どうして『-1』がないんだ。」
ひょっとしたら、「ユッコ」が…と、思いはしたが、もしも「-1」の葉書が存在して、そこに何処かの景色が映っているのなら、「答え」であろう、その消印の場所を隠す必要はないだろう…と、那由太は思い直した。
消印を隠す必要があるのは、今、せつながいるであろう場所を示す、最後の数枚の葉書だけのはずだからだ。
「それでは、一体…?」
那由太はひとまずアパートに戻らなければならないと考えていた。
ひょっとしたら、最後に届くのが「-1」それだったのだろうか、と淡い期待を抱いて、炎天下の中、駅からアパートまでの道のりをひたすら走っていた。
近くの町工場から、正午を告げる放送が流れているのが聞こえていた。
数分後、那由太は呆然として郵便受けの中を見つめていた。
そこには、朝、那由太が取るのを忘れていた新聞が差し込まれていただけであったのである。
那由太は階段の下の段差に腰を降ろすと、頬を滴り落ちる汗も拭かずに途方に暮れていた。
「約束」は、明日の日没である。せつなは俺を待っている…。
ひょっとして、郵便配達員が間違って隣のポストに入れたのかも知れない。そう思うと那由太はすがるような思いで再び立ち上がり、隣のポストの中を覗いてみた。
しかし、那由太のポストの左側は空室のもので、郵便受けもわけの分からないチラシが入っているだけだった。
そして、右側の郵便受けには逆に、配達を止めていないままなのか、数日分の新聞が無理矢理押し込まれ、下にも2部ほどが落ちているような乱雑な状態で、その中にはとても今日届けられた那由太への葉書が入っているとは思えなかった。
全ての郵便受けの中を確認したが、やはりそれらしいものを見つけることはできなかった。
那由太は、再びそこに座り込んでしまい、頭を抱えていた。
プールに向かう小学生であろうか、透明のバッグを抱えた数人の子供が、楽しそうな歓声をあげながら那由太の横を通り過ぎていく。
夏休み最後の日を楽しむ笑い声がアパートの壁に響いている。
那由太の頭の上には、彼を嘲嗤うかのような太陽。強い日差しがアスファルトを照りつけて、熱気が那由太の体を包み込むように流れてくる。
那由太は神に祈るような気持ちで空を見上げた…。
その那由太の思いが天に届いたのだろうか、…その時、アパートの駐車場に一台の車が入ってきたのである。黒みがかった赤と青のツートンカラーのバン。
もの凄いカラーリングのその車には「クリーンサービス“ウィンド”」と書かれていた。
一度見たら忘れない…その車は、那由太の記憶にも残っていた。このアパートの管理社が派遣している清掃会社のもののようであり、何度かアパートの駐車場に停まっているのを見たことがあったのである。
年配の男性が大儀そうに車から降りてきた。箒にちりとり、そしてビニール袋を持っている。那由太は、不審者だと思わるのも癪だと思い、そそくさと立ち上がった。
その男性は郵便受けの所に歩み寄ると、階段を上がりかけていた那由太に話しかけた。
「201号はオタクじゃないですよね。この新聞は撤去させてもらいますから。」 そのぶっきらぼうな言葉は、那由太にとって、神々しいお告げのように響き渡った。
「201号」は那由太の隣であり、先程、新聞が溢れていた所の部屋番号である。 …そこで、那由太は気づいたのであった。
「そうだ、あの時も…田舎から戻って来た時、俺の郵便受けには当日の新聞しか入ってなかった。」
那由太は慌てて上りかけていた階段を駆け下りると、清掃員のおじさんにおそるおそる尋ねた…。
「あの…、撤去した新聞は、どこへ行くんですか」
那由太はその返事を待つほんの数秒の間を、数時間のようにすら感じていた。もしも、『捨てるよ』という言葉が返ってきたら、そこで、また探索の糸が切れてしまうのだ。
おじさんは、「溜まったら捨てるんやけど、返してくれって苦情が出ることもあるんでね、一旦保管するんだよ。そこの倉庫に…」と、箒の柄で一階の一番端の倉庫らしい扉を指した。
那由太はすかさず尋ねた。
「10日ほど前の新聞はありますか?」
おじさんは、「さあねえ」と言いながら一階廊下をゆっくりと歩き、じゃらじゃらとカギ束を作業着のポケットから取り出すと、その倉庫の扉を開けた。
ツン、と鼻を突く塩素か消毒液のような臭いが溜まったその小さな倉庫の中には、掃除用具やハシゴなどが入っているのが見える。おじさんはその中から青い大きなカゴを引っ張り出した。そのカゴの中には、底から3分の2ほどの所まで、新聞が無造作に入れてあった。
那由太は、
「探してもいいですか?」
と強い言葉で言った。
「いいけど、あと片付けといてな。」
そう言い終わると、清掃員のおじさんは脇の溝の中に転がっている空き缶を拾い始めた。那由太は、荷物を脇に放り出して新聞の山と対峙した。
幸い、那由太の取っている新聞は『日経』である。きっと探しやすいだろうと、那由太は思ったが、手に取る新聞は『読売』『朝日』などの全国紙ばかりで、那由太は焦りを感じ始めた。
しかし、底が見えるか見えないかの所まで掘り出した所で、とうとう4部ほどの『日経』があるのを発見した。那由太は手を振るわせながら、その新聞を両手で大切に持ち上げた。そして、静かに一部一部を分けていった。
「あっ。」
那由太は思わず声を上げた。
8月14日付けの新聞を裏にした時、新聞をまとめるための帯のところに、半分折れ曲がった葉書のようなものが挟まっていた…。
那由太はそれを天の救いのような思いで見つめていた。
「御子神那由太 様」
紛れもない、それはせつなからの5枚目の葉書であった。
そして、宛名の下隅には、はっきりと「-1」の文字が見て取れた。
…そして、せつなのメッセージは、
「もうすぐ2周年だね。」
であった。
那由太はそのせつなの文字を読んで、思わず涙ぐみそうになった…が、大急ぎで新聞を片づけると、おじさんにお礼を言った。
そして、今まででに出したことないほどの猛スピードで階段を駆け上がった。
写真の風景はこれも那由太の見覚えのないものであった。
ただ、カードは既製品であり、右隅に小さな文字が印刷されたあった…。
「秋吉台」
「『秋吉台』って…山口県かァ…。遠いな…。」
しかし、それがどこであろうと今の那由太にとって関係はなかった。例え北海道であっても沖縄であっても、どこまででも駆けつけるつもりはできていたのだ。
那由太は早速準備を始めた。持っていく物はそれほどない…。帰りは…、早くても明後日になるだろう…。着替えは二日分あれば足りるか…。
と、その時である。
那由太の目がカレンダーの上で止まったまま、動かなくなってしまった。
カレンダーの9月4日の所に、「勝負、最終面接9:00~」という自分の赤い文字を発見したのである。
9月3日のことばかり頭にあった那由太は、9月4日に何があるかなどということは、ここの所全く意識の外であった。
その面接は、那由太にとって第1志望の企業…服飾関係の会社のものであった。
そこを、キャンセルすると、もう残りは「安全パイ」しか残らない…。
ただ、那由太の気持ちは妙に穏やかだった。
「今更、面接の日を換えて欲しいといったところで、無理に決まっている。
…嘘を付くのは嫌だ。きっと、これが自分の運命…『道』なんだ…。」
この数日間、那由太は今までに考えたことがない程に、「自分自身」について考えさせられていた。「自分」とは何か…。自分の「今まで」、そして「これから」は…。
言うまでもなく、それはせつなの「挑戦状」があったからこそである。初めはせつなの「思い」が理解できずに、腹を立てもした那由太であったが、それが今の段階ではもう、感謝へと変わっていた。そして、せつなへの愛情に…。
そして、自分自身で出した結論は、
「自分の『これから』はせつなと共にある。」
これが彼にとっての最終命題であった。
那由太の中には、この夏の数日間で、他の何物にも代え難い「答え」が導き出されていた。
「…辞退届けは明日すればいい。」
那由太は素速く身支度を整えると、今まで届いていたせつなの葉書を全て一括りに輪ゴムで束ね、読みかけの専門書の間に挟んだ。そして着替えやら何やらを一まとめにしてザックに放り込んだ。
「…もう夜行列車は間に合わないだろう。でも、明日の朝一番の電車に乗れば、 何とか間に合う…。今日はあいつの所に停めてもらおう…。明日の朝は早いぞ。」
那由太の頭はもの凄い速度で回転していた。
そして、ザックを右側の肩に掛けると、部屋を勢いよく飛び出して行った。
机の上の写真の中で、せつなが笑っていた。
エピローグ
那由太は秋吉台に向かう観光バスの中にいた。
彼の胸は次第に高まってくる高鳴りを抑えられなかった。時刻はもう夕刻に迫ろうとしていた。
太陽は次第に傾き、空気が淡い琥珀色に輝き始めている。もう、夕暮れの気配が漂いはじめていた。
胸の鼓動を沈めようとして、那由太は、何度見たか分からないせつなからの葉書をもう一度順番に眺めていた。
もう、那由太には全ての「意味」が見通せていた。
「-」、マイナスのついている葉書はせつなの「過去」だ。
せつなの、父との思い出が…彼女が訪れた日本各地の風景に重なっていく。
実際にせつなが訪れた順序とは違っているのかも知れないが、せつなはとうとう見つけたのである。
「原風景…。」
それが「-1」の記された、秋吉台の風景であることに違いはなさそうであった。
そして、「0」は、せつなと那由太の通う大学のキャンパス。二人の「ゼロ地点」だ。そして、その写真には…あの日、図書館の窓から二人で眺めた金色の銀杏が輝いていた…。
「+α」は数学者「ウイリアム・ハミルトン」である。
せつながどうしてこの数学者を選んだのかは分からない。「-1」という暗号のためだけに選ばれたのかも知れない。…けれど、あの日の図書館での会話…あれがきっかけで、自分はせつなに惹かれていった…。そんな実感がある自分には、ロマンチストだったその数学者の横顔にも何か特別な意味があるような気がするのだった。
せつなからの「挑戦状」は、それほど凝ったものではなかった。
気が付けば、実に簡単な謎かけだった。…自分が、彼女と歩んだ「道順」を、大切に覚えてさえいれば…。
数式が記された最後の葉書。そこに描かれたパリの風景の意味も那由太にはもう分かっていた。…それは、せつなにとっての「未来」である。
那由太の中で、せつなの言葉が鮮やかに、そして静かに甦っていた。
「いつかはパリに行って美術館巡りをするの…。」
「するの…。」の後、じっと自分の目を見つめたせつな。彼女はそこで、敢えて何も言わなかったのだろうけれど、きっと「那由太と一緒に…。」と言いたかったのだろう…。
せつなは、過去も現在も未来もすべて自分に投げかけてくれたのだ。
…そう思うと、また那由太の胸は鼓動を速めるのだった。
バスは山道に入り、暫く進んで行くと、せつなのくれた絵葉書通りの風景が那由太の目の前に広がっていた。
何処までも続くかのような草原と、力強く剥き出した岩々。那由太にとっては見たことのないものだったけれど、それはどこか懐かしいような風景であった。
展望広場のような所で、那由太はバスを降りた。バスから降りるのは那由太だけであり、殆どがこれから帰ろうとして乗り込んでくる人ばかりであった。
帰りの手段のことなどは、今は考えもしていなかった…。
バスから降りると、涼しげな風がTシャツ姿の那由太の脇を吹き抜けていく。
もうここだけには「秋」が訪れているかのようであった。
そして、那由太は取り憑かれたように、歩き始めた。
次第に傾いていく夕陽を追いかけるようにして、高原の道を歩いていった。目の前に見える小高い丘の方へ。
草を踏みしめながら歩く那由太の頭の中を、学生時代の思い出のシーンが、一コマずつ、一コマずつ、浮かんでは消えていった。
そして、そのシーンの全てには、せつなの笑顔があった…。
那由太はその丘の上に立った。
沈んでいく大きな夕陽。そして、それに重なるかのように、小さな人影が那由太の視界に入っていた。
小さな岩に腰掛け、淋しそうに沈む夕陽を見つめているその後ろ姿…。
少し赤味を帯びた夏の夕陽が、彼女の向こうで輝いてはいたが、それよりも濃く、鮮やかに、赤のキャップが那由太の目に映っていた。
「『この風景』が俺の『原風景』になるんだ…。」
那由太は涙をこらえながら草原の中を走り始めていた…。
《了》
まだ朝の8時前だというのに、もうゆらゆらと陽炎が立ち上る隣の民家の屋根を見ながら那由太は呟いた。
そして、出かける支度を整えると窓を閉めてカギを掛けると、机の上に飾られた写真をちらりと見た。
それは彼がせつなと二人で撮った一番お気に入りの写真である。昨年の夏に二人で行った裏磐梯、そこで撮った写真である。那由太は少しカメラ目線から外れて空の方を見ているが、せつなは黒目がちの目を真っ直ぐにカメラに向けている。
二人の後ろには鮮やかなブルーの水面が見える。「毘沙門沼」だったか…、五色沼の一つで、とても色の鮮やかな沼の脇で撮った一枚である。
せつなの部屋にも、これと同じ写真が飾られていることも那由太は知っていた。 …二人の絆を感じさせてくれる写真。
那由太にとってはとても大切なものであり、せつなに逢えない日が続くと、ついつい見入ってしまう写真なのであった。
今日も調べ物とアルバイトである。就職活動は一時休止であった。
結果的に那由太の道は二社に絞られていた。というか、それだけしか那由太には選択肢が残らなかったのであった。
一社は地元では比較的大きな企業で、服飾関係の会社である。そして、もう一社は先日説明会に出かけていった食品関係の中小企業。那由太にとっては「安全パイ」の会社である。
「就職は地元でするんだ」と言い張っておきながら、就職活動も後手後手になってしまった挙げ句に、最終選考まで残った会社はたった二社であった。
友人達は、いっそ「就職浪人したら?」などと安易なアドバイスをよこしたりする。しかし、那由太は、「どこでも自分が頑張りさえすればいいのだから…」と、本心とも強がりとも言えるような台詞を口にしつつ、あくまで今年中に決めるつもりを強くしていた。
那由太にとっての最優先事項。それは、とにかく今年中に就職を決めること。そして、それは次第に那由太の中で日に日に強くなっていたのである。
何故かというと、それが決まりさえすれば、「次の一歩」が踏み出せそうだったからなのだ。それは彼自身の将来でもあったが、同時に「せつなとの未来」も意味する「一歩」であった。
那由太は机の上の写真立ての前に、せつなから届いた葉書を綺麗に並べて部屋を後にした。ただ、外国人の写真が印刷された、あの一枚だけはカバンに入れて持ち出していた。
今、那由太の頭を占めていたのは、せつなの顔と同じぐらい、その外国人の顔であった。多分100年は経っているであろう、その写真に写った白髪の男性は、鋭い眼差しで斜め前を見つめている。
その視線の方向が、あの写真…せつなと一緒の写真の中の自分と一緒と似ている…と、下らないことに気がつきはしたが、それはどうにもせつなのメッセージを解読するヒントにはなりそうになかった。
「一体誰なんだろう?」
大学で出逢った友人たちに尋ねても、「音楽家か誰かかなあ」というぐらいで、誰も分からない。せつなの専門は美術史だから、芸術家か誰かであろうか、とも思った。
以前、この写真とは違うけれど、こんな写真がいくつか出ている本をせつなが図書館で読んでいたことがあった…。そんなことをうっすらと那由太は記憶していたのだ。しかし、それが何かまでは思い出すに至らなかった。
それで、昨日は図書館で西洋の芸術家を片っ端から調べたが、結局分からず仕舞いであったのだ。
そこで、今日も時間があれば、調べてみようというのが那由太の考えであった。
その日は、幾らか早くアルバイトが上がった。もう一度図書館へ戻って調べようかと思いもしたが、アルバイトの場所から大学は反対方向になってしまい、余りにロスが大きい。午前中に調べた科学者達の中にも、あの人物はいなかった。
「もう、今日はやめておこう。」と、那由太は決めて帰ることにしていた。
那由太はここの所、いつもコンビニの弁当だなと、反省し、今日は自分で料理でもしようかと、帰り道に、駅から少し回り道をして比較的大きなスーパーへと向かった。
夏の日差しはまだまだ強く、六時を回っていても、日差しが肌を焦がすような感じである。「ジリジリ」と音が聞こえてきそうな気さえする。
八月ももう終わりなのに、一段と暑さが増しているようなここ数日であった。
「今日はカレーでも作ってみようか」と、張り切って買い物をすませ、いつもと違う道を家へと向かって歩いていた時であった。向こう側から見覚えのある若い女性がこちらに歩いてくるのが見えた。その娘が、せつなと仲良しの研究室の友達だと分かり、すれ違いざまに那由太は「こんにちは」と声を掛けた。
彼女は顔を上げ、那由太に気づいた。すると、と妙に驚いたような顔でどぎまぎしながら「あ、どうも…」と言うと、足を速めて過ぎ去ってしまった。
那由太はせつなのことを尋ねようかと思ったが、何やら声を掛けられることを拒否するかのような彼女の態度に、タイミングを逸してしまい、去っていくその娘の後ろ姿を見ながら、道の中程に立ちつくしていた。
「あの娘の家って、この駅周りだったっけ? それにしても、急いでたのかな?」
那由太は、何度か会話も交わしたことのあるその娘の態度があまりにぶっきらぼうだったことに釈然とせず、そこからの数百メートルを、とぼとぼと下宿まで歩きながらあれこれと思いを巡らせていた。
アパートの前まで来ると、階段下に回る。
那由太は少し大きめのビニール袋を提げて郵便受けの前に立った。その時、那由太には何となく、予感がしていた。
せつなからの最後の葉書が、今届いている。そんな妙な確信があった。
そして、果たして郵便受けの中に、その葉書はあった。
「御子神那由太 様」
いつものせつなの字である。そして、その下にはとうとう那由太の恐れもし、期待もしていた言葉が記されていた。
「9月3日 一緒に夕陽を。」
その文字は、いつもよりも少しだけ大きく、力強く見えた。
那由太の予想していた通り、とうとう、具体的な日時を示すメッセージがせつなから送られてきたのだ。そして、その隅には…
「i 2 =j 2 =k 2 =ijk=」
と、何かしら数式のようなものが記されていた。
送られてきたそれは、再び既製品のポストカードであったのだが、裏返して写真を見ると、何とそこにはエッフェル塔らしき景色が映っていた。
その場所はフランス、パリであることは言うまでもなかった。消印は…やはり押されていなかった。
覚悟していたこととは言え、那由太は慌ててしまった。何故なら、今日は8月31日である。9月3日まではあと3日しかない。
しかも、まだせつなのメッセージの内容は、よく分からないままである。
「せつなが待っているはずの場所は、まさかフランスってことはないだろう…が、 場合によっては1日では行くことのできない場所になるかも知れない。」
那由太はもう食事を作ることも忘れ、机の前にせつなからの葉書を並べ、頭を抱えてしまった。もう、何度見たか分からないほど眺めた葉書ではあったが、改めてそれを表側にしたり、裏側にしたりして、何かを見つけ出せないだろうか、と彼は必死であった。
そして、もう一度送られてきた順番に丁寧に読み返してみた。
最初の5枚は国内のポストカードである。
1枚目には「旅をしています」と「-5」。写真は栃木県の戦場ヶ原の写真であり、消印も栃木県である。
2枚目は「まだまだ続きそうです。」と「-4」。写真は東尋坊で消印は、これは石川県であった。
そして、3枚目は四万十川に「-3」。そして「就活順調ですか?」消印は高知。 4枚目は鹿児島の消印で、枕崎の海岸が写ったもの。「旅を続けています」と、「-2」である。
しかし、それらを幾ら眺めていていも一向に答えらしいものはは浮かんでこないのだった。
5枚目は那由太とせつなの通う大学のもの。メッセージは「元気です。」と「0」である。「0」を「オー」と読むことも、それ以外の何かに読むことも考えてみたが、今更特に何も閃くことはなかった。そして、これには消印が記されていなかった。
きっとせつなはどこか、旅の途中で「答え」を見つけたのだ。そして、それがきっと待ち合わせの場所なのだ。せつなは、今そこにいて、その場所から自分に向けて最後の数枚を送っているのだろう。
だから、その場所が分からないように消印の無い葉書を…。
知らない間にもう時刻は9時になっていた。
もう1枚は誰のものか分からない古いポートレイト。そして「+α」。「覚えてる?」のメッセージ。
そして、最後の一枚はフランスの景色と数式なのであった。
「i」や「j」「k」は何かのイニシャルだろうかとも思った。しかし、そこについている指数の「2」の意味が分からない。なぜ、二乗するのだろうかと考えてもよく分からない。
最後の「イコール=」の先には何かが当てはまるのだろうか。しかし、それも全く見当がつかないのであった。
幾ら考えても何も浮かんでこない自分に苛立ちを感じる那由太であったが、自分に腹を立てても仕方がないことぐらいは心得ていた。
最もヒントらしいものと言えば、「+α」の古い外国人の写真である。そこに記されたせつなのメッセージ「覚えてる?」が、何を自分に思い出させようとしているのか…。
彼は食事をするのも忘れていた。買ってきたものは、そのままほとんど冷蔵庫に放り込んだままであった。空腹を感じ、食べ残しのパンを囓り、牛乳を飲んだだけで、横になってしまった。
そして、せつなとの思い出をあれこれと思い浮かべていると、切ないような虚しいような妙な感覚に陥って、そのまま知らない間に眠りに落ちていた。
その夜、那由太は夢を見た。那由太はせつなと二人で歩いていた。
何もない白い大地。せつなは那由太の少し前を歩いている。那由太はスーツ姿。せつなはいつものジーンズにパーカーで、トレードマークの赤いキャップを被っている。
那由太はせつなに追いつこうとするが、なかなか思うように前に進めない。スーツが体にまとわりつき、革靴はぬかるみを歩いているように足を取られる。
そして、せつなはこちらを振り向くこともせずに前へ前へと歩いて行ってしまう。「待ってくれよ」と声を出そうとしても、声も出せない。
せつなと自分の距離はどんどんと開いていく。焦れば焦るほど、那由太の足は余計に動かず、せつなの赤いキャップは次第に小さくなっていく。
地平線の向こうに赤い点消えかかる…。
せつながの姿が見えなくなると、もう全てが終わってしまうような気がして…那由太は夢中で叫び声をあげた。
…ベッドから飛び起きた那由太は、周囲を見まわした。
「夢か…。」と呟き、大きく息をついた。
外はもう白々としており、扇風機は虚しく首を振り続けていた。点けたままの電灯を見ながら、那由太は「何だったんだ…」と、溜息ともつかない深い吐息とともに小さく言葉を吐き出した。
「夢の中での叫び声は、せつなに届いたのだろうか…」
そんな朧気な不安のようなものが頭の隅に残り火のように虚しく燻っていた。
もう、時刻は5時過ぎであった。次第に頭がはっきりしてくると、那由太は早速身支度を整えた。彼に残された時間は僅かしかなかった。何とか早いうちに「答え」を見つけ出さなければならないのだった。
那由太の今日とるべき行動は決まっていた。写真の外国人を調べることもあったが、まずは昨日スーパーの帰り道ですれ違ったせつなの友達に会うことであった。
消印の無いせつなからの葉書が、誰かに直接届けられたものであるということは、想像に難くないものであったが、昨日のあの子が「配達人」であろうということは那由太にはピンと来ていた。
ただ、その子を尋ねることで問題を解決することは、せつなからしてみれば不本意であろう…そう考えはした。
しかし…昨夜の夢のせつなの後ろ姿。どことなく淋しそうな後ろ姿…。
那由太に今はあれこれ手段を考えている暇はなかったのである。
「せつなに逢いたい。」彼は今それだけの思いに突き動かされていた。
文学部の棟は、那由太の通う経済学部の棟とは隣り合わせである。那由太は、図書館と文学部棟のどちらもが見える中庭のベンチに座っていた。
「ユッコ」とせつなはその娘を呼んでいたのを那由太は覚えていたが、本名は知らなかった。研究室が同じということは明らかであったので、ひょっとしたらここに張り込んでいれば会えるかも知れないと考えたのであった。
ただ、今は夏休みで講義も行われていない。4年生にもなると、学校に来なくなる者も多い。しかし、昨日その娘を見たということは、地方出身者であれば少なくとも帰省はしていないはずだ。卒業論文のための調べ物などをしてこちらに残っている者はキャンパス内に姿を現すことが多い。特に、美学であるとか美術史であるとかの研究は、「図書館が一番なの。」…これはせつなのいつもの台詞であった。
那由太はそれに賭けた。ただ、だらだらと時間を過ごす訳にもいかなかったので、自分の卒業研究のための専門書を膝の上に置いて、ひたすら待ち続けた。
自分の本も、読むには読んでいたが、人影が見えるたびに顔を上げることになるし、本自体が内容も難しいものなので、2時間ほどで15頁ほどしか進まない。
図書館にある時計台はもう10時30分を指していた。
那由太のいるベンチは、一応木陰にはなっているものの、空には雲一つなく、真夏の日差しが容赦なく照りつけている。そんな所に坐っているのは、那由太一人であり、通り過ぎていく人は物珍しそうな眼差しを投げかけてくる。
那由太は校舎付近に何度か、その娘に良く似た姿を見つけ、「ハッ」と息を飲んだ。しかし、それはいずれも人違いであった。
次第に気温が上がっていき、緊張と暑さで那由太は用意していたペットボトルのお茶を飲み干してしまっていた。しかし、再びのどの渇きを抑えられなくなり、ベンチには荷物をそのままにして、殻のペットボトルを手に持つと、近くにある自動販売機まで出向いて行った。
「ポン、ポン」と、殻のペットボトルを左手の手のひらで叩き、そのままゴミ箱に殻押し込む。財布から硬貨を取り出して、新製品のスポーツドリンクを一本購入し、ボトルとおつりを取るためにしゃがんだ那由太は立ち上がりざま後を振り返った…その時である。
何という幸運であろうか、那由太の後に自販機を利用しようとして立っていたのは「ユッコ」その人であった。
思わず「あっ」と声を上げる那由太。そして、彼の目に入ってきたのは、全く昨日の夕方の再現フィルムを見ているような彼女の表情であった。
ただ、今回は「ユッコ」はその場を立ち去ることはできなかった。彼女は両手に重そうな大版の専門書を数冊抱えていたのである。
那由太の、「ちょっといいですか?」という言葉に俯いたままの彼女は何だか可哀想な気さえするほど縮こまっていた。ただ、那由太はそれに遠慮している場合ではなかった。
那由太はズバリ確信を突く質問を浴びせた。
「せつな…星崎せつなの葉書を届けてくれましたよね。」
やや、カマをかけた感じであったが、那由太の自信たっぷりの言葉に、否定はできないと思ったのであろう「ユッコ」声は小さいながらもはっきりとした返事を返してくれた。
「はい。せつなに頼まれたんです。…でも、ごめんなさい…それ以上の事は言えません。」
その声は小さいながらも非常に強い調子で、それ以上に那由太の追及の手は及びようもないことを感じさせるものであった。那由太は口元まで出かかっていた「今、せつなが何処にいるか知ってますか?」という野暮な質問を喉の奥に押し込んだ。
ペットボトルを握りしめる手に力がこもる。冷たい雫が指と指の間を伝っていくのが感じ取れる。
那由太は言葉を失い、窮してしまった。
先に口を開いたのは意外にも「ユッコ」であった。
「ごめんなさい。何も言えないんです。約束してるから…。でも、那由…あ、御子神さん…頑張って下さい。せつなは待ってます。絶対にせつなの所に行って下さい。せつなは御子神さんのことを本当に大切に思っています…。」
説得力のある重い言葉だった。
那由太はそれに対して、「うん。ありがとう。」というのが精一杯で、彼女に背をむけるとその場を後にし、とぼとぼとベンチまで歩いた。
濃い影がアスファルトの上で小さく那由太の足もとにまとわりついていた。
その日は昼からアルバイトであった。一刻を争う那由太はそれどころではなかったが、どうしても抜けられなくて、那由太は気乗りのしないまま、電車に揺られてアルバイト先のある駅に向かっていた。
車内の冷房は心地よかったが、那由太の心は澱んでいた。あの後、残された時間は図書館に行って例の外国人探しに費やしたが、徒労に終わっていた。
「ひょっとしたら」と、見当をつけた経済学者や外国文学作家の肖像にも、あの白髪の男性はいなかった。
その日は薄暗くなる頃に那由太は下宿に辿り着いた。郵便受けには、朝取り忘れた新聞が差し込んであるだけであった。
部屋に入ると、いつもはあまり見ないテレビのスイッチを入れる。ちょうど7時からのニュースが始まっている。…連日の異常な暑さのために、都市部の冷房がフル回転で、電力量の供給が間に合っていないことをアナウンサーが涼しげな顔で告げていた。
那由太の部屋には縁遠い話だった。きっとこの部屋の温度は軽く30度を超えているであろう、額を流れる汗が温度計替わりである。
Tシャツは汗でびっしょり濡れている。那由太は、あまりの暑さに冷蔵庫の中で眠っていたとっておきのビールを取り出して飲み始めた。
お酒が入ると、気分は幾らか上向きになってきた。
明日はアルバイトも休みだし、研究室に行く用事もない。一日かけて、絶対に謎をといてやる。昨日作り損ねたカレーを、今日は作ろう。好物のカレーを食べれば何か閃くかもしれない…そう思った那由太は、早速カレーの準備を始めた。が、汗も流したい気分になり、「よし、今日は水風呂だ」と、風呂場に行って水道の蛇口をひねった。勢いよく水がほとばしる。
最初は、日中水道管の中で温められていたお湯のようなものが吹き出したが、暫くするとほどよい冷たさになってきた。
那由太は水道を出しっぱなしにして、風呂場を出ると、再び台所に立って玉ねぎの皮をむき始めた。
洗った野菜を切り、玉ねぎとニンニクを炒めて一段落したところである。
鍋に水を入れてあとは煮込むだけ、という所であった。ふと、風呂場の方から音がするのに気づいた。
「しまった。」
那由太は浴槽に水を溜めていたのをすっかり忘れてしまっていたのだ。炒め物の音で風呂場から聞こえてくる水の音に気が付かなかったのだ。
慌てて風呂場に駆け込むと、もう水はとっくに浴槽を超えてザバザバと音を立てて水が溢れ出ていた。
「ま、お湯でなかったのが幸いか…」
蛇口を締めながら、随分と勿体ないことをした…と、少々悔やみもしたが、気を取り直した那由太は、溢れる水で濡れた足をタオルで拭うと、取りあえず、鍋の火を弱火にして汗を流すことにした。
体と頭を洗っても、溢れ出るほど…イヤ、実際に溢れ出ていた浴槽の水は、まだまだたっぷりある。
「ええい。」
と、那由太は一気に浴槽に体を沈めることにした。
勢いよく溢れ出す水。洗い場の椅子や石鹸置きが慌ただしく壁の方に流されていく。
ほどよく冷たい水に浸かると、アルコールも入って火照っていた体が一気に冷やされていく。
「フーッ。」息を飲むような快感である。那由太は子供の頃、よくわざと浴槽のお湯を溢れさせ、父に叱られていたことを思い出した。
「アルキメデスみたいに、何か閃かないかなあ…」
次第に落ち着いていく水面を眺めながら那由太はぼんやりと考えていた。
「で、アルキメデスは何を閃いたんだっけ?」
那由太に、そんな妙な疑問がとりついた。暫く思い出そうとしたが、はっきりと思い出すことができない。
「確か…王冠を沈めて溢れ出す水で王冠の真偽を突きとめたんだっけ。でも、な んで水が溢れたら分かったのかな…。」
那由太は理科音痴で、どうも物理とか化学の話になるとさっぱり苦手なのであった。同じく理科系が苦手なせつなと、よくお互いの無知比べをしたものである。
「でも、せつなは時々やたら詳しいことがあったよな…」
その時、那由太の中に再び何かが甦ろうとした…そんな感覚を自分自身の中に感じた。しかし、残念ながら今回もそれは「気」だけで終わってしまった。
それが何か分からないことにまた歯痒い思いをしたが、取りあえず那由太は先程の疑問を解決しようと考えた。そこから何か閃かないかと思ったのである。
「『ユリイカ』だったっけ。アルキメデスが、閃いた時に発した言葉は…『大発見。見ィーつーけた。』って感じの言葉だったよナ…。」
那由太は、妙なことは覚えているものだ…と、自分に感心しながら、冷えた体を拭きつつ、何かが自分の中でつながり始めている予感を嗅ぎ取っていた。
すっかり、体は冷えて爽快な気分で那由太は風呂からあがり、短パンにTシャツ姿になると、早速カレーの仕上げに入った。
そして、ふと本棚の大型国語辞典に目が止まると、先程の疑問を思い出した。
「アルキメデスって、本当に何を発見して、それで『ユリイカ』って叫んだんだっけな。」
辞典で「アルキメデス」を引けば、さっきの疑問が解決するのでは、と思い、那由太は早速「アルキメデス」という項目を調べてみる。
しかし、残念ながらそこには那由太の疑問を解決するような記事はなかった。「アルキメデスの原理」というのも、那由太が思っていたものとはちょっと違っていた。「古代ギリシアの数学者・物理学者・技術者…か。」
辞典の冒頭の言葉にもう一度目が行っていたその時である。那由太の目が、釘付けになった。
「数学者…そうか、そうだったのか。」
第3章『「夏」の終わり』
9月2日。那由太は大学の図書館の前で、開館の時を今や遅しと待っていた。
「一刻も早く、謎を解かなければ、約束の期日に間に合わないかも知れない。」 気が逸る那由太の頭の中には、次々と過去のシーンが鮮やかに甦っていた。
あれは、確か大学2年生の秋だった…。
那由太とせつなが急接近していた頃である。せつなのメールで呼び出された那由太は図書館で調べ物をしているせつなの所へ行った。せつなはテーブル一杯に本を広げて何か書き物をしている所だった。
その時、那由太は何でせつなに呼び出されたのかは記憶になかったが、喜々として図書館に向かった…その気分は今でもくっきりと心に刻まれている。前々から気になっていた「星崎さん」から呼び出しを受け、逸る気持ちを抑えつつ図書館へ走ったことがついこの間のことのようである。
秋真っ盛りだった。キャンパスはすっかり秋色であり、黄金色に輝く銀杏を窓越しに見ながら、人気のない図書館の片隅で、那由太とせつなは長々と話をしたのだった。
「…つきあい始めの頃は、お互いの身の上や趣味や、幾らでも話をすることがあ ったよな…。」
思い出すだけで胸が苦しくなるような甘い思い出である。
その時のせつなの話である。
「御子神くん、『原風景』って言葉を知ってる?」
せつなの突然の問いかけに、驚いた那由太であった。
「『ゲンフウケイ?』聴いたことはあるけど…」
と、ちょっぴり知ったかぶりをしながら、せつなに話を合わせたことが記憶にある。
せつなは文学的な素養があり、「どこで覚えたのだろうか」と感心させるような、那由太の知らない洒落た言葉をよく知っていた。
聴けば、せつなには「原風景」なる「風景」の記憶があるのだが、それが何処であるかを思い出すことができないということだった。
その時は知っている振りをしたが、気になって後から調べた那由太は、「原風景」が、「記憶の底に残っていて、いつまでもその人に影響を与え続ける『原体験』が風景の形をとったもの…」という意味を後から確認して感心したのだった。
せつなは子供の頃、お父さんを亡くしたのだが、旅行好きのお父さんはことあるごと、あちこちに家族を連れて行ってくれたそうであった。…しかし、幼かったせつなは、自分が行った場所をほとんど覚えていないとのことであった。
ただ、せつなはその中のどこかを、非常に強烈な印象とともに自分の記憶に焼き付いているのだと言った。
それが何処なのかは具体的に記憶にはなく、「風景」と言っても、どちらかというとイメージの方が先行しているのだ…とも言っっていた。
せつなは、「そこに行けば必ず分かる自信はある、」と言っていた…。
そして…
せつなは、「その場所をいつか探しに行こうと思っている」と…。
せつなにとっての『原風景』…そこには「父」の姿があり、「幸せな家族」のあたたかさが重なっているのであろう。それは那由太にとってもよく分かる話であった。しかし、せつなにとっての『原風景』がなぜその場所なのか…それは那由太には到底知り得なかった。
確実に言えることは、その場所がせつなの「原点」だということ…。
せつなは、そこがどこかを母に訊いても、「あまり多くの場所に行ったから一々覚えていない」と、そう言うのだとこぼしてはいた。けれども、那由太は説明するせつなの言葉の調子に、どことなく漂っている嬉しそうな思いを感じ取っていた。
せつなは、いつか自分の力でその「原風景」を探り当てようとしている…。と。
「…セツのやつ、それで、その旅を始めたってことだったんだな…。」
那由太は、あれほど悩んでおきながら…、我ながら大切なことをすっかり忘れていた、と、情け無い思いで一杯であった。
が、それでも、まだ完全につながりきっていない、「せつなとの思い出」と今回の「彼女の問いかけ」、そして「答え」について、もどかしい思いを胸に抱えたまま、図書館の前のベンチに座って時計ばかりを眺めていた。
図書館が開くと、すぐさま那由太は4Fの自然科学のフロアへ走った。
今までは歴史とか哲学、芸術と言った方面にばかり目を向けていた。先日は、科学者を調べはしたが、「数学者」については全くノーマークであった。
階段を駆け上がる那由太は、まだ自分の中で釈然としないものはあったが、何故か妙に確信めいたものを感じていた。
「数学者」きっと、そこに「答え」がある…と。
そして、ほとんど足を踏み入れたことのない「自然科学」のフロアの片隅、「数学史」の書架の前に那由太は立った。天井から流れてくるエアコンのひんやりとした冷気の中に、古い本独特の黴臭いような、薬品臭いような匂いが漂っている。
那由太はそこから何冊かめぼしい本を抜き出した。そしてそれを抱えて、窓際のテーブルへと移動した。
…その時である。那由太には、もう一つの記憶がまざまざと甦り始めていた。
「ここだ。」
あの時…、せつなに呼び出されて自分が来たのは…紛れもなく、この場所であった。あれは、ここのテーブルだったんだ…。
那由太にそう確信させるものが目の前にあった。
窓の外には、まだ色づいてはいないが、美しい銀杏の緑が朝の光を受けて輝いていた。
我が校のシンボルとも言える銀杏の大木が見えるのは、この図書館では…このフロアの、この場所からだけなのだ…。
「数学って、美術とか、宗教とかとつながりが深いのよ。」
あの時せつなと長々と話したのは、「原風景」の話だけではなかった…。
確かあの時…せつなは、美術史のレポートを書くためだ、と言いながら数学史の勉強をしていたのだ。
「三平方の定理で有名なピタゴラスだって、『ピタゴラス教団』だったんだって。 数学は混沌とした世界を説明する神秘的な『術』だったのね。」
あの時の生き生きとしたせつなの顔…知的に輝く黒目がちな瞳…あれがきっかけで、俺はせつなのことを本気で好きになっていったのだった…。
そして、あの時の出来事がきっかけで、きっとせつなも俺のことを…。
「覚えてる?」
那由太は、せつなが葉書に書いていたそのメッセージの意味を、今になって痛いほどに感じていた。
そして那由太の中には、今までそれぞれの「点」としてしか存在していなかったせつなのメッセージと過去の出来事が「線」としてつながり始めていた。
「ウィリアム・ハミルトン」の名前を見つけ出すのに那由太は、それほど時間を要しなかった。予想通り、せつなの葉書に描かれていたその肖像は、
「ウイリアム・ハミルトン1805~1865」
…アイルランドの数学者のものであった。
そこまでくれば、もうゴールは目の前であった。
那由太の持ってきた本には、例の数式は載っていなかったが、那由太はウイリアム・ハミルトンの業績を一つずつ拾いあげ、それを数学事典で調べていった。
「行列代数」「グラスマン代数」「四元数」…那由太にとっては今まで聞いたこともない人物であり、出てくるのも、頭の痛くなるような数学の専門用語ばかりであった。が、その項目の多さからもその人物が数学の世界では偉大な研究者であると言うことは嫌と言うほど分かるのだった。
暫く貪るように本のページを繰っていた彼の目は、黄ばんだ紙の上にとうとう期待するものを発見したのである。
「i 2 =j 2 =k 2 =ijk=」 …四元数の基本式
ハミルトンは、散歩の途中でこの美しい基本式を思いついき、それを運河の橋の欄干に刻みつけた…そんなエピソードもそこには書かれていた。せつなの喜びそうな話である。実にロマンチックで…。
そうである。せつなの書いていた式の最後の=の先を満たす数字は…
「-1」であった。
ただ、喜びと同時に、那由太の心には暗雲が広がり始めていた。
「-1がない…。」
那由太は家へと向かう電車の中で、冷や汗ともつかない、何とも気持ちの悪い汗を背中に感じつつ、どうしようもなく焦っていた。
「どうして『-1』がないんだ。」
ひょっとしたら、「ユッコ」が…と、思いはしたが、もしも「-1」の葉書が存在して、そこに何処かの景色が映っているのなら、「答え」であろう、その消印の場所を隠す必要はないだろう…と、那由太は思い直した。
消印を隠す必要があるのは、今、せつながいるであろう場所を示す、最後の数枚の葉書だけのはずだからだ。
「それでは、一体…?」
那由太はひとまずアパートに戻らなければならないと考えていた。
ひょっとしたら、最後に届くのが「-1」それだったのだろうか、と淡い期待を抱いて、炎天下の中、駅からアパートまでの道のりをひたすら走っていた。
近くの町工場から、正午を告げる放送が流れているのが聞こえていた。
数分後、那由太は呆然として郵便受けの中を見つめていた。
そこには、朝、那由太が取るのを忘れていた新聞が差し込まれていただけであったのである。
那由太は階段の下の段差に腰を降ろすと、頬を滴り落ちる汗も拭かずに途方に暮れていた。
「約束」は、明日の日没である。せつなは俺を待っている…。
ひょっとして、郵便配達員が間違って隣のポストに入れたのかも知れない。そう思うと那由太はすがるような思いで再び立ち上がり、隣のポストの中を覗いてみた。
しかし、那由太のポストの左側は空室のもので、郵便受けもわけの分からないチラシが入っているだけだった。
そして、右側の郵便受けには逆に、配達を止めていないままなのか、数日分の新聞が無理矢理押し込まれ、下にも2部ほどが落ちているような乱雑な状態で、その中にはとても今日届けられた那由太への葉書が入っているとは思えなかった。
全ての郵便受けの中を確認したが、やはりそれらしいものを見つけることはできなかった。
那由太は、再びそこに座り込んでしまい、頭を抱えていた。
プールに向かう小学生であろうか、透明のバッグを抱えた数人の子供が、楽しそうな歓声をあげながら那由太の横を通り過ぎていく。
夏休み最後の日を楽しむ笑い声がアパートの壁に響いている。
那由太の頭の上には、彼を嘲嗤うかのような太陽。強い日差しがアスファルトを照りつけて、熱気が那由太の体を包み込むように流れてくる。
那由太は神に祈るような気持ちで空を見上げた…。
その那由太の思いが天に届いたのだろうか、…その時、アパートの駐車場に一台の車が入ってきたのである。黒みがかった赤と青のツートンカラーのバン。
もの凄いカラーリングのその車には「クリーンサービス“ウィンド”」と書かれていた。
一度見たら忘れない…その車は、那由太の記憶にも残っていた。このアパートの管理社が派遣している清掃会社のもののようであり、何度かアパートの駐車場に停まっているのを見たことがあったのである。
年配の男性が大儀そうに車から降りてきた。箒にちりとり、そしてビニール袋を持っている。那由太は、不審者だと思わるのも癪だと思い、そそくさと立ち上がった。
その男性は郵便受けの所に歩み寄ると、階段を上がりかけていた那由太に話しかけた。
「201号はオタクじゃないですよね。この新聞は撤去させてもらいますから。」 そのぶっきらぼうな言葉は、那由太にとって、神々しいお告げのように響き渡った。
「201号」は那由太の隣であり、先程、新聞が溢れていた所の部屋番号である。 …そこで、那由太は気づいたのであった。
「そうだ、あの時も…田舎から戻って来た時、俺の郵便受けには当日の新聞しか入ってなかった。」
那由太は慌てて上りかけていた階段を駆け下りると、清掃員のおじさんにおそるおそる尋ねた…。
「あの…、撤去した新聞は、どこへ行くんですか」
那由太はその返事を待つほんの数秒の間を、数時間のようにすら感じていた。もしも、『捨てるよ』という言葉が返ってきたら、そこで、また探索の糸が切れてしまうのだ。
おじさんは、「溜まったら捨てるんやけど、返してくれって苦情が出ることもあるんでね、一旦保管するんだよ。そこの倉庫に…」と、箒の柄で一階の一番端の倉庫らしい扉を指した。
那由太はすかさず尋ねた。
「10日ほど前の新聞はありますか?」
おじさんは、「さあねえ」と言いながら一階廊下をゆっくりと歩き、じゃらじゃらとカギ束を作業着のポケットから取り出すと、その倉庫の扉を開けた。
ツン、と鼻を突く塩素か消毒液のような臭いが溜まったその小さな倉庫の中には、掃除用具やハシゴなどが入っているのが見える。おじさんはその中から青い大きなカゴを引っ張り出した。そのカゴの中には、底から3分の2ほどの所まで、新聞が無造作に入れてあった。
那由太は、
「探してもいいですか?」
と強い言葉で言った。
「いいけど、あと片付けといてな。」
そう言い終わると、清掃員のおじさんは脇の溝の中に転がっている空き缶を拾い始めた。那由太は、荷物を脇に放り出して新聞の山と対峙した。
幸い、那由太の取っている新聞は『日経』である。きっと探しやすいだろうと、那由太は思ったが、手に取る新聞は『読売』『朝日』などの全国紙ばかりで、那由太は焦りを感じ始めた。
しかし、底が見えるか見えないかの所まで掘り出した所で、とうとう4部ほどの『日経』があるのを発見した。那由太は手を振るわせながら、その新聞を両手で大切に持ち上げた。そして、静かに一部一部を分けていった。
「あっ。」
那由太は思わず声を上げた。
8月14日付けの新聞を裏にした時、新聞をまとめるための帯のところに、半分折れ曲がった葉書のようなものが挟まっていた…。
那由太はそれを天の救いのような思いで見つめていた。
「御子神那由太 様」
紛れもない、それはせつなからの5枚目の葉書であった。
そして、宛名の下隅には、はっきりと「-1」の文字が見て取れた。
…そして、せつなのメッセージは、
「もうすぐ2周年だね。」
であった。
那由太はそのせつなの文字を読んで、思わず涙ぐみそうになった…が、大急ぎで新聞を片づけると、おじさんにお礼を言った。
そして、今まででに出したことないほどの猛スピードで階段を駆け上がった。
写真の風景はこれも那由太の見覚えのないものであった。
ただ、カードは既製品であり、右隅に小さな文字が印刷されたあった…。
「秋吉台」
「『秋吉台』って…山口県かァ…。遠いな…。」
しかし、それがどこであろうと今の那由太にとって関係はなかった。例え北海道であっても沖縄であっても、どこまででも駆けつけるつもりはできていたのだ。
那由太は早速準備を始めた。持っていく物はそれほどない…。帰りは…、早くても明後日になるだろう…。着替えは二日分あれば足りるか…。
と、その時である。
那由太の目がカレンダーの上で止まったまま、動かなくなってしまった。
カレンダーの9月4日の所に、「勝負、最終面接9:00~」という自分の赤い文字を発見したのである。
9月3日のことばかり頭にあった那由太は、9月4日に何があるかなどということは、ここの所全く意識の外であった。
その面接は、那由太にとって第1志望の企業…服飾関係の会社のものであった。
そこを、キャンセルすると、もう残りは「安全パイ」しか残らない…。
ただ、那由太の気持ちは妙に穏やかだった。
「今更、面接の日を換えて欲しいといったところで、無理に決まっている。
…嘘を付くのは嫌だ。きっと、これが自分の運命…『道』なんだ…。」
この数日間、那由太は今までに考えたことがない程に、「自分自身」について考えさせられていた。「自分」とは何か…。自分の「今まで」、そして「これから」は…。
言うまでもなく、それはせつなの「挑戦状」があったからこそである。初めはせつなの「思い」が理解できずに、腹を立てもした那由太であったが、それが今の段階ではもう、感謝へと変わっていた。そして、せつなへの愛情に…。
そして、自分自身で出した結論は、
「自分の『これから』はせつなと共にある。」
これが彼にとっての最終命題であった。
那由太の中には、この夏の数日間で、他の何物にも代え難い「答え」が導き出されていた。
「…辞退届けは明日すればいい。」
那由太は素速く身支度を整えると、今まで届いていたせつなの葉書を全て一括りに輪ゴムで束ね、読みかけの専門書の間に挟んだ。そして着替えやら何やらを一まとめにしてザックに放り込んだ。
「…もう夜行列車は間に合わないだろう。でも、明日の朝一番の電車に乗れば、 何とか間に合う…。今日はあいつの所に停めてもらおう…。明日の朝は早いぞ。」
那由太の頭はもの凄い速度で回転していた。
そして、ザックを右側の肩に掛けると、部屋を勢いよく飛び出して行った。
机の上の写真の中で、せつなが笑っていた。
エピローグ
那由太は秋吉台に向かう観光バスの中にいた。
彼の胸は次第に高まってくる高鳴りを抑えられなかった。時刻はもう夕刻に迫ろうとしていた。
太陽は次第に傾き、空気が淡い琥珀色に輝き始めている。もう、夕暮れの気配が漂いはじめていた。
胸の鼓動を沈めようとして、那由太は、何度見たか分からないせつなからの葉書をもう一度順番に眺めていた。
もう、那由太には全ての「意味」が見通せていた。
「-」、マイナスのついている葉書はせつなの「過去」だ。
せつなの、父との思い出が…彼女が訪れた日本各地の風景に重なっていく。
実際にせつなが訪れた順序とは違っているのかも知れないが、せつなはとうとう見つけたのである。
「原風景…。」
それが「-1」の記された、秋吉台の風景であることに違いはなさそうであった。
そして、「0」は、せつなと那由太の通う大学のキャンパス。二人の「ゼロ地点」だ。そして、その写真には…あの日、図書館の窓から二人で眺めた金色の銀杏が輝いていた…。
「+α」は数学者「ウイリアム・ハミルトン」である。
せつながどうしてこの数学者を選んだのかは分からない。「-1」という暗号のためだけに選ばれたのかも知れない。…けれど、あの日の図書館での会話…あれがきっかけで、自分はせつなに惹かれていった…。そんな実感がある自分には、ロマンチストだったその数学者の横顔にも何か特別な意味があるような気がするのだった。
せつなからの「挑戦状」は、それほど凝ったものではなかった。
気が付けば、実に簡単な謎かけだった。…自分が、彼女と歩んだ「道順」を、大切に覚えてさえいれば…。
数式が記された最後の葉書。そこに描かれたパリの風景の意味も那由太にはもう分かっていた。…それは、せつなにとっての「未来」である。
那由太の中で、せつなの言葉が鮮やかに、そして静かに甦っていた。
「いつかはパリに行って美術館巡りをするの…。」
「するの…。」の後、じっと自分の目を見つめたせつな。彼女はそこで、敢えて何も言わなかったのだろうけれど、きっと「那由太と一緒に…。」と言いたかったのだろう…。
せつなは、過去も現在も未来もすべて自分に投げかけてくれたのだ。
…そう思うと、また那由太の胸は鼓動を速めるのだった。
バスは山道に入り、暫く進んで行くと、せつなのくれた絵葉書通りの風景が那由太の目の前に広がっていた。
何処までも続くかのような草原と、力強く剥き出した岩々。那由太にとっては見たことのないものだったけれど、それはどこか懐かしいような風景であった。
展望広場のような所で、那由太はバスを降りた。バスから降りるのは那由太だけであり、殆どがこれから帰ろうとして乗り込んでくる人ばかりであった。
帰りの手段のことなどは、今は考えもしていなかった…。
バスから降りると、涼しげな風がTシャツ姿の那由太の脇を吹き抜けていく。
もうここだけには「秋」が訪れているかのようであった。
そして、那由太は取り憑かれたように、歩き始めた。
次第に傾いていく夕陽を追いかけるようにして、高原の道を歩いていった。目の前に見える小高い丘の方へ。
草を踏みしめながら歩く那由太の頭の中を、学生時代の思い出のシーンが、一コマずつ、一コマずつ、浮かんでは消えていった。
そして、そのシーンの全てには、せつなの笑顔があった…。
那由太はその丘の上に立った。
沈んでいく大きな夕陽。そして、それに重なるかのように、小さな人影が那由太の視界に入っていた。
小さな岩に腰掛け、淋しそうに沈む夕陽を見つめているその後ろ姿…。
少し赤味を帯びた夏の夕陽が、彼女の向こうで輝いてはいたが、それよりも濃く、鮮やかに、赤のキャップが那由太の目に映っていた。
「『この風景』が俺の『原風景』になるんだ…。」
那由太は涙をこらえながら草原の中を走り始めていた…。
《了》
© Rakuten Group, Inc.