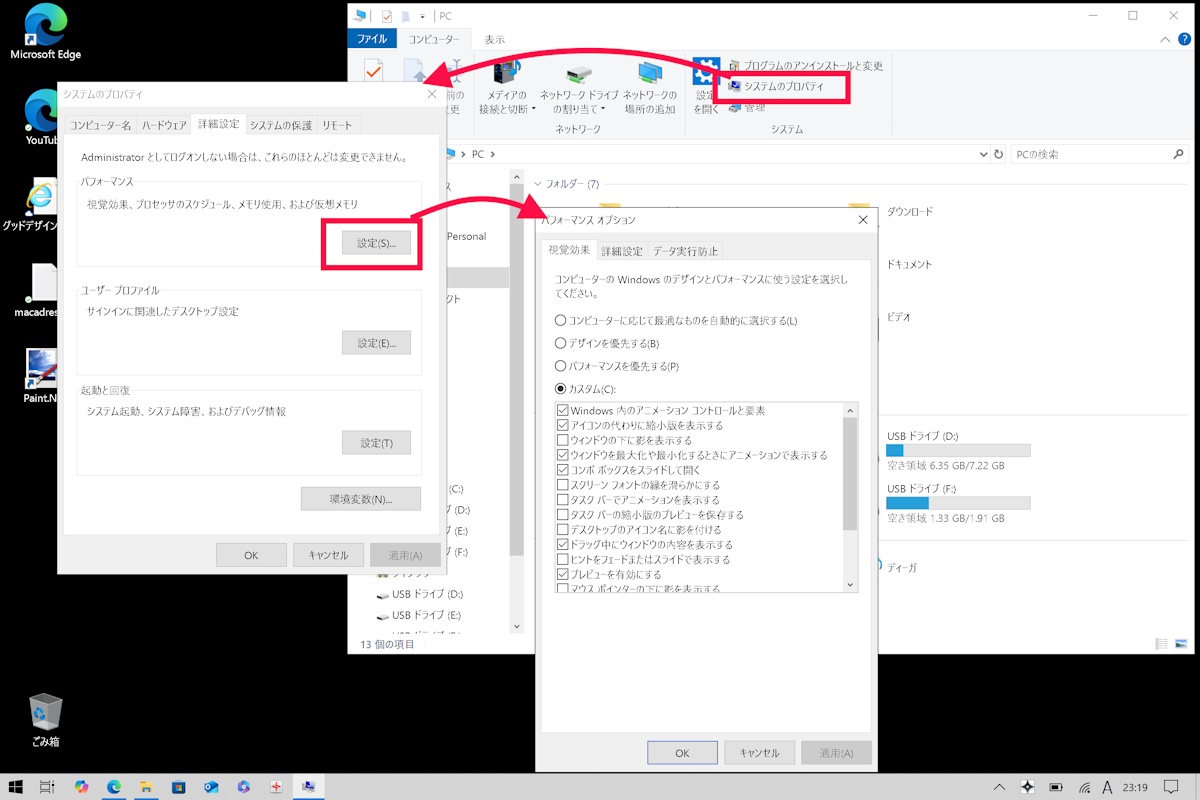「その4」 第四部~エピローグ
【第四部】
【1】
二人は少し歩いて、また水路のある通りまで出た。
そして暫く行くと、道路と水路の間が少し広くなっている場所が見えてきた。
そこは広く敷き詰められた石畳に、小さな噴水とベンチがある。水路を挟んだ向かい側には煉瓦造りの古い大きな建物があり、そこには蔦が絡まっている。ちょっとした休憩所であるが、とても雰囲気がよいお気に入りの場所
…高校時代によく二人で話をした思い出の場所だった。
修也が黙ってベンチ脇に自転車を停めると、紫織も何となく慣れた感じで彼よりも先にベンチに腰を降ろした。
ベンチには色づいた落ち葉が数枚乗っていた。
修也が、すぐ近くに自動販売機を見つけ「ちょっと待ってて。」と立ち上がった。
もう、すっかり飲み物はホットが中心になっている。それもその筈、二三日辺り前から、朝夕には本格的な秋の到来を感じさせる冷たい風が吹き始めている。
修也は迷わず缶コーヒーのホットを2本買うと、またベンチに戻って紫織の左側に腰掛けた。
「ありがとう。さすが、気が利くわね」
「なんの。ちょっとドキドキの連続だったんで、喉が渇いちゃってさ。」
「カシュッ」と、栓を開けて温かい珈琲を口に含むと、ほんのりとした甘さが広がる。それをのみ下すと、修也は「ハーっ」と、大きな息をついた。
その様子を、隣で紫織が優しい笑顔で見つめている。そして、紫織も修也に続いて缶の栓を開けた。
街路樹は美しく紅葉を初めており、午後の柔らかな陽射しに照らされて、それは何とも言えない色合いを醸し出している。
そして、落ち着いた所で、修也は先程撮った携帯電話の写真に写った『§』の刻印を紫織に見せた。
紫織はそこに移った紛れもない『§』を見ながら、
「ふーっ」
と一つ大きく息をついた。
それに合わせるかのように、修也は言った。
「いやあ、それにしても凄い二日間だったよな。」
少し間を置いて紫織も、
「そうね。でも、何だか私…色々考えちゃった。」
「だよな。オレも、夢と小説と現実とがごっちゃになって、何だか凄く妙な気分なんだけど。」
「うん…。」
その「うん」を自分でも確かめるように、紫織は缶を両手で握りしめたまま、水面を見つめていた。彼女のその目はどこか遠くを見ているようだった。
…あの話が本当なら、オレの曾祖父さんと、紫織の曾祖母さんは100年ほど前に、ここで悲恋の主人公とヒロインを演じていたってことだ。そして、どういう縁か知らないけれど、今その曾孫たちがこうしてここにいる。これって、一体何なのだろう…。
修也はそう考えると、不思議なような、嬉しいような気もしたが、自分たちの結びつきが、そういう「宿命」的な必然から来るものだったとしたら…、と考えると、何となく抵抗感を覚えるのだった。
自分たちの出逢いは、単なる純粋な「偶然」であり、自分と紫織の関係はそういうピュアな「運命」であって欲しいという気がしてならなかったのである。
「…きっと紫織もそんなことを想ってるのだろうな。」
修也は横目で、もう一度紫織の顔を覗き見た。が、その目は意外にも優しく温かい色を湛えていた。
と、紫織はいきなり立ち上がると、
「うーん。」
と、大きく背伸びをした。そして振り返ると、暫く黙って遠くを見ていたが、突然指を宙に差し出して、片目をつむった。
「ここからの角度、いいわね」
紫織はどうやら、絵の構図を考えているようだった。
修也も立ち上がって、紫織の見ている方向を見た。
ちょうど街路樹と街路樹の間から、図書館の洒落た建物が見えている。
そして、…4階のあの「窓」もここからは良く見えた。
「さっき、オレはあそこにへばり付いていたんだな…。」と思うと修也はちょっと恥ずかしいような、くすぐったいような気分になった。
「私、決めた。」
と、紫織。
「え、何を?」
「…私の、本格的な油絵の処女作は、ここからの風景にするわ。」
「そう。…いいね。なかなかいいんじゃない。」
そして、修也も、紫織と同じように両腕を突き出して、L字にした指先を組み合わせてみた。
そして、紅葉した樹木に包まれる図書館の美しい風景を切り取ってみた。
確かに絵になる。
しかし、修也の目は自分の指で切り取られたフレームの内側ではなく、外にあるものに奪われていた。
目を輝かせながら、構図を考えている紫織の姿…それは本当に魅力的だった。
修也は、そんな紫織を見つめながら、そっと上着のポケットの中に手を入れると、探り当てたそれを握りしめていた。
【2】
二人はそして、もう一度ベンチに腰を降ろすと、話を続けていた。
水面には、街路樹の鮮やかな赤や黄色が映ってゆらゆらと揺れている。
…よく見れば、濁っていた水路の水はいつの間にか澄んで、静かに流れはじめていた。
「オレも…、あの小説…もう一度ちゃんと書いてみるよ。…最後まで。」
修也はぽつりと、しかし強い気持ちを込めてその言葉を口にした。
「そう。…それがいいわね。」
紫織は、そう言って口元に微かな笑みを浮かべた。そして、また暫く黙っていた。
そんな彼女の様子は、修也の口から出る次の言葉を待っているようでもあった。
修也は、そんな彼女に、
「できあがったら、また…読んでくれよな。」
と言うのが精一杯だった。
その修也の言葉に、紫織はにっこりと微笑むと、しっかりと顔を修也に向けて、
「もちろんよ。私が最初の読者だからね。」
と告げた。
「うん。」
修也は、自分が先程から考えていたような「先祖の宿命」というものを、ひょっとしたら彼女も感じているのではないか…と、少し心配していた。
が、自分を見る彼女の目の中にはそういったものを感じることはなかった。
それは、彼にとってとても嬉しいことであった。
「今度、いつ逢えるかな…。」
その話題を切り出したのは紫織だった。
「そうだね…。冬休みには必ず帰ってくると思うんだけど…。」
そう言った後、修也は慌てて次の言葉を継いだ。
「いや、まあ…。分かんないんだけどさ…取りあえず、必修の授業があるから、明日には行かなきゃ。」
と、少し見当外れのことを口にしながらも、一応の所は取り繕った。
そして、「…紫織は?」と尋ね返した。
修也は、先程の自分の言葉が「冬休みまで逢わない。」という意味だと、紫織にとられなかったか、と思ったのである。
しかし、紫織はそんな様子もなく、
「ふうん。」
と、言った後、
「…私も明後日から講義が始まっちゃうけど…、
まずはここでスケッチして帰る…。それからは…。」
そこまで言って、また黙ってしまった。
思わず、「それから?」と、問い返そうかと思った修也であったが、それはちょっと野暮だと咄嗟に思い、口を噤んだ。そして、ちらりと横を窺った。
紫織の顔はやはり凄く淋しそうだった。
修也は、図書館にいる時にふと見せた、その紫織の表情が、いつ見たものだったかを、また思い出しそうになりながら、あと少しの所で思い出せずにいた。
「逢えない距離じゃないよね。」
と、紫織が次の台詞を口にした時、修也は突然思い出した。
一瞬それは既視感のように修也の脳裏に到来した。
「え、…うん。」と言いながら修也は絶句していた。
その、「紫織の表情」「紫織の言葉」。…それは言うまでもなく、まさに「今」の現実として眼の前にある。
しかし、それは確かな記憶として修也の胸中にもあった。
それは、過去にあった実際の出来事だった。
【3】
「あれは高校3年生の終わり頃、確かこの場所だった…。」
修也は思い出していた。
…自分の大学が決定した時、紫織はまだ進む大学が決まっていなかった。
その時、紫織は第一志望の大学の結果待ち、という状況だった。
既に第一志望に合格していた自分は、紫織を励ます意味で告げた。
「第一志望…受かるといいね。」と。
そして、紫織のその時の言葉は、
「うん。ありがとう。」
だった。
それは、ごく普通のやりとりだった。
しかし、その時、ふと浮かべた彼女の表情…。それが、まさに今日の彼女の「あの」表情だったのだ。
そして結果的に、第一志望に落ちてしまい、第二志望の大学に進学することが決定した。
その時…彼女は確かにこう言った。
「逢えない距離じゃないよね。」
紫織の第一志望の大学は首都圏にあり、そこへ進学してしまうと、帰省しない限りなかなか会うことは難しい。それは修也にも紫織にもよく分かっていた。
ただ、修也は自分の大学に近いからという理由で、紫織に「第二志望の大学に行って欲しい。」とは口が裂けても言えなかった。
…だから、結果的にそうなったことは正直嬉しかった。が、その気持ちを修也は封印していたのである。
紫織から「第二志望の大学に行く」と報告を受けた時、何故か修也はその時の彼女の気持ちを量りかねてしまった。そして、彼女に感じた「違和感」は静かに修也の心に沈澱していったのだった。
それが…ここで、再び甦ったのだった。
その時感じた「違和感」というのは、紫織が第一志望の大学に不合格だった割には少しも哀しそうではなかったということ。そして、「逢えない距離じゃない…」という彼女の表情からは、喜びさえも感じられた、ということだった。
ただ、今日の彼女の「逢えない距離じゃない…」という台詞は、あの時感じたものとは違い、どことなく愁いを帯びたものだった。
修也は、紫織の自分に対する気持ちにやっと気付いたような気がした。もっとも、それは、まだ確信とは言えないものであったが。
そして… 修也は、さっきの言い方ははやり不味かったかなと思い、
「今度は…、オレから連絡するからさ。向こうで…逢おうよ。」
と、誠意を込めて言った。
「約束よ。」
紫織は、小指を立てて修也の方に右手を差し出した。顔には笑顔が戻っていた。
「そんな、子どもじゃないし…。」
「いいの。早く。」
そして、二人は指切りをした。知らない間に、二人の座る距離はうんと近くなっていた。そして、二人は肩が触れ合う程の距離で、また一頻り話し込むのだっだ。
いつの間にか、辺りには夕暮れが迫っていた。
修也は、突然言った。
「もし、オレの書いた小説が、本になるような日がきたら、表紙の絵、絶対書いてくれよな。」
少し間があったが、紫織は
「…ええ、いいわよ。でも、私なんかでいいの?」
「もちろん。」
そして、
「表紙だけでいい? 挿絵だって何だって描いちゃうわよ。」
「頼もしいね。」
「ふふ。」
「…私も、この街の絵をいっぱい描きたい。この街、大好きだもの。」
「そうだね。オレも、こんな街を舞台にした話をいっぱい書きたいな。」
「お互いに、頑張らなきゃね。」
二人の口からは、もう曾祖父母の話は出てこなかった。ただ、あえてその話題を避けているような感じも無かった。
しかし、修也は別れ際に、事の発端になったあの瓶をザックから取り出した。
「これ、お前が持ってなよ。」
紫織は暫く考えたあと、言葉少なに、
「そうする。」
と言い、修也の差し出した瓶を受け取った。
それは、修也の手元にあるよりも紫織が持っている方が相応しい。
これはお互いに説明の必要のないことだった。
【エピローグ】
紫織を見送った後、自転車を漕ぎながら、修也はまた片手をポケットの中に入れた。
そして、静かに自転車を道路脇に停めると、探り当てたそれを掌の上に載せ、暫く見つめるのだった。
それは…指輪だった。
修也は、図書館で、あの『§』と刻まれた煉瓦を見つけた時、それの中から、蝋で塗り込められていた指輪を見つけていた。
最初はすぐさまそれを彼女に見せようと思ったが、ちょうどその時、紫織は司書と話をしていて、…運悪くそれができなかった。
が、しかし…、あの4階の窓の下にしゃがみ込んで待っている間…、その指輪を見ながら彼は思い直したのだった。
「…オレの曾おばあちゃんは、これを二人の愛の証としてここに納めたのだ。
そして、『いつか自分たちの血を引く者が何らかの形でそれを叶えてくれる…。』 そんな願いも込めて…。」と。
そして、まさに、今自分はその筋書きの真上にいた。
ただ、修也には戸惑いがあった。
一つは、「宿命」に縛られることが嫌だったこと。
そして、
一つは、まだ二人が「恋人同士」とは言えない情況にあるということ。
そして何より、
自分と紫織の関係を、この「宿命」の力に頼って成就させること。それだけは、絶対にしたくなかった。
『何時か、きっと…本当にこれを彼女の指にはめられる時が…。』
その時に、きちんと説明しよう。
…きっと紫織は判ってくれる。
二人の「S」が結ばれる時が、そして、二人ともが、「S・S」のイニシャルに、
…『§』になれる時がきたら。
修也は指輪を大事そうにポケットにしまうと、また自転車を漕ぎ始めた。
ペダルを踏む力は自ずと強くなっていた。
「…ひょっとしたら、紫織はもう何か気付いているかも知れない。」
修也の頭には、そんな思いも浮かんでいた。
さっき、別れ際に紫織が言った
「じゃあね。『待ってる』…から。」
という言葉。
何気ない言葉だったけれど、その中の「待ってる」の部分…。そしてそれを口にした瞬間の彼女の瞳の表情に、修也は何か特別な思いを感じ取ったのだった。
「紫織は、鋭い女の勘で、すべてをお見通しなのかも…
…でも、それならそれでいいさ。」
修也の気持ちはもう決まっていた。
「…とにかく、今の自分にできること。それは、あの『夢』の物語。あれをとにかく書き上げること。
…『ラスト』もそうだけど、もう一度、最初から自分の作品として考え直そう。それに、もっともっと勉強して、文章にも磨きをかけなきゃ。
紫織は、あの時『ハッピーエンドがいい』って言ってた…。
でも、ラストだって…、『事実』にとらわれる必要なんかないさ。
だって、紫織とオレの物語も、まだ始まったばかりなんだから…。」
修也の自転車は、落ち葉の散り敷く石畳の坂道を勢いよく走り抜けていた。
《了》
© Rakuten Group, Inc.